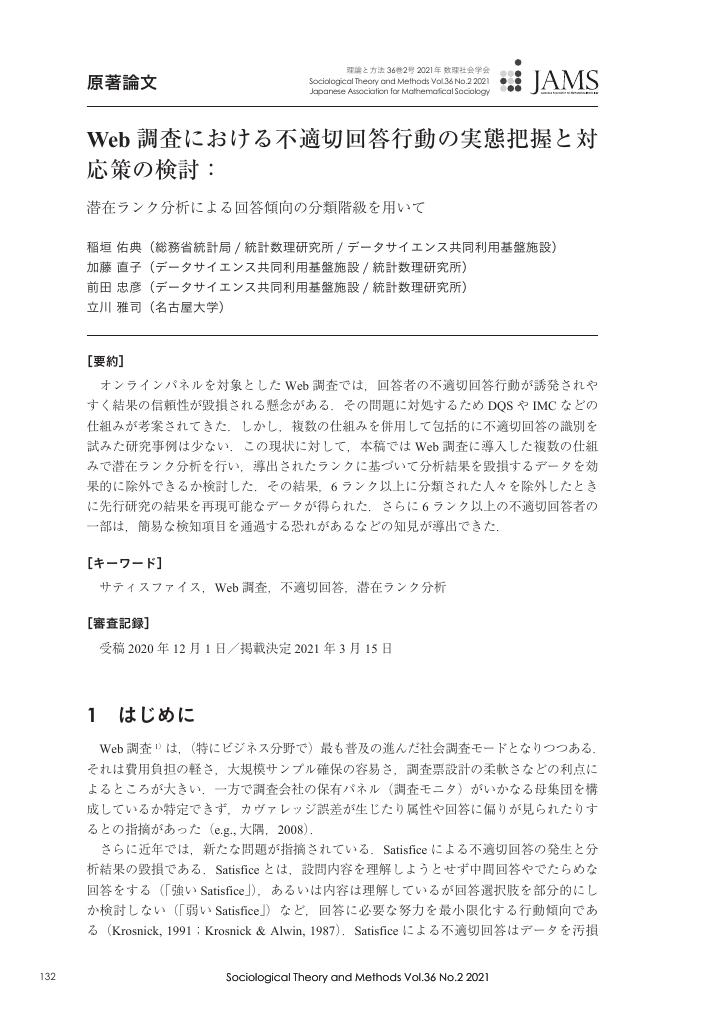5 0 0 0 OA デュエム=クワイン・テーゼとポパー
- 著者
- 立花 希一
- 出版者
- 日本科学哲学会
- 雑誌
- 科学哲学 (ISSN:02893428)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.85-99, 1998-05-10 (Released:2009-05-29)
This paper deals with the problem whether Popper's falsificationism has been refuted by the Duhem-Quine thesis. According to the Duhem-Quine thesis it is not an isolated hypothesis but a theory as a whole that is subjected to an experimental test. And it is claimed that by adding an ad hoc hypothesis or by changing a minor auxiliary hypothesis any falsifications of a theory as a whole can be evaded or at least main hypotheses can be saved from falsifications. Against this I claim that it is not always possible to evade the falsifications. Thus Popper's falsificationism has not been refuted by the Duhem-Quine thesis.
5 0 0 0 OA 知覚の志向説と選言説
- 著者
- 小草 泰
- 出版者
- The Philosophy of Science Society, Japan
- 雑誌
- 科学哲学 (ISSN:02893428)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.1_29-1_49, 2009 (Released:2009-09-30)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 2
Intentionalism and disjunctivism are two main views in the current debate about perceptual experience. In this paper, I will focus on a couple of (supposed) basic properties of perceptual experience, put forward by disjunctivists, which they claim will motivate disjunctivism as opposed to intentionalism. One is the epistemologically special status of perceptual experience as (providing) knowledge; the other is the phenomenological property that this or that particular object seems to be given to us in perceptual experience. By examining these properties, I will show that, in spite of disjunctivists' claim, they do not exclude intentionalism, and that they can be appropriately accommodated into intentionalsits' view.
5 0 0 0 OA 疑似科学とのつきあいかた ~教師を目指す皆さんへ~
5 0 0 0 OA 公共政策大学院設立過程序説 : 専門職大学院制度の形成
- 著者
- 森田 朗
- 出版者
- 北海道大学公共政策大学院
- 雑誌
- 年報 公共政策学 (ISSN:18819818)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.47-61, 2022-03-31
In Japan, the public policy graduate school system as a professional graduate school was established in 2004. This graduate school system was created in conjunction with administrative, civil service system, and legal education reform. Many issues were considered during the process, such as the mission of the graduate school, educational content, and school organisation. Participating in this process, I think that in the turmoil of administrative and university reform, we were able to launch a public policy graduate school, which is nothing more than a small boat with hope, and I assume that it has been sailing smoothly since.
5 0 0 0 OA ウクライナ・ロシア関係論 : ソルジェニーツィンのウクライナ論
- 著者
- 阿部 三樹夫 Mikio Abe
- 出版者
- 久留米大学法学会
- 雑誌
- 久留米大学法学 = Journal of law and politics (ISSN:09150463)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, pp.106-83, 2003-08-30
5 0 0 0 OA 会津藩家老山川家の明治期以降の足跡 ―次女ミワの婚家・桜井家の記録から ―
- 著者
- 遠藤 由紀子
- 雑誌
- 昭和女子大学女性文化研究所紀要 = Bulletin of the Institute of Women's Culture,Showa Women's University (ISSN:09160957)
- 巻号頁・発行日
- no.45, pp.13-36, 2018-03-31
Yamakawa was the chief retainer of the Aizu Domain at the end of the Edo Period. TheYamakawa family comprised seven siblings, of whom the first son Hiroshi, second son Kenjiro,and fifth daughter Sutematsu were famous. This paper clarified the life of the second daughter Miwathat has remained unknown to date. Miwa moved to the border of the Shimokita Peninsula when theAizu Domain was reconstructed as the Tonami Domain after the Boshin War. Her husband MasaeiSakurai worked as the principal of an elementary school. In 1886, all members of her family settledin Nemuro as a colony because her first son Yasuhiko was recruited as militia settlement. Miwadelivered five sons and five daughters. As she was education-obsessed, she sent most of them toTokyo from Nemuro and let them live in the Yamakawa family home as students. All brothers andsisters of the Yamakawa family maintained harmonious relations and supported each other wellinto adulthood. Miwa was an ideal, dutiful wife and devoted mother who always stayed with herhusband and educated her children over the course of her lifetime, though she taught sewing at onetime in her life.
5 0 0 0 OA 存在の根拠としての無 : 『隨眠の哲学』再読
- 著者
- 木岡 伸夫
- 出版者
- 關西大學文學會
- 雑誌
- 關西大學文學論集 (ISSN:04214706)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.1, pp.A1-A26, 2019-07-30
5 0 0 0 ノッチがポインティングの操作時間に与える影響
- 著者
- 大塲 洋介 宮下 芳明
- 雑誌
- 研究報告ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI) (ISSN:21888760)
- 巻号頁・発行日
- vol.2022-HCI-199, no.2, pp.1-8, 2022-08-15
MacBook Pro(2021)にはディスプレイの上端中央にノッチ(描画が行われない黒い領域)が配置された.デフォルトのカーソルサイズの場合,このノッチとカーソルが重なると,カーソルの全部もしくは一部が隠れてしまう状況が観察された.このような状況下では,ユーザはノッチ内でのカーソルの位置がわからなくなったり,カーソルを見失ってしまったりする可能性がある.それにより,ノッチを回避する経路をとったり,ノッチ付近で慎重に操作したりすることで操作時間が増加するかもしれない.本研究では,画面上端にあるターゲットから,同じく画面上端にある他のターゲットを選択する場合(例えば,メニューバーの「ファイル」項目を選択後,「検索」項目を選択する場合),ノッチが操作時間に与える影響を調査した.結果,本実験条件のうち,ノッチがターゲットの間にある条件では,操作時間が約 11.8% 増加することがわかった.
5 0 0 0 気候学・気象学辞典
- 著者
- 吉野正敏 [ほか]編
- 出版者
- 二宮書店
- 巻号頁・発行日
- 1985
5 0 0 0 地形学辞典
- 著者
- 町田貞 [ほか]編集
- 出版者
- 二宮書店
- 巻号頁・発行日
- 1981
5 0 0 0 OA 体液調節と女性ホルモン
- 著者
- 鷹股 亮
- 出版者
- 日本生気象学会
- 雑誌
- 日本生気象学会雑誌 (ISSN:03891313)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.57-64, 2017-09-01 (Released:2017-10-16)
- 参考文献数
- 27
体液の浸透圧と量は浸透圧調節系と容量調節系で調節されている.浸透圧上昇時には口渇とバソプレッシン分泌による腎臓での水の再吸収の亢進により浸透圧が調節される.エストロゲンは,口渇を抑制する作用が報告されているが,浸透圧調節機能に及ぼすエストロゲンの影響についてはわからない部分も多い.容量調節系は主に体内のナトリウム量を調節することにより行われる.エストロゲンとプロゲステロンはともに血漿量を増加させるが,そのメカニズムは異なる.また黄体期は立位時の下肢静脈への血液の貯留と血管外への水の漏出を促進する.しかし,女性ホルモンの体液調節系に及ぼす影響については未だに不明な点が多い.
5 0 0 0 OA 内閣の危険水域 : 支持率30%は妥当か(世論調査の60年)
- 著者
- 今井 正俊
- 出版者
- 公益財団法人 日本世論調査協会
- 雑誌
- 日本世論調査協会報「よろん」 (ISSN:21894531)
- 巻号頁・発行日
- vol.103, pp.30-32, 2009-03-31 (Released:2017-03-31)
5 0 0 0 OA 2.高齢社会における統合医療,漢方の役割―災害時漢方診療の経験をもとに―
- 著者
- 高山 真 沼田 健裕 岩崎 鋼 黒田 仁 加賀谷 豊 石井 正 八重樫 伸生
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.128-131, 2014 (Released:2014-05-23)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 2 4
背景と目的:東日本大震災の際,災害弱者である高齢者は避難に難渋し避難所においても体力の衰え,免疫力の低下などから様々な疾患を患うことも多かった.本報告では,東北大学病院漢方内科が被災地域で行った漢方診療を振り返り高齢者における統合医療,漢方の役割について述べる.方法:発災から10週間までの期間に被災地域の避難所で行った漢方診療に関し,診療録をもとに症状の変遷や漢方診療の内容についてまとめた.結果:震災から2週間までは低体温や感冒,胃腸炎が多く,当帰四逆加呉茱萸生姜湯や人参湯,桂枝湯,五苓散などを処方した.2週間から6週間まではアレルギー症状や呼吸器症状が多く,小青竜湯や麦門冬湯などを処方し,6週間から10週までは精神症状が多く,抑肝散や加味帰脾湯などを処方した.これら経過を振り返るに,高齢者においては発災から間もないころには低体温症例が比較的多く,6週間以降は特に精神症状を訴える例が多かった.考察:震災後に行った漢方診療を振り返るに,多くはすでに西洋薬等が処方されていたものの症状が遷延している例も多く,漢方薬の追加で症状の改善をみる症例を数多く経験した.基礎代謝が低下し,津波をかぶり体が冷え切った低体温の高齢者には,体を温める漢方薬は西洋薬にない効果を発揮した.また,長期間続く避難所生活による精神的,肉体的ストレスによる免疫力低下にも漢方薬が貢献できた可能性がある.さらには,高齢者では効果の強い睡眠導入剤を使用することにより,余震の際に朦朧として力が入らずに転倒する危険性があるが,軽度に鎮静作用を持つ漢方薬は睡眠を補助しつつ,筋緊張を低下させないため使いやすかった.結論:漢方薬のエビデンスが蓄積されつつある現在,西洋医学と漢方医学の併用は災害時の困難な状況においても,統合医療として相補的に用いられるのが理想と考える.
5 0 0 0 OA 電子化お薬手帳の使用実態と患者の意識調査
- 著者
- 高松 大騎 小林 江梨子 伊藤 晃成 佐藤 信範
- 出版者
- 一般社団法人 レギュラトリーサイエンス学会
- 雑誌
- レギュラトリーサイエンス学会誌 (ISSN:21857113)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.139-150, 2016 (Released:2016-05-31)
- 参考文献数
- 8
医療保険制度における薬剤服用歴管理指導料の算定は, 現在, 紙形式の手帳が従来より用いられている. 薬局を対象として, 紙形式および電子化形式のお薬手帳に含まれるデータの種類などを明らかにするため, アンケート調査を行った. また, 薬局に来局した患者を対象として, お薬手帳に対する患者の意識を明らかにするため, アンケート調査を行った. 1,000薬局のうち547薬局が回答を返送してきた. 対象としたすべての薬局が “紙媒体のお薬手帳” を利用していたが, “電子化お薬手帳” を “紙媒体のお薬手帳” とともに使用している薬局は, 回答した薬局の15.9%にすぎなかった. 307人の患者に回答を依頼し227人の患者が回答した. “電子化お薬手帳” を利用している患者は, 回答した患者の0.5%にすぎなかった. また, “電子化お薬手帳” に記載されている項目は, “紙媒体のお薬手帳” に記載されている項目に比べて少なく, ばらつきがあった. お薬手帳を利用している患者のうち, 20.9%はお薬手帳に自分自身で情報を記入することがあると答えた ( “血圧”, “体調の変化” など). お薬手帳に対する患者の意識としては, お薬手帳の情報を, “みせたい医療関係者だけにみせたい” とする患者と, “医療関係者ならだれでもみてもらってよい” とする患者に考え方が二分していた. したがって, “電子化お薬手帳” の運用にあたっては, “紙媒体のお薬手帳” の項目と同様の項目を網羅して記載すること, 患者の意識に応じて閲覧の制限ができることなどが必要と考えられた.
5 0 0 0 OA 「家庭教育支援条例」をめぐる近年の動向について ―「福井県家庭教育支援条例」を中心に―
- 著者
- 友野 清文 Kiyofumi Tomono
- 出版者
- 昭和女子大学現代教育研究所
- 雑誌
- 昭和女子大学現代教育研究所紀要 (ISSN:24335053)
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.1-11, 2022-02-28