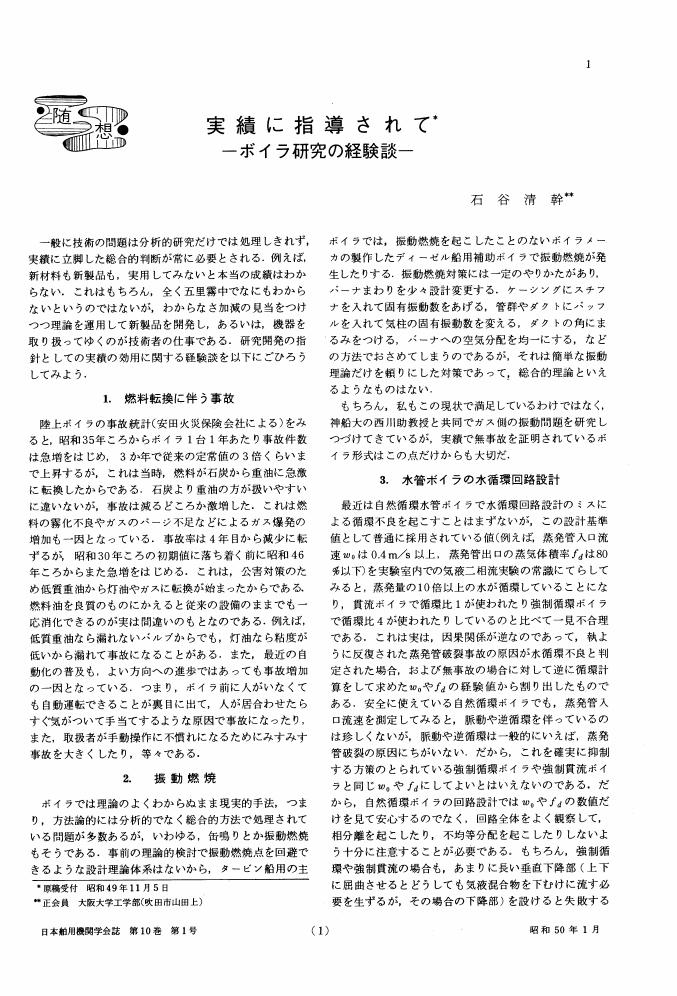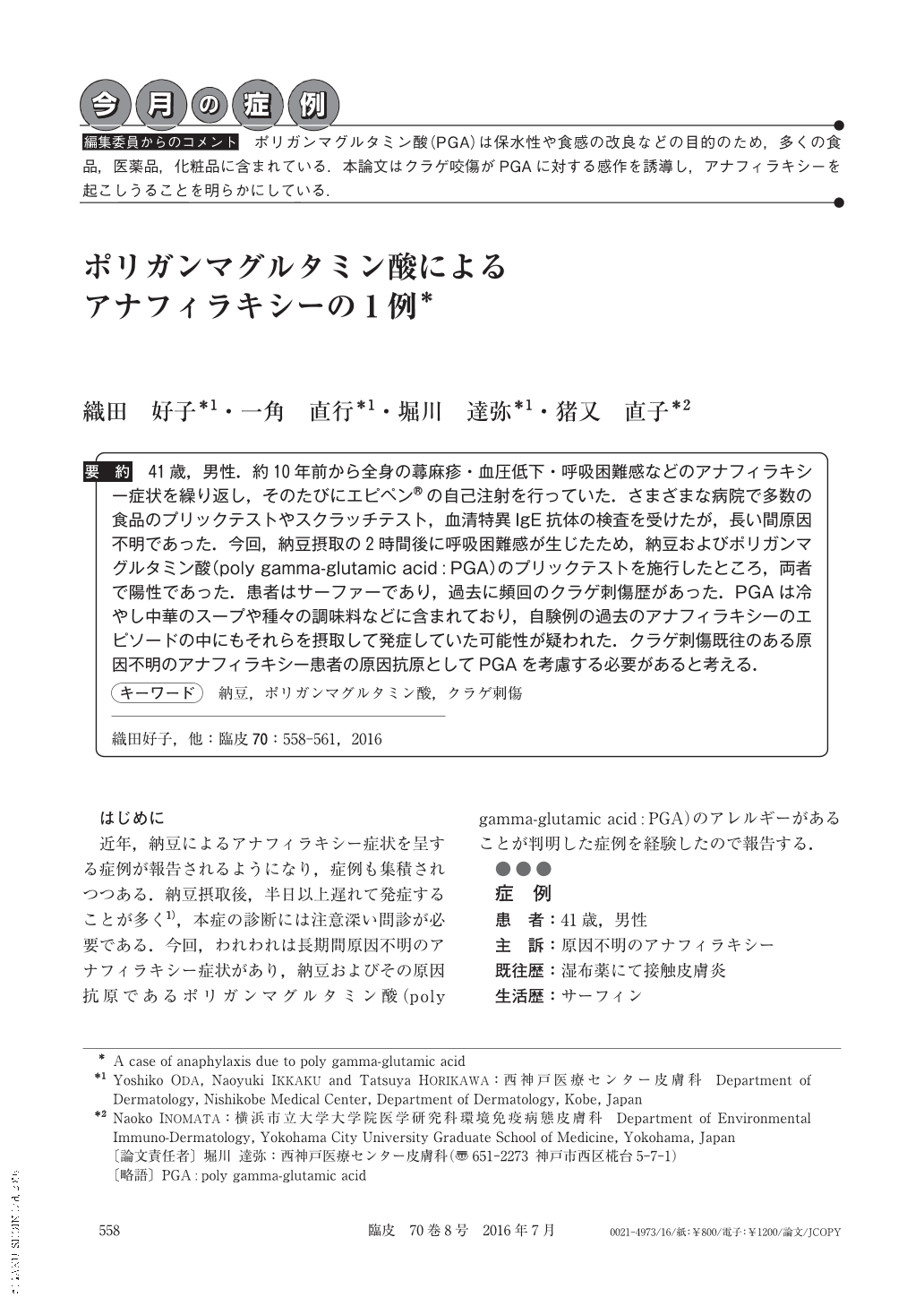5 0 0 0 OA 賭博行動に関する心理学的研究の展望
- 著者
- 小河 妙子
- 出版者
- 心理学評論刊行会
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.200-214, 2014 (Released:2018-07-13)
5 0 0 0 OA 東日本における中間温帯性自然林の地理的分布とその森林帯的位置づけ
- 著者
- 野崎 玲児 奥富 清
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.57-69, 1990-08-30 (Released:2017-05-24)
- 被引用文献数
- 5
Based on a detailed survey of forest distribution, the vegetation structure of the temperate zone in eastern Japan was reexamined in relation to climatic factors, and the natural forest of this zone was divided into three principal types : (1) Fagus crenata forest ; (2) Intermediate-temperate forest (IMTF) ; (3) Upper-temperate forest (UTF). Under an oceanic climate Fagus crenata forest predominated throughout the temperate zone, whereas IMTF and UTF flourished under an inland climate. The geographical boundary between IMTF and UTF was located in the southern part of Hokkaido Island, and the vertical approximately in the middle of the temperate zone along an altitudinal gradient. The geographical differentiation between these two forest types is attributed to a differential response of their dominants to thermal climate, especially during the cold season. Therefore, although previously considered as intrazonal or ecotonal, IMTF and UTF were here recognized as having essentially a zonal character in the context of vegetation structure. In conclusion, the "Intermediate-temperate zone"shows no correspondence with the intermediate zone between the warm-temperate and the cool-temperate, but clearly corresponds to the "lower temperate zone".
5 0 0 0 OA ボイラ特集号 随想
- 著者
- 石谷 清幹 武田 康生 久保田 芳雄 幸田 功 吉見 豊 石川 哲司
- 出版者
- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会
- 雑誌
- 日本舶用機関学会誌 (ISSN:03883051)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.1-11, 1975-01-01 (Released:2010-05-31)
- 被引用文献数
- 2
5 0 0 0 OA ジョン・ロールズの「公正としての正義」論
- 著者
- 田中 成明
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1972, pp.161-203, 1973-10-30 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 9
5 0 0 0 OA 心筋代謝
- 著者
- 森反 俊幸
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バイオレオロジー学会
- 雑誌
- 日本バイオレオロジー学会誌 (ISSN:09134778)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.52-54, 1995-03-31 (Released:2012-09-24)
- 参考文献数
- 5
- 著者
- 池田 朋子 大貝 彰
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.494, pp.161-168, 1997
- 被引用文献数
- 5 5
A novel expresses a world as a model with concrete and universal descriptions, which includes expressions of landscapes. In this study, we analyze fifty-five novels which won Akutagawa Literary Prize from 1970 to 1994, to understand images of landscapes in recent years. Landscapes in the text are categorized into nine items and understood with stages of stories and periods. First, they are grasped quantitatively by the level of words. Then, reading stories around the words lead us to understand the meaning of items of the landscapes. As the results, after high economical growth, landscapes and their meanings decrease such as mountains as boundaries, rivers with plays, hills for understanding oneself relatively in the town and fields viewed on one's ways. Landscapes such as flowers, woods and skies which have been still left become to get more meanings.
5 0 0 0 學籍簿性行概評身體状況用語例集
- 著者
- 永井 暁行
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.54-66, 2018-03-30 (Released:2018-04-18)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 6 5
本研究は,友人関係で傷つきを回避しようとする傾向にあると分類されていた大学生の中にも,高いソーシャルスキルを持ち円滑な関係を築ける大学生と,そうではない大学生がいることを示し,それぞれの大学生の友人との付き合い方の特徴を明らかにする目的で行われた。そのため,友人関係で傷つくことを回避しようとするか否かという態度と,ソーシャルスキルによって大学生の友人との付き合い方を分類し,また,その分類ごとの居場所の実感について検討した。本研究では大学生357名(男性122名,女性235名)を対象とした質問紙調査を行った。分析の結果,態度とスキルによる友人関係の類型は5群に分類された。それぞれの類型はその特徴から配慮・スキル不足距離確保群,スキル標準傷つき無関心群,スキル成熟傷つき回避群,スキル不足傷つき回避群,スキル成熟親密関係群と命名された。この類型によって居場所の実感の違いを検討したところ,居場所を実感しやすいのはスキル成熟傷つき回避群,スキル成熟親密関係群であった。本研究から傷つきを避けるような気遣いをしてしまう大学生の中にもソーシャルスキルが高く,受容される関係を形成・維持できている大学生がいることが明らかになった。
5 0 0 0 OA バイオロギングによる鳥類研究
- 著者
- 高橋 晃周 依田 憲
- 出版者
- 日本鳥学会
- 雑誌
- 日本鳥学会誌 (ISSN:0913400X)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.3-19, 2010-05-01 (Released:2010-06-03)
- 参考文献数
- 96
- 被引用文献数
- 8 7
鳥類は最も機動性の高い動物群であり,自然条件下で個体の生理,行動,生態に関する情報を得るのは困難な場合が多い.この問題を解決するため,動物自身に装着した小型記録計を用いて,自由に動き回る動物の研究を行うバイオロギング技術の開発が進められてきた.バイオロギングは1970年代に単純な潜水深度の記録計から始まり,海鳥類の驚異的な潜水能力を明らかにしてきた.現在,動物装着型記録計は,多様化,小型化が進み,潜水性海鳥類のみならず,鳥類全般での生物学的な研究に利用可能な技術となっている.本論文では,バイオロギングを用いた鳥類研究の最近の進展を,移動,採餌,運動性能,生理状態,認知,社会行動,外的環境の7つの研究分野にわたってレビューした.またバイオロギングが直面する現状における課題,将来の方向性として,記録計の小型化と装着・回収方法の改良,時空間的に相関した大量データを適切に解析する手法の開発,個体ベースで情報が得られる他の研究手法との併用,分野横断的な研究の推進,を取り上げて論じた.バイオロギングによって開ける新しい研究領域は,バイオメカニクス,生理学,行動学,生態学といった既存の学問分野を個体レベルで統合する可能性をもち,自然環境における鳥類の理解を深めることに役立つだろう.
5 0 0 0 『三国志演義』の結末に対する一試論--司馬炎を起点として
- 著者
- 竹内 真彦
- 出版者
- 中文研究会
- 雑誌
- 未名 (ISSN:09146334)
- 巻号頁・発行日
- no.15, pp.55-84, 1997-03
5 0 0 0 強酸性水による根管清掃効果
- 著者
- 竹村 正仁
- 出版者
- 大阪歯科学会
- 雑誌
- 歯科医学 (ISSN:00306150)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.3, pp.g7-g8, 1997
根管の器械的清掃時には作業液を応用した根管の拡大・形成を進め, 拡大・形成後の化学的清掃には3〜5% NaOCl溶液および3% H_2O_2溶液による交互洗浄が一般に応用されている。しかし, 根管の拡大・形成の良否によっては根管内に応用する洗浄液の根尖歯周組織への溢出という危険性も考えられるため, 使用する洗浄液には可能な限り組織親和性を示すものが望ましい。最近, 水道水の電気分解で得られる強酸性水が広範囲な殺菌作用を示す一方, 細胞毒性が低く, 人体に何ら影響を及ぼさない水として注目されている。そこで本実験は, 根管拡大・形成後の根管洗浄液として強酸性水の根管壁スメアー層およびdebrisの除去効果を検索し, 臨床応用が可能かどうかを検討した。実験にはヒト抜去上顎中切歯120歯を使用し, 洗浄法に従いシリンジ洗浄群および超音波洗浄群の2群に60歯ずつを分割した。実験歯の髄室開拡後は, 通法に従いステップバック法にて根管の拡大・形成を終了した。なお根管の拡大・形成中は, 各群の60歯を15歯ずつの4グループにそれぞれ, 分割し, グループ1〜3は5% NaOClを, グループ4には強酸性水を作業液として応用した。根管の拡大・形成後, 各グループの根管洗浄を以下のように行った。すなわち, シリンジ洗浄群では22ゲージの注射針を装着した10 ml注射筒を用いて, グループ1の実験歯には精製水, グループ2には強酸性水, グループ3には15% EDTA, グループ4には強酸性水をそれぞれ用いて根管洗浄を行った。各グループはさらに5歯ずつの3つのサブグループに分け, 各洗浄液の使用量を10, 20および30 mlとした。超音波洗浄群では#30のファイルを超音波発生装置に装着し, シリンジ洗浄群の各グループと同様の洗浄液を使用して超音波洗浄を行った。超音波作用時間は各グループの実験歯をさらに5歯ずつの3つのサブグループに分け, 1分, 3分および5分間とした。全実験歯の根管洗浄後は歯冠部を切除したあと, 歯根を歯軸に沿って2分割し通法に従って電顕用試料とした。根管壁面の観察には走査型電子顕微鏡を用いて根中央部および根尖1/3部の写真撮影を行い, 根管壁面に残存するスメアー量ならびにdebris量を0〜3の数値にスコアー化し評価した。その結果, シリンジ洗浄法および超音波洗浄法ともに根管洗浄液の使用量および超音波作用時間の違いによる清掃効果には差を認めなかった。スメアー層除去効果については, 作業液にNaOCl溶液を使用した根管拡大・形成後に洗浄液として強酸性水をシリンジ清浄法で使用したグループ2は, EDTAを洗浄液として使用したグループ3と同程度の洗掃効果が得られた。しかし, 超音波洗浄法による清掃効果では強酸性水はEDTAより多少劣っていた。一方, NaOCl溶液を作業液として応用し根管拡大・形成を行ったのち, 精製水にて根管洗浄を行ったグループでは洗浄方法に関わらず根管壁面全体がスメアー層で覆われており, 明らかな歯細管の開口は認められなかった。この結果は, 強酸性水を作業液および根管洗浄液として用いたグループと類似の結果を示していた。Debris除去効果については, シリンジ洗浄法において, 強酸性水を使用したグループ2がEDTAを使用したグループ3より優れたdebris除去効果を示したが, 超音波洗浄法では両者の間に差はみられなかった。また, 作業液にNaOCl溶液を使用し, 根管拡大・形成後に根管洗浄液として強酸性水を使用したグループでは, 超音波洗浄法によって良好なdebris除去効果を示したが, シリンジ洗浄法では中等度の除去効果であった。さらに, 作業液および根管洗浄液に強酸性水を応用したグループでは, 洗浄方法に関わらず中等度のdebris除去効果を示したにすぎなかった。以上のことから, 根管拡大・形成時にNaOCl溶液を作業液として応用し, 拡大・形成後に強酸性水を根管洗浄液として応用すると根管壁面のスメアー層やdebrisの除去が十分に行われ, 強酸性水は根管洗浄液として臨床応用が可能であることが明らかになった。
5 0 0 0 OA 運動年鑑
- 著者
- 朝日新聞社運動部 編
- 出版者
- 朝日新聞社
- 巻号頁・発行日
- vol.昭和12年度, 1937
5 0 0 0 ポリガンマグルタミン酸によるアナフィラキシーの1例
要約 41歳,男性.約10年前から全身の蕁麻疹・血圧低下・呼吸困難感などのアナフィラキシー症状を繰り返し,そのたびにエピペン®の自己注射を行っていた.さまざまな病院で多数の食品のプリックテストやスクラッチテスト,血清特異IgE抗体の検査を受けたが,長い間原因不明であった.今回,納豆摂取の2時間後に呼吸困難感が生じたため,納豆およびポリガンマグルタミン酸(poly gamma-glutamic acid:PGA)のプリックテストを施行したところ,両者で陽性であった.患者はサーファーであり,過去に頻回のクラゲ刺傷歴があった.PGAは冷やし中華のスープや種々の調味料などに含まれており,自験例の過去のアナフィラキシーのエピソードの中にもそれらを摂取して発症していた可能性が疑われた.クラゲ刺傷既往のある原因不明のアナフィラキシー患者の原因抗原としてPGAを考慮する必要があると考える.
5 0 0 0 IR 韓国における日常食の特徴と基本パターン : 忠清南道一両班村落の事例を中心に
- 著者
- 林 在圭 イム ゼエギュ Jaegyu Lim
- 雑誌
- 静岡文化芸術大学研究紀要 = Shizuoka University of Art and Culture bulletin
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.17-30, 2011-03-31
韓国の伝統的な食生活は医食同源の考え方に基づき、日常の食事は主食と副食から構成されている。そのため、野菜を中心とする多様な副食から均衡のとれた栄養素を取り込むことが可能である。 そこで本稿では、韓国農村の一村落を対象として日常の食事記録をとり、日常食の特徴と基本パターンを検証する。「飯バンサン床」と呼ばれる日常の食事は固有のルールをもっており、基本飲食を除くおかずの数によって格式化されている。 しかし実際に調査してみると、調査対象村落における日常食の基本パターンは主食1に副食4の5品であった。最も質素な「三サムチョップバンサン楪飯床」の7品に比べ、当該村落は2品が少ない結果となった。また日常食の特徴としては今日でも主食と副食とが明確に区別されており、食材と調理法の重複を避けて、栄養バランスがとれるように工夫されている。したがって、韓国の村落社会における医食同源の考え方は、依然として強く受け継がれていることが確認できる。しかし近年、幼児を含む世帯を中心に外食行動も増え、肉食化の傾向がみられる。Based on the concept of the importance of food in health, Korea's traditional food lifestyle has everyday food comprised of a staple andsupplementary foods. This enables them to obtain balanced nutritional elements from diverse supplementary foods, especially vegetables.Thus in this paper, we take daily food records in one village in rural Korea, and investigate the characteristics and basic pattern ofeveryday foods. Based on characteristic rules, everyday foods called "bansang" have their status raised by the number of side dishesapart from basic food and drink. According to our specific fieldwork survey, the basic pattern of everyday foods in the village surveyed is one staple food with four or fivesupplementary dishes. Compared to the seven dishes of a very modest "samcheob-bansang" meal, the survey showed this village hastwo dishes less. Also, a characteristic of everyday foods is that even today they are clearly divided into staple and supplementary foods,and they avoid overlapping ingredients and cooking methods, working to obtain nutritional balance. We thus confirmed that the concept ofthe importance of food in health is still a strong tradition in Korea's rural society. However, in recent years, especially households includingchildren are increasingly eating out, and we see a trend towards meat in the diet.
5 0 0 0 OA 子どもの権利と共同親権・共同監護--非監護親の養育責任とひとり親家庭の福祉施策をめぐって
- 著者
- 河嶋 静代
- 出版者
- 北九州市立大学文学部
- 雑誌
- 北九州市立大学文学部紀要, 人間関係学科 = Journal of the Faculty of Humanities, Kitakyushu University.Human Relations (ISSN:13407023)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.1-25, 2010-03
5 0 0 0 IR 「視覚は人間の情報入力の80%」説の来し方と行方
- 著者
- 加藤 宏
- 出版者
- 筑波技術大学学術・社会貢献推進委員会
- 雑誌
- 筑波技術大学テクノレポート (ISSN:13417142)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.95-100, 2017-12
「人の情報入力は視覚から8 割と" いわれる"。」,だから,「視覚を失うことはほとんどの情報のない世界に生きることになる」は妥当か。これらフレーズの出どころをたどろうとすると引用元が明記されていない場合が多い。広く語られることの多いこの視覚優位について,この言説の出処と科学的根拠をたどってみた。さらに,人口に膾炙したこの言葉がなぜその根拠についてあまり疑問にも付されず繰り返し引用され再生されてきたのか,そして,人間への情報入力の問題をどのように考えるべきなのかを考察する。
5 0 0 0 OA 大江匡房
- 著者
- 山口 昌男
- 雑誌
- 比較文化論叢 : 札幌大学文化学部紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.9-68, 2003-03-15
5 0 0 0 OA 国内で起きるカビ毒汚染の実態と防御-パツリンを中心として
- 著者
- 田端 節子
- 出版者
- 日本マイコトキシン学会
- 雑誌
- マイコトキシン (ISSN:02851466)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.129-135, 2008 (Released:2008-10-07)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 6 5
一般に,国内では,一部の地域を除きアフラトキシン汚染が起きる可能性は低いと考えられているが,ペニシリウム属のカビが産生するパツリンやフザリウム属のカビが産生するデオキシニバレノール等は,我が国の気候条件でも産生される.近年,これらのカビ毒の国内での汚染が注目され,詳細な汚染実態の把握と,防御対策の開発が急務となっている.今回は,国内で起きているカビ毒汚染の状況と,リンゴ等のパツリン汚染について,その汚染の傾向から防御の対策について述べる.国内での自然汚染が確実に普遍的に起きているカビ毒は,麦中のデオキシニバレノールとニバレノールとリンゴ中のパツリンである.国内で汚染が起きている可能性が高いものに,麦中のゼアラレノン,ブドウ中のパツリン,黒糖中のアフラトキシンがある.また,穀類等のオクラトキシン汚染も国内で起きている可能性がある.国産リンゴを原料として使用するジュース製造工場から腐敗・傷害のため廃棄されたリンゴについてパツリン汚染調査を行った結果,一部に高濃度のパツリンの自然汚染が起きていることが判明し,低温保存でも保存期間が長くなるとパツリン汚染が進む傾向が認められた.リンゴのパツリン汚染を防止するには,汚染が起きている場所を特定し,菌の排除を行うこと,傷の付いたリンゴは長期間保存せず,早く加工してしまうことも効果的であると考えられる.
5 0 0 0 IR 欧米のピアノメーカーの歴史 : ピアノの技術革新を中心に
- 著者
- 大木 裕子
- 出版者
- 京都産業大学
- 雑誌
- 京都マネジメント・レビュー (ISSN:13475304)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.1-25, 2010-10
初期のピアノにはウィーン式とイギリス式の2つのアクションが存在していたが,イギリスと大陸を行き来する音楽家を介して双方のよさを取り入れたピアノが開発されるようになった.イギリスを中心としたヨーロッパのピアノ製作は伝統にこだわる一方で,アメリカでは積極的な技術革新が進められ,世界のピアノ生産の中心はアメリカに移っていった.本稿では欧米の主要ピアノメーカーを中心に,19世紀の終わりに完成したピアノという楽器の技術革新の過程を振り返る.