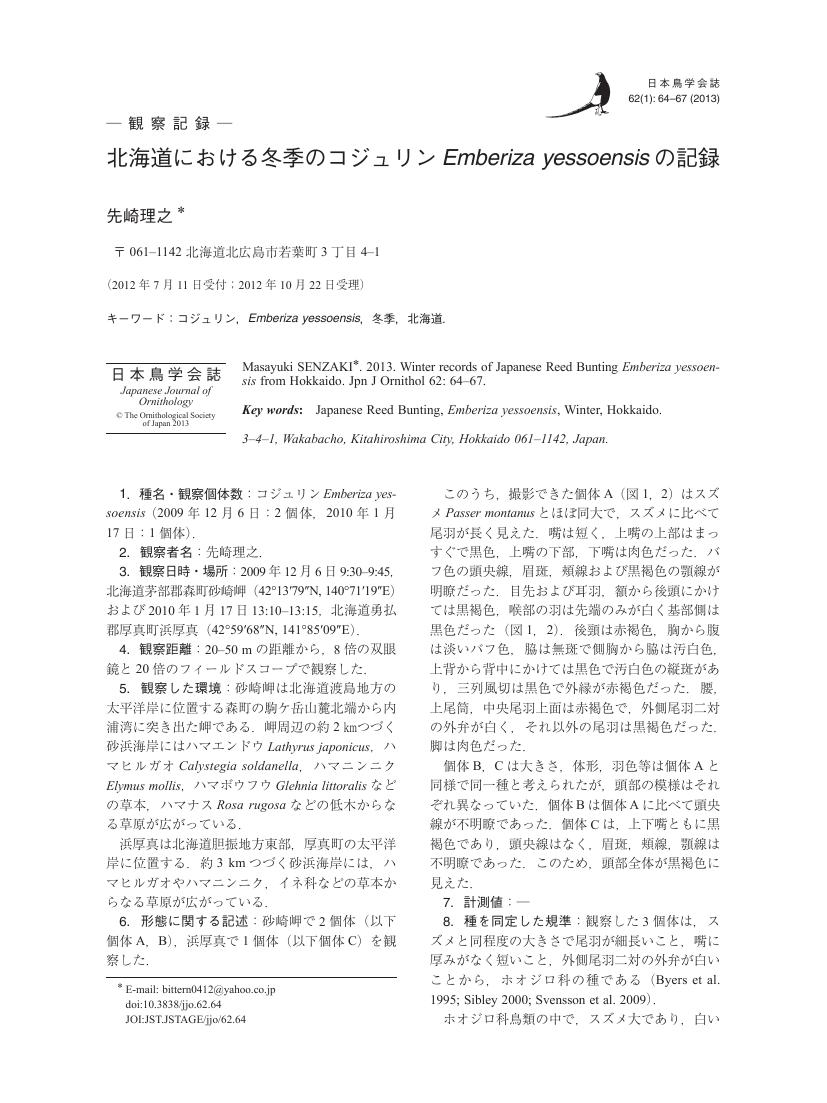1 0 0 0 腎癌の予後に関する臨床統計
- 著者
- 里見 佳昭 福田 百邦 穂坂 正彦 近藤 猪一郎 吉邑 貞夫 福島 修司 井田 時雄 広川 信 森田 上 古畑 哲彦 熊谷 治巳 塩崎 洋 石塚 栄一 宮井 啓国 仙賀 裕 福岡 洋 佐々木 紘一 公平 昭男 中橋 満
- 出版者
- 社団法人日本泌尿器科学会
- 雑誌
- 日本泌尿器科學會雜誌 (ISSN:00215287)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.5, pp.853-863, 1988-05-20
- 被引用文献数
- 20
1965年1月より1985年12月までの21年間に横浜市立大学病院及びその関連病院に於いて経験した腎癌550例の遠隔成績と予後因子について検討し,次の結論を得た.1. 全症例の生存率は,5年生存率48%,10年生存率36%,15年生存率27%と、術後5年をすぎても長期にわたり死亡する予後不良の癌である.2. 40歳未満の若年者腎癌では術後2年以上経てから死亡する例はなく予後が比較的良好である.3. 予後不良因子としては,発熱,体重減少,食欲不振,全身倦怠などの症状のほか,赤沈亢進,CRP陽性,α_2-globulinの上昇,AL-P上昇,貧血などがあげられた.ツベルクリン反応陰性,LDH上昇,レ線上の腎の石灰化像などは予後不良因子ではなかった.4. 経腰的腎摘除術と経腹的腎摘除術の遠隔成績はほぼ同じであり,症例を選べば手術は経腰的腎摘除術で十分な場合もあると考えた.5. 4分類法のgrade分類は予後を比較的よく反映した.Robsonのstage分類ではstage IとIIの間に差がなく,stage分類法に欠陥あることを指摘した.6. 腎癌にはslow growing typeとrapid growing typeがあり,前者は予後良好であると安心しがちであるが,それは誤りであり,前者は緩慢なる経過を取るだけであり,術後5年経てから転移や死亡症例が多くなり,長期的にはrapid growing typeの症例の生存率に近づくと理解すべきである.
1 0 0 0 VOL.11 新里尚也(スポットライト : イケメン&イケジョ)
- 著者
- 新里 尚也
- 出版者
- 日本微生物生態学会
- 雑誌
- 日本微生物生態学会誌
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.92-93, 2014-09-01
1 0 0 0 OA ハルマゲドン : 天魔両軍の決戦
1 0 0 0 IR チャンバラ映画における「殺陣」
1 0 0 0 OA 文体と難易度を制御可能な日本語機能表現の言い換え
- 著者
- 松吉 俊 佐藤 理史
- 出版者
- 一般社団法人 言語処理学会
- 雑誌
- 自然言語処理 (ISSN:13407619)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.75-99, 2008-04-10 (Released:2011-03-01)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 4 5
日本語には, 「にたいして」や「なければならない」に代表されるような, 複数の形態素からなっているが, 全体として1つの機能語のように働く複合辞が多く存在する. われわれは, 機能語と複合辞を合わせて機能表現と呼ぶ. 本論文では, 形態階層構造と意味階層構造を持つ機能表現辞書を用いることにより, 文体と難易度を制御しつつ, 日本語機能表現を言い換える手法を提案する. ほとんどの機能表現は, 多くの形態的異形を持ち, それぞれの異形は, その文体として, 常体, 敬体, 口語体, 堅い文体のいずれかをとる. 1つの文章においては, 原則として, 一貫して1つの文体を使い続けなければならないため, 機能表現を言い換える際には, 文体を制御する必要がある. また, 文章読解支援二などの応用においては, 難易度の制御は必須である. 実装した言い換えシステムは, オープンテストにおいて, 入力文節の79% (496/628) に対して, 適切な代替表現を生成した.
1 0 0 0 小山高専サテライト・キャンパスにおける科学技術倫理カフェ
- 著者
- 上野 哲
- 出版者
- 独立行政法人国立高等専門学校機構
- 雑誌
- 論文集「高専教育」 : kosen kyoiku (ISSN:03865681)
- 巻号頁・発行日
- no.36, pp.435-440, 2013-03
The purpose of this paper is to answer the following question: how have Japanese general citizens' ideasabout the control of science and technology changed after participation in the Scientific Ethics Café? Until now,Japanese citizens are in fact less inclined to involve themselves in discussions about science and technology withprofessionals and specialists. Since the nuclear plant accident in Fukushima, rather than recognizing that it isimportant for citizens to participate in the discussions contributing to decision making concerning science andtechnology, it seems that citizens are much more likely to leave the decisions concerning science and technology tospecialists and professionals. To break such a current state, This paper propose a direction in which the ethicseducation of science and technology for general citizens in Japan should aim using the questionnaires and transcriptsderived from discussions with citizens in Tochigi, in a unique process arranged by the author known as ScientificEthics Café; a process that has been operating since 2010.
1 0 0 0 OA 3d遷移金属化合物の強磁性-反強磁性転移
- 著者
- 和田 裕文
- 出版者
- 物性研究刊行会
- 雑誌
- 物性研究 (ISSN:05252997)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.6, pp.717-731, 1994-09-20
この論文は国立情報学研究所の電子図書館事業により電子化されました。
1 0 0 0 OA 北海道における冬季のコジュリンEmberiza yessoensisの記録
- 著者
- 先崎 理之
- 出版者
- 日本鳥学会
- 雑誌
- 日本鳥学会誌 (ISSN:0913400X)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.64-67, 2013 (Released:2013-05-28)
- 参考文献数
- 20
1 0 0 0 紀元二千六百年祝典記録
- 出版者
- [出版者不明]
- 巻号頁・発行日
- vol.第11冊, 1940
- 著者
- 酒井 健太郎
- 出版者
- 筑波大学大学院博士課程芸術学研究科・人間総合科学研究科
- 雑誌
- 芸術学研究
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.1-8, 2002
1 0 0 0 ロックフェラー財団 : その歴史と業績
- 著者
- レイモンド・B.フォスディック 著
- 出版者
- 法政大学出版局
- 巻号頁・発行日
- 1956
1 0 0 0 新内 蘭蝶(一)
- 著者
- (初世)鶴賀 若狭掾[作詞]
- 出版者
- コロムビア(戦前)
- 巻号頁・発行日
- 1929-09
1 0 0 0 OA ロミオとジュリエット幻想
- 著者
- 渡辺 芳敬
- 出版者
- 早稲田大学教育会
- 雑誌
- 学術研究 : 複合文化学編 (ISSN:1882417X)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, pp.69-85, 2011-02-25
1 0 0 0 プロジェクトの実現可能性を検討するための負荷容量参照モデルの提案
- 著者
- 艸薙 匠 齋藤 彰儀 落水 浩一郎
- 出版者
- 情報処理学会
- 雑誌
- 研究報告ソフトウェア工学(SE) (ISSN:18840930)
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, no.4, pp.1-8, 2010-11-04
- 被引用文献数
- 2
本研究では,WBSをベースとした従来型のプロジェクト計画立案とその実現可能性を検討する方法に関わる課題を整理し,それに基づいて,プロジェクトの負荷構造と組織の容量構造を定義し,負荷容量参照モデルを提案する,さらに参照モデルの事例から割り当ての自動化と実現可能性の検証を行う方法を検討する.提案する参照モデルは,プロジェクト計画の初期段階で計画の効率的検証を支援することが期待される.This paper discusses some problems about a project planning and a verification method for the acceptance of a project in a software development organization. We propose the conceptual framework for a project design that defines an effort structure of a project and the capacity of an organization. The proposed framework supports us to verify a project plan efficiently at a early stage.
1 0 0 0 OA 「同情」と「隣人愛」から見る阿部次郎と武者小路実篤の宗教と社会観―「第三の社会」―
- 著者
- 吉本 弥生 Yayoi YOSHIMOTO ヨシモト ヤヨイ
- 出版者
- 総合研究大学院大学文化科学研究科
- 雑誌
- 総研大文化科学研究 = Sokendai review of cultural and social studies (ISSN:1883096X)
- 巻号頁・発行日
- no.9, 2013-03-28
一九〇〇年頃、日本の思想界では人格主義が大きな影響を与えていた。日本の人格主義は、感情移入美学との関連があり、その影響を強く受けていたのが阿部次郎(一八八三~一九五九)であった。同時に武者小路実篤(一八八五~一九七六)にもその傾向が見られ、両者の思想は互いに似たところがあった。 そこで、当時の社会思想について阿部と似た意識のあった武者小路実篤の「理想的社会」(『生長する星の群』一九二三年一月~八月)を取り上げ、阿部の『人格主義』(岩波書店、一九二二年)と比較することで、両者の相違と同時代受容を検証した。これまで、阿部と武者小路の社会観を考察する研究はなされていない。その際、浮上したのが「同情」と「隣人愛」の概念である。これは、阿部がリップスの感情移入を「同情」と訳していたことから始まった。阿部は、彼自身の解釈でこの言葉を用いていたが、「同情」「隣人愛」は、当時の日本において重要な役割を果たしている。 本稿では、「同情」に着目し、キリスト教と反キリスト教の両面から考察し、この視点から一例として、ショーペンハウア―受容を取り上げた。それは、阿部だけでなく、武者小路や森鴎外(一八六二~一九二二)、島村抱月(一八七一~一九一八)など、当時の知識人達に広まっていた。中でも、井上哲次郎(一八五六~一九四四)に見られるように、ショーペンハウアーは仏教の側面からも解釈されており、阿部と武者小路の社会観でも人格的価値や善という側面に共通性が見られた。 また、阿部と武者小路は各々「第三の社会」や「第三のもの」という国家や共同体観を持っており、これは当時、既に受容されていたイプセンの戯曲に登場する『皇帝とガラリヤ人』(一八七三年)で著した「肉の王国」と「霊の王国」を経て霊肉一致の「第三帝国」を求める人々の姿を想像させる。 イプセンの戯曲では、ギリシアの古代精神とキリストの精神を統一融合した世界として「第三帝国」が表現されるが、阿部と武者小路の目指す社会は、同時代に受容された感情移入説と人格向上が融合したものであった。 以上の考察の結果、武者小路の共同体はカントの「目的の国」と似ており、阿部の国家はヘーゲルの『法哲学』の国家観と似た特徴を持ち、両者は善の社会を目指している点では共通した思想を持っていたのである。Abe Jirō (1883–1959) declared that a good society can be created through “personalism” (1922). He thought that the improvement of individual personalities would lead to a virtuous society. Mushakōji Saneatsu (1885–1976) had a similar idea. Abe Jirō’s idea of “personalism” resembled Mushakōji Saneatsu’s thinking about the “ideal society.” In this essay, I have inspected their ideas. Abe Jirō said that sympathy is a kind of empathy; and empathy, when seen aesthetically, is also applicable to society. I investigated the problem of sympathy from the point of view of empathy. The theory of empathy proposed by Theodor Lipps (1851–1914) was introduced in Japan in discussions of aesthetics and psychology. Mori ōgai (1862–1922) was the first to take up the problem, and it spread among the intellectuals of that time. Sympathy was understood in terms of religion when Schopenhauer’s thought was transmitted to Japan. Schopenhauer can be interpreted from a Buddhist point of view, as seen in the writing of Inoue Tetsujirō (1856–1944). I investigate “sympathy” and “neighborly love” from the time of Schopenhauer’s reception in Japan. Lipps’s idea applies to all interpretations. Therefore, their interpretation differentiate with that of someone. But Abe’s and Mushakōji’s ideas resembled those of others in the same period. Ibsen (1828–1906), in his play Kejser og Galilaer (1873), had put forward something similar in his idea of “the third society” that unites the flesh as expressed by the Greek mind and the spirit as expressed by the Christian mind. Similarly, in Japan, Abe Jirō and Mushakōji Saneatsu saw their country as one in which sympathy and personalism were fused. Abe’s idea may also be compared to Hegel’s “philosophy of law,” and Mushakōji’s ideal society may be compared to Kant’s idea of a “goal country.” Abe and Mushakōji thought that religion is goodness.
1 0 0 0 OA 分子病理学に基づくグリオーマ分類
- 著者
- 溝口 昌弘
- 出版者
- 日本脳神経外科コングレス
- 雑誌
- 脳神経外科ジャーナル (ISSN:0917950X)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.6, pp.366-377, 2015 (Released:2015-06-25)
- 参考文献数
- 93
TCGAに代表される大規模癌ゲノム解析により, 体系的かつ包括的なゲノム解析が推進され, グリオーマにおいて新たな知見が続々と報告されている. ゲノム, トランスクリプトーム, エピゲノムといった複層的な解析により, その全体像が明らかとなりつつある. 次世代シークエンサーに代表される, 近年の技術開発に伴い, その解析速度は飛躍的に向上し, 大量のゲノムデータが公開されるとともに, その複雑さも明らかとなった. 本稿では膠芽腫を中心に, これまで明らかとなった知見を総括し. 現時点での問題点と今後の課題について考察した.
- 著者
- 津川 恵子
- 出版者
- 一般社団法人 口腔衛生学会
- 雑誌
- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.4, pp.322-338, 1977
- 被引用文献数
- 2 2
著者は, 歯牙酸蝕症を初期に発見することによって予防対策, 職場転換等の適切な処置に対処することのできることを目的として某バッテリー工場における酸蒸気の発生する部門に従事する従業員を対象として4年間にわたり肉眼的方法 (著者らの教室で定めたもの) 及び林の方法によるレプリカ法での光学顕微鏡所見とを観察し, 更にそのなかから4年間にわたって検しえた同一人について年次的な推移を比較検討した。また肉眼的方法による診断とレプリカ法による所見との関係について観察した。<BR>対象作業部門の空気中酸量は, 平均0.475mg/klであり許容濃度1mg/klに比してかなり低い濃度であった。<BR>結果<BR>1) 従業員の自覚症状は, 約半数が何らかの症状を訴え, 前歯に冷たい空気がしみる, 時々前歯に嫌な感じがする, 作業中に前歯がしみる等が多くみられた。<BR>2) 罹患者は, 年齢別には20歳代に多く, 職齢では6~10年に多くみられた。<BR>3) 罹患歯率は上顎に比し下顎に多く, 歯別では下顎中切歯に多く, 上顎切歯に少ない。逐年的に罹患歯率は, 増加を示した。<BR>4) レプリカ所見では, 林の程度分数 (R<SUB>0</SUB>-R<SUB>4</SUB>) のうちR<SUB>2・3</SUB>が1年度で77.5%と高率を示したが, R<SUB>2</SUB>は逐年的に減少し, R<SUB>3</SUB>は増加した。<BR>5) 同一被検者についての4ヵ年間の推移では, 経年的に罹患率を増し, 罹患歯率では直線的な増加を示した。許容濃度以下の空気中酸量にあっても長期間にわたって作業に従事することによって, 次第に侵蝕の状況が進んでゆく状況をみることができる。レプリカ法においてもR<SUB>0・1</SUB>からR<SUB>3</SUB>へと進行する状況をみることができた。<BR>6) 肉眼的診断とレプリカ所見との関係では, E<SUB>0</SUB> (肉眼的に正常のもの) から48~65%に, F<SUB>±</SUB> (凝問型) においても70~80%にR<SUB>2・3</SUB>をみとめた。<BR>7) 歯牙酸蝕症の初期変化は, レプリカ法を用いて鏡検することによって早期に発見が可能であるので, その時点, あるいは進行度によって職場転換や予防のための処置を実施することが可能となる。
1 0 0 0 台風0221による千葉県・茨城県下の園芸施設構造の被災状况と考察
- 著者
- 森山 英樹 佐瀬 勘紀 小綿 寿志 石井 雅久
- 出版者
- 農業施設学会
- 雑誌
- 農業施設 (ISSN:03888517)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.199-212, 2003-12-25
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 4
2002年10月1日20時半頃に、台風0221が神奈川県川崎市付近に上陸した。関東地方太平洋側を北上した本台風は、中心付近の最大風速が35m/sの、関東地方における戦後最大級の強さの台風であった。そのため、台風の危険半円に位置した千葉県東総地方および茨城県鹿行地方では、パイプハウスを中心とする多くの園芸施設が倒壊等の被害を受けた。今後の台風対策に資するために、被災した園芸施設7事例に関する現地調査を行った。また調査結果の整理・被災園芸施設の構造解析・接合部および基礎の耐風性の算出を行い、破壊メカニズムに関する考察を加えた。その結果、(1)南南東風を中心とする風速35m/s以上の風によって園芸施設の被災が生じたことを確認し、さらに事例毎に、(2)50m/sの風では基礎が浮き上がることと、さらに施工不良基礎では引き抜き耐力が70%以上低減すること、(3)基礎を現状よりも10cm深く埋設することにより50m/sの風でも浮き上がらなくなること、(4)斜材の設置されていない鉄骨補強パイプハウスの柱梁接合部は50m/sの風には耐えられないことを明らかにした。また、(5)風下側妻面の開放による施設内部の負圧増加が屋根を押しつぶそうとする荷重を増加させたとする破壊メカニズムの可能性を指摘し、(6)風上側に風の流れを大きく変化させる物体が存在する場合の園芸施設に適した風圧力算定方法の必要性について指摘した。