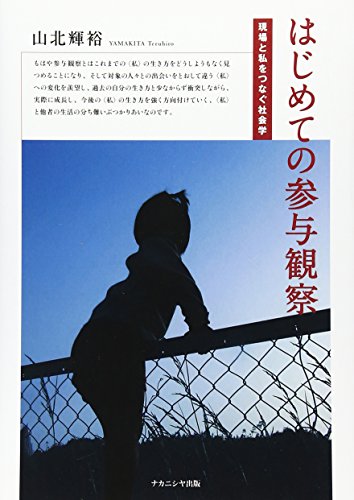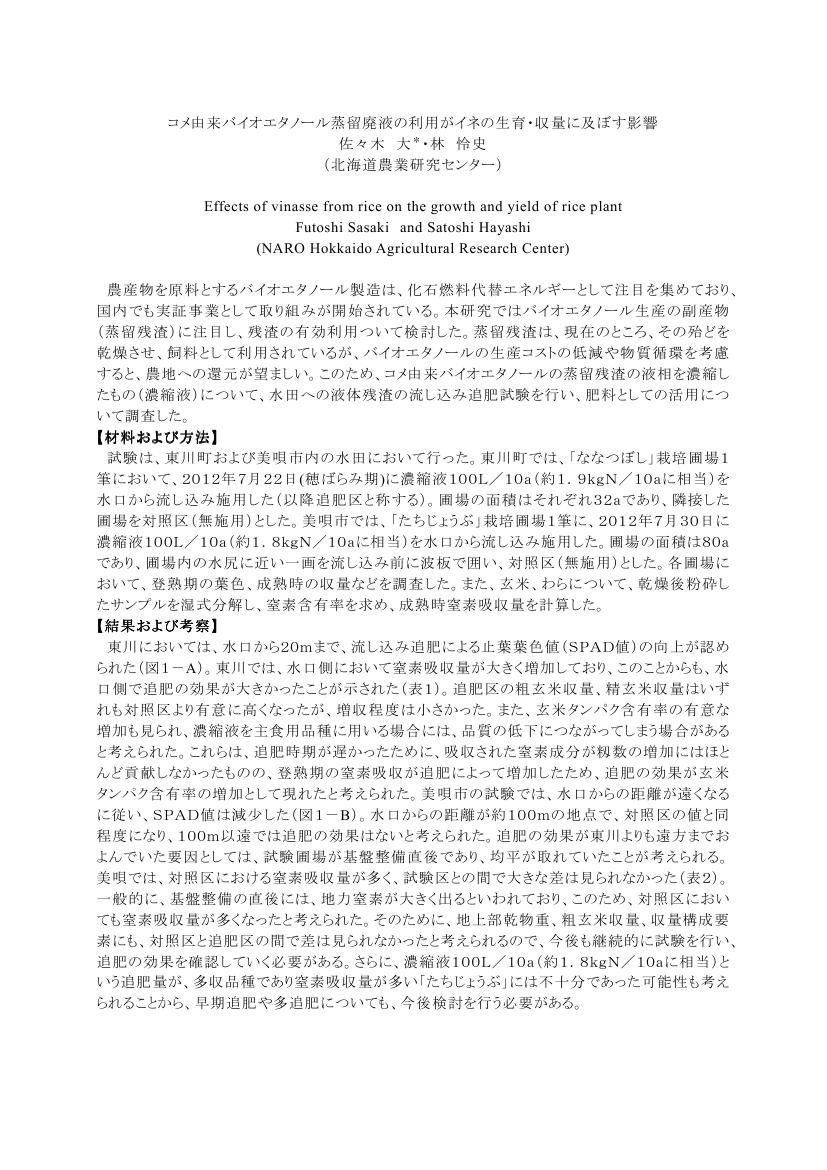1 0 0 0 OA 「絶対的無輸血」 から 「相対的無輸血」 へ
- 著者
- 瀬尾 憲正
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.498-512, 2008 (Released:2008-06-07)
- 参考文献数
- 23
「エホバの証人」 信者の宗教的理由による輸血拒否への医療従事者の対応には, いわゆる 「絶対的無輸血」 と 「相対的無輸血」 の立場がある. これまで 「エホバの証人」 信者の輸血拒否に関する訴訟は散見されるが, いずれの立場をとるべきかについては, 法令による規制はない. 自治医科大学附属病院は2007年8月30日より 「絶対的無輸血」 から 「相対的無輸血」 の立場をとることに変更した. 対応においては, 宗教的理由による輸血拒否を人格権として認めるとともに, 病院全体としての立場を明示し, 十分に説明した後に, 病院の立場を認めるかどうかについて, 宗教的圧迫にも配慮して自由に意思決定ができるようにすることが重要である.
1 0 0 0 旧タコマナローズ橋の構造減衰特性に関する一考察
- 著者
- 米田 昌弘
- 出版者
- Japanese Society of Steel Construction
- 雑誌
- 鋼構造論文集 (ISSN:18809928)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.52, pp.25-35, 2006
In this paper, the damping characteristics of the Old Tacoma Narrows Bridge which was collapsed in 1940 by wind is discussed based on the energy evaluation method. The damping values of the destroyed bridge are analyzed to grasp the contribution of dissipation energy from each construction components of the bridge. The structural damping is also discussed by using loss factors of the steel bridge which was identified by full scale measurements. From these calculation results, some pieces of useful information for the damping characteristics are obtained to reconsider the aerodynamic stability of the Old Tacoma Narrows Bridge.
1 0 0 0 OA 台湾産アゲハチョウ科の1未記録種
- 著者
- 白水 隆
- 出版者
- 日本鱗翅学会
- 雑誌
- 蝶と蛾 (ISSN:00240974)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.23-29, 1961-10-20
1961年6〜7月の台湾旅行の際に,埔里の木生(モクセイ)昆虫採集所の余清金氏の蒐集品中に台湾より未記録の美麗なアゲハチョウ科の1種を見出し,幸にこれを譲り受けて研究することが出来た.調査の結果,本種は支那大陸より知られるIphiclides alebion (GRAY,1852)の顕著な1新亜種と認むペきものであることを知ったので,次に新名を付して記載したい.また和名は余清金氏の功績を記念するため,同氏の経営になる木生昆虫採集所に因んでモクセイアゲハと呼ぶことにしたい.
1 0 0 0 顔の動きの強調
- 著者
- HILL Harold 蒲池 みゆき POLLICK Frank JOHNSTON Alan TROJE Nikolaus
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. HIP, ヒューマン情報処理 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.534, pp.19-24, 2002-12-13
- 参考文献数
- 8
似顔絵作者が人の見かけを強調して描くことができるように,ものまね芸人は人々の会話や動きを強調することができる.本研究では,平均的な値からの差分を強調するという静止画の顔の強調で用いられる概念を利用して,顔の動きを空間,時間ともに強調した.知覚実験では,意図的な情動を選択的に強調する場合において空間的な強調がより効果的であることがわかった.空間的な強調は時間に依存しているが,時間を一定にした平均値に対して行われた強調よりもより効果的である.このことは,動きそれ自体よりも強調を行う際に重要となってくる.結果としては一般に表情が知覚されるタイミングの効果が現れ,怒りは短い提示時間,悲しみはより長い提示時間で効果が現れた.この効果は意図された情動以外にも見られた.結果は時間もしくは時空間というより,空間的な手がかりが課題には重要であることを示し,強調による効果は適切な平均値からの差分を増幅した場合にのみ得られることが明らかになった.
- 著者
- 中村 正美 吉岡 俊朗 宮崎 俊行 中村 和彦
- 雑誌
- 精密工学会大会学術講演会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2002, no.2, 2002-10-01
1 0 0 0 失語症者とのコミニュケーションの展開について
- 著者
- 浅野 紀美子
- 出版者
- 日本失語症学会 (現 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会)
- 雑誌
- 失語症研究 (ISSN:02859513)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.3, pp.208-212, 1997
全失語を呈する症例のコミュニケーション行動を,次のような観点から記述した。 (1) コミュニケーションの文脈 : 患者の身体的—情動的状態に基づく文脈 (これをここでは「内的文脈」と呼ぶ) を,どう理解するか。患者の置かれた環境,患者とかかわる人,患者の生活の時間など,患者の周囲の文脈 (これを「外的文脈」と呼ぶ) を,どのようにして患者の「内的文脈」に取り込めるようにするか。 (2) メッセージ : 双方の主体のやりとり関係を維持するための行為・言語 (相互性) 。主体の意図,欲求,指示などを伝え,あるいは伝えられ,それを状況に反映させるための行為・言語 (伝達性) 。主体の知識,経験,思考などを伝え,共有するための行為・言語 (情報性) 。これらのメッセージが,どのようなかかわりのなかで交換されるか。 (3) コミュニケーションの手段 : 身体全体,身体の一部,表情,発声などの身体的表現。事物の提示や指さしによる指示的表現。ものまねや身ぶりによる象徴的表現。言葉や文字による言語的表現。これらの表現手段が,メッセージの交換のなかで変化したか。
1 0 0 0 周波数領域における混合音声の分離
- 著者
- 半田 正樹 長井 隆行 榑松 明
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. CAS, 回路とシステム (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.100, no.717, pp.1-6, 2001-03-22
- 参考文献数
- 7
音声認識システムでは、周囲に雑音が存在すると認識率が大幅に低下してしまう.複数の人が音声認識システムを利用するような環境では、入力音声に周辺の人の音声が重畳してしまい誤認識をしてしまう.この様な環境でも音声認識システムを効率的に使うためには、入力音声から周辺の人の音声を分離する必要があり、混合音声の分離方法を確立することが求められる.そこで本稿では、周波数振り分けによるマルチチャンネルの混合音声の分離法を提案する.これは、Caoらが提案する固有分解法の周波数領域での解釈から導かれる.本手法は、入力音声をFFTにより周波数領域に変換し、各周波数成分が元々どのチャンネルの成分だったのかを判断して、周波数の振り分けを行うことにより音声分離を行う.独立成分分析(ICA)との性能比較、計算機シミュレーションにおける実験結果、および実環境での実験を通して、本提案手法の有効性を明らかにする.
- 著者
- 久保田 裕子
- 出版者
- 日本近代文学会
- 雑誌
- 日本近代文学 (ISSN:05493749)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, pp.277-280, 2013
1 0 0 0 OA 3回目のフィリピンのミンダナオ島でのジュゴン調査
1 0 0 0 院展の90年<特集>
- 著者
- 土門 拳
- 出版者
- 美術出版社
- 雑誌
- 美術手帖 (ISSN:02872218)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.916, pp.188-195, 2008-12
1 0 0 0 テクストを解き放つために(学界時評)
- 著者
- 久米 依子
- 出版者
- 日本近代文学会
- 雑誌
- 日本近代文学 (ISSN:05493749)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, pp.171-175, 2013
1 0 0 0 はじめての参与観察 : 現場と私をつなぐ社会学
1 0 0 0 地中レーダによる地下イメージング
- 著者
- 佐藤 源之
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌. C, エレクトロニクス (ISSN:13452827)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.7, pp.520-530, 2002-07-01
- 被引用文献数
- 42
地中レーダを用いた地下計測について現状とイメージングのための技術について解説する.地中レーダ計測が実用的に利用されている分野を紹介し,弾性波計測に対する地中レーダの特徴をまとめる.次にイメージングのために現在用いられている逆散乱問題としてのアプローチとマイグレーションによるアプローチを紹介する.現状では地中レーダについてはマイグレーションによるイメージングが多く利用されており,本論文ではKirchhoffマイグレーション,f-κマイグレーション,リバースタイムマイグレーションについて具体的なデータを用いて説明する.
1 0 0 0 OA 恋愛における告白の状況と個人差 (シャイネス・社会的スキル) に関する研究
- 著者
- 栗林 克匡
- 出版者
- 北星学園大学
- 雑誌
- 北星学園大学社会福祉学部北星論集 (ISSN:13426958)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.11-19, 2002-03
1 0 0 0 OA コメ由来バイオエタノール蒸留廃液の利用がイネの生育・収量に及ぼす影響
- 著者
- 佐々木 大 林 怜史
- 出版者
- 日本作物学会
- 雑誌
- 日本作物学会講演会要旨集 第236回日本作物学会講演会
- 巻号頁・発行日
- pp.210, 2013 (Released:2013-09-08)
1 0 0 0 OA SVMによる笑顔度推定技術を用いた音楽療法効果の評価
- 著者
- 嶋田 敬士 山田 亨 高崎 友香 野口 祥宏 山崎 郁子 福井 和広
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.12, pp.2569-2581, 2014-12-15
病院でのリハビリテーションの一環として行われる取り組みの1つに,音楽療法士が音楽の力を意図的・計画的に利用して,患者の心身障害の回復や機能の改善に役立てる音楽療法がある.従来その効果は,病院や音楽療法士が各々独自に設けた評価基準と介入内容の記録などを通じて質的・量的に評価する方法が試みられてきたが,患者の症状,回復状況や個性が様々なことなどから,客観的で統一的な評価方法を確立することは非常に困難であった.そこで我々は,患者の心身賦活にともなって広く一般的に見られる表情である笑顔に着目し,評価記録用に撮影された音楽療法時の映像データのみから患者の笑顔度を定量化した.さらに,あらかじめ構造化されていた療法内容に着目し,介入の質が異なる場面での笑顔度の違い,それらの経過回数にともなう変化を統計的に検定した.その結果,療法内容と経過にともない統計的に有意な患者の表情変化を確認するとともに,その変化が従来行われてきた主観評価結果とも高い相関を示していることを確認した.
1 0 0 0 OA 望月喜市教授略歴・著作目録
- 出版者
- 北海道大学スラブ研究センター
- 雑誌
- スラヴ研究(Slavic Studies) (ISSN:05626579)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.246-253, 1994