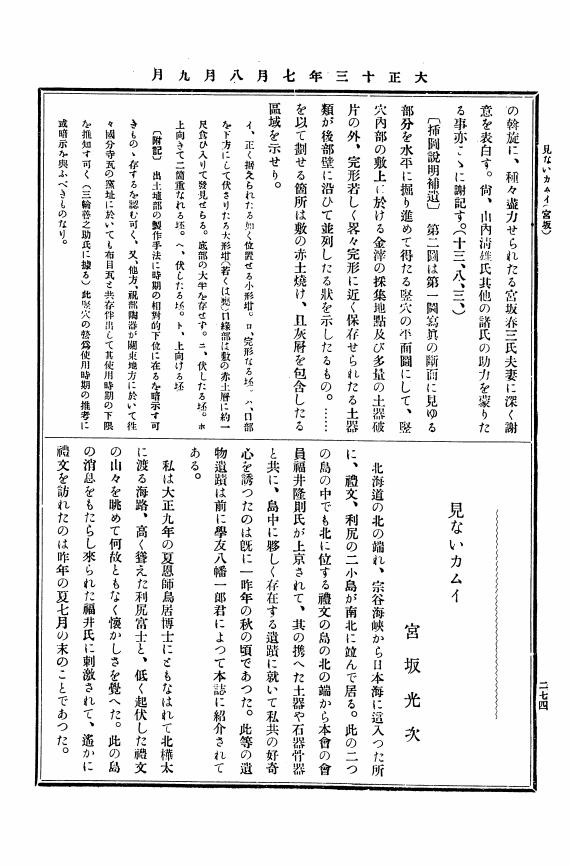2 0 0 0 OA 明治以降昭和戦前までの北海道における観光的取組の展開過程に関する研究
- 著者
- 大西 律子 渡邉 貴介
- 出版者
- 日本観光研究学会
- 雑誌
- 観光研究 (ISSN:13420208)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.25-34, 1998 (Released:2017-04-01)
This study aims to clarify the evolution process of tourism policies and developments in Hokkaido pushed by the authority since the Meiji era to the beginning of the Showa era. Based on related historical documents the chronological table is originally made, on which the analysis is concluded. The findings are as follows; (1) The development process can be divided into three stages in broad sense and into six in precise sense. (2) Through the process seven strategic ideas had been invented or introduced in Hokkaido, most of which were more leading than in other parts of Japan.
2 0 0 0 OA ネットワーク社会における〈告白〉事情
- 著者
- 山口 達男
- 出版者
- 一般社団法人 社会情報学会
- 雑誌
- 社会情報学 (ISSN:21872775)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.55-70, 2021-02-28 (Released:2021-03-16)
- 参考文献数
- 24
本稿は,Z. BaumanがSNSやインターネットへのアップロードを「告白」として捉え,それらが日常的に行なわれている現代社会を「告白社会」と評したことに対して,批判的に検討する試みである。その際にまずM. Foucaultの議論を参照し,4~5世紀の修道院で行なわれていた「エグザコレウシス」や,中世以降のキリスト教における「告解」の特徴を整理することで,キリスト教的告白には「権力関係」「言表行為」「文脈依存」「秘密主義」という四つの特徴があることを明らかにした。次に,非キリスト教的な在り方を探るため,日本近代文学で描かれてきた告白についても言及した。そこでもやはり「権力関係」「言表行為」という特徴を見出すことができた。他方,インターネットをコミュニケーションの技術的な基盤としている現代社会にとって,こうした特徴はすべて無効化されてしまう。「ネットワーク」の特性として「平面化」「データ化」「脱文脈化」「透明化」を挙げることができるからだ。つまり,ネットワークの特性は告白の特徴を無化してしまうのである。したがって,ネットワーク社会の現代では,SNSやインターネット上で告白するのは不可能な営みと指摘できる。むしろ,ネットワークの特性から窺えるのは,われわれのあらゆる情報がインターネット上に〈露出〉していってしまう状況である。すなわち,われわれはインターネットに向けて何かを告白しているのではなく,ネットワークの「運動」によってわれわれの営みが露出させられているのだ。このことを踏まえると,Baumanが評したのとは異なり,現代社会は「告白社会」ではなく〈露出化社会〉と称すべきだと言い得る。
2 0 0 0 OA 見ないカムイ
- 著者
- 宮坂 光次
- 出版者
- 一般社団法人 日本人類学会
- 雑誌
- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.7-9, pp.274-279, 1924-11-14 (Released:2010-06-28)
2 0 0 0 OA 中国雲南省に居住する彝族の婚姻慣習法に関する考察 ―法人類学の視点から―
- 著者
- 高橋 孝治
- 出版者
- 日中社会学会
- 雑誌
- 21世紀東アジア社会学 (ISSN:18830862)
- 巻号頁・発行日
- vol.2019, no.10, pp.149-165, 2019-08-31 (Released:2019-12-04)
- 参考文献数
- 43
中国的少数民族之一、彝族的婚姻习惯法至今被认为 “在彝族血缘等级制度和意识形态的庇护下,彝族实行严格的本族内婚、家支外婚、等级内婚、姑舅表优先婚等,这些牢不可破的婚姻法则历经数千年不变”。但是,住在不同的地方的彝族的习惯也不同。所以,本文是住在云南省的各彝族按住在的地方分类,考察各个地方彝族的婚姻习惯法的。 本文指摘“彝族实行严格的本族内婚、家支外婚、等级内婚、姑舅表优先婚”的认识不对,要认为“彝族的婚姻习惯法有本族内婚、家支外婚、等级内婚、姑舅表优先婚的倾向。
- 著者
- 茅 明子 奥和田 久美
- 出版者
- 研究・イノベーション学会
- 雑誌
- 年次大会講演要旨集 29 (ISSN:24327131)
- 巻号頁・発行日
- pp.109-112, 2014-10-18 (Released:2018-01-30)
2 0 0 0 OA 成長期の予備校英語教育-我が青春賦-
- 著者
- 祐本 寿男
- 出版者
- 日本英語教育史学会
- 雑誌
- 日本英語教育史研究 (ISSN:0916006X)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.177-192, 1994-05-10 (Released:2012-10-29)
- 著者
- 神宮 字寛 露崎 浩
- 出版者
- 日本雑草学会
- 雑誌
- 雑草研究 (ISSN:0372798X)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.55-62, 2007 (Released:2008-08-09)
- 参考文献数
- 16
ガムシ科の甲虫コガムシHydrophilus affinis Sharpは,卵のうを形成する際に生の雑草の葉を利用する。近年,コガムシの個体数の減少が各地で報告され,絶滅危惧種に指定した県が複数ある。筆者らは,コガムシの個体数の減少には,卵のうを形成するために必要な水田内および畦畔雑草の減少が関与していると考えた。そこで,本種の保全を図るためにコガムシの産卵と雑草の関係を調査した。 コガムシは主に畦畔の雑草の葉身を卵のう形成に用いた。平均卵のう数は,水田内区の0.5個/m2に比べて畦畔隣接区で9.3個/m2と有意に多かった。畦畔隣接区で確認された草種の18科40種のうち,11科16種が卵のう形成に利用された。Jacobsの選択指数から,正の選択指数を示す種(ツユクサ,クサヨシなど),畦畔辺によって正あるいは負の選択指数を示す種(ヤナギタデ,イヌタデなど),および負の選択指数を示す種(スズメノテッポウなど)に分類できた。 卵のう形成に用いられた葉身の76%は,畦畔水際から30cmの範囲内に存在し,葉身の切除位置は水面下1cm∼水面であった。葉身の大きさは,長さ23mm∼34mm,幅9∼20mmの範囲に分布した。卵のう内の平均卵数は69∼81卵数を示し,草種ごとに大きな差は認められなかった。以上の結果を基に,卵のう形成に用いる草種の選択性および利用様式について考察するとともに,保全生物学的な観点から畦畔雑草の管理を考えた。
- 著者
- Yuta NISHIYAMA Yasuhiro FUKUYAMA Takuya MARUO Shinichiro YODA Masataka IWANO Shinpei KAWARAI Hideki KAYANUMA Kensuke ORITO
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.21-0060, (Released:2021-06-18)
Tegafur is a prodrug of fluoropyrimidine 5-fluorouracil (5-FU), while TS-1TM is an oral fixed-dose combination of three active drugs, tegafur, gimeracil, and oteracil. This pilot study evaluated the safety of tegafur/gimeracil/oteracil in the treatment of cancers in dogs. Tegafur/gimeracil/oteracil was administered orally at a mean dose of 1.1 mg/kg twice daily on alternate days, Monday-Wednesday-Friday, every week to 11 dogs with tumors. Partial response and stable disease were observed in one dog each, whereas six exhibited progressive disease. Three dogs were not assessed. Adverse events, the most serious being grade 2, were noted in seven dogs. Adverse events were acceptable, and the drug was effective in some dogs. Therefore, tegafur/gimeracil/oteracil may be useful for treating malignant solid tumors in canines.
2 0 0 0 OA 対称性と魅力・美しさの関係
- 著者
- 尾田 政臣
- 出版者
- 日本認知心理学会
- 雑誌
- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第6回大会
- 巻号頁・発行日
- pp.106, 2008 (Released:2008-11-10)
動物行動学では,繁殖のための相手選びに体の対称性が重要な役割を果たしていると主張している。顔の魅力についても同様の議論がなされている。本稿では,顔および顔以外の対象として幾何学図形,模様,動物,昆虫などを選び,魅力度ならびに美しさを評定させる心理実験を行った。実験は1課題につき4種類の図形を同時に提示し,各図形に対して絶対評価で評定させた。その結果,従来の実験結果と同様に,片目が大きく他の部位は対称である非対称顔が,総ての部位が対称である顔より魅力度・美しさが高い値を示した。また,いずれも左右対称である4種の幾何学図形に対しては,図形の種類によって評価値が異なり,動物や昆虫については,ある程度の非対称性があっても許容され高い評価値を示していた。即ち,対称性が常に魅力を決定する最大の要因となるわけではなく,また魅力と美しさの評価は必ずしも一致する訳ではないことが明らかになった。
2 0 0 0 OA 新型コロナウイルス対策における線引き問題―レギュラトリーサイエンスの視点から―
- 著者
- 永井 孝志
- 出版者
- 一般社団法人 日本リスク学会
- 雑誌
- リスク学研究 (ISSN:24358428)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.3, pp.147-153, 2021-04-25 (Released:2021-04-24)
- 参考文献数
- 12
The present study investigated the rationale for the derivation of criteria in the measures against novel Coronavirus Disease (COVID-19). The following four cases were included in this study: the physical distance (social distance) of “1–2 m”; the criterion for ending isolation and returning to work after a COVID-19 suspected fever of “8 days after onset of fever”; the criterion for medical consultation and examination of “fever of more than 37.5°C for 4 days”; and the criteria for lifting intervention of self-restraint in each prefecture. These criteria could not be derived based on clear scientific facts in all cases. The actual processes of how the criteria were derived were organized.
2 0 0 0 OA 貯蔵期間の異なる手延そうめんの性状と構造観察
- 著者
- 細田 捺希 高山 裕貴 赤田 樹 青井 雄幹 原 信岳 吉村 美紀
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.6, pp.386-394, 2019-12-05 (Released:2019-12-20)
- 参考文献数
- 22
貯蔵期間の異なる手延べそうめんの性状と構造に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。貯蔵期間0ヶ月,6ヶ月,12ヶ月,24ヶ月の試料を用いた。放射光X線マイクロCT観察の結果から,貯蔵期間の長い12ヶ月,24ヶ月貯蔵試料は,乾麺内部に大きな隙間構造と乾麺表面には線吸収係数の大きな構造物が多く観察された。示差走査熱量測定において,貯蔵期間が長くなると,第1吸熱ピーク及び第2吸熱ピークのピークが低温側と高温側に移動し,乾麺試料1 mgあたりのエンタルピーは増加する傾向がみられた。これにより小麦でんぷんの結晶性が増加し,でんぷんの糊化及びたんぱく質の変性が抑制されると推察した。
- 著者
- Yusuke Ide
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE (ISSN:21854106)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.16-27, 2019 (Released:2019-01-01)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1
In this paper, we show reduction methods for search algorithms on graphs using quantum walks. By using a graph partitioning method called equitable partition for the the given graph, we determine “effective subspace” for the search algorithm to reduce the size of the problem. We introduce the equitable partition for quantum walk based search algorithms and show how to determine “effective subspace” and reduced operator.
2 0 0 0 OA 認知症の治療の進歩
- 著者
- 脇田 英明 冨本 秀和
- 出版者
- 日本神経治療学会
- 雑誌
- 神経治療学 (ISSN:09168443)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.5, pp.491-494, 2018 (Released:2018-04-05)
- 参考文献数
- 10
Dementia affects over 35 million people in the world with a rapidly increasing prevalence. Alzheimer's disease (AD) is the most common form of dementia. No fundamental treatment for AD has been established, and novel therapeutic strategies are under investigation. This progress has led to the development of numerous therapeutic strategies in the clinical testing. Immunotherapy against Aβ has been pursued extensively as a therapeutic approach to Alzheimer's disease, and several other promising trials are currently ongoing. In addition, new therapeutic strategies have been reported in Huntington's disease and frontotemporal dementia. This review overviews recent advances in basic and clinical research in dementia.
2 0 0 0 OA 二人称の死
- 著者
- 養老 孟司
- 出版者
- 日本医学哲学・倫理学会
- 雑誌
- 医学哲学 医学倫理 (ISSN:02896427)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.179-183, 1999-10-01 (Released:2018-02-01)
- 著者
- Fletcher DEL VALLE Sherwin CAMBA Dennis UMALI Kazutoshi SHIROTA Kazumi SASAI Hiromitsu KATOH Tomoko TAJIMA
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.5, pp.520-526, 2020 (Released:2020-05-30)
- 参考文献数
- 17
Three strains of chicken anemia virus (CAV) were detected in 11 to 14-weeks old chickens, showing depression, wasting, and increased mortality, from three farms in eastern Japan. Another strain was detected in 12-weeks old chickens from one farm without clinical signs. Bacterial infections were suggested in three farms with clinical signs and its involvement in the occurrence of the diseases might be suspected. Sequence analysis of the VP1, VP2, and VP3 genes of four CAV strains revealed that the three from farms with clinical signs belonged to genotype A2, whereas that from the apparently-normal farm belonged to A3. This may be a rare case report about the diseases suspected of the involvement of the CAV infection in older birds.
2 0 0 0 OA ライオンによる外傷の初期画像診断に関する報告1例
- 著者
- 水津 利仁 水野 正之 阿部 雅志 松本 尚
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.52-57, 2020-02-29 (Released:2020-02-29)
- 参考文献数
- 8
諸外国(アフリカやインドなど)では遭遇する機会もまれではないが,わが国ではきわめてまれなライオンによる外傷を経験したので報告する。わが国では大型の野生動物による外傷といえばクマによる外傷の報告が多く,頭頸部と顔面から胸部までの上半身に与える損傷が大多数である。本症例はクマによる報告同様,頭部と頸部に受けた損傷が大きく,それ以外の部位では擦過傷程度であった。また,クマによる外傷は殴打による爪外傷の報告が多いのに対し,ライオンは牙による咬傷が多く,受傷形態はイヌ・ネコによる咬傷に近い。クマとライオン,イヌ・ネコとライオンそれぞれの外傷の類似点を踏まえ,今後同じような症例に遭遇した場合,造影CT検査を行ううえでの撮影法とその考え方について考察した。
2 0 0 0 OA 音声知覚の運動理論をめぐってて(<小特集>人間の音声情報処理機構の解明に向けて)
- 著者
- 柏野 牧夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.5, pp.391-396, 2006-05-01 (Released:2017-06-02)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 2
2 0 0 0 OA 精神障害者の地域ケアの中での社会生活技能訓練(展望,<特集>精神障害者援助とSST)
- 著者
- 安西 信雄 池淵 恵美
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.11-22, 2004-03-31 (Released:2019-04-06)
わが国の精神保健分野における社会生活技能訓練(SST)の本格的な導入は、1988年の米国UCLAのLiberman来日から始まった。その後約15年の発展経過をSSTの普及状況に関する6回のアンケート調査にもとづき検討した。その結果、(1)SSTは生活行動の改善を目標にデイケアを中心に開始され、(2)診療報酬化(1994年)以後は医療機関だけでなく非医療機関においても実施施設数の増加がみられ、(3)対象の拡大(統合失調症以外の気分障害や神経症圏、さらに司法など医療以外の対象へ)と技法の多様化(基本訓練モデルに加えて各種モジュールも実施)の傾向が認められた。普及の過程で生じた誤解や批判について検討し、普及におけるSST普及協会の役割を検討した。 SSTに関連した研究報告の経年推移を検討し、研究の動向を概括した。今後のわが国の地域ケアへの転換に関連して、生活の場での行動改善、長期在院患者の退院促進等にSSTが寄与すべきことを考察した。
2 0 0 0 OA 医師の立場から(急性期)
- 著者
- 岩坂 日出男
- 出版者
- 日本静脈経腸栄養学会
- 雑誌
- 静脈経腸栄養 (ISSN:13444980)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.3, pp.867-874, 2012 (Released:2012-06-15)
- 参考文献数
- 37
急性期重症患者の栄養管理の目的は除脂肪体重量の維持にある。この目的に栄養アセスメントは重要な位置を占めてくる。しかし急性炎症反応による血管透過性の亢進、輸液負荷などにより伝統的な栄養アセスメント法である身体計測、アルブミン値、Rapid turnover proteinの有効性は消失してしまう。また基本的な病歴聴取も不可能な場合が多くなる。このような状態での栄養アセスメントのためには疾患の重症度、全身炎症反応の程度、これらによってもたらされるストレス誘導性高血糖などの病態を理解し、早期経腸栄養など適切な栄養療法を選択する必要がある。また栄養療法に伴って生じるRefeeding症候群などを理解し、常に栄養療法の効果、合併症についてアセスメントを繰り返すことが重要と考えられる。
2 0 0 0 OA 鈴木大拙における妙好人研究の位置づけ
- 著者
- 末村 正代
- 出版者
- 宗教哲学会
- 雑誌
- 宗教哲学研究 (ISSN:02897105)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.72-84, 2017-03-31 (Released:2017-06-01)
D. T. Suzuki (1870-1966) is a philosopher of Zen Buddhism known as a person who introduced it to the West. He is known for studies not only about Zen but also Pure Land thought on Buddhism, and he was certain that there was a kind of common state between Zen and Pure Land thought. He studied about both Zen and Pure Land thought all his life, in particular, his thought achieved remarkable development from the 1930’s to the 1940’s. One of the reasons for this development was connected with a discovery of the people called myoko-nin in the early 1940’s. Myoko-nin are the people who are firm believers on Shin Buddhism. Through contact with their faith and their religious experiences, Suzuki deepened his understanding about Pure Land thought. In this paper, the author will compare Suzuki’s Pure Land thought in the 1930’s with that in the 1940’s, and attempt to clarify the reason why he devoted himself to myoko-nin studies and how the studies influenced on his Pure Land thought and his whole philosophy.