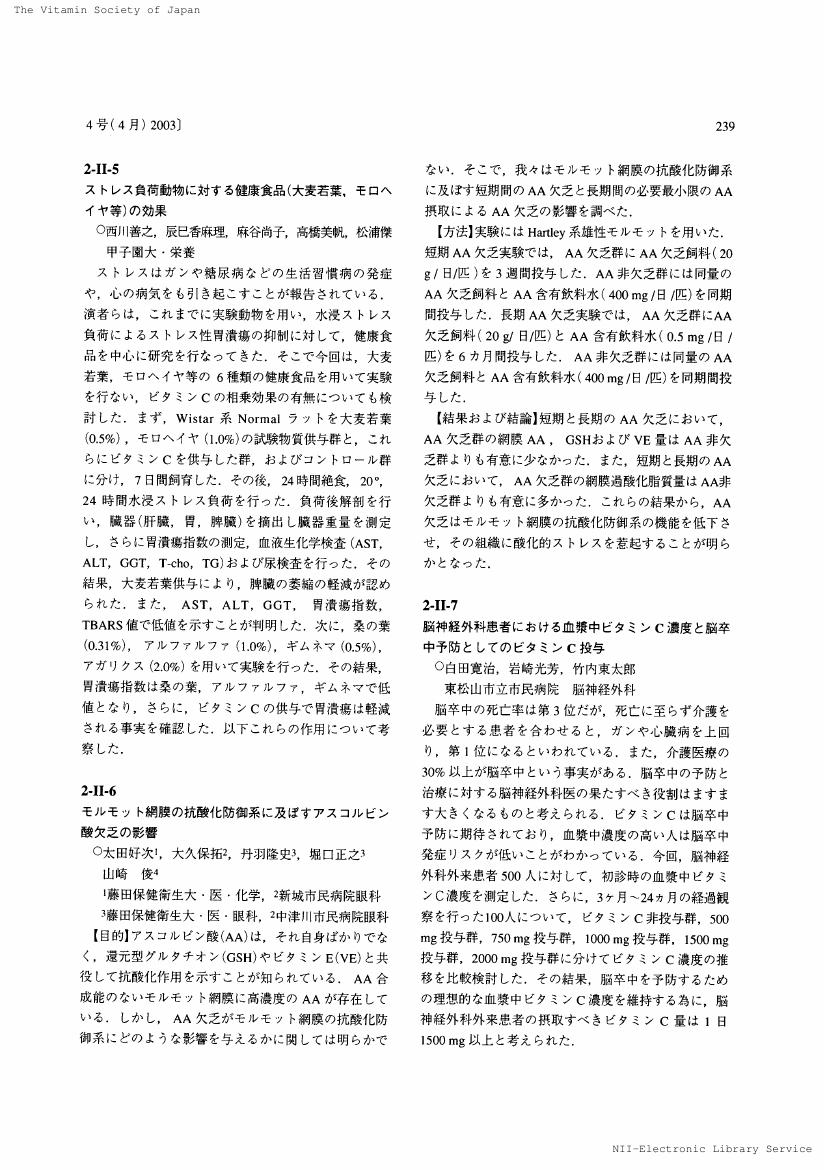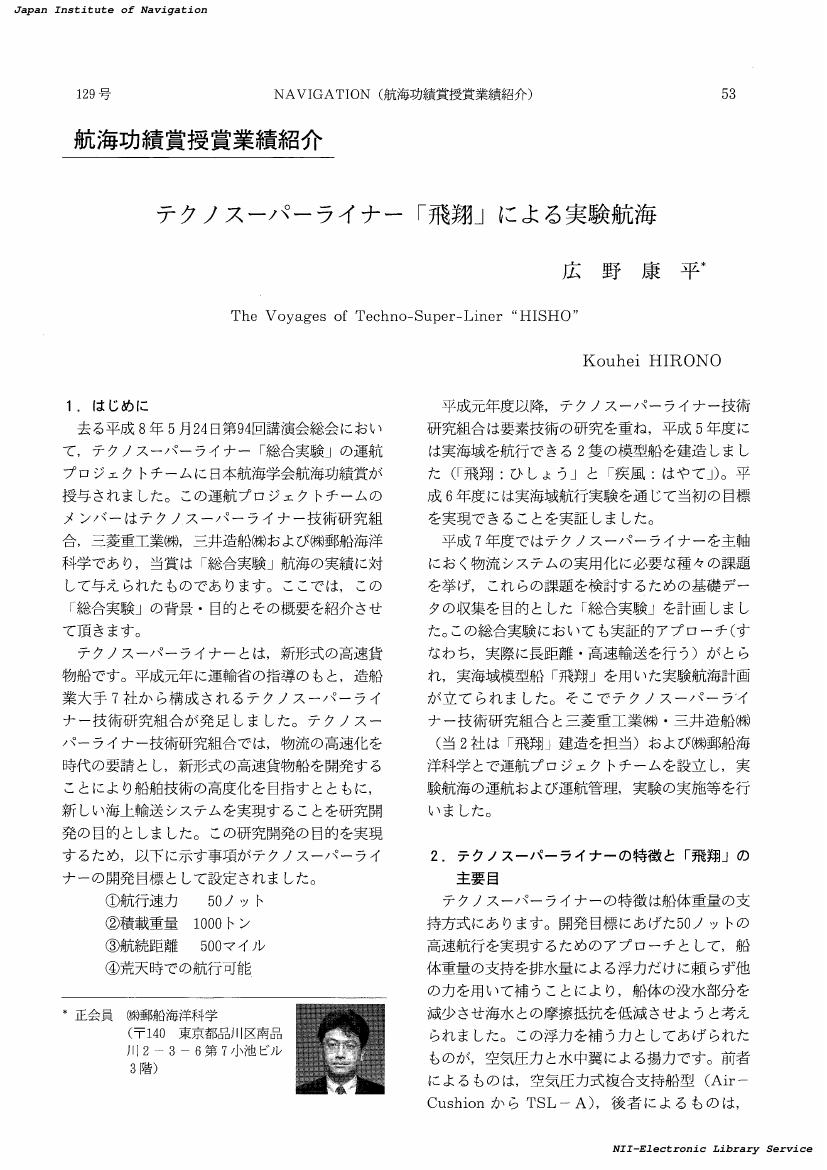2 0 0 0 OA セラミックス複合系における微粉末混合に及ぼすアルコール溶媒の影響と焼結体の性質
- 著者
- 中平 敦 武田 真一 塩見 治久 大西 宏司
- 出版者
- The Ceramic Society of Japan
- 雑誌
- Journal of the Ceramic Society of Japan (日本セラミックス協会学術論文誌) (ISSN:09145400)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, no.1247, pp.662-667, 1999-07-01 (Released:2010-08-06)
- 参考文献数
- 29
Effect of alcohol solvent in mixing process on the microstructure and sintering behavior of ceramic-based composites was investigated in detail. The mixture of fine ceramic powders was prepared through the conventional ball-milling method with various alcohol media. The particle distributions of fine ceramic powders were strongly dependent on the kind of alcohol employed during ball-milling. Ceramic-based composites were fabricated by hot-pressing the mixture of fine ceramic powders. Their microstructures and some mechanical properties of the ceramic-based composites were evaluated. It was found that the viscosity of alcohol, surface tension and contact angle greatly affect the sinterability and some of the mechanical properties of ceramic-based composites.
2 0 0 0 OA 胸骨圧迫によって下行大動脈に偽腔破裂を呈したと考えられた急性大動脈解離術後の1救命例
- 著者
- 有馬 大輔 梅木 昭秀 山本 哲史
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本心臓血管外科学会
- 雑誌
- 日本心臓血管外科学会雑誌 (ISSN:02851474)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.73-76, 2019-01-15 (Released:2019-02-02)
- 参考文献数
- 5
心肺蘇生の際の胸骨圧迫に伴うさまざまな合併症が報告されている.大動脈解離術後に心肺停止に陥り胸骨圧迫による偽腔破裂を呈したと考えらえた症例を経験した.症例は79歳の女性.上行大動脈にentryを呈した急性大動脈解離(Stanford A型,DeBakey I型)の診断で,緊急手術を施行した.術後は特に問題なく経過し,POD 5にICUを退室するも,POD 6に痰詰まりから心肺停止となり,胸骨圧迫が施行された.蘇生したが,左胸腔ドレーンから血性排液が増加したため,施行した造影CT検査で下行大動脈偽腔から左胸腔に造影剤の流出を認めた.硬膜外血腫も同時に呈しており,保存的加療と低体温療法を施行した.幸い輸血と止血剤の投与で血管外漏出が停止した.開心術症例の胸骨圧迫後には,造影CTなどで出血の確認をするべきで,大動脈解離術後の胸骨圧迫では,稀ではあるが偽腔破裂が生じ得る可能性が示唆された.
- 著者
- 岸田 功
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.34-35, 2002-01-20 (Released:2017-07-11)
2 0 0 0 OA コルモゴロフ複雑度による乱流のランダムさ表現(混合層の場合)
- 著者
- 一宮 昌司 中村 育雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集B編 (ISSN:18848346)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.788, pp.794-810, 2012 (Released:2012-04-25)
- 参考文献数
- 62
- 被引用文献数
- 4 4
Investigations on the definition and randomness of turbulence was reviewed at first. Then, the Kolmogorov complexity which measures the randomness were introduced. Numerical and graphic data in the mixing layer which was formed downstream of two-dimensional nozzle exit were compressed with the aid of a compression program. Approximated Kolmogorov complexity, AK, and normalized compression distance, NCD, were obtained. The AK indicated the regularity of the laminar flow and the randomness of the turbulent flow quantitatively. The NCD of the numerical value varied with data length. Between the same data, it approached zero, yet, on the other hand, between different data, it approached unity as the data length increased. The NCD of the numerical value in the natural transition process in the mixing layer increased monotonically downstream. Thus the NCD appears to be the measure of the transition process. In the natural transition process in the mixing layer, the AK of the numerical value and the NCD of the graphic data did not change monotonously in the downstream direction. Thus they contain some uncertainty for the measure of the transition process.
2 0 0 0 OA H5N1鳥インフルエンザウイルスはヒトで流行するか?
- 著者
- 渡辺 登喜子 渡辺 真治 河岡 義裕
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.10, pp.2705-2713, 2013-10-10 (Released:2014-10-10)
- 参考文献数
- 11
H5N1高病原性鳥インフルエンザウイルス(以後,“H5N1ウイルス”と呼ぶ)が,世界各地に拡大している.それに伴い,ヒトにおける感染例も増えてきており,これまでに600人ほどの感染が確認され,60%近い致死率が報告されている.確認されている感染例が限られていることから,ヒトには比較的感染しづらく,感染したとしてもヒトからヒトへの伝播が起こりにくいと考えられている.しかし,ウイルス遺伝子の交雑やウイルス蛋白質のアミノ酸変異により,ひとたびH5N1ウイルスが,これまでよりヒトへ感染しやすくなり,さらにヒトからヒトへと効率よく伝播する能力を獲得すれば,致死率の高いH5N1ウイルスが世界的大流行(パンデミック)を起こす危険性がある.本稿では,最近の研究から得られた知見を元に,H5N1ウイルスがパンデミックを起こす可能性について議論したい.
2 0 0 0 OA 人工生命と生物指向人工物
- 著者
- 上田 完次
- 出版者
- 科学基礎論学会
- 雑誌
- 科学基礎論研究 (ISSN:00227668)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.1-6, 1995-12-25 (Released:2009-07-23)
- 参考文献数
- 14
2 0 0 0 OA 学習をもたらす職場:情報の開放性と職場の凝集性の学習行動への影響
- 著者
- 鈴木 竜太
- 出版者
- 特定非営利活動法人 組織学会
- 雑誌
- 組織科学 (ISSN:02869713)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.2, pp.16-27, 2014 (Released:2015-04-25)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 2
本論文は,個人の2つの学習行動をもたらす職場の要因について明らかにすることが目的である.具体的には,職場における情報の開放性と凝集性が自分自身の能力や知識を高める個人学習行動と自分の持っている知識や情報を職場の同僚と共有する組織学習行動への影響と,個人学習行動の組織学習行動への効果への影響について実証研究によって明らかにする. 実証研究の結果からは職場の2 つの要因は直接的に2つの学習行動に影響を与えないが,個人学習行動を行う人がより組織 学習行動を行うようになることを促す効果があることが示された.
2 0 0 0 OA ROSを利用した宇宙機ミドルウェアの構築
- 著者
- 斎藤 達彦 加藤 裕基 平野 大地
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.10, pp.729-732, 2018-10-10 (Released:2018-10-13)
- 参考文献数
- 9
- 著者
- David CHANDLER
- 出版者
- イギリス・ロマン派学会
- 雑誌
- イギリス・ロマン派研究 (ISSN:13419676)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, pp.62-66, 2020-03-30 (Released:2021-04-21)
2 0 0 0 OA 秋田縣下ノ古器物ニ付キテ簑虫老人ヨリノ書簡
- 出版者
- 一般社団法人 日本人類学会
- 雑誌
- 東京人類學會雜誌 (ISSN:18847641)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.23, pp.108, 1888 (Released:2010-06-28)
2 0 0 0 OA Persistent Systemic Inflammation Is Associated With Bleeding Risk in Atrial Fibrillation Patients
- 著者
- Yuma Hamanaka Yohei Sotomi Akio Hirata Tomoaki Kobayashi Yasuhiro Ichibori Nobuhiko Makino Takaharu Hayashi Yasushi Sakata Atsushi Hirayama Yoshiharu Higuchi
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-19-1006, (Released:2020-02-11)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 8 17
Background:This study investigated the impact of systemic inflammation on bleeding risk in non-valvular atrial fibrillation (NVAF) patients treated with direct oral anticoagulants (DOAC).Methods and Results:We conducted a single-center prospective registry of 2,216 NVAF patients treated with DOAC: the DIRECT registry (UMIN000033283). High-sensitivity C-reactive protein (hsCRP) was measured ≤3 months before (pre-DOAC hsCRP) and 6±3 months after initiation of DOAC (post-DOAC hsCRP). Multivariate logistic regression model was used to assess the influence of systemic inflammation and conventional bleeding risk factors on major bleeding according to International Society on Thrombosis and Haemostasis criteria. Based on the findings, we created a new bleeding risk assessment score: the ORBIT-i score, which included post-DOAC hsCRP >0.100 mg/dL and all components of the ORBIT score. A total of 1,848 patients had both pre- and post-DOAC hsCRP data (follow-up duration, 460±388 days). Post-DOAC hsCRP was associated with major bleeding (OR, 2.770; 95% CI: 1.687–4.548, P<0.001). Patients with post-DOAC hsCRP >0.100 mg/dL more frequently had major bleeding than those without (log-rank test, P<0.001). ORBIT-i score had the highest C-index of 0.711 (95% CI, 0.654–0.769) compared with the ORBIT and HAS-BLED scores.Conclusions:Persistent systemic inflammation was associated with major bleeding risk. ORBIT-i score had a higher discriminative performance compared with the conventional bleeding risk scores.
2 0 0 0 OA 超電導発電機
- 著者
- 武居 秀実
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会誌 (ISSN:13405551)
- 巻号頁・発行日
- vol.124, no.7, pp.401-404, 2004-07-01 (Released:2008-04-17)
- 参考文献数
- 2
- 著者
- 西川 善之 辰巳 香麻理 麻谷 尚子 高橋 美帆 松浦 傑
- 出版者
- 公益社団法人 日本ビタミン学会
- 雑誌
- ビタミン (ISSN:0006386X)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.4, pp.239, 2003-04-25 (Released:2017-12-26)
2 0 0 0 OA 準定在的で非常に長い極域成層圏雲層境界の事例研究
- 著者
- Peter VOELGER Peter DALIN
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, no.2, pp.497-504, 2021 (Released:2021-04-26)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 2
A case study of the occurrence of polar stratospheric clouds (PSCs) on February 13th, 2017, in northern Sweden is reported in this paper. For the first time, a quasistationary edge of a bright and extended PSC layer (∼ 600-km long) on the eastern side of the Scandinavian mountain range was photographed and registered using lidar observations. Both lidar measurements and model simulations demonstrated that atmospheric conditions were fairly unchanged for several hours during the presence of the PSC. Strong winds across the Scandinavian mountain range were responsible for triggering the formation of mountain lee waves in the Kiruna area, which induced the formation of the quasistationary long and straight edge of the PSCs.
- 著者
- JAIN Shipra CHHIN Rattana DOHERTY Ruth M. MISHRA Saroj K. YODEN Shigeo
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- pp.2021-021, (Released:2021-01-13)
Equilibrium climate sensitivity (ECS) is defined as the change in global-mean surface air temperature due to the doubling or quadrupling of CO2 in a climate model simulation. This metric is used to determine the uncertainty in future climate projections, and therefore the impact of model changes on ECS is of large interest to the climate modeling community. In this paper, we propose a new graphical method, which is an extension of the Gregory's linear regression method, to represent the impact of model changes on ECS, climate forcing and climate feedbacks in a single diagram. Using this visualization method, one can quantify (a) whether the model- or process-change amplifies, reduces, or has no impact on global warming, and evaluate (b) the percentage changes in ECS, climate forcing and climate feedbacks and (c) ranges of the uncertainties in the estimated changes. We demonstrate this method using an example of climate sensitivity simulations with and without interactive chemistry. This method can be useful for multi-model assessments where the response of multiple models for the same model experiment (e.g., usage of interactive chemistry as compared to the prescribed chemistry as shown here) can be assessed simultaneously, which is otherwise difficult to compare and comprehend. We also demonstrate how this method can be used to examine the spread in ECS, climate forcing and climate feedbacks with respect to the multi-model mean (or one benchmark model) for multi-model frameworks like Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 or for different ensemble members in a large ensemble of simulations carried out using a single model.
- 著者
- Prasad Rajkishore Fumitoshi Matsuno
- 出版者
- Japan Society for Fuzzy Theory and Intelligent Informatics
- 雑誌
- SCIS & ISIS
- 巻号頁・発行日
- pp.1983-1988, 2006 (Released:2008-09-12)
This paper investigates role of humming sound in the healing process by Bhramari Pranayama (BP) which has been recommended, in many literatures on yoga, for removing stress and healing many mental abnormalities and has also been claimed to be recuperative for the same by many practitioners. Pranayama is a Sanskrit word which literally means a yogic act performed for controlling flow of vital energy in the body and mind. One of the main acts during doing BP is that subject imitates humming sound of bumble bee while exhaling. The analysis of the humming sound produced during pranayama shows a little variation in pitch confined within lower frequencies with concentration of energy in the lower frequency bands. Nasal formants are also present. The humming sound has also vibrato. It is hypothesized that such sound produces not only bone conducted audition but also vibration in cranium and changes in the brainwave patterns leading to relaxation and healings.
2 0 0 0 ニワトリの味覚受容:うま味に対する行動応答とうま味受容体の発現
- 著者
- 吉田 悠太 川端 二功 西村 正太郎 田畑 正志
- 出版者
- 公益社団法人 日本畜産学会
- 雑誌
- 日本畜産学会報 (ISSN:1346907X)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, no.1, pp.17-23, 2021-02-25 (Released:2021-04-03)
- 参考文献数
- 54
味覚は,動物の摂食行動を制御する重要な化学感覚である.産業動物の味覚受容機構を明らかにすることで,産業動物の味覚嗜好性に基づいた飼料設計が可能になると考えられる.これまでに我々は,重要な産業動物であるニワトリの味覚受容機構に関する研究を実施してきた.本稿では,これまでのニワトリの味覚研究について概説した後,ニワトリのうま味受容に関する最近の知見をまとめた.一連の研究において,ニワトリがうま味成分に対して味覚感受性を有していること,ならびにニワトリの味蕾においてうま味受容体が発現していることが明らかとなってきている.これらの研究から,ニワトリ飼料の設計においてうま味が重要である可能性が味覚受容の観点から示されている.
2 0 0 0 OA 鍼灸院通院患者の鍼灸医療に対する満足度に関する横断研究
- 著者
- 高野 道代 福田 文彦 石崎 直人 矢野 忠
- 出版者
- 社団法人 全日本鍼灸学会
- 雑誌
- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.5, pp.562-574, 2002-11-01 (Released:2011-08-17)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 3 1
【はじめに】近年、良質な医療が求められ、その指標の1つとして、医療に対する患者の満足度が重視されている。勿論、鍼灸医療においても良質な医療を提供し、患者の満足度を重視していくことが大切である。しかしながら鍼灸医療に対する満足度について多面的な観点から調査された研究はない。そこで、我々は鍼灸院通院患者の鍼灸医療に対する満足度及び満足度に影響を与える要因について疫学的に検討したので報告する。【対象・方法】対象は、明治鍼灸大学同窓会会員の開業する鍼灸院からランダムに抽出した101軒の鍼灸院に通院した患者2,210名とした。調査期間は平成12年7月10日~同年7月23日の2週間であった。調査票は健康状態、鍼灸治療状況全般、鍼灸以外の医療機関の利用状況 (治療院、病院等) 、患者の基本情報等で構成し独自に作成したものを使用した。回答形式は、Visual Analogue Scale (VAS) 、選択式回答法、自由回答法を使用した。調査は、標本調査による配布郵送調査法にて実施した。統計解析は、t検定、信頼性分析、Pearsonの相関係数、重回帰分析 (変数増加法) を使用した。【結果】回収数は、1,319通 (59.7%) であった。満足度 (有効回答数 : 1268名) は、VASにおいて平均81.4±13.8であった。満足度と他の内容とで有意に相関を認めた内容は、治療効果、施術者の技術評価、施術者の信頼度、施術者の理解度、説明の分かりやすさ、施術者の説明度であった。さらに、重回帰分析では、治療効果、施術者の技術評価、施術者の信頼度、診療室の清潔さ、訴えの理解度、尋ねやすさが抽出された。【考察】鍼灸院通院患者の鍼灸医療に対する満足度は高値であった。それは治療効果、施術者の技術評価といった治療要因、施術者の信頼度、訴えの理解度、尋ねやすさといった施術者の人間的要因、診療室の清潔さといった環境要因の3つの要因で構成されていることが示された。
2 0 0 0 OA JR釧網本線の路線計画と形態
- 著者
- 横平 弘
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木史研究 (ISSN:09167293)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.339-346, 1994-06-09 (Released:2010-06-15)
- 参考文献数
- 24
JR釧網本線は当初の路線計画策定後の路線変更に伴って、施工された現有路線は全体的に迂回路線となった。迂回の著しい2区間について、施工の難易姓や路盤建設費から直結線と比較した結果、いずれも施工難工区を有し、迂回に伴って必要となった費用は全竣工額の18.7%にも達したことから、路線建設の妥当性は不十分とみられ、迂回のより著しい1区間については当初計画 (直結近似) 路線の方が有利である。
2 0 0 0 OA テクノスーパーライナー「飛翔」による実験航海(航海功績賞受賞業績紹介)
- 著者
- 広野 康平
- 出版者
- 公益社団法人 日本航海学会
- 雑誌
- 日本航海学会誌 NAVIGATION (ISSN:09199985)
- 巻号頁・発行日
- vol.129, pp.53-60, 1996-09-25 (Released:2017-06-30)