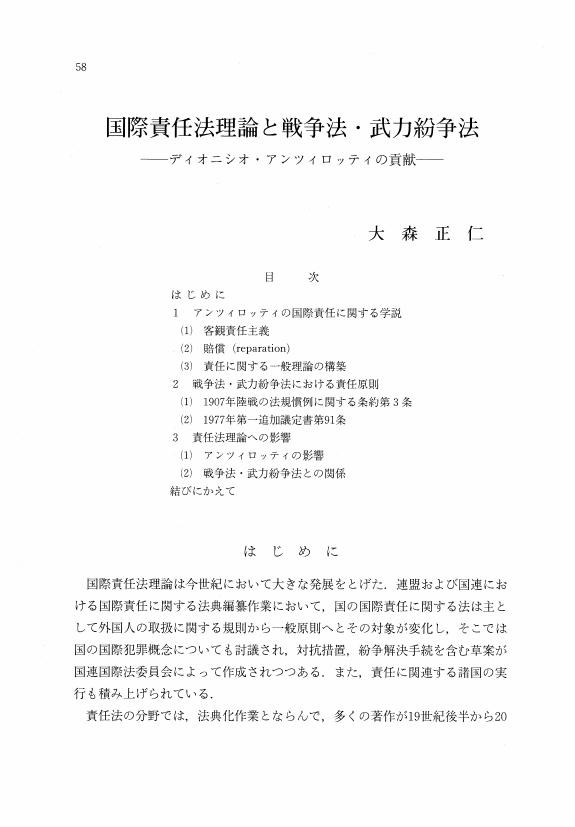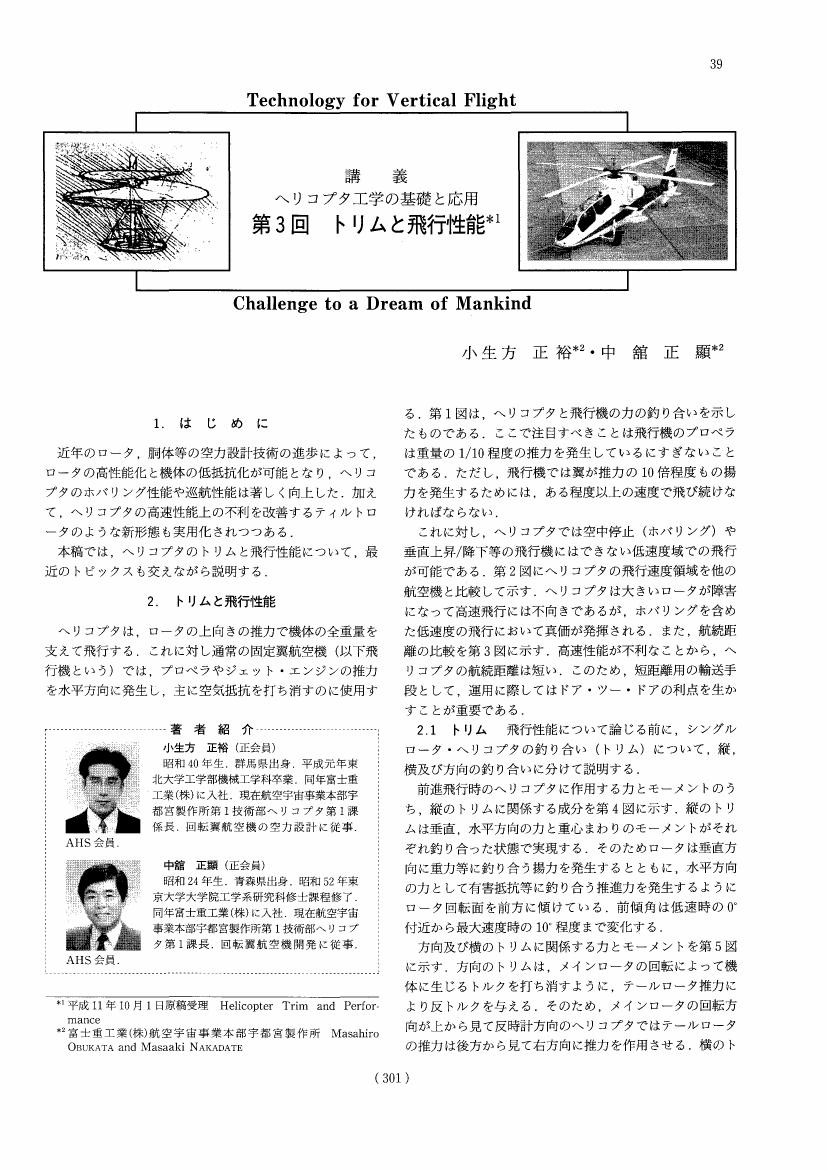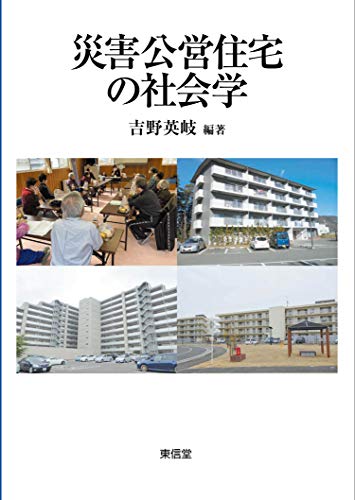4 0 0 0 OA 4.IL-1阻害薬
- 著者
- 山崎 聡士 川上 純
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.100, no.10, pp.2985-2990, 2011 (Released:2013-04-10)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1 1
インターロイキン-1(IL-1)は重要な炎症性サイトカインであり,その病態生理の解明に伴い,IL-1阻害薬のコンセプトが確立してきた.当初,関節リウマチでの応用が期待されたが,TNF阻害薬ほど劇的な効果は得られなかった.しかし,クリオピリン関連周期性発熱症候群をはじめとする他疾患におけるIL-1の重要性が次々に明らかとなり,IL-1阻害薬の可能性は新たな展開を見せている.
4 0 0 0 OA 中国古小説訳注 : 『續齊諧記』
- 著者
- 先坊,幸子
- 出版者
- 広島大学文学部中国中世文学研究会
- 雑誌
- 中国中世文学研究
- 巻号頁・発行日
- no.59, 2011-09-20
4 0 0 0 OA 国際責任法理論と戦争法・武力紛争法 ディオニシオ・アンツィロッティの貢献
- 著者
- 大森 正仁
- 出版者
- 世界法学会
- 雑誌
- 世界法年報 (ISSN:09170421)
- 巻号頁・発行日
- vol.2001, no.20, pp.58-76, 2001-01-30 (Released:2011-05-24)
- 参考文献数
- 42
4 0 0 0 OA 鋼材の火花試驗に關する研究1)(第1報)
- 著者
- 三島 徳七 三橋 鐵太郎
- 出版者
- The Iron and Steel Institute of Japan
- 雑誌
- 鐵と鋼 (ISSN:00211575)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.117-136, 1942-02-25 (Released:2009-07-09)
- 参考文献数
- 49
Die Schleiffunken der allen Stahlsorten haben kenzeichnende Merkmale. Die Funkenprobe bildet daher ein einfaches und weitverbreitetes Mittel zur Feststellung der Werkstoffzusammensetzung und zur Vermeidung von Werkstoffvermischung.Ein Teil dieser Arbeit, über den hier berichtet wurde, sollte Genauigkeit dieser Funkeprobe fur C-Stähle, auch die Zusammenhang zwischen die Funkenformen und die Menge der speziellen Elementen, wie Ni, Cr, Mn, Si, feststellen.In Fe-C-Mn Legierungen befindet sich ein schwerfunkbares Gebiet. Die Abhängigkeit von der Härte und dieser Schwerfunkbarkeit wurde nicht festgestellt.Karbide im Gusseisen ist immer schwerfunkbar, welches nach Graphitisation beim Ausglü hen wieder wesentlich funkbar wird. Das Gleiche wird auch im Cr-Gusseisen festgestellt, welches in Abhängigkeit von der steigernden Al Gehalten allmählich schwerfunkbar wird.Das Gefüge der amerikanischen handelsübrigen nichtfunkbaren Legierungen, die zu Ni-Cr-und Fe-W-Cr-VLegierungen (z.B. 18-4-1 Typus) gehören, besteht aus Austenit und Karbide.
4 0 0 0 OA トリムと飛行性能
- 著者
- 小生方 正裕 中舘 正顕
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.551, pp.301-308, 1999-12-05 (Released:2019-04-09)
- 参考文献数
- 9
4 0 0 0 IR 幕末明治期の漢字表記についての研究
4 0 0 0 OA ツマグロヒョウモンの北上に関する生気候学的研究
- 著者
- 望月 宏美 山口 隆子
- 出版者
- 日本生気象学会
- 雑誌
- 日本生気象学会雑誌 (ISSN:03891313)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.4, pp.135-141, 2021-03-31 (Released:2021-04-23)
- 参考文献数
- 15
ツマグロヒョウモンの著しい生息域の拡大は,地球温暖化の影響として広く一般に知られている.一方,近年,本種の食草であるスミレ類(パンジー等)の増加も一要因ではないかと言われているが,実際に双方の関係性に関する研究論文は少ない.本研究では,ツマグロヒョウモンの北上を,冬季の最低気温の上昇とパンジーの栽培地域の拡大という観点から複合的に考察した.その結果,1990年代初頭のガーデニングブームを契機に,パンジーの栽培地域は顕著に拡大した事が分かり,全国的な冬季の最低気温の上昇と共に,ツマグロヒョウモンの北上を助長した可能性が示唆された.
4 0 0 0 OA 「嬰児殺」をめぐる言説──「共同体の秩序維持」から「自己責任」へ──
- 著者
- 狩谷 あゆみ Ayumi KARIYA
- 出版者
- 広島修道大学ひろしま未来協創センター
- 雑誌
- 広島修大論集
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.89-102, 2018-02-28
4 0 0 0 OA 絶滅した日本のオオカミの遺伝的系統
- 著者
- 石黒 直隆
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医師会
- 雑誌
- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.225-231, 2012-03-20 (Released:2017-05-26)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 3 3
4 0 0 0 OA 宗教活動に基づく不法行為と宗教法人の責任
- 著者
- 櫻井 圀郎
- 出版者
- 日本私法学会
- 雑誌
- 私法 (ISSN:03873315)
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, no.75, pp.186-193, 2013-04-30 (Released:2017-04-03)
4 0 0 0 OA 空間と時間の社会的構成
- 著者
- ハーヴェイ・ D
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- Geographical review of Japan, Series B (ISSN:02896001)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.2, pp.126-135, 1994-12-31 (Released:2008-12-25)
- 被引用文献数
- 12 18
地理学者は,「空間」,「場所」,「環境」のどれか1つを取り出して学問を構築しようとしてきたが,本当は3つの概念を同時に相関的に扱わねばならない。ただ本日は,このうち「空間」を中心にし,空間と時間の社会的構成について話したい。 異なる社会は各々に個別性ある時空概念を構築する。社会的構成は物質世界の外にある純粋な主観でなく,物質世界の様相において時空を理解するやり方である。時空の尺度を選択するのは自然でなく社会である。この選択は社会の作用にとり基礎的・個人にとり客観的事実で,個人がなされた選択から逃れると罰をうける。決定された時空様式は生産・消費様式や権力と結びつき,時空様式を中立とみると社会変革の可能性の否定になる。 社会変容は構成された時空の変容と結びつく。支配的社会はそれ固有の時空概念を従属的社会におしつける。ここから,時空様式の変革から社会を変革しようとする思想と行動が生まれた。時空概念は社会諸部分の相異なる目的や関心により変容し,異なる時空性は互いに葛藤する。例えば,数十年の将来を利子率だけでみる新古典派経済学者と無限の将来にわたる持続性を説く環境論者とで時空性は異なる。男女の旧い分業に基づく時空性に基づき計画された都市と,そこに住み社会で働く女性がもつ時空性とは矛盾をきたす。 空間と時間について,ニュートンの「絶対」,アインシュタインの「相対」,ライプニッツやルフェーブルの「相関」の3概念がある。「絶対」では,時空がその中で作用する過程から独立な物質的枠組とみなされる。「相対」では,依然独立とされる時空の尺度がその物的性質に応じ変化するが,時空の多元性を許容しない。これまでの議論と整合的なのは,各過程が自らの時空を生産するという「相関」である。ライプニッツは,ニュートンの同僚クラークとの論争で案出した「可能な諸世界」の考えを説いた。マルクス主義唯物論者として私はこれを世俗化し,利害と過程の多元性が諸空間の不均質性を規定し,この諸空間のなかから支配的権力がもつ利害を反映した時空が選びだされる,としたい。 この考え方は,現実における時空の多元性を強調するホワイトヘッドと共通している。彼にあって空間と時間は,異なる諸過程が関連しあって生み出される「一体性」,ならびに共存せざるを得ない諸過程の相互依存から空間と時間の共存とその統一された編成が出てくる「共成性」生成の研究により定義される。コミュニケートしあう諸過程はある支配的な空間と時間の考えを規定するから,これはコミュニケーションと類義となる。 現代社会の空間と時間についてみると,『資本の限界』で論じたように,資本主義は19世紀以来永続して革命的で,回転期間と資本流通の高速化が技術革新により達成されてきた。また,空間がコミュニケーションにとってもつ障害は.一層減少し,時間・空間の圧縮が生じた。これにより同時に,旧い時空リズムは創造的に破壊され全く新しい時空性をもった生活様式が生まれる。だが,この支配的過程がもつ効果は,場所の発展や環境利用のパターンに影響する労働市場や資本主義の経済システム内部における位置や立地などの位置性によって断片化され,時間・空間の圧縮全体の効果が断片化される。内的に整合性あるたった1つの過程が,都市人口内部などに断片化された時空性をもたらすのである。 ラディカル運動の任務の1つは,現在を変革した先にある世界がもつ時空に直面する問題に取り組み,現実的な可能性として規定することである。移りゆく時空の諸関係にそれと違う方向付けを与える課題は,今日の地理学者に避けがたく緊要である。(水岡不二雄)
4 0 0 0 OA 説明可能AIにおける目的帰属型の説明についての検討
- 著者
- 葛谷 潤 荒井 ひろみ
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第36回 (2022) (ISSN:27587347)
- 巻号頁・発行日
- pp.4G3OS4b02, 2022 (Released:2022-07-11)
人工知能(AI)システムの解釈可能性が求められるようになったことを受け、自らの振る舞いを説明できる説明可能AIの研究が進められている。従来の研究が主に焦点を合わせていたのは、振る舞いのきっかけとなる原因やそれを支えるメカニズムについての説明である。しかし、説明可能なAIに期待される効用を踏まえると、別の種類の説明、すなわち目的帰属型の説明を考慮する必要があると思われる。本報告の主な目的は、生物学・心・人工物の哲学の知見に基づき、目的帰属型の説明とは何かを定式化した上で、AIシステムを含む人工物の社会的受容にとってそれがもつ重要性を指摘することである。本報告では、まず説明可能なAIに期待される効用と従来の研究を整理し、次に目的帰属型の説明の定式化と人工物の社会的受容に対するその重要性の指摘を行い、最後にAIシステムの振る舞いの目的ないし機能を同定するための方策を考察する。
- 著者
- 青木 栄一
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.4, pp.374-385, 2011-12-29 (Released:2018-12-26)
伝統的な教育行政学は領域学としての性質を強く持っていた。教育行政学は教育行政に関する記述情報を蓄積してきたが、記述的推論や因果的推論を蓄積することは乏しかった。なぜなら、教育行政学の先行研究には比較という方法論が欠如していたからである。本稿は、比較制度分析や制度の多様性に関する研究を参照し、教育行政学に方法としての比較を導入することを提案する。さらに比較が成り立つための要件についても言及する。
4 0 0 0 OA 組織の雇用行動を観察する: 不平等研究への意義,その方法
- 著者
- 吉田 航
- 出版者
- 数理社会学会
- 雑誌
- 理論と方法 (ISSN:09131442)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.2-13, 2023 (Released:2023-09-01)
4 0 0 0 災害公営住宅の社会学
4 0 0 0 OA レンズ付きフィルム「写ルンです」のリユース・リサイクルシステム開発
- 著者
- 鎌田 光郎
- 出版者
- マテリアルライフ学会
- 雑誌
- マテリアルライフ (ISSN:09153594)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.4, pp.165-169, 1999-10-30 (Released:2011-04-19)
4 0 0 0 OA 不貞行為に基づく慰謝料請求権
- 著者
- 岡林 伸幸
- 出版者
- 末川民事法研究会
- 雑誌
- 末川民事法研究 (ISSN:24328456)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.1-18, 2021-03
4 0 0 0 OA 中国における刑罰改革をめぐる最近の動向
- 著者
- 張 明楷 金 光旭
- 出版者
- 日本刑法学会
- 雑誌
- 刑法雑誌 (ISSN:00220191)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.253-275, 2015-02-28 (Released:2020-11-05)
4 0 0 0 OA トリチウムのトレーサ利用および同位体交換反応による化学反応性測定
- 著者
- 今泉 洋
- 出版者
- 公益社団法人 日本アイソトープ協会
- 雑誌
- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.12, pp.933-944, 1998-12-15 (Released:2010-07-21)
- 参考文献数
- 54
- 被引用文献数
- 2 1
4 0 0 0 OA 量子群の普遍 R 行列の積公式について
- 著者
- 寺崎 敏志
- 出版者
- Tohoku University
- 巻号頁・発行日
- 2015