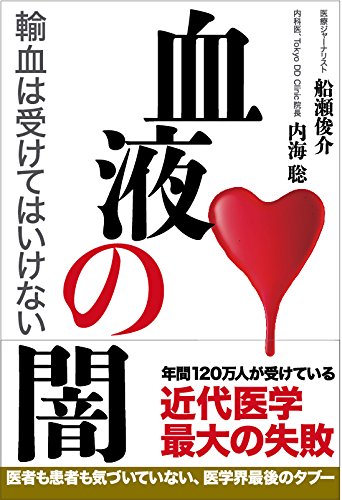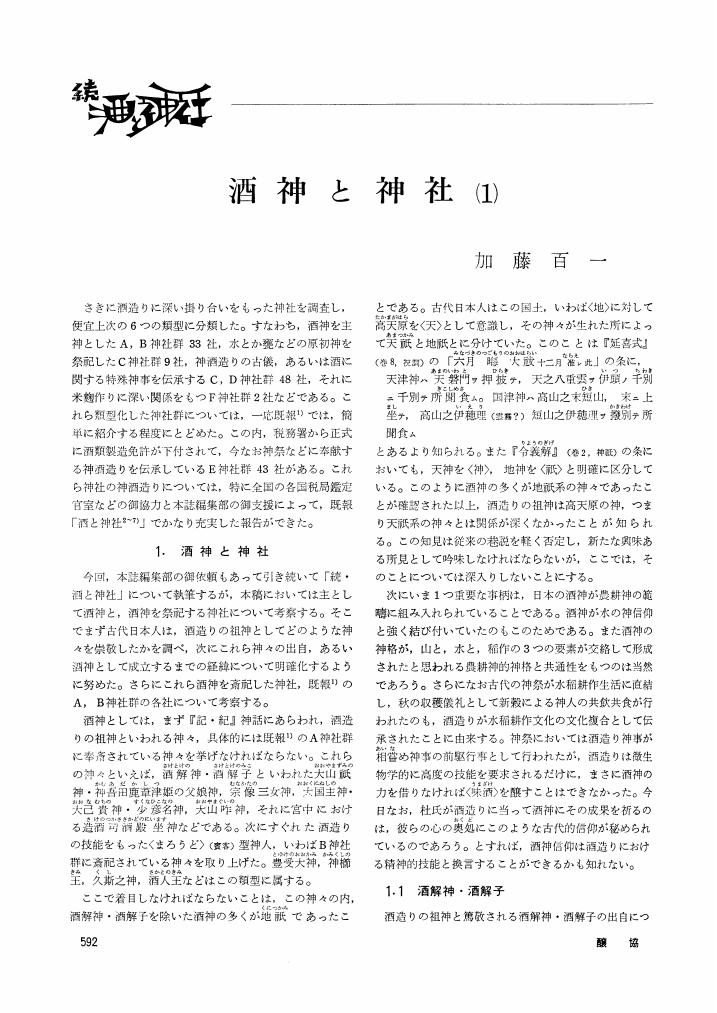4 0 0 0 血液の闇 : 輸血は受けてはいけない
4 0 0 0 OA 血清微量元素欠乏に伴う味覚障害の治療経験
- 著者
- 根来 篤 梅本 匡則 任 智美 阪上 雅史 藤井 恵美
- 出版者
- Japanese Society of Otorhinolaryngology-Head and neck surgery
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, no.3, pp.188-194, 2004-03-20 (Released:2008-12-15)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 4 2
(目的)味覚障害の原因として血清亜鉛欠乏に伴う味覚障害がよく知られているが,血清鉄欠乏に伴う味覚障害はあまり知られていない.兵庫医科大学味覚外来における血清鉄欠乏症例の味覚機能を検討し,鉄欠乏性味覚障害の臨床像について検討した.(対象と方法)1999年1月から2003年2月の間に当科味覚外来を受診し,血清鉄低下を認め,鉄内服療法を行った25例(男性3例,女性22例,平均56.1±16.5歳)を対象とした.味覚機能は電気味覚検査,濾紙ディスク法で評価した.鉄剤はクエン酸第一鉄ナトリウム(フェロミアR)を使用,血清亜鉛低下症例には亜鉛製剤内服療法を併用した.(結果)男女比は約1:7,年齢分布は40歳と70歳の2峰性のピークを認めた.初診時電気味覚検査では約70%に閾値上昇が認められ,濾紙ディスク法における4基本味別認知閾値の平均値では,酸味の閾値がやや上昇していた.鉄•亜鉛内服療法群の味覚改善率は鉄製剤内服群より,自覚症状,電気味覚検査,濾紙ディスク法で上回った.鉄剤内服療法開始までの罹病期間別の治療成績では,各期間に改善度の差は認められなかった.(考察)血清鉄欠乏に伴う味覚障害を認めた時,鉄剤内服療法もしくは鉄•亜鉛内服療法を積極的に行う必要があると思われた.
- 著者
- Kaito Sato Kenji Sawada
- 出版者
- Fuji Technology Press Ltd.
- 雑誌
- Journal of Robotics and Mechatronics (ISSN:09153942)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.298-307, 2023-04-20 (Released:2023-04-20)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1
In vehicle control, state estimation is essential even as the sensor accuracy improves with technological development. One of the vehicle estimation methods is receding-horizon estimation (RHE), which uses a past series of the measured state and input of the plant, and determines the estimated states based on linear or quadratic programming. It is known that RHE can estimate the vehicular state to which the extended Kalman filter cannot be applied owing to modeling errors. This study proposes a new computational form of the RHE based on primal-dual dynamics. The proposed form is expressed by a dynamic system; therefore, we can consider the computational stability based on the dynamic system theory. In this study, we propose a continuous-time representation of the RHE algorithm and redundant filters to improve the convergence performance of the estimation and demonstrate its effectiveness through a vehicle path-following control problem.
4 0 0 0 OA パーシステンス図の逆問題
- 著者
- 大林 一平
- 出版者
- 一般社団法人 日本応用数理学会
- 雑誌
- 応用数理 (ISSN:24321982)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.4, pp.7-14, 2017 (Released:2017-03-25)
- 参考文献数
- 11
Persistence homology is an important tool for topological data analysis(TDA), and a persistence diagram is a visualization tool of persistent homology. We can compute the geometric features of the data quantitatively using persistence diagrams. When using persistence diagrams, we often want to know which part of the input data is related to the geometric features shown in the persistence diagram. In this paper, we show some approaches to the problem.
4 0 0 0 OA 北澤毅教授退職記念特集
- 雑誌
- 立教大学教育学科研究年報
- 巻号頁・発行日
- vol.62, pp.5-34, 2019-02
4 0 0 0 OA 精神分裂病者の宗教を主題とした妄想について
- 著者
- 新井 治美 川原 延夫 上島 国利 福田 和夫
- 出版者
- 杏林医学会
- 雑誌
- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.23-29, 1981-03-30 (Released:2017-02-13)
最近5年間に杏林大学および三恵病院に入院し, 宗教を主題とした妄想が認められた20名の精神分裂病者について, 現代日本の社会宗教的状況を考慮に入れつつ検討を加えた。20名を信者グループと非信者グループに分けると前者では急性に発症し, 妄想も一過性であるのに対し, 後者では慢性の経過をたどり, 妄想も持続する傾向が認められた。そこで前者のようなタイプを急性型, 後者を慢性型とし, 後者についてはさらに宗教的妄想以外の妄想の有無に従い単一型と併存型に分けた。急性型の多くは憑依状態を呈し, 憑いたとされる対象は多岐にわたっていた。神という言葉でいろいろな宗教的対象が表現されていて, それを教派別にみると新宗教がもっとも多く, キリスト教がついで多かった。慢性型においては宗教は患者にとってそれほど重要な意味は持たないが, 急性型においては宗教に対する患者のかかわり方は全人格的であるという傾向が認められた。
4 0 0 0 低エネルギー放射線を用いたDNA主鎖切断誘発機構の研究
あらゆる放射線生物作用の初期過程は、低エネルギー電子線の作用に還元できる。しかし、低エネルギー電子線(10eVから数100eV)の照射実験は技術的に極度に困難であり、DNA分子に照射できる施設は、現在、英国グレイ研究所にしかない。一方、励起・電離等のエネルギー吸収モードを制御できる低エネルギー単色真空紫外線源として、我々が多くの業績をあげた東大学物性研軌道放射物性研究施設が閉鎖された現時点では、KEK・PFのBL-20Aが残されている。低エネルギーの電子線と単色光子は、放射線生物効果誘発機構を解明するためには相補的な役割を持つ。本研究は、日本と英国の専門家が協力して、おのおののグループが得意とする放射線源を用いて、DNA主鎖切断誘発機構を総合的に解明しようという国際協力研究である。得られた結果をまとめると、(1)15eV電子線によって1本鎖および2本鎖切断が、総量に対してほぼ直線的に誘発された。このことは1本鎖および2本鎖切断誘発の閾値が15eV以下であることを示す。特に2本鎖切断誘発の閾値が15eV以下であることが実験的に示された成果は大きい。(2)低エネルギー電子線は2本鎖切断を1本鎖切断の数十分の1の比率で誘発し、この比がγ線による比と極端に違わないことが示された。(3)低エネルギー単色光子によるDNA主鎖切断は、効率は極端に低いが4.3eVでも誘発された。この意味では主鎖切断誘発の閾値エネルギーは存在しないが、通常の定義に従えば10eV程度の閾値エネルギーが得られることが実証的に示すことができた。(4)単色真空紫外線をプラスミド水溶液に照射するための照射方法を開発し、水溶液中DNAの2本鎖切断が7eV程度でも誘発されることを明らかにすることができた。本研究によって、シュミレーション計算で用いるDNA主鎖切断誘発の閾値を決める際に参考にすべき重要な情報を得ることができた。
- 著者
- Ya-Nan Ma Xuemei Jiang Wei Tang Peipei Song
- 出版者
- International Research and Cooperation Association for Bio & Socio-Sciences Advancement
- 雑誌
- BioScience Trends (ISSN:18817815)
- 巻号頁・発行日
- pp.2023.01207, (Released:2023-09-01)
- 参考文献数
- 165
- 被引用文献数
- 3
Studies have found that intermittent fasting (IF) can prevent diabetes, cancer, heart disease, and neuropathy, while in humans it has helped to alleviate metabolic syndrome, asthma, rheumatoid arthritis, Alzheimer's disease, and many other disorders. IF involves a series of coordinated metabolic and hormonal changes to maintain the organism's metabolic balance and cellular homeostasis. More importantly, IF can activate hepatic autophagy, which is important for maintaining cellular homeostasis and energy balance, quality control, cell and tissue remodeling, and defense against extracellular damage and pathogens. IF affects hepatic autophagy through multiple interacting pathways and molecular mechanisms, including adenosine monophosphate (AMP)-activated protein kinase (AMPK), mammalian target of rapamycin (mTOR), silent mating-type information regulatory 2 homolog-1 (SIRT1), peroxisomal proliferator-activated receptor alpha (PPARα) and farnesoid X receptor (FXR), as well as signaling pathways and molecular mechanisms such as glucagon and fibroblast growth factor 21 (FGF21). These pathways can stimulate the pro-inflammatory cytokines interleukin 6 (IL-6) and tumor necrosis factor α (TNF-α), play a cytoprotective role, downregulate the expression of aging-related molecules, and prevent the development of steatosis-associated liver tumors. By influencing the metabolism of energy and oxygen radicals as well as cellular stress response systems, IF protects hepatocytes from genetic and environmental factors. By activating hepatic autophagy, IF has a potential role in treating a variety of liver diseases, including non-alcoholic fatty liver disease, drug-induced liver injury, viral hepatitis, hepatic fibrosis, and hepatocellular carcinoma. A better understanding of the effects of IF on liver autophagy may lead to new approaches for the prevention and treatment of liver disease.
4 0 0 0 OA 異なる提示音の間で出現するピッチ知覚の相違に関する実験的研究
- 著者
- 新山王 政和
- 出版者
- 日本音楽教育学会
- 雑誌
- 音楽教育学 (ISSN:02896907)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.1-9, 2008 (Released:2017-08-08)
- 参考文献数
- 14
これまで音高に問題のある歌唱を扱った研究では, 100セント以上ピッチが外れた事例を取り上げる場合が多かった。これとは異なり筆者の一連の研究では50セント程度以内の微小なピッチ差で低く歌い続けてしまう現象 (以下, フラットシンギングと記述) に着目し, 他の先行研究でも報告されている「提示に用いる音 (以下, 提示音と記述) の種類によって声の再生ピッチが異なる現象」に関して, ピッチ知覚の面から洗い直すことを試みた。その結果, 声による提示とピアノによる提示では, 指導現場における現実的対応にも直結する次の4つの傾向が潜んでいる可能性を確認した。1. ピッチを知覚する段階 (ピッチ知覚レベル) と発声で再現する段階 (ピッチ再生レベル) では, 提示音に対して異なる反応が顕れる。2. ピッチを知覚する段階では, 提示音に対する慣れや聴き取り方の習熟度が影響する。3. ピッチを知覚する段階では, ボーカル音よりもピアノ音の方がピッチを判別し易い傾向がある。4. ピッチを知覚する段階では, 高い方向へのピッチ差は判別し易く, 低い方向へのピッチ差は判別しにくい傾向がある。これがフラットシンギングの発生する一因である可能性も考えられる。
4 0 0 0 OA トリチウムの環境動態
- 著者
- 阪上 正信
- 出版者
- 社団法人 プラズマ・核融合学会
- 雑誌
- 核融合研究 (ISSN:04512375)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.5, pp.498-511, 1985-11-20 (Released:2011-03-04)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1 1
Various studies about the behavior of tritium in the environment are reviewed with comments on several origins of their occurances. For atmospheric tritium, different chemical species and their seasonal variation have been studied. The average tritium concentration in river waters was found to be 1.5-2 times higher than that of precipitations at various sites of Japan.The vertical distribution of tritium in ground water has raised an interest for the samples collected from different wells in depth. The effect of the accidental release of tritium and the tritium level around nuclear facilities are also mentioned.
4 0 0 0 OA クーポンマーケティングにおけるUplift Modeling適用の問題点と新しい評価指標
- 著者
- 清水 亮洋 富樫 陸
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第34回 (2020)
- 巻号頁・発行日
- pp.1H4OS12b02, 2020 (Released:2020-06-19)
クーポンマーケティングにおけるUplift Modelingの正しい評価とは何でしょうか?昨今、クーポンマーケティングの費用対効果を向上させるために、Uplift Modelingの適用例が増えてきています。多くは、Uplift Modelingを用いることで、本当にクーポンが必要な人だけにクーポンを配り、費用対効果を向上することを目的としています。しかし、実際にはUplift Modelingにおける評価指標とクーポンマーケティングにおける費用対効果の構造を正しく把握しなければ、きちんと費用対効果を向上することができない可能性があります。私たちは、従来のUplift Modelingの評価指標が正しく費用対効果に結びつかない例を提示し、これを解決することのできる新しい評価指標を提示します。
4 0 0 0 OA 免疫チェックポイント阻害薬投与に起因する肝障害の臨床的特徴と難治例への対策
- 著者
- 田所 智子 谷 丈二 琢磨 慧 中原 麻衣 大浦 杏子 藤田 浩二 三村 志麻 小野 正文 森下 朝洋 正木 勉
- 出版者
- 一般社団法人 日本肝臓学会
- 雑誌
- 肝臓 (ISSN:04514203)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.3, pp.107-119, 2022-03-01 (Released:2022-03-08)
- 参考文献数
- 27
免疫チェックポイント阻害薬(Immune Checkpoint Inhibitors;ICI)による免疫関連有害事象(immune-related Adverse Events;irAE)では従来の化学療法と異なるマネジメントが要求され,特に肝障害においてはステロイドや免疫抑制剤の開始時期や難治例への対応など様々な問題がある.当院においてICIを投与された370症例を対象としirAE特にirAE関連肝障害の臨床的特徴について検討した.全irAEの頻度は41.1%,Grade2以上のirAE関連肝障害の頻度は5.1%で,良好な腫瘍縮小効果を認め,他のirAEを合併した症例が多かった.ガイドラインに準拠した治療にて多くの症例が軽快したが,死亡例および難治例もあり,これらの治療過程ではサイトメガロウイルス感染症が問題となっていた.難治例について症例提示し,当院での治療方針について報告する.
4 0 0 0 OA 幻の都市計画:ヴォーティシズムに見るデザインのイデオロギーの展開
- 著者
- 要 真理子
- 出版者
- 跡見学園女子大学
- 雑誌
- 跡見学園女子大学文学部紀要 = JOURNAL OF ATOMI UNIVERSITY FACULTY OF LITERATURE (ISSN:13481444)
- 巻号頁・発行日
- no.58, pp.A139-A152, 2023-03
This article focuses on Vorticism --the only avant-garde art movement in Britain in the first half of the twentieth century-- and, more specifically on its central figure, Wyndham Lewis, dealing with the ideology found in texts and activities of Vorticists. The fact that the latter-mentioned group, which started in 1914 and ended the following year, envisaged an ideal urban plan based on a philosophy of vortex (the origin of this group’s name) is made clear in the avant-garde magazine Blast (1914, 1915), as well as and in the book the Caliph’s Design(1919), written by Lewis after the demise of the group’s activities. Unlike the avant-garde art movements of the 1920s in other Western European countries, there was no expansion from contemporary art to extensive urban planning in Britain. It is therefore worth noting the ambitious, if abortive, attempts at urban renewal that Vorticism left behind in its writings. In those writings, we can see that, for Vorticists, the city is always shaped by some force indicated by “vortex”. This vortical force is typically found in the designs in drawings and magazines created by the hands of Vorticists, but it was also a model for this urban restructuring. In the current article, we do not read these designs visually, but reconsider their design ideology - -which is common across genres such as painting, literature and architecture-- from the perspective of urban planning, specifically from Lewis’s texts.
4 0 0 0 OA 【書評】川上郁雄・三宅和子・岩﨑典子編 移動とことば
- 著者
- 牲川 波都季
- 出版者
- 早稲田大学大学院日本語教育研究科
- 雑誌
- 早稲田日本語教育学 (ISSN:18823394)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.211-215, 2019-06-14
- 著者
- 古田 弥生 木下 奈穂 杉本 博是 荒木 浩
- 出版者
- 日本緩和医療学会
- 雑誌
- Palliative Care Research (ISSN:18805302)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.4, pp.367-371, 2018 (Released:2018-12-28)
- 参考文献数
- 19
乳がんの皮膚浸潤は出血や臭気を伴う滲出液のため,患者のQuality of Lifeを低下させる.局所処置療法としてMohsペーストや亜鉛華デンプン外用療法がある.Mohsペーストは正常組織の変性壊死による疼痛の有害作用があること,亜鉛華デンプン外用療法は止血・止臭効果が不十分という問題点がある.その問題点を改善した,紫雲膏・亜鉛華デンプン・メトロニダゾール(MNZ)療法の皮膚浸潤を伴う乳がん患者に対する,出血,臭気の緩和効果について報告する.症例は86歳女性.乳がんの皮膚浸潤に対して紫雲膏・亜鉛華デンプン・MNZ療法を行い,出血,感染兆候,臭気,滲出液,壊死組織が処置により客観的に改善し,ガーゼ交換の頻度は日に1回,処置は簡便であることが確認できた.紫雲膏・亜鉛華デンプン・MNZ療法は皮膚浸潤を伴う乳がん患者に対する,出血,臭気の緩和効果に有用で,従来の方法に加えて局所処置療法の一つになりうる可能性がある.
4 0 0 0 OA 超伝導理論の発展(<特集>超伝導発見から100年を迎えて)
- 著者
- 斯波 弘行
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.10, pp.735-743, 2011-10-05 (Released:2019-06-14)
- 参考文献数
- 48
超伝導の理論はカマリング・オネスによる発見から40数年間の実験研究の上に提出されたギンツブルクとランダウの超伝導の現象論(GL理論,1950年)とバーディーン,クーパー,シュリーファーの超伝導のミクロな理論(BCS理論,1957年)の2つの画期的な仕事によって基礎が築かれた.その後の半世紀にこれらの理論の深化,拡大が進み,超伝導のメカニズムについての現在の理解はBCS理論直後とはずいぶん違っている.また,物性科学の他の問題との接点へ研究者の目が向きつつある.この小論では超伝導現象の理解に向けた現在までの理論研究を(1)超伝導はなぜ多くの物質で普遍的に起こるのか,(2)超伝導にはどれほどの多様性があるのか,それは物性物理の他の分野の発展とどのように関係しているか,の2つの観点から整理したい.
4 0 0 0 OA 運動学習はここまでわかった
- 著者
- 嘉戸 直樹 伊藤 正憲
- 出版者
- 関西理学療法学会
- 雑誌
- 関西理学療法 (ISSN:13469606)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.49-52, 2008 (Released:2009-01-15)
- 参考文献数
- 10
It is important to understand about the mechanism of motor learning. Moreover, it is necessary to guide automated behavior by intervening according to each stage of motor learning. In this paper, we summarize the neural mechanism and strategy of motor learning.
4 0 0 0 OA 酒神と神社 (1)
- 著者
- 加藤 百一
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.9, pp.592-596, 1981-09-15 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 10
4 0 0 0 OA 周産期心筋症と周産期の心不全管理
- 著者
- 神谷 千津子
- 出版者
- 日本循環制御医学会
- 雑誌
- 循環制御 (ISSN:03891844)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.23-27, 2020 (Released:2020-05-22)
- 参考文献数
- 19
周産期心筋症は、心筋疾患既往のない女性が、妊娠から産後に重度の心機能低下に伴い心不全を発症する、未だ原因不明の心筋症である。高齢、妊娠高血圧症候群や多胎妊娠などが危険因子として知られている。息切れや浮腫などの心不全症状は、健常妊産婦も訴える症状と似ているため、診断遅延や重症化の要因となり、主な母体死亡原因疾患のひとつに挙げられる。近年、モデル動物による基礎実験を基に、病因に関する新たな知見が報告され、遺伝子解析研究により、他の心筋症との関係も明らかになってきた。心不全治療においては、周産期特有の病態を踏まえる必要がある。一方で新たな疾患特異的治療として、抗プロラクチン療法の試みが始まっている。