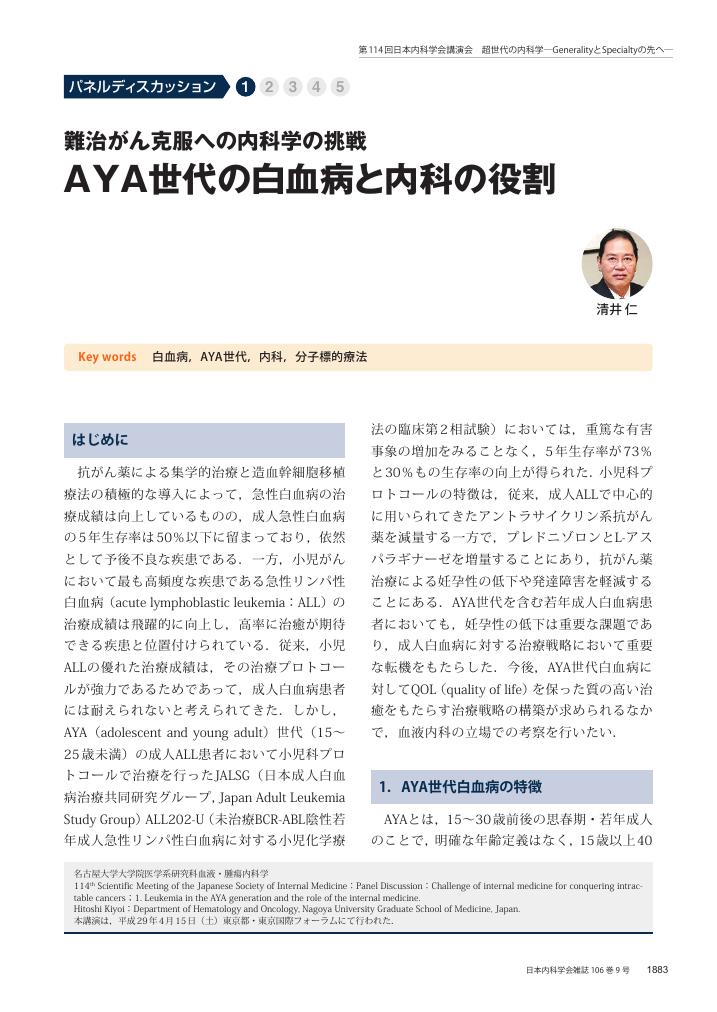4 0 0 0 OA 英米でのビデオゲーム制作の現状
- 著者
- Wade Alex 小山 友介
- 出版者
- 日本デジタルゲーム学会
- 雑誌
- デジタルゲーム学研究 (ISSN:18820913)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.102-114, 2008 (Released:2021-07-01)
本論文の目的は、 ビデオゲーム制作に関する具体的議論の前段階となる省察を示すことにある。 ビデオゲーム産業がメジャーな娯楽メディアとして始まる段階からの歴史的概括を行い、当時から現在まで存続しているビデオゲーム開発手法が後に引き起こした成功と失敗を検証する。そこから得られた知見を、文化的に関連の深い理論モデルと関連づける。欧米の開発者、プログラマー、アーティスト、プロデューサーヘのインタビュー結果から、ビデオゲーム産業の現状を評価するとともに、現在のビデ オゲーム制作が持つ過去との関連性、問題点、類似性について分析する。最後に、将来のビデオゲーム制作についての私見を述べる。
- 著者
- 那須 高志 小林 渓紳 大堀 正明
- 出版者
- Saitama Physical Therapy Association
- 雑誌
- 理学療法 - 臨床・研究・教育 (ISSN:1880893X)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.40-44, 2023 (Released:2023-09-01)
- 参考文献数
- 18
【はじめに】大腿骨近位部骨折の術後患者における歩行自立度を予測する因子と,そのカットオフ値を調査することとした。【対象および方法】大腿骨近位部骨折を受傷し,手術を施行された40名において術後14日目の歩行が自立した群としなかった群で比較した。また歩行自立度を目的変数とし,年齢と荷重率と荷重時痛を説明変数とし,ロジスティック回帰分析を実施した。さらに影響を与えている説明変数に関してはROC曲線からカットオフ値を算出した。【結果】非自立群は自立群に比し荷重率が低く,荷重時痛が高かった。また術後14日の歩行自立度に影響を与えているものは荷重率で,そのカットオフ値は72.3%であった。AUCは0.86であった。【考察】荷重率は歩行自立度に影響を与えており,その予測能は高かった。以上のことから,術後7日目の荷重率を測定することで,術後14日目の歩行自立度を予測できる可能性が考えられた。
4 0 0 0 OA 小学校英語教育の効果に関する研究 ―先行研究の問題点と実証分析の可能性―
- 著者
- 豊永 耕平 須藤 康介
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.2, pp.215-227, 2017-06-30 (Released:2018-04-27)
- 参考文献数
- 28
小学校英語教育の効果に関する先行研究では、交絡要因を統制して代表性のあるサンプルを分析するという統計的因果推論の過程が軽視されてきた問題点があり、異文化理解などの情意面への効果や、開始学年による違いも十分に検討されてこなかった。大規模調査データの二次分析の結果、小学校英語教育は1・2年生から始めた場合のみ、中学生の英語学力に正の効果をもたらす可能性があるが、外国への親しみやグローバル人材意識などには統計的に有意な効果をもたらさないことが示された。
4 0 0 0 OA 皮膚濡れ感覚の支配要因
- 著者
- 小柴 朋子 田村 照子
- 出版者
- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会
- 雑誌
- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.119-124, 1995-01-25 (Released:2010-09-30)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 3
人体皮膚の濡れ感覚感受性の支配要因を明らかにするため, 2種の方法で身体各部に濡れ刺激を負荷し, 濡れ感受性を調査した.I.面積の異なるろ紙 (12.52cm, 7.52cm, 52cm, 2.52cm) を温水で濡らして身体26部位の皮膚に貼付したときの濡れ感を測定した.被験者は成人女子5名.II.環境温25・34℃において身体6部位に対し水温・水量・荷重の異なる濡れた綿メリヤス布を接触子として静止・滑動させたときの濡れ感を測定.被験者は成人女子10名.その結果, 温度・熱流量変化が皮膚濡れ感の主たる要因であり, 荷重・水量等は温熱的要因ほどには皮膚濡れ感覚に影響しなかった.濡れ感受性には部位差が見られ, 皮膚濡れ感受性の内的支配要因として温・冷点や触点の知覚神経の分布密度が重要であることが示唆された.
4 0 0 0 OA 駅売弁当の変遷 (2)
- 著者
- 小田 きく子
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.3, pp.204-208, 1980-03-15 (Released:2011-11-04)
- 被引用文献数
- 1
前回に引続き昭和時代に入ってからの駅売弁当の変遷について述べていただいた。
4 0 0 0 OA ヨウ素129の分析を通じた福島原発事故起源のヨウ素131の広がりと沈着量の再構築
- 著者
- 村松 康行 松崎 浩之 大野 剛 遠山 知亜紀
- 出版者
- 一般社団法人日本地球化学会
- 雑誌
- 日本地球化学会年会要旨集 2013年度日本地球化学会第60回年会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- pp.189, 2013 (Released:2013-08-31)
福島原発事故においても大量のI-131が放出されたが、もしも、初期被ばくが大きい場合は後になって甲状腺への影響が出る可能性がある。しかし、半減期が8日と短いため、事故当初の放射性ヨウ素の広がりや住民が受けた被ばく線量に関するデータは十分でない。そこで、I-131と同時に放出されたと考えられる長半減期の同位体であるI-129(半減期1,570万年)が指標になる。文科省が集めた土壌試料や我々が独自に集めた試料を用い、I-129の分析を試みた。AMSを用いたI-129の分析結果から約400箇所のI-131沈着量を推定した。今まで殆どデータがなかった福島原発から20 km圏内や南西側の地域を中心に、I-131の沈着量のマップを作成した。今回、値が加わったことで、I-131の沈着量の地域分布の特徴がより鮮明になってきた。
4 0 0 0 OA 1)AYA世代の白血病と内科の役割
- 著者
- 清井 仁
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, no.9, pp.1883-1887, 2017-09-10 (Released:2018-09-10)
- 参考文献数
- 8
4 0 0 0 OA 語りの中の国境の変更 ―群馬県多野郡神流町生利地区戸野コーチを事例に―
- 著者
- 間所 瑛史
- 出版者
- 一般社団法人 日本民俗学会
- 雑誌
- 日本民俗学 (ISSN:04288653)
- 巻号頁・発行日
- vol.311, pp.35-53, 2022-08-31 (Released:2023-08-31)
- 参考文献数
- 22
This article offers observations on the oral history of Tono-kochi in the Shori District of Kannamachi in Tano-gun, Gunma Prefecture, which is located near the boundary with Saitama Prefecture. It explains the historical background as seen from the local peopleʼs narrative and how this is understood at present. Kannamachi was part of an area called sanchuryo, or a domain under the direct jurisdiction of the Edo Shogunate, during the early modern period. In the Genroku Era (1688-1704), a dispute over the fief boundary arose between the sanchuryo and Bushu. A court verdict determined that the line along the mountain ridge was the boundary. On the other hand, research has shown that the Kannagawa River running in the center of the sanchuryo used to be the fief boundary. It has been noted that perception of the boundary has been ambiguous. In Tono-kochi on the right bank of the present Kannagawa, oral history has it that coal was buried in the mountain during the Meiji Period as evidence that a court decision changed the fief boundary. The former Shinto priest family of the Tono Shrine relayed the detailed history of the beginning of Tono-kochi and the change of fief boundary. However, the Tono Shrine was a shrine that had had connections with Chichibu since the Genroku Era. Moreover, the history of its affiliation with Bushu was known even outside Chichibu, and this history has gradually been understood through the ancestorsʼ experience and the excellent Shinto funeral tradition in the area on the right bank of Kannagawa. Furthermore, the period when the change of boundary allegedly took place was a time when the boundaries with Joshu, Iwahana Prefecture, and Gunma Prefecture were in flux. This was behind the history of fief boundary shift. The history of boundary change in Tono-kochi has been passed on in oral history not only by way of the experience of people in the past, but also through present day geographical and cultural disparities.
- 著者
- Wataru Hashimoto Takahiro Shinagawa
- 雑誌
- 研究報告システムソフトウェアとオペレーティング・システム(OS) (ISSN:21888795)
- 巻号頁・発行日
- vol.2023-OS-160, no.9, pp.1-9, 2023-07-27
Low-level languages including C/C++ require manual heap management, which often leads to memory-related bugs. The key challenge of UAF prevention is to ensure that freed heap objects are not accessed through dangling pointers, while not introducing significant performance overhead, and preserving the source code compatibility. We present LeaseMalloc, a system that combines a source code transformation and a runtime library to detect UAF. It ”leases” heap objects to users, then ensures that memory is not accessed through dangling pointers by supervising the lease status of heap objects. Lease information is updated dynamically at runtime, which allows LeaseMalloc to skip the lease check to reduce the performance overhead. We implement LeaseMalloc as an LLVM Pass Plugin to instrument target application and confirmed that it can detect temporal memory errors without modifying application source code.
4 0 0 0 OA 関東大震災下における朝鮮人の帰還
- 著者
- 西村 直登 Naoto Nishimura
- 出版者
- 同志社大学人文科学研究所
- 雑誌
- 社会科学 = The Social Science(The Social Sciences) (ISSN:04196759)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.33-61, 2017-05-31
本稿は、1923年9月1日に発生した関東大震災を経験した朝鮮人にとって、朝鮮への帰還がどのような意味を持ったのかについて検討したものである。震災下における朝鮮人の帰還は、震災発生直後から「排外心のるつぼ」と化した日本から逃れるための、いわば「避難」としての帰還にとどまらなかった。「避難」は文字通りの「災難を避けて、安全な場所へ立ち退くこと」だけでなく、生き延びようとする、そして真相を明らかにするための「抵抗」の表れであった。
4 0 0 0 OA 「風評被害」という言葉の罪と罰―「トリチウム水」強制放出をどう考える?―
- 著者
- 関澤 純
- 出版者
- 一般社団法人 日本リスク学会
- 雑誌
- リスク学研究 (ISSN:24358428)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.31-42, 2022-09-15 (Released:2022-09-23)
- 参考文献数
- 73
Recently attention is focused on the disposal of treated radioactively polluted water to the ocean from collapsed Fukushima nuclear power plant. Japanese government claiming safety of the treated water, is trying to mitigate “reputational damages” of Fukushima fishery people. However, there are real risks with the damaged plant, such as lowering of water level in the reactor vessel by a big earthquake early 2021. After the plant accident, Japanese government forced the Fukushima residents to leave their home towns by setting difficult-to-return zones, etc. Besides, Japanese government set new strict rules on radioactive pollution of foods. These regulations have caused difficult situations in living conditions of Fukushima people through long time evacuation and superfluous testing of many foods etc. Consequently, based on these critical governmental regulations, not only “reputational damages”, but real serious damages, are brought about to many people. Rules must be based on basic safe sciences and be reasonable in minimizing possible risks to people and the society. This paper is dedicated to the Ukrainian who suffer from unjustifiable war crime.
4 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1935年09月03日, 1935-09-03
4 0 0 0 OA てんかん患者における睡眠障害
- 著者
- 吉澤 門土 千葉 茂
- 出版者
- 一般社団法人 日本総合病院精神医学会
- 雑誌
- 総合病院精神医学 (ISSN:09155872)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.48-57, 2014-01-15 (Released:2017-05-03)
- 参考文献数
- 36
成人における睡眠障害は4〜5人に1人の頻度でみられる。てんかんでは,この約2〜3倍高い頻度で睡眠障害がみられると報告されている。本稿では,睡眠障害の国際分類・診断,てんかん患者にみられる睡眠障害,および,てんかん発作と睡眠障害の鑑別について概説する。てんかん患者では,不眠症や,過剰な日中の眠気,閉塞性睡眠時無呼吸症候群,睡眠時随伴症,睡眠関連運動障害などが合併しやすい。睡眠障害を合併したてんかん患者では,てんかんは睡眠障害をもたらし,睡眠障害はてんかんを悪化させるという相互促進的な関連性が存在すると考えられる。したがって,てんかんにおける睡眠障害を発見・治療することはてんかんの治療としても重要である。てんかんと睡眠障害の鑑別診断に際しては,背景にある病態生理を明らかにするために,ビデオ・睡眠ポリグラフィ(video-polysomnography;V-PSG)を施行できる医療機関との診療連携がきわめて重要である。
4 0 0 0 OA ウェアラブルなCDアルバムによるユーザの動きに連動したインタラクティブな音楽体験
- 著者
- 林田 明香里 加藤 邦拓 太田 高志
- 雑誌
- エンタテインメントコンピューティングシンポジウム2023論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2023, pp.313-315, 2023-08-23
本研究ではスピーカを取り付けた洋服を実装し,ユーザの動きによるインタラクティブな音楽体験を設計する.具体的には,CD アルバムのジャケット画像が印刷された洋服をユーザが着用すると,洋服上のスピーカからアルバム内の楽曲が再生される.またユーザ同士が肩を組む,あるいはハグといったスキンシップをすることで,お互いの洋服から同じ楽曲が再生されて,音楽を共有できるインタラクションを設計する.提案手法により,ユーザは音楽配信サービス上でダウンロードした音源を物理的に所有できるようになり,洋服を着用することによる視覚的かつ聴覚的な自己表現が可能になる.また,ユーザ同士の自然なコミュニケーションによる楽曲共有を可能にすることが目的である.
4 0 0 0 OA 秋田県八郎湖流域における浸透移行性殺虫剤と代謝物の濃度レベルと水平分布
- 著者
- 木口 倫 吉田 真 斎藤 康樹 岡野 邦宏 西川 裕之 髙橋 政之 宮田 直幸
- 出版者
- 公益社団法人 日本水環境学会
- 雑誌
- 水環境学会誌 (ISSN:09168958)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.6, pp.257-270, 2022 (Released:2022-11-10)
- 参考文献数
- 76
- 被引用文献数
- 2
2020年6月と8月に秋田県八郎湖流域における浸透移行性殺虫剤および代謝物の濃度レベルと水平分布の調査を行った。その結果, ジノテフラン, イミダクロプリド, チアクロプリド, チアメトキサム, クロチアニジン, エチプロールとフィプロニルおよび代謝物のチアクロプリドアミドが検出された。最大検出率はジノテフランが100%, チアクロプリドアミドが80%であり, 水稲生産の影響が示唆された。最大検出濃度は, 8月の湖内でジノテフランが2,200 ng L-1, 6月の流入河川でチアクロプリドアミドが60 ng L-1であった。8月のジノテフランは調査水域の広い範囲で検出され, 他の農薬に比べて1-3桁高かった。ユスリカ幼虫の急性毒性値によるPNECと最大検出濃度を用いた初期リスク評価ではジノテフランのみが1より大きかった。しかしながら, 本研究では四季を通じた動態は不明であり, 詳細な調査が必要であると考えられた。
4 0 0 0 OA アイスクリームの保存温度の変動による 氷結晶形態の変化
- 著者
- 則竹(安藤) 寛子 加藤 豊望 梶原 一人 鈴木 徹
- 出版者
- 公益社団法人 日本冷凍空調学会
- 雑誌
- 日本冷凍空調学会論文集 (ISSN:13444905)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.263-270, 2012-06-30 (Released:2013-06-30)
- 参考文献数
- 12
The quality of ice cream surface degrades significantly from alteration of the surface properties due to the repetition of thaw-recrystallizing accompanied with temperature vibration at subzero temperature, a little above the melting temperature. For understanding the phenomena in detail, ice crystals in ice cream after once thawed and recrystallized was observed morphologically, and evaluated quantitatively by fractal analysis. It was shown that the shape of ice crystal recrystallized from once thawed ice cream was modified from round shape to complex shape, of which the degree depended on thawing temperature at subzero temperature. However, the ice crystal retuned gradually into round shape with increasing the holding time at the thawing temperature. These phenomena would be caused by spatial micro distribution of high concentration part which was organized in thawed ice cream by freezing concentration. That is, the complex ice crystal formed in thawed ice cream at subzero temperature would be induced by losing the micro uniformity of concentration.
4 0 0 0 OA 空間識失調と対策
- 著者
- 溝端 裕亮 藤田 真敬 大類 伸浩 菊川 あずさ 小林 朝夫 高田 邦夫 立花 正一 岩本 鉄也 山口 大介 木村 幹彦 別宮 愼也
- 出版者
- 航空医学実験隊
- 雑誌
- 航空医学実験隊報告 (ISSN:00232858)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.4, pp.79-93, 2016 (Released:2020-04-11)
- 参考文献数
- 54
- 被引用文献数
- 1
Spatial disorientation (SD) is a false perception of position, motion or attitude by the pilots, and the largest risk factor for fatal accidents. Prevention of SD is difficult. Early realization and withdrawal from SD using instrument flight is the best way to prevent accidents. To prevent accidents due to SD, aircraft’s systems have been developed, and SD training have been conducted. Terrain Awareness and Warning System (TAWS) provides pilots with visual and auditory warning. Automated Ground Collision Avoidance System (Auto GCAS) recovers flight attitude automatically when aircraft goes near into the ground. Spatial Orientation Retention Device (SORD) is multi-sensory warning system. Tactile Situation Awareness System (TSAS) gives vibration to the pilots to indicate pilot’s posture. Three Dimensional Landing Zone (3D-LZ) System projects view of landing zone to the cockpit even in bad weather. In this study, we collected information related to SD training among 21 military forces belong 17 countries. SD training usually includes lecture and experience learning. Pilots receive initial training and periodic training in 17/21 forces. Average frequency was 4 years (range: 6 months to 6 years). Japan Air Self-Defense Force has not conducted periodic SD training. The way of experience with SD is use of simulator similarly JASDF or in-flight demonstration. The simulator training is lower cost and safer than the in-flight training. To maintain and develop aircraft’s systems and SD training is continuously necessary.