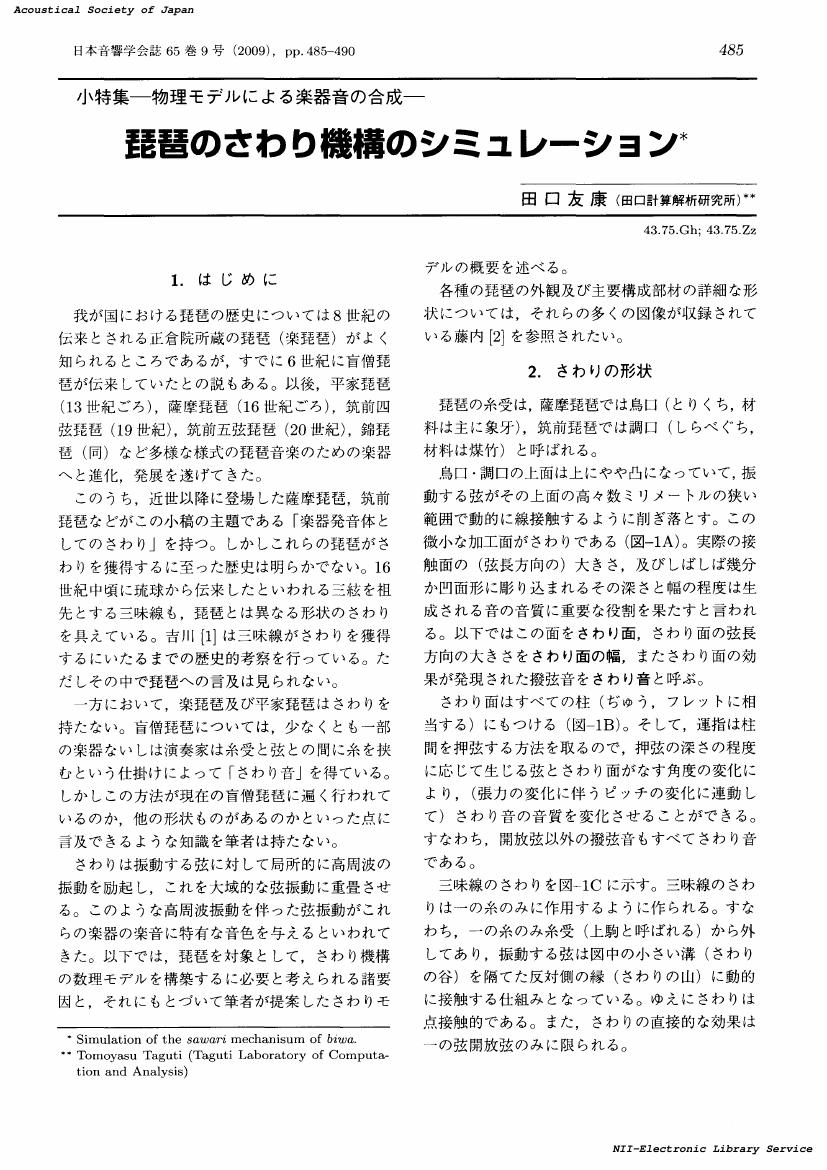4 0 0 0 OA 上中部食道潰瘍の臨床的検討―剥離性食道炎本邦50例の検討を含めて―
- 著者
- 石井 圭太 三橋 利温 今泉 弘 内藤 吉隆 芦原 毅 大井田 正人 安海 義曜 西元寺 克禮
- 出版者
- Japan Gastroenterological Endoscopy Society
- 雑誌
- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.363-371_1, 1992-02-20 (Released:2011-05-09)
- 参考文献数
- 42
- 被引用文献数
- 2
過去10年間に当科にて経験した上中部食道潰瘍31例につき検討した.平均年齢は,42.1歳と下部食道潰瘍症例(平均58.5歳)に比し,比較的若年者に多く,男15例,女16例と性差は認めなかった.原因の明らかなものは17例で,薬剤によるものが12例と多く,その他,異物,放射線治療,飲食物および扁平苔癬によるものを認めたが,原因が不明のものも14例みられた.症状は,胸骨後部痛,つかえ感,嚥下痛が多かった.潰瘍の性状は,不整形,略円形,剥離型の3つに分類できた.不整形と略円形が,大半を占め,剥離型は4例のみであった.症状消失期間および内視鏡的治癒期間を比較すると,不整形と略円形では,ほとんど差を認めないのに対し,剥離型は早期に治癒する傾向を認めた.このように剥離型は,その特徴的な形態はもちろんのこと臨床経過においても,不整形及び略円形とは明らかに異なり,これは剥離型では病変がより表層にあるためと思われた.剥離型とした症例は,いわゆる剥離性食道炎の範疇に入るもので,本邦における剥離性食道炎50例につき併せて検討した.なお,同期間に経験した下部食道潰瘍130例との比較も行った.
4 0 0 0 OA 指揮命令系統から見た秋田藩戊辰戦争 ―参謀・監軍・軍将―
- 著者
- 畑中 康博
- 出版者
- 秋田大学史学会
- 雑誌
- 秋大史学 (ISSN:0386894X)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, pp.68-95, 2019-03-31
4 0 0 0 OA 琵琶のさわり機構のシミュレーション(<小特集>物理モデルによる楽器音の合成)
- 著者
- 田口 友康
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.9, pp.485-490, 2009-09-01 (Released:2017-06-02)
- 参考文献数
- 12
4 0 0 0 OA フッ素とその化合物の健康影響
- 著者
- 河野 公一
- 出版者
- The Japanese Society for Hygiene
- 雑誌
- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.5, pp.852-860, 1994-12-15 (Released:2009-02-17)
- 参考文献数
- 46
- 被引用文献数
- 6 6
Fluoride, the ionic form of fluorine, is a natural component of the biosphere and 13th most abundant element in the crust of the earth. It is, therefore, found in a wide range of concentrations in virtually all inanimate and living things. Many trace elements perform a definite function in human metabolism and the question of the value of fluoride, always found in the body, has been raised. Much evidence suggesting that the inclusion of fluoride in drinking water has beneficial as well as adverse effects on human health was obtained. Either alone or in combination with calcium and/or vitamin D, it is used in high daily doses for the treatment of osteoporosis. Although organic fluorine compounds are used in medicine and commerce, the inorganic fluorine compounds are of greater importance toxicologically because they are more readily available. The major pathway of fluoride elimination from the human body is via the kidney. When renal function deteriorates, the ability to excrete fluoride markedly decreases, possibly resulting in greater retention of fluoride in the body. At this point, more research is needed to evaluate the effects of physiological variables on the fluoride metabolism in humans.
4 0 0 0 OA 転職経験による心理的契約の異同に関する研究
- 著者
- 服部 泰宏
- 出版者
- 経営行動科学学会
- 雑誌
- 経営行動科学 (ISSN:09145206)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.3, pp.229-237, 2008-12-31 (Released:2011-01-27)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1
The present study examined whether turnover experience would affect the nature of the psychological contract between employees and employers. Two reasons exist for this study to look at turnover experience as a determinant of the psychological contract. First, the turnover rate is increasing in Japan, and the need has emerged for the management to work out how to treat newcomers from other organizations. Second, people who can change their employers tend to have some expertise and exhibit considerable bargaining power in their job hunting activities, which may cause differences in the nature of psychological contract between them and those who have continued to stay in the same organizations. The result indicated that some dimensions of psychological contract are differently perceived between the leavers and the stayers. The implications of the study and future directions are discussed.
4 0 0 0 六大学野球部物語
- 著者
- 森茂雄 等著
- 出版者
- ベースボール・マガジン社
- 巻号頁・発行日
- 1956
4 0 0 0 OA 日本植民地都市計画に見る伝統的計画原理の取扱に関する論説
- 著者
- 五島 寧
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.41.3, pp.893-898, 2006-10-25 (Released:2018-06-26)
- 参考文献数
- 54
本論説では,景福宮および満州国執政府の改変・建設事例に着目し,伝統的な計画原理と日本の都市計画との間の関係を検討した。景福宮では,計画原理は意図的に破壊すべき対象という認識にすら達しないほど軽視されたと考えられ,執政府では,溥儀の意向に抗えなかった結果南面が表出したが,意識的な周礼の適用は考えがたいと結論した。計画原理の作為的破壊あるいは尊重という相矛盾した評価は,いずれも植民地都市計画の一面に対する過大評価とするのが筆者の見解である。
4 0 0 0 OA 国家捕獲報告書とアパルトヘイト後の南アフリカの暗部――新たな転換点――
- 著者
- 細井 友裕
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- アフリカレポート (ISSN:09115552)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.47-52, 2022-09-09 (Released:2022-09-09)
- 参考文献数
- 8
4 0 0 0 OA 人工循環に拍動流は必要か
- 著者
- 矢田 公
- 出版者
- 一般社団法人 日本人工臓器学会
- 雑誌
- 人工臓器 (ISSN:03000818)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.5, pp.1055-1061, 1994-10-15 (Released:2011-10-07)
- 参考文献数
- 26
4 0 0 0 OA 業績評価指標の仕組みと調べ方 : Top10%論文を中心に
- 著者
- 千葉 浩之
- 巻号頁・発行日
- pp.1-32, 2017-11-08
4 0 0 0 OA 「蝶」と「蛾」、“butterfly”と“moth”をめぐって
- 著者
- 関田 敬一
- 出版者
- 創価大学英文学会
- 雑誌
- 英語英文学研究 (ISSN:03882519)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.75-85, 2014-09-30
4 0 0 0 OA 日本錦 : 一名・武夫の友
4 0 0 0 OA 本邦における1979年以降6年間の小児細菌性髄膜炎の動向
- 著者
- 藤井 良知 平岩 幹男 野中 千鶴 小林 裕
- 出版者
- 一般社団法人 日本感染症学会
- 雑誌
- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.6, pp.592-601, 1986-06-20 (Released:2011-09-07)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 15 9
小林らの1966年から16年間の小児細菌性髄膜炎と比較し本邦に於ける1979年以降6年間の小児細菌性髄膜炎の現況を把握する目的で同じ施設107についてアンケート調査を行った.1,246名の症例を集計出来たが入院患者に対する比率は年次的に1984年の0.31%まで緩かな減少傾向を続けており, また地域差も見られた.新生児期24.8%と最も頻度が高く以降漸減するが4歳未満までに総数の84.7%が含まれ, この年齢別累積頻度は小林の報告と殆ど一致する.男女比は平均1.62: 1であった.起炎菌は3ヵ月未満の新生児・乳児ではE.coliとGBSが集積し, 3ヵ月以降ではS.pneimoniaeとH.influenzaeが集積してこの4菌種で菌判明例の70.1%を占め, 第5位のSmmsは各年齢に分散した.結核菌14, 真菌3, 嫌気性菌5などを除きグラム陽性菌と同陰性菌の比は1: 1.2であり少数宛ながら極めて多様なグラム陰性桿菌が検出された.髄膜炎菌22, リステリアは18件検出された.複数菌検出例は10例に認められた.起炎菌不明例は279例で年次的に3ヵ月未満群で菌判明率が梢高くなる傾向が見られた.
4 0 0 0 OA ヒューマンエラーを裁けるか─「裁く文化」は安全文化を阻害する─
- 著者
- 芳賀 繁
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.7, pp.954-960, 2012 (Released:2013-02-12)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
事故が起き,被害が生じた場合,わが国では警察が捜査して責任者を特定し,刑事裁判で裁くということが行われている.本稿では,ヒューマンエラーと刑事罰の現状を紹介し,ミスを結果論で裁くことが安全性向上に寄与しないどころか,マイナスの作用をすることを解説する.東日本大震災などで,マニュアルを超えた臨機応変な対応の重要性が再認識されるに至った.安全文化の一要素に「柔軟な文化」があり,それは近年ヒューマンファクターズの分野で注目される「レジリエンス工学」の概念に通じる.組織や個人の柔軟性,レジリエンスを支えるためにも,ヒューマンエラーを結果論で処罰しない「公正な文化」が必要なことを論じる.
4 0 0 0 OA ARPAの機能と性能
- 著者
- 曽我 直樹
- 出版者
- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会
- 雑誌
- マリンエンジニアリング (ISSN:13461427)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.5, pp.864-867, 2007-09-01 (Released:2010-05-31)
- 参考文献数
- 2