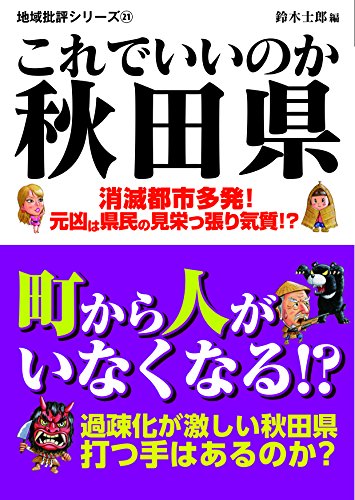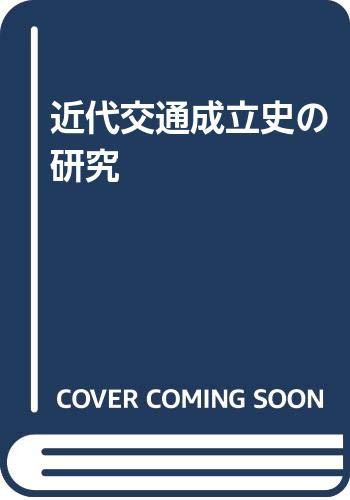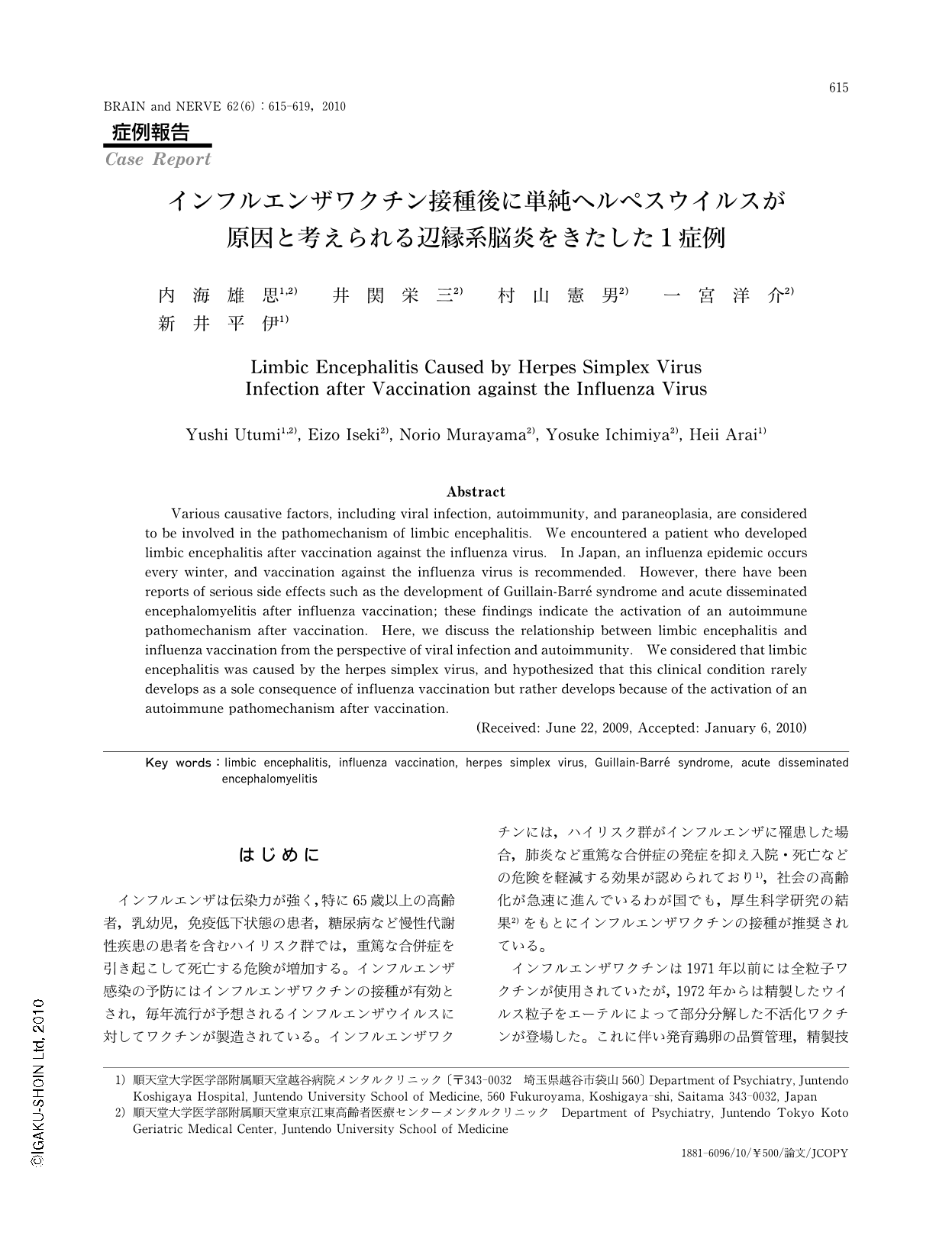4 0 0 0 OA シンポジウム
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.Suppl, pp.S-28-S-87, 2013 (Released:2017-09-12)
4 0 0 0 遺伝子診断・ゲノム編集技術の倫理的課題
- 著者
- 岩本 禎彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本血栓止血学会
- 雑誌
- 日本血栓止血学会誌 (ISSN:09157441)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.5, pp.541-548, 2015 (Released:2015-10-19)
- 参考文献数
- 15
要約:最近の遺伝子解析技術の爆発的進化は,臨床医学における遺伝子診断を,ますます身近なものにすると期待されている.遺伝子診断の中でも生殖細胞系列の遺伝子診断は,①将来の発症予見性,②生涯変化しないこと,③非発症保因者を診断できること,④血縁者,人種,地域共同体に共有されている可能性があること,という,他の医療情報にはない特徴を持つために,最も倫理的な配慮が必要である.とりわけ保因者診断,発症前診断,出生前診断には,遺伝カウンセリングが必須である.また,次世代シークエンサーを用いて全ゲノムやエクソーム解析を行った場合には,本当に診断したかった症候に関連した遺伝子異常だけではなく,予期せぬ遺伝子に配列異常が見出された場合にどう伝えるべきかが問題になっている.遺伝性疾患の根本的治療として,従来,ウイルスベクターを用いた治療が行われているが,受精卵や胚を治療の対象とすることは禁じられている.最近,中国で受精卵のゲノム編集が実施されたことが発表され,物議を醸している.ヒトの生殖細胞のゲノム編集についての議論を,日本でも開始するべきと考える.その際,人類遺伝学を正しく理解しておくことが重要なことである.
- 著者
- 今村 彰生 速水 花奈 坂田 雅之 源 利文
- 出版者
- Pro Natura Foundation Japan
- 雑誌
- 自然保護助成基金助成成果報告書 (ISSN:24320943)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.162-172, 2020 (Released:2020-09-29)
- 参考文献数
- 13
本研究は,環境DNAによりニジマスOncorhynchus mykissの分散ポテンシャルをマップ化し,さらに環境DNAメタバーコーディングにより在来魚群集の生息状況をマップ化することを目的とした.その上で,在来魚群集にとって好適な水系や生息地を抽出し,ニジマスの分散から受けるリスクの大小を視覚化した「ハザードマップ」を作成し,在来魚群集の保全への具体的な指針の提示を目指した.調査地はPNF27期助成での調査地の3地点と29期に合わせて追加した地点の計16地点とした.2018年10月—2019年8月にかけて1ヶ月に1回の環境水の採集を計11回実施しMiFish法によるメタバーコーディングを実施した.その結果,サケ科やコイ科を含め12科36群の魚類を検出した.地点ごとの種数の範囲は12–23種で,フクドジョウBarbatula barbatula,ドジョウMisgurnus anguillicaudatus,ハナカジカCottus nozawaeが全地点で検出され,外来サケ科のニジマスは16地点で検出された.国内外来種であるナマズも2地点で検出された.全体として,ニジマスを除くと在来種の比率は高かった.重点を置いているサケ科については,ヤマメ(またはサクラマス)Oncorhynchus masou sspp.の検出地点が15,アメマス(広義イワナ)Salvelinus leucomaenis sspp.が12,オショロコマSalvelinus malma sspp.が11,サケ(シロザケ)Oncorhynchus ketaが11と,在来サケ科は全地点で検出された.立地条件を加味して調査地点ごとに整理すると,石狩川中流域(旭川市内)でも検出種数は多く,なかでも旭川市の中心の調査地点旭橋では最大の23種が検出された.また,鱒取川やピウケナイ川という石狩川への流入河川と忠別川の調査地点で検出種数が多い傾向が見られたが,石狩川の支流でもオサラッペやノカナンでは検出種数が少なかった.また,忠別ダムの周囲は上流側下流側を問わず,全体として検出種数が少なかった.以上から,忠別ダムの周辺での淡水魚相が劣化傾向にある一方で,忠別川下流および忠別川と石狩川との合流点より下流において淡水魚相が豊かである傾向が示された.ニジマスとの排他的な関係については計画当初の予測に反して検出できず,今後の検討課題である.
4 0 0 0 OA 自己犠牲的行為の説明 ――行為の演技論的分析への序論――
- 著者
- 田村 均
- 出版者
- 日本哲学会
- 雑誌
- 哲学 (ISSN:03873358)
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, no.61, pp.261-276_L16, 2010 (Released:2011-01-18)
- 参考文献数
- 19
A self-sacrificial action is not consistent with rational decision-making. If an agent decides to take the rational course of action, that is, the best action among the options, the decision is not truly self-sacrificial. The agent has sought the best option and, therefore, nothing is really sacrificed. We need, then, a scheme other than that of rational decision making to explain self-sacrifice. I propose a theory which explains a self-sacrificial action as a kind of play-acting. In a play, an actor may take a role that is undesirable in real life. In a social situation involving self-sacrifice, the agent must accept such a course of action as undesirable but inevitable for anyone in the same situation. In a sense, the agent is coerced into playing an undesirable role. We cannot but see the agent as accepting it as an actor would. In instances of sacrifice, such as the sacrificial rite of the Ainu Bear Festival (IYOMANTE) or the legend of Iphigenia at Aulis, there is a traditional, social scenario that prescribes proper action. The self-sacrificial agent accepts such action in the same way that an actor accepts an unattractive role. The agent will intentionally perform the action; however, this is only in response to the prescription of the scenario. In other words, it is not based on an authentic decision, but on a play-acting decision. In this way, we can explain an act of self-sacrifice that implies a moral split for the agent. Contemporary theories of action, such as G. E. M. Anscombe's intellectualist theory or Donald Davidson's voluntarist-like theory, take it for granted that in any situation an agent is an integrated person with no moral split in principle. Moral splits, or dilemmas, are not, however, rare in everyday life. I put forward the play-acting theory of action as an alternative to contemporary theories.
4 0 0 0 OA 北朝鮮帰還事業の政治・外交過程、及び、邦人拉致工作に対するその前史形成の検証
4 0 0 0 OA 高等教育政策に関する一考察 : 新設される大学に着目して
- 著者
- 大橋 充典 野田 耕 行實 鉄平 奥野 真由 浦上 萌 Mitsunori Ohhashi Koh Noda Teppei Yukizane Mayu Okuno Moe Uragami
- 出版者
- 久留米大学人間健康学部
- 雑誌
- 久留米大学人間健康学部紀要 = Bulletin , Faculty of Human Health , Kurume University (ISSN:24350036)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.53-65, 2020-09-01
本稿の目的は,日本における高等教育の現状について,主に文部科学省の政策を中心に整理し,今後の高等教育のあり方について検討することであった。具体的には,高等教育における「マス化」および「ユニバーサル化」について,マーチン・トロウの高等教育論を参考として大学進学率の推移からこれまでの日本における高等教育がどのように変容してきたのかについて整理し,その上で,過去10年において設置が認められた新たな大学の特徴から日本における今後の高等教育政策について提言を行った。戦後の日本における高等教育の歴史は,1947年の学校教育法の成立による1949年の新制大学の発足が始まりとされる。その後,2010年代まで徐々に増加傾向をたどってきたが,2009年には進学率が50%を超えることになり,高等教育が「ユニバーサル化」する時期に差し掛かっている。2009年以降に新たに開設された大学における設置組織について概観してみると,特に看護や医療系の学部や学科,また理学療法や作業療法の専攻が半数程度を占めている。こうした状況を見ると,日本における高等教育は文部科学省主導で量的な拡大が行われてきたと言えるが,一方で,質の向上を含めた「計画的な整備」が進められてきたのかについては,今後も議論する余地が残されている。
4 0 0 0 近代交通成立史の研究
4 0 0 0 OA マイオカインは運動模倣薬となるか?
- 著者
- 眞鍋 康子
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.138, no.10, pp.1285-1290, 2018-10-01 (Released:2018-10-01)
- 参考文献数
- 41
Exercise is generally considered to have health benefits for the body, although its beneficial mechanisms have not been fully elucidated. Recent progressive research suggests that myokines, bioactive substances secreted from skeletal muscle, play an important role in mediating the benefits of exercise. There are three types of myokines in terms of the muscular secretion mechanism: those in which the secretion is promoted by stimulation, such as irisin, interleukin (IL)-6, and IL-15; those whose secretion is constitutive, such as thioredoxin, glutaredoxin, and peroxiredoxin; and those whose secretion is suppressed by stimulation, such as by a macrophage migration inhibitory factor. Although dozens of myokines have been reported, their physiological roles are not well understood. Therefore, there currently exists no advanced drug discovery research specifically targeting myokines, with the exception of Myostatin. Myostatin was discovered as a negative regulator of muscle growth. Myostatin is secreted from muscle cells as a myokine; it signals via an activin type IIB receptor in an autocrine manner, and regulates gene expressions involved in myogenesis. Given the studies to date that have been conducted on the utilization of myostatin inhibitors for the treatment of muscle weakness, including cachexia and sarcopenia, other myokines may also be new potential drug targets.
4 0 0 0 OA 建築家・白井晟一の著作にみる習書の意味
- 著者
- 羽藤 広輔
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.719, pp.179-186, 2016 (Released:2016-01-30)
While Seiiti Sirai was an architect, he spent a lot of time practicing calligraphy in his last years. Comparing the features of this activity with his theory of tradition, it can be said that both of his intentions are similar. In addition to the commonality of attaching importance to “utility,” according to the theory of tradition, the concept of grasping the inner potential of an object without being misled by its external form and source, can be realized by the “ascetic practices,” which can make something exceed consciousness and form by practicing calligraphy.
4 0 0 0 IR 朝食摂取が持つ知的作業への影響
- 著者
- 小林 幸子 坂本 元子 飯淵 貞明 内田 雅人 三橋 洋子
- 出版者
- 和洋女子大学
- 雑誌
- 和洋女子大学紀要 家政系編 (ISSN:09160035)
- 巻号頁・発行日
- no.40, pp.107-116, 2000-03
朝食摂取が知的作業に及ぼす影響をみる目的で実験をした。女子大生18名を対象に,適正食および不適正食の朝食を,同一人に交互に摂取させ,昼食前に知的作業を実施した。また知的作業と同時に,注意の持続性,集中力,精神的耐久性をみるためにクレペリンテストも実施した。朝食の給与は,女子大生の1日の平均摂取エネルギー量を1,500kcalと考え,その約30%を朝食とし,500kcalを適正食,100kcalを不適正食とした。朝食の食材は大学で調達し,秤量区分けした各食材を実験前日に被験者に渡し,実験当日の朝8時までに摂取させた。前日の夕食は午後9時までに済ませ,それ以降の飲食は禁じた。知能テストは田中式知能検査様式Bのテストから3種(置換,異同弁別,抹消の各問題)に計算問題,創造性問題を加えた5種類を平成10年10月20,21日,27,28日に実施した。置換問題は「図形記号に働く知覚速度と記憶の能力」「視覚的弁別あるいは判断の速さ,正確さと記憶の確かさ」をみる。異同弁別問題は「記憶・注意力に関係する視覚体制の確立度」「短期記憶と注意の維持の確かさ」をみる問題。抹消問題は「視覚的弁別の確かさと判断・反応の速さ」「注意の持続,弁別・判断・反応の速さ,確かさ」をみる問題。計算問題は「演算処理の正確さ,速さ」をみる。創造性問題は「拡散的思考の豊かさ,柔軟な思考」をみる。適正食群において視覚的弁別の確かさ,判断・反応の速さ,記憶・注意力・演算処理の正確さ,速さ等に有意に高得点がみられた。クレペリンテストの評価は,朝食の適,不適食の摂取が短期間では行動のバランスを乱すことや,心身の不安定に影響していないと思われる。
4 0 0 0 OA メタ認知から見た意識の生物学
- 著者
- 藤本 蒼 野口 真生 小村 豊
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.468-471, 2018-07-01 (Released:2020-09-29)
4 0 0 0 OA グローバル・ジャスティス運動が世界政治に与える影響に関する研究
本研究の成果は、類縁集団を基底としたグローバル・ジャスティス運動が世界政治に与えている影響を明らかにしたことである。本研究では、フローバル市民社会としてNGO以外にもオキュパイ・ウォールストリートや香港の抗議行動等、サイバースペースでの紐帯を活用した世界規模で見られる類縁集団ベースの運動を「社会運動2.0」と名付けて分析した。そこではグローバル・ジャスティス運動が、国際規範の形成と強化に寄与しており、これら新たな直接民主主義の波による国境のきわを越えた国際規範形成につき「社会運動のクラウド化」という概念を用いて説明し、現行のヘゲモニーや国際秩序への変更を求める同運動の特徴と動態を理論化した。
はじめに インフルエンザは伝染力が強く,特に65歳以上の高齢者,乳幼児,免疫低下状態の患者,糖尿病など慢性代謝性疾患の患者を含むハイリスク群では,重篤な合併症を引き起こして死亡する危険が増加する。インフルエンザ感染の予防にはインフルエンザワクチンの接種が有効とされ,毎年流行が予想されるインフルエンザウイルスに対してワクチンが製造されている。インフルエンザワクチンには,ハイリスク群がインフルエンザに罹患した場合,肺炎など重篤な合併症の発症を抑え入院・死亡などの危険を軽減する効果が認められており1),社会の高齢化が急速に進んでいるわが国でも,厚生科学研究の結果2)をもとにインフルエンザワクチンの接種が推奨されている。 インフルエンザワクチンは1971年以前には全粒子ワクチンが使用されていたが,1972年からは精製したウイルス粒子をエーテルによって部分分解した不活化ワクチンが登場した。これに伴い発育鶏卵の品質管理,精製技術の改良や発熱物質の除去などの技術的進歩によって,発熱や神経系の副作用は大幅に減少した。しかしながら,極めて稀ではあるが,Guillain-Barre症候群(Guillain-Barre syndrome:GBS)やacute disseminated encephalomyelitis(ADEM)など自己免疫機序が推定される脳神経障害を生じて後遺症を残す例も報告されている3,4)。 今回われわれは,インフルエンザワクチン接種後に単純ヘルペスウイルスによると考えられる辺縁系脳炎をきたした症例を経験した。インフルエンザワクチン接種後に生ずる脳神経障害は重篤な後遺症を残しかねず,最悪の場合死に至ることもある。これらを未然に防ぐためにも,インフルエンザワクチン接種後の副作用の発症機序を個々の症例ごとに検討することは重要である。
4 0 0 0 OA ハイパースペクトルイメージングと最適化 ―復元と合成―
- 著者
- 小野 峻佑
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.138-146, 2020-10-01 (Released:2020-10-01)
- 参考文献数
- 66
- 被引用文献数
- 1
ハイパースペクトル(HS)画像は紫外線領域から近赤外線域までの広い波長(スペクトル)帯の情報を細かく分光イメージングすることで取得される空間(二次元)―スペクトル(一次元)の3Dデータであり,人間の目や既存のRGBカメラでは捉えられなかった物理的性質や現象を可視化できる.しかし,空間―スペクトル情報を完全に取得することは計測環境/光学的設計の観点から困難なことが多く,計測の際に生じるノイズなどによる劣化も避けられない.本稿では,最適化を活用することで不完全かつ劣化を伴う計測データから所望のHS画像を推定する技術について解説する.
- 著者
- MOGI Motoyoshi
- 出版者
- 日本昆虫学会
- 雑誌
- 昆蟲 (ISSN:09155805)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.3, pp.387-392, 1975
- 被引用文献数
- 1
A new species of hippoboscid fly belonging to the genus Lipoptena is described. This is the second species of this genus parastic on the Japanese deer Cervus nippon in Japan.
- 著者
- 橋岡 由佳 佐藤 慎祐 徳田 泰司
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器がん検診学会
- 雑誌
- 日本消化器がん検診学会雑誌 (ISSN:18807666)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.6, pp.1128-1140, 2019
<p>入れ歯安定剤が硫酸バリウム(以下バリウム)の胃壁への付着過多を起こした場合の検査中の対応について検討した。</p><p>3社(A社, B社, C社)のバリウムと入れ歯安定剤2製品(以下D, E)を用いて粘度測定を行った。バリウムに人工胃粘液と発泡剤を加え粘度を測定した後D, Eを加えて再度測定した。既知の報告により本実験は50°Cのお湯30mLを追加して粘度測定をした。次にマーゲンファントムを撮影して視覚評価も行った。</p><p>D, E付加で粘度が上昇した。湯の追加で粘度はD, E付加前と同等または低下した。視覚評価では付着の評価も病変の評価も一部の条件を除き, D, E付加でバリウム溶液と有意差があり, 湯の追加でバリウム溶液と有意差はない結果となった。</p><p>バリウム溶液は懸濁液が冷水では粘度が上昇するためD, E付加で上昇した粘度を検査中に下げるにはお湯の方が効率的であると考えられた。ゆえにお湯30mLの追加は画質を担保できバリウムの付着を改善することが期待出来る。</p>
4 0 0 0 OA 都市空間の中の子育てネットワーク
- 著者
- 立山 徳子
- 出版者
- 日本都市社会学会
- 雑誌
- 日本都市社会学会年報 (ISSN:13414585)
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, no.29, pp.93-109, 2011-09-07 (Released:2012-12-19)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1 1
From the perspective of ‘family/community issues' and with an emphasis on the level of urbanization, this paper examines how families position themselves as ‘a family in a network' and recruit resources when they could not cope with childcare issues. The findings are as follows: 1) Depending on the area that includes inner-city, suburb and rural, there is a difference between the distribution of the network a mother possesses. 2) The location of the parents (especially their own parents) is related to the attainment of the mothers' own childcare networks. In relation to this, 3) among these areas, the attainment of resources for childcare networks was poor in suburban mothers. 4) Support from the husband also promotes social intercourse and attainment of childcare networks for the mother (wife). 5) Although support from husband and their own parents have an effect on reducing parenting related isolation of the mother. In general, 6) depending on the urbanization level of these areas, rural mothers attained strong childcare networks whereas suburban mothers attained weak childcare network. However, 7) suburban mothers seemed to actively use friends who are mothers as substitutes and tend to expect ‘childcare support' from them. Overall, 8) a structure in which a lack of intra-family childcare support is compensated by that of external-family cannot be found. It can be said that intra-family supports and external-family supports are in a positive correlation.