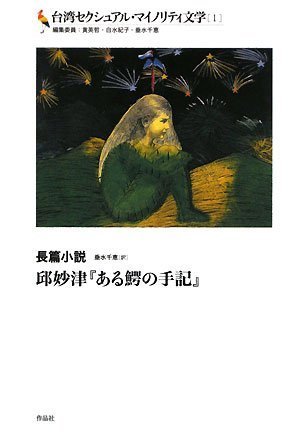3 0 0 0 OA PNLPの音声的形状と言語的機能
- 著者
- 前川 喜久雄
- 出版者
- 日本音声学会
- 雑誌
- 音声研究 (ISSN:13428675)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.16-28, 2011-04-30 (Released:2017-08-31)
Penultimate Non-Lexical Prominence, or PNLP, is a variant of phrase final rising-falling intonation in Standard (Tokyo) Japanese. In the first half of the paper, phonetic difference between the authentic rising-falling intonation and PNLP was examined using the phonetic data of the Corpus of Spontaneous Japanese (CSJ). In the last half, PNLP's linguistic function was analyzed using CSJ's monologue speech and clause boundary labels that provide information about the relative strengths of various clause boundaries. Analysis of the distribution of PNLP with reference to clause boundaries revealed two interesting functions. Firstly, PNLP seemed to have culminative function; it occurred, typically, only once in an utterance bounded by absolute (i.e., the strongest)clause boundaries. Secondly, modest delimitative function was also observed; PNLP occurred, most frequently, but not regularly, in the penultimate accentual phrase of an utterance thereby predicting the end of an utterance. These findings and pilot text analysis suggested tentative conclusion that native speakers of Japanese used PNLP to predict the end of an utterance and a change in topic at the utterance boundary.
3 0 0 0 OA 日本人第3大臼歯欠如頻度の時代変化
- 著者
- 山田 博之 近藤 信太郎 花村 肇
- 出版者
- 一般社団法人 日本人類学会
- 雑誌
- Anthropological Science (Japanese Series) (ISSN:13443992)
- 巻号頁・発行日
- vol.112, no.2, pp.75-84, 2004 (Released:2004-12-24)
- 参考文献数
- 87
- 被引用文献数
- 2 3
人の第3大臼歯は最も発生が遅く,形態変異も大きく,欠如率も高い。環境要因の影響を最も受けやすく,小進化を反映しやすい歯である。そこで,日本人集団の歯牙形態の小進化を考察する目的で,第3大臼歯の先天的欠如率を時代順に調べた。その結果,縄文時代人は欠如頻度が低く,ほとんどの第3大臼歯は発生していたが,弥生時代人になると急激に欠如頻度が高くなっていた。この急激な変化は,外来集団からの遺伝的影響によって生じたと考えられる。弥生時代人以降,欠如頻度はさらに高くなり,昭和初期にはピークに達した。その後,先天的欠如頻度は急激に減少し,第3大臼歯が存在する人は多くなっていた。昭和時代以降の変化は高栄養物の摂取と,それに伴う高身長化や性成熟の加速化によるものと思われる。
3 0 0 0 邱妙津『ある鰐の手記』 : 長篇小説
3 0 0 0 OA Cultural Japanの構築におけるジャパンサーチ利活用スキーマの活用
- 著者
- 中村 覚
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.4, pp.348-351, 2020-10-01 (Released:2020-11-16)
- 参考文献数
- 9
日本国内では、国の分野横断型統合ポータルである「ジャパンサーチ」が公開され、国内の多様なデジタルコンテンツに対するアクセスが容易となりつつある。一方、国外の機関が所蔵・公開する日本文化に関するデータの発見可能性は十分に高くない。そこで筆者らはIIIF/RDFなどのデータ相互運用技術を活用して、世界中の機関が公開する日本文化に関するデータを収集し、それらの発見可能性を高める仕組みである「Cultural Japan」の構築を行っている。本研究ではこの構築において、特に「ジャパンサーチ利活用スキーマ」の利用について述べる。本研究が、他のプロジェクト等での「ジャパンサーチ利活用スキーマ」の利用における参考事例となることを目指す。
3 0 0 0 IR 【研究ノート】近江学園を作った人々から学ぶ福祉の在り方 糸賀一雄・池田太郎・田村一二
- 著者
- 石野 美也子
- 出版者
- 京都文教短期大学
- 雑誌
- 京都文教短期大学研究紀要 (ISSN:03895467)
- 巻号頁・発行日
- no.58, pp.69-78, 2020-03-01
現代を取り巻く多くの福祉の課題は、児童虐待、高齢者虐待、いじめ、児童の貧困など解決すべき問題は多岐にわたる。今後、福祉はどうあるべきかを社会事業から社会福祉に転換をはかり、近江学園を創設した糸賀一雄、池田太郎、田村一二の人間観、福祉観およびその思想形成の過程を振り返ることで考察する。
3 0 0 0 OA 口から食べるリハビリテーション
- 著者
- 小山 珠美
- 出版者
- 一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会
- 雑誌
- 日本静脈経腸栄養学会雑誌 (ISSN:21890161)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.5, pp.1113-1118, 2015 (Released:2015-10-20)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
口から食べるリハビリテーションで重要なことは、非経口栄養の長期化や活動性低下による廃用症候群を予防した上で、食べるための包括的アセスメントとアプローチが必要である。本項では、廃用症候群への警鐘、安全・安楽・自立性を意図した食事援助の要素、認知症がある場合の特徴的な摂食行動と対応、QOLを高め経口摂取を継続していくための地域連携などについて紹介する。
- 著者
- 渡嘉敷 亮二 平松 宏之
- 出版者
- 日本喉頭科学会
- 雑誌
- 喉頭 (ISSN:09156127)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.02, pp.129-136, 2019-12-01 (Released:2020-05-20)
- 参考文献数
- 21
Understanding the three-dimensional (3D) movement of immobile vocal folds (VFs) is very important. Because endoscopic findings reflect only the two-dimensional movement of VFs, it is impossible to obtain a correct diagnosis. The cases presented in this article include not only those of unilateral vocal fold paralysis (UVFP) but also arytenoid dislocation, laryngeal scarring and other statuses. The main diseases are described below.UVFP : Even in cases of light UVFP, the paralyzed arytenoid is passively displaced cranially during phonation. Some surgical procedures may be applied to manage UVFP, but only arytenoid adduction can resolve this passive movement. I will also describe several specific types of UVFP, such as adductor branch paralysis (AdBP).Arytenoid dislocation (AD) : AD can be divided into two types: posterior and anterior dislocation. Our 3D computed tomography (CT) study revealed that posterior AD is very rare and often misdiagnosed as AdBP (and vice versa). We detected two subtypes of anterior AD: cranial and caudal. The VFs in cases of caudal AD are located in the mid position, and the patient’s voice is not severely affected; as such, these cases are sometimes misdiagnosed as medial UVFP.Other types of immobile VF : A number of rare and unique types of immobile VF have been reported, such as scarring after intubation or trauma, fracture, congenital and VF of many other causes. Endoscopy is insufficient for understanding what happens to a patient’s immobile VF However, 3DCT can reveal the actual status of these cases.
3 0 0 0 IR 『医療と福祉』誌にみる1990年代以降のMSWの対象認識
- 著者
- 村上 武敏
- 雑誌
- 聖隷クリストファー大学社会福祉学部紀要 = Bulletin of the School of Social Work Seirei Christopher University
- 巻号頁・発行日
- no.18, pp.1-21, 2020-03-31
特に1990 年代以降の医療制度改革により、MSW は必然的に退院援助業務に傾斜してきた。それは医療機関の組織的活動として位置づけられるようになり、MSW は政策的にも医療機関からも期待される活動を担いうる存在となったが、援助過程において効率性を求められるその業務にあって、しかも一貫した長期の援助を展開しにくい環境にあって、MSW の社会科学的な対象認識は希薄になりつつあるように感じられるのである。 本研究では、この1990 年代以降におけるMSW の対象認識の特徴を捉えるために、MSW による実践報告および調査報告、論文等について、1980 年から2014 年までの35 年間を分析した。 意思決定支援に対する関心が高く、さらに退院援助システムなど連携体制構築においても医療福祉固有の対象認識をうかがわせるような記述はなく、「患者一般」という対象像が垣間見える。MSWに求められてきた社会階層的な対象認識は希薄になり、生活問題を社会問題として捉えて解決に向かう実践の志向性は弱くなっている様子がうかがえた。医療福祉が社会科学的な対象認識を失うならば、医療福祉の社会的意義もまた失われることになる。時代に合わせて変化するMSW の存在形態とともに、変化を否定する医療福祉の本質部分を確認する作業となった。
3 0 0 0 OA 分子栄養学研究の立場から
- 著者
- 笠岡(坪山) 宜代
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.4, pp.183-187, 2005-08-01 (Released:2010-02-09)
- 参考文献数
- 8
3 0 0 0 OA 2.脳血管障害の血圧管理(急性期-慢性期)
- 著者
- 藤島 正敏
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.4, pp.553-558, 1991-04-10 (Released:2008-06-12)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 3 2
脳卒中の急性期・慢性期の血圧管理は次の点に留意する. (1)急性期の血圧上昇は自然降圧する.したがって脳出血の一部を除き降圧治療は行わない. (2)慢性期(発症1ヵ月以降)の高血圧は再発防止のために降圧治療を行う.降圧目標レベルは病型・重症度・年齢を考慮し,高齢者の血圧は高めに保つ.目標レベルまでは2ヵ月以上かけ降圧は緩徐に行う. (3)脳循環に悪影響のない降圧薬を選び,必要に応じて脳血管拡張薬・抗血小板薬を併用する.
3 0 0 0 OA 担われなければならない肉 故メルロ=ポンティへの老ドゥルーズの最後の一瞥をめぐって
- 著者
- 小倉 拓也
- 出版者
- 日本メルロ=ポンティ・サークル
- 雑誌
- メルロ=ポンティ研究 (ISSN:18845479)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.31-44, 2015-09-27 (Released:2015-09-26)
- 参考文献数
- 18
Dans Qu’est-ce que la philosophie?, son dernier travail conjoint avec Guattari, Deleuze envisage le concept merleau-pontien de « chair ». Dans ce livre, il définit l’art – distingué de la philosophie et de la science – comme la création de l’« être de sensation » qui n’est ni représentation ni perception. Dans cette recherche, le philosophe suggère que la chair pourrait révéler cet être. Cependant tout à la fin de son œuvre, il nous laisse une affirmation énigmatique selon laquelle la chair est « trop tendre » pour porter l’être de sensation et que « c’est la chair qui doit être portée ». Il introduit ainsi sa propre logique de la sensation à laquelle la chair merleau-pontienne manque.Dans cet essai, nous explorerons la manière selon laquelle Deleuze élabore sa conception de l’être et de la logique de la senation, en faisant face au « logos du monde sensible » et à l’invention du concept de chair chez Merleau-Ponty. En s’appuyant sur la pensée d’Erwin Straus, à qui les deux philosophes doivent beaucoup dans leurs théories de la sensation, nous traçons la problématique de la sensation qui les pénètre, pour comprendre la raison pour laquelle la chair est « trop tendre » et ce qui pourrait remplacer à celle-ci.
3 0 0 0 OA 金融論と簿記論・会計学との親和性について
- 著者
- 建部 正義
- 出版者
- 中央大学商学研究会
- 雑誌
- 商学論纂 (ISSN:02867702)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.4, pp.601-641, 2014-03-01
3 0 0 0 OA まだ,没落する大学 --私立大学のガバナンス問題について--
- 著者
- 城 達也
- 出版者
- 大阪経大学会
- 雑誌
- 大阪経大論集 (ISSN:04747909)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.1, pp.161-174, 2022-05-15 (Released:2022-05-31)
- 著者
- 木村 昌紀 磯 友輝子 大坊 郁夫
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.69-78, 2011 (Released:2012-03-24)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 1 3
本研究の目的は,関係に対する展望が対人コミュニケーションに及ぼす影響を関係継続の予期と関係継続の意思の観点から検討することである。先行研究では,実験操作による外発的な関係継続の予期に注目していた。そこで本研究では,自発的に生起した関係継続の意思に注目して,これらの関係に対する展望が対人コミュニケーションに及ぼす影響の共通点と相違点を調べた。未知関係20組40名と,友人関係25組50名の大学生が実験に参加した。結果は以下のとおりであった。先行研究と一致して,これからも関係が続いていくと思うときは,コミュニケーションの動機づけが促進されて,対人的志向性の個人差が消失した一方で,その場限りの一時的な関係と思うときは,社会的スキルの高い人ほど,積極的にコミュニケーションに取り組んでいた。また,先行研究では,関係継続の予期があるときは相手を知るために視線量が増加したのに対して,本研究では,関係継続の意思があるときは発話量が増加して,対人コミュニケーションをポジティブに認知していた点が異なっていた。そして,関係継続の意思が対人コミュニケーションに及ぼす影響の程度は,友人関係よりも未知関係において大きかった。
3 0 0 0 OA 宮崎県沿岸から得られたヤイトハタの記録
- 著者
- 緒方 悠輝也 宇都宮 伸一 和田 正昭 村瀬 敦宣
- 出版者
- 国立大学法人 鹿児島大学総合研究博物館
- 雑誌
- Ichthy, Natural History of Fishes of Japan (ISSN:24357715)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.1-5, 2021 (Released:2021-06-03)
3 0 0 0 OA 研究評価の拡大と評価指標の多様化
- 著者
- 林 隆之
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.4, pp.158-163, 2017-04-01 (Released:2017-04-03)
研究評価は,過去には研究者個人の研究業績や研究プロジェクトをピア(同分野の専門家)が科学的知識の妥当性から評価することが中心であった。しかし,研究活動自体が多様化するとともに,機関や組織による研究マネジメントの重要性が増し,研究成果による社会・経済的効果も期待されるようになる中で,研究評価の対象は拡大し,評価指標は多様化している。本稿では,研究評価の現状を概観することを目的に,研究評価の種類,大学等の機関の研究評価が導入された政策的背景,研究評価の方法の考え方,指標の多様性の必要性,インパクト評価の導入と課題,研究マネジメントへの活用について説明する。
- 著者
- YU ITO NORIO TANAKA
- 出版者
- The Japanese Society for Plant Systematics
- 雑誌
- Acta Phytotaxonomica et Geobotanica (ISSN:13467565)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.1, pp.15-28, 2013-06-29 (Released:2017-03-21)
- 参考文献数
- 51
Hybridization is a common phenomenon in many plant genera, and among them is the world's largest aquatic genus, Potamogeton (Potamogetonaceae) with about 69 species and 50 hybrids reported. Here we provide genetic insights into Potamogeton hybrids from China, where ten or more putative hybrids exist, of which eight have been genetically confirmed. In the study presented here, we verified the hybrid status and inferred the origins of three Potamogeton hybrids using molecular phylogenetic analyses of plastid (chloroplast) trnT-trnF and nuclear ITS sequence data sets that include previously published and newly generated data. The hybrids identified were: 1) P. ×inbaensis, a known hybrid from Japan; 2) a hybrid between P. perfoliatus s.l. and P. wrightii, and 3) a hybrid between tetraploid maternal P. distinctus and diploid paternal P. octandrus. Potamogeton ×inbaensis is reported from China for the first time, whereas the latter two hybrids are new to science.
3 0 0 0 OA 視覚障害児の発育・発達
- 著者
- 中田 英雄
- 出版者
- Japan Society of Human Growth and Development
- 雑誌
- 発育発達研究 (ISSN:13408682)
- 巻号頁・発行日
- vol.1995, no.23, pp.67-73, 1995-06-30 (Released:2010-03-16)
- 参考文献数
- 46
It is reported that physical growth of blind and partially sighted children is in a poor level and the adolescent growth spurt is earlier in the blind than in the partially sighted and the sighted. Most of studies of age at menarche have noted earlier onset in the blind than in the sighted. These studies have suggested that blindness is associated with an age of menarche which is earlier than sighted adolescents. Previous studies described delays in the appearance of motor skills, especially agility, with poor physical work capacity and balance. A recent research has suggested that the physical work capacity and postural control of the blind and partially sighted can be developed by appropriate training. By some well-designed program, the blind and partially sighted children should be able to enhance the ability to use their potential to the fullest. The adapted physical activity should be better understood.