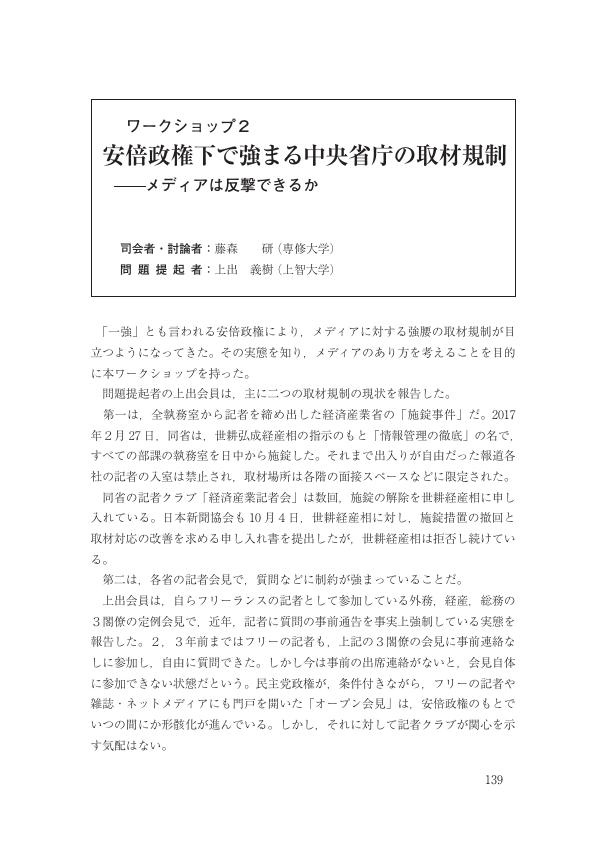3 0 0 0 OA ワークショップ2 安倍政権下で強まる中央省庁の取材規制
- 著者
- 藤森 研
- 出版者
- 日本マス・コミュニケーション学会
- 雑誌
- マス・コミュニケーション研究 (ISSN:13411306)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, pp.139-140, 2018-07-31 (Released:2018-10-13)
3 0 0 0 OA 東京職工学校の成立と展開 - 工業教育制度の下方拡充をめぐって -
- 著者
- 戸田 清子 Kiyoko TODA 奈良県立大学 Nara Prefectural University
- 雑誌
- 奈良県立大学研究季報 = NARA PREFECTURAL UNIVERSITY KENKYUKIHO (ISSN:13465775)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.61-92, 2012-02-29
3 0 0 0 OA 酒造用白米の形状と精米効率
- 著者
- 齋藤 富男
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.3, pp.170-177, 1993-03-15 (Released:2011-09-20)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 1 2
精米技術は, 近年の精米機の進歩などによって, ほとんど完成したかにみえる。しかし, 筆者の問題提起により, 現在のように特に低精米歩合の技術について見直す必要があろう。
3 0 0 0 OA 筋線維組成を規定する遺伝子多型は生活習慣病発症を予測するバイオマーカーとなるか
本研究では、骨格筋の速筋線維や遅筋線維の割合を規定する遺伝子多型を明らかにし、それらの遺伝子多型が将来の生活習慣病リスクとなるか否かについて検討を行った。日本人男性において、ACTN3 R577X多型およびACE I/D多型が骨格筋の筋線維組成に関連することを明らかにした。さらに、これら2つの遺伝子多型の組み合わせが、将来の高血圧発症リスクに影響を及ぼすことを明らかにした。これらの研究成果から、ACTN3 R577X多型およびACE I/D多型は骨格筋の筋線維組成に関連し、将来の高血圧リスクを反映する可能性が示唆された。
3 0 0 0 OA 脳の老化とシナプスの可塑性
- 著者
- 安藤 進
- 出版者
- バイオフィリア リハビリテーション学会
- 雑誌
- バイオフィリア リハビリテーション学会研究大会予稿集 バイオフィリア リハビリテーション学会第8回大会予稿集 (ISSN:18848699)
- 巻号頁・発行日
- pp.6, 2004-08-07 (Released:2004-10-25)
年とともにボケが心配になります。物忘れが激しくなると、痴呆症に近づいているのではないかと不安に襲われます。誰にでもくる老化ではあっても、なかにはいつまでも頭のしっかりしている人がいます。脳の老化はどのようにやってくるのか。一方、脳の健康はどうしたら保たれるのか。脳の科学、特にシナプスの働きから脳の機能低下を理解し、シナプスの機能向上の鍵を知ることによって、脳の老化への対処法がみえてくるかも知れません。
3 0 0 0 IR 「認知症鉄道事故裁判」に含まれる意味と記述
- 著者
- 海老田 大五朗
- 出版者
- 新潟青陵学会
- 雑誌
- 新潟青陵学会誌 (ISSN:1883759X)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.11-21, 2021-09
本研究の目的は、「認知症鉄道事故裁判」についての論文や資料を分析することで、この裁判における社会福祉的含意を引き出すこと、および本裁判で問題になったいくつかの記述を検討することである。本研究では、被告支援ネットワークの形成、「リスクの社会化」をめぐる議論、司法と行政の関係、認知症患者が起こした事故を「加害」と記述することへの違和感を考察した。被告支援ネットワークの形成には高齢者福祉や精神保健福祉行政の理念が深く関係していた。また、最高裁判決後、「リスクの社会化」についての議論が盛んになされた。最後に、本裁判と強く関係する「加害」や「徘徊」という記述の不適切性を指摘した。
3 0 0 0 OA TRPGにおけるGMBotの曖昧な発話が人間に与える印象の評価
- 著者
- 遠藤 水紀 宮本 友樹 片上 大輔
- 出版者
- 日本知能情報ファジィ学会
- 雑誌
- 日本知能情報ファジィ学会 ファジィ システム シンポジウム 講演論文集 第36回ファジィシステムシンポジウム
- 巻号頁・発行日
- pp.157-162, 2020 (Released:2020-12-18)
- 著者
- Yutaro Kaneko Yoshihisa Naruse Taro Narumi Makoto Sano Yuichiro Maekawa
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-22-0488, (Released:2023-01-14)
- 参考文献数
- 2
- 著者
- 福田 珠己
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.5, pp.404-405, 2018-09-01 (Released:2022-09-28)
- 参考文献数
- 1
3 0 0 0 OA 中学校国語教科書における「だろう」の変遷
- 著者
- 山下 真里 Mari Yamashita
- 出版者
- 熊本大学教育学部
- 雑誌
- 熊本大学教育学部紀要 (ISSN:21881871)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, pp.23-29, 2022-12-15
3 0 0 0 OA 行動分析学的「当事者研究」に可能性はあるのか—谷(2016)へのコメント—
- 著者
- 武藤 崇
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.159-160, 2016-05-31 (Released:2019-04-27)
- 参考文献数
- 5
3 0 0 0 IR <論文>"ズー"になる --ドイツにおける動物性愛者たちによるセクシュアリティの選択
- 著者
- 濱野 千尋
- 出版者
- 京都大学大学院人間・環境学研究科 文化人類学分野
- 雑誌
- コンタクト・ゾーン (ISSN:21885974)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2019, pp.62-94, 2019-08-31
本論文の目的は、ドイツにおける動物性愛者への調査に基づいて、動物性愛というセクシュアリティがもたらす、人間と動物のセックスを含めた種間関係のあり方を考察するものである。その際に本論文で焦点を当てるのは、動物性愛を意図的に選択し、自ら動物性愛者になっていく人々である。このような人々の存在について、これまで他領域を含む先行研究では言及されてこなかった。動物性愛というセクシュアリティを選び取る人々について学術的な言説のなかで言及するのは本論文が初めてである。本論文では彼らの実態を紹介し、事例を踏まえてダナ・ハラウェイによる伴侶種概念と比較検討しつつ、伴侶種を論じる際のセクシュアリティに対する視点の必要性を指摘する。動物性愛を選択する人々がいる事実は、動物性愛というセクシュアリティを生来的なものではなく、身近な動物との共生のためのオルタナティブな方法として受け入れうるものと説明できる可能性がある。本論文では、このような人々の事例をもとに、セクシュアリティの選択と、その結果としてもたらされる、異種間関係および人間関係の変容について論じる。
3 0 0 0 OA 診療看護師が行う超音波検査の有用性
- 著者
- 齋藤 真人 渡邊 隆夫
- 出版者
- 東北文化学園大学医療福祉学部看護学科
- 雑誌
- 東北文化学園大学看護学科紀要 = Archives of Tohoku Bunka Gakuen University Nursing (ISSN:21866546)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.3-10, 2018-03-31
超音波検査は非侵襲的かつリアルタイムに患者の身体情報を収集できるアセスメント機器である。フィジカルアセスメントや看護ケアを行う際のツールとして超音波検査は画像で評価をおこなうことから情報の客観性が高く、患者に対して無侵襲かつ経時的に評価が可能である。さらには必要な情報を可視化できる点で非常に有用である。患者に接する時間の多い看護師にとって超音波検査は聴診器とならび臨床業務の補助器具として有用性が高い機器である。大学院教育で超音波検査について系統的に学習する診療看護師が看護学領域での超音波検査の活用をリードしていくことで臨床看護にとって超音波検査が身近な存在となりえる可能性が示唆された
- 著者
- 井川 孝之 Takayuki IGAWA
- 出版者
- 国立社会保障・人口問題研究所
- 雑誌
- 人口問題研究 = Journal of Population Problems (ISSN:03872793)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.4, pp.549-576, 2022-12
特集 II
3 0 0 0 OA 新型コロナウイルス感染拡大に伴う国内人口移動傾向変化の人口学的分析―東京圏を中心として―
- 著者
- 小池 司朗 Shiro KOIKE
- 出版者
- 国立社会保障・人口問題研究所
- 雑誌
- 人口問題研究 = Journal of Population Problems (ISSN:03872793)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.4, pp.509-527, 2022-12
特集Ⅰ
3 0 0 0 OA 秋田県における山菜の利用とシロザの活用に関するバングラデシュとの比較
- 著者
- 藤本 恵子 池本 敦 FUJIMOTO Keiko IKEMOTO Atsushi
- 出版者
- 秋田大学教育文化学部
- 雑誌
- 秋田大学教育文化学部研究紀要 自然科学 (ISSN:24334960)
- 巻号頁・発行日
- no.75, pp.1-11, 2020-03-01
The edible wild plants were anciently important food materials as sources of nutrients such as vitamins but their utilization has been decreasing in the present day. To elucidate the utilization of edible wild plants in Akita prefecture of Japan, we performed questionary survey targeting at the inhabitants of the wide age age group. Elatostema umbellatum (“Mizu”), Osmunda japonica (Asian royal fern, "Zenmai") and Oenanthe javanica, (Java waterdropwort. “Seri”) were eaten well most. Laportea cuspidate (“Aiko”), Parasenecio hastatus (“Honna”) and Parasenecio delphiniifolius (“Shidoke”) were utilized well in Tohoku region and their rate of experiences of eating exceeded 70%. It is observed that Chenopodium album (white goosefoot, “Shiroza”) grows on the roadside in Japan, but 82.4% of the inhabitants did not know that they were edible. We also performed questionary survey in Bangladesh, where Chenopodium album is cultivated and eaten well. In our investigation, all Bangladeshi had the experiences of eating and it was used as a materials of the traditional cuisine such as sauteed vegetables, bhorta and curry. The values of Chenopodium album as foods in emergency and its availabilities as the teaching materials for safeguard against disaster were also discussed.
3 0 0 0 OA 表層型メタンハイドレート回収技術開発に向けたメタンハイドレート粒子運動に関する研究
- 著者
- 渡邊 裕章 廣瀬 智陽子 青山 千春
- 出版者
- 日本混相流学会
- 雑誌
- 混相流 (ISSN:09142843)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.4, pp.407-414, 2022-12-15 (Released:2023-01-13)
- 参考文献数
- 15
Methane hydrate is expected as domestic energy resources in near future in Japan. Especially the shallow-type methane hydrate and the associated methane plume are regarded as sustainable energy resources. In this paper, the investigation of the methane hydrate particle motion in the methane is presented. A quantitative analysis of the motions of the ascending methane hydrate particles seeping from the seafloor and reproduced by the numerical simulation is performed by the two-dimensional motion analysis technique and the behavior is discussed in detail.
3 0 0 0 OA 重症アトピー性皮膚炎に対する、ウェットラッピング法の併用
- 著者
- 村藤 大樹 木村 和弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会学術総会抄録集 第58回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)
- 巻号頁・発行日
- pp.178, 2009 (Released:2010-03-19)
アトピー性皮膚炎の治療は,一時期ステロイドバッシン グや民間療法の喧伝などにより混乱をきたしていたが, 2000年に日本皮膚科学会によるアトピー性皮膚炎診療ガイ ドラインが作成されてからは徐々に治療の統一がなされ, ステロイド外用剤の適正使用と保湿剤によるスキンケアの 重要性が強調されている。しかし,スキンケアの重要性に 対する認識は個々の医師によって差があり,その方法もま ちまちなのが実状である。 我々は2003年に小児科の専門外来として「アトピー外 来」を開設し,2009年4月現在の患者総数は1,135人であ る。そのうち重症と判断した319人(うち小児193人)を対 象に,ウェットラッピング法を用いて治療を行った。 ウェットラッピング法とは,保湿剤(炎症の強い個所には ステロイド外用剤を併用)を塗布した後に水で濡らした下 着やクッキングペーパーで体を覆い,さらにその上から調 理用ラップで被覆して2~3時間過ごすという手技で,通 常のスキンケアで対応困難な重度の乾燥肌に対し,初期治 療として行うものである。 治療の標準化を図るために,クリニカルパスを用いて4 日間の入院治療を行った。入院中に計6~8回のウェット ラッピングを行い,退院後も含めて計10回行った後通常の 外用療法のみへ移行した。患者は早ければ治療2日目の朝 には皮膚状態の改善を実感し,退院時にはほぼ全例で乾燥 肌の明らかな改善がみられた。短期間に皮膚の状態が劇的 に改善することで退院後の外用療法に対する治療コンプラ イアンスが向上し,ひいては治療期間の短縮とステロイド 外用剤使用総量の減量を達成することが可能となった。 アトピー性皮膚炎治療ガイドラインに準拠した外用療法 にウェットラッピング法を併用することは,重症アトピー 性皮膚炎の高度な乾燥肌に対する初期治療として非常に有 用であると考えられた。
- 著者
- 土井 寛大
- 出版者
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所
- 雑誌
- 森林総合研究所研究報告 (ISSN:09164405)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.4, pp.261-265, 2023-01-16 (Released:2023-01-17)
- 参考文献数
- 24
2022年5月および6月に、つくば市の森林総合研究所構内で旗振り法によるマダニ採取を行ったところ、キチマダニ、フタトゲチマダニ、アカコッコマダニ、タカサゴキララマダニが採取された。地域内の野生動物宿主相がシカやイノシシなどの大型動物を欠くことから、小・中型野生動物や野鳥をよく利用するキチマダニ、フタトゲチマダニ、アカコッコマダニは所内外を出入りする野生鳥獣によって運ばれていると考えられる。しかし、タカサゴキララマダニはイノシシが生息する地域によく分布する。さらに、本種の幼若期は人体刺症例が多い。これらのことからタカサゴキララマダニが構内に侵入した経路として、構内に出入りする小・中型野生動物によって持ち込まれた可能性とともに、イノシシの生息地で作業した人の衣類や機材に紛れて侵入した可能性を考慮しなければならない。
3 0 0 0 OA 脊髄小脳変性症患者の重心動揺に及ぼす重錘および緊縛帯負荷の効果
- 著者
- 本井 ゆみ子 松本 博之 千葉 進 野呂 浩史 梁田 由樹子 宮野 良子 兼重 裕
- 出版者
- The Japanese Association of Rehabilitation Medicine
- 雑誌
- リハビリテーション医学 (ISSN:0034351X)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.137-143, 1992-02-18 (Released:2009-10-28)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 2
【対象と方法】脊髄小脳変性症患者19名に重錘または弾性緊縛帯を足首および腸骨稜の高さで腰部に負荷し,負荷前後における重心動揺の改善率を求めた.その成績を起立・歩行状態,神経症状,およびMR画像と対比検討した.【まとめ】(1)重錘負荷時では足首と腰部負荷時改善率との間に相関を認めた(p<0.01).(2)足首および腰部前面重錘負荷は歩行が顕著に障害されているものの,独歩が可能な例に有効例が多い傾向にあった.(3)重錘負荷では深部腱反射亢進群は非亢進群に比較して有意な改善を示し(p<0.01),小脳虫部に比較して橋の萎縮が目立つ症例に有効例が多かった(p<0.05).(4)緊縛帯負荷では重錘負荷で認められた一定の傾向はなかった.