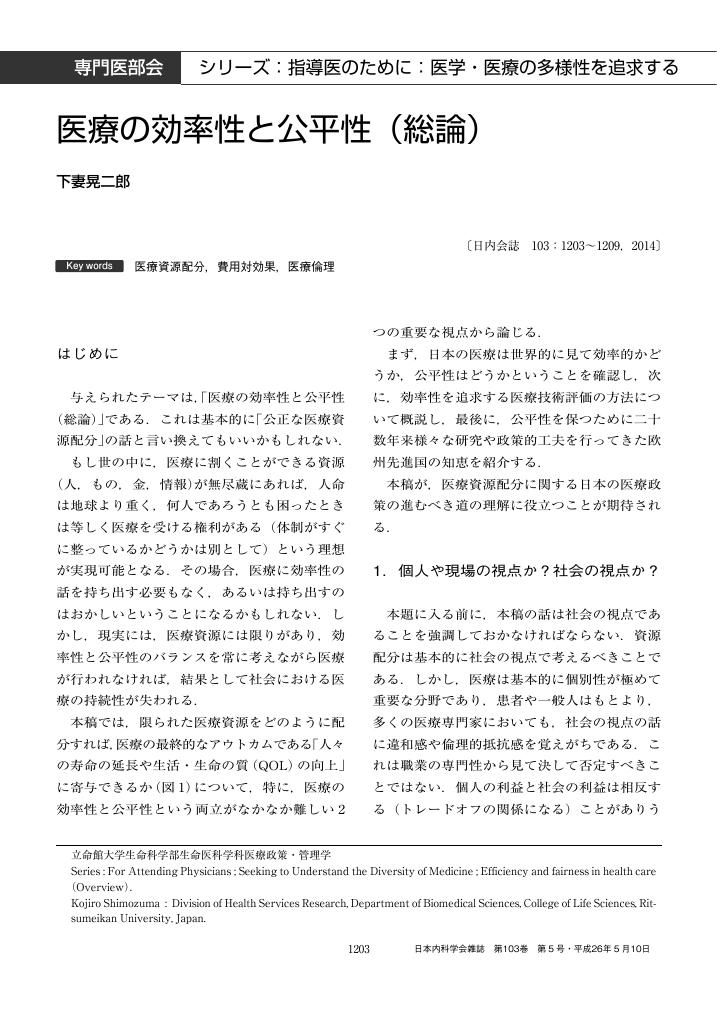3 0 0 0 OA 「病いの語り」と「治癒の語り」
- 著者
- 中村 英代
- 出版者
- 関東社会学会
- 雑誌
- 年報社会学論集 (ISSN:09194363)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.19, pp.165-176, 2006-07-31 (Released:2010-04-21)
- 参考文献数
- 29
In this study, I interviewed people who recovered from eating disorders. This revealed that individual understanding of their illness experiences had changed before recovery and after recovery. Heretofore, the research emphasis in the field of medical anthropology and medical sociology has been on “Illness Narratives” by individual suffering. In contrast, this study has focused on “Healing Narratives” by individual recovery. By showing the sociological research issues found in these “Healing Narratives”, I give meaning to hear the voices of people who have recovered from illness and difficulties.
- 著者
- 松田 侑子
- 出版者
- 日本キャリア教育学会
- 雑誌
- キャリア教育研究 (ISSN:18813755)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.11-20, 2014-09-30 (Released:2017-06-24)
3 0 0 0 OA 小児滲出性中耳炎に対するツムラ柴苓湯の臨床効果
3 0 0 0 OA 戦後日本人の憲法意識 ―世論調査集積法による分析
- 著者
- 三輪 洋文 境家 史郎
- 出版者
- 日本政治学会
- 雑誌
- 年報政治学 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.1, pp.1_34-1_57, 2020 (Released:2021-06-16)
- 参考文献数
- 17
本研究は、戦後に主要7調査機関が実施した憲法に関する世論調査の結果を包括的に分析することで、戦後日本人の憲法意識の変遷を追うことを目的とする。動的線形モデルを応用した世論調査集積法を用いることによって、質問内容やワーディングの違い、調査機関・調査方法ごとの傾向、標本誤差を考慮した上で、憲法改正に対する潜在的な賛成・反対率を推定できる。推定結果からは、有権者の認識において1950年代には憲法改正が全面改憲を意味したのに対して、1960~80年代にかけて争点が9条改正に収斂していったこと、1990~2000年代には9条以外の論点が明確に意識されるようになったこと、小泉政権後は焦点が再び9条問題に絞られつつあることが読み取れる。さらに、質問内容やワーディングに関する分析結果からは、一般的に9条の改正が2項の改正として有権者に認識されていることや、戦争を連想させることが9条改正の反対率を高めることなどが示唆される。
3 0 0 0 OA 後天性眼球運動障害の視能訓練
- 著者
- 深井 小久子
- 出版者
- JAPANESE ASSOCIATION OF CERTIFIED ORTHOPTISTS
- 雑誌
- 日本視能訓練士協会誌 (ISSN:03875172)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.49-61, 1998-07-10 (Released:2009-10-29)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 3 3
1.視能矯正ニーズの変遷視能矯正は小児の弱視と斜視が主要対象であったが,早期発見と予防・治療の進歩で,重篤な弱視や斜視の感覚運動異常は減少した.1993年には,視能訓練士法に検査業務が明確化され,視能検査が拡充した.21世紀を間近にして視能矯正の社会的ニーズは,乳幼児の健診,成人病検診,リハビリテーション(眼球運動障害),ハビリテーション(Low Vision),高次脳機能(学習障害,重複障害等)の領野に発展がある。本報では高齢社会でニーズが高まっている「後天性眼球運動障害の視能訓練」を報告する.2.どんな後天性眼球運動障害が増加したか23年間の後天性眼球運動障害の視能訓練数は296例であった。その発症原因は,外傷(頭部・眼)が第一位,次いで,炎症や脳血管障害があげられる。これは39歳以下と40歳以上でその頻度は異なる。前者は外傷(頭部・眼)によるものが第一位であり,後者では炎症,脳血管障害による眼球運動障害が増加している。3.教科書どおりの患者はいない後天性眼球運動障害は眼窩機械的,筋性,眼運動神経,核間などの障害で発症し,部位や程度により訓練の適応や効果が異なる。しかし,視能訓練をすすめる前提として「原因は何か」「どんな症状があるか」「何が不自由か」を分析し患者の実際的ニーズを知る。4.効果的な訓練法はなにか相反神経支配の異常と融像異常の状態から視能訓練プログラムを作成した。垂直偏位が水平より大きい場合は眼球運動訓練から輻湊,そして融像訓練にすすむと良好な結果が得られる。5.訓練により“治った”評価296例の結果は,治癒度Iは45%,治癒度IIは約44%であった。訓練の最終目標は,日常生活と社会復帰が“できる”満足度である.従って訓練により“治った”という基準には,日常生活での体験的な評価を含めたものが望ましい.融像の向上と日常生活の不自由度(満足度)の関係は必ずしも一致しなかった。6.視能訓練の社会的意義視能訓練は専門性が高い機能回復訓練であり,これにより社会復帰が可能なものは約88%ある。後天性眼球運動障害は外眼筋自己受容器系の障害であり,融像機能で視覚性と筋性の眼球位置覚を統合させ再建させることができる。この効果を具体的に示し,社会ニーズに応えていくことは,これからの視能矯正の発展につながる.
3 0 0 0 OA 医療の効率性と公平性(総論)
- 著者
- 下妻 晃二郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.103, no.5, pp.1203-1209, 2014-05-10 (Released:2015-05-10)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
3 0 0 0 OA L-アスパラギナーゼ関連凝固障害の機序 ~包括的凝固線溶機能による評価~
- 著者
- 石原 卓 野上 恵嗣
- 出版者
- 日本小児血液・がん学会
- 雑誌
- 日本小児血液・がん学会雑誌 (ISSN:2187011X)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3, pp.201-207, 2017 (Released:2017-12-08)
- 参考文献数
- 25
L-アスパラギナーゼ(L-Asp)を含む小児急性リンパ性白血病(ALL)の寛解導入療法の合併症の一つに凝固障害症がある.L-Asp投与によるアスパラギンの枯渇から生体内での蛋白合成が阻害され,肝臓における凝固因子や線溶因子などの産生障害がL-Asp関連凝固障害症の機序の一端になり得るとされるが,L-Asp関連凝固障害の病態はいまだ完全には解明されていない.新鮮凍結血漿,アンチトロンビン製剤,低分子ヘパリンなどによる支持療法が行われてきたが,至適な支持療法の確立にも至っていない.我々の教室は,包括的な凝固能と線溶能を同時に評価可能なトロンビン・プラスミン生成試験(T/P-GA)を新たに確立し,小児ALL3例(第1寛解期の再寛解導入療法2例と初発時寛解導入療法1例)においてこの評価法を用いて検討した.3例ともL-Asp投与中は包括的な凝固能が亢進し,逆に線溶能は抑制され,特にL-Asp投与相後半のフィブリノゲン(Fbg)低下時に向凝固・低線溶状態が顕著であり(差が1.5~2.6倍),相対的に凝固能優位な凝血学的に不均衡状態であることを初めて報告し,真の病態解明への第一歩を踏み出すに至った.L-Asp関連凝固障害の病態解明と最適な支持療法の確立のために,現在,血栓症の好発時期とされる寛解導入療法後半に着目し,新規診断された小児ALLの寛解導入療法において試料を収集して包括的な凝固線溶機能解析を行う多施設共同の前方視的臨床研究が進行中である.
3 0 0 0 OA 人工心臓の完全埋込み化技術
- 著者
- 柴 建次
- 出版者
- 一般社団法人 日本人工臓器学会
- 雑誌
- 人工臓器 (ISSN:03000818)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.86-88, 2014-06-15 (Released:2014-09-17)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
3 0 0 0 岩波講座日本歴史
- 著者
- 朝尾直弘 [ほか] 編集委員
- 出版者
- 岩波書店
- 巻号頁・発行日
- 1975
3 0 0 0 OA 暴行罪における「暴行」概念の史的展開 -立法・学説史にみる「暴行」の多元性-
- 著者
- 芥川 正洋
- 出版者
- 早稲田大学法学会
- 雑誌
- 早稻田法学会誌 (ISSN:05111951)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.1-51, 2016-10-25
- 著者
- 宮本 圭 和田 英敏 長坂 忠之助 髙野 はるか 本村 浩之 瀬能 宏
- 出版者
- 国立大学法人 鹿児島大学総合研究博物館
- 雑誌
- Ichthy, Natural History of Fishes of Japan (ISSN:24357715)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.9-13, 2022-07-08 (Released:2022-07-09)
3 0 0 0 OA 周期依存性の房室ブロックをきたしペースメーカー植込みを要した症候性HVブロック症例
- 著者
- 田村 美恵子 野田 誠 村上 輔 渡部 真吾 大山 明子 山本 康人 田代 宏徳 薄井 宙男 市川 健一郎 恵木 康壮 針谷 明房 高澤 賢次 磯部 光章
- 出版者
- 一般社団法人 日本不整脈心電学会
- 雑誌
- 心電図 (ISSN:02851660)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.5-10, 2012 (Released:2015-06-18)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
症例は47歳,男性.生来健康で,胸痛などの自覚症状はない.意識障害にて当院救急外来を受診したところ,心電図上完全房室ブロックによる最大10秒までの心停止を繰り返した.徐脈による症状と推定し,緊急入院のうえ経静脈ペーシングを行い,待機的に電気生理学的検査ならびにペースメーカー植込み術を施行した.冠動脈に異常はなく,左室収縮機能も正常であった.His束心電図ではHVブロックを認めたが,逆行性房室伝導はみられなかった.洞結節回復時間を確認するため洞調律より20bpm速い頻度(110bpm)で刺激を加えたところ,刺激直後から1:1の関係を保って持続的に心房刺激が心室を捕捉する所見がみられた.刺激停止後に再びHVブロックによる房室伝導障害が顕在化した.本現象は器質的心疾患の指摘されない健常心筋に生じた徐脈依存性ブロックと考えられ,その機序に第4相ブロックの関与が示唆された.
3 0 0 0 全国フェリー・旅客船ガイド : 運賃・航路時刻表
- 著者
- 運輸省海運局定期船課 [監修] 日本旅客船協会 [編集]
- 出版者
- 日刊海事通信社
- 巻号頁・発行日
- 1981
3 0 0 0 OA 可能世界意味論から見た現象学
- 著者
- 内田 種臣
- 出版者
- 日本科学哲学会
- 雑誌
- 科学哲学 (ISSN:02893428)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.41-55, 1976-11-10 (Released:2009-05-29)
- 参考文献数
- 24
3 0 0 0 OA 両親の夫婦関係に関する認知が子どもの自己肯定に及ばす影響 —女子青年の場合—
- 著者
- 宇都宮 博
- 出版者
- 一般社団法人 日本健康心理学会
- 雑誌
- 健康心理学研究 (ISSN:09173323)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.1-10, 2004-12-25 (Released:2015-01-07)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 2
The influence of perceived interparental commitment on self-affirmation in female adolescents was investigated. Participants (n=131) completed a questionnaire composed of interparental commitment, fulfillment and self-esteem. The Children's Perception of Interparental Commitment Scale contains four dimensions: “Whole acceptance of being / Unsubstitution”, “Social pressure / Powerless”, “Idea of permanence / Group orientation”, and “Material dependence / Efficiency. Self-affirmation in female adolescents was negatively affected by mother's “Social pressure / Powerless and “Material dependence / Efficiency”. Father's “Idea of permanence / Group orientation” was predictive of the low self-affirmation in female adolescents. Conversely, mother's “Idea of permanence / Group orientation” was predictive of high self-affirmation in female adolescents. The mother's commitment may play an important role in self-affirmation of female adolescents.