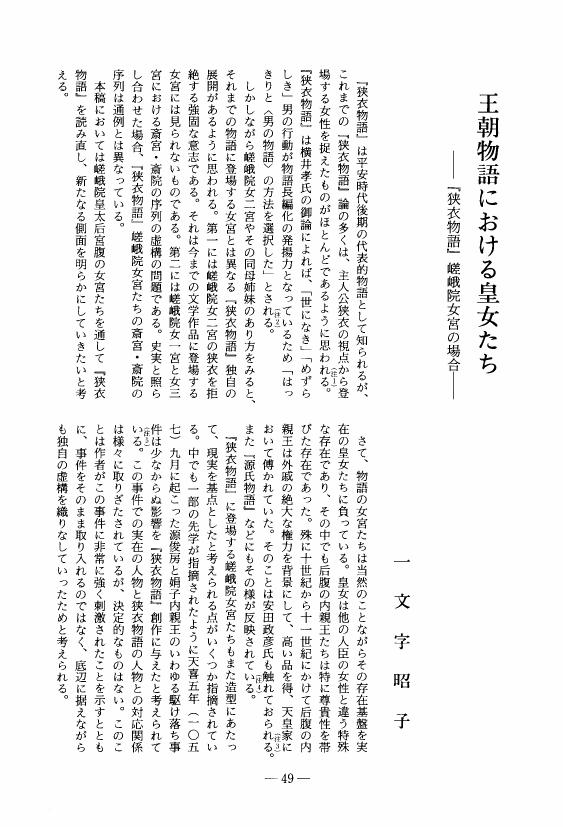2 0 0 0 OA 任意標本調査の母集団
- 著者
- 関 弥三郎
- 出版者
- 關西大学經済學會
- 雑誌
- 關西大學經済論集 (ISSN:04497554)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.4-5, pp.461-479, 1977-01-25
2 0 0 0 OA 悪性褐色細胞腫の診断と治療
- 著者
- 成瀬 光栄 田辺 晶代 立木 美香 難波 多挙 中尾 佳奈子 津曲 綾 臼井 健 田上 哲也 島津 章
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.8, pp.2330-2338, 2012 (Released:2013-08-10)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1
褐色細胞腫は治癒可能な内分泌性高血圧と位置づけられる一方,その約10%を占める悪性褐色細胞腫は早期診断法および確立された治療法のない希少難治性がんである.厚労省研究班の調査の推計患者数は約300人である.初回手術時にはその約30%以上が良性と診断され,一定期間後に骨,肝臓,肺などへの転移および局所浸潤を認める.病理組織所見の組み合わせによるスコアリング,SDHB遺伝子変異が悪性診断に有用とされるが,精度,感度,特異度はさらに検討を要する.治療はカテコールアミンの過剰があればαブロッカーを基本とする降圧治療を実施する.悪性では131I-MIBGの取り込みが十分なら内照射,取り込みがないならCVD化学療法が一般的であるが,いずれもわが国では厳密には適応外で,かつ無効例でのセカンドライン治療はない.近年,キナーゼ阻害薬のスニチニブの有効性が注目されており,海外では臨床試験が進行中である.本疾患は希少疾患であることから,個々の施設で単独の取組をするのではなく,多施設の連携,協力にて取組むことが重要である.
2 0 0 0 OA BEN-OIL IN ANCIENT EGYPT
- 著者
- Jiro KONDO
- 出版者
- The Society for Near Eastern Studies in Japan
- 雑誌
- Orient (ISSN:04733851)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.44-55, 1991 (Released:2009-02-12)
- 参考文献数
- 40
2 0 0 0 芥川竜之介「地獄変」覚書--その地獄へと回転する構造
- 著者
- 渡辺 正彦
- 出版者
- 日本近代文学会
- 雑誌
- 日本近代文学 (ISSN:05493749)
- 巻号頁・発行日
- no.27, pp.p158-168, 1980-10
- 著者
- 浅野 俊和
- 出版者
- 幼児教育史学会
- 雑誌
- 幼児教育史研究 (ISSN:18815049)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.19-32, 2013-11-20 (Released:2018-03-27)
2 0 0 0 OA 近代デジタルライブラリーの文字切り出しにおける実際的手法
- 著者
- 福尾 真実 高田 雅美 城 和貴
- 雑誌
- 研究報告数理モデル化と問題解決(MPS)
- 巻号頁・発行日
- vol.2012-MPS-87, no.34, pp.1-6, 2012-02-23
本研究では,近代デジタルライブラリーが所蔵する画像データから上手く文字を切り出す実際的手法の開発を行う.国立国会図書館では近代デジタルライブラリーとして,所蔵する書籍を Web 上で一般公開している.これらは,画像データとして公開されており,文書内容を用いた検索が行えないため,早急なテキスト化が求められている.そのため,近代書籍に特化した多フォント漢字認識手法が提案されている.しかし,ルビが振られた書籍からは上手く文字が切り出せず,認識ができない.そこで本稿では書籍の本文からルビを取り除く手法を開発する.
- 著者
- Seira Nishibe-Toyosato Yosuke Ando Nayu Nakasuji Takahiro Hayashi Kaori Ito Hidezo Matsuda Naho Tsujii Masahiro Tsuge Kazuyoshi Imaizumi Kenji Kawada Shigeki Yamada
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.505-510, 2023-03-01 (Released:2023-03-01)
- 参考文献数
- 25
Pharmaceutical consultation targeting outpatients at the Fujita Health University Hospital (Japan) provides support to patients undergoing anticancer drug treatment. This study aimed to explore factors that affect the comprehension of cancer chemotherapy among outpatients who received cancer treatment at our hospital. A questionnaire survey was conducted, and comprehension was scored on a scale of 1–5 (1, no comprehension; 5, full comprehension). When factors other than age and sex [the influence of which on comprehension has been reported in previous reports] were noted, differences in comprehension between the questionnaire items were comparatively analyzed according to the presence/absence of the relevant factors. Overall, 536 patients were included. Age (<70 years) and pharmacist interventions were identified as factors contributing to a comprehension score. The levels of comprehension regarding the name of the cancer chemotherapy, content/schedule of the treatment, purposes of the prescribed drugs, and objectives of blood tests were significantly higher in the group that received the pharmaceutical interventions; conversely, the level of comprehension for the self-management of adverse events was significantly lower in this group than in the group that did not receive any pharmaceutical interventions. Age and interventions by the pharmacist affected the comprehension of cancer chemotherapy by patients.
2 0 0 0 IR 芥川竜之介「おぎん」の位置--<文明批評>と<存在論>と
- 著者
- 井上 洋子
- 出版者
- 九州大学国語国文学会
- 雑誌
- 語文研究 (ISSN:04360982)
- 巻号頁・発行日
- no.84, pp.1-15, 1997-12
2 0 0 0 裏切りのエシックス : 太宰治「駈込み訴へ」論
- 著者
- 高橋 宏宣
- 出版者
- 福島工業高等専門学校
- 雑誌
- 研究紀要 = Research reports,Fukushima National College of Technology (ISSN:09166041)
- 巻号頁・発行日
- no.54, pp.43-53, 2013
2 0 0 0 IR インタビュー 解放後,韓国知識人の歩み : 安秉直氏に聞く(下)
- 著者
- 安 秉直 今西 一
- 出版者
- 小樽商科大学
- 雑誌
- 商學討究 (ISSN:04748638)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.291-315, 2017-07
2 0 0 0 OA 〈論説〉再審有罪判決の可否 ―冤罪救済の貫徹―
- 著者
- 原田 保
- 出版者
- 愛知学院大学法学会
- 雑誌
- 愛知学院大学論叢. 法學研究 = THE AICHIGAKUIN LAW REVIEW (ISSN:04393252)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.1,2, pp.29-46, 2020-06-01
2 0 0 0 『怪談牡丹灯籠』語彙総索引
2 0 0 0 赤田光男論集歴史民俗学の展開
- 著者
- 赤田光男 [著] 高田照世 杉﨑貴英 [編集]
- 出版者
- 赤田彰子
- 巻号頁・発行日
- 2022
2 0 0 0 赤田光男遺稿集中近世大和の民俗世界
- 著者
- 赤田光男著 帝塚山大学奈良学総合文化研究所編
- 出版者
- 帝塚山大学奈良学総合文化研究所
- 巻号頁・発行日
- 2022
2 0 0 0 OA 驅逐艦の公試運轉成績
- 著者
- K.M.
- 出版者
- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- 造船協会雑纂 (ISSN:24331023)
- 巻号頁・発行日
- vol.172, pp.428-434, 1936 (Released:2018-03-01)
2 0 0 0 OA 王朝物語における皇女たち ―『狭衣物語』嵯峨院女宮の場合―
- 著者
- 一文字 昭子
- 出版者
- 中古文学会
- 雑誌
- 中古文学 (ISSN:02874636)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, pp.49-59, 1998-11-30 (Released:2019-05-18)
2 0 0 0 OA 【研究ノート】ソンディ・テストにまつわる諸問題について―倫理的課題を中心に―
- 著者
- 上松 幸一
- 出版者
- 京都文教大学
- 雑誌
- 臨床心理学部研究報告 = Reports from the Faculty of Clinical Psychology Kyoto Bunkyo University (ISSN:18843751)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.125-138, 2020-03-31
The purpose of this study was to understand and examine the recognition of experts in Japan and overseas about the ethical issues of Szondi-test.Primary recognition of Szondi-test's ethical issue in forein countries is that Szondi-test is unscientific.On the other hand, in japan, primary ethical issues of Szondi-test are considered that (1) to use face photos of mental disease person and criminal, (2) in the first place, to utilize faces of person as a tools, (3) to be bad influences by presenting strong invasive stimulus photos to testee.There was also a side where it can't be said that it was ethical partially by the current state as a response to recognition of our country, but the all could think it couldn't be said non-ethics-like.And in our country, there are person who recognize that Szondi-test is unscientific. But we must be careful consider whether they all recognize Szondi test as unethical.With respect to invasiveness, although there are relatively many people who feel the problem, in comparison with other projective tests , there is no recognition that significantly strong.There are several aspects of invasiveness, and it was speculated that this study focused only on the stimulus intensity of the photos.
2 0 0 0 OA 精神保健福祉法第34条による移送制度の現状と課題
- 著者
- 伊東 秀幸
- 雑誌
- 田園調布学園大学紀要 = Bulletin of Den-En Chofu University
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.41-56, 2010
都市部を中心に民間患者搬送業者が家族等からの依頼を受けて、精神障害者の入院に伴う搬送業務を請け負うという事例が問題化されたことから、1999(平成11)年の精神保健福祉法改正によって移送制度が創設された。法第34条による移送制度は、受診を拒否する精神障害者の移送を都道府県知事の責任において実施されるものである。ところが創設当時から、地域間の格差が大きいことなどさまざまな問題が指摘されていた。創設から10年経過したが、当時の問題が未だに解消されておらず、現在でも民間患者搬送業者による患者搬送が実施されている現実がある。今後、受診について非自発的な患者の医療アクセスを保障する手段として、移送制度を適正に実施されなければならないと考える。
2 0 0 0 OA 抗体医薬品の体内動態制御に関わる受容体:FcRn
- 著者
- 石井 明子 鈴木 琢雄 多田 稔 川西 徹 山口 照英 川崎 ナナ
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.136, no.5, pp.280-284, 2010 (Released:2010-11-10)
- 参考文献数
- 45
- 被引用文献数
- 2 2
腫瘍や自己免疫疾患等の治療を目的とした分子標的薬として,抗体医薬品の研究開発が国内外で活発に行われている.抗体医薬品の特徴は標的分子に高い親和性をもって極めて特異的に結合することであるが,他のバイオ医薬品と比較して血中半減期が長いことも特筆すべき点である.ペプチドあるいはタンパク質を医薬品として応用する場合には血中半減期が実用化のためのハードルとなることが少なくない.しかし,多くの抗体医薬品は,生体内IgGの分解抑制に関わるneonatal Fc receptor(FcRn)を介したリサイクリング機構を利用することができるため,数日~数週間という長い血中半減期を有している.FcRnは齧歯類の新生児小腸に高発現し,乳汁に含まれる母親由来IgGの吸収に関与する受容体として同定された.その後の研究により,FcRnが成体においても種々の組織に発現し,IgGのリサイクリングやトランスサイトーシス等に関与していることが報告され,母子免疫以外にも様々な側面でIgGの体内動態制御に関わっていることが明らかにされている.我々は,既承認抗体医薬品のFcRn結合親和性を解析し,ヒトでの血中半減期とFcRn結合親和性の相関,および抗体医薬品のFcRn結合親和性を規定する構造特性の一端を明らかにした.近年の創薬研究では,FcRn結合親和性を改変した抗体医薬品等の開発が進んでいる他,FcRnのもう1つのリガンドであるアルブミンを利用することにより体内動態特性を改変したタンパク質医薬品の開発も進んでいる.FcRnは,抗体医薬品をはじめとするバイオ医薬品の体内動態制御に関わる鍵分子の1つと言えるであろう.
- 著者
- Atsumu Osada Chinatsu Sakuragi Chisashi Toya Akiko Mitsuo
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.5, pp.749-753, 2022-03-01 (Released:2022-03-01)
- 参考文献数
- 47
- 被引用文献数
- 14
We herein report the case of an 80-year-old Japanese woman who presented to our hospital with bilateral pain in the shoulders and hips lasting for a month since 2 days after the second dose of the BNT162b2 COVID-19 vaccine. Her physical findings, laboratory data, and ultrasonographic findings of bilateral biceps tenosynovitis and lateral subacromial bursitis were consistent with a diagnosis of polymyalgia rheumatica (PMR). She was successfully treated with oral prednisolone 15 mg/day. Although a causal relationship could not be definitively confirmed, PMR should be considered as a differential diagnosis in cases of persistent myalgia after administration of the BNT162b2 vaccine.