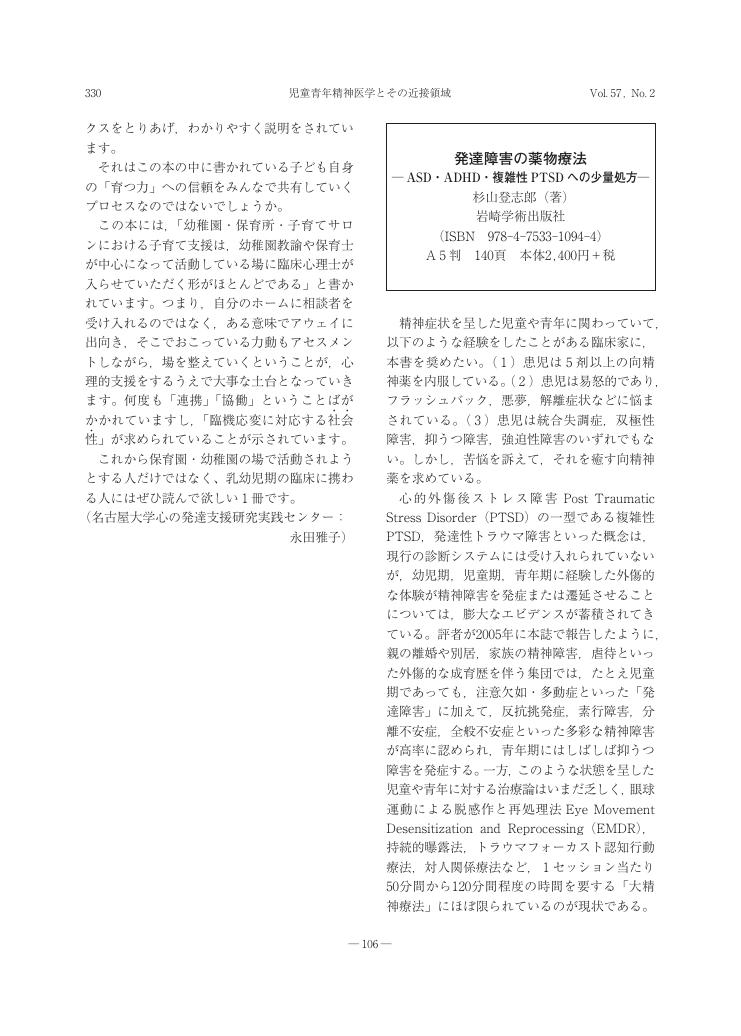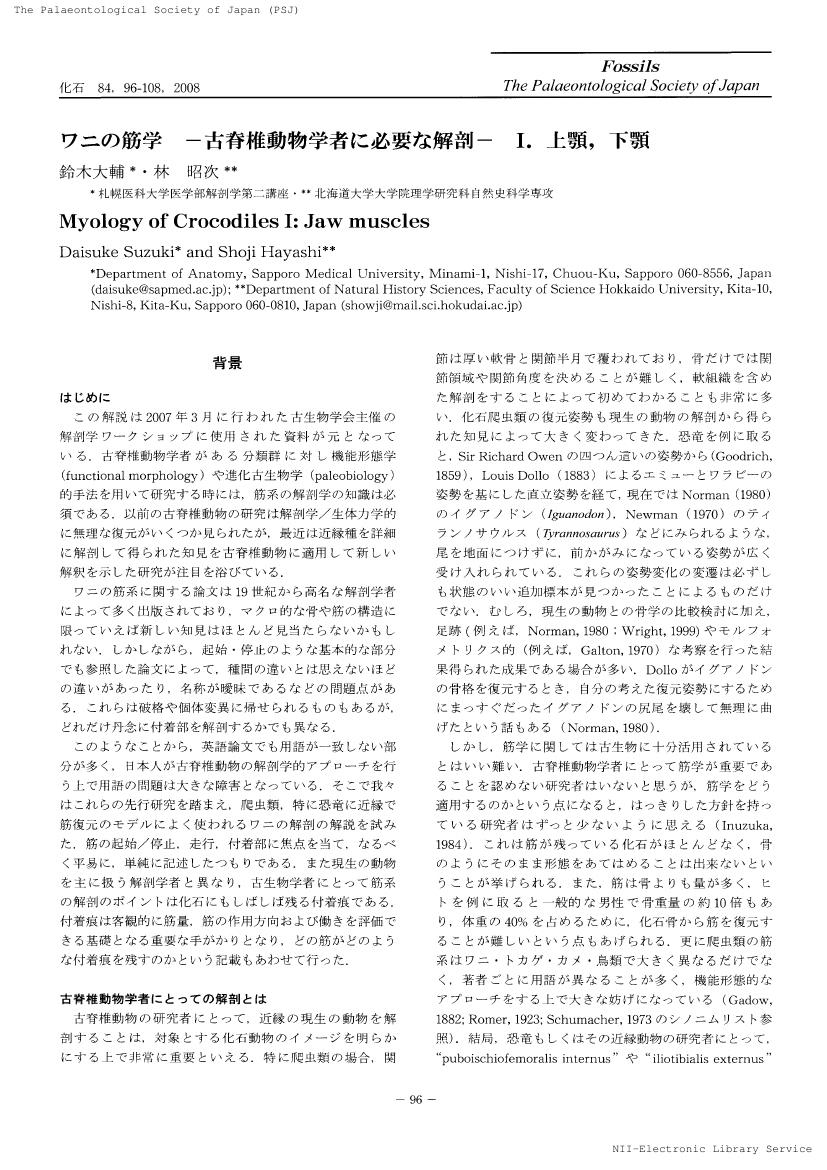2 0 0 0 OA 3.アトピー性皮膚炎・かゆみと脳機能
- 著者
- 石氏 陽三
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.6, pp.777-782, 2017 (Released:2017-07-12)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 2
2 0 0 0 OA プラナリアのオペラント条件づけ
- 著者
- 田積 徹 溝口 大和 阿孫 さや香 大足 彩月 工藤 裕輝 星野 菜々子 渡邉 みなみ
- 出版者
- 文教大学
- 雑誌
- 人間科学研究 = Bulletin of Hman Science (ISSN:03882152)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, pp.103-114, 2023-03-01
Planarians have the basic brain structure of an animal and, like mammals, their brain produces a variety of neurotransmitters, suggesting that they have a learning and memory function. Based on a previous study (Chicas-Mossier & Abramson, 2015), six students in seminar of the 3rd year examined the effects of shaping in the acquisition of operant conditioning by planarians. Results indicated that planarians trained by shaping acquired operant conditioning earlier than planarians not trained by shaping and that training led them to display stable operant behavior. In contrast, planarians that were not trained by shaping were slow to acquire operant behavior and they did not display stable operant behavior. The current work compared the results of this experiment to those of previous studies and it discussed the possibility that the behavioral measures used to gauge operant behavior may differ depending on the protocol and the species of planaria used. Moreover, this work discussed the feasibility of introducing operant conditioning experiments with planarians in lessons such as seminars and laboratory classes.
2 0 0 0 OA Alday-Gaiotto-Tachikawa予想とその発展
- 著者
- 瀧 雅人
- 出版者
- 素粒子論グループ 素粒子論研究 編集部
- 雑誌
- 素粒子論研究 (ISSN:03711838)
- 巻号頁・発行日
- vol.119, no.4B, pp.171-243, 2012-02-20 (Released:2017-10-02)
2009年にAlday、GaiottoおよびTachikawaによって発見された新しいタイプの「双対性」について概論したい.摂動的な計算結果の観察から、彼らはN=2四次元超対称ゲージ理論のインスタントン分配関数が、二次元共形場理論のVirasoro共形ブロックと解析的に結びついていることを見抜いた.すなわちこれは四次元ゲージ理論の分配関数と二次元共形場理論のカイラル相関関数が等価であることを意味している.つまり少なくともこれらのセクターにおいては、両理論の間に双対性が存在していることが強く示唆されている.このレビューでは、共形ブロックとインスタントン分配関数の組み合わせ論的計算手法を紹介する.その後でAlday-Gaiotto-Tachikawaの原論文に従い、AGT対応を発見法的に確認する.さらに、その他の双対的記述や弦理論との関係、あるいは証明の試みなどについても紹介したい.なお本稿は、2010年11月に東京工業大学素粒子論研究室で行ったセミナーの講義ノートを大幅に加筆したものである.
2 0 0 0 OA 確率モデルを用いて国家試験合格率を予測する方法
- 著者
- 江原 義弘 前田 雄 須田 裕紀 佐藤 未希 郷 貴博
- 出版者
- 新潟医療福祉学会
- 雑誌
- 新潟医療福祉学会誌 (ISSN:13468774)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.61-66, 2021-11-30 (Released:2021-11-30)
- 参考文献数
- 13
医療系大学ではほとんどの学生が国家資格を取得することを目標に入学しているので国家資格試験の合格率は最大の関心事である。各学生の国家試験合格確率と学科全体の合格率が1年前から推定できる方法を提案した。これによって昨年と同じ対策で良いのか、それとも対策を変更する必要があるのかを、具体的なデータに基づいて検討することを可能とするためである。定員40名のある学科の1年間の模擬試験の成績と実際の合格・不合格のデータから、ある時期の模擬試験である点数を取った学生のうち何人の学生が合格していたかの合格確率を点数ごとに計算した。この確率と経時変化を折れ線グラフでモデル化した。このモデルを他の年度のデータに適用した。これによって各回の模擬試験の点数から各学生が昨年度と同じ努力をした場合の本番の試験の合格確率が推定できた。合格確率を合算することで学科全体で何人が合格可能かを推定できた。4年間の結果は、予測された合格率を実際の合格率で除した値を的中率とすると、各年度における2か月前の時点での的中率は0.86、1.00、0.99、1.13となった。当初の予想が悪い結果であれば対策を変更し、試験直前の予測が合格率100%となり、試験当日100%合格を実現できるのが理想的なシナリオである。
2 0 0 0 OA 野生動物を食べる “ジビエと食品衛生の課題”
- 著者
- 山﨑 朗子
- 出版者
- 日本家畜臨床学会 ・ 大動物臨床研究会・九州沖縄産業動物臨床研究会
- 雑誌
- 産業動物臨床医学雑誌 (ISSN:1884684X)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.3, pp.114-121, 2020-11-10 (Released:2021-01-26)
- 参考文献数
- 19
昨今,ジビエ産業が賑わいを見せているが,社会一般的には突如巷に現れた野生動物食ブーム,という感が強く,その背景や生産過程についてはあまりよく知られていない.元来食肉は家畜と家禽に由来するもので,相応の法的規制の下に生産されるが,現在の日本の食肉生産方法に野生動物を組み込むことは衛生面から不安が多いため,家畜とは異なる解体施設での食肉生産を義務付けられている.しかし,大自然の中で生育した野生動物が保有する微生物によるヒトへの危害性については未知の部分が多いにもかかわらず,家畜でないため,家畜に課せられる法律が適用できないことから生産された食肉の安全性に不安を持つ声も少なくない.既に産業としてのジビエ生産が確立されている米国,欧州ではそれぞれに適した衛生管理政策によって衛生管理を実現しているが,その方法は両者とも大きく異なっている.これらの先行している衛生管理政策を参照し,我が国に適したジビエの衛生管理法の構築が望まれる.
2 0 0 0 OA 運動部活動の顧問が認知する体罰関連要因と体罰行為経験との関連
- 著者
- 霜触 智紀 笠巻 純一
- 出版者
- Japan Society of Sports Industry
- 雑誌
- スポーツ産業学研究 (ISSN:13430688)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.4, pp.4_433-4_452, 2022-10-01 (Released:2022-10-14)
- 参考文献数
- 33
This study aims to examine the structure of the corporal punishment-related factor and to explore predictors of corporal punishment behavior through a nationwide survey. A questionnaire survey was administered to teachers of athletic club activities working at Japanese junior high and high schools (337 valid responses from 39 prefectures) . Items of the corporal punishment-related factor scale, basic attributes, experiences of corporal punishment behavior, and experiences of feeling likely to use corporal punishment comprised the survey’s content. The scale’s items were scored from 1 to 5 points; the higher the scale score, the greater the awareness of the corporal punishment-related factor. An exploratory factor analysis (maximum likelihood method, Promax rotation) was conducted to examine factor structure. Covariance structure analysis was then conducted to examine the relationship between extracted corporal punishment–related factors and the experiences of corporal punishment behavior. (1) Results of factor analysis revealed 26 items associated with five factors: I) “teacher’s policy and beliefs”, Ⅱ) “unachieved goals of students and team”, Ⅲ) “teacher’s view of victory’s importance”, Ⅳ) “pressure to win the game” and V) “negative attitudes of students”. Reliability examination and Cronbach’s alpha coefficients confirmed the scale’s internal consistency. Additionally, subscale items’ factor loadings confirmed the simple structure, and factor validity was generally confirmed based on categories of corporal punishment–related factors from previous studies. (2) Results of analysis of covariance structure indicated that “teacherʼs policy and beliefs” and “teacher’s view of victory’s importance” might predict corporal punishment behavior. Additionally, this study found that pressure to win the game may be the cause of corporal punishment behavior. The results of this analysis could be used to assess corporal punishment–related factors that teachers perceive in athletic club activities.
- 著者
- 鈴木 太
- 出版者
- 一般社団法人 日本児童青年精神医学会
- 雑誌
- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.330-331, 2016-04-01 (Released:2019-08-21)
2 0 0 0 OA <断絶>と<連続>のせめぎ合い : 太宰治『パンドラの匣』論
- 著者
- 金 ヨンロン
- 出版者
- 日本近代文学会
- 雑誌
- 日本近代文学 (ISSN:05493749)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, pp.63-76, 2014-05-15 (Released:2017-06-01)
太宰治の『パンドラの匣』は、一九四五年一〇月二二日から翌年一月七日にかけて「河北新報」に連載された。連載の期間は、初期占領改革が行われる一方で、天皇制の維持、即ち象徴天皇制の成立への道を露呈する時期であった。まさに戦中から戦後へ、軍国主義の<断絶>と天皇制の<連続>の運動が同時進行しているこの時期、『パンドラの匣』は、「健康道場」というフィクショナルな空間を創造し、「玉音放送」が流れた一九四五年八月一五日を<断絶>として受け入れる青年に対して、戦後日本の思想を「天皇陛下万歳!」という叫びに求める<連続>の主張を突きつける様相を描いている。本稿では『パンドラの匣』における<断絶>と<連続>のせめぎ合いを同時代において捉え直すことで、その批評性を問う。その際、手紙の形式に注目し、共通の記憶を呼び起こす「あの」という空白の記号に日付という装置が加えられ、様々な同時代の文脈が喚起される過程を明らかにする。
2 0 0 0 OA 発達障害児の衝動性とセルフコントロール(<特集>選択行動研究の現在)
- 著者
- 嶋崎 まゆみ
- 出版者
- 一般社団法人 日本行動分析学会
- 雑誌
- 行動分析学研究 (ISSN:09138013)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1-2, pp.29-40, 1997-06-30 (Released:2017-06-28)
- 被引用文献数
- 1
セルフコントロールのパラダイムを用いた選択行動の研究は、近年動物や健常者の基礎研究が盛んに行われているが、発達障害児を対象とした研究はきわめて少ない。注意欠陥多動性障害および自閉性障害の子どもたちは、多動性と衝動性を主要な症状として持っている。したがって、そのような子どもたちの衝動性とセルフコントロールに関する実験的な研究は重要であろう。本稿では、それらの研究を次の2つの観点に基づいて概観した。すなわち、(1)衝動性の測定と評価に関する研究、(2)セルフコントロールの研究から得られた訓練手続きに関する研究である。さらに、発達障害児にセルフコントロールのパラダイムを適用する際の問題点について論議した。主な論点は、言語教示に関する問題、強化子の査定、満足の遅延パラダイムとの関係の3点であった。
2 0 0 0 OA 木材の光変色に及ぼす照射波長の影響
- 著者
- 山本 健 片岡 厚 古山 安之 松浦 力 木口 実
- 出版者
- 一般社団法人 日本木材学会
- 雑誌
- 木材学会誌 (ISSN:00214795)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.6, pp.320-326, 2007 (Released:2007-11-28)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 6 8
紫外線から可視光線(278~496 nm)を波長幅約20 nmに分光して6樹種の木材に照射し,照射光の波長と材の変色との関係を調べた。照射前のCIELAB色空間におけるL* 値が70以上,a*値が8未満の淡色材には,紫外域での暗・濃色化と,可視域での明・淡色化が見られた。厳密には,暗・濃色化と明・淡色化の境界波長は樹種によって異なり,針葉樹では,境界波長が広葉樹よりもやや長波長側に見られる傾向があった。一方,照射前のL* 値が70未満,a* 値が8以上の濃色材の変色パターンは複雑であったが,抽出処理後の照射では,淡色材の変色傾向にやや近づく傾向が見られた。照射前の木材の色調と分光照射による変色の関係について,照射前のL* 値が小さい材ほど短波長の光でL* 値が減少から増加に転じ,照射前のa* 値が大きい材ほど短波長でa* 値が増加から減少に転じる傾向があった。しかし,b* 値にはこのような関係は見られなかった。
2 0 0 0 OA 木材の光劣化とその深さ分析
- 著者
- 片岡 厚
- 出版者
- 一般社団法人 日本木材学会
- 雑誌
- 木材学会誌 (ISSN:00214795)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.4, pp.165-173, 2008-07-25 (Released:2008-07-28)
- 参考文献数
- 75
- 被引用文献数
- 9 12
光劣化は,木材が屋外で気象劣化する際のキープロセスである。また屋内でも変色などの問題を引き起こす。木材の光劣化は,基本的には表面反応であり,化学構造の変化は表層付近に留まるとされている。しかし,これまでに報告された木材の光劣化層の深さは,80μmから2540μmまで幅広い。木材が光劣化するメカニズムについて深さ分析による理解を深めることは,劣化しやすい木材の表層の部分を特定して,より効果的に耐光化処理する技術を開発するためにも重要である。本稿では,木材の光劣化に関わる基礎的な知見を概説するとともに,光劣化の深さ分析におけるこれまでの研究展開と理解の深まりを紹介する。
2 0 0 0 OA 近代小説のエクリチュールと主体 ――ロラン・バルト、安藤宏と田中実――
- 著者
- 李 勇華
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.8, pp.47-60, 2014-08-10 (Released:2019-08-30)
「言語論的転回」以後、書かれたものならば、なんでもエクリチュールとされるので、「近代小説のエクリチュール」という表現はトートロジーではないか。また、「作者の死」が宣告されたので、主体のことが語りうるのかと言われるが、その通りである。しかしそれはポストモダンの文学研究の枠組みであり、それを超えるには、主体のあらためての召還、他者を認め、自己否定を内包する書く行為のある近代小説が求められる。それが田中実の〈近代小説〉の特徴である。それを明らかにするために、本稿ではバルトの書こうとする「小説」と絡めて、安藤宏の〈表現機構〉と田中実の〈第三項〉を比較してみたい。
2 0 0 0 OA 流言研究の歴史とアプローチ
- 著者
- 木下 富雄
- 出版者
- 心理学評論刊行会
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.132-156, 1957 (Released:2023-03-16)
2 0 0 0 OA 薬剤師国家試験形式の試験成績の統計的分析によるグループ化および合否に影響する科目の検討
- 著者
- 弓削田 祥子 西丸 宏 加瀬 義夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本薬学教育学会
- 雑誌
- 薬学教育 (ISSN:24324124)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.2021-026, 2022 (Released:2022-03-31)
- 参考文献数
- 7
武蔵野大学薬学部6年生に対して実施した薬剤師国家試験と同形式の試験(9月~2月に計6回実施)における総合計および各科目の成績推移をグループ化できるかについて,3年間(2017–2019年度)のデータを用いたクラスター分析を行って検討した.その結果,総合計およびすべての科目について上位・中位・下位の3グループに分類することができたが,その構成人数は科目によって異なる傾向を示した.また,すべての科目について総合計との相関が見られた.ある時点の試験成績から薬剤師国家試験の合否に関して有意に影響がある科目を見いだせるかについて多重ロジスティック回帰分析で検討したところ,薬理など複数の科目で合否に影響がある可能性が示唆された.本研究は,各学生の早い時期の試験成績から,学習到達度の把握や今後の成績推移の見通しを予測し,国家試験対策における学生指導や学習方略の構築を検討する際に有用な知見となる可能性を示している.
2 0 0 0 OA ワニの筋学 : -古脊椎動物学者に必要な解剖- I.上顎,下顎
2 0 0 0 OA 地域・官署による簡牘形状の違い―敦煌漢簡「両行」簡を中心に―
- 著者
- 髙村 武幸
- 出版者
- 東洋文庫
- 雑誌
- 東洋学報 = Toyo Gakuho (ISSN:03869067)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, no.3, pp.1-35, 2022-12-16
It is widely known that there are “two-line” (lianghang 兩行) slips among bamboo and wooden slips from the Han period. Among these “two-line” slips dating from the second half of the Former Han and unearthed in the Hexi 河西 region, there exist two types: one type has a ridge down the centre of the writing surface which divides the two lines, while the other type has a flat surface with no ridge. However, in the past there has been no examination of this difference. In this article, I focus primarily on the “two-line” slips among the Dunhuang 敦煌 Han slips, unearthed in former Dunhuang Commandery in Hexi, and compare them with the “two-line” slips among the Juyan 居延 Han slips unearthed in former Zhangye 張掖 Commandery, also in Hexi. By this means, I clarify the fact that there exist various differences, starting with the shape of slips of the same type, between regions and government offices, and I also gain leads for adding further depth to research so that it extends to regional differences between slips. There was found a clear-cut difference between the Dunhuang Han slips, which include roughly the same number of “two-line” slips with a ridge and without a ridge, and the Juyan Han slips, which include almost no “two-line” slips with a ridge. In the case of the Xuanquan 懸泉 Han slips from Dunhuang, wood from the tamarisk (hongliu 紅柳; Tamarix ramosissima) is used in more than 70% of the “two-line” slips with ridges, and few of them have been made from spruce (song 松; Picea neoveitchii or Picea crassifolia), used in many of the “two-line” slips without a ridge. In addition, the “two-line” slips with ridges are narrower than those without a ridge. In view of these facts, it is to be surmised that in order to make effective use of the branches of the tamarisk, which, properly speaking, are unsuitable for making “two-line” slips because they are comparatively narrow, and produce “two-line” slips, the branches were processed in the same way as “two-line” bamboo slips so as to add ridges to them. It was for this reason that regional differences in shape arose among slips of the same type. When one examines the reasons for these differences, it is to be surmised that differences in regional conditions lay behind them. That is to say, the Juyan region belonged to Zhangye Commandery, where a transportation route had been established to the Qilian 祁連 Mountains where spruce suitable for making wide “two-line” slips were produced, whereas Dunhuang Commandery did not have a large supply of spruce because it was a long way from the Qilian Mountains and use could not be made of transportation by water or some other means.