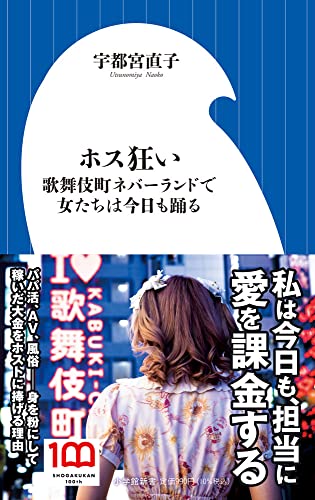- 著者
- Kosuke NISHI Ai KONDO Takeaki OKAMOTO Hiroyuki NAKANO Miho DAIFUKU Sogo NISHIMOTO Kenji OCHI Terumi TAKAOKA Takuya SUGAHARA
- 出版者
- Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry
- 雑誌
- Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry (ISSN:09168451)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.1, pp.40-46, 2011-01-23 (Released:2011-01-23)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 16
The water-soluble fraction of kale (Brassica oleracea L. var. acephala DC.) had immunoglobulin (Ig) production stimulating activity in human hybridoma HB4C5 cells and human peripheral blood lymphocytes. The biochemical and physical properties of the main active substance in kale were found to be a heat-stable protein with a molecular weight higher than 50 kDa. The Ig production-stimulating factors were assumed to act on the translational and/or secreting processes of Igs. This Ig production-stimulating effect was also observed in lymphocytes from the mesenteric lymph node and Peyer’s patches of mice that had been administered with the kale extract for 14 d. The partially purified kale extract was analyzed by LC-ESI-MS/MS, the result indicating ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase (rubisco) as an active substance. Rubisco from spinach indeed exhibited Ig production-stimulating activity in HB4C5 cells. These findings provide another beneficial aspect of kale as a health-promoting foodstuff.
2 0 0 0 OA Minecraftを用いたまちづくりワークショップの開発
- 著者
- 西 昭太朗 饗庭 伸
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.68, pp.430-435, 2022-02-20 (Released:2022-02-20)
- 参考文献数
- 12
The purpose of this paper is to develop of town planning workshop using Minecraft through clarifying reproduction, understanding spaces and discussion. The possibility of reproduction is Minecraft can reproduce the large scale. The problem is Minecraft cannot reproduce small scale. The possibility of understanding the space is participants can understand a city and buildings by using two viewpoints of overlook and the ground level. The problem is participants cannot understand the small scale. The possibility of discussion is discussions influence each other by adjusting with the facilitator. The problem is participants do not discuss to lose themselves in operating.
2 0 0 0 OA 畳み込みニューラルネットワークによるチンパンジーの個体識別
- 著者
- 池田 宥一郎 飯塚 博幸 山本 雅人
- 雑誌
- 2018年度人工知能学会全国大会(第32回)
- 巻号頁・発行日
- 2018-04-12
近年の情報科学の発展は,動物行動学の研究に大きく寄与している.我々は札幌市円山動物園において人工知能により動物を管理する負担の軽減を試みを行っている.我々の目標の1つは,健康管理と飼育環境の整備のためにチンパンジーのエソグラムを自動的に作成することである.エソグラムとはある特定の個体や種の全行動パターンの目録であり,動物の行動を研究するうえでもっとも基本的な記録である. エソグラムの作成には個体識別が必要があるため,本研究では画像認識分野で高い精度を出している畳み込みニューラルネットワークを用いて個々のチンパンジーを認識できるか検証した。 実験の結果,我々のシステムはチンパンジーの個体識別が可能であることを示した。
2 0 0 0 OA 1941―1945年の国民学校放送における幼児向け放送童話台本の研究
- 著者
- 中村 美和子
- 出版者
- Society for the Historical Studies of Early Childhood Education and Care in Japan
- 雑誌
- 幼児教育史研究 (ISSN:18815049)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.1-14, 2019 (Released:2020-03-25)
- 参考文献数
- 36
During the Asia-Pacific War (1941―1945), it was necessary for the Japanese people to listen to the radio in order to get information about the war. Radio programs for children were also presented during this period, popular since they were first broadcast by JOAK (Japan's oldest public broadcasting radio station) in 1925. This study aims to clarify the planning process and the content of ‘National School Hour' educational programs aired from April 1941 to March 1945, focusing on story programs for preschoolers. Materials of ‘National School Hour,' monthly radio textbooks and twenty-two scripts of story programs that were aired from June 1941 to January 1945 provided evidence for this analysis. The scripts had not been previously analyzed. Based on the result of this study, the following points are revealed: 1. The planning process 1) Programming was designed to be suitable for a pre-schooler's inner world, as discussed by the School Hour Committee composed of education experts and the JOAK production staff; and 2) To present monthly goals (from January 1942 to March 1943) designed to align with program themes, based on the guidelines for pre-schooler life determined by the School Hour Committee. 2. The content 1) There was a tendency for some scripts written from January 1942 to March 1943 to depend on the guideline of pre-schooler life; and 2) A tendency of the scripts of ‘National School Hour' in consideration of pre-schooler life, to focus on their play. The story programs were produced to emphasize normal pre-schooler life; however, there were some scripts that followed military national policy during the war years.
2 0 0 0 OA 建武式目解
- 巻号頁・発行日
- 1837
- 著者
- 駒澤 真由美
- 出版者
- 立命館大学大学院先端総合学術研究科
- 雑誌
- Core Ethics : コア・エシックス = Core Ethics : コア・エシックス (ISSN:18800467)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.59-71, 2019
- 著者
- 幡鎌 一弘
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.148, pp.331-356, 2008-12
本稿は、十七世紀中葉における吉田家の活動を、執奏、神道裁許状、行法、勧請・祈祷、神学の五つに分類し、それぞれの実態と相互の関係を検討しながら、神社条目によって吉田家の神職支配が確立していった際の問題点を明らかにしたものである。以下、三点を指摘した。第一に、幕府が寛文五年に神社条目を発布したとき、吉田家の地方神職への支配は確実に広がりをみせていたが、吉田家は幕府が想定するほど朝廷内での地位を持ち合わせていなかった。そのため、従来の研究史では、吉田家の地位を過大評価することになり、執奏をめぐる争論の理解を不十分なものにしていた。第二に、従来の研究では、吉田家と地方との関係について、執奏や神道裁許状の発給による支配関係、身分編成に眼を奪われ、吉田神道の行法の広がりについて、十分理解できていなかった。このため、吉田家と地方大社の複雑な関係について、分析する視点を持ち得なかった。第三に、吉田家の神学の停滞があらわになり、神社祭祀(裁許状・行法の伝受)への特化を決定付けたのは、神社条目が発布された直後に神学への欲求の高まったことと、その発布に力を尽した吉川惟足の活動(講釈という手法)が大きく影響していた。
2 0 0 0 マイルカ科鯨類における系統学的及び比較形態学的研究
2 0 0 0 OA 中国における気功活動の展開と法輪功事件
- 著者
- 浜 勝彦 Katsuhiko HAMA
- 出版者
- 創価大学文学部外国語学科中国語専攻
- 雑誌
- 創大中国論集 (ISSN:13440683)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.1-57, 2000-03-01
2 0 0 0 OA 最近英語問題集 : 解法ヒント附
2 0 0 0 OA 準拠情報的影響過程におけるGroup Polarization効果
- 著者
- 杉本 久美子
- 出版者
- The Japanese Group Dynamics Association
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.137-144, 2001-07-15 (Released:2010-06-04)
- 参考文献数
- 9
本研究では, 極化したプロトタイプに同調するという準拠情報的影響過程の立場から, Group Polarization (集団成極化: 以下GPと略す) の生起過程を明らかにすることを目的とした。プロトタイプは内集団の類似性と外集団との差異性を考慮したメタ・コントラスト比 (MCR) で規定される。内集団と外集団の態度が同質の場合には, 内集団の位置づけをより明確にしようとするためプロトタイプが極化し, そのプロトタイプに同調することでGPが生起する, また態度が異なる場合では方向性にかかわらず生起しないと仮説を立て, 実験検証を行った。外集団の態度は内集団と同質, 同方向だがより極端, 逆方向の3水準に設定し, VTRで操作した。VTRを呈示した後, 実験参加者に討論を行わせた結果, 仮説は支持される傾向を示した。また, 従来のGP研究の従属変数である態度変化量と本研究で用いた準拠情報的影響過程による同調との関連性を検討した結果, 外集団が同質な条件ではプロトタイプへの同調が生起し, 実際の態度変化も生起したことから, GPを準拠情報的影響過程で説明することの妥当性が示唆された。
2 0 0 0 OA 照明教室
- 著者
- 戸塚 博美 才治 勉 渡辺 賢亮 浅井 孝夫 杉山 春夫 石井 弘允
- 出版者
- 一般社団法人 照明学会
- 雑誌
- 照明学会雑誌 (ISSN:00192341)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.11, pp.598-626, 1974-11-25 (Released:2011-07-19)
2 0 0 0 ホス狂い : 歌舞伎町ネバーランドで女たちは今日も踊る
2 0 0 0 OA 大谷芳久とかんらん舎とは : 個人と社会の関係性からの考察
- 著者
- 藤岡 勇人
- 出版者
- 東京藝術大学美術学部
- 雑誌
- 東京藝術大学美術学部紀要 (ISSN:05638151)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.25-44, 2021-12-31
2 0 0 0 OA レボブピバカインの術後鎮痛における使い方
- 著者
- 髙畑 治
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.131-138, 2010-01-15 (Released:2010-02-19)
- 参考文献数
- 17
術後鎮痛法における硬膜外鎮痛法の役割について概説し, 新たに臨床導入されたレボブピバカインの特徴を述べた. レボブピバカインは, その長時間作用性とブピバカインに比較して運動神経遮断作用が軽減されていることから, 上腹部手術での有用性を検討した. レボブピバカイン単剤による硬膜外鎮痛では, 施行する椎間により下肢運動機能への影響が異なり, 上腹部手術症例では十分な鎮痛と下肢運動機能を維持することができた. このことは, 周術期における麻薬性鎮痛薬使用量を削減する可能性も意味している. 術後早期離床が重要視される上腹部手術において, レボブピバカインが硬膜外鎮痛薬として優れていることが示唆された.
2 0 0 0 OA 術後硬膜外PCAの実際
- 著者
- 小幡 典彦 溝渕 知司
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.5, pp.879-891, 2010 (Released:2010-12-24)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 1
術後痛対策として硬膜外鎮痛法は非常に効果的な方法であり,最近では術後の鎮痛だけでなく中長期的なアウトカムまで改善する可能性が示されている.硬膜外鎮痛の薬剤投与方法には,単回投与法,持続投与法および自己調節硬膜外投与法(自己調節硬膜外鎮痛 patient-controlled epidural analgesia:PCEA)があるが,PCEAは単回投与や持続投与のみに比べ,鎮痛の質や患者の満足度が高く,さまざまな専用デバイスも開発されたことにより,安全かつ確実に行われるようになっている.使用される薬剤は,局所麻酔薬とオピオイドが主体であり,現在では両者を併用することが一般的である.最も適した薬液の種類,濃度,投与方法などは,議論のある点で今後の更なる検討が必要であるが,硬膜外に投与するおのおのの薬剤の特性を知って使用する必要がある.
2 0 0 0 OA 外乱オブザーバによるロバスト・モーションコントロール
- 著者
- 大西 公平
- 出版者
- The Robotics Society of Japan
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.4, pp.486-493, 1993-05-15 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 82 220