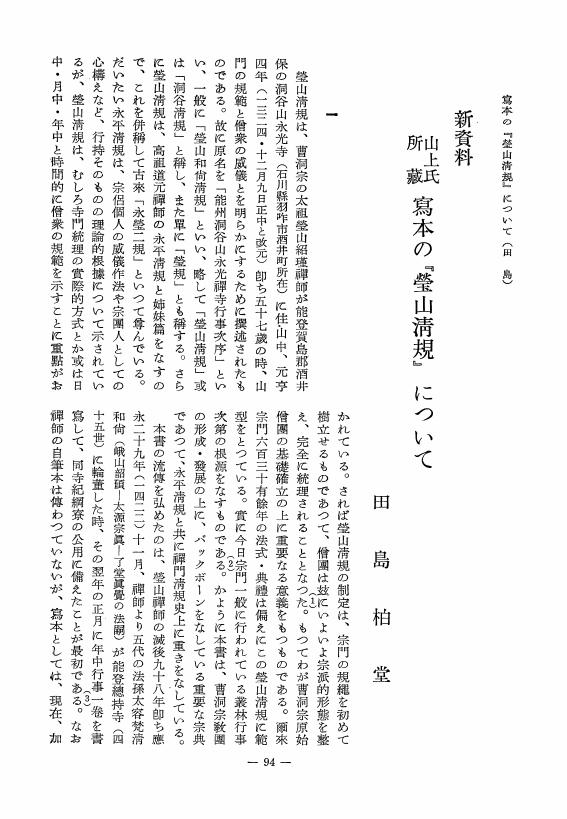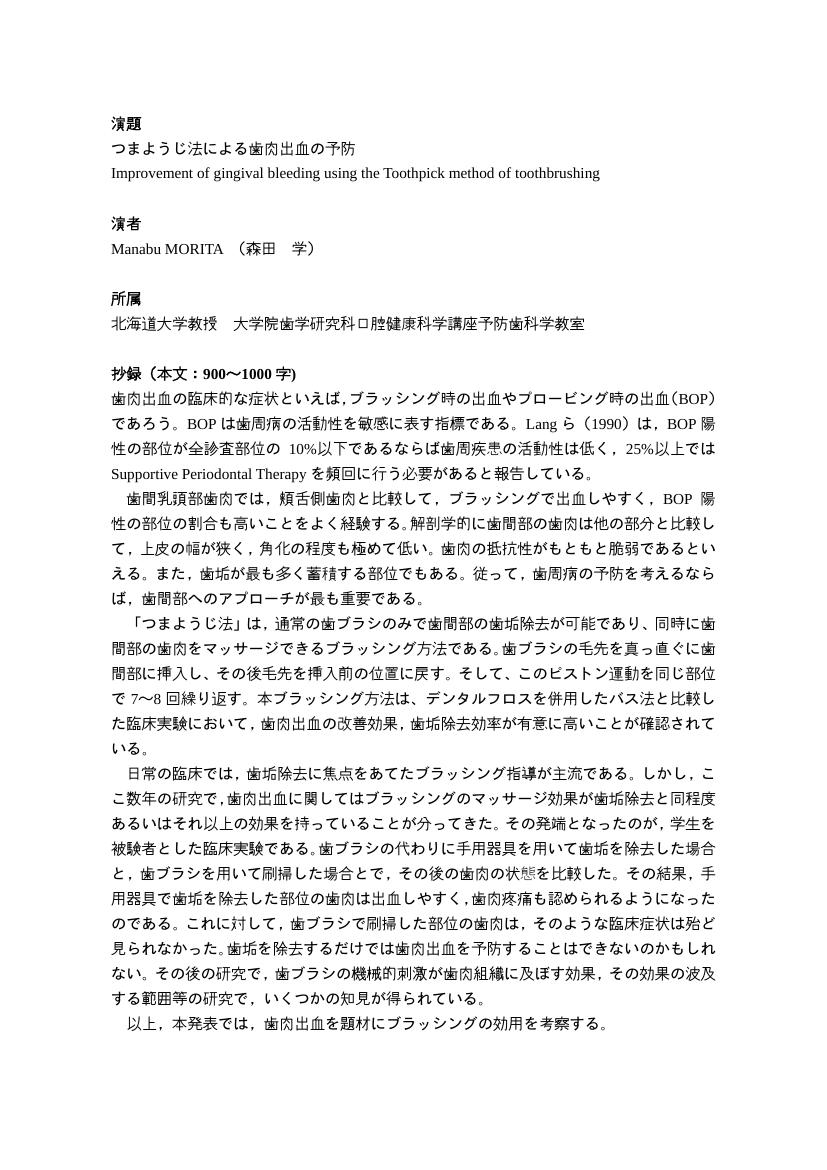- 著者
- Tomohiro Sugino Sayaka Aoyagi Tomoko Shirai Yoshitaka Kajimoto Osami Kajimoto
- 出版者
- SOCIETY FOR FREE RADICAL RESEARCH JAPAN
- 雑誌
- Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition (ISSN:09120009)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.3, pp.224-230, 2007 (Released:2007-10-30)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 17 24
We examined the effects of citric acid and L-carnitine administration on physical fatigue. In a double-blind, placebo-controlled, 3-way crossover study, 18 healthy volunteers were randomized to oral citric acid (2,700 mg/day), L-carnitine (1,000 mg/day), or placebo for 8 days. The fatigue-inducing physical task consisted of workload trials on a cycle ergometer at fixed workloads for 2 h on 2 occasions. Before the physical load, salivary chromogranin A, measured as a physiological stress marker, was lower in the group given citric acid than in the group given placebo. Also, after the physical load, the subjective feeling of fatigue assessed with a visual analogue scale was lower in the citric acid group than in the placebo group. In contrast, L-carnitine had no effect on chromogranin A or subjective fatigue. These results suggest that citric acid reduces physiological stress and attenuates physical fatigue, whereas L-carnitine does not.
2 0 0 0 OA 山上氏所藏寫本の『瑩山清規』について
- 著者
- 田島 柏堂
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.94-104, 1958-12-01 (Released:2010-03-09)
2 0 0 0 OA 色の傾向性理論を擁護する ――色の現象学と存在論――
- 著者
- 小草 泰
- 出版者
- 科学基礎論学会
- 雑誌
- 科学基礎論研究 (ISSN:00227668)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1-2, pp.1-21, 2018 (Released:2018-05-07)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1
Dispositionalism of color claims that colors are dispositions to cause certain sorts of visual experiences in perceivers. Lately, this theory has been criticized as conflicting with the phenomenology of color experiences. Critics insist that our visual experiences represent colors not as dispositional properties, but as simple, monadic, intrinsic features of physical objects, and that this poses a serious threat to dispositionalism. First, I will examine four versions of this kind of objection and defend dispositionalism against them. Second, based on these considerations, I will explicate the notion of ‘certain sorts of visual experiences' that dispositionalists refer to. More specifically, I will offer a promising view of color experiences through examining the phenomenon of color constancy.
- 著者
- 藤谷 拓嗣
- 出版者
- 日本微生物生態学会
- 雑誌
- 日本微生物生態学会誌 (ISSN:24241989)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.8-11, 2010-03-01 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 13
2 0 0 0 OA 宗教結社、権力と植民地支配 : 「満州国」における宗教結社の統合
- 著者
- 孫 江
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.163-199, 2002-02-28
一九三二年三月一日、関東軍によって作られた傀儡国家「満州国」が中華民国の東北地域に現れた。本稿で取り上げる満州の宗教結社在家裡(青幇)と紅卍字会は、いずれも満州社会に深く根を下ろし、「満州国」の政治統合のプロセスにおいて重要な位置を占めていた。
2 0 0 0 OA 機能性食品成分ペクチンによるアレルギー応答調節機構の解明と治療への応用
近年,食物アレルギーの患者数は増加しており,その症状を緩和する食品成分が切望されている。水溶性食物繊維であるペクチンはアレルギー応答を調節する食品成分であることが示唆されている。しかしながら,その効果や機序など不明な点が多い。本研究では,ペクチンを食物アレルギーモデルマウスに摂取させ,予防および治療効果を調査した。その結果,ペクチン摂取により血中IgG1濃度とアレルゲン特異的抗体価の上昇が抑制され,アレルギー性の下痢症状が緩和されることが判明した。ペクチンは抗原提示細胞に作用することでアレルギー性の炎症を抑制している可能性が示唆された。
2 0 0 0 OA 倭訓栞
- 著者
- 谷川士清 纂
- 出版者
- 篠田伊十郎 [ほか4名]
- 巻号頁・発行日
- vol.[15], 1830
2 0 0 0 OA 海外だより ~韓国の淸州より~
- 著者
- 李 映昊
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.204-205, 2022 (Released:2022-07-25)
2 0 0 0 OA われらが内なる実証主義バイアス
- 著者
- 沼上 幹
- 出版者
- 特定非営利活動法人 組織学会
- 雑誌
- 組織科学 (ISSN:02869713)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.32-44, 2000 (Released:2022-07-27)
本稿はまず合理主義と経験主義の対立を明らかにし,本来,その両者が相互に影響を及ぼしあって社会システムに関する認識の地平が拡大していくことを主張する.その上で近年の経営学的研究の見取り図を作成し,〈極端な実証主義〉的バイアスの位置づけを明確にする.さらに,そのバイアスの源泉あるいは促進要因として,①経営学研究に関する存在論・認識論的な見取り図の欠如,②文献研究否定運動,③経済学者の経営学領域への侵入,④大学院大学化が指摘される.
- 著者
- Hiroki Mizuno Naoki Sawa Akinari Sekine Noriko Inoue Yuki Oba Daisuke Ikuma Masayuki Yamanouchi Eiko Hasegawa Tatsuya Suwabe Hisanori Suzuki Junichi Hoshino Yoshifumi Ubara
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- pp.9624-22, (Released:2022-05-31)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
A 79-year-old man was admitted with a compression fracture of the first lumbar vertebra. His alkaline phosphatase (ALP) level was 35 IU/L, and his dual energy X-ray absorptiometry T score was -3.7 standard deviations, indicating osteoporosis. A genetic analysis showed a mutation of the alkaline phosphatase biomineralization-associated gene encoding tissue-nonspecific alkaline phosphatase. Hypophosphatasia-related osteoporosis was diagnosed. Alendronate, teriparatide, and minodronate were administered in that order. The ALP level increased during teriparatide use. A bone biopsy performed after three years of teriparatide treatment showed that cancellous bone was adynamic. In cortical bone, tetracycline double-labeling indicates enhanced bone formation. Teriparatide may thus be a viable treatment option even in patients with hypophosphatasia.
2 0 0 0 IR 「歴史学から見た内陸文化研究」 (内陸文化研究会報告)
- 著者
- 笹本 正治
- 出版者
- 信州大学
- 雑誌
- 内陸文化研究 (ISSN:13464108)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.39-60, 2001-03
2 0 0 0 OA 医学的観点から見た高齢者の定義
- 著者
- 大内 尉義 Yasuyoshi OUCHI
- 出版者
- 国立社会保障・人口問題研究所
- 雑誌
- 社会保障研究 = Journal of Social Security Research (ISSN:03873064)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.5-16, 2022-06
特集論文
2 0 0 0 OA 「柔道整復師」序論Ⅰ ― 柔道整復師の起源と歴史 ―
2 0 0 0 OA とろみ液の簡易評価法としてのシリンジテストの検証
- 著者
- 佐藤 光絵 山縣 誉志江 栢下 淳
- 出版者
- 一般社団法人 日本摂食嚥下リハビリテーション学会
- 雑誌
- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会雑誌 (ISSN:13438441)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.102-113, 2021-08-31 (Released:2021-12-31)
- 参考文献数
- 24
【目的】嚥下調整食学会分類2013 推奨のとろみ液の簡易評価法であるLine Spread Test(LST)は,溶媒や増粘剤の種類によっては正しく粘度評価できないと報告されている.一方,International Dysphagia Diet Standardisation Initiative(IDDSI)推奨のシリンジテストを検証した報告は少ない.本研究は,シリンジの種類による誤差の検証,溶媒の種類による影響の検証,およびLST との比較を目的とした.【方法】試料は,ずり速度50 s-1 における粘度が50,150,300,500 mPa・s 程度になるよう,とろみ調整食品で粘度調整した.試験1:水と経腸栄養剤をキサンタンガム系,デンプン系のとろみ調整食品でとろみ付けし,3社(BD, TERUMO, JMS)のシリンジを用いてテストを行った.また,BDの結果より検量線を作成し,各シリンジテストの残留量より粘度を推計,誤差を検証した.試験2:水,食塩水,お茶,オレンジジュース,経腸栄養剤をキサンタンガム系とろみ調整食品でとろみ付けし,シリンジテストを行った.試験3:水と経腸栄養剤をキサンタンガム系とろみ調整食品でとろみ付けし,シリンジテストとLSTを行った.【結果と考察】試験1:シリンジの種類により残留量が変化したが,BD のシリンジテストの検量線を用いてTERUMO・JMS の残留量より粘度を推計したところ,全試料の約8 割は粘度との差が10% 未満で,現実的に問題は少ないと思われた.試験2:お茶とオレンジジュースは水と同様の残留量となった.経腸栄養剤は残留量が他の溶媒より少ない傾向があり,食塩水はばらつきが大きかった.経腸栄養剤は実際の粘度より薄く評価しやすいこと,食塩水はテスト値が不安定であることに注意を要すると思われた.試験 3:LST は経腸栄養剤の全試料において,低粘度の水よりLST 値が高くなることがあった.シリンジテストは,LST でみられたような順位の逆転が粘度の高い領域のみでみられた.薄いとろみに関しては粘度の分類に矛盾がない点において,シリンジテストはLST よりとろみ液の簡易評価法として優れていると考えられた.
2 0 0 0 OA 近世後期上方語と名古屋方言をめぐって : 形容詞「どえらい」を中心に
- 著者
- 増井 典夫
- 出版者
- 愛知淑徳大学国文学会
- 雑誌
- 愛知淑徳大学国語国文 (ISSN:03867307)
- 巻号頁・発行日
- no.24, pp.43-57, 2001-03-20
2 0 0 0 OA 三重・愛知・岐阜県境地域の言語使用と言語意識
2 0 0 0 OA 建築構造物の過去・現在・未来
- 著者
- 中根 淳
- 出版者
- 公益社団法人 日本コンクリート工学会
- 雑誌
- コンクリート工学 (ISSN:03871061)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.23-27, 1999-01-01 (Released:2013-04-26)
- 参考文献数
- 6
2 0 0 0 OA PC 用日本語版アイオワギャンブル課題の開発と英語版との同等性
- 著者
- 遊間 義一 金澤 雄一郎 河原 哲雄 東條 真希 荻原 彩佳 石田 祥子
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- pp.93.20232, (Released:2022-02-10)
- 参考文献数
- 28
This study aimed to develop a Japanese version of the Iowa Gambling Task (IGT) using Psychology Experiment Building Language based on the English version. Additionally, we tested the equivalence of these versions using a biological equivalence test. We randomly assigned 63 undergraduate and graduate students from several Japanese universities to our parallel design experiment. We evaluated equivalence by determining differences between the logs of the number of cards chosen from the advantageous decks in the Japanese and English versions in five blocks. We defined an equivalence margin as ± 30% (log (0.70 = -0.36, log (1/0.70) = 0.36, for log-transformation). All two-sided 90% family-wise confidence intervals in the five blocks were within the equivalence margin. Our results confirmed the equivalence of the Japanese and English versions of the IGT. The Japanese version can be used with the compiled executables and source code without charge. Future comparative studies should evaluate the IGT on Japanese samples or between samples from Japan and other countries.
2 0 0 0 OA つまようじ法による歯肉出血の予防
- 著者
- 森田 学
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本歯周病学会
- 雑誌
- 特定非営利活動法人 日本歯周病学会学術大会 プログラムおよび講演抄録集 日本歯周病学会50周年記念大会プログラムおよび講演抄録集
- 巻号頁・発行日
- pp.174, 2007 (Released:2007-08-31)
2 0 0 0 OA 19世紀のアイヌ社会における和名化の展開過程
- 著者
- 遠藤 匡俊
- 出版者
- 社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地學雜誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.113, no.3, pp.421-424, 2004-01-01
蝦夷地は2度にわたり幕府の直轄地となり,アイヌの風俗・習慣を和人風に変えるという同化政策が実施された。この同化政策によって,アイヌの個人名がアイヌ名(アイヌ語の名)から和名(日本語の名)に改名される和名化が生じた。これまで和名化は,幕府の同化政策によってアイヌ文化が変容する事例として注目されてきた。また,アイヌ社会には「近所に生きている人と同じ名をつけない」という個人名の命名規則が存在していた。個人名の命名にあたって,文字をもたなかったアイヌは,周囲の人々の名を思い浮かべて,同じ名とはならないように配慮したものと考えられる。しかし,従来の研究では,和名化の展開過程は明確ではなく,和名化と命名規則の関係についても必ずしも明確ではなかった。本研究の目的は,アイヌ社会における和名化の展開過程を示した上で,和名化と命名規則の関係について検討することである。