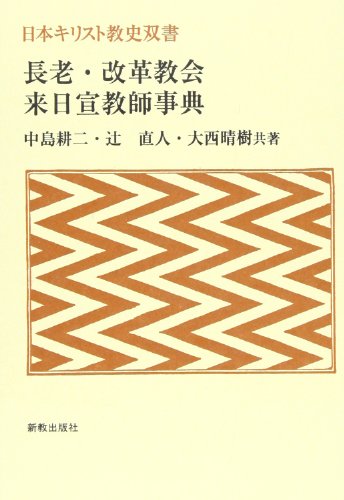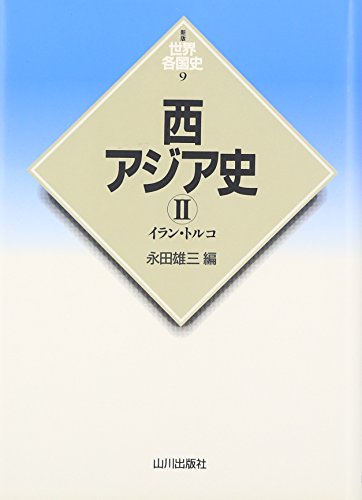2 0 0 0 長老・改革教会来日宣教師事典
- 著者
- 中島耕二 辻直人 大西晴樹共著
- 出版者
- 新教出版社
- 巻号頁・発行日
- 2003
2 0 0 0 OA 鼻副鼻腔疾患におけるビタミンE代謝に関する研究
- 著者
- 賀来 美寛
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.2, pp.182-201, 1970 (Released:2007-06-29)
- 参考文献数
- 101
- 被引用文献数
- 2
鼻副鼻腔疾患に栄養が大きく影響していることはすでに知られているが, ビタミンE (以下Eと略す) は近年多くの研究がなされているにもかかわらず, 耳鼻咽喉科領域での基礎的系統的研究は皆無といつてよく, そこでまず萎縮性鼻炎, 血管神経性鼻炎, 慢性副鼻腔炎, 肥厚性鼻炎の患者につき正常者を対照として血清中E量を測定し, 又全例にE負荷後血中値を測定した.最も低値を示したのは萎縮性鼻炎であり, Eとその病態成立が最も密接な関係にあると思われたが, 血管神経性鼻炎, 慢性副鼻腔炎においても正常者より低値を示し, 何らかの関連は否定出来ないと推考した.次に慢性副鼻腔炎の上顎洞粘膜につき病型別にE量を測定し, 又正常家兎及び実験的副鼻腔炎を惹起した家兎副鼻腔粘膜を螢光法による組織化学的検索及びミクロラジオオートグラフイにより観察した所, E定量では線維型は浮腫型, 化膿型に比し低値を示したが, E負荷による変動はいずれの型にもほとんど認められなかつた. 螢光法ではEはわずかに上皮, 腺に認められたが正常粘膜と病的粘膜の間に螢光の差は認められず, Eの負荷による螢光の増加も認められなかつた. オートラジオグラムでは上皮, 腺にグレインが観察された.さらに実験的E欠乏家兎の鼻粘膜を全身諸臓器と共に病理紹織学的に検索した所, 全身臓器ではすでに報告されている如き変化を得, 鼻粘膜では短期欠乏群で萎縮変性がみられ, 長期欠乏群では萎縮性が強く, 慢性炎症性所見がみられ, 純然たるE欠乏のみによる変化と断定は出来ないにしてもE欠乏により鼻粘膜にも病的変化を来す事は疑いないと断定した.
- 著者
- 李 明 石丸 紀興
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.610, pp.221-227, 2006-12-30 (Released:2017-02-17)
This paper focuses on Akira UENAMI's architectural design of the Telephone Exchange Branch of Hiroshima Post Office built in 1928 and Hiroshima Posts and Telecommunications Office built in 1933. We try to concern real images of design activities by Akira UENAMI. In addition, this paper is consisted of 3 chapters as follows; 1) It focuses on various design activities by Akira UENAMI as a staff of the Ministry of Posts and Telecommunications. 2) It points out relations on Akira UENAMI and two buildings designed by him, Telephone Exchange Branch of Hiroshima Post Office and Hiroshima Posts and Telecommunications Office. 3) It clarifies tendency of his works comparing with the characteristics of typical buildings of the Ministry of Posts and Telecommunications.
- 著者
- Haipeng Fu Yipeng Mu Xin Zhang
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- IEICE Electronics Express (ISSN:13492543)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.14, pp.20220241, 2022-07-25 (Released:2022-07-25)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 2
A 2.58THz detector based on plasma-wave theory proposed by Dyakonov and Shur was designed and fabricated in 55nm standard CMOS process. Each detector consists of a filter patch antenna and a metal-oxide-semiconductor field-effect-transistor (MOSFET). We design a filter antenna to receive the terahertz signal, and the output of detector is extracted by a phase-locked amplifier. The antenna generates filtering function by adding two pairs of branches to the feeding lines. The frequency selection function of high spectral resolution detector proposed in this paper is mainly realized by filtering antenna. According to the test results and HFSS simulation results, the proposed filter antenna is feasible. The detector can achieve a room-temperature maximum responsivity (RV) of 67.2V/W. Our results show that CMOS terahertz detectors have potential applications in the imaging field.
2 0 0 0 OA 通信ネットワークインフラを支える新ノードシステムの開発
- 著者
- 鈴木 滋彦
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン (ISSN:21860661)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.122-130, 2017-09-01 (Released:2017-09-01)
- 参考文献数
- 16
2 0 0 0 OA 北カリフォルニアにおける日系人花卉栽培の形成
- 著者
- 矢ヶ崎 典隆
- 出版者
- Tokyo Geographical Society
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.3, pp.149-166, 1980-06-25 (Released:2010-10-13)
- 参考文献数
- 76
Japanese immigrant agriculturists on the west coast of the United States in the pre-World War II period enjoyed a highly competitive position with their small but labor intensive operations even under social conditions that often discouraged their activities. One of the biggest factors in their competitive success in agriculture was their organizational effectiveness. Ethnic solidarity was maintained by first generation immigrants of most ethnic backgrounds both in fraternal and economic activities and they tended to cluster geographically and by occupation. But the Japanese agriculturists developed especially tight and efficient organizations to meet special needs and to protect themselves in this new and unaccustomed environment.The present paper describes and analyzes the development of Japanese floriculture in the San Francisco Bay Area from its beginnings in the late nineteenth century to the World War II relocation of the Japanese, with special emphasis on grower organizations as a key factor in their success.The early pioneering efforts and success of the immigrants, who were mostly of rural background, invited the participation of other Japanese in commercial flower production. The mild climatic conditions of the Bay Area, especially the absense of temperature extremes, were favorable for cut flower production, and the rapidly growing population created an increasing demand. Although two other ethnic groups, Italians and Chinese, were already in the business when the Japanese first started to grow flowers commercially, the industry itself was not fully organized. The Japanese thus moved into a niche that was waiting to be filled.In the early period the Japanese flower growers were mainly located in the East Bay region, producing carnations, roses and chrysanthemums in greenhouses. Marketing of flowers was undertaken on an individual basis, peddling them from wicker or bamboo baskets carried on the back or by opening flower stands on busy streets, which was generally inefficient and time consuming. As the number of growers increased and production expanded, intense competition developed among them. Gradually they became aware of a need for their own trade organization and marketing facility.
2 0 0 0 IR 国民的歴史学運動における「国民」化の位相--加藤文三「石間をわるしぶき」を手がかりとして
- 著者
- 小国 喜弘
- 出版者
- 東京都立大学人文学部
- 雑誌
- 人文学報 (ISSN:03868729)
- 巻号頁・発行日
- no.327, pp.47-72, 2002-03
- 著者
- 箸野 照昌 田中 寿美玲 野口 愛天 峯元 愛 園中 智貴 徳田 佳秀 山畑 雅翔 内田 海聖 大城 新秀 畑島 康史 吉盛 巧人 園田 倭可 谷口 大介 兎澤 瑛太郎
- 雑誌
- JpGU-AGU Joint Meeting 2020
- 巻号頁・発行日
- 2020-03-13
研究の動機 過去4年間「関口日記」「二條家内々御番所日次記」「妙法院日次記」「守屋舎人日帳」「弘前藩庁日記」に記述された天気を分析した。 そこで、今年は「鶴村日記」を分析した。「鶴村日記」とは、江戸時代の石川県の儒学者、金子鶴村が書き残した1801年(文化4年)から1838年(天保9年)までの災害、文化、生活等の記録である。 研究の目的(1)過年度に調べた「関口日記」「二條家内々御番所日次記」「妙法院日次記」「守屋舎人日帳」「弘前藩庁日記」と合わせてデータベースを作る。(2)インドネシアのタンボラ火山の1812年からの噴火の影響で「夏のない年」と言われた1816年と、天保の飢饉で一番被害が苛烈であった1836年を比較検証する。 研究の方法 天気は現在の気象庁の分類に近づけて、雪>雨>曇>晴れと判別した。1年の1/3の欠測のある年は集計から削除した。ただし、1836年を検討する際は、欠測のない5月~7月、及び9月のみデータを使った。 取得したデータは21年間で、7,148日だった。 データ1 鶴村日記の天気の全期間の出現率と、タンボラ火山の噴火を含む期間である1812年から1816年を算出した。火山の噴火期間は晴れの出現率が低下し、雨の出現率が上昇していることが分かった。 また、1836年の天保の大飢饉においてはさらに晴れの出現率が低下し、雨の出現率が大幅に増えたことが分かる。 データ2 1808~1832年の天気の出現率を季節ごとにグラフにすると、タンボラ火山の噴火の続く、夏の期間の雨の出現率が晴れの出現率を上回っていることがわかる。 データ3 4つの古文書で1816年と1836年の5月から9月の天気を比べると、7月の曇りの出現率が高いことが共通している。 1816年と1836年の違いは、1816年の8月の晴れの出現率の持ち直しが顕著である。 データ4 雷の発生率を四季でみると、1816年の夏の雷は前後の年に比べて減少している。一方、秋は1816年が一番高く、大陸からの季節風の影響の可能性が高い。 データ5 国立情報学研究所の市野美夏さんの論文を参考に天気階級と全天日射量を計算して比較した。市野さんの論文に倣い、日記天気階級は(1)晴れ、(2)曇り、(3)雨天・雪の3つに分類した。そして、現代の気象庁データの平均から得られた地上の全天日射量Qd、地理的データ及び天候から得られるQsを使い、qを求める。 qは地球上にそそぐ太陽のエネルギーの減衰する割合を表している。 求めたQsと天気階級の積を平均したものがQeである。このQeを平年値と比較する。 古文書の天候の情報から毎年の全天日射量に換算し、複数年で比較したのがグラフ6で、1816年、1836年のいずれも1821年から1850年の平均値より低い量になっている。つまり、この2年に関しては、年間通して、全天日射量が低く、寒い時期が続き、農作物などへの影響があったことが読み取れる。 考察(1)データ1のように、タンボラ火山の噴火活動期の1812年~1816年の晴れの出現率は36.12%で、全期間より1.88%低いことから、日照時間が低下し気温も低かった可能性がある。 さらに、データ2から、1816年は鶴村日記の夏から冬において、雨の出現率が晴れの出現率を上回る。夏や秋の気温が上昇しない年だったと考えられる。(2)天保の飢饉は特に東北の冷害が深刻だったとされるが、調査した古文書の緯度があがるにつれて1816年と1836年の晴れの出現率の差が大きいことがわかった。(3)鶴村日記において、 1821年から1850年までの全天日射量の平均と、1816年と1836年の夏の全天日射量を比較すると、両年とも通年で全天日射量が低いことから、気温も低下していたことを示唆する。 まとめ(1) 「鶴村日記」のタンボラ火山の噴火活動期の晴れの出現率は36.31%で、全期間より1.71%低く、日照時間が低下し気温も低下した可能性がある。(2) 天保の飢饉は特に東北の冷害が深刻だったとされるが、古文書の書かれた地点の緯度が上がるにつれて、1816年と1836年の晴れの出現率の差が大きくなっていく。(3)「鶴村日記」の全天日射量をみると、1816年、1836年のいずれも1821年から1850年の平均値より低い量になっていた。 つまり、この2年に関しては、年間通して、全天日射量が低く、寒い時期が続いたことがわかる。 今後の課題 「鯖江藩日記」(福井)をデータ化してデータベースを作り、気象変動を調べて、本年までの分析を裏づけるとともに、オリジナルな全天日射量の計算式を作り、江戸時代の日射量を算出する。
2 0 0 0 OA 死体遺棄罪と不作為犯
- 著者
- 松尾 誠紀 Motonori Matsuo
- 雑誌
- 法と政治 = The journal of law & politics (ISSN:02880709)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.75-104, 2017-05-30
2 0 0 0 OA 仙台市内河川敷にみるネズミ分布相の特性-広東住血線虫や紅斑熱感染環との絡み-
- 著者
- 高田 伸弘 藤田 博己 安藤 秀二 川端 寛樹 矢野 泰弘 高野 愛 岸本 壽男
- 出版者
- 日本衛生動物学会
- 雑誌
- 日本衛生動物学会全国大会要旨抄録集 第61回日本衛生動物学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.22, 2009 (Released:2009-06-19)
昨2008年7月に, 仙台市内東半部を貫流する小河川の梅田川堤防で散歩を日課とした住民が紅斑熱を発症, 特異的検査で北アジア共通Rickettsia heilongjiangensis(Rhj)の感染が強く示唆されたため, 同地区のネズミ相やマダニ相など感染環の調査を行った.同年9, 12月および本年1月の現地踏査では, まず, 梅田川中流堤防ではドブネズミおよびハタネズミの2種しか得られなかったが, ドブネズミそして植生から得られた北方系チマダニ種からRhjが高率に証明され, 同時にドブネズミ1頭の肺からは好酸球性髄膜脳炎起因性の幼虫移行症として注目される広東住血線虫Angiostrongylus cantonensis(Ac)の生虫体が見出された.梅田川がじきに七北田川に注ぐ地点の堤防では何故かネズミは捕れなかったが, 続く下流の仙台港近い河川敷ではようやくアカネズミが見出され, 一部は紅斑熱抗体を保有, またフトゲツツガムシの寄生もみた.以上から本地区のネズミ相の特性として, 梅田川周辺は市街化まもなくて郊外要素も残るに関わらず全国的普通種アカネズミが不在または超希薄という近年では稀な環境であるらしいこと, しかしそこではハタネズミと共存するドブネズミがAc(おそらく東京圏と北海道の間の東北地方では初記録)の感染環を維持し, 同時にRhj媒介チマダニ幼若期の吸血源にもなっているらしいことが挙げられる.とは言え, 重要な病原体の感染環が, 概ね密度は高くないネズミ相の中で如何に維持されているものか, 詳細な調査によって検証する必要があり, 2~3月には市内を貫流する広瀬川や名取川地区でも比較調査を予定しているので, 結果を合わせ報告する. 本調査は2008年度厚労科研(略題:リケッチア症の実態調査と警鐘システム構築)によった.<研究協力者:岩崎恵美子(仙台市副市長), 広島紀以子ほか(同市衛研)の各位>
2 0 0 0 OA 宗教法人法の構造とその問題点
- 著者
- 櫻井 圀郎
- 雑誌
- キリストと世界 : 東京基督教大学紀要 = Christ and the world
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.114-136, 1997-03-01
2 0 0 0 OA モンゴル遊牧民の夏の食に関する調査
- 著者
- 石井 智美 鮫島 邦彦
- 出版者
- The Japan Society of Home Economics
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.8, pp.845-853, 1999-08-15 (Released:2010-03-10)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1
A dietary survey on the nutritional intake of the Mongolian Gel tribe was conducted while living with the tribe from June to July in 1997. The traditional Mongolian diet consists mainly of dairy products in the summer and meat in the winter, supplemented by flour. The meals are of a very simple style, with five of the nine main dishes being dairy products which are consumed almost daily. The average energy intake for a householdhead is around 2, 200 kcal, which is just sufficient for health maintenance. Dairy products account for 48% of the total energy intake and 40% of the total protein intake. Although the use of flour in the summer diet is thought to ensure an adequate dairy energy intake, flour is also thought to lead to an increase in salt intake. Lactose in dairy products, and collagen in meat both help to make up for the lack of vegetables in the Mongolian diet, while vitamin C is provided by the consumption of internal organs and blood, as well as by-kumiss. The Gel tribe are therefore able to effectively obtain sufficient by utilizing all of the available foodstuffs.
2 0 0 0 OA 刑法と感情 ―感情による法的判断の正当化―
- 著者
- 原 塑
- 出版者
- 日本感情心理学会
- 雑誌
- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.49-54, 2014-02-01 (Released:2014-06-04)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 2
On May 2009, laws came into force in Japan to enable citizen participation by introducing lay judges in criminal courts. Lay judges, who are randomly selected out of the electoral register, comprise the majority of the judicial panel to help decide the outcome in trials for certain severe crimes. To make their own judicial decisions, lay judges must rely heavily on moral intuitions that are often driven by emotions, due to the lack of judicial expertise. Under what conditions can lay judges, guided by their emotions, come to reasonable decisions? What is the definition of rational emotions capable of guiding reasonable judicial decisions? These questions must be answered to make the lay judge system feasible. Recently, Martha C. Nussbaum, together with Dan M. Kahan, has developed a theory of emotion-based criminal judgment. In this paper I am going to answer above questions relying on Nussbaum’s theory of emotional judgments.
2 0 0 0 OA 遠隔授業におけるADHD のある学生への合理的配慮 : 本学の現状と課題を中心として
- 著者
- 黄 淵煕
- 出版者
- 東北福祉大学教育・教職センター特別支援教育研究室
- 雑誌
- 東北福祉大学教育・教職センター特別支援教育研究年報 (ISSN:21850275)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.3-10, 2021-03-31
遠隔授業の実施に伴って相談需要が増加したADHDのある学生の支援を中心に、相談件数及び相談内容の現状についてまとめた。また、相談内容に対して本学で行った支援について、他大学の支援を参考にしながら、今後の課題について考察した。
2 0 0 0 OA 雇用分野のジェンダー不平等はなぜ解消されないのか
- 著者
- 浅倉 むつ子
- 出版者
- 日本法社会学会
- 雑誌
- 法社会学 (ISSN:04376161)
- 巻号頁・発行日
- vol.2016, no.82, pp.81-92, 2016 (Released:2021-05-05)
Despite the thirty years of the implement of the Equal Employment Opportunity Act, gender inequality in employment still remains unsolved. The primary factor of the gender inequality in employment in Japan is the deep-seated stereotyped roles for men and women in Japanese society. Child rearing and household affairs are largely regarded as women’s duties and about 60 percent of female workforce retires for childbearing. The second factor is corporate systems and customs deeply rooted in Japanese business community, which are only superficially gender-neutral. For instance, assessment standards of typical wage systems include subjective criteria that are susceptible to gender views of assessors, e.g. “enthusiasm,” “cooperativeness” and “tractability.” This article analyzes the current status of the doctrine of leading cases in relation to gender inequality in Japan, and proposes development of a framework to enhance the effectiveness of anti-discriminatory legislation, an efficient working- hour law to reduce long working hours of male labor force, and a system to apply the principle of equal pay for equal value work to the norms of lawsuit.