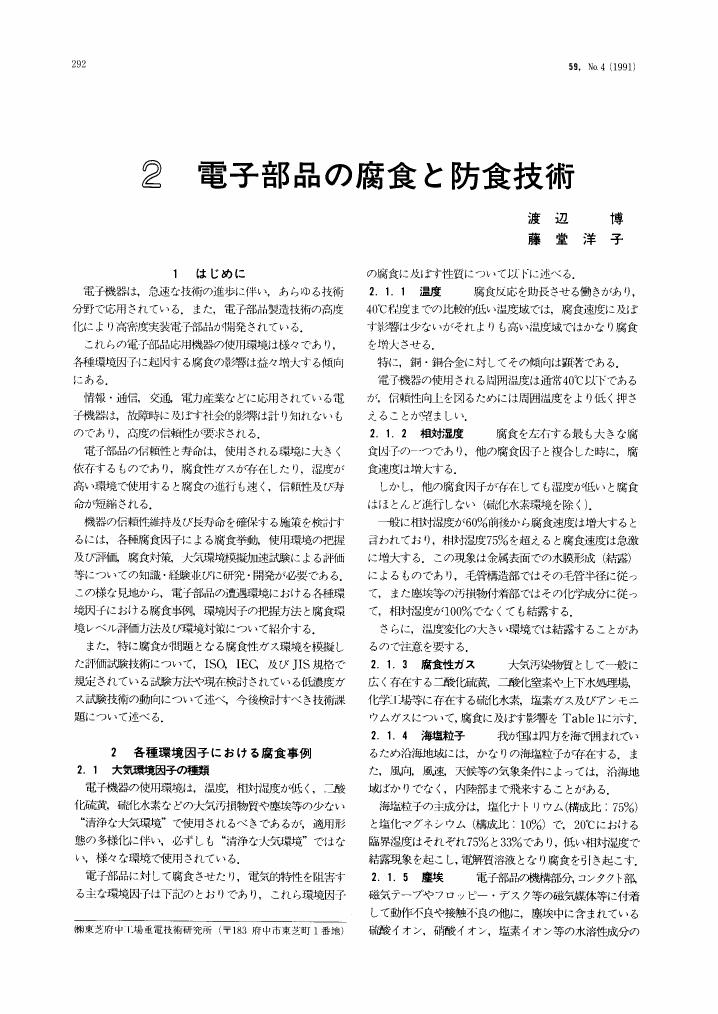- 著者
- 高田 久夫 鈴木 隆文 丸山 明紀
- 出版者
- 公益社団法人 日本コンクリート工学会
- 雑誌
- コンクリート工学 (ISSN:03871061)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, pp.47-52, 2016
2 0 0 0 OA 翻刻 キリシタン版『さるばとる・むんぢ』
- 著者
- 漆﨑 正人
- 出版者
- 藤女子大学日本語・日本文学会
- 雑誌
- 藤女子大学国文学雑誌 (ISSN:02869454)
- 巻号頁・発行日
- no.97, pp.35-52, 2017-11-25
2 0 0 0 OA 加害行為の脳内表象:fMRI研究
- 著者
- 宮内 誠 カルロス
- 出版者
- Tohoku University
- 巻号頁・発行日
- 2013-03-27
課程
2 0 0 0 OA 光刺激による状況判断の有無が方向転換動作に及ぼす影響
- 著者
- 川原 布紗子 吉田 拓矢 野中 愛里 谷川 聡
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, pp.77-90, 2021 (Released:2021-02-13)
- 参考文献数
- 35
The purpose of this study was to examine the effect of decision making under a light stimulus on movement during a change of direction (COD). Twelve male soccer players performed 2 types of lightbased backward agility test (BAT): normal condition and pre-planned condition (BAT-PP). Their motions were videotaped using 2 high-speed cameras operating at 300 Hz for three-dimensional motion analysis. The time, step parameter, and each kinematic variable were compared to determine the differences between the BAT and BATPP. The results showed that the times for 5–13 m and 0–13 m in the BAT were slower than those in the BAT-PP. The velocity of the center of gravity at the lowest point of the velocity in the BAT was lower than that in the BATPP. During the pre-COD phase, the body inward lean angle, shoulder rotation angle, and pelvis rotation angle were all smaller in the BAT than in the BAT-PP. At the COD foot contact, foot placement in the left-right direction was shorter and knee flexion was greater in the BAT than in the BAT-PP. Furthermore, hip flexion during the deceleration phase, and shoulder and pelvis rotation during the acceleration phase were larger in the BAT than in the BAT-PP. Overall, these results may indicate that players who performed the BAT were required to maintain a posture that allowed them to turn to the left or right until the presentation of the light stimulus; therefore, their bodies were upright, and their trunks were facing the direction of approach before COD. Moreover, the knee joint flexed with a short distance to the left of the COD foot placement, the velocity of the center of gravity decreased with hip flexion, and the trunk rotated significantly to a new direction in the BAT.
2 0 0 0 OA 脳活動に基づくプログラム理解の困難さ測定
- 著者
- 中川 尊雄 亀井 靖高 上野 秀剛 門田 暁人 鵜林 尚靖 松本 健一
- 出版者
- 日本ソフトウェア科学会
- 雑誌
- コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.2_78-2_89, 2016-04-22 (Released:2016-06-22)
本論文は,NIRS (Near Infra-Red Spectroscopy; 近赤外分光法)による脳血流計測を用い,開発者がプログラム理解時に困難を感じているかの判別を試みた我々の先行研究(レター論文)を発展させたものである.本論文では,20名の被験者に対して,難易度の異なる三種類のプログラムの理解時の脳血流を計測する実験を行った.実験が中断された3名を除く17名中16名において,(1)難易度の高いプログラムの理解時に脳活動がより活発化するという結果(正確二項検定, p < 0.01)が得られた.また,(2)被験者アンケートによって得られた難易度の主観的評価と,脳活動値の間には有意な相関(スピアマンの順位相関係数 = 0.46, p < 0.01)がみられた.
2 0 0 0 OA 腐食工学の最先端 2.電子部品の腐食と防食技術
- 著者
- 渡辺 博 藤堂 洋子
- 出版者
- 公益社団法人 電気化学会
- 雑誌
- 電気化学および工業物理化学 (ISSN:03669297)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.4, pp.292-301, 1991-04-05 (Released:2019-09-25)
2 0 0 0 OA スーパーライザーの星状神経節近傍照射後の睡眠効果について
- 著者
- 山田 将弘 江島 加渚 吉田 英樹
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.37 Suppl. No.2 (第45回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.F4P2305, 2010 (Released:2010-05-25)
【目的】直線偏光近赤外線(以下SL)の星状神経節照射は、副交感神経優位になると多々報告がされている。その反面あまり効果がないのではないかという報告もされている。そこで、SLの星状神経節近傍照射は副交感神経優位になるのかということ、さらに、SLの星状神経節近傍照射により副交感神経優位になるという仮説の元、睡眠を誘うか否かという2点を検討することを目的とした。【方法】SLの星状神経節近傍照射には、東京医研株式会社製スーパーライザー(HA-2200・TP1)を使用した。スーパーライザーの先端ユニットをSGユニット・照射モードをTミックスとし、身体に重篤な既往及び疾患のない健常成人25名(男性14名、女性11名、25.1±2.5歳)の星状神経節にSLを体表から10分照射を行った。自律神経機能評価にはフクダ電子株式会社製解析機能付きセントラルモニタ(ダイナスコープ7000シリーズ・DS-7600システム・DS-7640)を用いて、連続する100心拍の心電図R-R間隔変動係数(以下CVR-R)を計測した。対象者に対して、温度(26~27°C)及び湿度(50%前後)を可能な限り一定に保った室内にて、可能な限り交感神経の緊張状態を回避するために安静臥位での馴化時間を設定した。馴化時間については、17例を対象とした予備実験において10分の群と30分の群を比較した結果、明らかな違いは認められなかったので、10分を採択した。CVR-Rの測定は、馴化時間後のSL照射前と照射終了直後とし、両者の値を対応のあるt検定にて検討した。なお、統計学的検定での有意水準は5%未満とした。なお、対象者の内、男性3名、女性2名の計5名には、日本光電株式会社製脳波計(EEG-1714)を使用したSLの星状神経節近傍照射前後での脳波計測を実施し、睡眠段階判定を行った。睡眠段階の判定は医師が行い、睡眠段階判定の基準としては国際基準(Rechtschaffen&Kales,1968年)に基づき判定を行った。【説明と同意】ヘルシンキ宣言に基づき、対象者には本研究の目的と内容を事前に説明し、研究参加の同意を得て実施した。【結果】SLの星状神経節近傍照射前後でのCVR-Rの変化については、SLの星状神経節近傍照射前と比較して照射後にCVR-Rの上昇を示した例が13例、逆に低下した例が12例であり、SLの星状神経節近傍照射に伴うCVR-Rの変化パターンに一定の傾向は認められなかった(P=0.16)。一方、脳波計側によるSLの星状神経節近傍照射前後での睡眠段階の結果については、男性ではstage1からstageWへの変化例が1例、stage1からstageWへの変化例が1例、stageWから変化なしの1例となり、女性ではstage1からstage2への変化例が1例、stage1からstage3への変化例が1例であった。全体として、睡眠段階のstage変化なしが1例、低下が2例、上昇が2例であった。【考察】本研究では、SL照射は睡眠を誘うか否かを検討した。CVR-RについてはSLによる星状神経節刺激により、自律神経系に影響を及ぼすのではないかと思われたが、副交感神経優位となる傾向は見られなかった。これは、佐伯らの先行研究(2001)と同様の結果であった。本研究で対象とした若年健常例は、自律神経活動が正常と考えられるため、SLの星状神経節近傍照射により大きな影響を受けなかったことも考えられる。また、若年者では安静時交感神経活動が低いとされており、あまり効果が期待できないのではなかろうか。また、脳波計測によるSLの星状神経節近傍照射前後での睡眠段階の結果では、睡眠段階の変化なしが1例、stage低下が2例、上昇が2例となり、睡眠に効果があるとは言い難い結果となった。睡眠段階の判定を担当した医師の見解でも、SLの星状神経節近傍照射は睡眠に効果があるとは言い難い結果となった。しかし、睡眠段階については、女性2名中2名においてSLの星状神経節近傍照射に伴いstageが上昇していたことを考慮すると、性差による違いも考慮した更なる検討が今後必要と考える。【理学療法学研究としての意義】今回の結果を見る限り、SLの星状神経節近傍照射は、自律神経系への効果の面で疑問が残る。他の光線(レーザーやキセノン光)を用いた星状神経節近傍照射との比較研究や、効果の検証を進める必要があるのではなかろうか。その一方で、今回の結果は、女性に対するSLの星状神経節近傍照射が「睡眠への介入の可能性」という観点で、今後更なる検討の余地があることも示している。このことは、理学療法上、極めて意義深い示唆ではないかと考えられる。
2 0 0 0 OA 共創=脱構築としての存在―群れにおける予期を例として―
- 著者
- 郡司 ペギオ幸夫
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.11, pp.1029-1036, 2012-11-10 (Released:2020-04-23)
- 参考文献数
- 20
2 0 0 0 対中国輸出統制委員会(ChincoM)の展開に関する研究
平成13年度から開始した標記研究課題を達成するため、第一次資料と第二次資料の収集と分析を進めるとともに、研究成果の一部としてかつて発表した論文の補強・修正を行う一方、研究課題と深くかかわる現代の国際輸出統制問題と中国の関与に関して論文の執筆を行った。しかしながら、標記研究課題に関する収集資料は膨大にのぼり、また研究対象となるCHINCOMの活動期間が長期に及ぶため、資料を完壁に収集するに至らなかった。特にCHINCOMが消滅した1957年にまで遡って検証するには、関係者の残した日記・手記などの第一次資料の収集やヒアリングが不可欠と思われるが、日中貿易関係者や政府において輸出統制にあたった関係者のほとんどが他界した現在、これらの資料の収集には難渋を極めている。これらの資料の収集は、研究期間が終了した現在も継続して実施している。
2 0 0 0 OA <論文>近世薩摩における豪商の活躍とその没落について
- 著者
- 高向 嘉昭 Yoshiaki TAKAMUKI
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.1-27, 1994-03-31
2 0 0 0 OA 高校生の数学的問題解決方略使用を促す授業外学習教材の開発 自己調整学習との関連に着目して
- 著者
- 橋本 佳蓉子 渡辺 雄貴
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.Suppl., pp.137-140, 2021-12-20 (Released:2022-02-02)
- 参考文献数
- 15
自ら振り返り次につなげるような学習活動として,自己調整学習が注目されている.自己調整学習は数学的問題解決と過程の段階において関連が考えられる.そこで,本研究では自己調整学習との関連に着目した,高校生の数学的問題解決方略使用を促す授業外学習教材の開発を目的とした.高校1年生を対象に数学Ⅰの2次方程式・不等式の単元で実践した.質問紙調査の結果,数学的問題解決方略は,問題の得点の上位群で問題解決の見通しに関する点で改善が見られた.しかし,授業外学習での自己調整学習方略と動機づけに改善が見られず,成績に応じて問題内容を変えることや授業内容と関連させることなどの教材の課題が明らかとなった.
2 0 0 0 OA e-教室プロジェクト:
- 著者
- 新井 紀子
- 出版者
- 独立行政法人 科学技術振興機構 情報事業本部
- 雑誌
- 情報科学技術研究集会予稿集 第40回情報科学技術研究集会予稿集
- 巻号頁・発行日
- pp.B61, 2003 (Released:2003-11-14)
- 参考文献数
- 3
「e-教室」プロジェクトは、新井らが開発を行った「NetCommons」という情報共有ポータルシステムを活用して、研究者·教員らが協力しながら、中高校生とともにインターネット上の学びのコミュニティを創出する試みである。「NetCommons」では、インターネット上で提供されているデジタルコンテンツを、ニーズに応じて、柔軟に活用しながら、テキストと画像を組み合わせて投稿できる掲示板システムを提供している。「e-教室」に参加している学習者は、学習支援者とともにコミュニティを形成しながら、インターネット上の学びの空間を体験する。ここでは、デジタル教材を利用しながらも、既存のシナリオにはとらわれない、自由度の高い総合的な学習を実現している。
2 0 0 0 IR 職場環境配慮義務と昇格・昇進請求権 - パワー・ハラスメント防止の時代に考える-
- 著者
- 笹沼 朋子
- 出版者
- 愛媛大学法学会
- 雑誌
- 愛媛法学会雑誌 (ISSN:03898571)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.33-53, 2021-12-27
2 0 0 0 OA デュルケム社会形態学における社会と空間
- 著者
- 島津 俊之
- 出版者
- The Human Geographical Society of Japan
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.333-350, 1993-10-28 (Released:2009-04-28)
- 参考文献数
- 98
- 被引用文献数
- 3 2
It is challenging for social geographers to scrutinize the role of space in social theory. The author examines the significance of space in the development of Durkheim's conception of social morphology.The origin of social morphology is found in Durkheim's earlier presentation of the system of sociology. Durkheim, influenced by organicist theory prevailing in the 19th century, elaborated the system of sociology by analogy with that of biology and recognized the presence of‘morphology’inquiring into the way in which society is composed, i.e. into‘structure.’In The Rules of Sociological Method (1895), social morphology was regarded as a branch concerned with the classification of‘social types’in terms of differences in structure. However, at that time, it was to‘function’of society, such as morality or the law, that Durkheim attached much importance as subject matter. In fact social morphology, in the Rules, was assigned to provide for sociological explanations the‘laboratories’(social types) furnished with the value of alleged independent variables, i.e.‘dynamic density’and‘social volume.’On the other hand, Durkheim made his own distinction between the‘base’and‘superstructure’ of society. In his view, the‘base’means social groups from which the‘superstructure’ i.e.‘function’originates, which are called the‘substratum.’In the Rules Durkheim regarded as the subject matter of sociology‘social facts, ’which were classified into two major categories: substratum (morphological facts) and social life (physiological facts). In this classification system the elements of space (dwellings and the network of communications) were incorporated into the concept of substratum for the first time. Durkheim thought that the substratum was social life consolidated while it was a visible vehicle through which invisible social life might be approached.The above significance of the substratum became a precondition for the renewal of social morphology as an explanatory analysis of the substratum. This renewal was completed probably in response to Friedrich Ratzel's conception of geography. In this stage Durkheim incorporated into the substratum various kinds of space connected with society, especially Ratzelian concepts of‘Raum’and‘Grenzen.’Thus it is considered that space is a visible‘social form, ’a visible manifestation of society. The task of social morphology was to explain from the category of‘collective representations’the shaping of the substratum as an amalgam of social groups and space.Durkheim, however, went in the direction of distinguishing analytically between social groups and space. He utilized Georg Simmel's‘form-content’-dichotomy for this distinction. Further, the category of social group was given the term‘population’while that of space was called‘social space.’In the end social morphology was conceived to include a double task of explaining the formation of population distribution and of social space.
2 0 0 0 OA デュルケムの社会空間論 : その意義と限界
- 著者
- 島津 俊之
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.20-36, 1995-03-31 (Released:2017-05-19)
本稿は, デュルケムの社会空間論を発掘し, その意義と限界を明らかにすることを通じて, <社会-空間理論>構築への足がかりを得ようとするものである. これは, 彼の地理学的想像力を再評価する試みでもある. デュルケムにおける社会空間論の起点は, 1893年刊行の『社会分業論』の時点で形成されていた. 彼のいう社会空間は, 一貫して<社会が占める地理空間〉>を意味する概念であり, ラッツェルの刺激によって考案されたとも考えられる. デュルケムの社会存在論のなかで, 社会空間は社会集団とともに<基体=社会の身体>と位置づけられ, <社会の精神>たる社会生命に対峙することになる. 社会空間は, 社会生命が空間に下ろした<足場>ともなる. 一方で, 未開社会を対象に<知識社会学>を展開したデュルケムは, 社会空間が分類体系や空間カテゴリーのモデルになったと推論する. 社会空間は, ある種の社会生命の生成に際して, それに<かたち>を与える媒介変数の地位を与えられたのである. デュルケムの社会空間論は, 様々の限界や矛盾を孕む一方で, 豊かな地理学的想像力の見木を提供するものでもある. それは, 社会空間を社会の不可欠な要素と認識し, その役割を積極的に評価しようとするものであった.
2 0 0 0 IR 日本の法外な特権と法外な負担
- 著者
- 青木 浩治 Koji AOKI
- 出版者
- 甲南大学経済学会
- 雑誌
- 甲南経済学論集 = Konan economic papers (ISSN:04524187)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.1-43, 2019-09-30
本稿は, 第一に, 世界51ケ国の国際投資ポジション(International Investment Position: IIP) の超過収益率を計測することによって日本のIIP 超過収益率の源泉の特徴を浮き彫りにする。特に, 世界第一位の債権大国・日本のIIP 超過収益は主として債券投資超過収益に依存しているものの, 国際比較の観点からはこの日本の特徴はむしろ例外的であり, IIP 超過収益率はエクイティ関連投資, なかでも直接投資の超過収益率に強く依存していることを明らかにする。第二に, 日本の正のIIP 超過収益率が発生する理由を, リスク回避度の差に着目したシンプルなリスク分担モデルで分析し, 日本のようなリスク回避度の高いと考えられる経済はリスク・オフ期における実質為替レート増価というヘッジ機能を提供する代償として正のIIP 超過収益を享受できることを示す。第三に, 日本のIIP 超過収益の源泉が債券投資超過収益から直接投資超過収益にシフトしつつある中で, 外国人投資家による日本株保有増加と株高による負債面での評価損によって, 安倍政権発足後急速に日本のIIP超過収益率が低下している現状を報告する。
2 0 0 0 OA 土地利用と土壌組成の関係性からみた見沼田圃公有地化推進事業による保全の再検討
- 著者
- 石井 秀樹 斎藤 馨
- 出版者
- 一般社団法人 環境情報科学センター
- 雑誌
- 環境情報科学論文集 Vol.25(第25回環境研究発表会)
- 巻号頁・発行日
- pp.293-298, 2011 (Released:2014-05-08)
本稿では「見沼田圃公有地化推進事業」を事例として,見沼田圃各地に点在する公有地の土地利用と土壌組成の関係性に注目し,地の利にあった土地管理を検討した。見沼田圃の土壌はりん酸が枯渇しやすい黒ボク土だが,地下には大量の植物遺骸が埋没しており腐植が多い。調査の結果,有機物を土壌還元する「見沼田んぼ福祉農園」では,りん酸や加里を充足する土壌システムが形成されている可能性が示唆された。市民活動には,収益性よりも手間・暇をかけ達成感を得ることを目的とする活動も多く,有機物を還元に重きをおいた管理方法は見沼田圃の地の利を活かすとともに,保全活動の魅力を高め,当該事業の持続可能性を高めると考えられた。
2 0 0 0 環境学習のためのDVD植物季節カレンダー
- 著者
- 斎藤 馨 藤原 章雄 石井 秀樹 志村 正太郎 矢野 安樹子 大場 有希子
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 日本林学会大会発表データベース
- 巻号頁・発行日
- vol.115, pp.P2032, 2004
東京大学秩父演習林内に設置した2台の森林映像記録ロボットカメラの映像(動画と音)を利用して、森林に関する環境学習の教材として、季節変化を映像と音で閲覧できるDVDとWebページの作成と、小学校の授業で児童が容易に季節変化を見ることのできる印刷物を作成した。印刷物は、児童が容易に閲覧し、印を付けたり、異なる日の写真を比較できることに着目し、2001年と2002年の過去のロボットカメラの写真を1年間並べる際に、2004年版のカレンダーの形式を用いて、カレンダーの日付と同一の過去の写真を配置した。これにより小学生が、1年分に並んだ過去の森林の写真を、1年間の日々の並びとして直感的に理解できる。ロボットカメラの映像には森林の音も記録されていて、鳥や蝉の鳴き声が入っている。音から鳥の種を同定しカレンダーの日付欄に記載した。また映像を使ってDVDとWebページを作成し、カレンダーで一覧している1年間の変化を、視聴できる教材を作成した。今後は実際に小学校での授業に試験的に用いて、これらの教材の有用性を検証していく。