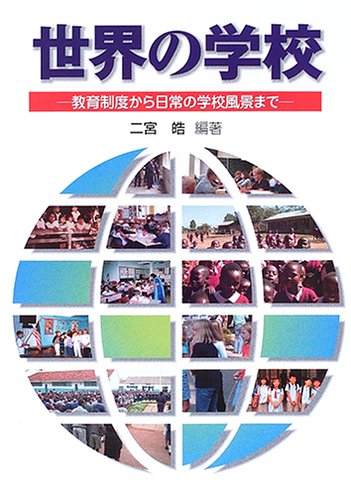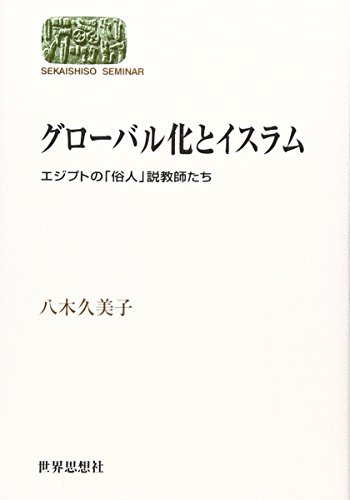- 著者
- 竹本 潔 船戸 正久
- 出版者
- 日本重症心身障害学会
- 雑誌
- 日本重症心身障害学会誌 (ISSN:13431439)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.83-89, 2015
Ⅰ.はじめに高度な医療的ケアが必要な小児が退院して家庭で暮らすケースが増加している1)。しかし退院後の在宅療養では、介護されるご家族の長期にわたる相当な肉体的、心理的負担が発生し、日常的な外出の困難や慢性的な睡眠不足など多くの問題を抱えながら生活されている現状がある。大阪府の調査によると2)、家族が地域で安心して暮らし続けるうえで最も必要と感じているサービスはショートステイ事業所の増加であった。重度の障害を持った児を短期間施設でお預かりするショートステイはご家族が最も望まれる支援のひとつであり、今後小児在宅医療を推進するにあたって必要不可欠な支援である3)。今回、これまでの当センターでのショートステイの実績を報告し、現状でのショートステイの課題について考察したので報告する。Ⅱ.方法当センターは大阪市南部に位置し、最初1970年肢体不自由児治療施設「聖母整肢園」として開設された。2006年大阪市の委託を受けて重症心身障害児入所施設「フェニックス」を新たに開設し、同時に全体施設を「大阪発達総合療育センター」と命名した4)。現在入所施設としての機能は、医療型障害児入所施設(主として肢体不自由児)「わかば」棟:40床、医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児)「フェニックス」棟:80床で、内ショートステイ:17床(21%)で運営している。当センターにとってもショートステイの提供は重症心身障害児の在宅支援の大きな柱である。ショートステイの登録は、事前に依頼しておいた診療情報提供書を基に医師、病棟看護師が十分程度時間をかけて病歴、医療的ケア、および患児の日常生活の様子や注意すべき点について確認している。その後引き続き医療ソーシャルワーカーより契約に関して説明し、希望があれば病棟の見学を行っている。今回2008年度から2013年度の6年間における当センターフェニックスでのショートステイの利用状況について、登録患者数、年間総利用のべ人数、年間総利用のべ日数、1回あたりの利用日数、年間利用回数、利用者の年齢、利用者の医療的ケア、利用理由、キャンセルとキャンセル待ちの人数、利用中に体調変化した人数とその理由について調査した。Ⅲ.結果1.登録患者数図1のように、ショートステイの登録患者数は年々増加し、2012年度末で578名が登録されていた。2010年に申込み多数にて登録を一時中断、2011年に一定期間以上利用がないケースに連絡し登録を抹消した経緯がありいったん減少したが、その後また増加した。2.年間総利用のべ人数と年間総利用のべ日数2008年度~2013年度のショートステイの年間総利用のべ人数と年間総利用のべ日数を図2に示す。2011年度に開始したNICUの後方支援により総利用のべ人数、総利用のべ日数ともやや減少したが、その後また増加に転じた。2013年度はノロウイルス、アデノウイルスの流行が発生したため再び減少し1日平均11人の利用であった。3.1回あたりのショートステイ利用日数2010~2012年度の3年間における1回あたりのショートステイの利用日数を図3に示す。7日以上の利用は全体の5%に過ぎず、1泊2日と2泊3日で全体の49%を占め、82%が5日間以内の短期利用であった。4.利用者の年間利用回数2012年度の総利用者数305人の年間利用回数を図4に示す。1回のみの利用者が89人で最も多く、2回が62人、3回が54人であった。44人が1年間に6回以上利用していた。5.利用者の年齢2010~2012年度の3年間の利用者の年齢分布を図5に示す。全体の10%が6歳以下、28%が12歳以下、51%が18歳以下であった。一方で30歳以上の利用者も全体の17%を占めていた。6.利用者の医療的ケア2012年度は全体の46%が超・準重症児で占められていた(図6)。2012年4月よりショートステイ特別重度支援加算として、加算Ⅰ(超・準重症児)388点/日、加算Ⅱ(運動機能が座位までで、かつ特定の医療処置<経管栄養法、褥瘡処置、ストーマ処置等>が必要)120点/日の算定が認められており、加算Ⅰ(46%)+加算Ⅱ(12%)で全体の58%を占めていた。また人工呼吸器使用児(NPPVを含む)の利用も年々増加し(図7)、2013年度は全体の17%を占めていた。7.ショートステイの利用理由2010~2012年度の3年間の総利用者におけるショートステイの利用理由を図8に示す。休養のための利用(レスパイト)が最も多く全体の52%を占めていた。次いで冠婚葬祭(8%)、お試し(5%)、兄弟の学校行事(3%)、家族のけが・病気(3%)、旅行(3%)、次子出産(1%)が続いた。その他に分類された理由は仕事、帰省、引越などがあった。8.キャンセルについて2010年~2013年度の4年間の1カ月平均のキャンセル数とキャンセル待ちを図9に示す。最近3年間は毎月10人以上のキャンセルが発生し、キャンセル待ちは毎月30人以上存在していた。キャンセルの理由は全例体調不良であった。9.ショートステイ中の体調変化について2010年~2012年度の3年間のショートステイ利用者のべ3,006人で、入所中に何らかの追加医療処置が必要となったケースは154人(5.1%)で、理由は発熱が93人(3.1%)で一番多かった。対応としては105人(3.5%)に投薬を、33人(1.1%)に点滴を行っていた。また11人(0.4%)が急性期病院へ搬送されていた。重篤な事例としては、・突然の心停止で蘇生に反応せずに死亡・胃穿孔からショック状態→蘇生後転送し緊急手術にて救命・食事の誤嚥による窒息(蘇生にて回復)・更衣介助中の大腿骨顆上骨折・けいれん重積などがあった。Ⅳ.考察2012年7月の集計によると5)、大阪府全体(大阪市・堺市など政令都市も含む)の重症心身障害児(者)数は7,916人であり、人口1,000人あたり0.89人であった。これは従来より言われている人口1,000人あたり0.3人より大幅に多く、近年、特に都市部では医療の進歩による救命率の向上と寿命の延伸によってその数が増加していることが示された。一方、その内医療型障害児入所施設(療養介護事業も含む)の入所者数は659人(8%)に過ぎなかった。また、入所者の内18歳未満の児は95名(14%)に過ぎず、18歳以上の者が564名(86%)を占めていた。すなわち、障害児入所施設にもかかわらず、入所者の80%以上が18歳以上の成人が占めている現実が示された。残りの7,257人(92%)は在宅生活をしており、その内約50%が何らかの医療的ケアが必要であった。また、驚くことに在宅児者の方が施設入所児者よりも医療的ケアの重症度が高いという事実が判明した。在宅児者914人と施設入所児者568人の比較によると5)、気管切開を施行している児者の割合は、在宅14.8% に対して施設入所6.3%であり、同じく人工呼吸器使用は在宅7.2%に対して施設入所2.6%であった。それにもかかわらず、現在このような高度な小児在宅医療を支援する人材が不足し、小児に対応できる訪問診療医・訪問看護師・訪問リハビリテーション療法士や医療的ケアに対応できる訪問ヘルパー等の育成が緊急の課題となっている。一方前述したように在宅生活を継続している家族の最大の要望は、レスパイトケアを含んだショートステイの拡充である2)。このことは、全国重症心身障害児(者)を守る会での調査でも、在宅生活継続のための大切な柱と位置付けてられている6)。当センターのショートステイは西日本で最も多い登録患者数(2014年9月現在約600名)、利用人数(年間総利用のべ人数約1,000人)で、現在も約50名が登録診察待ちの状況である。今後も登録患者数はさらに増加することが予想される。利用者の49%は3日以内の非常に短い利用であった。これは毎日入退所が頻繁に行われていることを意味している。2012年度の総利用者数は305人で、これは1年間に全登録者の約半数が利用していることになる。年間利用回数は1回のみの利用者が最も多く、約半数が年間2回以下の利用であった。この理由の一つはベッド不足であり、本当は頻繁に利用したいが申し込んでも落選することによる。もう一つは次々に登録される新規登録者が緊急利用時のことを考えて、ひとまず一度体験利用することによる。当センターのショートステイは初回利用は原則1泊2日としており、このことが全体の利用日数の短縮にも影響していると考えられた。利用者の年齢は全体の28%が12歳以下、51%が18歳以下で占められていたが、一方で30歳以上の利用者も全体の17%を占めており、重症心身障害児(者)の幅広い年齢分布がここでも窺えた。また全体の46%が超・準重症児、17%が人工呼吸器使用で、医療要求度が高い傾向を認めた。(以降はPDFを参照ください)
【目的】 中学校技術・家庭科家庭分野の「A家族・家庭と子どもの成長」は、家庭分野の導入として、ガイダンスの位置づけとすることになっている。しかしこの内容に含まれている「自分の成長と家族とのかかわり」は、中学校入学当初のみならず、家庭分野の学習を通して生徒に見つめさせていきたい内容である。中学生の時期に自立の概念をとらえ、今後の自分の人生を展望することは極めて重要であり、キャリア教育の視点も加味しつつ、家庭科学習との関わりで自らの成長を振り返る契機としたいと考えた。以上の授業観に基づき、中学生が自らの成長を家族との関わりを可視化することを通して考える授業を設定し、その効果と課題を明らかにすることを目的として、「絵本」を教材とした授業実践とその分析・考察を試みた。【方法】 2012年10月に、国立大学附属K中学校第1学年4クラスの生徒を対象として、家族と家庭生活に関する内容の絵本を教材とした授業を試みた。授業は2時間続きで行われ、1時間目には本授業のために制作されたオリジナルのデジタル絵本『「なりたい自分」になるために必要なこと』を、2時間目には、レイフ・クリスチャンソン:文(にいもんじまさあき:訳)、ディック・ステンベリ:絵の『じぶん』(岩崎書店、1997年)という絵本を使用し、他者とのかかわりの中で、相手意識をもって「自分に何ができるのか」を考えるように促した。 授業の中では、現在に至るまでの、家族とのかかわりに着目させることとし、自分の成長の背景には、家族をはじめとする身近な大人たちの存在が不可欠であり、そうした人々との関わりを通して今の「自分」を形成してきたのだということに生徒たちが気づくための手立てを考え、授業の内容が組み立てられた。本授業における生徒の気づきをワークシートや授業後の感想から読み取り、分析を行った。【結果と考察】1.生徒にとっての「自立」: 1時間目の授業の冒頭で、教師は「自立」のイメージマップを生徒たちに書かせた。その結果、「自立」という言葉から直接枝分かれして書かれている言葉は、「一人暮らし」「視野が広がる」「自分の意思をもつ」「自分の力で生活する」ということであった。自立には、生活的な自立、精神的自立、経済的自立があることをとらえていることが分かった。しかし、「自分の力で生活する」と言う言葉から派生しているのは、「自分のことは自分でやる」ということであって、「一人でできるようになる」ということが自立の根本的な考え方として捉えられていた。「誰かと共に助け合って生活する」「誰かのために役立つ自分になる」という「共生」の概念は、この「自立」のマップからは見取ることができなかった。2.「共生」というコンセプトについての生徒の理解: 1時間目の授業では、「自立」の概念に続いて、「共生」の意味についても生徒に提示している。「共生」の概念を押さえたうえで、2時間目の「いまの自分・これからの自分と家族とのかかわりについて考えてみよう」という小題材へと学習は展開した。「自分の成長と家族とのかかわり年表」は、自分の成長とともに家族それぞれも年齢を重ねていくということを可視化させる手がかりとなり、家族とのかかわりを見つめ直した様子がうかがえた。3.教材としての絵本の効果: 授業後のアンケートにより、生徒たちの絵本教材に対する意識を把握したところ、約4割の者が絵本に対する関心を持っていた。しかしほぼ同率で「あまり関心がない」と回答する者もおり、授業にあたり、絵本それ自体に対しては、自発的な興味・関心を抱いている学習者ではなかった。しかし、それにもかかわらず、今回使用したデジタル絵本に対しては肯定的な評価が得られ、約6割が「わかりやすかった」と回答し、約4割が「いまの自分のことを考える手がかりになった」「文章(言葉)がよかった」と回答している。「将来の自分のことを考える手がかりになった」という回答も約4割見られ、これからの自分の生活を考える視点を持つきっかけになったと推察された。
2 0 0 0 OA 管理栄養士および栄養士養成施設における食環境整備に関する教育の実態と教育に関連する要因
- 著者
- 赤松 利恵 小澤 啓子 串田 修 小島 唯 阿部 絹子
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.6, pp.355-364, 2021-12-01 (Released:2022-02-08)
- 参考文献数
- 13
【目的】管理栄養士・栄養士養成施設における食環境整備に関する教育の推進に向けて,その教育の実態を把握し,関連する要因を検討すること。【方法】厚生労働省委託事業「令和2年度管理栄養士専門分野別人材育成事業」の食環境整備に係る人材育成検討部会が行った教員(管理栄養士養成施設432人,栄養士養成施設224人)を対象としたデータを用いて,養成施設別に,食環境整備に関する教育に関わる個人要因と環境要因,食環境整備に関する教育の実施状況をMann-WhitneyのU検定,Kruskal-Wallis検定,ロジスティック回帰分析を用いて調べた。【結果】管理栄養士養成施設(210人,48.6%)では,教育の実施高得点群に,食環境整備に関する研究と社会活動の経験(オッズ比[95%信頼区間]各々2.45[1.09~5.48],3.64[1.59~8.31])等の要因が関係していた一方で,栄養士養成施設(73人,32.6%)では,所属施設内の管理栄養士養成課程の有無(8.74[1.44~53.25])の環境要因が関係していた。栄養学教育モデル・コア・カリキュラム(以下,コアカリ)の活用は,両施設で関係していた(各々2.83[1.22~6.58],11.37[2.28~56.71])。【結論】食環境整備の教育には,教員の専門性と職場環境が関連していた。また,養成施設での教育において,コアカリの活用を推進する必要性が示された。
2 0 0 0 OA 幼児の偏食と健康状態および夕食の食品群別摂取量,栄養素等摂取量
- 著者
- 深澤 向日葵 吉井 瑛美 會退 友美 赤松 利恵 長谷川 智子
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.6, pp.338-344, 2021-12-01 (Released:2022-02-08)
- 参考文献数
- 18
【目的】幼児の偏食と健康状態,夕食における食品群別摂取量,栄養素等摂取量との関連を検討することを目的とした。【方法】2018年12月,1次調査として幼児を持つ母親を対象にインターネット調査を実施し,そのうち希望者から抽出された者を対象に2019年3~5月,2次調査として写真法による食事調査を実施した。1次調査より幼児の偏食,健康状態,属性を用い,2次調査より幼児の夕食の食品群別摂取量,栄養素等摂取量を用いた。偏食得点の三分位値で分けた低群,中群,高群の属性,健康状態および食品群別摂取量,栄養素等摂取量の違いを,χ2 検定,Kruskal-Wallisの検定および多重比較で検討した。【結果】1次調査の解析対象者は1,899人,2次調査は118人であった。幼児の偏食得点三分位値は14,17点であり,低群614人(32.3%),中群708人(37.3%),高群577人(30.4%)となった。偏食低群には,発熱しにくい者,風邪をひきにくい者,疲れにくい者が多かった(それぞれp<0.001)。食品群別摂取量では野菜類に有意差がみられ,偏食高群で摂取量が少なかった(p=0.016)。栄養素等摂取量は,偏食3群間で違いはみられなかった。【結論】偏食低群の幼児の健康状態は良好であった。偏食高群の幼児は,夕食で野菜類の摂取量が少なかったが,栄養素等摂取量は偏食の程度による違いはみられなかった。
2 0 0 0 世界の学校 : 教育制度から日常の学校風景まで
2 0 0 0 OA 欧米の学校建築にみる多様性 : 日本の学校建築の相対化
- 著者
- 鈴木 賢一
- 雑誌
- 芸術工学への誘い (ISSN:21850429)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.17-27, 2015-03-31
欧米の学校建築には、日本にはない多様な計画設計の実例がある。1)学校規模と南面教室配置、2)教える教室と学ぶ教室、3)魅力的な廊下、4)学習リソースの未来、5)学校の管理運営、6)場所から生まれる形、7)歴史を刻む学校、という7つの観点から、日本と欧米を比較しながら学校建築の計画条件と実際に構築された学習環境の違いを記述した。多様な姿かたちを表わす海外の学校建築を知ることは、建築技術以上に、前提となる考え方の違いに触れることである。ひいては、日本における学校の計画設計の選択肢を増やすことにもつながる
- 著者
- 林 上
- 出版者
- 地理科学学会
- 雑誌
- 地理科学 (ISSN:02864886)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.3, pp.200-208, 1993-07-28 (Released:2017-04-27)
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 グローバル化とイスラム : エジプトの「俗人」説教師たち
2 0 0 0 OA ウイルスを抑える自然細菌
2 0 0 0 OA 兵器生産基本教程
- 著者
- 陸軍兵器学校 編著
- 出版者
- 兵器航空工業新聞出版部
- 巻号頁・発行日
- vol.第6巻 (銃器), 1943
2 0 0 0 OA 「春の夜の香り」について ―『古今和歌集』躬恒歌を中心に―
- 著者
- 田中 幹子
- 出版者
- 中古文学会
- 雑誌
- 中古文学 (ISSN:02874636)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, pp.1-9, 1996-05-20 (Released:2019-05-18)
- 著者
- エーデルマン リー 藤高 和輝
- 出版者
- 岩波書店
- 雑誌
- 思想 (ISSN:03862755)
- 巻号頁・発行日
- no.1141, pp.107-126, 2019-05
- 著者
- 三澤 康彦 三澤 文子
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経アーキテクチュア (ISSN:03850870)
- 巻号頁・発行日
- no.974, pp.84-86, 2012-04-25
日本は国土のうち約6割を森林が占める。しかし、木材自給率はわずか2割程度。木造住宅も、その大半が外材でつくられている。国産材にこだわる三澤康彦・三澤文子夫妻に、価格や流通の実情を聞いた。─構法の話に入る前に、木材について教えてください。三澤さんたちは、木造住宅でも、特に国産材を使った木造を推奨されていますね。
- 著者
- 岩本 雅郎
- 出版者
- 日本弁護士連合会
- 雑誌
- 自由と正義 (ISSN:04477480)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.11, pp.p56-61, 1990-11
- 著者
- 板垣 信悦 押野見 喜八郎
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経レストラン (ISSN:09147845)
- 巻号頁・発行日
- no.328, pp.72-76, 2003-05
首都圏の大手和食ファミリーレストランに4年、低価格イタリア料理店の大手チェーン、サイゼリヤに5年勤めた後、故郷の青森県弘前市に戻り、99年10月末、イタリア料理店を開きました。弘前にサイゼリヤのような店がなかったことから、グラスワインを190円で提供するなど、安さを前面に打ち出した店にしました。 最初の数カ月はまずまずでしたが、すぐに低迷。
2 0 0 0 OA マーケティング戦略におけるネガティブな側面と問題点 : 負のマーケティング論研究序説
- 著者
- 折笠 和文
- 雑誌
- 名古屋学芸大学研究紀要. 教養・学際編 = The journal of liberal arts, Nagoya University of Arts and Sciences
- 巻号頁・発行日
- no.創刊号, pp.11-25, 2005-02
2 0 0 0 OA VR環境下での社会的態度に関する文献の紹介
- 著者
- 阿部 慶賀
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.4, pp.509-515, 2019-12-01 (Released:2020-03-01)
- 参考文献数
- 12
本稿ではBailenson らの研究グループによる,ヴァーチャルリアリティを用いた社会的態度の変容に関する研究を紹介する.Bailenson らは,近年のヘッドマウントディスプレイ (HMD) を用いた没入型のデジタルゲーム環境を用い,さまざまな社会心理学的研究に着手している.近年のデジタルゲームの多くは,プレイヤー自身を代替してゲーム環境内でふるまうアバターを登場させ,他者とコミュニケーションをとれるよう設計されている.この時のアバターは,必ずしもプレイヤーの姿を忠実に模している必要は無く,むしろプレイヤーが望む容姿に設計できるようになっていることが多い.顔つきや体格はもちろんのこと,年齢や性別にかかわる特徴も自由に変更できる. デジタルゲームの環境では容姿が自由自在に変えられる.その一方で,私たちは相手の外見や容姿によって態度を変えてしまうことも知られている.初対面ならだらしない身なりの者よりは,清潔に整えた身なりの者を信用してしまうし,好みの容姿の異性はその内面もポジティブに評価してしまうこともある.Bailenson らの研究グループでは,他者に対して抱く偏見や態度を,VR によって克服する可能性を模索している.普段の自分ではない他者の姿,特に偏見の目を向けていた相手の立場になるようアバターを変更し,文字通り相手の身になって電脳世界の中をふるまい,他者と接触する.こうすることでそれまで抱いていた偏見を克服できるのではないか,という期待のもと,実際に実験を重ねている. 今回紹介するのは,高齢者の立場になってみる実験と,異なる人種の立場になってみる実験である.近年ではVR 開発環境も容易に整いやすくなったが,いざ心理学実験の環境として実装するには配慮すべき点が多数有ることを再確認させられる論文である.そのため,実験環境や手続きに関する記述を詳細に示すことにした.今回紹介する論文はやや時間の経過した論文ではあるが,身体性研究,そして近年本学会でも活発に展開されている「プロジェクション科学」研究においても,これらの知見は実用的な価値を含むものとして一読の価値があろう.