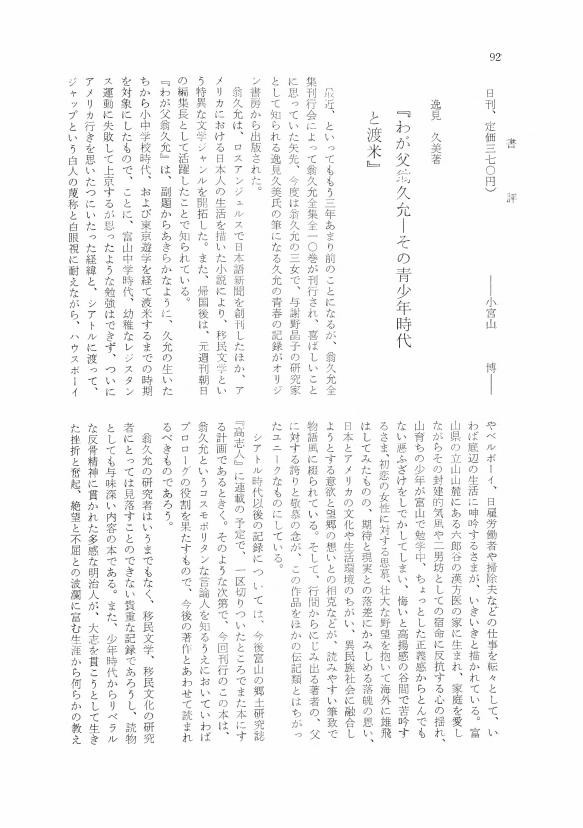2 0 0 0 OA 立山侵食カルデラの形成と崩壊
- 著者
- 藤井 昭二
- 出版者
- 公益社団法人 砂防学会
- 雑誌
- 砂防学会誌 (ISSN:02868385)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.6, pp.3-8, 1997-03-15 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 25
The Tateyama volcano is located in the central part of the Japanese Islands and situated on the northern part of Norikura volcanic zone.Volcanic activities of the Tateyama volcano in the late Quaternary, were classified into four stages. Andestic lava and pyroclastic materials were erupted during those activities. Eruption of the second stage produced so many pyroclastic materials as forming caldera. Afterwards this caldera was eroded and grew larger. A part of caldera wall was broken at Shiraiwa about twenty thousand years ago, and as the result, a lot of debris flowed over the caldera into Joganji River. The Tateyama Sabo Work is one of the largest Sabo work in Japan. Its most important work is the control of the Tombidoro which was produced by the deformation of the Tombiyama (Mt. Tombi) in the earthquake induced by the Atotsugawa fault in 1858. Deformation of the caldera wall by the earthquake may have occurred at any place in the caldera. But why did Tombi collapse occur at Tombiyama? From investigating topography of Kanayamadani and the Tombi collapse, I may conclude the cause of Tombi collapse is that Tombiyama was the terminal place of the right lateral Atotsugawa fault, and force of tension stress and depression concentrated here.
2 0 0 0 OA 歌唱者の音声障害に対する音声治療の効果
- 著者
- 金子 真美 平野 滋 楯谷 一郎 倉智 雅子 城本 修 榊原 健一 伊藤 壽一
- 出版者
- 日本音声言語医学会
- 雑誌
- 音声言語医学 (ISSN:00302813)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.201-208, 2014 (Released:2014-09-05)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 2 3
一般人の音声障害に関する音声治療については多くの報告があり,高いエビデンスレベルのものもある.しかし歌唱者の音声障害に対する音声治療については国内外で報告は少なく,現時点で確立された手技もない.今回われわれは歌唱者の音声障害に対し音声治療を行い,症状に一定の改善を認めた.対象は声帯結節,声帯瘢痕,声帯萎縮,過緊張性発声障害のいずれかと診断され,音声治療を施行した歌唱者9例(男性5例,女性4例,平均年齢53.3歳)である.口腔前部の共鳴を意識した音声治療を施行し,効果をGRBAS,ストロボスコピー,空気力学的検査,音響分析,自覚的評価,フォルマント周波数解析で評価した.治療後,音声の改善は個人差があるものの全例で認められ,MPTやVHI-10,GRBASで有意差が認められた.また,歌唱フォルマントもより強調されるようになった.歌唱者の音声障害に対する音声治療は一定の効果が期待できると考えられた.
2 0 0 0 OA 逸見久美著 『わが父翁久允―その青少年時代と渡米』
- 著者
- 大社 淑子
- 出版者
- 日本比較文学会
- 雑誌
- 比較文学 (ISSN:04408039)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.92-93, 1978-12-25 (Released:2017-07-31)
2 0 0 0 OA プロパガンダと芸術-「冷戦期/冷戦後」の<芸術>変容
- 著者
- 長田 謙一 楠見 清 山口 祥平 後小路 雅弘 加藤 薫 三宅 晶子 吉見 俊哉 小林 真理 山本 和弘 鴻野 わか菜 木田 拓也 神野 真吾 藤川 哲 赤塚 若樹 久木元 拓
- 出版者
- 首都大学東京
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2008
従来プロパガンダと芸術は、全体主義下のキッチュ対自律的芸術としてのモダニズムの対比図式のもとに考えられがちであった。しかし本研究は、両者の関係について以下の様な新たな認識を多面的に開いた:プロパガンダは、「ホワイト・プロパガンダ」をも視野に入れるならば、冷戦期以降の文化システムの中に東西問わず深く位置付いていき、芸術そのもののありようをも変容させる一要因となるに至った;より具体的に言えば、一方における世界各地の大型国際美術展に示されるグローバルなアートワールドと他方におけるクリエイティブ産業としてのコンテンツ産業振興に見られるように、現代社会の中で芸術/アートはプロパガンダ的要因と分かち難い形で展開している;それに対する対抗性格をも帯びた対抗プロパガンダ、アートプロジェクト、参加型アートなどをも含め、芸術・アートは、プロパガンダとの関係において深部からする変容を遂げつつあるのである。
我々は、2005年5月から再生医科学研究所で樹立されたヒトES細胞(KhES-1,-2,-3)の解析を行っている。これらの細胞株からもドーパミン産生ニューロンが誘導され、培地中にドーパミンを放出しうることを確認した。パーキンソン病モデルカニクイザルの線条体に移植を行ったところ、3頭中1頭で腫瘍形成が認められた。このケースでは、PETスキャンにおいて腫瘍部位に限局して糖代謝の亢進が確認され、細胞分裂を示すfluorothimidineの取り込み上昇も認められた。組織診断では、未分化細胞の増殖が限局的にみられたが、奇形種を裏付ける骨・軟骨、皮膚、筋肉、消化管などの形成は認められなかった。fluorothimidine陽性部位に一致して、ES細胞のマーカーであるOct3/4陽性細胞の集積が認められた。移植細胞の解析を行ったところ、分化誘導期間の違いにより、腫瘍形成がみられたケースでは移植細胞の中にES細胞が混入していたのに対し、腫瘍形成がなかった2頭ではES細胞の混入はみられなかった。つまり、移植細胞へのES細胞混入が腫瘍形成の原因であると考えられた。また、MRIやPETは腫瘍形成を確認する上で有用な手段であることが確認された。これらの結果は現在投稿準備中である。移植細胞による腫瘍形成について、我々はマウスES細胞と正常マウスを用いて検討を加え、分化誘導後に神経系細胞のみを選別して移植することによって腫瘍形成が抑えられることを明らかにした(Fukudaら)。これらの研究によって、安全で効果的なES細胞移植を行うためには、神経幹細胞の純化が必要であることが明らかとなった。現在はヒトES細胞の選別方法開発に取り組んでいる。
我々は、ES細胞由来神経系細胞移植によるパーキンソン病治療法の開発を目指して研究を進めているが、臨床応用を目指すにはヒトと同じ霊長類を用いた実験が必要不可欠である。そこで、カニクイザルES細胞から誘導したドーパミン産生神経をカニクイザルパーキンソン病モデル脳に移植し、行動解析を行った。カニクイザルES細胞をPA6という間質細胞の上で約2週間培養すると、ほとんどの細胞が神経幹細胞様になる。この細胞をsphere法で培養しFGF2とFGF20を加えると、全体の約半数がニューロン、その4分の1がドパミン神経に分化するようになる。MPTPの静脈内投与でカニクイザルパーキンソン病モデルを作成し、その線状体にES細胞由来ドパミン産生神経(前駆細胞)を移植すると移植群においては徐々に神経脱落症状の改善がみられるようになり、移植後10週目に有意な改善が認められた。その後、F-dopaの取り込みをPETにて評価した。コントロール群においてはF-dopaの取り込みが低下しているのに対し、移植群においては有意な上昇がみられ、移植細胞がドーパミン神経として機能していることが確認された。PET後に脳切片の染色を行った。移植に先立ち細胞をBrdUでラベルしたが、移植群の線条体においてBrdU陽性細胞の生着がみとめられた。さらにTH陽性細胞やDAT陽性細胞も確認された。これらの多くはBrdUと共陽性であり、移植されたES細胞由来のドーパミン神経であると考えられた。また、腫瘍形成は認められなかった。カニクイザルES細胞から分化した中脳ドーパミン産生神経の移植によってカニクイザルパーキンソン病モデルの行動が改善したことは、同じ霊長類であるヒトにもこの方法が適応できる可能性を示唆する。ただし、実際の臨床応用の前には1年以上の長期経過観察によって、その効果と安全性の検証が行われなければならない。と同時に、ヒトES細胞からの中脳ドーパミン産生神経誘導とその移植実験が必要である。
- 著者
- 中西 重忠 森吉 弘毅 横井 峰人 笹井 芳樹 CARON Marc CARON Marc G 影山 龍一郎 別所 康全
- 出版者
- 京都大学
- 雑誌
- 国際学術研究
- 巻号頁・発行日
- 1995
グルタミン酸受容体は神経の興奮を伝達する受容体として働き、記憶・学習という高次脳機能や神経細胞死を制御する中枢神経系の重要な受容体である。本研究は、Nash博士の参加(平成7年5月から1年間滞在)も含め、相手側MarcCaron博士との共同研究のもとに、グルタミン酸受容体の細胞内情報伝達系と調節機構を明らかにすることを目的としたものである。具体的には、1.受容体の燐酸化による調節機構、2.受容体の活性化による細胞内情報伝達系の制御機構、3.細胞内情報伝達系の調節による脳神経機能のメカニズムを明らかにすることであり、得られた結果をまとめると以下の通りである。1.メタボトロピック型受容体の中で、mGluR1とmGluR5は共にIP_3細胞内情報伝達系に共役し、細胞内Ca^<2+>を増加させる。mGluR1とmGluR5を発現させた細胞を比較することにより、mGluR5はmGluR1と異なりCa^<2+>の増加がoscillatoryな反応を示すこと、又この反応はプロテインキナーゼCによるmGluR5の特異的なスレオニンの燐酸化によって引き起こされることを明らかにした。さらにastrocyteの培養系を用い、mGluR5は神経細胞においてもoscillatoryなCa^<2+>応答を示すことを明らかにした。以上の結果は、Ca^<2+>のoscillatoryな反応をもたらす標的蛋白を初めて同定し、そのメカニズムを明らかにしたものである。2.yeast two hybrid systemを用い、AMPA型グルタミン酸受容体の中でCa^<2+>の透過に重要な役割を果たすGluR2サブユニットと神経伝達物質の分泌を調整するNSF蛋白が結合することを明らかにした。さらにNSFはAMPA型グルタミン酸受容体のチャンネル活性を抑制することを示し、伝達物質放出の新しい調節メカニズムを明らかにした。
- 著者
- Kei YOSHIMURA Taikan OKI Nobuhito OHTE Shinjiro KANAE
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.5, pp.1315-1329, 2004 (Released:2004-12-17)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 56 86
This study investigated the dynamic motion of atmospheric water advection by an analytic method called colored moisture analysis (CMA), that allows for the estimation and visualization of atmospheric moisture advection from specific source regions. The CMA water transport model includes balance equations with the upstream scheme and, uses external meteorological forcings. The forcings were obtained from the Global Energy and Water Cycle Experiment (GEWEX) Asian Monsoon Experiments (GAME) reanalysis. A numerical simulation with 79 global sections was run for April to October 1998. The results clearly showed seasonal variations in advection associated with large-scale circulation fields, particularly a difference between rainy and dry seasons associated with the Asian monsoon. The paper also proposes a new definition of southwest Asian monsoon onset and decay, based on the amount of water originating from the Indian Ocean. Earliest onset occurs over southeastern Indochina around 16- 25 May. Subsequent onset occurs in India one month later. These results agree with previous studies on the Asian monsoon onset/end. The CMA provides a clearer, more integrated view of temporal and spatial changes in atmospheric circulation fields, particularly Asian monsoon activities, than previous studies that focused only on one or two distinct circulation features, such as precipitation or wind speed. Furthermore, monsoon transition in a specific year, 1998, first became analyzable, whereas the previous studies used climatologies.
- 著者
- 西倉 実季
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学フォーラム (ISSN:18842348)
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.58-65, 2015-09-20
- 著者
- Satow Sir Ernest Ruxton Ian Kornicki Peter
- 出版者
- Lulu.com
- 巻号頁・発行日
- 2008-02-05
1. PRO 30/33 11/2 Satow to Aston (1870-81)|2. PRO 30/33 11/3 Satow to Aston (1882-1909)|3. PRO 30/33 11/5 Satow to Dickins (1877-90)|4. PRO 30/33 11/6 Satow to Dickins (1891-1905)|5. PRO 30/33 11/7 Satow to Dickins (1906-18)
2 0 0 0 福利と自律 : 真正幸福説の検討
- 著者
- 米村 幸太郎
- 出版者
- 成蹊大学法学会
- 雑誌
- 成蹊法学 (ISSN:03888827)
- 巻号頁・発行日
- no.77, pp.174-155, 2012
- 著者
- 成田 和信
- 出版者
- 日本倫理学会
- 雑誌
- 倫理学年報 (ISSN:04830830)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, pp.16-25, 2012
2 0 0 0 レズビアン
- 著者
- ハンス・エバーハート著 阿部孔子訳
- 出版者
- 青弓社
- 巻号頁・発行日
- 1994
2 0 0 0 OA 理科に対する興味の分類
- 著者
- 田中 瑛津子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.23-36, 2015 (Released:2015-08-22)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 4 10
理科における種類の異なる興味を弁別可能な尺度を作成し, それぞれの興味の特徴について検討することを目的とし, 小学5年生から高校1年生まで1,998名を対象とした質問紙調査を行った。結果, 理科に対する興味は「自分で実験を実際にできるから」などの項目からなる「実験体験型興味」, 「実験の結果に驚くことがあるから」などの項目からなる「驚き発見型興味」, 「わかるようになった時うれしいから」などの項目からなる「達成感情型興味」, 「色々なことについて知ることができるから」などの項目からなる「知識獲得型興味」, 「自分で予測を立てられるから」などの項目からなる「思考活性型興味」, 「自分の生活とつながっているから」などの項目からなる「日常関連型興味」, 以上6つに分類されることが示された。また, 「思考活性型興味」や「日常関連型興味」は, 「意味理解方略」や「学習行動」と関連のある重要な種類の興味であるにもかかわらず, どの学年においても他の種類の興味に比べて低い, ということが示唆された。
2 0 0 0 国際比較を通した特別支援教育に関する制度・政策の変遷と現代的課題
- 著者
- 金 珉智 小原 愛子 權 偕珍 下條 満代
- 出版者
- 一般社団法人 アジアヒューマンサービス学会
- 雑誌
- Journal of Inclusive Education
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.40-49, 2019
本稿では、既存の研究等を用いて特別支援教育における制度・政策の変遷について国際的比較を行い、日本の特別支援教育における課題を見出すことを目的とする。学校教育法の一部改正により、2007年からこれまでの特殊教育が変わり、特別支援教育が本格的に実施された。特別支援教育は、日本を含め、世界各国で障害者の権利に関する条約を基に実施されている。日本では、インクルーシブ教育を行うための人的・物的な環境整備等が十分に行われず、理念が先走ったインクルーシブ教育導入への危険性があり、特別支援教育の先進国であるイギリスとイタリアの例を参考にしながらインクルーシブ教育の現状を丁寧に分析していく必要がある。一方、障害児に対する特別支援教育の制度及び政策は、国によって体制が異なるとはいえ、インクルーシブ教育を目指す目標は同一であり、学びの場である学校は特別支援教育の制度において中心的機能をしていることが示された。
2 0 0 0 OA ナメクジ類に寄生するナメクジカンセンチュウ属(和名新称)線虫の国内における感染状況
- 著者
- 脇 司 澤畠 拓夫
- 出版者
- 日本動物分類学会
- 雑誌
- タクサ:日本動物分類学会誌 (ISSN:13422367)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, pp.23-29, 2019-08-31 (Released:2019-09-12)
- 参考文献数
- 33
Nematodes of the genus Phasmarhabditis Andrássy, 1976 (Secernentea: Rhabditida: Rhabditidae) are terrestrial gastropod parasites and mainly target land slugs. In this study, land slugs were surveyed at 14 locations in seven prefectures of Honshu Island, Japan, to determine Phasmarhabditis spp. infection. Juvenile nematodes of unknown species were found in Meghimatium bilineatum Benson, 1842, at five of the 14 locations. The prevalence and mean intensities ranged from 4.5% to 93.3% and from 4.7 to 22.5 nematodes per host, respectively. A total of 881 juveniles were incubated with slug tissues for 2–10 days, and subsequently developed into adult stage showing the diagnostic characteristics of Phasmarhabditis spp. No nematodes were found from slugs of the genus Lehmannia sampled where M. bilineatum were infected, indicating a difference among host species in their sensitivity to the nematodes. Twenty M. bilineatum from Meguro in Tokyo, Japan, where the prevalence in the host population was >90%, were maintained under laboratory conditions. After 23 days, 11 of the 20 slugs died and the cadavers were infected with numerous nematodes. Since three species of Phasmarhabditis nematodes are known to be lethal to terrestrial gastropods, the nematodes we sampled possibly have a lethal effect on the host slugs.
2 0 0 0 OA コスト・ベネフィット比較におけるマン・レムの価値: 文献的検討
- 著者
- 稲葉 次郎
- 出版者
- Japan Health Physics Society
- 雑誌
- 保健物理 (ISSN:03676110)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.109-116, 1977 (Released:2010-02-25)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
As any radiation exposure may involve some degree of risk the International Commission of Radiation Protection recommends that any unnecessary exposure be avoided, and that all doses be kept ALARA, i. e., as low as is readily achievable, economic and social considerations being taken into account. To define the level at which it can be said that a dose is ALARA the use of cost- (or risk-) benefit analysis is required. In making a cost-benefit calculation the most difficult step is the conversion of positive and negative effect into a consistent set of units, i. e., conversion of man-rem into dollars. This paper presents the monetary value of population dose which appeared in the past reports (six papers reffered by ICRP Publication 22, BEIR Report and NRC-10CFR50, App. I).We must be very careful in the application of cost-benefit analysis to decision making of individual cases, but the estimated risk in monetary term may help us at least to check whether we act in a consistent way.
- 著者
- JIN Hao JIN Yi DOYLE James D.
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- pp.2019-011, (Released:2018-11-12)
- 被引用文献数
- 2
Typhoon Nepartak was a category 5 tropical cyclone of 2016 and had significant societal impacts. It went through a rapid intensification (RI), with an increase of maximum wind speed of 51 m s-1 and a decrease of minimum sea level pressure of 74 hPa in 42 h. The real-time forecast from the Coupled Ocean/Atmosphere Mesoscale Prediction System – Tropical Cyclone (COAMPS-TC), starting from 1200 UTC 3 July, predicted the track and intensity reasonably well for Super Typhoon Nepartak and captured the storm’s RI process. Positive interactions among primary and secondary circulations, surface enthalpy fluxes, and mid-level convective heating are demonstrated to be critical for the RI. The storm structure variations seen from the simulated satellite infrared brightness temperature during RI bear considerable resemblance to the Himawari-8 satellite images, although the forecast inner core is too broad, presumably due to the relatively coarse resolution (5 km) used for the real-time forecasts at the time.
2 0 0 0 OA 新撰製図用文字及図譜集
2 0 0 0 IR 翻訳文学史から見る『赤い鳥』と海外作品の〈再話〉
- 著者
- 溝渕 園子
- 出版者
- 日本フランス語フランス文学会 中国・四国支部
- 雑誌
- フランス文学 (ISSN:09125078)
- 巻号頁・発行日
- no.32, pp.52-64, 2019-06-01
本稿は、2018年度日本フランス語フランス文学会中国・四国支部大会(2018年12月2日、於広島大学)のシンポジウム「鈴木三重吉創刊『赤い鳥』とフランス語文学の移入と再話」において、「『赤い鳥』と海外の作家」と題して行った口頭発表の内容を基にしたものである。