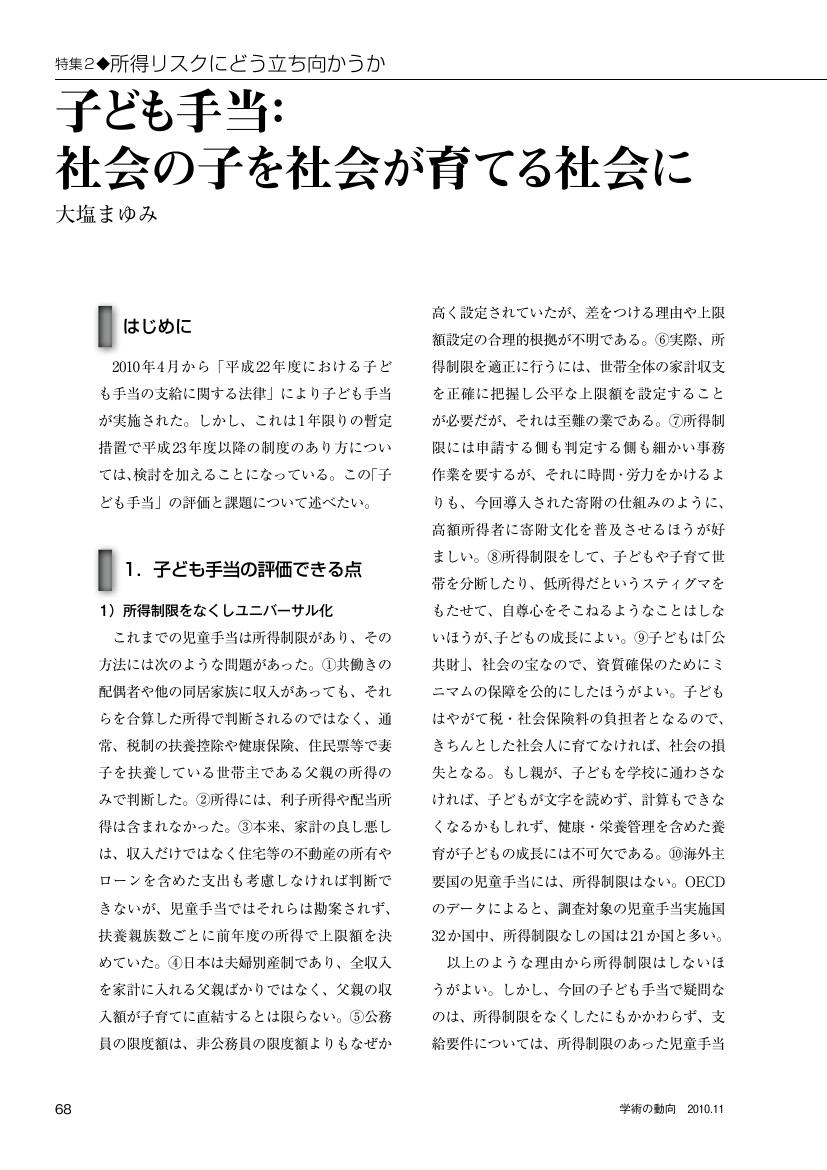1 0 0 0 OA 天然物創薬の再興のために
- 著者
- 佐藤 文治
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.2, pp.127-131, 2014 (Released:2016-04-05)
- 参考文献数
- 5
次世代天然物化学技術研究組合(略称:天然物組合)では,天然物,特に微生物産物からの創薬を長年にわたって手がけてきた大手製薬企業等の組合員企業が,自社で所有している天然物ライブラリーの組合員企業間での相互利用およびアカデミアへの普及拡大(以下,総称して「天然物ライブラリーの相互利用」という)を行い,創薬の研究開発効率を上げようという取り組みを行っている.ライブラリーの作成と維持のような人手と手間がかかる創薬基盤的な技術開発を各社で協力して行い,日本では縮小傾向にある天然物からの創薬を再度活性化させたいという狙いがある.本稿では,主に天然物組合におけるライブラリーの相互利用について述べる.
1 0 0 0 OA リード化合物の構造変化を最小限に留める化学変換による医薬品最適化
- 著者
- 飯倉 仁
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.34-38, 2014 (Released:2016-02-01)
- 参考文献数
- 14
低分子医薬品に求められる性質として,薬効,物理化学的性質(physicochemical property:PCP,水溶性や膜透過性,代謝安定性などの経口投与のために必要な性質群),安全性(変異原性,CYP阻害,一般毒性など)などが挙げられる.これらの性質のうち1つでも基準値に満たないと,医薬品として世に出ることは難しい.低分子創薬の医薬品最適化では,化学修飾を施して1つの性質を改良させると他の性質が悪化して基準値を下回ってしまうことが頻繁に起こる.創薬化学者は多くの時間を,あと一歩のところで臨床開発に値する化合物創出に至らないジレンマとの格闘に費やしている.このようなジレンマを解決する手法として,リード化合物の構造変化を最小限に留める化学修飾の価値は高い.構造変化が小さいため,特定の性質が改良された際の,残りの性質への影響が小さくなる可能性が高いからである.フッ素置換(炭素―水素結合の炭素―フッ素結合への置き換え)は,導入するフッ素原子の近傍に存在する官能基(例えばアミノ基)との相互作用を無視できる場合には,リード化合物の立体的構造変化を最小に留めると同時に,分子全体の極性変化も限定された化学修飾である.本稿では,この長所を活用する手法として,簡便なフッ素スキャン法※1の開発を述べる.本法では,リード化合物の様々な位置にランダムにフッ素原子を導入して最適位置を容易に探索することが可能になる.また,フッ素原子導入の効果を述べるとともに,窒素置換(炭素原子の窒素原子への置き換え)をランダムに行った窒素スキャンとの効果の対比を述べる.窒素置換は立体的な構造変化が小さい点でフッ素置換と類似する一方で,分子全体の極性変化がより大きい点でフッ素置換と対照的である.我々は,フッ素スキャンと窒素スキャンの2つの化学修飾を軸にして,臨床開発化合物1(CH5126766/RO5126766)を創出した.本化合物は,500種類存在するキナーゼの中から,Raf/Ras/MEK/ERK経路を構成する2つのキナーゼであるRafとMEKの機能を特異的に阻害する.
1 0 0 0 OA バイオメディカル境界領域におけるフッ素化学
- 著者
- 尾島 巌
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.11-13, 2014 (Released:2016-02-01)
ファルマシア委員会より本特集号のコラム「挑戦者からのメッセージ」に執筆して欲しいとの依頼があった.このコラムの前例を幾つか送っていただいたが,どうも定年退官時の著名教授あるいは功成り名遂げた社長が研究人生を振り返って,若い世代に激励のメッセージを送るという趣旨のようである.私は68歳になったが,米国の大学には定年がないので完全に現役で,大学院生,博士研究員達と研究教育に励んでいる.しかし考えてみれば,私も若い世代に何かメッセージを残す歳になったのかもしれない.今春米国化学会のフッ素化学賞を受賞したので,この特集号のコラムにちょうどよいと考えられたのであろう.どの程度お役に立つかは分からないが,まず有機フッ素化学のバイオメディカル分野での現状について簡単に述べ,その後,30年以上にわたる私とフッ素化学との触れ合い,研究テーマ,研究戦略の変遷等について述べたい.
1 0 0 0 OA 生合成工学による創薬
- 著者
- 阿部 郁朗
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.6, pp.509-511, 2014 (Released:2016-07-02)
- 参考文献数
- 5
今後の医薬資源の開発について考えた場合,多様性に富む化合物群をいかに効率よく生産し,創薬シードとして提供できるかが鍵になる.学生時代,モルヒネやペニシリンなどの薬用天然物に魅せられて以来30年,一貫して天然物の生合成研究に取り組んできた.生物がどのようにしてあの複雑で多様な二次代謝産物の構造を作り上げるのか? 生物のものづくりの仕組みを解き明かし,更に利用,改変することで創薬に生かすことができれば,との思いからである.
1 0 0 0 OA ネイチャー・テクノロジー事始
- 著者
- 石田 秀輝
- 出版者
- 公益社団法人 日本金属学会
- 雑誌
- まてりあ (ISSN:13402625)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.4, pp.156-159, 2009 (Released:2012-09-21)
- 参考文献数
- 16
- 著者
- Hassan Mohamed Elsangedy Kleverton Krinski Daniel Gomes da Silva Machado Pedro Moraes Dutra Agrícola Alexandre Hideki Okano Sergio Gregório da Silva
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.6, pp.1795-1800, 2016 (Released:2016-06-24)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 15
[Purpose] This study examined the exercise intensity and psychophysiological responses to a self-selected resistance training session in sedentary male subjects. [Subjects and Methods] Twelve sedentary male subjects (35.8 ± 5.8 years; 25.5 ± 2.6 kg·m2) underwent four sessions at 48-h intervals: familiarization; two sessions of one repetition maximum test and a resistance training session in which they were told to self-select a load to complete 3 sets of 10 repetitions of chest press, leg press, seated rows, knee extension, overhead press, biceps curl, and triceps pushdown exercises. During the latter, the percentage of one repetition maximum, affective responses (feeling scale), and rating of perceived exertion (OMNI-RES scale) were measured. [Results] The percentage of one repetition maximum for all exercises was >51% (14–31% variability), the rating of perceived exertion was 5–6 (7–11% variability), and the affective responses was 0–1 point with large variability. [Conclusion] Sedentary male subjects self-selected approximately 55% of one maximum repetition, which was above the intensity suggested to increase strength in sedentary individuals, but below the recommended intensity to improve strength in novice to intermediate exercisers. The rating of perceived exertion was indicative of moderate intensity and slightly positive affective responses.
1 0 0 0 OA 母性遺伝・ミトコンドリアDNAを指標とした人類の分子進化解析
- 著者
- 宝来 聰
- 出版者
- 日本動物遺伝育種学会
- 雑誌
- 動物遺伝研究会誌 (ISSN:09194371)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.Supplement, pp.10-15, 1997-11-10 (Released:2010-03-18)
- 参考文献数
- 19
アフリカ人, ヨーロッパ人, 日本人と4種の類人猿のミトコンドリア遺伝子の全塩基配列を解析した.オランウータンとアフリカ類人猿の分岐年代 (1, 300万年前) のもとでは, ヒトとチンパンジーが490万年前に分岐したという結果が得られた.この分岐年代に基づいて推定した同義座位およびDループ領域における置換速度を用いることにより, ヒトmtDNAの最後の共通祖先の年代は143, 000±18, 000年前と推定され, 現生人類ホモサピエンスのアフリカ起源説が強く支持された.
- 著者
- Hiroki TSUJI Hisanori ITOH Kensuke NAKAJIMA
- 出版者
- (公社)日本気象学会
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.3, pp.219-236, 2016 (Released:2016-07-02)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 15
To understand the basic mechanism governing the size evolution of tropical cyclones (TCs), we systematically perform numerical experiments using the primitive equation system on an f-plane. A simplified, TC-like vortex is initially given and an external forcing mimicking cumulus heating is applied to an annular region at a prescribed distance from the vortex center. Moist process and surface friction are excluded for simplification. We focus on the sensitivity of size evolution to the location of the forcing. The vortex size is defined as the radius of 15 m s-1 lowest-level wind speed (R15). The evolution of R15 depends on the forcing location, and its dependence can be understood by considering radial transport of the absolute angular momentum (AAM) at R15 due to the heat-induced secondary circulation (SC), whose structure is governed by the distribution of inertial stability. When the forcing is applied to the outer part of a vortex but still inside R15, where inertial stability is weak, the SC extends to the outside of R15 and carries AAM inward. Thus, R15 increases. Conversely, when the forcing is applied near the center of the vortex, where inertial stability is strong, the SC closes inside R15 and R15 hardly increases. These results indicate that extension of the heat-induced SC to the outside of R15 is important for the evolution of the vortex size. Moreover, the further beyond R15 the SC extends, the more the vortex size increases. This relationship is consistent with the result of the parcel trajectory analysis; the larger the extent of SC, the longer distances the parcels cover, conserving larger AAM. Finally, when the forcing is applied to the outside of R15, smaller AAM is carried outward by the SC on the inward side of the heating location, resulting in the decrease of R15.
1 0 0 0 OA 食品産業廃棄物と家庭系食品廃棄物の実態とそのゆくえ
- 著者
- 牛久保 明邦
- 出版者
- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会
- 雑誌
- 廃棄物学会誌 (ISSN:09170855)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.4, pp.216-227, 2003-07-31 (Released:2010-05-31)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 4 6
食品から排出される廃棄物は, 生産・流通の段階のみならず消費段階における家庭から発生する廃棄物が, 食品廃棄物総排出量の半分以上を占めている。このような状況のなか, 食品リサイクル法が施行され食品廃棄物の発生を抑制し, 資源として有効に活用する循環型社会の形成が求められている。そこで, 食品製造業から発生する食品産業廃棄物と家庭から発生する家庭系食品廃棄物の実態を明らかとするために調査を実施した。食品産業廃棄物中の汚泥排出量は, わが国の汚泥排出総量の3.1%を占め, 動植物性残さは動植物性排出総量の78.2%に達していることが明らかとなった。また, 家庭系食品廃棄物の内, 調理くずと食べずに捨てられるものが廃棄物の発生重量の70%を占めていた。家庭系食品廃棄物の家庭内でのリサイクルには困難さが多く, 発生抑制や分別の徹底が資源として活用する上で重要である。
1 0 0 0 OA 高血圧自然発症ラットに対する大麦黒酢の血圧降下作用
- 著者
- 小田原 誠 荻野 裕司 瀧澤 佳津枝 木村 守 中村 訓男 木元 幸一
- 出版者
- 社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.81-86, 2008-03-15 (Released:2008-04-30)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1 1
大麦黒酢,大麦糖化液,酢酸を高血圧自然発症ラット(SHR)に与え,大麦黒酢が血圧に与える影響について調べた.その作用機序の検討としてin vitroにおけるアンジオテンシンI変換酵素(ACE)阻害活性の測定を行った.また,酸度とエキス分を等しくした大麦黒酢と米黒酢について,SHRを用いた単回投与試験を行い,血圧降下作用を比較した.(1)単回投与試験,連続投与試験のいずれにおいても,大麦黒酢は蒸留水(対照)と比較して有意に血圧を降下させることが示された.これにより,大麦黒酢は血圧降下作用を有することが明らかとなった.(2)連続投与試験において,酢酸だけでなく大麦糖化液においても血圧降下作用が認められたことから,大麦黒酢の血圧降下作用は,酢酸と大麦由来の成分の両方によるものと考えられた.(3)大麦糖化液ならびに中和した大麦黒酢においてACE阻害活性が認められたことから,大麦黒酢には大麦由来の血圧降下作用物質が含まれ,ACEを阻害することで血圧上昇を抑制していることが示された.(4)酸度とエキス分が等しくなるように調製した大麦黒酢と米黒酢について,SHRを用いた単回投与試験を行った.大麦黒酢と米黒酢はどちらも対照と比較して有意に血圧が降下しており,今回の実験では大麦黒酢の方が血圧降下の程度が高かった.このことから,大麦黒酢は米黒酢と同等以上の血圧降下作用を有することが示された.
1 0 0 0 OA 往来 人口減少社会のゆくえ
- 著者
- 原 俊彦
- 出版者
- 北海道社会学会
- 雑誌
- 現代社会学研究 (ISSN:09151214)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.35-44, 2015 (Released:2016-07-02)
- 参考文献数
- 17
1 0 0 0 OA 家族戦略?
- 著者
- 武川 正吾
- 出版者
- 日本家族社会学会
- 雑誌
- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.43-51, 2013-04-30 (Released:2014-11-07)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 2 1
この報告は,家族戦略論のなかに公共政策を新しい変数として導入することを提案する.家族戦略の「構造的諸条件」の多くが公共政策の決定の結果として生み出されているからである.他方で,個々の家族戦略の集積の結果として,これらの「構造的諸条件」は単純再生産されたり,拡大再生産されたり,構造自体が変化する場合もある.日本も他の先進諸国と同様,グローバル化と個人化の影響を受けている.しかしその影響が他国と同様に純粋的な形で現れないのは,日本では「家族」が緩衝地帯としての役割を果たしているからである.このようなことが可能となった背景には,日本の福祉レジームの存在がある.しかし,その家族そのものの数が現在減少しつつある.家族変動に対する公共政策の影響は,これまで十分に評価されてきたとはいえない.しかし,公共政策の最初の一撃は,家族変動を含む社会変動にとって重要である.家族戦略と公共政策との間の正のスパイラルを確立するために,現在の日本では「公共政策による最初の一撃」が求められている.
1 0 0 0 OA 子ども手当: 社会の子を社会が育てる社会に
- 著者
- 大塩 まゆみ
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.11, pp.11_68-11_71, 2010-11-01 (Released:2011-01-20)
- 参考文献数
- 9
- 著者
- 本田 孝志
- 出版者
- 日本高圧力学会
- 雑誌
- 高圧力の科学と技術 (ISSN:0917639X)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.149-156, 2016 (Released:2016-06-21)
- 参考文献数
- 28
In this article, we introduce our recent high-pressure study on magnetism and multiferroicity in olivine-type Mn2GeO4. This compound shows successive magnetic transitions at ambient pressure and a ferroelectric ground state driven by spin-spiral order, i.e., a multiferroic state. The multiferroicity under high pressure was taken by using a recently constructed measurement system equipped with a diamond anvil cell. The pressure evolution of the magnetic structures was investigated with powder and single-crystal neutron scattering experiments using a Paris-Edinburgh press. We found that the ferroelectricity in the lowest-temperature phase disappears at 6 GPa where an incommensurate-commensurate magnetic phase transition is observed. The origin of the pressure-induced transition is discussed. Some details of the high-pressure experimental techniques will be also presented.
- 著者
- 岡本 佳男 毛利 晴彦 中村 雅昭 畑田 耕一
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 日本化学会誌 (ISSN:03694577)
- 巻号頁・発行日
- vol.1987, no.3, pp.435-440, 1987-03-10 (Released:2011-05-30)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 4 7
光学活性なポリ(メタクリル酸トリフェニルメチル)(PTrMA)を3種の異なる方法で大孔径シリカゲルに化学結合させ,高速液体クロマトグラフィー用のキラルな充填剤を調製した。その結果,メタクリル酸トリフェニルメチルとメタクリル酸3-(トリメトキシシリル)プロピルとのブロック共重合体を用いるともっとも多量のPTrMAをシリカゲルに化学結合できることが明らかになった。メタノールを溶離液に用いた場合の種々のラセミ体に対する光学分割能は,従来までのPTrMA担持型充填填剤と類似していた。また,この化学結合型充填剤ではPTrMAが溶解するテトラヒドロフランやクロロホルムといった溶離液も使用可能であった。クロロホルムを溶離液に用いて,(±)-PTrMAを(+)体と(-)体に部分的に光学分割することができた。また,ラジカル重合で得られたポリ(メタクリル酸ジフェニル-2-ピリジルメヂル)も光学分割でき,このポリマーがらせん構造を有していることがわかった。化学結合型充填剤はGPC用の充填剤としての性質も有していた。分子量数千から百万までの単分散ポリスチレンを分析すると,分子量の対数値と溶出時間との間によい直線関係が得られた。
1 0 0 0 OA 不随意運動を主徴とし,両側大脳基底核病変を呈したビタミンB12欠乏症の1例
- 著者
- 北村 泰佑 後藤 聖司 髙木 勇人 喜友名 扶弥 吉村 壮平 藤井 健一郎
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- pp.cn-000884, (Released:2016-06-30)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 4
患者は86歳女性である.入院1年前より認知機能低下を指摘され,入院2週間前より食思不振,幻視が出現し,意識障害をきたしたため入院した.四肢に舞踏病様の不随意運動を生じ,頭部MRI拡散強調画像で両側基底核は左右対称性に高信号を呈していた.血液検査ではビタミンB12値は測定下限(50 pg/ml)以下,総ホモシステイン値は著明に上昇,抗内因子抗体と抗胃壁細胞抗体はともに陽性であった.上部消化管内視鏡検査で萎縮性胃炎を認めたため,吸収障害によるビタミンB12欠乏性脳症と診断した.ビタミンB12欠乏症の成人例で,両側基底核病変をきたし,不随意運動を呈することはまれであり,貴重な症例と考え報告する.
1 0 0 0 OA グローバル時代のシティズンシップ教育—問題点と可能性:民主主義と公共の論理—
- 著者
- 池野 範男
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.2, pp.138-149, 2014 (Released:2015-06-18)
- 参考文献数
- 46
- 被引用文献数
- 2
本稿では、現代のグローバル社会におけるシティズンシップ教育を構成員教育の一形態と考え、構成員教育の類型化を行い、現代のシティズンシップ教育の位置を特定化する。その上で、現代のシティズンシップ教育の多様な形態を整理し、3タイプに大別し、それぞれの課題と可能性を検討する。その結果、現代に求められているシティズンシップ教育は、これまでの目標であった市民になるや市民に育てることではなく、公共空間を形成する人を作り出すことを目標にしていると主張する。
1 0 0 0 OA 朝鮮時代仏教歌辞に現らわれた浄土信仰
- 著者
- 趙 明烈
- 出版者
- JAPANESE ASSOCIATION OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.857-853, 1998-03-20 (Released:2010-03-09)
1 0 0 0 OA 総合型地域スポーツクラブ政策の地域的「転換」過程
- 著者
- 嘉門 良亮
- 出版者
- 日本スポーツ社会学会
- 雑誌
- スポーツ社会学研究 (ISSN:09192751)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.63-78, 2016-03-25 (Released:2016-04-25)
- 参考文献数
- 40
今日、総合型地域スポーツクラブ関連のものを筆頭にスポーツ振興政策は地域で支えるものという位置づけがなされ、地域での量的拡大を既に終えた。総合型クラブがスポーツを通じて「新しい公共」を担い、コミュニティの核となるということが標榜され、推奨されてきた。しかし、スポーツ振興政策はスポーツ組織と地域の生活課題、社会構造・生活構造の関係を考察してこなかった。なぜならスポーツの「界」は地域の生活課題の解決をあくまでスポーツ振興の手段や必要条件としかみなして来なかったからである。 こうした問題意識を基に本稿は、少子高齢化と人口減少による縮小化に対応を迫られる企業城下町である茨城県日立市の滑川地区を事例に、総合型地域スポーツクラブと地域コミュニティ組織の関係から地域における生活課題とその対応を明らかにした。その上で、地域の実情に合わせて総合型クラブを改変することの意味を論じた。 本稿の事例から明らかになったのは、上からのスポーツ振興政策に対し、地域住民が戦略的に読み替えを行い、総合型クラブを自らの生活課題に対応するための実務的な組織として運営していく取り組みであった。すなわち、既存の小学校区での地域コミュニティ活動の流れを汲みつつ、高齢者の生活問題などの課題に対応していく総合型クラブの姿であった。総合型クラブと住民組織の間には大きな性質の差異が認められつつも、その協力関係は、スポーツ振興と地域自治を繋ぐ一つの方策として機能していた。 また、スポーツ振興を前提として地域に押し付けるのではなく、地域社会の文脈を継続的に読み取る必要性が明らかになった。
- 著者
- 佐々木 俊則 大島 有美子 三島 江津子 伴 晶子 桂川 健司 永松 秀紹 吉岡 祐貴 築山 郁人 久田 達也 板倉 由縁 水谷 三浩
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.136, no.7, pp.1023-1029, 2016 (Released:2016-07-01)
- 参考文献数
- 15
It is often necessary to modify the dose or schedule of eribulin mesilate (Eri) because of adverse events. Therefore, we retrospectively investigated the optimal approach for Eri dose adjustment and/or dosage interval adjustment. Patients who received Eri at the institutions affiliated with the Division of Oncology of the Aichi Prefectural Society of Hospital Pharmacists between July 2011 and November 2013 were enrolled in this study. We compared the group that underwent dose reduction without changes to their dosage interval (dose reduction group) with the group that had a change in their dosage interval (dose-interval prolongation group). The primary end-point was time to treatment failure (TTF), and the secondary end-points were overall survival (OS), overall response rate (ORR), clinical benefit rate (CBR), and adverse events. The TTF and OS of the dose reduction group were approximately two times longer than those of the dose-interval prolongation group. In addition, the dose reduction group had significantly improved ORR and CBR, which together indicate an antitumor effect (p=0.013 and 0.002, respectively). Although peripheral neuropathy occurred significantly more frequently in the patients in the dose reduction group (p=0.026), it was grade 1 and controllable in most of the cases. There were no differences in the occurrence of other adverse effects between the two groups. Therefore, we suggest that dose reduction with maintenance of the dosage interval is the preferred treatment approach in cases where Eri dose or schedule modification is necessary.