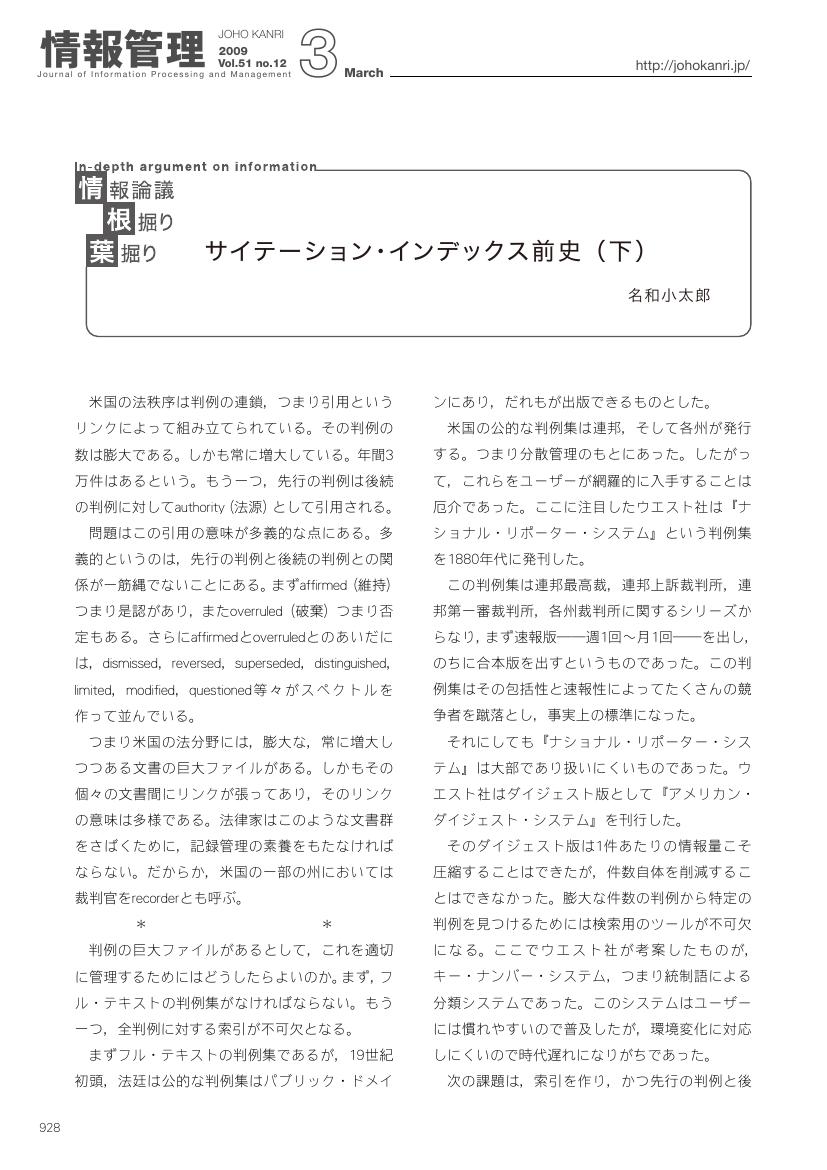1 0 0 0 OA UK COM遺伝毒性ガイダンス(翻訳)
1 0 0 0 OA 2. 映像ダイジェスト配信システム「チョコパラTV」
- 著者
- 日高 浩太 宮下 直也 藤川 勝 湯口 昌宏 佐藤 隆
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.12, pp.1885-1888, 2006-12-01 (Released:2008-12-01)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA サイテーション・インデックス前史(下)
- 著者
- 名和 小太郎
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.12, pp.928-929, 2009 (Released:2009-03-01)
1 0 0 0 OA 学術情報流通の促進に向けて
- 著者
- 太田 暉人
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.12, pp.924-927, 2009 (Released:2009-03-01)
- 参考文献数
- 5
- 著者
- Hideo SUZUKI
- 出版者
- ACOUSTICAL SOCIETY OF JAPAN
- 雑誌
- Acoustical Science and Technology (ISSN:13463969)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.3, pp.163-166, 2000 (Released:2001-01-31)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 2 4
A single-degree-of-freedom(SDOF) system with a mass(m), a spring(k), and a damping(c) is a basic mechanical system.It is well known that a complex mechanical system is represented by a combination of infinite number of SDOF systems.The modal analysis theory is based on this principle, but only one type among various types of SDOF systems is presently employed for a modeling of complex systems.When one needs to estimate m, k, and c of a SDOF system from the measurement of the resonance frequency and the loss factor, the relationships between them must be exactly known.Those relationships are known for commonly used SDOF systems, but those for rather unfamiliar types are not known.In this technical report, various types of SDOF systems and their equivalent electrical circuits are listed, and equations that relate the resonance frequencies to the undamped resonance(natural) frequencies and the loss factors are given.It is also shown that, for some type of SDOF systems, some cares must be taken how to interpret the loss factor.
1 0 0 0 OA Byssochlamys spp. 同定のための遺伝子指標の評価
- 著者
- 渡辺 麻衣子 加藤 裕子 戸上 敬子 山中 実喜子 若林 佳子 小川 裕由 稙田 裕子 後藤 慶一 工藤 由起子 天野 典英 横田 明
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.82-87, 2008-04-30 (Released:2008-05-26)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 4 3
Byssochlamys spp. について,簡便,迅速かつ正確に種を同定するために有効な遺伝子指標を評価する目的で,26株のByssochlamys spp. および関連菌種の18S rDNA, 26/28S rRNA遺伝子D2領域およびlys2 の塩基配列を決定し,分子系統解析および相同性解析を行った.その結果,いずれの遺伝子を用いても,その塩基配列の相同性を指標として,それぞれの菌種あるいはグループを識別することができた.3種類の遺伝子のうち,最も優れた解像度を有するのはlys2 であったが,最も簡便に結果を得ることができたのは26/28S rDNA D2領域であった.また,分子系統解析の結果,Byssochlamys spp. とその関連菌種は再分類の必要性があることが示唆された.
1 0 0 0 OA SRU/SRWを用いた教育図書館資料の書誌検索システムの構築
- 著者
- 江草 由佳 高久 雅生
- 出版者
- 情報知識学会
- 雑誌
- 情報知識学会誌 (ISSN:09171436)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.69-74, 2007 (Released:2007-06-27)
- 参考文献数
- 13
日本語書誌データを対象としてSRU/SRWプロトコルに対応した書誌検索システムを開発した。国立教育政策研究所教育図書館が提供している「教育研究論文索引」の日本語論文書誌データ約12万件を対象とし,さらに同図書館OPACログデータを元にしたテストクエリセットを作成し,これらの検索がSRU/SRWを通じて行えるかを確認するとともに,実運用規模における検索システムの可能性について考察した。
1 0 0 0 OA 歩行現象の力学原理から見たヒトの歩行
- 著者
- 佐野 明人 池俣 吉人 藤本 英雄
- 出版者
- バイオメカニズム学会
- 雑誌
- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.3, pp.119-122, 2006 (Released:2008-06-06)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1 1 4
受動歩行は,歩行機のもつダイナミクスと環境との相互作用のみによって,理想とする自然な歩容を形成する.特に,安定したリミットサイクルが存在するという重要な特徴をもつ.状態がリミットサイクル上を遷移する限り歩行は安定となる.歩行は物理現象そのものであり,ヒトは歩行現象を移動原理として巧く使っているのではないか.本稿では,歩ける原理として,受動歩行の平衡点の力学的構造ならびに安定メカニズムを紹介し,この力学原理からヒトの歩行を概観する.
1 0 0 0 OA 現場のこころ
- 著者
- 朝日 雅也
- 出版者
- バイオメカニズム学会
- 雑誌
- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.67-71, 2004 (Released:2005-02-23)
- 参考文献数
- 9
心身の機能に障害があっても,あるいは老化に伴い介護を必要とする状態になっても,その人らしく地域の中で当たり前に暮らしていく.そんなノーマライゼーションの実現が強く求められている.そのために,様々な生活課題を解決する働きかけが実践されている.その際には,サービスの利用者を中心に据えた,利用者の思いに沿った支援が必要である.そして,利用者の真のニーズを反映するのが現場のこころである.様々な生活課題に関連した現場のこころは,今日的には,自立の支援,個別性に基づく支援,コミュニケーションの重視といった点から捉えることができる.現場のこころに向き合った支援こそ,ノーマライゼーションの実現のための推進力となりえる.対人援助に関わる人々は,現場のこころの理解を出発点とした支援のあり方を希求しなければならない.
1 0 0 0 OA 高齢者ケアとコンピュータ・アートセラピー
- 著者
- 齋藤 佐智子
- 出版者
- バイオメカニズム学会
- 雑誌
- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.55-58, 2006 (Released:2008-01-18)
- 参考文献数
- 7
アートセラピーは治療的な自己表現の一環として,心理臨床現場や,保育・教育現場,または地域などさまざまな環境や状況下で行われている.現代社会は,幼児・児童虐待,いじめ,引きこもり,家庭不和,離婚,社会不適応,リストラ,高齢化など,多くの問題を内包しており,言語的な関わりのほかにも諸アートを媒介とした療法を十分な理解のもと,適切に提供・利用する必要性がある.本稿では,筆者の臨床現場での経験をもとに,日本社会における課題のひとつである高齢者ケアに着目し,今日行われている高齢者アートセラピーと,アートセラピーの新しい可能性として考えられるコンピュータ利用について論じる.
1 0 0 0 OA ウェーブレット変換を用いるアンペロメトリックバイオセンサーの電流応答解析
- 著者
- 四反田 功 板垣 昌幸 河合 大輔 渡辺 邦洋
- 出版者
- 公益社団法人 日本分析化学会
- 雑誌
- 分析化学 (ISSN:05251931)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.183-189, 2008 (Released:2008-03-24)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 2 2
アンペロメトリックバイオセンサーの電流応答をウェーブレット変換を用いて解析した.グルコースバイオセンサーと過酸化水素バイオセンサーの2種類を作製した.グルコースバイオセンサーには,グルコースオキシダーゼをポリイオンコンプレックスで固定化した電極を用いた.アンペロメトリーによってグルコースを添加したときの酸素還元電流の減少値を測定した.測定した電流応答をウェーブレット変換したところ,ノイズに埋もれた応答を抽出することができた.シグナルノイズ比は最大で9倍に向上した.ウェーブレット変換を施すことでセンサーの検出下限は3倍になった.過酸化水素バイオセンサーには,西洋ワサビペルオキシダーゼをポリピロール膜によって固定化した電極を用いた.過酸化水素の応答は,ポリピロールの還元電流値から評価した.過酸化水素バイオセンサーの検出下限を5倍向上させることができた.
1 0 0 0 OA NPYと関連神経ペプチドの機能的相互作用と摂食調節
- 著者
- 上野 浩晶 中里 雅光
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.127, no.2, pp.73-75, 2006 (Released:2006-04-01)
- 参考文献数
- 9
近年,肥満者の増加と,肥満を基礎にして発症する糖尿病,脂質代謝異常,高血圧症などの肥満症やメタボリックシンドロームを呈する患者数が増加している.しかし,その根底にある肥満の治療法は不十分なままである.最近,NPYやそのファミリー(PP,PYY)を含めてさまざまな摂食調節物質の同定や機能解析が進んでいる.NPYは中枢神経系に存在しており,強力な摂食亢進作用を有している.NPYニューロンを活性化する入力系としてグレリンやオレキシン,抑制する入力系としてレプチンやインスリンがある.入力系の中でも胃から分泌される摂食亢進ペプチドであるグレリンは迷走神経や神経線維を介してNPYニューロンにシグナルを伝達してその作用を発揮している.PPは主に膵臓に発現しており,摂食抑制作用を有する.PYYは十二指腸から結腸までの腸管で産生され,摂食抑制作用を有する.PYYは迷走神経を介して中枢の摂食抑制系ペプチドであるPOMCニューロンを活性化してその作用を発揮している.これら摂食調節ペプチドの機能解析が進んで,ペプチドそのものや受容体のアゴニスト,アンタゴニストといった新規の抗肥満薬の開発や実用化が期待される.
1 0 0 0 OA 適応ギャップがユーザのエージェントに対する印象変化に与える影響
- 著者
- 小松 孝徳 山田 誠二
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.232-240, 2009 (Released:2009-01-22)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 10 6
We describe an ``adaptation gap'' that indicates the differences between the functions of artificial agents users expect before starting their interactions and the functions they perceive after the interactions. We investigated the effects of this adaptation gap on users' impressions of the artificial agents because any variations in impressions before and after the start of an interaction determine whether the user feels that this agent is worth continuing an interaction. The results showed that the positive or negative signs of the adaptation gap and the subjective impression scores of the agents before the experiment affected the final users' impressions of the agents significantly.
1 0 0 0 OA 酪酸プロピオン酸ベタメタゾン軟膏の混合が及ぼす防腐効果への影響
- 著者
- 大谷 道輝 中井 達郎 大沢 幸嗣 金 素安 松元 美香 江藤 隆史 假家 悟 加野 象次郎 内野 克喜
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.122, no.12, pp.1153-1158, 2002-12-01 (Released:2003-02-18)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 10 12
Twenty percent of dermatologists have experienced a separation of water or deterioration of topical corticosteroids mixed with commercially available ointments and/or creams. However, few investigations of this deterioration of admixtures have been reported. To assess the effects of preservatives in preventing microbial contamination of these admixtures, we attempted to investigate the concentration of preservative agents in admixtures and the microbial contamination of these admixtures with a topical corticosteroid ointment (Antebate®). The concentration of parabens was reduced by half using an admixture of corticosteroid ointment with four types of moisturizing creams, Urepearl, Pastaronsoft, Hirudoid, and Hirudoidsoft. After a further 3 months, no decrease in parabens was seen. No microbial contamination was found in any admixture stored at room temperature for 1 week and touched two times daily with a finger. The concentration and ratio of the parabens in the aqueous phase and oil phase were entirely different in the admixtures before being centrifuged. The aqueous phase of the admixtures of the oil/water (O/W)-type emulsions of Urepearl and Hirudoid was not found to have microbial contamination immediately after being centrifuged. All aqueous phases stored at room temperature or in a refrigerator for 1 week and touched with a finger twice daily exhibited microbial contamination. These experiments demonstrated that O/W-type emulsions, in which the water easily separates from the bases, should be thoroughly mixed to prevent microbial contamination.
- 著者
- Mika Kobayashi Kenji Inoue Eiji Warabi Takashi Minami Tatsuhiko Kodama
- 出版者
- 一般社団法人 日本動脈硬化学会
- 雑誌
- Journal of Atherosclerosis and Thrombosis (ISSN:13403478)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.3, pp.138-142, 2005 (Released:2005-07-13)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 69 195
In the study of vascular biology, analyses of endothelial cells (EC) and smooth muscle cells (SMC) are very important. The mouse is a critical model for research, however, the isolation of primary EC from murine aorta is considered difficult. Previously reported procedures for the isolation of EC have required magnetic beads, or Fluorescence Activated Cell Sorting (FACS) to purify the cells. In addition, these procedures were applied to the heart, eyeball, or lung, not the aorta. Therefore we developed a simple method of isolating EC or SMC from the murine aorta without the need for any special equipment. To verify the purity of the cell culture, we performed both an immunofluorescence study and a DNA microarray analysis. The immunofluorescence study demonstrated specific expression of PECAM-1 in isolated EC cultures. In contrast, the isolated SMC didn’t exhibit PECAM-1, but rather, smooth muscle actin. The DNA microarray analysis demonstrated the expression of EC (16 genes) or SMC (5 genes) specific genes in each cell. This is due to the fact that pure EC or SMC can be isolated from the aorta, without the use of any special equipment. These results suggest that this method should be particularly useful for vascular biological research.
1 0 0 0 OA サブジェクトライブラリアンの重要性
- 著者
- 飯野 弘之 竺 覚暁
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.10, pp.766-779, 1999 (Released:2001-04-01)
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 問診票による口臭を主訴とした患者の分析
- 著者
- 福田 光男 有川 千登勢 村上 多恵子 坂井 誠 岩見 知弘 吉野 京子 大塚 亜希子 竹田 英子 中垣 晴男 野口 俊英
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本歯周病学会
- 雑誌
- 日本歯周病学会会誌 (ISSN:03850110)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.101-110, 2004 (Released:2005-09-30)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 1 3
本研究は, 口臭外来を受診した756名の患者の問診票を分析することにより, 口臭を主訴とする患者の心理的背景を読み取り, 患者対応を的確にすることを目的とした。口臭を意識したきっかけは, 63.6%が 「人に指摘されて」であり, 「人の仕草や態度で」33.7%, 「自分で気がついた」33.5%であった。口臭を指摘した相手は, 配偶者, 子供, 友人の順であった。口臭を感じる時間帯は 「起床時」が最も多く, 「一日中」「空腹時」「仕事中」「疲労時」と続いた。口臭を意識する時として 「対話中」が最も多く, ついで 「対話中の相手の態度を見た」「常に」「混んだ場所や狭い場所にいる」であった。口臭のため困ることでは 「話をするとき」が最も多く, ついで 「消極的になる」「人と一緒に行動できない」「物事に集中できない」の順であった。口臭に関する相談相手がいないと回答した人が半数以上みられた。また, 人からの指摘はなく自分で口臭に気づいたというケースでは, 人に口臭を指摘されて来院したケースより, 「消極的になる」「人と一緒に行動できない」「物事に集中できない」などの回答が有意に多かったことから, より生活上の制約を感じていることが示唆された。以上より口臭を主訴とする患者を診察する場合, 口臭を他人の態度や自分で気づいたと訴えるケースや, 相談相手がいないケースに, 患者の心理的背景まで考慮した対応が必要となってくると推察される。
1 0 0 0 OA Web上の学術情報資源におけるメタデータの利用
- 著者
- 齋藤 絵理 小野寺 夏生
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.174-174, 2001 (Released:2001-06-01)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 3 3
Web上において,高品質な学術情報資源を提供するサービスがQuality Controlled Subject Gateway (QCSG) である。ここでは,自然科学を主題分野とする国内外のQCSG(25機関)を対象とし,開発機関や内容記述に用いられるメタデータエレメントの特徴,QCSG間の標準化動向を調査した。開発機関は大学図書館や個人による単独のものが主であり,特徴のあるエレメントとしてはDublin Core,IAFA templateでは定義されていない“Level”が目立った。内容記述の標準化は理想的な目標とされているが,各機関の認識の相違などにより達成には至っていない。
1 0 0 0 OA 分子クラウディング環境は生命分子の物性と機能をいかに変えるか
- 著者
- 中野 修一 杉本 直己
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.5, pp.251-256, 2006 (Released:2006-09-25)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 1
The medium of biomolecules in a living cell differs remarkably from a dilute solution, and many properties of biomolecules that are not observed in vitro are emerged as a result of such intracellular environments. Molecular crowding which is one of the important intracellular environments changes equilibria and rates of biomolecular interactions. Studies with solutions containing high concentration of water-soluble inert cosolutes reveal influences of the molecular crowding on the structures and interactions of proteins and nucleic acids, providing significant insights not only into traditional biology but also bionanotechnology.
1 0 0 0 OA 店舗におけるユーザ体験評価の枠組み - 感性・視線・インタラクション
- 著者
- 田丸 恵理子 廣瀬 吉嗣 蓮池 公威 大山 努
- 出版者
- Japanese Society for the Science of Design
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集
- 巻号頁・発行日
- pp.F18, 2004 (Released:2005-06-15)
インターネットの普及によって、仮想スペース上での商品の売買がさかんになる一方、物理的な店舗空間の意味の再考が求められている。店舗は単に商品を売るという場所から、新しいサービスを提供する場へと変化が求められている。このような背景から考えると、店舗を評価する際、「ユーザ体験」という観点からの捉えなおしが必要となってくるであろう。店舗という空間は、単に建造物そのものとして成り立っているのではなく、むしろ、人と空間とのインタラクションで構築されていると言える。それゆえに、空間のデザインや評価は、物理的な空間を評価することではなく、そこでのユーザの体験を評価することである。このような観点から、われわれは感性評価、視線分析、インタラクション分析を融合し、店舗のような空間でのユーザ体験を評価・分析するフレームワークを提案する。さらに、本フレームワークを、新しいコンセプトに基づいて構築された銀行の試験店舗に適用し、この店舗空間がどのような顧客の新しい体験を創出できるのかを評価した。この結果から、本フレームの有効性を確認した。