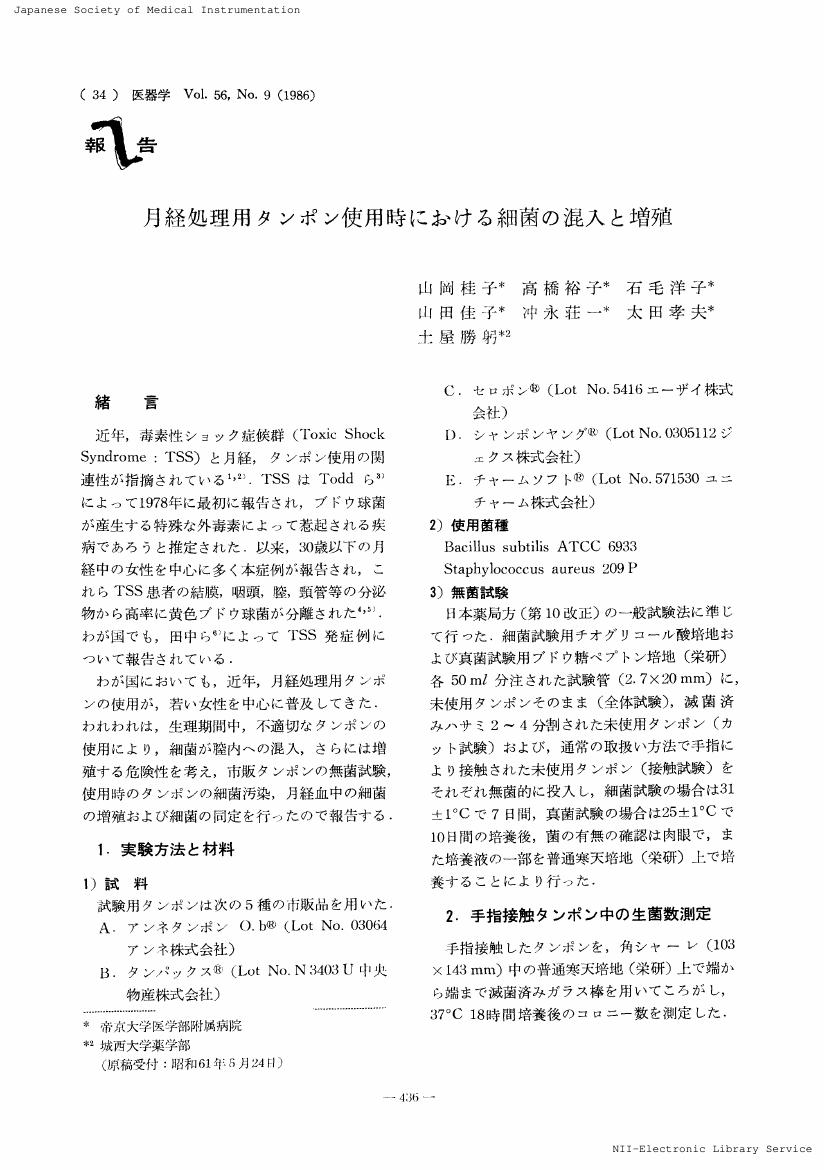37 0 0 0 OA 月経処理用タンポン使用時における細菌の混入と増殖
- 著者
- 山岡 桂子 高橋 裕子 石毛 洋子 山田 佳子 冲永 荘一 太田 孝夫 土屋 勝躬
- 出版者
- 一般社団法人 日本医療機器学会
- 雑誌
- 医科器械学 (ISSN:0385440X)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.9, pp.436-439, 1986-09-01 (Released:2021-05-17)
7 0 0 0 OA 昭和戦前期における伊勢参宮修学旅行の研究
- 著者
- 太田 孝
- 出版者
- 一般社団法人 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.283-301, 2013 (Released:2018-01-26)
- 参考文献数
- 66
- 被引用文献数
- 2 2
As Japan was reorganized on a war footing during the prewar Showa Era, various measures restricting consumption within citizens’ lives were enacted by the government. School trips to pay respects at the Ise Jingu Shrine, however, were widely carried out by schools throughout Japan as ‘specially permitted school trips’ due to the Tenno ideology or emperor system. This study is an examination of the influence of these school trips to the Ise Jingu Shrine on the development of postwar Japanese tourism. In conducting the study, the cultural aspect of tourism was focused on.In the postwar Japanese travel market, the travel boom known as ‘mass tourism’ took place. The Japanese travel style in the category of the mass tourism is often referred to as ‘a hurried group excursion. ‘Where do people’s motivations for a trip originate ? And where does their travel style come from ? An earlier study has pointed out that the development of tourism is largely influenced by such external factors as socio-economic environment and media information regarding tourism. But while these external factors can act as promotional or suppressive factors, they are not fundamental in determining the desires of people. The arising of a motivation to travel and the development of a travel style take on form only when there is already a basis in the mind that responds to these external factors, which must have been fostered over a long period of time. It might be supposed that such a basis had already formed in the mind of people in the prewar period. Based on the above-mentioned awareness, in order to examine the epoch-making nature of postwar Japanese tourism, this study shows how the basis of Japanese tourism has been formed, first through analyzing the practice of travel contemporary with that period, and second, through examining the process in people’s mind towards travel style in prewar period while looking the ‘school trip to Ise Jingu Shrine,’ which many schoolchildren had experienced, as a model case.While the school trip to Ise Jingu Shrine has often been studied from the perspective of militaristic indoctrination, the ideology of the Tenno system and of ritualization, and with regard to the history of its establishment and development, studies based on the cultural aspects of tourism are rather few. In addition to the significance and effect of the school trip in terms of reverence for the imperial household, the veneration of gods, respect for ancestors, and as an opportunity for educators to train and discipline, it consequently contributed to a better exchange of communication between teachers and pupils, and among the pupils themselves. The experience of the school trip itself as well as on-the-spot group training and the contact with friends have had an influence on the formation of the mass culture, in which the pupils got involved during the course of their later lives.In this study, I took a different approach from the conventional perspective in the history of school trips, and as a result, the extent to which the school trip to Ise Jingu Shrine has influenced the development of postwar Japanese tourism was revealed.
4 0 0 0 昭和戦前期における伊勢修学旅行と旅行行動意識の形成
- 著者
- 太田 孝
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, pp.22-22, 2011
(はじめに) 「修学旅行」という言葉は,ほとんどの日本人の心に思い出として残っている言葉であり,長年にわたって学校教育の中で大きな役割をになってきた。白幡1)は,昭和の日本人の「旅行」を「昭和が生んだ庶民の新文化」とする。この「庶民の新文化」がどのように形成され,日本人の特徴としての「団体型周遊旅行」という旅行行動が生まれてきたのかを明らかにすることが本稿の目的である。その際,特に着目したのが修学旅行である。 修学旅行は,日本の特徴的な文化の一つとして定着しており,日本人の旅行を考える上で,決して欠かすことのできないテーマである。昭和時代には国家体制と社会環境の影響を受けながらも,太平洋戦時下を除き息長く継続されてきている。「なんとか子どもたちを修学旅行にいかせたい」。それは父兄のそしてムラ・マチの大人たちの,戦前・戦後を通じての熱い思いであった。昭和戦前期また戦後の荒廃下でも,わが国の地域社会において,都市と農村や生活の格差を越えて幅広い層にわたって組織的に「旅行」を経験し,「外の世界」に触れたのは子どもたちであり,修学旅行にはひとりでも多くの生徒の参加がめざされていた。自分たちが「日頃行動できる範囲=日常生活圏」から離れ,見聞きしたことを家族やムラ・マチの人々に話す。この子どもたちの体験と情報は地域社会に大きな影響を及ぼしたと考えられる。このような問題意識を持ったとき,戦後における日本のツーリズムの画期性を考察するには,その土壌が出来上がる前段の,戦前における人々の「旅行行動の意識形成」の過程をとらえて論じる必要があることに気がつく。本稿のめざすところは,日本人の旅行行動の意識形成を明らかにすることであるが,それに影響を与える大きな役割をになった一つが,幅広い層にわたって誰もが経験した修学旅行であったと考えられる。日本人の旅のスタイルの特徴を形づくってきた淵源のひとつは修学旅行にあるのではないか。このような仮説と問題意識のもとに,戦前において「参宮旅行」と称して全国から修学旅行が訪れた「伊勢」をフィールドとして,筆者が発見した資料(1929~1940年の間に全国から伊勢神宮を修学旅行で訪れた学校の顧客カード3,379校分・予約カード657校分ほかが内宮前の土産物店に存在した)をもとに考察した。(得られた知見) まず第1に,「伊勢修学旅行の栞」による旅行目的と行程の詳細分析から,目的である皇国史観・天皇制教化としての「参宮」を建前としながらも,子どもたちにたくさんのものを見せ,体験させたいという「送り出し側(学校・父兄・地域)」の思いが修学旅行に色濃く反映していることが実証された。その結果としての,短時間での盛りだくさんな見学箇所と時間の取り方や駆け足旅行という特徴は,子どもたちに,『旅行とはこういうものだ』という観念を植えつけ,団体型周遊旅行の基礎を作り上げるとともに,『見るということに対するどん欲さ』を身につけさせた。第2に,夜行も厭わない長時間の移動と,食事・宿泊も一緒という実施形態により,団体型の行動や旅行に慣れていった。この形態が戦後の団体臨時列車,引き回し臨時列車,修学旅行専用列車,バスによる団体旅行等の旅行形態と,それを歓迎する(好む)旅行行動の意識形成につながった。第3に,現代の日本の団体旅行の誘致手法は,江戸時代の伊勢御師の檀家管理手法や講による団体組成方式にルーツがあり,その思想を受け継いだ伊勢の旅館や土産物店の修学旅行誘致・獲得策が,戦後の旅行業の団体営業型のモデルになった。ツーリズムは需要側と供給側の相互作用によって醸成されていくものである。この供給側の需要側に対する活動が日本人の団体型旅行行動意識形成の重要な部分を担ってきたことが検証された。第4に,旅行における『本音と建て前』の旅行行動の意識を明らかにした。すでに江戸時代から存在したものであるが,特に満州事変以降の戦時体制下において,子どもたちの修学旅行を実現するためにその考え方が強く現れている点を指摘した。この『本音と建て前の旅行文化』は,戦時体制下という事情とともに,日本人の余暇観・労働観が旅行行動の意識の根底にあるものである。このように,従来の研究ではとらえられていなかった,戦前の修学旅行が旅行の形態と旅行行動に関する意識形成に与えた影響を明らかにした。そして第5に,この影響は,「都市と農村」や「生活面での格差の階層」を越えた幅広い層の子どもたち本人と,その日常生活圏の人びとに対するものであったことも,戦後の日本のツーリズム形成の要因として見逃すことはできない。1)白幡洋三郎『旅行のススメ 昭和が生んだ庶民の「新文化」』1996.中公新書
2 0 0 0 IR 天体のライブ映像を教材とした理科教育実践とその評価
- 著者
- 千島 拓朗 成田 晋吾 大滝 学 高田 淑子 鈴木 雄太 木村 雄太 太田 孝弘
- 出版者
- 宮城教育大学情報処理センター
- 雑誌
- 宮城教育大学情報処理センター年報 = Miyagi University of Education Information Processing Center (ISSN:13404113)
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.30-36, 2007-03-31
天文分野の学習では、昼間に観察できる対象が少ないために、コンピューターや情報機器を活用して授業を行うことが多い。そこで、宮教大インターネット天文台を利用して、学校を対象に金星と月のインターネットライブ中継を行った。学習時期に合わせて、金星のライブ中継は2005年10月から12月、2006年11月から2007年1月まで、月のライブ中継は2006年10月から2007年1月までの平日の晴天日、10時から15時まで公開した。天体のライブ映像を公開することで、教室の中でリアルタイムの天体観察を行うことが可能となり、初等・中等教育で重要視される体験や対象を取り入れた授業を行うことができる。2005年には、中学校で宮教大インターネットライブ中継を用いて金星の観察を取り入れた授業を行った。授業中に金星の満ち欠けについて、リアルタイムで天体を観察することは、生徒の興味を惹きつける有効な教材であることがわかった。
2 0 0 0 OA 文化遺産としての大衆的イメージ-近代日本における視覚文化の美学美術史学的研究
- 著者
- 金田 千秋 加藤 哲弘 島本 浣 山田 俊幸 及川 智早 佐藤 守弘 石田 あゆう 岸 文和 前川 修 中谷 伸生 橋爪 節也 鈴木 廣之 太田 孝彦 石田 美紀
- 出版者
- 筑波大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2008
本研究は、大正期に流通していた大衆的な視覚表象に関する2つの課題を、豊かな対話関係において、遂行するものである。すなわち、第1の課題は、大衆的な視覚表象が果たしていたメディア的な機能の多様性を、可能な限り広範な資料に基づいて、美術史学的に明らかにすることである。第2の課題は、「文化遺産」の概念を鍛え上げることによって、何らかの大衆的イメージが後世に継承される/るべきさいの条件・方法などを、美学的に考察することである。
2 0 0 0 OA 植民地下朝鮮における淑明高等女学校 : 抗日学生運動を中心に
- 著者
- 太田 孝子
- 出版者
- 岐阜大学
- 雑誌
- 岐阜大学留学生センター紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.2002, pp.23-43, 2003-03
淑明高等女学校は,1906年5月,朝鮮李王家の高宗皇帝妃と日本人淵沢能恵の協力によって,朝鮮人女子のために京城に創設された女学校である。植民地下の朝鮮において,朝鮮人と日本人の協力によって創られた私立高女は淑明高女が唯一のものである。しかし,日本人教師が多かったこともあり,朝鮮人女子のために創られた当初の理念や目的と,実際の学校運営の間にはしばしば齟齬(そご)をきたすことがあり,朝鮮教育史に残るような同盟休校事件(「'27淑明抗日盟休運動」)を始めとする抗日学生運動が幾度となく起こった。本稿では,淑明高女で起こった抗日学生運動関連の史資料を検証することによって,運動の目的と実態,運動を巡っての日本人教師,朝鮮総督府の反応を明らかにし,植民地下の女子中等教育が内包する課題を指摘した。
1 0 0 0 画譜の研究-江戸時代の美術史学-
本研究は今まで等閑視されがちであった江戸時代の画譜に焦点を当て、それらがどのような作品をどのように収録しているかを分析することによって、江戸時代の美術史の様相を解明することであった。画譜の出版においては江戸時代中期、十八世紀初頭に活躍した橘守国と大岡春卜が代表的な存在である。そこで、大岡春卜が出版した『和漢名筆画本手鑑』(享保五年1720)と『和漢名画苑』(寛延三年1750)を取り上げ、そこに春卜の美術史観をうかがおうとした。彼は同時代美術を重視する姿勢を採っていた。『画本手鑑』において、彼は対象をよく知ることによって把握される動物の生態を生き生きと描き出す行為を重視する。狩野派の画家であり、絵手本として機能する画譜の出版でありながら粉本からの離脱を評価する。次にそのことと矛盾することになるが、装飾性という姿や形の美しさこそが世に賞賛されていると位置づける。さらに、奇想天外な意表をつく光景を略筆で描く「鳥羽絵」を「狂画」として「風流」な嗜みとして評価し、多く収録する。そして『名画苑』では、長崎に伝えられた最新の技法と感覚を評価する。また、一種の遊びの精神に満ちた絵、絵画におかしみを持ち込んだ作品、素人の絵画を高く買っていることも注目される。彼の関心が絵画の革新であることを告げる。このように、春卜は絵画革新の時代的潮流を敏感に感じ、「現在流行している作品は旧例の墨守ではない新しい試みの吐露である」と評価し、それらを画譜に掲載し、それらを通じてあるべき絵画の姿を語る。「戯画」である鳥羽絵が持つ「諧謔性」を従来にない絵画の特質と認識していたのである。鳥羽絵は町人の自由な精神の発露であり、これこそがあるべき絵画であると主張していたことを明らかにした。これが十八世紀初頭に生きた春卜の絵画観である。江戸時代に美術をそうしたものと考え、それを告げることが美術史であると考えていたことが明らかになった。
1 0 0 0 OA 昭和前半期における修学旅行と旅行文化
1 0 0 0 美的価値と芸術的価値
美的価値と芸術的価値の問題は美学及び芸術史研究にとってその中心をなすというべき重要な問題である。研究代表者の吉岡は60年度に美術史研究が独立した学問として成立するに至る過程をたどり、それが18世紀の西欧世界においてであること、そしてまた美術史学の成立と美学の成立とは互いに支えあって初めて可能であったことを明らかにした。(京都大学文学部美学美術史学研究紀要第7号)吉岡の研究は各研究分担者の個別的で緻密な研究に支えられ、そこから大きな示唆と教示を得て執筆されたのであるが、同時に問題の難しさを一層鮮明なものにする結果ともなった。即ち美の問題と美術の問題との、近代世界における新たなる関係如何という、美学にとってのより根底的な問いが避けられなくなってきたのである。美学が美と芸術の本質を探求する学として成立したのは18世紀半ばであるが、美と芸術が一つの学の中で、まとめて扱われたのは、芸術が美的価値の実現を目標とする人間活動と見倣されたからに他ならない。ところが、人間活動の一形態としての芸術は必ずしも美的価値を目標とするものではないのではないかという疑問や、西洋以外の諸文化圏の芸術は少くとも西洋の伝統的美概念には包摂できないという明白な事実が、研究者の意識に上ってくるようになると、美的価値と芸術的価値とは分離されざるをえなくなる。東洋・日本の美術の研究者は、中国や日本の美術の目差すところが、いわゆる西洋世界で確立された美的諸範疇といったものでは充分に説明できないこと、それにも拘らず人間の表現活動としては西欧の認識の心を深く感動させるものを有していること、従って美的価値概念と芸術的それとの再検討が地球的規模で行なわれなければならないこと、そして美的価値と芸術的価値との価値論的な新しい統一の試みが必要であるという点を明らかにしてきたのである。