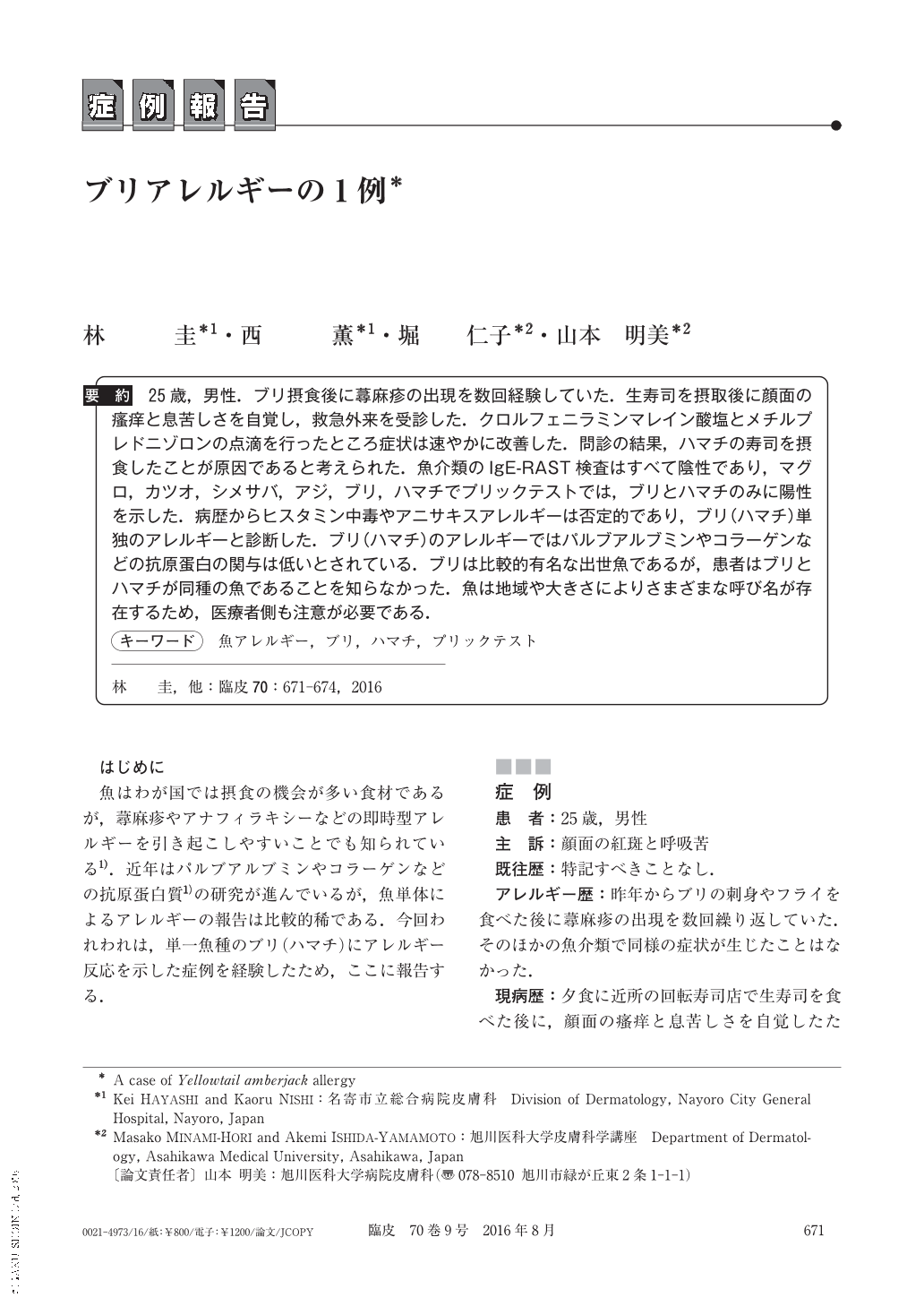685 0 0 0 OA 焼肉店での会食後に発生したE型肝炎ウイルス集団感染
- 著者
- 加藤 将 種市 幸二 松林 圭二
- 出版者
- 一般社団法人 日本肝臓学会
- 雑誌
- 肝臓 (ISSN:04514203)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.12, pp.688-688, 2004-12-25 (Released:2009-03-31)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 12 18
A patient died of fulminant hepatitis E in our hospital. To our surprise, a son of the patient was also infected with HEV. By executing a family study, it was revealed that 7 out of 13 relatives of the patient, all of whom had participated in a Yakiniku party, had infection markers for HEV. Our results corroborate previous report suggesting pig liver to be an important infection source in Hokkaido, Japan.
16 0 0 0 原発の危険性 (原発--差別のうえに建つ<特集>)
- 著者
- 小林 圭二
- 出版者
- 解放出版社
- 雑誌
- 部落解放 (ISSN:09143955)
- 巻号頁・発行日
- no.283, pp.p16-36, 1988-10
6 0 0 0 OA “種”のちがいを量る
- 著者
- 松林 圭
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.3, pp.171-182, 2019 (Released:2019-12-24)
- 参考文献数
- 78
- 被引用文献数
- 3
種分化とは、生物の多様性を生み出す原動力であり、“潜在的に交配可能な集団間に、交配を妨げる遺伝的機構(=生殖隔離)が進化すること”と定義できる。生物学的種概念を基礎とするこの種分化の定義は、広く進化生物学において受け入れられてきたが、実際の生物にこの基準を適用することには困難が伴う場合が多い。異なる個体群が、果たして異なる種にあたるのか否かは、進化生物学、生態学のみならず、分類学的にも重要な問題であった。この“種のちがい”を定量化する試みは、遺伝子マーカーを使用するものや形態的相違を判別形質とするものなど、様々な手法が使われてきた。これらはどれも、生殖隔離の存在やその強度を間接的に推定するものである。最近では、野外観察や行動実験を通して生殖隔離を直接測定する手法が普及しており、隔離障壁の進化やメカニズムに関する理解が大きく進んでいる。本総説では、種のちがいを量る方法として生殖隔離の定量化に着目し、近年になってこの分野で得られた知見を紹介する。
5 0 0 0 ブリアレルギーの1例
- 著者
- 林 圭 西 薫 堀 仁子 山本 明美
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 臨床皮膚科 (ISSN:00214973)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.9, pp.671-674, 2016-08-01
要約 25歳,男性.ブリ摂食後に蕁麻疹の出現を数回経験していた.生寿司を摂取後に顔面の瘙痒と息苦しさを自覚し,救急外来を受診した.クロルフェニラミンマレイン酸塩とメチルプレドニゾロンの点滴を行ったところ症状は速やかに改善した.問診の結果,ハマチの寿司を摂食したことが原因であると考えられた.魚介類のIgE-RAST検査はすべて陰性であり,マグロ,カツオ,シメサバ,アジ,ブリ,ハマチでプリックテストでは,ブリとハマチのみに陽性を示した.病歴からヒスタミン中毒やアニサキスアレルギーは否定的であり,ブリ(ハマチ)単独のアレルギーと診断した.ブリ(ハマチ)のアレルギーではパルブアルブミンやコラーゲンなどの抗原蛋白の関与は低いとされている.ブリは比較的有名な出世魚であるが,患者はブリとハマチが同種の魚であることを知らなかった.魚は地域や大きさによりさまざまな呼び名が存在するため,医療者側も注意が必要である.
4 0 0 0 OA 生態的種分化 ―適応の視点から多様化のメカニズムを探る―
- 著者
- 松林 圭 藤山 直之
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.561-580, 2016 (Released:2016-12-28)
- 参考文献数
- 159
要旨: 適応と多様化との関係を問う“生態的種分化”は、古典的な仮説でありながらも現代進化生態学において大きな進展を見せている。“異なる環境への適応によって隔離障壁が進化する”というこの仮説は、いわば伝統的な自然選択説の現代版であり、生態学の各分野で蓄積された膨大なデータを、進化生物学分野で培われてきた適応と種分化に関するアイディアによって俯瞰する形で成り立っている。生態的種分化は、進化学や生態学、遺伝学といった複数の分野を横断する仮説であるが、近年のこれらの分野における概念的統合およびゲノミクスとの融合に伴い、理論的に洗練された検証可能な作業仮説として、いまや多様性創出機構の議論に欠かすことのできないものとなってきた。日本の生物多様性の豊かさを考えたとき、潜在的に多くの生態的種分化の事例が潜んでいるものと思われるが、残念ながら日本の生物を対象とした実証研究は、今のところあまり多くない。このような状況を踏まえ、本総説では特に生態学者を対象として、生態的種分化のもっとも基礎的な理論的背景に関して、その定義、要因、地理的条件、特徴的な隔離障壁、分類群による相違を解説し、また、その対立仮説である非生態的種分化との違いを説明する。さらに、現在の生態的種分化研究の理論的枠組みにおける弱点や証拠の薄い部分を指摘し、今後の発展の方向性を議論する。
- 著者
- 加藤 将 種市 幸二 松林 圭二
- 雑誌
- 肝臓 = ACTA HEPATOLOGICA JAPONICA (ISSN:04514203)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.12, 2004-12-25
- 被引用文献数
- 11
3 0 0 0 OA フィールドノート・アーカイブズの基礎的研究
1.民俗学者桜田勝徳の調査研究資料の目録を作成し、このアーカイブが、柳田国男の薫陶を受け、民俗学を実践し始めた以降の資料が中心であることを明らかにした。2.桜田のフィールドノートの検討から、その記載形式に一貫性(右面に記載し、左面を補助的に利用)とともに変化(日次、立て横書き等)があること、彼のフィールドワークには2つのスタイルがあること、フィールドノートとフィールドワークの変化は、共に1940年代に認められることが分かった。3.GHQ下の社会調査において、桜田がGHQの改革案を指示する立場で働き掛けていた事実を明らかにし、このようなフィールドワークに関わる実践の民俗学的な意義を明らかにした。
- 著者
- 阿部 敏紀 相川 達也 赤羽 賢浩 新井 雅裕 朝比奈 靖浩 新敷 吉成 茶山 一彰 原田 英治 橋本 直明 堀 亜希子 市田 隆文 池田 広記 石川 晶久 伊藤 敬義 姜 貞憲 狩野 吉康 加藤 秀章 加藤 将 川上 万里 北嶋 直人 北村 庸雄 正木 尚彦 松林 圭二 松田 裕之 松井 淳 道堯 浩二郎 三原 弘 宮地 克彦 宮川 浩 水尾 仁志 持田 智 森山 光彦 西口 修平 岡田 克夫 齋藤 英胤 佐久川 廣 柴田 実 鈴木 一幸 高橋 和明 山田 剛太郎 山本 和秀 山中 太郎 大和 弘明 矢野 公士 三代 俊治
- 出版者
- The Japan Society of Hepatology
- 雑誌
- 肝臓 = ACTA HEPATOLOGICA JAPONICA (ISSN:04514203)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.8, pp.384-391, 2006-08-25
- 被引用文献数
- 18 56
極く最近まで殆んど不明状態にあった我国のE型肝炎の実態を明らかにする目的で,我々は全国から総数254例のE型肝炎ウイルス(HEV)感染例を集め,統計学的・疫学的・ウイルス学的特徴を求めてこれを解析した.その結果,[i]HEV感染は北海道から沖縄まで全国津々浦々に浸透していること;[ii]感染者の多くは中高年(平均年齢約50歳)で,且つ男性優位(男女比約3.5対1)であること;[iii]我国に土着しているHEVはgenotype 3とgenotype 4であるが,後者は主に北海道に偏在していること;[iv]年齢と肝炎重症度との間に相関があること;[v]Genotype 3よりはgenotype 4による感染の方が顕性化率も重症化率も高いこと;[vi]発生時期が無季節性であること;[vii]集積症例全体の約30%は動物由来食感染,8%は輸入感染,2%は輸血を介する感染に帰せしめ得たものの,過半の症例(約60%)に於いては感染経路が不明のままであること;等の知見を得た.<br>
2 0 0 0 27a-Z-1 チェルノービィリ原発事故による放射能の放出
- 著者
- 瀬尾 健 今中 哲二 小出 裕章 久米 三四郎 海老沢 徹 川野 眞治 小林 圭二
- 出版者
- 一般社団法人日本物理学会
- 雑誌
- 秋の分科会講演予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.1987, no.4, 1987-09-16
- 著者
- 星 奈美子 迎 慎二 新澤 穣太郎 渡邊 茂 粕川 禮司 折笠 博史 小林 圭子 佐伯 武頼
- 出版者
- The Japan Society of Hepatology
- 雑誌
- 肝臓 (ISSN:04514203)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.11, pp.492-497, 2002-11-25
- 被引用文献数
- 6 6
1996年4月, 29歳時に発症した成人発症II型シトルリン血症の男性. 特殊ミルク (高アンモニア血症・シトルリン血症フォーミュラ<sup>®</sup>) の内服で3年間症状の改善が認められたが, 1999年に, 血清アンモニア値の上昇とともに脳症のコントロールが困難となった. そこで経口アルギニン製剤 (アルギU顆粒<sup>®</sup>) を投与したところ, アンモニア値の正常化と脳症の改善が認められた. しかし8カ月後の2001年3月に再びアンモニア値の上昇と脳症が出現し, 約5年の経過で死亡した.
2 0 0 0 30p-YE-1 もんじゅ事故とその後
- 著者
- 小林 圭二
- 出版者
- 一般社団法人日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会講演概要集 (ISSN:13428349)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, 1997-03-17
1 0 0 0 OA 走査型容量顕微鏡によるMOSFET動作時の不純物分布計測
- 著者
- 臼田 宏治 木村 健次郎 小林 圭 山田 啓文
- 出版者
- 公益社団法人 日本表面科学会
- 雑誌
- 表面科学 (ISSN:03885321)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.84-90, 2007-02-10 (Released:2007-03-20)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1 1
We introduce scanning capacitance force microscopy (SCFM), a newly developed dopant profiling method, and a 3-dimensional wiring procedure enabling evaluation of dopant profile under metal-oxide-semiconductor field-effect-transistor (MOSFET) operation. The principle of the SCFM is based on measurement of an electrostatic force (ESF) that is induced by bias voltage of angular frequency ω between a tip and a sample. The focused ion beam (FIB) technique was employed to evaluate dopant profile for the cross-section of MOSFET devices under the device operation. Local etching, deposition, and formation of small wiring for the specified MOSFET were successively carried out with the FIB, and the variation of dopant profiling was clearly shown with applying voltage to the MOSFET. These techniques are expected to be utilized for the failure analysis and the development of next-generation devices.
- 著者
- 星 奈美子 迎 慎二 新澤 穣太郎 渡邊 茂 粕川 禮司 折笠 博史 小林 圭子 佐伯 武頼
- 出版者
- 一般社団法人 日本肝臓学会
- 雑誌
- 肝臓 (ISSN:04514203)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.11, pp.492-497, 2002-11-25 (Released:2009-03-31)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 6 6
1996年4月, 29歳時に発症した成人発症II型シトルリン血症の男性. 特殊ミルク (高アンモニア血症・シトルリン血症フォーミュラ®) の内服で3年間症状の改善が認められたが, 1999年に, 血清アンモニア値の上昇とともに脳症のコントロールが困難となった. そこで経口アルギニン製剤 (アルギU顆粒®) を投与したところ, アンモニア値の正常化と脳症の改善が認められた. しかし8カ月後の2001年3月に再びアンモニア値の上昇と脳症が出現し, 約5年の経過で死亡した.
1 0 0 0 OA 本邦におけるE型肝炎ウイルス輸血感染の現状
- 著者
- 田中 亜美 星 友二 長谷川 隆 坂田 秀勝 古居 保美 後藤 直子 平 力造 松林 圭二 佐竹 正博
- 出版者
- 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会
- 雑誌
- 日本輸血細胞治療学会誌 (ISSN:18813011)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.531-537, 2020-06-25 (Released:2020-07-17)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 2 5
E型肝炎ウイルス(HEV)の輸血感染対策を検討するため,輸血後E型肝炎感染患者として,既報(Transfusion 2017)の19例も含め,2018年までに判明した34症例について解析した.原因献血者は全国に分布し,関東甲信越での献血者が半数以上を占めた.原因血液の88.2%(30例)がHEV RNA陽性かつHEV抗体陰性で,多くはHEV感染初期と考えられた.分子系統解析の結果,原因HEV株の遺伝子型は3型が29例(90.6%),4型が3例(9.4%)で,それぞれ異なるクラスターに存在し,多様性に富むことが示された.一方,輸血後感染34症例中少なくとも16例(47.1%)は免疫抑制状態にあった.多くは一過性急性肝炎であったが,確認できた半数(8例)でウイルス血症が6カ月以上持続した.臨床経過中の最大ALT値の中央値は631IU/lで,輸血による最少感染成立HEV RNA量は2.51log IUと推定された.輸血されたウイルス量や遺伝子型と,最大ALT値に相関は認められなかった.HEV RNAスクリーニングの全国導入はHEV輸血感染対策として有効と考えられる.
1 0 0 0 OA 放射妨害波測定用超広帯域アンテナの設計・開発
- 著者
- 石上 忍 石崎 利弥 小林 圭太 川又 憲 張間 勝茂 祷 真悟
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌 B (ISSN:13444697)
- 巻号頁・発行日
- vol.J105-B, no.6, pp.458-465, 2022-06-01
本論文では,現在の妨害波測定に使用されている市販の広帯域アンテナの使用可能帯域を一つのアンテナで実現するための超広帯域アンテナの設計と開発について述べた.まず本アンテナの原理について述べ,更に試作したアンテナについて,複素アンテナ係数,絶対利得,及びアンテナ反射特性の測定結果を示した.その結果,本提案アンテナは,500 MHzから20 GHzまでEMC用のアンテナとして使用可能であることがわかった.
1 0 0 0 IR 亀ヶ岡式土器成立期の研究 : 東北地方における縄文時代晩期前葉の土器型式
- 著者
- 小林 悠 飯田 樹里 坂田 秀勝 松林 圭二 佐藤 進一郎 生田 克哉 紀野 修一
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会
- 雑誌
- 医学検査 (ISSN:09158669)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.4, pp.740-747, 2021-10-25 (Released:2021-10-25)
- 参考文献数
- 24
E型肝炎ウイルス(HEV)はE型肝炎の原因ウイルスであり,本邦では遺伝子型3型と4型が検出されている。北海道では高病原性である4型が他地域よりも高率に検出されるため,われわれは3型と4型を迅速に鑑別可能なマルチプレックスreal-time RT-PCR法(鑑別PCR)を開発した。今回,遺伝子型およびHEV RNA濃度既知の献血者由来検体を対象に,リアルタイムPCR試薬であるQuantiTect Probe RT-PCR Kit(従来試薬)およびReliance One-step Multiplex RT-qPCR Supermix(BIO-RAD,A試薬)を用いて,鑑別PCRにおいて感度などに変化があるかを検討した。各遺伝子型のリニアダイナミックレンジは,3型に対しては同等で,4型に対してはA試薬が従来試薬よりも線形区間が10倍広範囲であった。PCR効率は,3型で109.9% vs. 108.3%,4型で89.7% vs. 97.1%であり,血漿1,000 μL使用時の検出感度は,3型で20 IU/mL vs. 19 IU/mL,4型で66 IU/mL vs. 16 IU/mLであった(いずれも従来試薬vs. A試薬)。A試薬により4型に対するPCR効率および検出感度は向上し,高病原性である4型の感染者において遺伝子型情報をより早期に提供可能であり,その後の治療に有用と考えられた。
1 0 0 0 OA 文化財の視点からみたトロロアオイ生産技術の現状 ―茨城県小美玉市の実例を通じて―
- 著者
- 菊池 理予 林 圭史 渡瀬 綾乃
- 出版者
- 東京文化財研究所
- 雑誌
- 無形文化遺産研究報告 = Research and Reports on Intangible Cultural Heritage
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.79-99, 2020-03-31
Tororo-aoi(黄蜀葵:Abelmoschus manihot)is a plant similar to okura that produces a yellow flower. Viscous liquid extracted from its root is called “neri” and has been used in the production of handmade Japanese paper. In April 2019, it was reported that the manufacture of tororo-aoi will be terminated. This report brought about fear among persons concerned that it will no longer be possible to obtain tororo-aoi. In the present study, then, the present condition of the manufacture of tororo-aoi and its system in Omitama-shi, Ibaraki Prefecture were explored and the reasons for the decrease in its manufacture was debated. In addition, by searching into the question of how much handmade paper has been protected as a cultural property of Japan ever since the enactment of the Law for the Protection of Cultural Properties, the necessity for the protection of the technique of manufacture of its raw materials is considered. As a result, the following has been made clear. First, tororo-aoi is clearly noted as one of the designated conditions for the manufacture of handmade Japanese paper, which is an important intangible cultural property. Second, Mr. Uekubo Ryoji, a manufacturer of misu paper who is selected as a holder of the technique for the manufacture of handmade Japanese paper for mounting, and Mr. Ebuchi Eikan, a manufacturer of paper for restoration, both manufacture handmade paper using tororo-aoi. Stable procurement of raw materials is necessary for the continuance of the technique. In the system of distribution of tororo-aoi in the 1950s there was a group of people called “neriya” who dealt with the buying of seeds and acted as “go-betweens” who were entrusted by the neriya. These go-betweens encouraged and guided the manufacture of tororo-aoi and were engaged even in the transport and testing of the materials. The existence of neriya was effective in the maintenance of the quality of tororo-aoi. But such a system no longer exists, and today a farmer sends the product to Japan Agricultural Cooperatives (JA) which in turn sends it to groups or individuals engaged in the manufacture of handmade paper. Tororo-aoi rots easily so that by the time it reaches the paper manufacturer, there is bound to be loss due to damage. For stable procurement, some measures should be taken in the system of transport so that damage will not occur. Furthermore, there are some processes in the cultivation of tororo-aoi that cannot depend on machinery and must be done by hand. Even though it costs manpower, the manufacture of tororo-aoi alone does not bring so much income as to make it a livelihood. It has also become clear that since tororo-aoi cannot be cultivated on the same land successively, a farm needs to have a large piece of land to produce tororo-aoi consecutively. In the present circumstances, other products require less work and can bring in as much profit. In other words, the continuance of the manufacture of tororo-aoi currently depends much on the intention of the persons manufacturing. It is thought that a new system of support is necessary for the stable manufacture of tororo-aoi. Persons concerned currently sincerely wish the local governing bodies and people associated with JA to have a correct understanding of the importance of tororo-aoi and the significance of the fact that it is being manufactured in Omitami-shi today. Active discussion toward protection is necessary in the future.
1 0 0 0 本邦におけるE型肝炎ウイルス輸血感染の現状
- 著者
- 田中 亜美 星 友二 長谷川 隆 坂田 秀勝 古居 保美 後藤 直子 平 力造 松林 圭二 佐竹 正博
- 出版者
- 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会
- 雑誌
- 日本輸血細胞治療学会誌 (ISSN:18813011)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.531-537, 2020
- 被引用文献数
- 5
<p>E型肝炎ウイルス(HEV)の輸血感染対策を検討するため,輸血後E型肝炎感染患者として,既報(Transfusion 2017)の19例も含め,2018年までに判明した34症例について解析した.</p><p>原因献血者は全国に分布し,関東甲信越での献血者が半数以上を占めた.原因血液の88.2%(30例)がHEV RNA陽性かつHEV抗体陰性で,多くはHEV感染初期と考えられた.分子系統解析の結果,原因HEV株の遺伝子型は3型が29例(90.6%),4型が3例(9.4%)で,それぞれ異なるクラスターに存在し,多様性に富むことが示された.</p><p>一方,輸血後感染34症例中少なくとも16例(47.1%)は免疫抑制状態にあった.多くは一過性急性肝炎であったが,確認できた半数(8例)でウイルス血症が6カ月以上持続した.臨床経過中の最大ALT値の中央値は631IU/<i>l</i>で,輸血による最少感染成立HEV RNA量は2.51log IUと推定された.輸血されたウイルス量や遺伝子型と,最大ALT値に相関は認められなかった.</p><p>HEV RNAスクリーニングの全国導入はHEV輸血感染対策として有効と考えられる.</p>
- 著者
- 林 圭史
- 出版者
- 地方史研究協議会
- 雑誌
- 地方史研究 (ISSN:05777542)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.4, pp.55-58, 2020-08