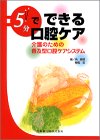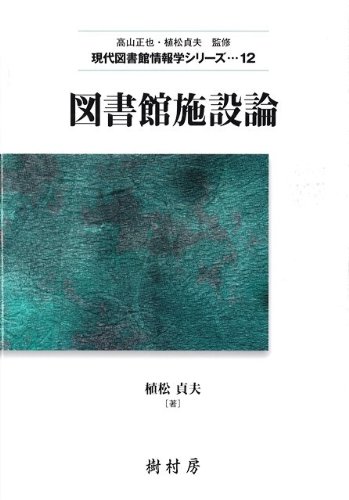1 0 0 0 OA ユーザ行動に基づくモバイルネットワーク故障検知と予測
モバイルネットワークサービス提供社の課題の一つが安定した高品質なサービス提供である.しかしながら,ネットワークトラフィックの急増や設備の経年劣化がスループットの低下などの品質劣化やネットワーク故障を引き起こすことがある.そのような問題において,サービス利用者はサービス提供社よりも早くサービスの使用不能や品質劣化を発見することがある.利用者は彼らの体感をすぐにソーシャルサービス上で発信したり,故障情報を得るためのWeb検索などを迅速に行う.これらのデータから異常を検知することで,故障検知および予測に役立つと考えられる.この論文では,複数のユーザ行動データを用いて,故障を検知および予測するための機械学習モデルアプローチを提案する.モバイルネットワークサービスの実データを用いた複数の実験により,提案するフレームワークの有用性を検証する.
- 著者
- 井口 誠 植松 太郎 藤井 達朗
- 雑誌
- 研究報告コンピュータセキュリティ(CSEC) (ISSN:21888655)
- 巻号頁・発行日
- vol.2018-CSEC-81, no.10, pp.1-8, 2018-05-10
昨今,ビッグデータ利活用促進のための取組みとして,個人データの流通が重要な役割を果たすようになっている.この流れを受け,日本でも 2017 年 5 月に改正個人情報保護法が全面施行された.結果,匿名加工情報制度の創設など,プライバシー保護を図りつつ個人データを第三者に提供可能とする環境整備が整いつつある.しかし,環境整備は整ったものの,具体的な個人データの第三者提供ルールはまだ策定されていない状態にある.一例として匿名加工情報を見た場合,一律の基準は存在せず具体的な加工方法は明確にはなっていない.本稿では,リスクベースアプローチを用いて実用的な個人データの第三者提供ルールを策定する手法を検討する.特に米国の HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996) 法を例に分析を行い,リスクベースアプローチが直感的な個人データの第三者提供ルールの策定に活用されていることを示す.また分析結果を踏まえ,他分野における第三者提供ルール策定へ向けた方法論を考察する.
- 著者
- 大須賀 愛幸 植松 洋子 山嶋 裕季子 田原 正一 宮川 弘之 高梨 麻由 門間 公夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.73-79, 2018-04-25 (Released:2018-04-25)
- 参考文献数
- 12
高タンパク食品中の酸性タール色素分析法について,回収率に優れ,かつ簡便で迅速な試験法を作成した.試薬量等のスケールダウンを行い,さらにポリアミド (PA) カラムに負荷する液の調製法として,溶媒留去の替わりに抽出液を水で希釈し有機溶媒濃度を下げ,色素をPAカラムに保持させることにより,操作の簡便化および迅速化を達成した.またPAカラムで色素を精製する際,負荷する液のpHを汎用されるpH 3~4からpH 8.5にすることで,高タンパク食品における,キサンテン系色素の回収率が大きく向上した.高タンパク食品の中でも特に酸性タール色素の分析が困難とされてきた辛子明太子での11種類の色素の回収率はpH 8.5で精製することで63~101%となり,pH 3.5での精製(回収率18~95%)に比べ大幅な改善が認められた(5 μg/g添加).
- 著者
- 春日井 守 竹内 玉行 加藤 昭年 大河内 敏博 植松 伸夫
- 出版者
- 社団法人日本鉄鋼協会
- 雑誌
- 鐵と鋼 : 日本鐡鋼協會々誌 (ISSN:00211575)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.13, 1986-09-09
1 0 0 0 IR 士農工商論における中・日比較
- 著者
- 植松 忠博
- 出版者
- 神戸大学
- 雑誌
- 國民經濟雜誌 (ISSN:03873129)
- 巻号頁・発行日
- vol.173, no.4, pp.15-30, 1996-04
1 0 0 0 尊属殺害原因としてのエデイプス錯綜
- 著者
- 植松 正
- 出版者
- 法曹会
- 雑誌
- 法曹時報 (ISSN:00239453)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.35-46, 1953-02
1 0 0 0 OA タンパク質と塩素との水中における反応による有機塩素化合物の生成
- 著者
- 名川 吉信 植松 喜稔 西 末雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本水環境学会
- 雑誌
- 水質汚濁研究 (ISSN:03872025)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.31-38, 1984-02-29 (Released:2009-09-10)
- 参考文献数
- 14
The reactions of proteins and their major constituent amino acids with chlorine in water have been studied and the following results are obtained.1) Proteins have the potential properties of yielding chloroform or total organic chloride (TOCI) as similar extent to humic acid.2) At the pH range of 4-10, the amounts of chloroform formed from proteins increase with increasing pH, whereas the yields of TOCI show maxima at pH8.5. In the cases of amino acids, the amounts of chloroform and TOCI formed vary depending on the kinds of amino acids. However, the pH dependencies in the chloroform formations from amino acids and in the TOCl formations from certain amino acids which yield higher levels of TOCl are similar to those in the cases of proteins.3) The amounts of chloroform and TOCl formed from proteins can be expressed as the following equation. [OCl]=K[P][Cl]mtnWhere [OCl] is the concentration of chloroform or TOCl, [P] is the concentration of protein, [Cl] is the concentration of chlorine, and K, m, and n are the parameter.
1 0 0 0 地域におけるメディカルフィットネスの役割
- 著者
- 千葉 辰徳 植松 圭悟 西 泰信 広瀬 友彦
- 出版者
- 日本臨床スポーツ医学会
- 雑誌
- 日本臨床スポーツ医学会誌 = The journal of Japanese Society of Clinical Sports Medicine (ISSN:13464159)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.258-260, 2008-04-15
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 ヒメダカの性行動展開の順序について〔英文〕
- 著者
- 小野 嘉明 植松 辰美
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.1-10, 1968
- 被引用文献数
- 3
ONO, Yoshiaki and Tatsumi UEMATSU (Kagawa Univ., Taka matsu) Sequence of the mating activities in Oryzias latipes. Jap.J.Ecol. 18,1-10 (1968). The quantitative research on the chain reactions among the behaviour unit patterns recognized during development of the mating behaviour patterns was made as a preliminary step to study both the mechanism and meaning of the chain reactions in Oryzias latipes. One hundred and twenty one full-grown pairs of both sexes were observed. Each experimental material was isolated and feeded sufficiently for 72 hours before the experiment. Then a male and a female of the same body length were introduced simultaneously in the glass aquarium under the condition of controlled light in the dark room and their behaviour patterns observed for 30 minutes were recorded. No bait was given to them during the observation. The results obtained are as follows. 1) Fifty of the 121 pairs observed developed to copulation (M7) and spawning (M8). 2) From the quantitative research on the chain relation among the mating behaviour patterns the sequence of development of the mating behaviour is concluded to be as follows. Approaching (S1)→following (S2)→courting orientation (M1)→head-up I (M2)→courting round dance (M3)→head-up II (M4)→floating-up (M5)→crossing (M6)→copulation (M7)→spawning (M8)→ejaculation (M9)→fertilization (M10). 3) Considering both the degree of development of each mating behaviour pattern and the mean time from the beginning of the observation to the first occurrence of each behaviour pattern, the mating behaviour seems to develop along two following main processes. S2→M1→M3→M5→M6→M7-10 S2→M1→ M5→M6→M7-10 Regarding S_2→M1→M3 as phase I and S2→M1→M5→M6 as Phase II, the above mentioned processes are represented as follows. Phase I→latter part of phase II→copulation Phase II→copulation 4) Phase I has the biological significance of the promotion of the sexual drive of both sexes. 5) The female behaviour patterns, head-up I and II, are regarded as the avoiding behaviour due to insufficient sexual drive. These behaviour patterns result in the repeating of the male courting behaviour. Then the sexual drive of both sexes is promoted and the synchronization of copulation results. 6) There was observed the repeated phase I when the sexual drive of bath sexes was too low to copulate. Phase II occurred frequently when the sexual drive of the male is high, but that of the female is not so high. When the sexual drive of the male is low, the frequency of the occurrence of the mating behaviour is low or zero. In the pair prepared sufficiently to copulate, there are few repeated occurrences of both phases, or phase I is omitted.
1 0 0 0 OA 瀬戸内海沿岸部における大気エアロゾル中の有機態窒素
- 著者
- 中村 篤博 成田 祥 金澤 啓三 植松 光夫
- 出版者
- 日本エアロゾル学会
- 雑誌
- エアロゾル研究 (ISSN:09122834)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.4-13, 2017-03-20 (Released:2017-04-03)
- 参考文献数
- 30
Chemical compositions and particle number densities of atmospheric aerosols were measured continuously in the coastal area of Seto Inland Sea during the spring of 2015. The mean concentrations of NH4+, NO3-, and water soluble organic nitrogen (ONws) were 1.6, 0.85, and 0.28 μg N m-3, respectively in total sampling mode. NO3- existed in both fine and coarse modes, while NH4+ and ONws existed primarily in fine mode. On the days of normal atmospheric conditions, the amount of ONws contributing to the total nitrogen was about 14% N in both fine and coarse sampling modes. This ratio was equivalent to the amount of NO3- content in fine mode and NH4+ in coarse mode. On the days with polluted atmospheric conditions, the amount of ONws contributing to total nitrogen was about 9.3% N in fine mode and about 5.0% N in coarse mode. This ratio was equivalent to the contributions of NO3- in fine mode and NH4+ in coarse mode. Dry deposition fluxes of particulate NH4+, NO3-, and ONWS in the area were 280, 660, and 83 μg N m-2 day-1, respectively. The flux of NO3- was more effective than any other nitrogen compounds, since the deposition rate depends upon a size distribution. The dry deposition of ONws accounted for about 8.1% of the total nitrogen dry deposition. Thus, ONWS cannot be ignored when considering the nitrogen budget and cycles in this area.
1 0 0 0 OA コミュニティバスのユニバーサルデザイン
- 著者
- 蓮見 孝 植松 知恵 田中 真一 星 幹男
- 出版者
- Japanese Society for the Science of Design
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集
- 巻号頁・発行日
- pp.196, 2006 (Released:2006-08-10)
つくば市は、2006年4月1日からコミュミティバス「つくバス」を運行を開始した。284.07平方kmの広大な地域における移動の利便性を保証しようとするもので、市内全域の集落をめぐる13路線の「地域循環」と、センター地区・筑波山を結ぶ「北部シャトル」、センター地区を回る「センター循環」の3路線からなり、1000を超えるバス停留所を持つ地域交通システムである。つくバスは、つくば市と関東鉄道株式会社により運営されるもので、つくば市と連携協定を結んでいる筑波大学が、公募された「つくバス」の名称選定、外装グラフィックデザイン、室内デザイン、バス路線ガイド・マップ、バス停留所の標識デザイン等を担当した。デザインを進めるにあたり、より多くの住民や来訪者の利用促進を図るため、誰にでも乗りやすいバスのデザインをめざし、「ユニバーサルデザイン」の考え方を積極的に取り入れた。
- 著者
- 植松 洋一 鹿野 一郎
- 出版者
- 一般社団法人日本機械学会
- 雑誌
- 講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, no.48, pp.90-91, 2013-03-15
1 0 0 0 日本及びアメリカ産ニホンナシ'二十世紀'の果実品質の比較
- 著者
- 植松 齊 佐藤 幹夫 久保井 榮 池田 勇治 新部 昭夫 大坪 孝之 舛水 康彦 URIU Kiyoto
- 出版者
- Japan Association of Food Preservation Scientists
- 雑誌
- 日本食品保蔵科学会誌 = Food preservation science (ISSN:13441213)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.4, pp.185-192, 1997-07-31
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1 1
本研究は日本産及び米国カリフォルニア産のニホンナシ'二十世紀'について果実品質の比較をしたものである。果実のサンプルはカリフォルニアではフレズノ及びサクラメントより, 日本は鳥取及び長野より各々市場に流通している標準的な大きさの果実を材料とした。<BR>1. 生育期間中の気象条件について, 米国カリフォルニアの最高気温及び平均気温は日本より高かったが, カリフォルニアの最低気温は日本より低い値であった。日本の降雨量はカリフォルニアより高く, 月平均約100-150mmの値を示した。カリフォルニアは生育期間中にはほとんど降雨がみられなかった。日本の湿度はカリフォルニアより高く, 日照量についてみるとカリフォルニアは日本より高い値であった。<BR>2. 日本産とカリフォルニア産果実はほぼ標準的なサイズをサンプリングするよう努力した。日本の階級区分で, カリフォルニア産果実はL, 日本産果実は2Lクラスであった。これらのことから日本産果実は果実重, 縦径及び横径とも僅かにカリフォルニア産果実より高い値であった。D/L値 (果形指数) は日本の値が僅かに高く, 僅かに平たい果実であった。果皮色は日本及びカリフォルニアには差がみられたが, 各々の地域をみると一定の傾向はみられなかった。米国産果実の果肉硬度は日本産果実より著しく高く (フレスノ : 5.55, サクラメント : 4.98, 鳥取 : 2.21及び長野 : 3.00kg/cm<SUP>2</SUP>), で硬度が高くなると著しく搾汁率が低下する傾向がみられた。日本産果実の搾汁率は高い値を示したが, 硬度及び搾汁率に顕著な相関関係は認められなかった。<BR>3. 米国産果実のシュークロース濃度は日本産果実より著しく高い値を (フレスノ : 5.54, サクラメント : 6.42, 鳥取 : 3.05及び長野 : 2.649/m<I>l</I>) 示し, さらにソルビトールも高い値を示した。カリフォルニアの昼夜間の温度較差, 日照量, 降水量など気象条件がシュークロース及びソルビトール集積に影響したものと思われる。グルコース及びフラクトースには顕著な差は認められなかった。<BR>4. 日本産果実のクエン酸濃度は米国より高く, また逆にカリフォルニア産果実のリンゴ酸濃度は日本産果実より高い値を示した。しかし全酸濃度には差は認められなかった。
1 0 0 0 カーネル法による新しい時系列分析
平成28年度の研究内容は主に,1.高次元時系列予測,2.スパース直交ファクター回帰,3.非定常非線形分位点回帰,4.非線形ファクターモデル,5.高次元FDRコントロール,の5点である:1.理論面では最適な予測誤差の上限とモデル選択の一致性を示したほか,実証面では米国の高次元マクロ経済データを用いたGDP予測を行った.この論文は昨年度末にJournal of Business & Economic Statisticsからの改定要求を受けていたため,今年度はその改訂作業を行い,同ジャーナルに再投稿した.2.昨年度に得られた理論的成果の証明について若干の修正を加え,論文全体も新しい理論に合わせて改訂した.この論文は最終的に,Journal of the Royal Statistical Society: Series B に再投稿した.3.昨年度再投稿したEconometric Reviewsからの2回目の改訂要求を受けて,再び論文の修正・加筆を行った.推定精度とパラメータ制約の検定に関するシミュレーションを刷新し,またバイアス修正した推定量の漸近理論も付け足した.結果,同ジャーナルに掲載が決まった.4.今年度は実証分析に焦点を当て,非線形ファクターがマクロ経済時系列の予測に有効かどうかを考察した.方法論は確立しているものの,細かなモデリングの差や,チューニングによって実証結果が変わるため,より良い結果が出るよう現在も研究を続けている.5.Barber and Candes (2015)は,FDRのコントロール手法として,Knockoff filterを提案した.これは既存の方法よりも優れた性能を示すが,モデルが高次元の場合には適用できない.この点を解決すべく,ファクター構造やモデルのスパース性を仮定することで次元縮約をしつつFDRをコントロールする枠組みを模索している.
1 0 0 0 OA 物語・説話における絵画化の起源と変容の研究ー日本近世刊本・写本を中心に
- 著者
- 浅野 秀剛 中部 義隆 瀧 朝子 宮崎 もも 古川 攝一 植松 瑞希 西田 正宏 大平桂一 桂一 徳原 賜鶴子 田中 宗博
- 出版者
- 公益財団法人大和文華館
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2009-04-01
物語の絵画化をめぐる諸問題について、物語・和歌系、説話・仏典系、童蒙・勧戒系の三つのグループを中心に研究を進めてきた。特に、『徒然草』と、能・幸若舞・歌舞伎といった舞台芸能のテクストの絵画化をめぐっては、シンポジウムを開催し、国文学・美術史、双方の立場から発表・議論を行い、その問題点や特色について理解を深めることができた。2013年度末には、これまで5年間に行った研究会、シンポジウム、展覧会の成果を報告書にまとめた。
1 0 0 0 5分でできる口腔ケア : 介護のための普及型口腔ケアシステム
1 0 0 0 よい図書館施設をつくる
- 著者
- 植松貞夫 [ほか] 著
- 出版者
- 日本図書館協会
- 巻号頁・発行日
- 2010
1 0 0 0 隠岐諸島および本州-九州におけるカヤネズミの形態変異
- 著者
- 高田 靖司 植松 康 酒井 英一 立石 隆
- 出版者
- The Mammal Society of Japan
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, pp.89-94, 2014
隠岐諸島をはじめ,本州から九州におけるカヤネズミ(<i>Micromys minutus</i>)の12集団について,下顎骨の計測値にもとづき,多変量解析(主成分分析,正準判別分析)をおこない,地理的変異を分析した.その結果,下顎骨について,全体的な大きさ(第1主成分)には集団間で差は認められなかったが,形(第2–第3主成分)には集団間で有意な差が認められた.特に,第2主成分は島の面積との間に有意な相関が認められたので,何らかの要因が形態変異に作用した可能性がある.正準判別分析では,隠岐諸島の集団間で形態変異が認められた.この変異には島の隔離に伴う遺伝的浮動が働いたと考えられた.しかし,下顎骨の大きさ(第1主成分)について集団間で差がみられず,また,遠く離れた地域の集団間で形態的な違いがみられなかった.これは,Yasuda et al.(2005)が明らかにしたように,日本列島におけるカヤネズミの低い遺伝的多様性を反映しているかもしれない.
1 0 0 0 淡路島南部の哺乳類
- 著者
- 宮尾 嶽雄 花村 肇 植松 康 酒井 英一 高田 靖司 子安 和弘
- 出版者
- THE MAMMAL SOCIETY OF JAPAN
- 雑誌
- 哺乳動物学雑誌: The Journal of the Mammalogical Society of Japan (ISSN:05460670)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.3, pp.128-140, 1983
1982年1月23~26日に, 淡路島南部, 諭鶴羽山地北西山麓部の哺乳動物の調査を行なった。翼手類については, 調査できなかった。<BR>1) .生息が認められた哺乳類は, 次の6目16種である。食虫目: ジネズミ, ヒミズ, コウベモグラ。霊長目: ニホンザル。兎目: ノウサギ。齧歯目: ニホンリス, アカネズミ, ヒメネズミ, カヤネズミ, ハツカネズミ。食肉目: タヌキ, テン, イタチ (チョウセンイタチ, ホンドイタチ) 。偶蹄目: イノシシ, シカ。<BR>2) .ムササビ, スミスネズミ, アナグマなどを欠いている点に, 島のファウナの特徴を示している。キツネも絶滅している。<BR>3) .ヒミズは, 腹部を中心に体毛の白化傾向が著しく, また, ヒミズの尾部にカンサイツツガムシの多数寄生例がみられ, 寄生率も高かった。<BR>4) .アカネズミの耳介にネズミスナノミ (<I>Tunga caecigena</I>) の寄生がみられた。淡路島に本種が分布していること, ならびにアカネズミが宿主になっていることは, 新しい知見であろう。