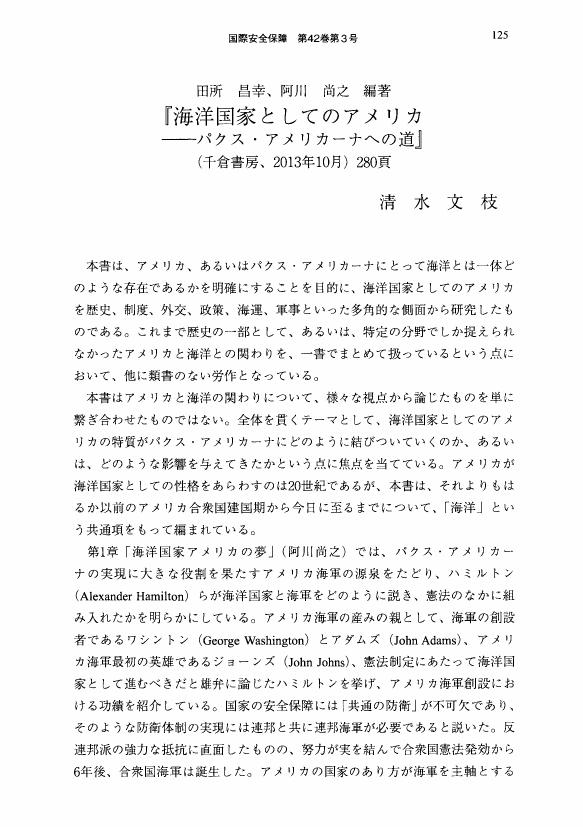1 0 0 0 OA メタファー対照に基づくビジネススピーチ分析
- 著者
- 清水 利宏
- 出版者
- Japanese Society for Global Social and Cultural Studies
- 雑誌
- 国際情報研究 (ISSN:18842178)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.20-28, 2009-12-20 (Released:2016-01-01)
- 参考文献数
- 3
本稿は、自動車産業界のビジネスリーダー、リー・アイアコッカ(クライスラー)とカルロス・ゴーン(日産自動車)が発表したビジネススピーチを対照研究の素材とし、概念メタファーおよびそのメタファー表現の特徴的な役割について考察するものである。両氏のスピーチには、いずれも「工場閉鎖を伴う経営陣の決断を、従業員と地域社会に伝達する」という二者共通の重要な役割がある。今回の研究では、類似の厳しい経営状況下で発表された両スピーチにおけるメタファー表現を手掛かりとし、各概念メタファーの変移傾向を分析することで、両者がいかなるメタファーを用いて、どのように自身の感情を意図通りに伝達(あるいは抑制)しようと試みたのかを考察する。
1 0 0 0 OA 成型爆薬式射出装置の改良とガスガンとの損傷結果比較
- 著者
- 永尾 陽典 木部 勢至朗 清水 隆之 戸上 健治 引地 誠
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 宇宙技術 (ISSN:13473832)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.61-70, 2007 (Released:2007-10-31)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1 1
国際宇宙基地の位置する地球低軌道,静止衛星の位置する高軌道,そして常に高度と位置を変える観測衛星などが位置する楕円軌道など,人工衛星が存在するすべての領域においてデブリの存在と発生が確認されている.また運用を終えた衛星自身はデブリと化し,さらに大小のデブリが互いに衝突して新たにデブリを発生させ,その数を増やす可能性も大きくなっている.これらのデブリと人工衛星などとの衝突が起きる懸念は現実のものとなっており,確認された例が報告されている.その他の未確認衛星故障においてもデブリ衝突が主因である可能性は高いと考えられる.宇宙滞在が2週間程度と短期間の米国スペースシャトルでも帰還後の検査によって微小デブリの衝突痕が確認され,その頻度はこの10年間ではそれ以前に比べて2倍以上であることが報告されている.このようにデブリ増加は具体的なデータによって確認されている. これらの環境を背景に,有人国際宇宙基地の与圧部構造では10 km/secで1 gのデブリ衝突に耐えることが求められ,デブリバンパーで構造を保護している.一方,耐デブリ性能の実証には試験が必要となるが,超高速衝突試験ができる設備は限られている.著者らは10 km/sec 以上の速度を安定的に生成することを目的に,成型爆薬(CSCと称す)による超高速加速装置を開発してきた.しかしCSCによって射出される金属ジェットは,固体と溶融体とが混在する状態(固液混相体と称す)の可能性が高いが,実際の宇宙デブリは固体である.したがって,実構造の耐デブリ性能を正確に評価するには,所定の速度と質量を射出できるCSC装置を用いても,固液混相体によるCSCジェットの衝突と固体の衝突による標的板損傷の相違を明確にし,両者の関係を把握することが必要となる. 著者らはすでに固体を射出できる2段式軽ガスガンのプロジェクタイルと固液混相体を射出するCSCジェットの質量と速度とを同じレベルにし,それぞれの両者による標的板損傷を直接比較するため,2段式軽ガスガンのほぼ上限速度である7 km/secかつ1 gのジェットを射出できるCSC装置を開発し報告した.この開発では所定の速度と質量を満たし,安定したジェット生成を実現できた.しかし先端ジェットの約半分の速度で飛翔する後追いジェットが存在することも確認された.この後追いジェットは、先端ジェットの衝突跡にさらに衝突することになり,固体プロジェクタイルが一個当たる損傷と直接比較することができなかった.従って,これを除去することが必須であり新たな技術課題となった. 本研究は,後追いジェットを除去する方式を新たに考案し,実験により有効性を確認するとともに装置の最適化を行って装置を完成した.また引き続きこの装置によって,本研究の最終的な目的である2段式軽ガスガンと同レベルでの質量と速度で高速射出試験を行い,それぞれの装置による損傷を比較し検討した.この過程で2段式軽ガスガンによるプロジェクタイルとCSC装置によるジェットの形状の差異が与える影響についても実験によって確認し,両者の関係を明らかにした.
1 0 0 0 OA ツキノワグマは春から夏をどうしのいでいるのか?-その行動生態学的研究-
- 著者
- 山崎 晃司 坪田 敏男 小池 伸介 清水 慶子 正木 隆 郡 麻里 小坂井 千夏 中島 亜美 根本 唯
- 出版者
- ミュージアムパーク茨城県自然博物館
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2012-04-01
ツキノワグマの行動生態研究の多くは,秋の食欲亢進期に行われており,春から夏の行動はよく分かっていない。本研究では,各種新型機材を利用し,冬眠明け後の春から夏の野生グマの生理状態の把握と共に,その行動生態の解明を試みた。その結果,夏期には活動量,体温,心拍計共に低下することを確かめた。春は低繊維,高タンパクの新葉が利用できたが,その期間は極めて短かった。夏は食物の欠乏期として捉えられ,夏眠のような生理状態に入ることでエネルギー消費を防いでいたと考えられた。本研究は,秋の堅果結実の多寡だけでは説明できていない,本種の夏の人里への出没機構の解明にも役立つことが期待できる。
1 0 0 0 OA ロシアの中東政策 ―プーチン大統領のシリア政策を通じて
- 著者
- 清水 学
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- 中東レビュー (ISSN:21884595)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.49-73, 2016 (Released:2019-12-03)
The active initiative taken by Russian President Vladamir Putin by bombarding the antigovernment forces in Syria at the end of September 2015 startled the world by its precalculated boldness. Russian intervention has radically changed the dynamic of the war by empowering the Syrian government of Bashar Assad, and has resulted in a ceasefire agreement which starts on 27th February 2016, led by Russia and the US. No one can predict at present the next stage of conflicts in Syria or whether it will result in a positive solution to the tragic wars there. However, there is no denying the fact that Russia has played an important role in the development of the game. This paper analyzes the motivations of Putin in intervening in the Syrian crisis and the factors which have enabled Russia to play an enlarged role in the Middle East, seemingly beyond its objective capabilities. Legacies of international networks built during the Soviet period; shrewd tactics in making use of the inconsistency and vacillation of US policies, particularly towards the Middle East; its historical experience of interaction with the Muslim cultures, including domestic ones; its geopolitical perception of world politics, and the export of energy resources and military weapons as tools of diplomacy are some of the factors which explain Russian behavior. At the same time, the personal leadership and accumulated experience of President Putin in formulating Russian diplomacy and in manipulating different issues in a combined policy should be taken into account. His initiative in Syria succeeded to some extent in turning world attention away from the Ukrainian issue, aimed at changing the present sanctions imposed by the West. Another phenomenon to be noted in the international arena is the newly developed mutual interaction between Russia and the Arab countries in the Gulf. Frequent visits to Russia by autocratic leaders, including kings, emirsand princes do not always reflect a shared common interest between Russia and the Arab leaders. On the contrary, in spite of sharp and fundamental differences in their attitude toward the issues related to Syria, Iran and Yemen, the Arab leaders find it necessary to communicate with Russia and to know Russia’s expected strategies and intentions towards the Middle East, apart from its oil and gas policies. The Iran deal on the nuclear issue in July 2015 may have been a factor behind the phenomena.
1 0 0 0 OA イスラエル経済:グローバル化と「起業国家」 第Ⅰ部:ネオリベラリズムとグローバル化
- 著者
- 清水 学
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- 中東レビュー (ISSN:21884595)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.42-53, 2017 (Released:2019-11-12)
With its geopolitical implications, Israel’s presence in the Middle East is conspicuous. Over the last two decades, Israel has rapidly expanded its sphere of influence to other parts of the world through economic transactions. Its dramatic development has been supported by its economic globalisation and high-tech industry. Israel currently belongs with the developed economies as a member state of the OECD, with a per-capita income of US$ 35,000, and is often referred to as a “success story” that other countries can draw lessons from for their own economic development.Part One attempts to analyse the factors, mainly related to economic policies, which contributed to the paradigm shift in Israel’s development strategy from the Zionist socialistic ideology to the neoliberal globalising policy orientation. The turning point was the economic reform introduced in 1985, which enabled the Bank of Israel to play an independent and leading role in monetary and fiscal policies against the rampant hyperinflation at the time. However, it should be noted that the reform package was a co-product of Israel and the US administration, supported by financial assistance attached to the reform. For the US, an economically stabilized Israel was an essential strategic asset against the Soviet Union. Since then, various reforms were introduced gradually, such as liberalisation of the labour market, privatisation, liberalisation of the financial market, and capital transfers. However, the voluminous favourable grant from the US was essential in absorbing balance of payment constraints and various social tensions through the transition period. Therefore, Israel’s transition to a neoliberal globalised economy was not a model that could be easily imported by other developing countries in the region.
1 0 0 0 OA 静止立位時の足趾接地状態が歩行に与える影響
- 著者
- 長谷川 正哉 島谷 康司 金井 秀作 沖 貞明 清水 ミシェルアイズマン 六車 晶子 大塚 彰
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.3, pp.437-441, 2010 (Released:2010-07-28)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 6 2
〔目的〕浮き趾が歩行中の足底圧に与える影響について調べることを目的とした。〔対象〕健常成人女性104名に対し静止立位時の足趾接地状態の評価を行った結果から,浮き趾群20名および完全接地群15名を実験対象として抽出した。〔方法〕浮き趾群および完全接地群に対し歩行中の足底圧の計測を行い,足趾および前足部の荷重量,足底圧軌跡の軌跡長を抽出し比較検討した。また軌跡の特徴を分類し比較検討した。〔結果〕完全接地群と比較し浮き趾群では,足底圧軌跡長,足趾荷重量が小さく,足底圧軌跡が足趾まで到達しないことが確認された。〔結語〕浮き趾群では足趾による安定した支持基底面の形成ができず,歩行中の重心の前方移動が困難であること,および中足骨頭部に荷重が集中し,足部のアライメント異常につながる可能性があることが示唆された。
- 著者
- 清水 由里子
- 出版者
- 内陸アジア史学会
- 雑誌
- 内陸アジア史研究 (ISSN:09118993)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.125, 2012-03-31 (Released:2017-10-10)
1 0 0 0 OA カシュガルにおけるウイグル人の教育運動(1934-37年)
- 著者
- 清水 由里子
- 出版者
- 内陸アジア史学会
- 雑誌
- 内陸アジア史研究 (ISSN:09118993)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.61-82, 2007-03-31 (Released:2017-10-10)
1 0 0 0 OA 中国新疆維吾爾自治区档案館における史料調査(研究動向)
1 0 0 0 OA 巻頭言 特集「ポスト真実と民主主義のゆくえ」に寄せて
- 著者
- 清水 晋作
- 出版者
- 東北社会学研究会
- 雑誌
- 社会学研究 (ISSN:05597099)
- 巻号頁・発行日
- vol.103, pp.1-5, 2019-10-16 (Released:2021-10-24)
- 参考文献数
- 11
1 0 0 0 OA 最後の知識人 ダニエル・ベル ベルの知識人論とニューヨーク知識人
- 著者
- 清水 晋作
- 出版者
- 東北社会学研究会
- 雑誌
- 社会学研究 (ISSN:05597099)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, pp.63-82, 2015-07-10 (Released:2022-01-21)
- 参考文献数
- 28
本稿は、知識人ダニエル・ベルの死がもつ意味を考察し、ベルの知識人論を検討することによって、「知識人の死」というテーマについて論じる。ベルは、二〇一一年一月に亡くなったが、「公共知識人」と評されるニューヨーク知識人の一員であり、さらにはその知識社会における中心的存在であった。R・ジャコビーは、ベルを含む同世代のニューヨーク知識人たちを「最後の知識人」と評価した。知識人として「公衆」に訴えかけるスタイルをとった最後の世代という意味である。 ベルの知識人論において、ニューヨーク知識人の特徴が示される。ニューヨーク知識人たちが共通にもつ特徴は、イデオロギーを掲げ、疎外の感覚をもち、思想闘争に参画してきたことである。ただしベル自身は、他のニューヨーク知識人と比べて、関心と活動の範囲が広く、特異な位置を占めていた。ベルは、公共政策の領域に深く関わり、政策レベルの論争に踏み込むことがしばしばあった。そのうえで、強い理論的志向を併せもち、彼の究極的意図は、社会学理論の再構築にあった。 知的専門分化が進み、そうした知的状況への批判として「公共社会学」について活発に議論される時代にこそ、「公共知識人」として評価されるベルやニューヨーク知識人の足跡を辿ることに意義があろう。
1 0 0 0 OA 尊王思想と出版統制・編纂事業
- 著者
- 清水 光明
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.129, no.10, pp.34-55, 2020 (Released:2021-12-01)
本稿の目的は、近世後期の尊王思想の流通について、幕府の政策(出版統制と編纂事業)との関係で再検討することである。ここでいう尊王思想とは、大政委任論・「みよさし」論・朝廷改革構想・尊王攘夷思想等を念頭に置いている。先行研究は、これらの尊王思想に関してその形成過程や機能に着目してきた。例えば、中国思想(朱子学)との関係や、内政状況(宝暦・明和事件や尊号一件)、外政状況(対露関係やペリー来航)、幕末の政治状況(将軍継嗣問題や安政大獄)等への着目である。 これらの研究は、尊王思想についての基礎的な成果と見做すことができる。その上で、次の課題は以下の二点である。一点目は、尊王思想の流通と幕府の政策との関係である。近世後期の尊王思想は、天皇・朝廷の権威の上昇や対外危機の勃発によって、幕府の統制を越えて流布したというイメージがある。このイメージは、天保改革における出版統制の強化によって補強される。しかし、尊王思想は、近世後期には広く公然と流布していた。例えば、中井竹山『草茅危言』、頼山陽『日本外史』、会沢正志斎『新論』等である。何故このような現象が生じたのであろうか。本稿では、幕府の政策(出版統制と編纂事業)との関係から、尊王思想が流布する過程と環境を検討する。 二点目は、天皇像と他の為政者像との関係である。よく知られているように、近世日本では幕府が朝廷を厳しく統制した。したがって、この時代の天皇像を考察するためには、天皇と他の為政者(将軍や大名)との相互関係に留意する必要がある。 以上の観点を踏まえて、本稿では、まず十八世紀から十九世紀にかけての出版統制の変遷と編纂事業の展開を跡付ける。その上で、天保改革において出版統制が大きく変更された経緯や背景を検討する。そして、その変更の結果や機能について分析する。これらの考察を通して、本稿ではこの出版統制の変更(一部規定の緩和)が尊王思想の流通や近世から幕末への連続面・非連続面を考える上で重要な転換点であることを明らかにする。
- 著者
- 清水 真志
- 出版者
- 経済学史学会
- 雑誌
- 経済学史研究 (ISSN:18803164)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.72-73, 2021 (Released:2022-01-13)
1 0 0 0 OA 田所 昌幸、阿川 尚之 編著『海洋国家としてのアメリカ――パクス・アメリカーナへの道』
- 著者
- 清水 文枝
- 出版者
- 国際安全保障学会
- 雑誌
- 国際安全保障 (ISSN:13467573)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.3, pp.125-129, 2014-12-31 (Released:2022-04-07)
1 0 0 0 OA 「保護する責任」と国連システム ―普遍的な規範形成とその実施をめぐる諸問題―
- 著者
- 清水 奈名子
- 出版者
- 国際安全保障学会
- 雑誌
- 国際安全保障 (ISSN:13467573)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.24-40, 2012-09-30 (Released:2022-04-07)
1 0 0 0 OA テロリズムと経済
- 著者
- 清水 寛文
- 出版者
- 国際安全保障学会
- 雑誌
- 国際安全保障 (ISSN:13467573)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.67-82, 2010-09-30 (Released:2022-04-14)
1 0 0 0 OA アラン・B・クルーガー著(藪下史郎訳)『テロの経済学―人はなぜテロリストになるのか』
- 著者
- 清水 寛文
- 出版者
- 国際安全保障学会
- 雑誌
- 国際安全保障 (ISSN:13467573)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.4, pp.95-99, 2009-03-31 (Released:2022-04-20)
- 著者
- 清水 奈名子
- 出版者
- 一般財団法人 日本国際政治学会
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.2022, no.206, pp.206_204-206_207, 2022-03-25 (Released:2022-03-31)
1 0 0 0 OA 数学史との50年(アゴラ)
- 著者
- 清水 達雄
- 出版者
- 日本科学史学会
- 雑誌
- 科学史研究 (ISSN:21887535)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.244, pp.266-267, 2007 (Released:2021-08-09)
1 0 0 0 OA Faradayにおける単極誘導の実験
- 著者
- 須藤 喜久男 清水 孝一
- 出版者
- 日本科学史学会
- 雑誌
- 科学史研究 (ISSN:21887535)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.154, pp.106-113, 1985 (Released:2021-04-07)