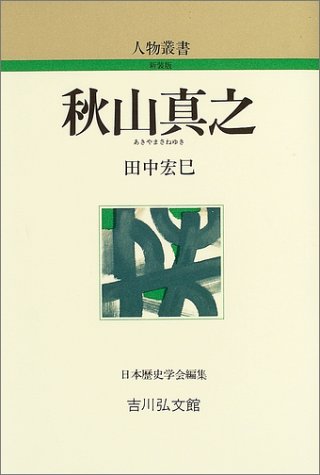1 0 0 0 OA 空間の心理評価における評価対象および評価方法の検討
- 著者
- 田中 宏子 植松 奈美 梁瀬 度子
- 出版者
- Japan Human Factors and Ergonomics Society
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.6, pp.347-356, 1989-12-15 (Released:2010-03-11)
- 参考文献数
- 14
空間の心理評価における実験方法の検討である. まず, 実大模型, 縮尺模型およびスライドの3つの評価対象における心理量の関連をSD法により検討した. 取り上げた要因は居間に置かれた家具の量と配置である. 因子分析の結果, いずれの評価対象も2つの共通因子が析出され, 価値因子と活動性因子と意味づけた. 活動性因子においては3者の感覚は非常に似通っていたが, 価値因子については在室感・臨場感といった空間と人間との相互作用が影響しており, 空間の価値判断と深い関わりがあると考えられる. ついでSD法の評価の妥当性を確認するために, ME法, 一対比較法の比較検討も試みた. その結果, かなりの整合性が認められた.
- 著者
- 田中 宏明
- 出版者
- 北海道大学高等教育推進機構
- 雑誌
- 高等教育ジャーナル : 高等教育と生涯学習 (ISSN:13419374)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.37-42, 2016-03
- 著者
- 田中 宏和 田淵 貴大 片野田 耕太
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- pp.22-061, (Released:2022-11-28)
- 参考文献数
- 36
目的 新型コロナウイルスワクチン接種状況と,旅行や飲食店利用など経済活動の活性化に向けた接種証明書(ワクチンパスポート)の活用に関して人々の意識を明らかにすることを目的とした。方法 2021年9-10月に実施された「日本におけるCOVID-19問題による社会・健康格差評価研究(JACSIS研究)」のデータから,最終学歴および職業ごとのワクチン接種率と接種率比を算出した。また,「ワクチン接種済み(2回)」群と「ワクチンの接種を希望しない」群に分けて「ワクチンを接種した(しない)理由」をそれぞれ分析した。さらに,ワクチンパスポートを「経済回復のために活用すべきだ」と考える割合と性・年齢階級・職業・最終学歴や政府のワクチン情報の信頼などとの関連を分析した。結果 27,423人の調査参加者(20-79歳;女性13,884人,男性13,539人)のうち,「ワクチン接種済み(2回)」が20,515人(74.8%),「接種したくない(接種希望なし)」が1,742人(6.3%)であった。ワクチン接種率は性で差がなく,『大学・大学院卒業者』は『高校卒業者』に比べて有意に接種率が高かった(調整済み接種率比,1.09;95%信頼区間:1.07-1.12)。職業別では『事務職』に対する『専門・技術職』の調整済み接種率比は1.05(95%信頼区間:1.01-1.09)であった。「ワクチン接種済み(2回)」群のうち,接種した理由で最も多かったのは「家族や周りの人に感染させたくないから」の53.0%だった。一方で,接種したくない理由で最も多かったのは「副反応が心配だから」の44.5%だった。ワクチンパスポートについて「経済回復のために活用すべき」と答えたのは「ワクチン接種済み(2回)」群で41.8%であり,「接種したくない」群で12.2%であった。職業別では『営業販売職』(40.4%)で最も高かった。この割合は,「政府のワクチン情報を信頼している」群(49.5%)では「どちらでもない」群(27.5%)に比べて有意に高かった(P<0.01)。結論 学歴や職業でワクチン接種率に差があること,政府のワクチン情報を信頼する人ほどワクチンパスポート活用に肯定的であることが明らかになった。しかし,経済活動の活性化のためのワクチンパスポート活用に関して,人々の期待や関心は社会全体では高くないことが示唆された。
1 0 0 0 OA 学生実験用NMR装置の開発
- 著者
- 田中 宏樹
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.234-250, 2012 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 26
本稿は,2000年代に進んだ公教育の分権化が,教育行政をめぐる自律性を志向した首長の政治的支持の上昇に結びついているかを,理論モデルから導かれる回帰式を推定することで実証的に解明する。より具体的には,都道府県別プール・データを用いて,2000年代中盤に進んだ義務教育費国庫負担金の総額裁量制への移行が,知事選での業績投票的な意味合いを強める方向に作用し,都道府県レベルでのElectoral Accountabilityの上昇に寄与したか否かを,実証的に解明することに力点を置く。実証分析の結果,公教育サービスの水準やその提供に要した財政措置は,有権者による知事の業績判断の材料となって,その政治的支持・不支持の決定に結びついているという理論の帰結が支持された。
1 0 0 0 OA 東欧におけるグローバル化と地域変容
- 著者
- 田中 宏
- 出版者
- ロシア・東欧学会
- 雑誌
- ロシア・東欧研究 (ISSN:13486497)
- 巻号頁・発行日
- vol.2001, no.30, pp.25-39, 2001 (Released:2010-10-27)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1
More than one decade has passed since“Berlin wall”fell down in 1989 in the Eastern Europe. This transformation has opened the door for East European countries to be integrated into the global economy. What influence did this globalization put on the regional changes in the transition of Eastern Europe?The purpose of this paper lies in analyzing the problems of these regional changes, aiming at breaking through the limits of research studied on the basis of the analysis unit of the state, industrial sector and enterprise.Chapter 1 characterizes the regional changes of Eastern Europe as follows, (1) rising and expanding of the new regional differentials in the whole European continent, (2) expanding of north-south differentials inside the Eastern Europe, (3) appearance of the new 4 types of area differential inside any East European country (leading areas, loser areas, negatively continuative areas and new entry areas in market transition), (4) administration, infrastructures, institutions and policies concerning the region are being restructured and newly shaped, upon which pressure of joining the EU has given a decisive influence.Chapter 2 is confined to Hungary, analyzing how the area-territorial structure has been changed under the influence of foreign capital investment inflows. The point to understand here is that the multilateral functional elements accumulated in the long term in the local areas constitute their characters by coming in touch with FDI.Chapter 3 is devoted to review the above regional changes in the historical perspective of 20th century, during which this East European region has been transformed three times. The industrialization in the beginning of 20th century gave birth to disproportionate and uneven regional development. Introduction of state socialism after the WW II produced the convergence of regional unevenness and contractions in a degree with some differentials among the areas left to some extent. And then, at the end of this century, the regions are faced with the alternative choice of mercantilist type development of regional economy or multinational firm one.As for this choice, developing of post-Fordism in the whole European continent has put great influence upon regional development in the Eastern Europe.
1 0 0 0 OA 東欧の体制移行と対外環境 ―地域協力とEU加盟から見えること―
- 著者
- 田中 宏
- 出版者
- ロシア・東欧学会
- 雑誌
- ロシア・東欧学会年報 (ISSN:21854645)
- 巻号頁・発行日
- vol.1998, no.27, pp.30-37, 1998 (Released:2010-05-31)
- 参考文献数
- 17
1 0 0 0 OA 形状可変アンテナにおけるアンテナゲイン情報を用いた変形形状推定
- 著者
- 田中 宏明
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 宇宙技術 (ISSN:13473832)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.19-25, 2008 (Released:2008-04-01)
- 参考文献数
- 19
For a reconfigurable antenna system, antenna surface deformations should be measured to achieve a high precision antenna system. In this study, a novel measurement method of antenna surface deformations is proposed. Relations between surface errors and changes of the antenna gains caused by intentional deformations are derived from the Ruze equation. In this method, an antenna surface is deformed additionally using surface adjustment mechanisms and changes of the gains caused by the intentional deformations are measured. An original deformation of the antenna surface is estimated using the relations. Some numerical simulations are carried out to investigate the feasibility of this method. From the results of the simulations, it is shown that the antenna deformations are estimated adequately by using this method.
1 0 0 0 OA 肝切除術における自己血輸血の有用性
- 著者
- 麦谷 達郎 谷口 弘穀 高田 敦 増山 守 田中 宏樹 小山 拡史 保島 匡和 高橋 俊雄
- 出版者
- Japan Surgical Association
- 雑誌
- 日本臨床外科医学会雑誌 (ISSN:03869776)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.6, pp.1295-1301, 1996-06-25 (Released:2009-02-10)
- 参考文献数
- 21
肝切除術71例を対象に自己血輸血法の有用性を検討した.貯血式自己血輸血を44例に施行した.術前貯血量は, rh-エリスロポェチン併用群で550g(平均値)とrh-エリスロポエチン非併用群より有意(p<0.05)に多く,採血後のHct値の低下はrh-エリスロポエチン非併用群と同程度に留まった.術中輸血法に関しrh-エリスロポエチン非併用自己血, rh-エリスロポエチン併用自己血,同種血,無輸血に分類し,術後の変化を検討した.術後Hct値は,同種輸血群で回復遅延を認め,第14病日に29.4%と他の3群より低値であった.術後総ビリルビン値,血中肝逸脱酵素は,同種輸血群で第1病日に他の3群に比し有意な上昇を認めた.自己血輸血の2群は無輸血群と同様の経過を示し,総ビリルビン値の上昇も1.20と軽度で,肝切除術には同種輸血は避け,自己血輪血が望ましいと考えられた.また,術前貧血の無い場合,術前貯血量800g, 術中出血量1,500g以下が同種輸血なしに自己血輪血のみで行える指標になると考えられた.
1 0 0 0 OA ニュートリノ観測から制約する核-マントルの化学組成
第一に、地球ニュートリノ流量モデリング法を地球科学的アプローチから見直すことにより、地震波トモグラフィのデータが得られればほぼ自動的にニュートリノフラックスを計算する方法が開発され、今後、世界的に爆発的な蓄積量増加が期待される地球ニュートリノ観測データに対応できる方法論を確立した。第二に、地球ニュートリノデータの安定取得方法論を確立した。第三に、到来方向検知型検出器の原理検証を模擬粒子を用いて行い、将来の地球ニュートリノイメージングに向けた技術基盤とした。
1 0 0 0 OA 骨接合の術後感染に対しインプラントを温存し得た症例
- 著者
- 上田 幸輝 佐々木 大 田中 宏毅 溝口 孝 伊東 孝浩 内村 大輝 水城 安尋 萩原 博嗣
- 出版者
- 西日本整形・災害外科学会
- 雑誌
- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.13-15, 2017-03-25 (Released:2017-05-01)
- 参考文献数
- 14
症例は43才女性.バイク事故による右脛骨プラトー骨折で創外固定と2回のプレート固定術を施行後,創より浸出液がつづき,培養でMRSEが検出されインプラント周囲感染と診断したが,インプラントが抜去できなかったため,術後2週よりリネゾリド,ミノマイシン,リファンピシンで治療開始した.開始後7日でCRP陰転化,16日で排液がなくなりその後再増悪を認めていない.骨接合術後に感染を生じた際はbiofilmの存在を考慮して,骨髄移行性とバイオフィルム透過性に優れた抗生剤を使用するべきである.
1 0 0 0 OA 現代日本語におけるドイツ語系外来語の概要
- 著者
- 田中 宏幸
- 出版者
- 金沢大学教養部 = The College of Liberal arts, Kanazawa University / 金沢大学 = Kanazawa University
- 雑誌
- 金沢大学教養部論集. 人文科学篇 = Studies in Humanities by the College of Liberal arts Kanazawa University (ISSN:02858142)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.89-126, 1986-03-20
1 0 0 0 OA 運動制御と感覚処理の最適理論
- 著者
- 田中 宏和
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.7, pp.500-505, 2017 (Released:2017-10-01)
- 参考文献数
- 17
1 0 0 0 OA 現代ドイツ語の語彙と造語の特色
- 著者
- 田中 宏幸
- 出版者
- 金沢大学教養部 = The College of Liberal arts, Kanazawa University / 金沢大学 = Kanazawa University
- 雑誌
- 金沢大学教養部論集. 人文科学篇 = Studies in Humanities by the College of Liberal arts Kanazawa University (ISSN:02858142)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.83-104, 1976-03-10
1 0 0 0 OA 気管支喘息児におけるトレーニング療法の効果
- 著者
- 荒木 速雄 加野 草平 西間 三馨 小笠原 正志 松崎 守利 田中 宏明 田中 守 進藤 宗洋
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.3-1, pp.205-214, 1991-03-30 (Released:2017-02-10)
- 被引用文献数
- 1
気管支喘息児12名に自転車エルゴメーターを用いて4週間のトレーニングを行い, WBPLA_1 (work load at first braking point of lactic acid) より設定した5段階負荷強度にて physical working capacity の向上, EIB の改善をトレーニング前後で比較した. また, 高張食塩水吸入による気道反応の変化についても検討し, 以下の結果を得た. 1)心拍数はトレーニング前の WBPLA_1 175%強度に相当する仕事率で, トレーニング前値の188.5±9.6bpmよりトレーニング後178.4±9.7bpmへと, また WBPLA_1 150%強度では174.0±11.9bpmより165.6±11.3bpmへと, それぞれトレーニング後に有意に低下した. また最大酸素摂取量(Vo_2max/wt)は34.5ml/min/kgより41.lml/min/kgに有意に上昇した. 2) FEV_<1.0>の運動負荷後のMax.%fall は WBPLA_1 175%強度にて, トレーニング前37.4±17.4%よりトレーニング後30.3±17.4%へと, また WBPLA_1 150%強度では27.1±24%より18.0±17.1%へとそれぞれトレーニング後に有意に低下した. 3) 3.6%高張食塩水吸入試験ではトレーニング群においてPD_<20>は4.2±5.9mlから8.1±8.0mlへと有意に増加した. なお, コントロール群では3.7±5.8mlより4.3±6.3mlへと有意な変化は認められなかった.
1 0 0 0 OA 妊婦の生理学
- 著者
- 田中 宏和
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.4, pp.533-537, 2018-07-15 (Released:2018-08-29)
妊娠時は週数に応じたさまざまな生理的変化をきたす.血液学的な変化は顕著で,妊娠後期にピークとなる血液量の増加,凝固系の機能亢進と線溶系の抑制が起こる.血液量の増加に伴い心機能は亢進し,循環血液量の増加によって腎機能も亢進する.また呼吸機能は子宮の増大に伴い横隔膜の運動は制限されるが,横隔膜挙上による機能的残気量の減少によって亢進し,酸・塩基平衡にも影響を与える.妊娠による内分泌環境の変化による糖や脂質代謝の変化も特異的である.さらに増大した子宮と内分泌環境の変化は,消化器系,尿路系,骨格系にも影響を及ぼす.それぞれが,妊娠に適応し分娩に対応できるように,合目的的な変化となっている.
- 著者
- 福元 伸也 Rehman Anis Ur 森東 淳 大塚 作一 三部 靖夫 田中 宏征 武田 光平 野村 雄司
- 出版者
- 一般社団法人 画像電子学会
- 雑誌
- 画像電子学会誌 (ISSN:02859831)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.5, pp.842-850, 2011-09-25
- 参考文献数
- 18
広告の意匠性と2次元デジタルコード(以下,コードと略す)を用いた情報伝達の容易性とを両立させることを目的として,コード撮影のために行う利用者の接近行動を距離センサにより検出することにより,コードを適応的に拡大表示する手法を提案する.まず,基礎実験として,実験1では,コードの拡大率とズーム時間の変化に対する利用者の印象変化を調査した.その結果,利用者が移動中の状態から一辺20cm程度の取得容易なコードサイズにズームアップした状態で停止する場合を想定すると,ズーム時間を1秒前後に設定すればよいことが明らかとなった.次に,実験2では,距離センサによるフィードバックを行ったプロトタイプを使用し,QRコード利用の未経験者4名を含む被験者14名による評価実験を行った.従来手法と提案手法との比較を行った結果,(1) 提案手法では平均情報取得時間が約1.8秒短縮される,(2) 提案手法では約1.5倍遠い位置での取得が可能となる,(3) 全被験者の86%(QRコード利用の経験者では100%)が提案手法を好む,という結果が得られ,本手法の有効性が確認された.
- 著者
- 田中 宏和
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.4, pp.276-285, 2021
<p><b>はじめに</b> 2019年末に中華人民共和国湖北省武漢市で初報告された新型コロナウイルス感染症(COVID-19)はわずか数か月で世界的に拡大し,欧州でも多くの感染者を出した。本稿はオランダにおける2020年7月末までの感染拡大とその対応についてまとめ,新興感染症による公衆衛生の海外での体験を一例として共有することを目的とした。</p><p><b>疫学</b> 2020年2月27日に初めての新型コロナウイルス感染症患者が確認されてから感染が急拡大し,第一波は新規感染者・死亡者ともに4月10日ごろにピーク(日別新規感染者1,395人,日本の人口換算で約10,000人)を迎えた。その後,感染拡大は収束したが5月31日時点で感染者46,422人,入院患者11,735人,死亡者5,956人が累計で報告された。死亡のほとんどが60歳以上で発生し,男性は80-84歳で,女性は85-89歳でそれぞれピークとなっていた。地理的な広がりとしてはアムステルダム・ロッテルダムといった都市圏での感染者は相対的に少なく,南部の北ブラバント州・リンブルフ州で多かった。</p><p><b>オランダ政府の対応</b> オランダ政府の対策の特徴は,最初の感染者の確認からわずか2週間で全国的な都市封鎖に追い込まれたこと,比較的緩やかな都市封鎖措置と行動制限を実施したこと,社会・経済活動の再開までに約3か月を要したことが挙げられる。2020年3月12日から段階的に全国的な対策を施行し,3月下旬にルッテ首相がインテリジェント・ロックダウン(Intelligent Lockdown)と呼ぶオランダ式の新型コロナウイルス感染防止対策が形成された。5月中旬以降,子どもに対する規制が緩和されたが対策措置の多くは6月中旬まで続き,段階的な緩和をもって社会・経済活動が再開,7月1日にほぼすべての規制が解除された。それ以降,在宅勤務の推奨,1.5メートルの社会的距離を取ることや公共交通機関でのマスク着用義務化など新しい日常への模索が続いている。</p><p><b>おわりに</b> オランダにおける感染拡大防止策は多様性と寛容に裏打ちされたオランダの国民性を体現したものだったが,感染者数および死亡者数は日本より深刻な状況であった。健康危機管理に関する他国の政策の評価には公衆衛生や医療資源の評価とともに,その背景にある社会の特徴を考慮することが重要である。</p>
1 0 0 0 ガンジーさんのいう「社会的罪」
- 著者
- 田中 宏樹
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.9, pp.88-89, 1999