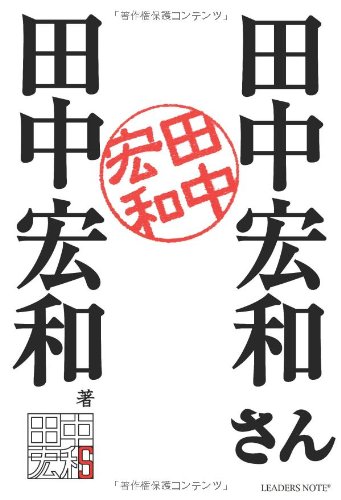2 0 0 0 論考 景勝期上杉氏の情報と外交--対豊臣氏交渉を中心として
- 著者
- 田中 宏志
- 出版者
- 駒沢大学大学院史学会
- 雑誌
- 駒沢大学史学論集 (ISSN:02865653)
- 巻号頁・発行日
- no.30, pp.35-44, 2000-04
2 0 0 0 田中宏和さん
- 著者
- 田中宏和 [ほか] 著
- 出版者
- リーダーズノート
- 巻号頁・発行日
- 2010
2 0 0 0 実用豚肉加工法 : 附・製革法
- 著者
- 田中宏, 大木市造 著
- 出版者
- 西ケ原刊行会
- 巻号頁・発行日
- 1933
2 0 0 0 現代日本の愛国主義とコスモポリタニズム(1)憲法・教育・歴史
- 著者
- 田中 宏明
- 出版者
- 宮崎公立大学
- 雑誌
- 宮崎公立大学人文学部紀要 (ISSN:13403613)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.99-118, 2004
現代日本は愛国主義化している。その日本とはどのようなものであり、そしてそれがどのような問題をもたらすのか。こうしたことを考察するために、愛国主義への対抗軸とじてコスモポリタニズムを置き、それに「大きな政府とリベラル・デモクラシー」と「強い国家とネオリベラリズム」との対抗関係を交え、その中で特に、「強い国家とネオリベラリズム」と「民主的コスモポリタニズム」の対抗関係に注目したい。この対抗関係はグローバリゼーションの文脈における対抗関係でもある。これを軸に現代日本における争点となる問題を検討する。すなわち、憲法、教育基本法、そして歴史認識/戦争観について考えることにしたい。最後に、以上の議論を現代日本の課題としてまとめ結論とする。
- 著者
- 竹内 孝治 古川 修 田中 宏典 西脇 秀幸 岡部 進
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.2, pp.123-133, 1986
- 被引用文献数
- 3
elcatoninのラットの急性胃・十二指腸損傷の発生,胃液分泌,十二指腸alkali分泌,胃運動に対する効果を検討した.elcatoninは以下の実験で全て皮下投与した.elcatonin 30 unit/kgの投与により塩酸・aspirin,塩酸・ethanol胃損傷の発生を各々81.6%,49.7%(P<0.05)抑制した.水浸ストレス,indomethacin胃損傷の発生もelcatoninは用量依存的に抑制し,前者の損傷は30 unit/kgで77.6%,後者の損傷は10 unit/kgで98.7%(P<0.05)抑制された.elcatonin 30 unit/kgの2回投与はmepirizole十二指腸損傷の発生に対して抑制の傾向(32.7%)を示したが,胃損傷の発生は著明に抑制した.indomethacin·histamine十二指腸損傷の発生に対してはelcatonin 30 unit/kgは59.5%(P<0.05)の抑制を示した.胃損傷もまた抑制した.対照薬として使用した16, 16-dimethylprostaglandin E<SUB>2</SUB>(16-dmPGE<SUB>2</SUB>)は各種胃・十二指腸損傷モデルを3~30 μg/kgの経口投与で強力に抑制した.elcatonin 10および30 unit/kgは幽門結紮ラット(4時間法)での胃液量,酸およびpepsin排出量を有意に抑制した.16-dmPGE<SUB>2</SUB> 3,10,30 μg/kgの十二指腸内投与で胃液には影響を与えなかった.elcatonin 30 unit/kgは十二指腸のアルカリ分泌に影響はなかったが,16-dmPGE<SUB>2</SUB> 30 μg/kgはアルカリ分泌を亢進した.elcatoninおよび16-dmPGE<SUB>2</SUB>は胃運動を2時間有意に抑制した.以上の結果よりelcatoninは抗胃および十二指腸損傷作用を有し,その機序の一部は胃液分泌および胃運動に対する抑制作用に基くことが示された.
- 著者
- 田中 共子 兵藤 好美 田中 宏二
- 出版者
- 日本社会心理学会
- 雑誌
- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.39-50, 2002
- 被引用文献数
- 3
This study analyzed 251 completed questionnaires concerning the social support network of caregivers for elderly family members. The hierarchy of social support resources was assumed to be in the order of co-resident family members, non-resident family members, friends, and neighbors to professional caregivers. Using the subcategory comparison method showed that a lower member compensates for a higher member's absence for emotional and instrumental support, and thus a hierarchical compensation model was supported. Social support network members conformed to the task specificity model regarding emotional, minor and major instrumental support, companionship, and informational support. Further, for companionship and informational support, particular resources indicated that compensation depends upon task specificity. Therefore, revision of the hierarchical compensation model is suggested. Caregiver levels of life satisfaction in cases of coresident family support are than those of non-resident family support. The importance of family support, the possibilities of compensation, and the differences of social support networks that depend on the relationships between caregivers and caretakers, are discussed.
2 0 0 0 OA 計算論的神経科学のすすめ : 脳機能の理解に向けた最適化理論のアプローチ
- 著者
- 田中 宏和
- 出版者
- 物性研究刊行会
- 雑誌
- 物性研究 (ISSN:07272997)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, no.2, pp.143-229, 2009-11-05
この論文は国立情報学研究所の電子図書館事業により電子化されました。
2 0 0 0 OA 加速度センサーを内蔵した歩数計による若年者と高齢者の日常身体活動量の比較
- 著者
- 樋口 博之 綾部 誠也 進藤 宗洋 吉武 裕 田中 宏暁
- 出版者
- 日本体力医学会
- 雑誌
- 体力科學 (ISSN:0039906X)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.111-118, 2003-02-01
- 被引用文献数
- 22 13
Daily energy expenditure has been measured by the physical activity recording and/or the questionnaire method. Recently, the accelerometer or pedometer is used to measure daily energy expenditure. The purpose of this study was to examine validity of the pedometer with accelerometer and to compare the daily physical activity between young and older Japanese. To examine validity of the pedometer, 10 young subjects worn the pedometer (Lifecorder) on the waist and then performed the walking test. Energy expenditure was measured by the expired gas analysis during the test. Fourty-three young and 54 older subjects worn the Lifecorder on the waist during free-living condition for 14 days. The intensity of Lifecorder had a high correlation with the physical activity intensity (METs) (r=0.958, P<0.001). In the free-living condition, daily energy expenditure was 2171±305 kcal in young and 1617±196kcal in older (P<0.001). Total step in young was significantly higher than older (young : 9490±2359 steps ; older : 6071±2804 steps. P<0.001). There was no significant difference in the duration of physical activities at the Lifecorder intensity 1 such as desk working, watching TV sitting on a sofa and driving a car. However, the duration more than the intensity 2 corresponding to 2.2 METs in young subjects was longer than that in older (P<0.001). We concluded that in older subjects, not only amounts of daily energy expenditure but also intensities of daily living were lower compared to the young subjects.
2 0 0 0 ミュー粒子を用いた火山内部のイメージング(交流)
- 著者
- 田中 宏幸
- 出版者
- 一般社団法人日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理學會誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.2, pp.70-79, 2010-02-05
- 被引用文献数
- 1
省電力・分割可搬型宇宙線ミュオンテレスコープ(PEAM:Power Effective Assemblable Muon telescope)による火山体の観測が可能になったことにより,活動中の火山の火道内部の詳細を測定できるという新たな進展の機会が得られた.宇宙線ミュオンラジオグラフィー(CMRG)では地震波などを用いた従来の地球物理学的観測に比べて,かつて無い高い空間分解能で山体内部の密度測定が可能である.結果は,世界で初めて可能となったマグマの脱ガス過程の直接的観測の結果から,新たな未解決の問題が提起されている.ここではCMRGの原理,及び火道内でのマグマ対流・マグマ脱ガス現象の物理の基本と宇宙線ミュオンによる火山体内部測定の現状を紹介する.
- 著者
- 水野 武郎 市村 秀樹 柴田 和男 田中 宏紀 山川 洋右 丹羽 宏 正岡 昭
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本肺癌学会
- 雑誌
- 肺癌 (ISSN:03869628)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.55-62, 1985-02-28 (Released:2011-08-10)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1 1
原発性肺癌56例の腫瘍径とtumor doubling timeからGeddesのノモグラムを用いて予測生存期間 (PST) を算出した.このPSTの組織型別平均値は, 扁平上皮癌14.7±11.8月, 腺癌39.9±437.月, 小細胞癌10.4±9.8月, 大細胞癌13.3±9.4月であった.PSTは実際の生存期間 (AST) と密接な相関Y=2.33±0.82X (r=0.80, p<0.01) を示し, 肺癌治療の効果を判定する良好な指標になると考えられた.PSTを大きく上廻るASTを示したものは, 1例を除き全例切除例であった.
1 0 0 0 OA 診断付き精神疾患会話コーパスを用いたうつ病の重症度自動分類と特徴量分析
- 著者
- 香月 祥 田中 宏和 中村 啓信 岸本 泰士郎 狩野 芳伸
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第37回 (2023) (ISSN:27587347)
- 巻号頁・発行日
- pp.4Xin150, 2023 (Released:2023-07-10)
我々はこれまで、診断や疾患評価、音声とその文字起こしや音声・言語学的アノテーションが付与されたUNDERPIN大規模精神疾患会話コーパスを構築してきた。このコーパスを用いて、うつ病患者の分類実験を行った。分類の際は、健常者・軽症患者・中等度以上の患者・うつ病と診断されたことがあるがテストの評価値で症状のない患者の4分類を設定し、4分類のすべてのペア6つそれぞれで2値分類を行った。結果、軽症・中等度以上の重症度に応じた分類ができること、また現在の症状にかかわらずうつ病になった性質で分類可能であることを確認した。分類に貢献した特徴量の分析では、重症度ごとに異なる特徴量や共通している特徴量を確認できた。今後は、新しい特徴量を追加しての学習や、特徴のもととなった人手のアノテーションを自動付与するシステムを構築したい。
- 著者
- 田中 宏
- 出版者
- 経済理論学会
- 雑誌
- 季刊経済理論 (ISSN:18825184)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.31-41, 2015-07-20 (Released:2017-07-03)
Does Hungary, one small EU member country located in the Central Eastern Europe, metamorphose into state capitalism? To study his topic is a main task of this paper. This task makes us, however, realize that almost any one did not recognize in the 1990s where Hungary would arrive at through the systemic transformation and preparing for joining the EU, with becoming aware that Hungary had four systemic change tasks to be solved: restoring the national independence and sovereignty, political democratization, joining the EU and transforming into a market economy. More than two decades of transformative struggles show us that capitalisms in Central Easter Europe seem to have been converted into a diff erent type of capitalism from those in Western Europe and that Hungarian capitalism becomes a different type among Central East European countries in many terms. The unorthodox economic reforms and policies implemented by Fidesz governmental party and its leader Victor Orban after 2010 are not only called 'Orbanomics', but also criticized as state capitalism both inside and outside of Hungary. This paper sheds light on whether and in what terms Hungary is turned into state capitalism. The second part of this paper, following the introduction, first, conducts book and literature reviews, second, discusses state capitalism in the 19th century and 20th century, and then defines state capitalism 3.0 in the 21st century, characterizing its particular features of newly and successfully entering into the world market, and multi-nationalizing of firms with the various helps and supports by the state organs and institutions. The third part describes actual historical processes of the systemic transformation in Hungarian economy from the end of 1980s till the beginning of 2010s, focusing on significant influences upon Hungarian economy exercised by the EU integration, Global Financial and Economic Crisis, and Euro Crisis along with the results of national election every four years. And then the fourth part, uncovering emergent relationships between the state and economic-business circles, examines activities of Hungarian emerging multinationals and re-nationalization movements of firms and public services. Finally, the fourth part reaches conclusions and considers some implications for further studies concerning on this topic. The conclusions summerize characteristic features of Hungarian economy as state capitalism in terms that the state has changed and expanded its role in economic development and interventions, like suspending functions of checks & balances on the state activities, giving (un)preferential treatments to specific groups, increasing the state ownership's share, increasing influences of the state upon newly emerging sectors, abolishing decentralised decision-making, centralizing decision-making and thier competences, changing institutional frameworks of regulations, increasing state-regulations of prices, increasing state regulations and state-capitals especially in the financial sectors, and moving public service activities from under market norms to under the state management and regulations. It reveals legacies of state socialism and traces of neo-liberal type of privatization and market liberalization, providing the evidences to show state capitalism 3.0 in Hungary. In addition it includes new unconventional features of taking special tax measures and regulations on bank-financial sectors. And finally, the paper reconfirms the necessity to look at Hungarian capitalism not only from the state capitalism perspective, but also from the mixed multiple perspectives.
- 著者
- 八十島 誠 友野 卓哉 醍醐 ふみ 嶽盛 公昭 井原 賢 本多 了 端 昭彦 田中 宏明
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集G(環境) (ISSN:21856648)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.7, pp.III_179-III_190, 2021 (Released:2022-03-10)
- 参考文献数
- 37
本研究では,感染者の排泄物に由来する陽性反応の利用が容易な個別施設を対象に,トイレ排水を排除するマンホールでの下水疫学調査でSARS-CoV-2の回収・検出を通じて感染者の早期発見を目的としたパッシブサンプラー(PoP-CoVサンプラー)を開発し,有効性を検証した.SARS-CoV-2中等症感染者が入院する病院施設と軽症者等宿泊療養施設での検証実験の結果,PoP-CoVサンプラーにはSARS-CoV-2が残存しており,マンホール調査での有効性が確認された.またPoP-CoVサンプラーでのCt値はグラブサンプルより最大7.0低かった.本法の社会実装を想定し,111名が勤務する事業場施設で調査を行ったところ,下水から陽性反応が得られた.陽性反応の原因として無症候性感染者からの排泄は否定出来ないものの,下水疫学によって1名の症候性感染者を陽性確定日の4~5日前に発見できる可能性が示唆された.
1 0 0 0 OA 脊髄造影検査にて神経徴候の悪化を生じた椎間板ヘルニアのミニチュアダックスフンド2症例
- 著者
- 坂口 裕亮 田中 宏 北村 雅彦 松本 有紀 中垣 佳浩 松倉 将史 川辺 朋美 中山 正成
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医師会
- 雑誌
- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.8, pp.e193-e196, 2023 (Released:2023-08-05)
- 参考文献数
- 9
CT検査により脊柱管内を大きく占拠する石灰化した椎間板物質を認めた椎間板ヘルニアのミニチュアダックスフンド2症例に遭遇した.2症例ともに脊髄造影検査を実施したところ,神経徴候が悪化した.片側椎弓切除術にて,椎間板物質の摘出を試みたが,周囲組織と癒着しており摘出は困難であった.このことから,CT検査で認められた石灰化した椎間板物質は,脊柱管内で時間経過を経たものと考えられ,脊柱管内を大きく占拠する椎間板物質に長い経過で圧迫されている脊髄に対し,造影剤を注入することで脊髄障害を悪化させた可能性が考えられた.以上より,CT検査によって脊柱管内を大きく占拠する石灰化した椎間板物質を認める症例に対し,脊髄造影検査を実施する際には悪化の可能性を考慮する必要があり,また,手術法やその適応など十分検討が必要であると考えられる.
1 0 0 0 OA 運動, 身体活動が心電図QT間隔延長に及ぼす影響
- 著者
- 道下 竜馬 飛奈 卓郎 松平 奈緒子 樋口 ゆう子 桧垣 靖樹 田中 宏暁 清永 明 Michishita Ryoma Tobina Takuro Matsuhira Naoko Higuchi Yuko Higaki Yasuki Tanaka Hiroaki Kiyonaga Akira
- 出版者
- 福岡大学研究推進部
- 雑誌
- 福岡大学スポーツ科学研究 = Fukuoka University Review of Sports and Health Science (ISSN:13459244)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.2, pp.13-23, 2015-03
1 0 0 0 英国テムズ川における抗生物質の水環境中動態のモデル化
抗生物質による水環境汚染は、世界的に解決すべき喫緊の課題となっている。我々は抗生物質の自然減衰に対して先駆的に研究を行い、英国テムズ川では、国内河川よりも抗生物質の減衰が大幅に速いこと、金属錯体形成反応や河床間隙水塊との水交換といった日本では観測されない反応や現象が生じていることを見出した。しかし、これらの反応・現象に対する知見はまだほとんどない。そこで本研究では、英国テムズ川を対象とし、現地調査、室内実験、数理モデルを駆使して、ⅰ)金属錯体形成反応を考慮した抗生物質の底質への収着のモデル化、ⅱ)河床間隙水塊を考慮した河川水-底質間の抗生物質の移動現象のモデル化、ⅲ)抗生物質の水環境中濃度予測モデルの構築を実施する。本研究は、新たな反応・現象のモデル化により、化学物質、特に現在、世界的課題となっている抗生物質管理に資する普遍的な環境濃度の予測システムを構築するものである。新型コロナウイルス蔓延のため、英国への渡航ができない状況が続いている。令和3年度は、これまで英国との交流のコアとなってきた、第23回日英内分泌かく乱物質・新興化学物質ワークショップが11月29日-30日にオンラインで開催され、それに参加するとともに、以下の内容を共同発表した。人に投与された医薬品の水圏への排出源は概ね明らかになっているが、家畜に投与された医薬品の水圏流出経路は国や地域によって異なっており、十分な知見は得られていない。そこで、本年度は動物用及び人用医薬品の河川調査を、全国各地の畜産地域において年間を通して実施した。また、昨年度構築した、畜産場・下水処理場・浄化槽を排出源とした医薬品の水圏排出モデルによる河川負荷量の予測値と、現地調査による観測とを比較することで、動物用及び人用医薬品の水圏流出量の予測可能性を評価した。
1 0 0 0 OA 諸外国でのがん登録データの地理情報の利用事例とわが国の全国がん登録の諸問題
- 著者
- 片野田 耕太 伊藤 秀美 伊藤 ゆり 片山 佳代子 西野 善一 筒井 杏奈 十川 佳代 田中 宏和 大野 ゆう子 中谷 友樹
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.3, pp.163-170, 2023-03-15 (Released:2023-03-23)
- 参考文献数
- 40
諸外国では,がん登録を始めとする公的統計データの地理情報を用いた研究ががん対策および公衆衛生施策に活用されている。日本でも2016年に全国がん登録が開始され,がんの罹患情報のデータ活用が制度的に可能となった。悉皆調査である全国がん登録は,市区町村,町丁字など小地域単位での活用によりその有用性が高まる。一方,小地域単位のデータ活用では個人情報保護とのバランスをとる必要がある。小地域単位の全国がん登録データの利用可否は,国,各都道府県の審議会等で個別に判断されており,利用に制限がかけられることも多い。本稿では,がん登録データの地理情報の研究利用とデータ提供体制について,米国,カナダ,および英国の事例を紹介し,個人情報保護の下でデータが有効に活用されるための方策を検討する。諸外国では,データ提供機関ががん登録データおよび他のデータとのリンケージデータを利用目的に沿って提供する体制が整備され,医療アクセスとアウトカムとの関連が小地域レベルで検討されている。日本では同様の利活用が十分に実施されておらず,利用申請のハードルが高い。全国がん登録の目的である調査研究の推進とがん対策の一層の充実のために,他のデータとのリンケージ,オンサイト利用など,全国がん登録を有効かつ安全に活用できる体制を構築していく必要がある。
- 著者
- 明石 光史 田中 守 田中 宏暁 檜垣 靖樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.745-754, 2014 (Released:2014-12-20)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 2
The purposes of this study were (1) to examine the effect of body contact (BC) on running power, and (2) to evaluate the relationship between physical ability and BC during measurement of both aerobic exercise and intermittent anaerobic running power in 14 male university handball players, all of whom were court players. Significantly shorter running distances were achieved in the yo-yo intermittent endurance test [yo-yo IE] with full BC than without BC, and there was a significant relationship between the final distance run and the degree of BC. Intermittent exercise was measured by the intermittent shuttle sprint test (ISST) that involved eight 20-m shuttle sprints with a 20-s rest period after each sprint. The subjects exhibited a significantly lower retention rate during the 8th repetition of the ISST with BC than during the eighth repetition of the ISST without BC, but there was no significant correlation between the mean retention rates during the 2 tests. A positive correlation between retention rates during the ISST BC and muscle strength and body weight was evident from the first 2—3 sets of the ISST with BC, and a negative correlation was evident between the retention rates during the ISST BC and the yo-yo IE from the first 5 sets of the ISST with BC. These results indicate that intermittent anaerobic running power is important for high aerobic ability. However, for intermittent exercise that includes BC, higher body weight and muscle strength are necessary to prevent any decrease in running power.
1 0 0 0 OA EATがスギ花粉症咽頭症状に有効であった一例
- 著者
- 西 憲祐 西 隆四郎 木村 翔一 西 総一郎 田中 宏明 山野 貴史
- 出版者
- 日本口腔・咽頭科学会
- 雑誌
- 口腔・咽頭科 (ISSN:09175105)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.37-42, 2022 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 18
アレルギー性鼻炎は日本において最も頻度が高いアレルギー性疾患の一つである.特にスギ花粉症患者は人口の約40%が罹患しており,重要な治療標的である.アレルギー性鼻炎はしばしば上咽頭のかゆみなどの咽頭症状を誘発する.慢性上咽頭炎に対して上咽頭擦過療法(Epipharyngeal Abrasive Therapy:EAT)が有効であるという報告が多数されており,後鼻漏,咽頭違和感,慢性咳嗽,頭痛といった典型的な症状以外にもアレルギー性疾患に有効であると報告されている.しかしながらEATがアレルギー性疾患に有効とされる機序に関しては不明な点が残されている.今回我々はEATがスギ花粉による上咽頭アレルギーに対して有効であった一例を報告するとともに,病理組織学的所見からその機序に関して考察した.症例は34歳男性でスギ花粉飛散時期に上咽頭の掻痒感を自覚していた.本患者に継続的にEATを施行することで,スギ花粉による上咽頭アレルギーを抑制する事が出来た.更に,この効果発現機序に関しては,EATによる繊毛上皮の扁平上皮化生と粘膜上皮直下の線維性間質の出現によるものと考えられた.