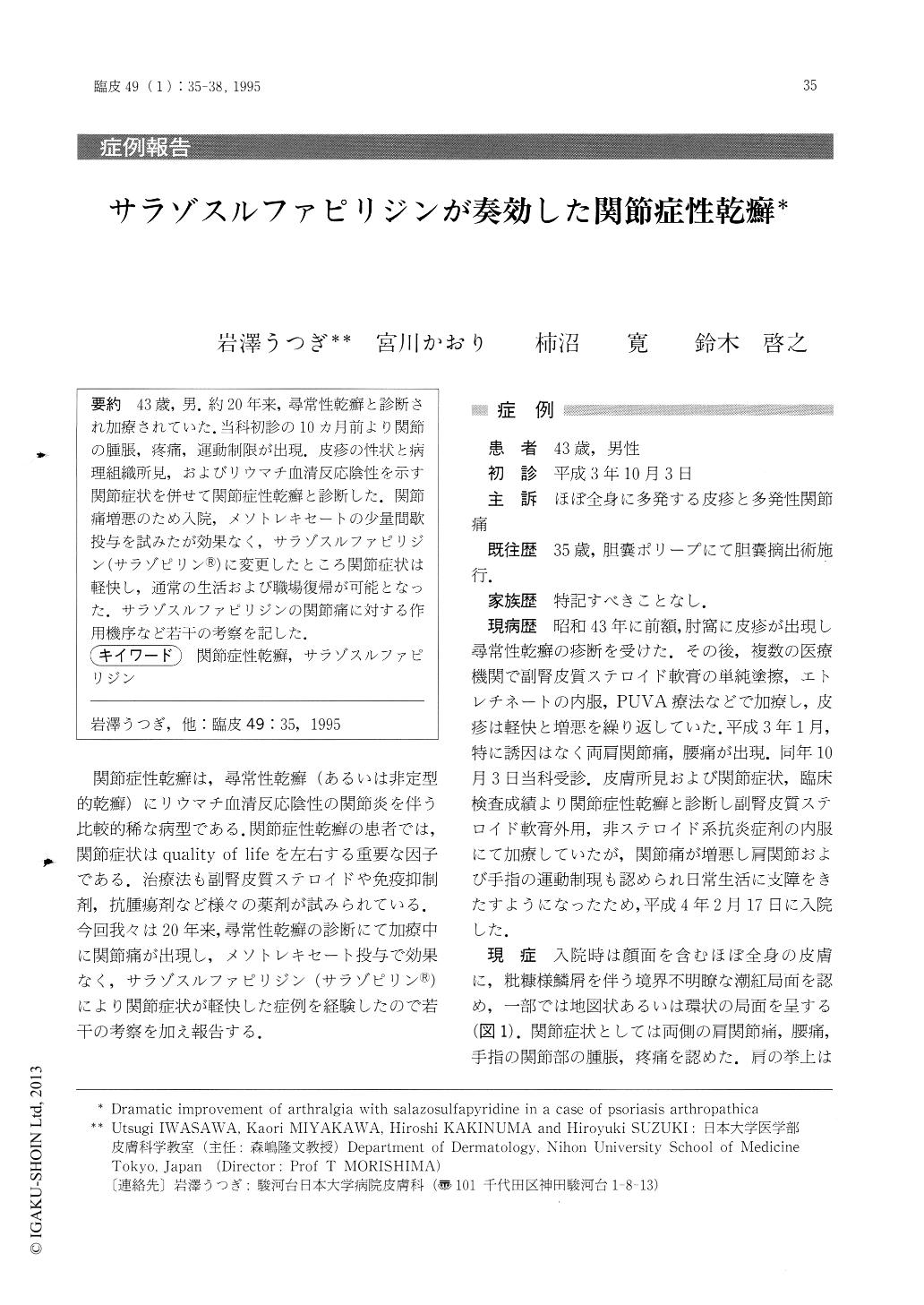1 0 0 0 暴力被害女性のサバイバル物語として読む「原阿佐緒」
- 著者
- 鈴木 道子
- 出版者
- 日本フェミニストカウンセリング学会
- 雑誌
- フェミニストカウンセリング研究
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.26-43, 2003
1 0 0 0 OA ZDDを用いたグラフ列挙索引化における頂点インデックスの追加
- 著者
- 鈴木 浩史1 湊 真一1 Suzuki 1 Hirofumi Shin-ichi Minato
- 雑誌
- SIG-FPAI = SIG-FPAI
- 巻号頁・発行日
- vol.B5, no.01, pp.41-46, 2016-08-01
- 著者
- 中村 雅俊 鈴木 亮
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経マネー (ISSN:09119361)
- 巻号頁・発行日
- no.336, pp.90-92, 2010-11
ええ、『ふれあい』でレコードデビューしてから37年目に入りました。これまで毎年、やらなかった年はありません。当初、ここまで続くとは、私もスタッフも誰も思いませんでした。──根強いファンを獲得できた理由はなんでしょうか。 当時、青春をテーマにしたドラマの役者さんはみんな歌を出したんです。
- 著者
- 本間 憲治 八反田 葉月 篠原 悠人 鈴木 康太 杉原 俊一
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2016, 2017
<p>【はじめに,目的】</p><p></p><p>近年,脳血管疾患(以下,CVA)死亡数は減少傾向にあるが,要介護状態となる主原因疾患とされている。一方,心不全(以下,HF)は高齢化に伴い患者数は増加傾向にあり,今後はCVAとHFなど重複障害例の増加が予想される。</p><p></p><p>当院は脳神経外科に加えて循環器科,心臓血管外科を併設した141床の一般病院で,回復期病棟も併設しており,急性期から在宅まで一貫したリハビリテーションを提供している。当院の地域は脳卒中地域連携パスによる医療連携が積極的に行われており,生活期との連携については,退院時の申し送りを中心に行っている。</p><p></p><p>そこで今回,CVAとHFの重複障害例の申し送り内容に特徴がないか後方視的に検討する事を目的とした。</p><p></p><p></p><p>【方法】</p><p></p><p>対象はH26年9月からH28年9月に当院回復期病棟から自宅退院したCVA症例中,退院前に申し送りを行った者110例とし,既往にHF及び入院中にHFを併発したHFあり群29例とHFなし群81例の2群に分類し,申し送り書の内容について比較検討した。</p><p></p><p>分析方法は退院時申し送り書より抽出した年齢,退院時の合計FIM,運動FIM,認知FIMの2群間比較には対応のないt検定,性別,高次脳機能障害,及び認知機能の低下の有無の2群間比較にはχ二乗検定を用い有意水準を5%未満とした。また,退院時申し送り書の項目より,「予想される問題点」と「依頼事項」の記述内容を,計量テキスト分析ソフト「KH-Coder」を使用し,2群の上記各項目に対し共起ネットワーク分析(サブグラフ検出・媒介)を用いjaccard係数を0.2以上とした。共起ネットワーク抽出語数,線の数,グループ数を抽出した。なお,共起ネットワークとは,テキスト中の単語間の出現パターンが類似したものを線で結んだ図で,結びつきの強さをjaccard係数で表している。</p><p></p><p></p><p>【結果】</p><p></p><p>年齢,性別,退院時の合計FIM,運動FIM,認知FIM,高次脳機能障害の有無,認知面低下の有無の全てにおいて,両群で有意差を認めなかった。「予想される問題点」について,共起ネットワーク抽出語数はHFあり32,HFなし98,線の数はHFあり46,HFなし77,グループ数はHFあり8,HFなし11で,HFありで全てにおいて少なかった。「依頼事項」について,共起ネットワーク抽出語数はHFあり41,HFなし126,線の数はHFあり73,HFなし117,グループ数はHFあり12,HFなし11で,HFありでグループ数を除き少なかった。</p><p></p><p></p><p>【結論】</p><p></p><p>「予想される問題点」「依頼事項」について,共起ネットワーク抽出語数,線の数はそれぞれHFありで少なく,障害が重複し,問題点の細分化が難しく,抽象的で個別性の低い内容となる傾向が示唆された。</p><p></p><p>HFありでは「予想される問題点」に比べ「依頼事項」のグループ数は増加しており,HFありの抽象的で個別性の低い内容から具体的な依頼事項を絞り込むことが困難なため,依頼事項が散在化した可能性が示唆された。</p><p></p><p>今後の展望として,重複障害例の申し送り時には身体活動の増加や予防を目的とした個別性の高い内容を伝え,生活期との連携を行いたいと考える。</p>
- 著者
- 今泉 有美子 杉原 俊一 鈴木 康太 市場 友梨 八反田 葉月 本間 憲治 篠原 悠人
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, 2014
【はじめに,目的】脳卒中片麻痺者において,一時的な移動手段として車いすを利用することは多い。その際,非麻痺側上肢ではハンドリムを回し,下肢では床面を蹴り駆動するため,非対称な動作を助長している場面を多く経験する。片麻痺者の車いす座位について,先行研究では殿部荷重パターンの報告は散見されるが,車いす駆動中の座圧の変化について言及している報告は少ない。本研究の目的は,健常成人にて片麻痺患者を模した環境を設定して片手片脚駆動を実施し,前額面上で座位姿勢の影響を明らかにすることである。【方法】対象は健常成人6名(性別:男性3名・女性3名,年齢:25.7±0.8歳)とした。計測にはモジュラー車いす(松下電工株式会社製)を使用し,前座高は下腿長+2cm,後座高・フットサポートの長さは下腿長,アームサポートの高さは肘頭高+2cmに調整した。課題は右上下肢での片手片脚駆動による直進走行とし,座クッションを外したシートの上にベニヤ板を水平に設置(以下,水平条件),ベニヤ板を右側が高くなるよう5°傾斜させて設置(以下,傾斜条件),座面の中心がたわむように調整した張り調整シートのみ(以下,たわみ条件)の3条件で,10秒間の安静座位を保持した後,任意のスピードで5メートル駆動するよう指示した。計測項目は,静止状態からの座圧中心の変化と,体幹の前額面上での傾斜角度とした。座圧中心には,3条件の座面にSRソフトビジョン数値版(東海ゴム工業製)を設置して測定した。体幹の傾斜角度は,胸骨部の高さで巻きつけた加速度センサーと,デジタルビデオカメラで撮影した正面画像から,両肩峰を結んだ線と水平面のなす角をImage Jを使用して測定した値を使用した。分析方法としては,右手でハンドリムを掴んだ瞬間からハンドリムから手を放した瞬間までを1駆動周期とし,1駆動周期中と安静状態の座圧中心の差の平均値と,1駆動周期の駆動開始時と駆動終了時の体幹傾斜角度の差(以下,体幹傾斜角度の変化)の平均値を各条件で比較した。【倫理的配慮,説明と同意】本研究の実施にあたり,被験者に研究の趣旨と測定の方法について説明を行い,協力の同意を得た後に測定を行った。【結果】座圧中心の安静状態と1駆動周期中の差の平均は,水平条件で右方向へ6.9±2.2mm,傾斜条件で右方向へ9.6±2.2mm,たわみ条件で右方向へ3.5±1.0mmであり,傾斜条件で駆動側への偏倚が大きく,たわみ条件では小さかった。加速度センサーで測定した体幹傾斜角度の変化の平均は,水平条件で右方向へ0.5±2.8°,傾斜条件で右方向へ1.1±1.0°,たわみ条件で左方向へ1.1±1.2°であり,傾斜条件で駆動側への傾斜が大きく,たわみ条件では駆動側と反対側への傾斜がみられた。画像から計測した体幹傾斜角度の変化の平均は,水平条件で右へ10.1±0.7°,傾斜条件で右へ11.7±1.0°,たわみ条件で右へ8.0±1.5°であり,傾斜条件で駆動側への傾斜が大きく,たわみ条件では小さかった。【考察】水平条件と傾斜条件では,駆動中の座圧中心の駆動側への偏倚,体幹の駆動側への傾斜を認め,いずれも傾斜条件で大きかった。健常者であっても,片手片脚駆動では体幹の前額面上での非対称性が生じると考えられた。また,傾斜条件は片麻痺者に見られる麻痺側股関節周囲筋の筋緊張低下や股関節外旋などによる骨盤の麻痺側への傾斜を模擬的に設定していることから,片麻痺者の片手片脚駆動では,骨盤の傾斜角度により体幹の非対称性が増強することが示唆された。今回たわみ条件では,座圧中心の偏倚と体幹傾斜角度ともに他の2条件に比べ小さかった。座面がたわんでいる環境では,駆動方向の重心移動が困難であることが考えられた。【理学療法学研究としての意義】脳卒中片麻痺者では,将来的に歩行を獲得する場合においても一時的に車いすを移動手段として利用する症例は多い。歩行獲得に向けて理学療法を進めていく上でも,車いす駆動中の身体の非対称性を軽減していくことは重要であると考えられる。車いすの片手片脚駆動での体幹の非対称性を明らかにすることで,車いす駆動の指導方法を検討する一助となると考えられる。
- 著者
- 杉原 俊一 鈴木 康太 八反田 葉月 松村 亮 三浦 いずみ 田中 敏明 加藤 士雄 棚橋 嘉美 宮坂 智哉
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2016, 2017
<p>【はじめに】今後の介護予防・日常生活支援総合事業では,元気な高齢者と二次予防事業対象者を分け隔てることなく,高齢者のニーズに応じた介護予防の取り組みが求められ,リハビリテーション専門職(以下リハ職)による互助活動を支援する仕組み作りが重要となる。そこで本研究では,二次予防事業終了者の自主体操グループにアセスメント訪問を実施し,今後の互助活動のリハ専門職の関与について検討することを目的とした。</p><p></p><p></p><p>【方法】対象は,T区地域包括支援センターが後方支援している自主体操グループ参加者のうち(10グループ),リハ職によるアセスメントを実施した4グループ28名(平均年齢76.4±6.1歳,69~86歳)とした。調査項目は生活空間の評価としてLife space assessment(LSA),日本語版Montreal Cognitive Assessment(MoCA-J,cut-off値26点),ハンドヘルドダイナモメーターによる等尺性膝伸展筋力の体重比(下肢筋力),Timed Up And Go Test(TUG),開眼片脚立位時間(片脚立位),CS-30とした。更に携帯型加速度計(AYUMIEYE,GE社製)により,垂直・側方・前後方向の体幹部の加速度の二条平均平方根(root mean square,以下RMS)を算出し,RMSを歩行速度の二乗値で除して正規化した後,TUG,片脚立位,CS-30との各指標の関連性についてピアソンの相関係数を求め,危険率5%未満を有意とした。</p><p></p><p></p><p>【結果】LSAは70.5±26.7点,MoCA-Jは20.7±4.4点,下肢筋力は31.9±12.4%BW,TUGは7.1±1.6秒,片脚立位は17.8±9.6秒,CS-30は16.5±4.2回で,MoCA-Jでは参加者の86%が,下肢筋力及び片脚立位では50%以上が転倒リスクのcut-off値以下であった。加速度との関連性は前後方向のRMSで相関を認めず,上下及び左右方向のRMSでTUG,CS-30,片脚立位時間で有意な相関を示した。</p><p></p><p></p><p>【考察】対象者の多くがMoCA-JによるMCIのスクリーニングでcut-off値以下を示し,生活機能において多面的な低下が危惧されることから,MCIの早期発見に向けたリハ職による関与の必要性が示唆された。LSAの結果より町内レベルの外出を行う対象者を含む場合,TUGやCS-30のみでは,転倒スクリーニングは困難な可能性が考えられた。一方,TUG等の各評価指標と歩行加速度については関連性を認めており,多様な参加者のアセスメントには,鋭敏に転倒リスクを捉えうる可能性がある加速度歩行指標の組み合わせが必要と考えられる。</p><p></p><p></p><p>【理学療法の意義】リハ専門職による互助活動の包括的な訪問アセスメントによる介護予防データの蓄積により,各地域における介護予防のスクリーニング法の確立に繋がる可能性がある。</p>
1 0 0 0 OA 中型猛禽類の営巣誘導 ―太枝がない若齢針葉樹における試み―
- 著者
- 工藤 琢磨 鈴木 貴志
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 日本森林学会誌 (ISSN:13498509)
- 巻号頁・発行日
- vol.97, no.5, pp.225-231, 2015-10-01 (Released:2015-12-23)
- 参考文献数
- 41
猛禽類の巣の土台となりそうな太枝がない若齢針葉樹に,人工巣を設置することで中型猛禽類の営巣を誘導できるか,試みた。その結果,オオタカとトビ,それぞれ一つがいが営巣を行った。オオタカは2羽の巣立ち雛を育てることに成功した。トビは育雛期になって巣を放棄したが,原因は山菜採りによる撹乱の可能性が疑われた。オオタカは前年に自ら構築した自然巣が近くにあったにもかかわらず,人工巣を利用した。トビが利用した人工巣は,もともとトビを含む中型猛禽類の営巣がみられなかった地域に設置されたものだった。これらの結果は,若齢や間伐遅れのために太枝が発達していない針葉樹でも,人工的に中型猛禽類の営巣を誘導することが可能であることを示した。この技術を利用すれば,営巣適木がない森林を営巣適地に変えることが可能で,結果として生息地域拡大も期待できる。
1 0 0 0 OA 耳型採取時の事故から学んだこと
- 著者
- 寺崎 雅子 小河原 剛 鈴木 貴裕
- 出版者
- 一般社団法人 日本聴覚医学会
- 雑誌
- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.5, pp.369-370, 2007-09-05 (Released:2010-08-05)
1 0 0 0 サラゾスルファピリジンが奏効した関節症性乾癬
43歳,男.約20年来,尋常性乾癬と診断され加療されていた.当科初診の10カ月前より関節の腫脹,疼痛,運動制限が出現.皮疹の性状と病理組織所見,およびリウマチ血清反応陰性を示す関節症状を併せて関節症性乾癬と診断した.関節痛増悪のため入院,メソトレキセートの少量間歇投与を試みたが効果なく,サラゾスルファピリジン(サラゾピリン®)に変更したところ関節症状は軽快し,通常の生活および職場復帰が可能となった.サラゾスルファピリジンの関節痛に対する作用機序など若干の考察を記した.
1 0 0 0 トラック木質バンドラの機能と可能性
- 著者
- 仁多見 俊夫 鈴木 欣一
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 日本森林学会大会発表データベース
- 巻号頁・発行日
- vol.126, 2015
木質バイオマスの収集効率を向上させることを目的として、圧縮成形機能をもつ処理機構をトラックに搭載した。圧縮成形機能を持つバンドラ―ユニットは重量6t、長さ5.5mで、林地残材などを受け入れるホッパー部、圧縮成形切断する主要部、圧縮成形されたバンドルを受けて側方へ流れ落とす受け部からなる。このユニットをトラックの後部車台へ、旋回可能に装架し、車両キャビン後方に装備した油圧グラップルクレーンでホッパー部へ材料を供給する。車両総重量は、18tである。林地残材は直径約70cm、長さ約4m、重量約400kgのバンドルに成形排出される。バンドル実証作業を行い、1本のバンドルを作成するための処理時間は平均約5分30秒、処理コストは約2千円/tであった。既往の同様な機構の作業では1バンドル処理時間は約2分であって、コストは約600円/tとなることが期待される。この処理量に対応する施業面積は間伐約200ha、主伐約70haとなり、トラックの機動性によって1台の単年の事業量として無理なく処理可能である。今後、さらに操作手順、ユニット機構、バランスの検討が必要である。
1 0 0 0 OA オフロキサシン耳用液の有用性と耳浴時間に関する臨床的研究
- 著者
- 原田 勇彦 加我 君孝 水野 正浩 奥野 妙子 飯沼 寿孝 堀口 利之 船井 洋光 井上 憲文 安倍 治彦 大西 信治郎 牛嶋 達次郎 宮川 晃一 伊藤 修 佐久間 信行 北原 伸郎 土田 みね子 飯塚 啓介 小林 武夫 杉本 正弘 佐藤 恒正 岩村 忍 矢野 純 山岨 達也 広田 佳治 仙波 哲雄 横小路 雅文 鈴木 光也
- 出版者
- 耳鼻咽喉科展望会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科展望 (ISSN:03869687)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.3, pp.380-387, 1994-06-15 (Released:2011-08-10)
- 参考文献数
- 15
鼓膜炎, 慢性化膿性中耳炎, 真珠腫性中耳炎の感染時, 中耳術後の再感染症例を対象として, オフロキサシン (OFLX) 耳用液の有用性と耳浴時間に関する臨床的研究を行った。研究参加施設を無作為に2群に分け, 1群では1回6-10滴, 1日2回, 7日間以上の点耳を行い, 毎回点耳後約10分間の耳浴を行うよう, II群では同様の点耳後に2-3分間の耳浴を行うよう患者に指示した。総投与症例は258例で, 全体では83.3%の改善率, 86.7%の菌消失率 (143例中) が得られた。副作用は1例もなく, 全体としては82.9%の有用率であった。統計学的検定により1群とII群の比較を行ったところ, すべての項目で両群間に有意の差はみられなかった。以上の結果から, OFLX耳用液は鼓膜, 中耳の炎症性疾患に対して極めて有用かつ安全なものであり, その点耳後の耳浴時間は2-3分でも十分な効果が得られるものと考えられる。
- 著者
- 鈴木 博人
- 出版者
- 法学新報編集委員会
- 雑誌
- 法学新報 (ISSN:00096296)
- 巻号頁・発行日
- vol.121, no.7, pp.163-212, 2014-12
日本法でもドイツ法でも法的な母子関係は、分娩によって発生する。父子関係と異なり、母子関係は分娩時に確定する。しかし、望まない妊娠等の事情により、母子関係の存在あるいは妊娠の事実が知られると困る場合、子が出生直後に遺棄されたり、時には殺害されることがある。この事情は、ドイツでも日本でも同じである。このような事態に対応するとして、ドイツでは一九九一年にベビークラッペが設置され、また匿名出産が事実上行われている。少数であるが、子の匿名での引受けを行う事例も存在する。ドイツでは二〇〇九年に倫理評議会が、ベビークラッペは廃止すべきであり、それに代わり一定の要件の下で限定的に母の匿名性を認めるべきという提言がなされた。それを受けた実態調査を踏まえて、妊娠葛藤法のなかに秘密出産制度が導入されて、二〇一四年五月一日から施行されるに至った。本稿では、第一に、秘密出産制度が制定されるに至った背景と新しい制度の内容を紹介、分析する。第二に、秘密出産制度で母の利益と子の利益が比較考量されて、望まない妊娠に典型的にあらわれる母と子それぞれの利益対立が、どのように調整されたのかを検証する。第三に、社会問題としては類似の問題を抱える日本で、仮に母の匿名性を例外的にであれ認めることによって、母子双方の福祉・権利の調整を図るとしたら、どのような問題を乗り越えなければならないかを指摘する。
1 0 0 0 OA 野川先土器時代遺跡の研究
- 著者
- 小林 達雄 小田 静夫 羽鳥 謙三 鈴木 正男
- 出版者
- Japan Association for Quaternary Research
- 雑誌
- 第四紀研究 (ISSN:04182642)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.4, pp.231-252, 1971-12-25 (Released:2009-08-21)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 1 3
A. The Nogawa Site and its Stone Culture (KOBAYASHI and ODA)1. The Nogawa site is located in Kamiishihara, Chofu City, Tokyo. It sits on a low bluff on the Tachikawa Terrace facing across a stream toward the higher Musashino Terrace marked by the Kokubunji Cliff Line (fig. 1).2. The site was first excavated in 1964, and exploratory excavations were carried on for the next several years (Kidder et al.: 1970). Then a project to widen the stream threatened to destroy the site, and in response the Nogawa Site Excavation Group was formed to excavate the endangered part of the site. Excavations were carried out from June to the end of August 1970 (Nogawa Iseki Chosa Kai: 1970, 1971a, 1971b, 1971c).3. Geologically the site has thirteen strata (fig. 3). The base stratum XIII is gravel. Over this are nine layers of loam, strata IV to XII, the so-called Tachikawa loam. Four of these strata, strata IVb, V, VII and IX, are black bands of fossil soils. Stratum III is the soft loam, stratum II is a brown humus, and stratum I is a black humus.4. Culturally there are eleven layers, ten Preceramic Period layers (numbered III, IV1, IV2, IV3a, IV3b, IV4, V, VI, VII and VIII to correspond to the geological strata in which they were found) and one mixed Jomon Period layer in stratum II. More than 10, 000 artifacts were recovered from the Preceramic Period layers. Over 2, 000 are tools or flakes. Another more than 7, 000 artifacts are fire-reddened gravel usually found in heaps. The clarity of stratification, the number of layers, and the quantity of artifacts make Nogawa the best stratified, Preceramic Period site in Japan.5. The Nogawa data, when correlated with data from other sites in Kanto (fig. 7-10) (in particular, the Heidaizaka Site and ICU Location 15 in Koganei City and the Tsukimino Site Group on the Sagami Terrace in Kanagawa Prefecture), allows definition of four broadly defined phases for the Preceramic Period. The earliest phase, Nogawa layers VIII to V (Heidaizaka layers X to V), has mostly flake tools plus some heavy-duty tools made from pebbles. Phase II, Nogawa layers IV4 to IV1, is characterized by backed blades. Temporally related changes in the form of these backed blade tools are apparent. The early assemblages of the phase are marked by lightly worked blades of knife-like form. Later assemblages see changes to smaller tools of more geometric form and the appearance of small, bifacially worked points. (Phase III of the South Kanto Preceramic Period is distinguished by the presence of microblades and the cores from which they were obtained. However, this phase is not represented at the Nogawa site). The latest Preceramic Period phase, phase IV, Nogawa layer III, consists mainly in large, biface points and pebble tools.6. The heaps of fire-reddened gravel are found mostly in Nogawa layers IV1 to IV4, i. e. Preceramic Period phase II. X-ray diffraction analysis done by M. Suzuki of Tokyo University shows the stones to have been heated to more than 600°C. The meaning of these heaps is unclear. It is not known whether they were used as found-single layers of gravel spread in near circular patterns one to two meters in diameter-or whether they were simply disposed of at a location in the site some distance from where they were used. However, many of the stones do have a kind of tar-like substance on them, and one is probably justified in thinking the stones were used directly in some manner for cooking. Also, pounding stones, grinding stones and anvil-like stones are frequently found in close proximity to the heaps.
- 著者
- 鹿江 宏明 鈴木 盛久
- 出版者
- 比治山大学・比治山大学短期大学部
- 雑誌
- 比治山大学・比治山大学短期大学部教職課程研究 Review of the research on teachers training (ISSN:21891745)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.173-180, 2015-03
1 0 0 0 進化学習による二輪車両型ロボットの自律走行の獲得
- 著者
- 菊光 美樹男 渡辺 美知子 ラワンカル アビジート 鈴木 育男 岩館 健司 古川 正志
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会学術講演会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2019, pp.94-95, 2019
<p>近年,自動車や自転車など従来の移動手段に加えて平地や坂道などを一人で移動する手段が求められている.この移動手段としては,セグウェイのように重心の移動を利用して多様な環境下でも対応できる方法がある.本研究ではセグウェイのような平行二輪型の立ち乗り車を三次元物理空間にモデリングし,障害物を回避しながら目的地まで自律的に走行する行動獲得を目的とする.自律行動の獲得には進化学習を用いる.</p>
- 著者
- 今井 明 鈴木 ひろみ 渡辺 晃紀 梅山 典子 塚田 三夫 中村 勤 松崎 圭一 加藤 開一郎 冨保 和宏
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳卒中学会
- 雑誌
- 脳卒中 (ISSN:09120726)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.6, pp.572-578, 2010-11-26 (Released:2010-12-03)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 2 2
脳卒中の自然経過を検討する目的で,生命予後と死因について調査し,AHAによる報告と比較した.対象は1998年4月から1999年3月に脳卒中を発症し,栃木県内で登録された5,081人である.発症から5年9カ月までの死亡の有無と,死因簡単分類で死因を調査した.生存率はKaplan-Meier法で算出した.脳卒中全体の5年生存率は62.3%であり,病型別の5年生存率は,くも膜下出血54.9%,脳出血57.9%,脳梗塞62.8%であった.死因の観察では,すべての病型で1位を脳卒中,2位を循環器系の疾患が占め,3位はくも膜下出血と脳出血では悪性新生物,脳梗塞では呼吸器系の疾患が占めた.くも膜下出血と脳出血では原疾患による急性期死亡が多く,75歳以上の脳梗塞では肺炎による死亡が多かった.AHAの報告によると,脳卒中の5年以内の致死率は男性47%,女性51%であり,栃木県の致死率は男性38.5%,女性36.7%とアメリカの報告より低かった.脳卒中の生命予後の改善には,急性期治療の充実と慢性期脳梗塞の肺炎に対する対策が重要と考える.
1 0 0 0 IR 24 「澁澤民間学」の生成 -澁澤敬三と奥三河-
- 著者
- 鈴木 正崇 Suzuki Masataka
- 出版者
- 神奈川大学 国際常民文化研究機構
- 雑誌
- 神奈川大学 国際常民文化研究機構 年報 (ISSN:21853339)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.170-182, 2010-10-30
1 0 0 0 第59回粘土科学討論会(山口大会)報告
- 著者
- 川俣 純 沢井 長雄 谷 誠治 鈴木 康孝 富永 亮
- 出版者
- 一般社団法人 日本粘土学会
- 雑誌
- 粘土科学 (ISSN:04706455)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.74-79, 2016
- 著者
- 鈴木 拓児
- 出版者
- 自治医科大学
- 雑誌
- 国際共同研究加速基金(帰国発展研究)
- 巻号頁・発行日
- 2017
呼吸に必須な肺サーファクタントは、肺II型上皮細胞と肺胞マクロファージによるその産生と分解のバランスによって恒常性が維持されている。肺胞蛋白症とは肺サーファクタント由来物質が肺の末梢気腔内に異常に貯留し呼吸不全に至る疾患群であり、その原因から自己免疫性、遺伝性、続発性などに分類され、その大部分は肺胞マクロファージの機能異常が原因である。申請者らはこれまで、ヒト遺伝性肺胞蛋白症の原因探索、診断、病態解明および新規治療法開発の研究に従事してきた。遺伝性肺胞蛋白症はGM-CSF受容体遺伝子(CSF2RAあるいはCSF2RB)変異によって生じるが、いまだ有効な疾患特異的な治療法はない。そこでマウスモデル(Csf2rbノックアウトマウス)を用いて、肺マクロファージ移植法という細胞治療および遺伝子治療を提唱してきた(Suzuki. et al. Nature. 2014)。同治療法は骨髄移植の際に必要な放射線照射や化学療法などを行わずに、マクロファージを一回、直接肺へ移植する方法であり、長期間にわたる移植細胞の生着と疾患の改善および安全性が確認されており、有効な治療法と考えられる。しかしながら、ヒトで患者数の多い(約9割を占める)CSF2RA遺伝子変異による疾患に相当するCsf2raノックアウトマウスはこれまで存在しなかったために、病態の解析や治療法の検討といった基礎的な研究が困難であった。そこで今回新たにCsf2raノックアウトマウスを作成し、同マウスの病態解析を行っている。さらに同マウスを用いて上記の新規治療法の開発研究をおこなっている。