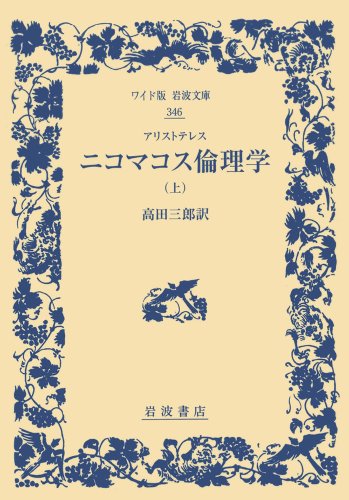1 0 0 0 OA 国防体制の学校経営 : 臣民錬成の教育
- 著者
- 高田師範学校附属国民学校 編
- 出版者
- 教育実際社
- 巻号頁・発行日
- 1941
- 著者
- 箕田 充志 淺田 純作 高田 英治
- 出版者
- 公益社団法人日本工学教育協会
- 雑誌
- 工学教育研究講演会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.63, pp.82-83, 2015-08-07
1 0 0 0 地方圏内における人口の社会移動分析
- 著者
- 近藤 光男 青山 吉隆 高田 礼栄
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木計画学研究・論文集 (ISSN:09134034)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.171-178, 1995
- 被引用文献数
- 1
本研究では、地方圏内における人口の社会移動を対象とし、農山村対都市部の構図の中で人口移動は地域の効用格差によって生じるとの仮定によってモデルを作成し、それを用いて移動のメカニズムを解明した。モデル分析では、わが国の地方圏の1つである徳島県を対象とし、県内の50市町村を分析単位とした。その結果、1人当たり所得、生活環境施設の利用機会、故郷や都市までの時間、地価が人口移動の影響要因になっていることが明らかになった。また、地域内の道路整備による時間短縮は都市部に比べ、農山村の効用をより高めることがわかった。しかしながら、農山村と都市部の間には大きな効用の差が依然として存在しており、農山村からの人口流出問題の解決は短期的には厳しい状況にあると思われる。
1 0 0 0 ニコマコス倫理学
- 著者
- アリストテレス [著] 高田三郎訳
- 出版者
- 岩波書店
- 巻号頁・発行日
- 2012
1 0 0 0 対人ストレスの経験時において,コーピングとサポートのどちらが先か
- 著者
- 髙本 真寛 高田 治樹
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.6, pp.596-602, 2016
- 被引用文献数
- 2
This study used structural equation modeling to investigate directional relationships between coping with interpersonal stress and received support. One hundred and seventy-seven undergraduates who had experienced interpersonal stress during the past month answered questions about coping with interpersonal stress and received support. Structural equation modeling based on third-order moment structures was used to examine the directionality of the relationship between these two variables. The results revealed interactive associations between distancing and emotional support. Received support affected coping with interpersonal stress in terms of active coping, planning and monitoring, and positive reappraisal. These results suggest that received support functions as a coping resource.
- 著者
- 石田 勝英 塩入 有子 石坂 泰三 岩崎 博道 藤田 博己 高田 伸弘
- 出版者
- 日本皮膚科学会大阪地方会・日本皮膚科学会京滋地方会
- 雑誌
- 皮膚の科学 (ISSN:13471813)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.55-61, 2004 (Released:2011-07-13)
- 参考文献数
- 12
症例は88歳,女性。約2日前に自宅近くの草むらに入り,全身を多数のマダニに咬着され,平成15年5月19日に当科を受診した。当科で229匹の虫体を摘除したが,すでに脱落した虫体も含めるとさらに多くの寄生を受けていたものと思われた。虫体はタカサゴキララマダニ幼虫と同定された。塩酸ミノサイクリンを予防投与したが虫体摘除2日後に発熱・全身関節痛・両腋窩リンパ節腫脹などの全身症状が出現した。塩酸ミノサイクリンは効果がなく中止し,多種の抗生剤を用いてようやく症状は軽快した。日本系および欧州系紅斑熱やライム病など,およそマダニが媒介し得るだけの各種感染症の血清抗体検査では陰性だった。全身症状の明らかな原因は特定できなかった。
- 著者
- 石川 正夫 武井 典子 石井 孝典 高田 康二 濵田 三作男
- 出版者
- Japanese Society of Gerodontology
- 雑誌
- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.37-45, 2015
超高齢社会が進展するなか,介護を必要としないことおよび認知症の予防が急務な課題となっている。そこで,われわれは高齢者の介護予防を目指した口腔機能の評価と管理システムを開発し,ケアハウス入所者において口腔機能の向上に役立つことを確認した。 今回は,本システムが認知機能の低下抑制に役立つか否かを明らかにする目的で,グループホームにて調査を行った。対象者は鹿児島県のグループホーム入所者(「GH-A」)および神奈川県のグループホーム入所者(「GH-B」)である。初回,6カ月後,1年後の検査に参加した GH-A12名および GH-B24名を対象に,口腔機能および認知機能の評価(MMSE)を行った。初回の口腔機能検査(①口腔周囲筋,②咀嚼機能, ③嚥下機能,④口腔清潔度)結果に基づいて,個々人に対応した口腔機能向上プログラムを本人および介護スタッフに提案・実施を依頼した。実施状況は,GH-Aは毎日,GH-Bは半分程度であった。 その結果,②咀嚼機能が 1 年後にGH-Aで改善した。③嚥下機能の指標であるRSST,オーラルディアドコキネシス「pa音」の回数が6カ月後に GH-Aで有意に増加した。さらに,MMSE得点は,GH-Bで1年後に有意に低下したが,GH-Aでは変化はみられなかった。以上の結果より,プログラム実施状況の影響はあるものの,本システムの介入により口腔機能の維持・向上を通して認知機能の低下抑制に貢献できる可能性が示唆された。
1 0 0 0 OA エボラウイルス研究の現状と展望
- 著者
- 高田 礼人
- 巻号頁・発行日
- 2015-07-18
- 著者
- 窪田 正彦 新井 清 頼光 彰子 島岡 真佐子 星野 響 林 一之 伊田 泰康 南 典昭 山本 博文 田中 恵一 高田 三千人 西原 正勝 藤谷 幸治 神田 博史
- 出版者
- 公益社団法人日本薬学会
- 雑誌
- 藥學雜誌 (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.113, no.11, pp.810-817, 1993-11-25
The cultivation of Papaver bracteatum, having thebaine as a major alkaloid, needs permission by the law of the narcotic regulation in Japan. Therefore, the flowergrowing of P. bracteatum as garden plants is prohibited by law. Chemical, morphological and cytological analyses of gardening 18 plants of the section Oxytona of the genus Papaver collected in western Hiroshima prefecture were carried out as a preliminary study. On inquiry, thebaine was identified as an only alkaloid from one of the gardening plants. The amounts of thebaine contained in this sample was 0.68%. Petals of this plant are scarlet with black spots at their bases which are surrounded by bracts. These results indicated that one of the investigated plants was identified to be P. bracteatum.
1 0 0 0 OA 一過性の聴力障害後に発症した心因性視覚障害の1例
- 著者
- 高田 有希子 奥出 祥代 林 孝彰 月花 環 片桐 聡 北川 貴明 久保 朗子 小島 博己 常岡 寛
- 出版者
- 公益社団法人 日本視能訓練士協会
- 雑誌
- 日本視能訓練士協会誌 (ISSN:03875172)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.153-159, 2014 (Released:2015-03-19)
- 参考文献数
- 25
【目的】心因性視覚障害で、色覚異常を主訴として眼科受診するケースは少ない。今回、一過性の聴力障害後に、色覚異常を訴えた心因性視覚障害の1例を経験したので報告する。【症例】15歳女性。2013年1月頃より、一過性の左聴力障害を認めていたが、経過観察していた。同年2月右眼の色覚異常を自覚し、近医眼科を受診。同年3月精査目的にて当科受診となった。矯正視力は右眼1.5、左眼1.2であった。左右眼ともに前眼部、中間透光体、眼底に異常所見は認めず、Goldmann動的量的視野は正常で、網膜電図の潜時・振幅は正常範囲内であった。石原色覚検査表の分類表誤読数は右8表、左4表。パネルD-15では右fail、左passであった。Farnsworth-Munsell 100 Hue Test(F-M 100 Hue)の総偏差点は右148(正常範囲外)、左84(正常範囲内)であった。精査中、頭部MRIにて左聴神経腫瘍を認めた。2013年6月頃には自覚症状の改善を訴えており、同年7月再度色覚検査を行ったところ、石原色覚検査表誤読数は右2表、左1表。パネルD-15は左右眼それぞれpassと改善がみられた。F-M 100 Hueの総偏差点は右108、左124(ともに正常範囲外)であった。【結論】発症時、高校受験勉強の最中であり、一過性の左聴力障害などストレスとなる背景がいくつか存在していた。明らかな視路疾患や眼疾患がなかったことから、色覚異常は重複したストレスによる心因性視覚障害が原因であると思われた。
1 0 0 0 OA 正常者におけるアポ蛋白への性, 年齢, 喫煙, 飲酒, 肥満の影響
- 著者
- 川西 昌弘 松岡 重信 平岡 政隆 小根森 元 高田 耕基 渡辺 哲彦 大谷 博正 梶山 梧朗
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.28-37, 1988-01-30 (Released:2009-11-24)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1 2
今回, 我々は新しいデータ解析の方法論としての exploratory data analysis の基礎的手法である boxplot および robust regression analysis を応用して正常集団におけるアポ蛋白値に及ぼす種々の背景要因の影響について検討し, 以下の結論を得た.1) Apo-AII (40歳代), Apo-B (30歳代), Apo-CII (40歳代), Apo-CIII (30歳代, 40歳代) は男性が女性より有意な高値を示した.2) 男性ではApo-B, Apo-CII, Apo-CIIIに, 女性ではApo-AII, Apo-B, Apo-Eに加齢の影響を認めた.3) 男性においてApo-AI, Apo-AII, Apo-CIIIの値は飲酒者が非飲酒者より高値であった.4) 男性においてApo-CII, Apo-CIIIの値は喫煙者が非喫煙者より高値であった.5) 肥満傾向の者は男性においてはApo-AII, Apo-B, Apo-CII, Apo-CIII, Apo-Eが, 女性においてはApo-AIIが高値であった.このように, 新しい統計的方法論を用いることにより比較的小数のデータでも多数例を用いた解析に劣らない有効な結果を得ることが可能であった.
1 0 0 0 OA 薬局及び訪問看護ステーションにおける他職種連携に関する調査研究
- 著者
- 高田 雅弘 中野 祥子 三田村 しのぶ 宮﨑 珠美 菊田 真穂 小森 浩二 首藤 誠 七山(田中) 知佳 森谷 利香 吉村 公一 石橋 文枝 塙 由美子 山本 淑子
- 出版者
- 日本社会薬学会
- 雑誌
- 社会薬学 (ISSN:09110585)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.116-127, 2015-12-10 (Released:2015-12-25)
- 参考文献数
- 10
With regard to proper drug use in home care, the failure of approximately half of all elderly patients to comply with their doctor’s medication instructions and many other issues have been reported. However, pharmacists’ involvement in home care support remains inadequate, as highlighted by a Ministry of Health, Labor and Welfare report which noted the lack of full utilization of pharmacists in community medicine as well as the fact that home nurses often have to manage their patients’ medications. The Setsunan University Faculty of Nursing was established in 2012, and the university’s Faculties of Pharmaceutical Sciences and Nursing collaborate in their educational activities. To increase pharmacists’ involvement in home care support, we launched a project to create a home care support model in which pharmacists and nurses work in collaboration, utilizing their respective faculty resources. In this study, we conducted a questionnaire survey of pharmacies and visiting nurse stations in Osaka Prefecture regarding the present status of and problems related to pharmacists’ participation in the home care system and visiting nurses’ current involvement in medication management, as well as what is expected of pharmacists. Based on these results, we are constructing a model in which Faculties of Pharmaceutical Sciences and Nursing collaboratively support the home care system with the aim of establishing the role that universities should play in a comprehensive regional care program.
- 著者
- 折橋 翔太 高田 涼生 松尾 康孝 甲藤 二郎
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告 = IEICE technical report : 信学技報 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.114, no.459, pp.131-136, 2015-02-23
本稿では,8K動画におけるH.265/HEVCの符号化方式制御の手法を提案する.8K動画では,その解像度の高さに伴い,動き量が大きなものとなる.このような動画に対しては,画面間予測における動き探索の探索範囲を拡大する必要があるが,動き探索は計算コストが大きいため,必要以上の探索範囲の設定は望ましくない.そこで本手法では,外部処理によって動画の動き量を推定し,推定された動き量に合わせて探索範囲を設定することによって,高効率な符号化を行う.ここで,探索範囲を拡大する場合には,HMの動きベクトル内挿機能を活用して,GOP間隔毎の探索範囲の拡大を行う.また,動きがランダムな動画に対しては,画面内予測のみで符号化することにより,低負荷な符号化を行う.
- 著者
- 折橋 翔太 高田 涼生 松尾 康孝 甲藤 二郎
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. ITS (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.114, no.459, pp.131-136, 2015-02-16
本稿では,8K動画におけるH.265/HEVCの符号化方式制御の手法を提案する.8K動画では,その解像度の高さに伴い,動き量が大きなものとなる.このような動画に対しては,画面間予測における動き探索の探索範囲を拡大する必要があるが,動き探索は計算コストが大きいため,必要以上の探索範囲の設定は望ましくない.そこで本手法では,外部処理によって動画の動き量を推定し,推定された動き量に合わせて探索範囲を設定することによって,高効率な符号化を行う.ここで,探索範囲を拡大する場合には,HMの動きベクトル内挿機能を活用して,GOP間隔毎の探索範囲の拡大を行う.また,動きがランダムな動画に対しては,画面内予測のみで符号化することにより,低負荷な符号化を行う.
1 0 0 0 P2-3-11 娘を持つ母親を対象とした子宮頸がん予防ワクチンに関する意識調査(Group44 子宮頸部腫瘍 疫学,検診,予防,一般演題,公益社団法人日本産科婦人科学会第67回学術講演会)
- 著者
- 高田 友美 上田 豊 森本 晶子 大道 正英 角 俊幸 木村 正 神崎 秀陽 万代 昌紀 関根 正幸 高木 哲 堀越 順彦 榎本 隆之
- 出版者
- 社団法人日本産科婦人科学会
- 雑誌
- 日本産科婦人科學會雜誌 (ISSN:03009165)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.2, 2015-02-01
1 0 0 0 ロシア農村共同体の実態--モスクワ県のある共同体の場合
- 著者
- 高田 和夫
- 出版者
- 九州大学教養部社会科学研究室
- 雑誌
- 社会科学論集 (ISSN:02867788)
- 巻号頁・発行日
- no.30, pp.p111-164, 1990-02
- 著者
- 高田 淳平
- 出版者
- 一般社団法人日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理學會誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.3, 2014-03-05
1 0 0 0 日常生活での遭遇履歴を用いたユーザクラスタリング手法
- 著者
- 玉井 祐輔 高田 秀志
- 出版者
- 情報処理学会
- 雑誌
- 研究報告グループウェアとネットワークサービス(GN) (ISSN:09196072)
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, no.17, pp.1-8, 2010-03-11
携帯端末の自律的な近接無線通信により情報交換を行うアドホックコミュニケーションでは,ユーザ同士がつながりを認識できないため,他のユーザとの間でグループを形成することが難しい.本稿では,アドホックコミュニケーションにおける遭遇履歴を用いて,ユーザをグループ化することを可能にするクラスタリング手法を提案する.本手法では,遭遇履歴によるユーザ間のつながり 「遭遇率」 として表し,クラスタリングの指標とする.また,時間帯ごとにクラスタを作成することで,人々が様々なグループに属している状況を表現できるようにする.これにより,アドホックコミュニケーションにおいてユーザ同士のつながりを反映した情報交換を行うことが可能となる.In the ad-hoc communication where the information is exchanged autonomously between mobile terminals with short range wireless network, it is difficult for users to create groups with other users because users can not recognize the connection between users. In this paper, a user clustering method based on users' encounter history in the ad-hoc communication is proposed. This method creates clusters with the measure called "encounter probability" that represents users relations based on users' encounter history. This method can also represent the situation where people belong to several groups by creating clusters based on time window. This clustering of users enables the information exchange considering the user connections in the ad-hoc communication.
1 0 0 0 超硬合金肺 (特集 じん肺症の画像診断をめぐって)
- 著者
- 森山 寛史 高田 俊範
- 出版者
- 克誠堂出版
- 雑誌
- 日本胸部臨床 (ISSN:03853667)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.12, pp.1430-1441, 2014-12
1 0 0 0 フォルクスワーゲンの不正ソフトウェアについて
フォルクスワーゲン(VW)が,不正なディーゼルエンジン制御ソフトウェアを用いていた事件が大きな波紋を広げている.この件に関して緊急に記事を書くように依頼され,本稿をまとめた.筆者は,車載ソフトウェアの開発技術を研究テーマの1つとしているが,エンジンや排ガス規制に関する知識があるわけではない.本稿の内容は,現時点(2015年10月7日)までに報道されている情報を自分なりに整理し考察したものであり,この記事が読まれる時点では大きく状況が変わっている可能性があることを最初にお断りする.