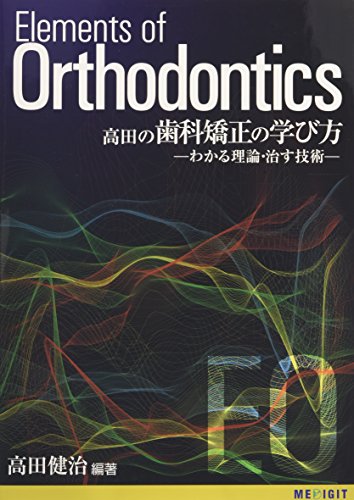1 0 0 0 OA 大阪市西成区北部におけるゲストハウス外国人宿泊者の日常生活に関する実証的研究
- 著者
- キーナー ヨハネス 水内 俊雄 コルナトウスキ ヒェラルド 冨永 哲雄 高田 ちえこ
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨 2013年人文地理学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.84-85, 2013 (Released:2014-02-24)
30名ほどのゲストハウス宿泊者を対象とした聞き取り調査の結果から、特にワーキングホリデーで来ている宿泊者の来日経由パターン、ゲストハウス生活、就労へのアクセス、ゲストハウス近隣に対するイメージを明らかにする。
1 0 0 0 OA 竹取物語断簡新出二葉 ―(付)延べ書き「富士山記」―
- 著者
- 高田 信敬
- 出版者
- 国文学研究資料館
- 雑誌
- 国文学研究資料館紀要 = The Bulletin of The National Institute of Japanese Literature (ISSN:18802230)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.1-20, 1984-03-30
従来二葉のみ知られていた伝後光厳院筆竹取物語に、今回さらに二葉の新出資料を追加、物語断簡の投げかける諸問題についてその一端を明らかにしたい。なお鎌倉後期l南北朝写と思われる延べ書き「富士山記」もあわせ紹介。 Two more sheets of paper of newly found materials were added to “Den Gokogonin hitsu Taketori monogatari”(伝後光厳院筆竹取物語)which only two sheets of paper were known conventionally. I would like to clarify one end about the issues that dankan (fragments) of the story raised. In addition, nobegaki (Classical Chinese texts forms rewritten in Japanese) ”Fuji san ki”(富士山記)that is thought to be copied from the late Kamakura period to the period of the Northern and Southern Courts was also introduced.
1 0 0 0 OA 病院にクラウン(道化師)が出現! : 病院訪問(ホスピタル)クラウンの現況
1 0 0 0 光量子論
- 著者
- A.Einstein著 物理学史研究刊行会編 高田誠二 広重徹 上川友好訳
- 出版者
- 東海大学出版会
- 巻号頁・発行日
- 1969
- 著者
- 田原 聖隆 藤井 千陽 高田 亜佐子
- 出版者
- 一般社団法人日本エネルギー学会
- 雑誌
- 日本エネルギー学会大会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- no.24, pp.248-249, 2015-07-27
In this study we were carried out the LCA of consumer's behavior level for LCT training. And we calculated the environmental load of the consumer behavior. There are big differences of the environmental load of each behavior by setting of the condition because consumer behaviors have variety. So, we calculated the consumer behavior on the condition that it was average and representative as possible. However, in order to lead to environmentally friendly behavior, consumer behavior was also calculated in different conditions that may be affected. For example the behavior of "to take a meal", we calculated about 100 Japanese typical menus. And in order to understand the differences in the environmental load of eco cooking, we calculated several type of cooking way on same menu.
1 0 0 0 IR 高校生の清潔行動と生活習慣に関する研究
- 著者
- 高田 直子 服部 洋兒 金子 恵一 平野 嘉彦 村松 園江 村松 常司
- 出版者
- 愛知教育大学保健管理センター
- 雑誌
- Iris health (ISSN:13472801)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.21-30, 2005
We have conducted an investigation for clean behavior and daily life style among high school students. As research subjects, 621 high school students were randomly selected, and given a questionnaire containing life style patterns, reasons for cleaning body, hygiene-related knowledge and self-esteem. As a result, in factor analysis of clean behavior, five factors, common evasion, clean custom strict enforcement, body surface clean maintenance, oral hygiene consciousness and environmental clean maintenance were extracted. Moreover, in the factor analysis of the reason for keeping the body clean, five factors of stress release body surface clean, prevention of a disease, personal manners and a clean attitude were extracted. The clean behavior currently performed in everyday life is related with a body surface clean maintenance factor, such as underwear is changed every day and taking a bath every day, and the thing about common evasion of a PET bottle turns and a drinker does not do, not grasping the strap of a train, etc. was seldom performed. The reason for keeping the body clean had many which catch the body surface clean maintenance factor for feeling refreshed etc. in the affirmative, in order to remove bodily dirt. Even if there was hygiene-related knowledge, it did not necessarily appear in behavior, and the relation of clean behavior and a self-esteem was not found. It can be said that the subject of how to connect hygiene-related knowledge to desirable behavior was shown from investigation of this high school students.本研究では,高校生の[|常生活における清潔行動,身体を清潔に保つ理由,衛生に関する知識,生活習慣,セルフェスティームを調査した。その結果,清潔行動の因子分析では「共用回避」,「清潔習慣励行」,「体表清潔保持」,「口腔衛生意識」,「環境清潔保持」の5つの囚子を抽出した。また,身体を清潔に保つ理由についての囚子分析では「ストレス解放」,「体表清潔」,「疾病予防」,「対人マナー」,「清潔態度」の5つの囚子を抽出した。日常生活で多く行われている清潔行動は「毎日下着を替える」,「毎日お風呂に入る」などの体表清潔保持に関するものであり,「ペットボトルの回し飲みはしない」,「電車のつり革を握らない」などの共用回避に関するものはあまり行われていなかった。身体を清潔に保つ理由は「体の汚れを落とすため」,「さっぱりするため」などの体表清潔に関するものが多かった。今回の結果からは清潔に関する知識があってもそれが必ずしも清潔行動につながっておらず,清潔行動とセルフェスティームとの関連もみられなかった。今回の高校生の調査結果からは清潔知識をいかに好ましい清潔行動に結びつけるかの課題が示された。
- 著者
- 高田 裕介 レオン 愛 中井 信 小原 洋 神山 和則
- 出版者
- 土壌物理学会
- 雑誌
- 土壌の物理性 = Journal of the Japanese Society of Soil Physics (ISSN:03876012)
- 巻号頁・発行日
- no.123, pp.117-124, 2013-03
わが国の農耕地における土壌情報で特に重要なものがデジタル農耕地土壌図と土壌環境基礎調査データベースである.本研究では,公開されている土壌情報の利活用の一例を示すために,土壌情報閲覧システムに収録されている農耕地土壌図および作土層の理化学性データベースを用いて炭素および窒素賦存量の全国試算を行い,それらの時空間的な変動を解析した.作土層中の炭素および窒素賦存量の平均値は有機質土壌グループおよび黒ボク土グループで高かった.また,炭素賦存量の主たる土壌群毎の経時変化は,水田で一定,普通畑で減少傾向,樹園地および牧草地で増加傾向にあった.他方,窒素賦存量の平均値は全ての地目において増加傾向であり,炭素/窒素比は減少傾向となった.作土層中の炭素および窒素総量は235から218TgCへ,また窒素総量は19.0から18.4TgNへと減少したが,農耕地面積の減少傾向とは一致しなかった.本結果は適切な土壌管理によって,耕地面積の減少による炭素および窒素賦存量の減少を抑制できるということを示している.
1 0 0 0 OA 休耕地における小哺乳類の生活史
- 著者
- 高田 靖司
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳動物学雑誌: The Journal of the Mammalogical Society of Japan (ISSN:05460670)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.3, pp.109-115, 1983-03-25 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 21
名古屋市緑区の農地に散在する休耕地において, 小哺乳類の記号放逐試験と捕殺を行なった。採集された小哺乳類はアカネズミ, ハツカネズミ, カヤネズミ, ジネズミおよびコウベモグラであった。そのうちで, アカネズミとハツカネズミは個体数が多く, 優占的にみられた。アカネズミ, ハツカネズミおよびカヤネズミは, 相互の分布の重複が少なく, 互いに排他的であることが示された。すなわち, アカネズミはセイタカアワダチソウ, ススキやヨシなど草丈が高く, 下草の豊富な草地を選択していたが, ハツカネズミはイヌムギ, エノコログサ, ヌカキビなど草丈の低いイネ科1年草の草地に強く結びついていた。これに対して, カヤネズミは特定の群落との結びつきが前2者程明確でなかった。
- 著者
- 高田健治編著
- 出版者
- メデジットコーポーレーション
- 巻号頁・発行日
- 2010
1 0 0 0 OA クローン病による消化管膀胱瘻の2例
- 著者
- 張 仁俊 澁澤 三喜 角田 明良 神山 剛一 高田 学 横山 登 吉沢 太人 保田 尚邦 中尾 健太郎 草野 満夫 田中 弦
- 出版者
- 日本大腸肛門病学会
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.4, pp.254-259, 1997 (Released:2009-06-05)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1 1
クローン病による消化管膀胱瘻は比較的まれで本邦では62例の報告がある.今回,著者らは教室においてクローン病による消化管膀胱瘻を2例経験したので報告する.症例1は32歳,男性.腹痛,発熱,混濁尿のため慢性膀胱炎として治療を受けていたが,糞尿が出現したため入院となった.小腸造影,注腸造影にて直腸S状結腸瘻,回腸直腸瘻がみられた.膀胱造影にて造影剤の漏出を認め,腸管膀胱瘻が強く疑われた.症例2はクローン病のためsalazosulfa-pyridineの内服治療を受けている28歳の男性.血尿,気尿,発熱を主訴に入院.膀胱造影にて直腸が造影され,クローン病による直腸膀胱瘻と診断した.いずれの症例も中心静脈栄養や成分栄養剤,prednisolonの投与等の内科的治療が奏効せず腸管切除と瘻孔部を含めた膀胱部分切除術を施行した.
ウッドセラミックス(WCS)は,廃木材を原料とし,フェノール樹脂と複合化して低酸素中での熱処理によって得られる炭素系新素材であり,木質由来の易黒鉛化炭素(多くのマクロ孔を有する)とフェノール樹脂由来の難黒鉛化炭素(ミクロ孔の生成に有効)から構成される複合炭素材料である.ウッドセラミックスの製法には2種類あり,中密度繊維板(MDF)に液状フェノール樹脂を含浸させて後,焼成する「MDF法」と,木粉とフェノール樹脂粉を混合後,室温プレスして後焼成する「粉末法」とがある.本研究は,このウッドセラミックスを有害ガスや水分の吸着材として活用することを目指して,その吸着量の指標となる比表面積を上昇させるには,MDF法がよいのか?木粉法がよいのか?さらに,フェノール樹脂の量は比表面積にどのような影響をおよぼすのか?また,原料に用いる木材の種類はどのようなものがよいのか?を調べるために行なった.得られた成果を列挙すると,以下のようになる.(1)同じフェノール樹脂量の場合,粉末法の方がより高い比表面積を得られることがわかった.すなわち,700℃焼成の場合,フェノール樹脂量を30%と一定にした場合,MDF法では,280m^2・g^<-1>,木粉法では,380m^2^<-1>であった.(2)粉末怯の場合,フェノール樹脂粉の量を増加させるにつれて,比表面積も増大した.ただ,100%フェノール樹脂粉にすると,かえって比表面積は低下した.700℃焼成試料の最高の比表面積は,70%フェノーノレ量の場合で450m^2・g^<-1>であった.(3)原料木材の種類が比表面積におよぼす影響を調べた結果,嵩密度の大きいうばめ樫は比較的低温の600℃ですでに330m^2・g^<-1>を示したが,その後800℃まで昇温してもその値はほとんど変わらなかった.一方,嵩密度の小さい針葉樹(松,杉)や竹,広葉樹のアオダモは,600℃で焼成では200-280m^2^<-1>とうばめ樫より低い値を示すが,700℃焼成では330m^2^<-1>とほぼ同じ値に追いつき,800℃焼成ではうばめ樫を追い越して330-450m^2^<-1>となった.このことから,600℃のような比較的低温焼成で大きな比表面積を得るためには,うばめ樫粉末とフェノール樹脂粉末を用いるのがよく,800℃での焼成ではアオダモや杉,松の粉末とフェノール樹脂の粉末を用いれば,高い比表面積を得ることが出来ると考えられる.
1 0 0 0 政界財界躍進日本を操る人々
1 0 0 0 OA 研究データリポジトリにおける時間軸を意識した版管理モデルの開発と実装
本研究では、研究データリポジトリにおけるメタデータの版管理手法およびバージョン管理された研究データ引用手法を提案し、プロトタイプシステムによる機能検証を実施した。版管理手法では、コンテンツおよびメタデータの双方の版を管理することとした。永続識別子はランディングページ毎に付与し、Memento Frameworkによる版管理情報の提供を実施した。研究データ引用手法では、Citation Style Languageによる引用情報の提供手法についての検討を実施した。
1 0 0 0 OA フローインジェクション法による土壌中の亜硝酸態,硝酸態及びアンモニウム態窒素の定量
- 著者
- 白上 房男 岡島 義昭 前小屋 千秋 高田 芳矩
- 出版者
- 公益社団法人日本分析化学会
- 雑誌
- 分析化学 (ISSN:05251931)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.9, pp.413-418, 1989-09-05
- 被引用文献数
- 1 3
土壌中の水溶性及び交換性の無機態窒素を迅速に連続測定するFIA法を検討した.亜硝酸及び硝酸態窒素の測定ではジアゾ化-アゾ化合物生成に高温反応(90℃)を適用した.なお,硝酸態窒素の測定では還元カラム(Cu-Cd粒状,φ3×300mm)の活性寿命及び還元効率への流量依存性を評価した.アンモニウム態窒素の測定では多孔質膜分離-インドフェノール法の常温反応における最適条件を検討した.土壌2gを浸出液50mlで振り混ぜ抽出し,その40μlを各成分の測定に供する.本法の繰り返し測定の再現性は相対標準偏差で0.3〜0.5%であり,定量範囲は亜硝酸態窒素:0.1〜7ppm,硝酸態窒素:1〜20ppm,アンモニウム態窒素:1〜150ppmである.なお,3成分連続測定の所要時間は約10分間である.
- 著者
- 西岡 泰弘 稲沢 良夫 高田 久 遠藤 純 斎藤 雅之 林 圭 米田 尚史 小西 善彦
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. A・P, アンテナ・伝播 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.111, no.231, pp.7-12, 2011-10-06
電気的・物理的に大型な被測定物のレーダ断面積(RCS)を精度良く測定できる計測技術を確立するために、筆者らは、屋外で地面反射波を利用して被測定物の近傍界RCSを測定し、それを遠方界に変換する計測方式の研究開発を行ってきた。しかしながら、これまでの検討における被測定物は平板などの単純な形状に限られていた。本稿では、複雑な形状を有する飛行機簡易モデルを被測定物に選定し、実環境下でのグランドプレーンレンジRCS計測精度検証およびRCS近傍界/遠方界(NF)変換技術の有効性検証結果を報告している。まず、アスファルト舗装道路上においてフレネル領域で測定した飛行機簡易モデルの近傍界RCS測定値とモーメント法による計算値とを比較し、両者が良く対応することを示している。次に、測定した近傍界RCS測定値をNF変換した結果とモーメント法による遠方界RCS計算値とを比較し、両者が良く対応することを示している。本検討により、複雑形状散乱体に対するグランドプレーンレンジRCS計測およびNF変換技術の有効性が実証された。
1 0 0 0 戦前の雑誌1冊を捜し歩いた細く長い径(歴史の小径)
- 著者
- 高田 誠二 西尾 成子
- 出版者
- 一般社団法人日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理學會誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.12, pp.938-940, 2011-12-05
1 0 0 0 大東亜戦争南十字星の下をゆく : 輸送船九七四丸
1 0 0 0 IR カントにおける神学と哲学の境界線 : 1783年の合理神学講義を中心に
- 著者
- 高田 太
- 出版者
- 同志社大学
- 雑誌
- 基督教研究 (ISSN:03873080)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.2, pp.40-57, 2006-12
神学と哲学との間の境界線はいかに画定されるのか。本論文の目的は、『純粋理性批判』の「超越論的方法論」における哲学体系の叙述と1783年の神学講義を中心にして、その時期のカントの哲学体系において定められうる神学と哲学の境界線について考察すると同時に、カント自身が両領域をいかに画定したのかを究明するところにある。カントは常に神学を形而上学として哲学体系の中に位置づけており、そういった位置を持たない宗教論と区別していた。形而上学としての神学は、超越的形而上学として内在的形而上学と区分されている。しかし哲学はあくまで両形而上学を包摂する。形而上学としての神学は合理神学と称され、カントはこれに啓示神学を対置している。しかしこの合理神学と啓示神学の間の境界線は、本来は哲学部と神学部という大学行政上の区分に過ぎない。合理神学はその行程の終わりに高次の啓示や神秘といったものに行き当たる。ここに哲学としての合理神学が越えることのできない境界線が存する。その境界線は本来の合理神学と啓示神学との、また合理神学と宗教論との境界線である。
- 著者
- 高田 信久 黒澤 忠弘 納冨 昭弘
- 出版者
- 公益社団法人日本放射線技術学会
- 雑誌
- 日本放射線技術學會雜誌 (ISSN:03694305)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.8, pp.1038-1044, 2006-08-20