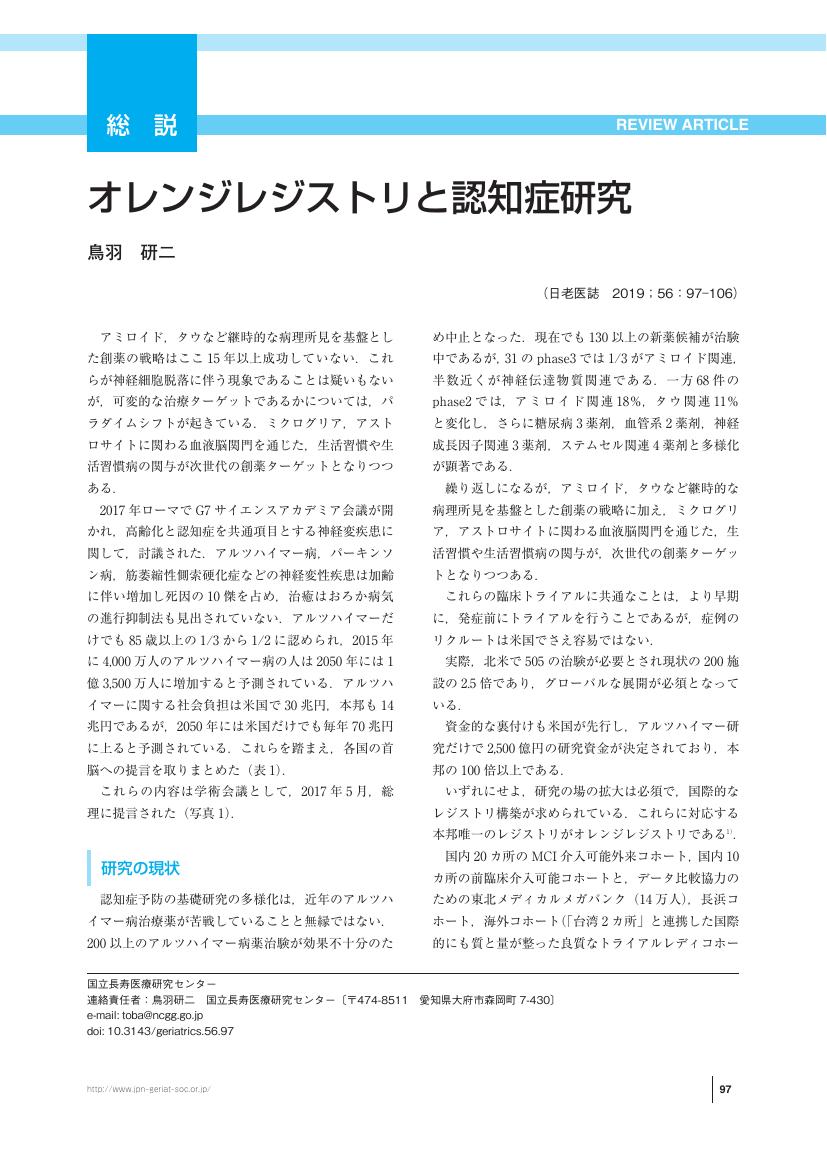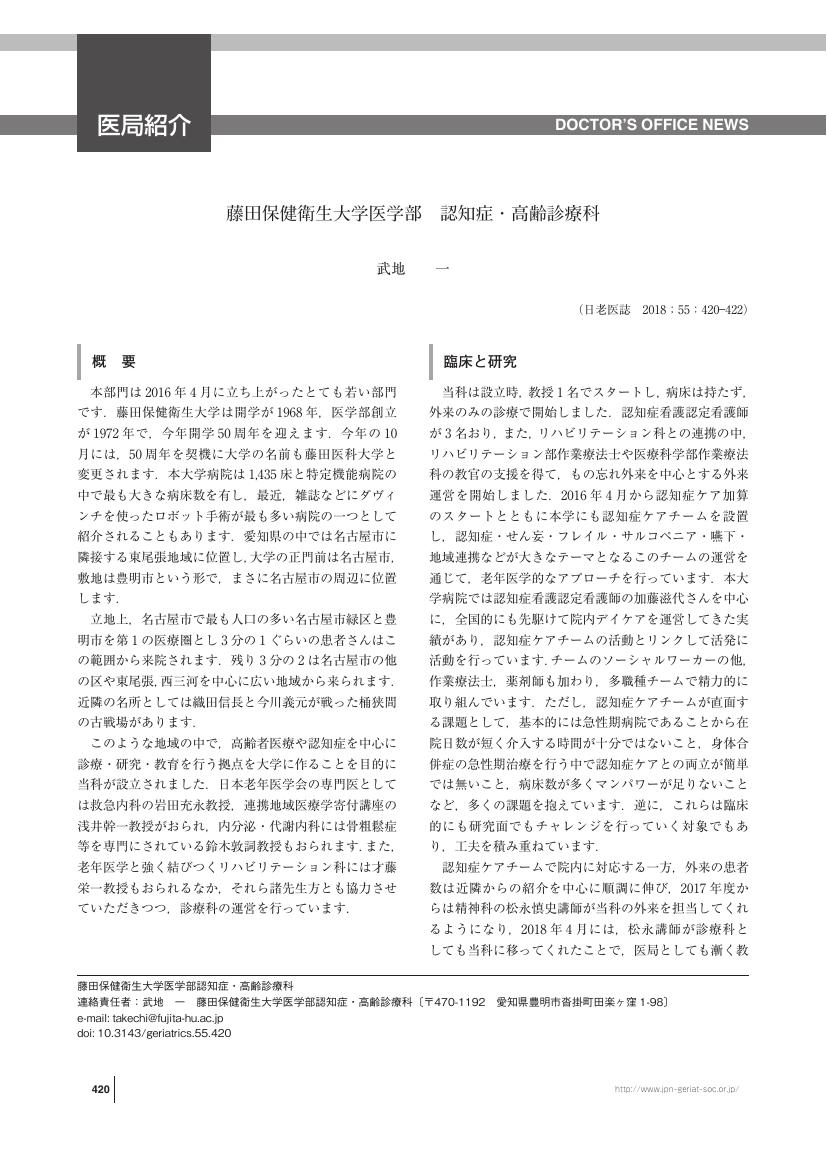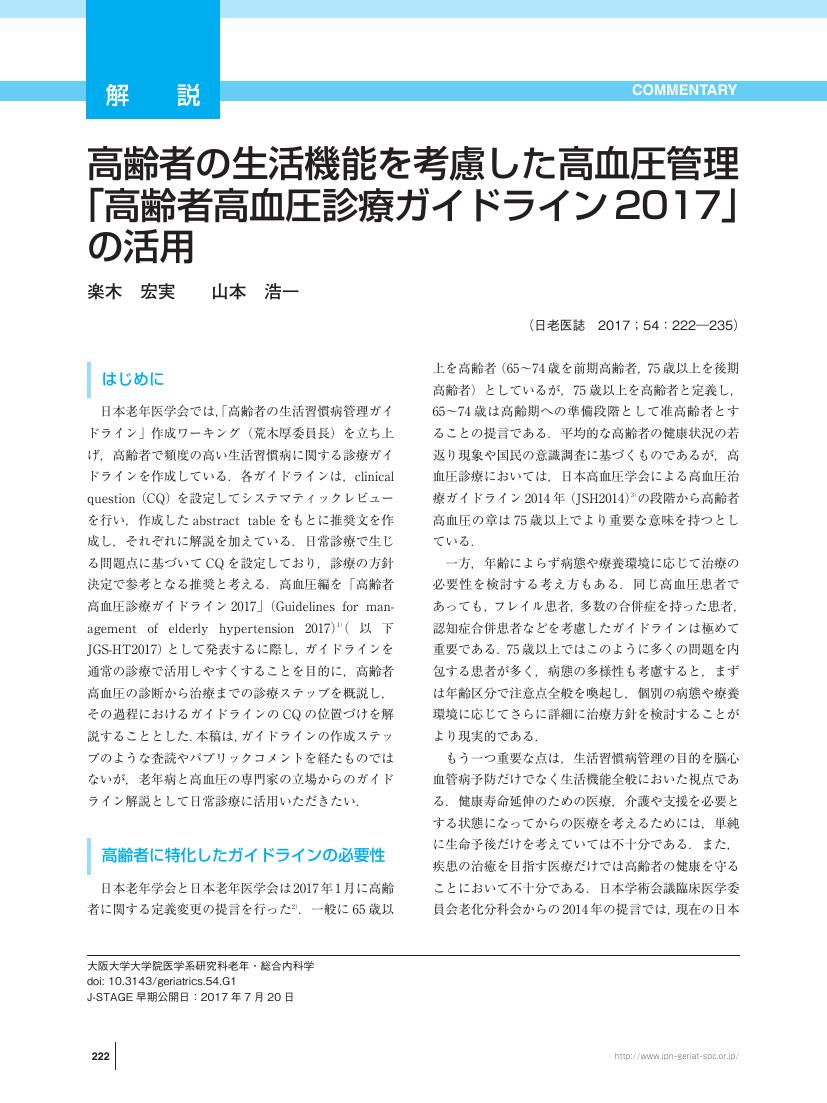1 0 0 0 OA オレンジレジストリと認知症研究
- 著者
- 鳥羽 研二
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.97-106, 2019-04-25 (Released:2019-05-16)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 OA Q:認知症カフェの経済的基盤について
- 著者
- 武地 一
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.154-157, 2018-01-25 (Released:2018-03-05)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA 藤田保健衛生大学医学部 認知症・高齢診療科
- 著者
- 武地 一
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.420-422, 2018-07-25 (Released:2018-08-18)
1 0 0 0 老人の体力とエネルギー代謝
- 著者
- 新開 省二 渡辺 修一郎 渡辺 孟
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.7, pp.577-581, 1993
基礎代謝量と関連が深い除脂肪量 (LBM) は加齢とともに減少する. しかし, 40歳代から60歳代の中高年者の基礎代謝量とその関連要因についての重回帰分析の結果からは, LBMの減少のみで加齢による基礎代謝量の減少は説明できなかった. そこで, 除脂肪組織成分 (EBM) と脂肪組織成分 (FTM) ごとの基礎代謝産熱量を性別, 年代別に推定した結果, 男女とも40歳代から60歳代にかけ, EBM単位重量当たりの基礎代謝産熱量が漸次減少していることが判明した. すなわち, 加齢に伴う基礎代謝量の低下には, 活性組織量の減少とともに活性組織単位重量当たりの基礎代謝量が減少していることも関与していることが示唆された.<br>中高年肥満女性に15週間の有酸素運動トレーニングを処方した結果, 全身持久力が向上し, 体構成でEBMが増加し, さらにEBM単位重量当たりの基礎代謝産熱量が21%増加した. 他方, FTMの基礎代謝産熱量には変化を生じなかった. このことから, 中高年者の活性組織の代謝活性ひいては全身の基礎代謝を向上する上で, 有酸素運動トレーニングが有効であることが示された.<br>さらに, 70歳代および80歳代の高齢者では個人差が大きいものの, 日常生活活動レベルが高いほど基礎代謝量が高く維持されているようであった. 身体的運動を継続する, あるいは活動的な生活を送ることによって加齢に伴う基礎代謝の低下を抑制し, 老人のエネルギー代謝を改善することが期待できる.
1 0 0 0 OA 「百寿者」の死因
- 著者
- 江崎 行芳 沢辺 元司 新井 冨生 松下 哲 田久保 海誉
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.116-121, 1999-02-25 (Released:2009-11-24)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 8 10
「老衰死」の有無を考察するため, 老年者の最高グループである百歳老人 (百寿者) 42剖検症例の死因を検討した. 対象は, 最近までのおよそ20年間に東京都老人医療センターで剖検された男性9例, 女性33例で, この性別比は全国百寿者のもの (1対4) にほぼ一致する.臨床経過や諸検査値を充分に考慮して剖検結果を検討すると, これら42症例の全てに妥当な死因があった. 死因となったのは, 敗血症16例, 肺炎14例, 窒息4例, 心不全4例などである. 敗血症の半数近くは腎盂腎炎を原因としており, 肺炎の多くが誤嚥に起因していた. 悪性腫瘍は16例に認められたが, その全てに前記死因のいずれかがあり, 悪性腫瘍自体が主要死因となったものは1例も存在しなかった.超高齢者では, (1) 免疫機能の低下, (2) 嚥下・喀出機能の低下, が致死的な病態と結びつきやすい. しかし, このことと「老齢であるが故の自然死」とは関わりがない.「老衰死」なる言葉に科学的根拠があると考え難い.
1 0 0 0 OA 多職種の視点から見た在宅高齢者の看取り
- 著者
- 平川 仁尚
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.97, 2014 (Released:2014-04-18)
- 参考文献数
- 1
1 0 0 0 OA 老齢者の便秘と体温の関係について
- 著者
- 島田 敏實 竹越 忠美
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.12, pp.945-952, 1992-12-25 (Released:2009-11-24)
- 参考文献数
- 10
老齢者の糞便貯留と体温との関係を明らかにする. 対象は65歳以上の入院患者34人 (男11人, 66歳から82歳, 平均70.3歳. 女23人, 65歳から84歳, 平均72.1歳. 全平均71.5歳) で毎日1回以上排便のある患者 (NCP) であるか3日間以上排便のない患者 (CP) である. CPにおいては排便前排便日を含んだ2日間における最低体温, 最高体温, および排便後排便日を含んだ2日間における最低体温の計3つの測定値を得た. NCPにおいては毎日排便があるので無作為に3日間を取出しその第1日の最低体温, 第2日の最高体温, 第3日の最低体温の計3つの測定値を得た. CPで排便前には28人中6人(21.4%) が37.3℃以上であった. NCPでは排便前の最高体温が平均36.39℃, 排便後の最低体温は平均36.0℃で, 排便前後の体温差は0.39℃であるが, CPでは排便前最高体温が37.03℃, 排便後最低体温が36.1℃で前後で体温の低下が0.93℃に及び差は0.54℃であった (F検定, p<0.001). 男女間ではNCPで差を認めず体温の変化は0.39℃に止まり, CPでは男女とも体温変化が強く女性が0.85℃男性が1.02℃であった (p<0.05). 緩下剤服用者の方が変化度が小さかった. 脳梗塞, 脳溢血や老人性痴呆をもつ患者ともたない患者とを比較してみると, NCPではその他の疾患と比較し差を認めなかったがCPでは中枢神経障害者で体温変化が大きかった(p<0.05). 糖尿病患者は非糖尿病患者に比しこの体温変動は有意差を示さなかった. NCPの年齢別にみた排便前後の体温の変化は加齢とともに大きくCPにおいては各年代とも体温変動が大きかった. 排便前後の白血球数は低下, 血沈が高進, CRPは変化せず体温は低下しエンドトキシンは減少又は不変であった. NCPの高齢者は糞便貯留により体温が上昇しやすいが糞便が貯留し便秘となると老齢者では年齢にかかわらず体温が排便後と比較し平均0.93℃上昇することが判明した.
1 0 0 0 OA 日本人の家族性アルツハイマー病
- 著者
- 永野 敬子 勝谷 友宏 紙野 晃人 吉岩 あおい 池田 学 田辺 敬貴 武田 雅俊 西村 健 吉澤 利弘 田中 一 辻 省次 柳沢 勝彦 成瀬 聡 宮武 正 榊 佳之 中嶋 照夫 米田 博 堺 俊明 今川 正樹 浦上 克哉 伊井 邦雄 松村 裕 三好 功峰 三木 哲郎 荻原 俊男
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.111-122, 1995-02-25 (Released:2009-11-24)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1 1
近年の疾病構造の欧米型への移行が指摘される中, 日本人における痴呆疾患の割合はアルツハイマー病の比率が脳血管性痴呆を越えたともいわれている. 本邦におけるアルツハイマー病の疫学的調査は, アルツハイマー病の原因究明に於ける前提条件であり, 特に遺伝的背景を持つ家族性アルツハイマー病 (FAD) の全国調査は発症原因の究明においても極めて重要であると考える.私たちは, FAD家系の連鎖分析により原因遺伝子座位を決定し, 分子遺伝学的手法に基づき原因遺伝子そのものを単離同定することを目標としている. 本研究では日本人のFAD家系について全国調査を実施すると共に, これまでの文献報告例と併せて疫学的検討を行った. また, 日本人のFAD家系に頻度の高いβ/A4アミロイド前駆体蛋白 (APP) の717番目のアミノ酸変異 (717Va→Ile) をもった家系の分子遺伝学的考察も行った.その結果, FADの総家系数は69家系でその内, 平均発症年齢が65歳未満の早期発症型FADは57家系, 総患者数202人, 平均発症年齢43.4±8.6歳 (n=94), 平均死亡年齢51.1±10.5歳 (n=85), 平均罹患期間6.9±4.1年 (n=89) であった. APP717の点突然変異の解析の結果, 31家系中6家系 (19%) に変異を認めた. また各家系間で発症年齢に明らかな有意差を認めた. 1991年に実施した全国調査では確認されなかった晩期発症型FAD (平均発症年齢65歳以上) 家系が今回の調査では12家系にのぼった.FADの原因遺伝子座位は, 現在のところ第14染色体長腕 (14q24.3; AD3座位), APP遺伝子 (AD1座位) そのもの, 第19染色体長腕 (19q13.2; AD2座位), 座位不明に分類され, 異なった染色体の4箇所以上に分布していることとなる. 日本人のFAD座位は, APPの点突然変異のあった6家系はAD1座位であるが, 他の大部分の家系ではAD3座位にあると考えられている. 今回の解析結果より, 各家系間の発症年齢に差異があることからも遺伝的異質性の存在を示唆する結果を得たが, FAD遺伝子座位が単一であるかどうかを同定する上でも, 詳細な臨床経過の把握も重要と考えられた.
1 0 0 0 OA 老年者発作性心房細動患者の虚血性脳血管障害発症率に関する研究
- 著者
- 中島 一夫 一之瀬 正彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.273-277, 1996-04-25 (Released:2009-11-24)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 3 4
目的: 65歳以降発症の発作性心房細動例 (E. PAf) の虚血性脳血管障害 (iCVD) 発症率を65歳以前発症の発作性心房細動例 (Y-PAf) 及び65歳以降発症の慢性心房細動例 (E-CAf) の発症率と比較し, その特徴を検討した.対象及び方法: 対象は, 弁膜症を有さず, 予防的抗凝固療法未施行のE-PAf 95例 (男54, 女41, 73.6±5.5歳) で, Y-PAf 79例 (男59, 女20, 52.4±11.6歳) 及びE-CAf 95例 (男54, 女41, 73.6±6.5歳)を対照として, 後向き調査にてiCVD全体及び成因別 (脳血栓症, 脳塞栓症) の発症率を算出した.結果: E-PAf は平均観察期間45.0カ月で, iCVD発症率は年間4.8% (塞栓2.7%, 血栓2.1%), Y-PAfは48.0カ月で年間2.5% (塞栓1.3%, 血栓0.6%, 分類不能な梗塞0.6%), E-CAfは59.8カ月で年間8.3%(塞栓5.1%, 血栓1.9%, 分類不能な梗塞1.3%) であった. iCVD全体の発症率で, E-PAf はE-CAf より有意に低率 (p<0.01), Y-PAfより有意に高率 (p<0.01), 脳塞栓症発症率でも, E-PAfはE-CAfより有意に低率 (p<0.01), Y-PAfより有意に高率 (p<0.01), 脳血栓症発症率では, E-PAfはY-PAfより有意に高率 (p<0.01) であった.E-PAf中, 1回のみのAf発作57例と複数回発作38例間で, iCVD発症率 (年間3.3% v.s. 6.0%) 及び脳塞栓症発症率 (年間0.8% v.s. 4.6%) は複数回例で有意に高率 (p<0.005), 一方, 脳血栓症発症率 (年間2.5% v.s. 1.4%) は有意差なし.E-PAf中21例 (22%) が慢性に移行し, 移行後, iCVD全体で5例 (年間発症率8.6%), その中, 脳塞栓症は3例 (年間発症率5.2%) に生じた.結語: 老年発症発作性心房細動群の虚血性脳血管障害及び脳塞栓症発症率は, 老年発症慢性心房細動群と若年発症発作性心房細動群の中間に位置し, 複数回の心房細動発作及び心房細動の慢性化が発症率をさらに上昇させる因子になると考えられた.
1 0 0 0 OA 高齢者の生活機能を考慮した高血圧管理「高齢者高血圧診療ガイドライン2017」の活用
- 著者
- 楽木 宏実 山本 浩一
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3, pp.222-235, 2017-07-25 (Released:2017-08-29)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1 1
1 0 0 0 OA 老年者肺炎における心筋梗塞様心電図
- 著者
- 蔵本 築 松下 哲 三船 順一郎 坂井 誠 村上 元孝
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.115-120, 1977-03-30 (Released:2009-11-24)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
老年者肺炎12例に於て肺炎と同時または稍遅れて前壁中隔硬塞を思わせる心電図変化を認めた. すなわちV1-V3, V4のQSまたはrの減高, ST上昇, 冠性Tが出現し, 肺炎の軽快と共に異常Qは約一週間, 陰性Tは1カ月以内に正常化し, その後剖検し得た8例にはいずれも前壁中隔硬塞を認めなかった. 臨床所見では狭心痛はなく, 呼吸困難, 咳痰, チアノーゼ, 意識障害等が見られ, 肺炎は2葉以上にわたる広範な病巣を示し, 胸膜癒着または胸水を伴った. 検査所見ではGOTの軽度上昇を4例に認めたにすぎず, BUNの一過性上昇, CRP強陽性, PO2低下と共にヘマトクリットは全例4~9%の著明な上昇を示した.剖検し得た8例では肺気腫を6例, 気管支炎を7例に, 剖検時肺炎を6例に認めた. 陳旧性後壁硬塞及び後壁心外膜下出血を各1例に認めた. 左冠動脈前下行枝の50%以上狭窄を7例に認め, 心筋小胼胝を5例に認めた.急性心筋硬塞様心電図の発現機序として慢性肺疾患によるQRS軸の後方偏位, 肺炎に伴う急性右心負荷, hypoxia, 中等度の冠硬化などの上にヘマトクリット, 血液粘度の上昇等が加わって心筋に広範な一過性虚血性変化を来たすものと考えた.
1 0 0 0 OA 悪性貧血に対し,経口的ビタミンB12投与が著効した橋本病合併高齢者糖尿病の1例
- 著者
- 和泉 賢一 藤瀬 剛弘 井上 佳奈子 森 仁恵 山崎 孝太 本郷 優衣 高木 聡子 山内 寛子 蘆田 健二 安西 慶三
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.4, pp.542-545, 2013 (Released:2013-09-19)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 3 6
症例は73歳男性.主訴は貧血.家族歴,生活歴ともに特記事項なし.既往歴に2型糖尿病,橋本病を認めた.血液検査所見にてMCV高値の大球性貧血を認めた(赤血球数279万/μL,ヘモグロビン12.2 g/dL,MCV 121.9 fL).葉酸は基準値内であったが,ビタミンB12を測定したところ,57 pg/mL(基準値:180~914)と低値を認めた.消化管内視鏡であきらかな貧血の原因と思われる所見を認めず,また,抗内因子抗体は陽性であった.治療について,本人と相談したところ,注射は絶対に拒否するとのことであった.同時期に糖尿病の神経障害の治療のため,メコバラミンを内服処方したところ,著明にHb,MCVに改善を認めた.経口によるビタミンB12投与により,悪性貧血が改善したと考えた. 高齢者に貧血は多く,その中でも,悪性貧血は高齢になるにつれ頻度の高くなる疾患であり,注意が必要である.悪性貧血は,ビタミンB12製剤の注射治療が主に行われており,内服治療は一般的ではない.しかし,最近,ビタミンB12大量内服で効果を認めた症例が報告されるようになった.本症例も,ビタミンB12経口内服後に貧血の改善を認めており,効果があると考えられた.身体機能が低下する傾向にある高齢者にとって,安全・安価に加え,侵襲度の低い治療選択肢が増えることは望ましい事と思われる.内服投与も,今後の高齢者悪性貧血の治療の選択肢として考慮して良いのではないかと考え,本症例を報告する.
- 著者
- 木下 かほり 佐竹 昭介 西原 恵司 川嶋 修司 遠藤 英俊 荒井 秀典
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.188-197, 2019-04-25 (Released:2019-05-16)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1
目的:外出低下は身体機能や抑うつの影響を受け,いずれも低栄養と関連する.低栄養の早期兆候である食事摂取量減少と外出低下との関連を検討した.方法:老年内科外来を初診で受診した高齢者で認知症あり,要介護認定あり,施設入所中,急性疾患で受診,調査項目に欠損がある者を除外し463名(男性184名,女性279名)を解析した.調査項目は性,年齢,BMI,服薬数,基本チェックリスト,MNA-SFとした.外出週1回未満を外出頻度低下とし,過去3カ月に中等度以上の食事摂取量減少ありを食事摂取量減少とした.外出頻度低下有無で2群に分け調査項目を比較した.目的変数を食事摂取量減少あり,説明変数を外出頻度低下ありとしたロジスティック回帰分析を行った.調整変数は,性,年齢,および,外出頻度低下有無2群間に差を認めた項目で多重共線性のなかった服薬数,基本チェックリストの栄養状態項目得点,口腔機能項目得点,身体機能項目得点,うつ項目得点とした.結果:平均年齢は男性79.6±5.9歳,女性79.9±6.1歳,外出頻度の低下は104名(22.5%).外出頻度低下あり群では外出頻度低下なし群と比べて,高年齢で服薬数が多く,MNA-SF合計点が低く,基本チェックリスト合計点が高かった(すべてp<0.05).ロジスティック回帰分析では性,年齢,服薬数,栄養状態項目得点,口腔機能項目得点で調整後,食事摂取量減少ありに対する外出頻度低下ありのオッズ比2.5,95%信頼区間1.5~4.4,さらに身体機能項目得点およびうつ項目得点で調整後のオッズ比2.0,95%信頼区間1.1~3.6であった.結論:生活機能の自立した高齢者では多変量調整後も外出頻度低下は食事摂取量減少と関連した.食事摂取量減少はエネルギー出納を負に傾け体重を減少させ低栄養をきたす.低栄養の早期予防には日常診療で高齢者の外出頻度に注目することが重要である.
1 0 0 0 OA 動脈硬化巣におけるマクロファージの血管内皮細胞増殖因子発現の制御に関する研究
- 著者
- 葛谷 雅文
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.4, pp.268-272, 1998-04-25 (Released:2009-11-24)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 3 5
Vascular endothelial growth factor (以下VEGFと略す) は血管内皮細胞に対する特異的増殖因子として同定され, 胎生期の血管形成, ならびに種々の病態に伴う血管新生に関与していることが明らかにされつつある. 我々は以前血管平滑筋細胞の培養上清に血管新生誘導物質が存在し, それがVEGFであることを報告した. さらに人動脈硬化巣, 特に atheromatous plaque において, 平滑筋細胞層のみならず, lipid core 近傍のマクロファージ由来泡沫細胞周辺にVEGFの存在を認めた. 以上の結果よりVEGFは動脈硬化巣に存在し, 動脈硬化形成になんらかの役割を果たしていると思われる. しかしながらVEGFの発現が動脈硬化巣でどのように制御されているか依然として不明である. 今回我々はマクロフアージのVEGF発現にターゲットをしぼり, 炎症性サイトカインと, 動脈硬化の発症進展に重要な役割をはたしていると思われる酸化的変性低比重リポ蛋白 (OX-LDL) の影響につき検討した. マクロファージ cell line であるRAW264細胞に interleukin 1β, tumor necrosis factor αを暴露すると, RAW 264細胞にVEGF mRNA の発現が誘導された. さらに, OX-LDLの暴露によっても濃度 (5~100μg/ml), 時間 (3h~24h) 依存性にVEGF mRNA発現の増強を認めた. それに伴い細胞上清中のVEGF蛋白量も増加した. 以上より, 既に動脈硬化巣に存在が確認され, 病変の進展に関与していると思われる炎症性サイトカインや, OX-LDLによりマクロファージのVEGF mRNA 発現が誘導されることが明らかとなった. VEGFは動脈硬化巣に存在する微小血管形成や, 血管透過性の亢進, さらには単球・マクロファージの病変部への集積等に関与している可能性があると思われた.
1 0 0 0 OA 高年者の血清コレステロール・トリグリセリドに関する疫学的研究
- 著者
- 七田 恵子 大場 京子 芳賀 博 上野 晴美 柴田 博 松崎 俊久 高橋 重郎 斉藤 紀仁
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.4, pp.260-267, 1977-07-30 (Released:2009-11-24)
- 参考文献数
- 24
東京都養育院老人ホームの老年者 (男子724名, 女子1,239名) 計1,963名を対象として血清コレステロール, トリグリセリドを測定し, 皮脂厚, 老人環, 収縮期血圧, 拡張期血圧, 心電図所見との関連について検討した.1) 血清コレステロール分布はほぼ正規型を呈し, トリグリセリドはやや右方に偏った分布を描いたが対数変換を行うと幾分偏りが是正された.2) 5歳間隔の平均値で血清コレステロールの加齢変化を検討すると, 男子は横ばい, 女子は加齢とともに減少傾向を示した. トリグリセリドについても同じ傾向であった. すべての年齢層で性差を認め, 男子に比し女子は有意に高値であった.3) 各変量における単相関係数を求めると, 血清脂質と皮脂厚の間に男女いずれも有意な相関が示された (血清コレステロール: 男子r=0.215, 女子r=0.241, トリグリセリド: 男子r=0.254, 女子r=0.327, いずれもp>0.001). 血清脂質と老人環の関係は男子のトリグリセリドにおいてのみ低い正相関 (r=0.101, p>0.05) がえられた. 夜間排尿回数と女子のコレステロールおよび, 夜間排尿回数と男子のトリグリセリドの間に低い負の相関がえられた. 血清脂質と血圧の関係では, 女子においてコレステロールと収縮期血圧との関係を除いて低い正相関々係を示し, 男子ではトリグリセリドと拡張期血圧の間にのみ低い正相関を示した.4) 血清コレステロール. トリグリセリドに関し, 年齢, 皮脂厚・老人環, 夜間排尿回数, 収縮期血圧, 拡張期圧の6項目に対する偏相関係数を求めると血清脂質と肥満の指標である皮脂厚との関連は単相関と同様強いが, 皮脂厚などの要因を除外すると, 血清脂質と年齢および血圧との相関は低くなった. 男子において老人環および夜間排尿回数とトリグリセリドの間に有意な相関が認められた.5) 血清脂質レベルによる心電図所見出現率に関して, 高脂血群に有意に高率である所見は見出せず, 低脂質群に心房細動ならびに高電位出現率の高い傾向が認められた. 年齢変化を鋭敏に表わした異常Q, ST-T所見についても脂質レベルによる一定の関係はなかった.
1 0 0 0 OA 老年者の臨床検査成績における加令変化に関する研究
- 著者
- 七田 恵子 大場 京子 芳賀 博 上野 晴美 柴田 博 松崎 俊久 高橋 重郎 斉藤 紀仁
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.38-43, 1977-01-30 (Released:2009-11-24)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 2 1
都老人ホームに居住する65歳以上の男724名, 女1,239名, 計1,963名を対象として集団検診を行い, 諸種臨床検査成績における加齢変化を検討し, 次の如き結果を得た.1) 老人環: 老人環出現率は年齢が進むにつれ有意に増加し, 程度も増強し, 加齢変化を顕著に現わす指標と考えられた. また老人環と血清コレステロールとの関係は認められなかった.2) 夜間排尿回数: 就寝してから朝起床するまでの排尿回数は, 加齢とともに頻回となり, この傾向は男に比し女に強く認められた.3) 肥満度: 肥満について身長, 体重より算定した肥満度ならびに栄研式皮厚計を用いて計測した皮下脂肪厚の両面より加齢変化をみると, 女では加齢にともないるいそう傾向が認められた. この関係は肥満度に較べ皮下脂肪厚により強く表現された. しかし男では加齢による体格変動は一定の傾向を示さず横ばいであった.4) 血圧: 収縮期血圧は加齢とともに上昇し, 拡張期血圧は下降の傾向がみられるが, とくに女に顕著な変化が認められた.5) 心電図: 加齢にともなう心電図異常はST-T変化, 脚ブロック, PQ延長, 心房細動, 左軸偏位であり,とりわけST-T異常の出現が目立った.6) 血清脂質: コレステロールの平均値について男は概して横ばい, 女は加齢とともに明らかな低下を示す. 中性脂肪は男・女ともに平均値の減少化をみるが, 女により強い傾向が認められた.
1 0 0 0 OA 2.百寿者調査研究の成果と展望
- 著者
- 広瀬 信義 新井 康通
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.6, pp.762-765, 2013 (Released:2014-03-13)
- 参考文献数
- 17
1 0 0 0 OA 高齢者用かくれ脱水発見シートの開発―介護老人福祉施設の通所者を対象とした検討―
- 著者
- 谷口 英喜 秋山 正子 五味 郁子 木村 麻美子
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.4, pp.359-366, 2015-10-25 (Released:2015-12-24)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 2 2
目的:介護老人福祉施設の通所者におけるかくれ脱水(脱水の前段階)の実態調査を行い,非侵襲的なスクリーニングシートを開発することを目的とした.方法:介護老人福祉施設の通所者70名を対象に血清浸透圧値を計測し,かくれ脱水(体液喪失を疑わせる自覚症状が認められないにもかかわらず,血清浸透圧値が292から300 mOsm/kg・H2O)の該当者を抽出した.該当者において,脱水症の危険因子および脱水症を疑う所見に関してロジスティック回帰分析を行い,オッズ比を根拠に配点を行った.配点の高い項目から構成される高齢者用かくれ脱水発見シートを作成し,該当項目に応じた合計点毎の感度および特異度を求め,抽出に最適なカットオフ値を探索した.結果:かくれ脱水の該当者は,15名(21.4%)であった.先行研究のかくれ脱水発見シートを改良し,①女性である(4点),②BMI≧25 kg/m2(5点),③利尿薬を内服している(6点),④緩下薬を内服している(2点),⑤皮膚の乾燥や,カサつきを認める(2点),⑥冷たい飲み物や食べ物を好む(2点),の6項目から構成される高齢者用かくれ脱水発見シートを考案した.このシートにおいて,かくれ脱水である危険性が高いと考えられるカットオフ値は,9点(合計21点)に設定した(感度0.73,特異度0.82;P<0.001).結論:高齢者においては,脱水症の前段階であるかくれ(潜在的な)脱水が一定の割合で存在し,非侵襲的なスクリーニングシートにより抽出が可能である.
1 0 0 0 OA 2.日本老年医学会50年の歩み
- 著者
- 小澤 利男
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.6, pp.582-584, 2008 (Released:2009-01-29)
1 0 0 0 内分泌性高血圧
- 著者
- 竹田 亮祐
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.3, pp.182-187, 1993
- 被引用文献数
- 1
褐色細胞腫の記載者である故村上先生の本邦第1例の業績を記念し, 内分泌性高血圧のうち, 褐色細胞腫次いで原発性アルドステロン症及び Cushing 症候群をとりあげ, わが国における「副腎ホルモン産生異常症」疫学調査成績をもとにその臨床症候や検査成績を60歳前後で比較した場合の特徴について考案を加え, さらに上記3疾患について最近話題の2, 3の事項を紹介した. また本態性高血圧症を内分泌代謝学的に亜分類しょうとする観点から, 11β-hydroxysteroid dehydrogenase (11β-HSD)部分的障害仮説についてわれわれの得つつある最近の知見を付言し, 培養動脈平滑筋細胞に11β-HSD mRNAの発現を認めること, SHRの血管 (腸間膜動脈) にいおてはWKYラットに比べ11β-HSD活性が低下していること, 同遺伝子異常の可能性を示唆する実験的事実を報告した.