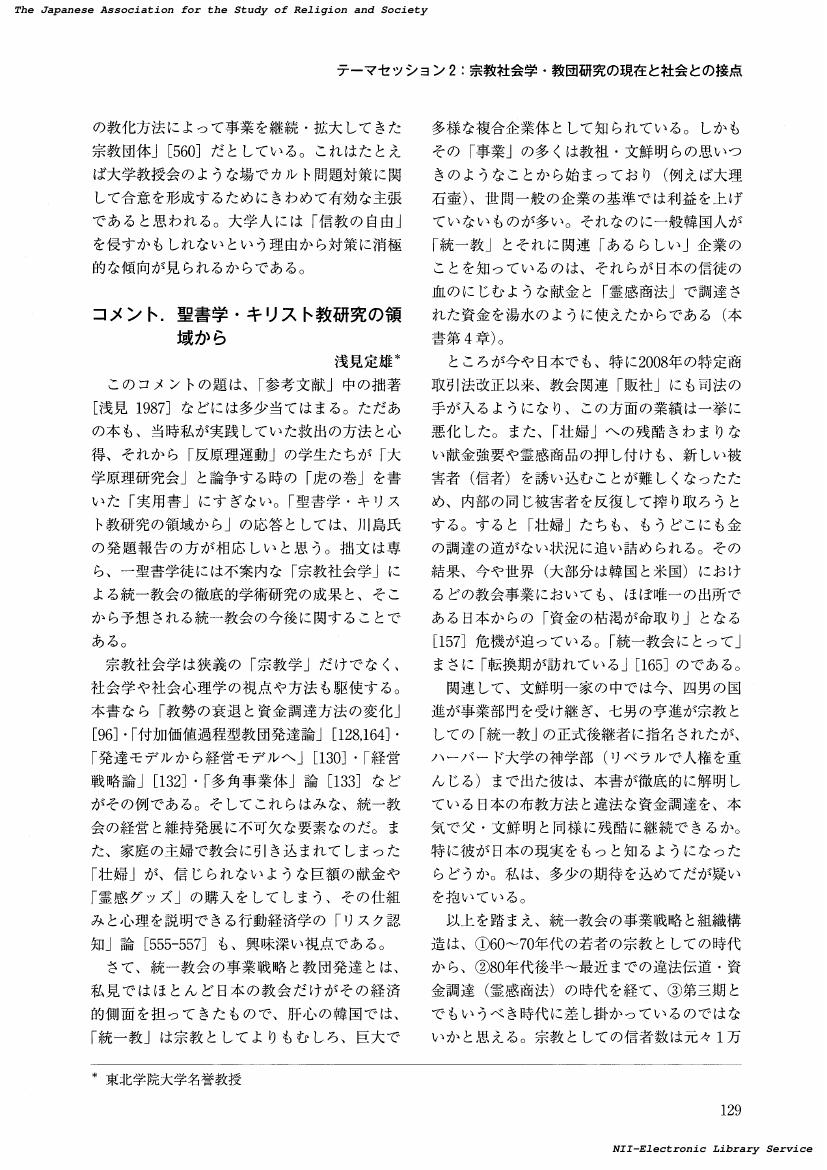1 0 0 0 OA 中学校教科書における巻頭詩の位置づけ(自由研究発表)
- 著者
- 永瀬 恵子
- 出版者
- 全国大学国語教育学会
- 雑誌
- 全国大学国語教育学会国語科教育研究:大会研究発表要旨集 127 (ISSN:24321753)
- 巻号頁・発行日
- pp.37-40, 2014-11-08 (Released:2020-07-15)
- 著者
- 日本トンネル技術協会 [編]
- 出版者
- 土木工学社
- 巻号頁・発行日
- vol.24(1), no.269, 1993-01
1 0 0 0 OA コーヒー抽出残渣施用が雑草と緑肥作物生育に及ぼす影響
- 著者
- 寺井 紀惠
- 出版者
- 聖心女子大学
- 雑誌
- 聖心女子大学大学院論集 = SEISHIN ESSAYS (ISSN:13428683)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.24-52, 2017-07-10
1 0 0 0 OA 世界の地域から : サンタフェ
- 出版者
- 自治体国際化協会
- 雑誌
- 自治体国際化フォーラム
- 巻号頁・発行日
- vol.2007年(2月), no.208, 2007-01-15
1 0 0 0 OA コメント.聖書学・キリスト教研究の領域から(宗教社会学・教団研究の現在と社会との接点-櫻井義秀・中西尋子『統一教会』を検討する-,テーマセッション2,2011年度学術大会・テーマセッション記録)
- 著者
- 浅見 定雄
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.129-130, 2012-06-16 (Released:2017-07-18)
- 著者
- 塚田 穂高
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.125, 2012-06-16 (Released:2017-07-18)
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 桑原 尚史
- 出版者
- 関西大学
- 雑誌
- 情報研究 : 関西大学総合情報学部紀要 (ISSN:1341156X)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.95-107, 2022-01-30
本稿は,ヒトの進化過程におけるヒトの情報行動の形成を概観することを目的とした.その結果,本研究においては,ヒトの進化および情報行動の形成を方向付けた要因として次の2つの要因が指摘された.ひとつは,乾燥化および寒冷化という環境の変化の要因である.もうひとつは,ヒトの生態学的地位の低さという要因である.ヒトは,この生態学的地位の低さを,道具の使用および集団の形成という2つの行為で克服し,環境の変化を生き延びた.そして,本研究においては,道具の使用および集団の形成は,発声器官を変化させ,言語を複雑化させ,社会的知性を発達させ,ヒトの脳を進化させたとの考察がなされた.
1 0 0 0 OA 2D画像生成ベースの疑似3Dモデルと仮想世界での利用方法
- 著者
- 近藤 生也 黒木 颯 百田 涼佑 松尾 豊 顾 世翔 落合 陽一
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第36回 (2022)
- 巻号頁・発行日
- pp.2M6OS19d01, 2022 (Released:2022-07-11)
物理世界の幅広い物体すべてをそのままの見た目や機能でデジタル化することは、仮想現実 (VR) の野心的な目標の1つである。現行のVRアプリケーションでは、物理世界の物体をメッシュなどの明示的なデータ形式に変換して活用し高速なインタラクションやレンダリングを可能にするが、このような明示的なデータ形式はVR内で表現できるリアルさの上界になっている。この限界を取り払うべく、ゲーム分野で使われる古典的なビルボードと呼ばれる技術から発想を得て、私たちはニューラルネットでリアルタイムにレンダリングされる2D画像だけで近似的に3Dオブジェクトを表現するDeep Billboardsを開発した。私たちのシステムは、一般的なVRヘッドセットでもクラウドレンダリングを活用することでリアルタイムかつ高解像度に、幅広い質感を持つあるいは変形するオブジェクトなどを利用することを実現し、物理世界と仮想世界の間のギャップを劇的に狭めることに貢献する。さらに、古典的なビルボードでは物理インタラクションが再現できなかった問題も単純な工夫により広く解決でき、DeepBillboardsが広く活用できることを示す。
1 0 0 0 OA 学部低学年向けの企業実データを用いた課題解決型演習とその教育効果に関する考察
- 著者
- 笹嶋 宗彦 石橋 健 山本 岳洋 加藤 直樹
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第36回 (2022)
- 巻号頁・発行日
- pp.1I1OS601, 2022 (Released:2022-07-11)
兵庫県立大学社会情報科学部では,実践力のあるデータサイエンティストの育成を目標に,学部1年生,2年生を対象として,連携企業の実データを用いた課題解決型演習(PBL)を実施している.本学部が育成を目指すデータサイエンティストとは,ITスキルを用いてデータを分析する力だけではなく,実社会において課題を発見・定式化し必要なデータを収集する力や,分析の結果を用いて社会をよくする提案が出来る社会実装力を備えた人材である.低学年は,データ分析力も,ITスキルも持っていないが,スキルに合ったやり方でデータを分析し,実店舗へ向けた販売施策を提案する過程を体験することで,経営を改善することへの興味を持たせることや,データだけでなく,現場を見て考えることの重要性を学ばせることを狙いとしている.2019年の学部創設以来,1年生向けのPBLを3回,2年生向けを2回実施し,それぞれ事後に学生アンケートを取ることで,演習を評価してきた.本稿では,今年度実施したPBL演習の概要と,これまでのPBL演習を通じて得られた,実データを利用するPBLの長所と課題について述べる.
1 0 0 0 OA 霊長類の乳児特徴とその認知の進化を探る
- 著者
- 川口 ゆり
- 出版者
- 一般社団法人 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 (ISSN:09124047)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.145-153, 2021-12-03 (Released:2021-12-07)
- 参考文献数
- 60
Primates behave differently toward infants and adults and experimental studies have also confirmed that they visually differentiate between adults and infants. Infants have some visual characteristics that primates may potentially use as age cues. For example, infants in some species have special coat or skin colors that are different from adults. Such coloration is called “infantile coloration” and the extent of it varies across species. Although previous studies have suggested several possible functional roles of it, such as inducing alloparenting behavior, they still remain unclear. Contrary to such species-specific color features, infants also have morphological characteristics that exist across species. “Baby schema” is a set of infantile morphological features, such as bigger eyes, smaller nose and mouth, proposed by Konrad Lorenz. Baby schema is supposed to be shared with various species and works as a releaser of caretaking behavior. I reviewed the studies investigating the effects of infantile coloration and baby schema on behaviors and cognition. Although studies showed that humans show robust preference for baby schema, there has been so far no evidence suggesting that non-human primates are also sensitive to it. In contrast, there is some evidence indicating the importance of species-specific infantile features, such as infantile coloration, for non-human primates. Thus, it may be possible that preference for baby schema was specifically acquired by humans during evolution, while species-specific infantile features, like infantile coloration, are more relevant for non-human primates. Further investigation combining studies with different approaches, such as observational studies in the field, comparative cognitive studies in labs, and image analysis of various species, will help us to understand the evolution of infantile features of each primate species.
1 0 0 0 OA ボノプラザン起因性collagenous colitisの1例
- 著者
- 小沼 宏徳 小沼 一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会 関東支部
- 雑誌
- Progress of Digestive Endoscopy (ISSN:13489844)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.1, pp.104-106, 2019-06-07 (Released:2019-06-20)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 2 1
The patient was a 66-year-old woman. Approximately 2 years after she was started on oral administration of vonoprazan fumarate (potassium-competitive acid blocker [P-CAB]) for treatment of intractable reflux esophagitis, she complained of diarrheal symptoms. Symptomatic treatment was administered for the diarrhea. However, because no symptom relief was obtained, colonoscopy (CS) was performed. In the segment from the sigmoid colon to the rectum, mucosal erythema and cat scratch signs were partially observed, while histological examination revealed an approximately 30-μm collagen band directly under the mucosal epithelium. Thus, collagenous colitis (CC) was diagnosed. Oral administration of P-CAB was discontinued, and the symptoms had disappeared one month later. When CS was repeated after another 3 months, no endoscopic abnormalities were observed. Based on histological examination, the collagen band had become thinner but persisted. Most superficial epithelium had exfoliated.Though a few reports have described endoscopic monitoring of CC, ours is the first reported case of CC caused by P-CAB.
1 0 0 0 خطبات اکابر
- 著者
- مرتب محمد اکبر شاہ بخاری
- 出版者
- مکتبہ رشیدیّہ
- 巻号頁・発行日
- 1998
1 0 0 0 OA 前頭葉症状を呈し、易怒性と拒否がある脳血管疾患患者に対す理学療法
- 著者
- 川上 恵治
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.34 Suppl. No.2 (第42回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.E1107, 2007 (Released:2007-05-09)
【はじめに】前頭葉損傷患者では自発性や意欲の低下、行動開始の遅延、衝動コントロールの不良などを伴うことが多く、これらの付加要因があるとリハビリテーションにのりにくい。今回、既往歴に小脳出血がある前頭葉症状を呈した症例を担当し、前頭葉症状の中核となる遂行機能障害に対し問題解決療法なる段階的教示を実施したところただちに改善が見られたが、その後拒否と易怒性のために理学療法実施が困難となった。認知症の辺縁症状を考慮して理学療法を実施した結果、著名な改善が見られた症例を経験したので報告する。【症例】62歳男性。介護老人福祉施設入所中平成18年6月14日熱発、6月19日誤嚥性肺炎で当院入院し絶食と補液。6月30日肺炎軽快。7月31日理学療法開始。既往歴は32歳腹膜炎、高血圧症、52歳小脳出血手術、多発性脳梗塞、高血圧症、平成18年1月腸閉塞。【初期評価】把握反射は両手陽性。動きは拙劣。左半身低緊張。体幹の立ち直り反応なし。意識清明。HDS-R6点。発語少ない。寝具に包まれ臥床している。寝返り、移乗動作全介助。端座位は左へ傾き立ち直ろうとせず。車椅子座位は左へ傾き背あてに押し付けている。食事動作全介助、排泄オムツ。問題点;1発動性の低下、2起居動作全介助、3食事動作全介助。ゴール:車椅子の生活、食事・トイレ動作の介助量の軽減。プログラム:1起居動作訓練、2食事動作訓練。【経過】段階的教示法に基づき動作を誘導した。起座は手すりを把持し軽介助。座位は口頭指示にて右へ重心移動可となり保持可能となった。車椅子座位は傾き、背もたれへの押し付けが減った。平行棒は介助にて1往復可能となった。食事動作は自力摂取可となったが、気が向かないと自力摂取せず、スプーンを持たせると拒否し怒った。同じように起居動作訓練も拒否し怒り実施困難となった。拒否されないように接し方を変え、一方的に誘導するのでなく本人の了解を一つ一つ得ながら実施した。その結果、拒否や暴言はなくなり訓練が可能となり食事も自力摂取するようになった。【退院時評価】拒否、易怒性が見られなくなり、食事動作は自力摂取となった。自発語が増加した。姿勢の傾きは減り体幹が安定してきた。排泄動作は訴えがなく実施できなかった。問題点:1発動性の低下、2起居動作要助、3排泄オムツ。【考察】認知症の評価は機能や生活上の問題点だけを課題抽出するのではなく、本人の能力や・願望・好みといった「したいこと」や「できること」をアセスメントする事であり、拒否や暴言は認知症の辺縁症状で、接し方により改善の可能性があると言われる。症例に対し評価の視点、接し方を変えることにより、辺縁症状が改善し理学療法の実施が可能となり効果が表れたと考える。
- 著者
- 張 添威 ZHANG Tianwei
- 出版者
- 東京大学
- 巻号頁・発行日
- 2019
審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 中村 仁彦, 東京大学教授 稲葉 雅幸, 東京大学教授 國吉 康夫, 東京大学教授 岡田 慧, 東京大学准教授 山本 江, 大阪大学特任教授 高野 渉
1 0 0 0 OA ポスト3.11時代の科学技術コミュニケーション 社会は原子力専門家を信頼できるのか
- 著者
- 八木 絵香
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.8, pp.546-549, 2011 (Released:2019-09-06)
- 参考文献数
- 6
3月11日以降,「社会に信頼されるためには何が必要か」と考える原子力専門家は少なくないだろう。しかし今は何を語っても,それだけでは信頼されないという前提からすべてを考え直すしかない。原子力の問題を,専門家主導の科学技術理解増進の観点でとらえるのではなく,科学に問うことはできるが,科学(だけ)では答えることのできない問題,すなわち「トランス・サイエンス(trans-science)」の課題としてとらえ直すという観点から,解説を加える。