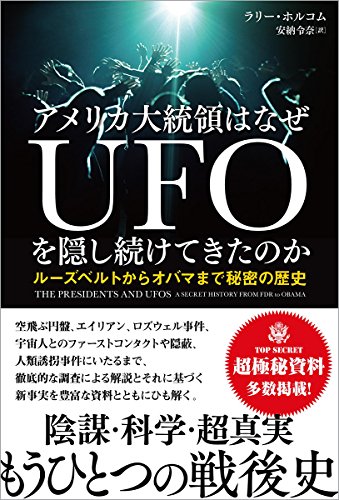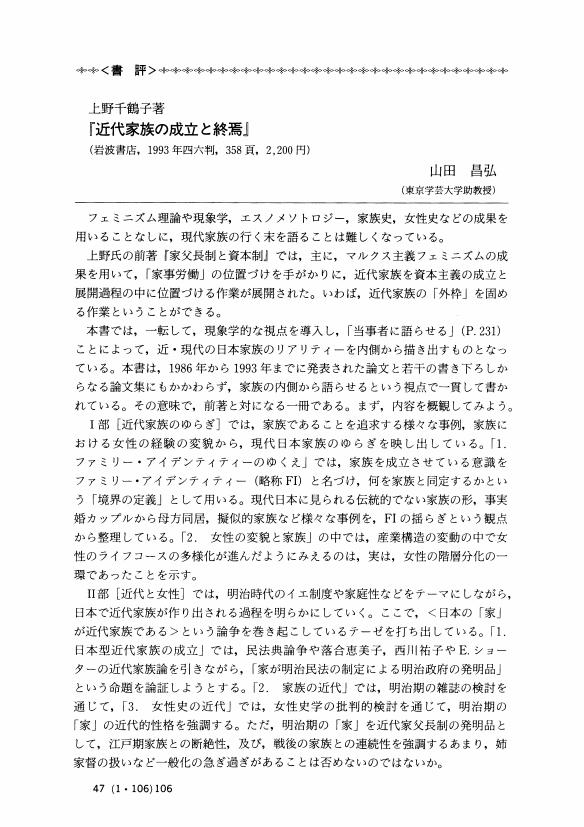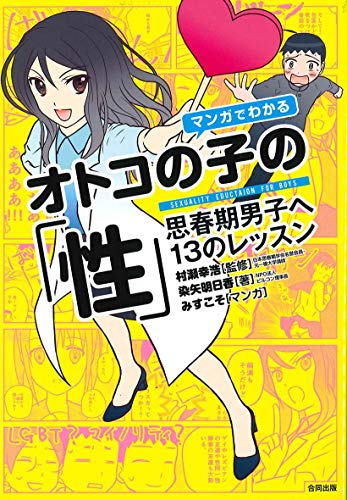1 0 0 0 OA aSNAQ: An adaptive stochastic Nesterov's accelerated quasi-Newton method for training RNNs
- 著者
- Indrapriyadarsini Sendilkkumaar Shahrzad Mahboubi Hiroshi Ninomiya Hideki Asai
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE (ISSN:21854106)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.4, pp.409-421, 2020 (Released:2020-10-01)
- 参考文献数
- 30
Recurrent Neural Networks (RNNs) are powerful sequence models that are particularly difficult to train. This paper proposes an adaptive stochastic Nesterov's accelerated quasi-Newton (aSNAQ) method for training RNNs. Several algorithms have been proposed earlier for training RNNs. However, due to high computational complexity, very few methods use second-order curvature information despite its ability to improve convergence. The proposed method is an accelerated second-order method that attempts to incorporate curvature information while maintaining a low per iteration cost. Furthermore, direction normalization has been introduced to solve the vanishing and/or exploding gradient problem that is prominent in training RNNs. The performance of the proposed method is evaluated in Tensorflow on benchmark sequence modeling problems. The results show that the proposed aSNAQ method is effective in training RNNs with a low per-iteration cost and improved performance compared to the second-order adaQN and first-order Adagrad and Adam methods.
1 0 0 0 OA なぜ富山市ではLRT導入に成功したのか? -政策プロセスの観点からみた分析-
- 著者
- 深山 剛 加藤 浩徳 城山 英明
- 出版者
- 一般財団法人 運輸総合研究所
- 雑誌
- 運輸政策研究 (ISSN:13443348)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.022-037, 2007-04-26 (Released:2019-05-31)
- 参考文献数
- 21
本研究は,富山市における LRT 導入と,関連するまちづくり施策の実現に関して,政策プロセスの観点から分析するものである.まず,政策プロセスを4つのフェーズにわけ,それぞれのフェーズにおける関係主体や検討の場,課題のフレーミングや主な論点などをまとめた.続いて,富山市を取り巻くさまざまな関係主体の立場を整理し,富山市によるフレーミングや利害調整を通じた対応のポイントを示した.その結果,政策プロセスにおける合意形成のためには,課題のフレーミング,議論の場のマネジメント,制約条件の活用,個別的な利害調整による対応等が重要であることが明らかになった.
1 0 0 0 OA 再燃を繰り返した乳癌術後放射線照射後器質化肺炎の1例
- 著者
- 中川 有 中鉢 誠司
- 出版者
- 日本臨床外科学会
- 雑誌
- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.7, pp.1577-1581, 2015 (Released:2016-01-30)
- 参考文献数
- 9
症例は55歳,女性.皮膚の浮腫と胸壁固定を伴う6cmの左乳房腫瘤を自覚し当院を受診した.浸潤性乳管癌(triple negative)と腋窩および傍胸骨リンパ節転移T4c N3bM0 Stage IIIcと診断し,FEC100×5,ドセタキセル×4を施行後,左乳房切除術および腋窩リンパ節郭清を施行した.病理組織学的には腫瘍径24mm,pN0であったが,化学療法前に傍胸骨リンパ節腫大を認めたことから,胸壁と鎖骨上窩に術後放射線照射(50Gy)を行った.照射6カ月後,発熱と呼吸苦あり,胸部レントゲンで左肺野に浸潤影を,胸部CTで多発する浸潤影とスリガラス様陰影意を認め,放射線療法後器質化肺炎と診断した.ステロイド投与を開始したが,ステロイド減量中に3回の再燃を繰り返したため,シクロスポリンを追加投与した.乳癌術後放射線照射後器質化肺炎にて免疫抑制剤の投与を必要とした症例を経験したので報告する.
- 著者
- Satoshi TANAKA Ryosuke TOMIO Norihiko AKAO Tsunemasa SHIMIZU Toshio ISHIKAWA Takeshi FUJIMOTO Terumasa NISHIMATSU
- 出版者
- The Japan Neurosurgical Society
- 雑誌
- NMC Case Report Journal (ISSN:21884226)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.177-181, 2022-12-31 (Released:2022-06-21)
- 参考文献数
- 19
Gelatin-based hemostatic agents are widely used in neurosurgery. This is a case of postoperative aphagia strongly suspected to be caused by an allergic reaction to a gelatin-based hemostatic agent after anterior cervical decompression and fusion for central cervical cord injury. A 55-year-old man underwent cervical anterior decompression and fusion at the C3/4 and 4/5 levels for central cervical cord injury. Immediately after the surgery, he could not swallow saliva at all, but his voice was not hoarse. Postoperative cervical computed tomography and magnetic resonance imaging showed significant edema from the post-hypopharynx wall to the front of the vertebral body. The retropharyngeal space was remarkably enlarged to 15.8 mm with cervical spine X-rays. Without neurological symptom improvement, his condition was diagnosed as marked edema of the area where Surgiflo (porcine-derived gelatin-based hemostatic agent; Johnson & Johnson Wound Management, Somerville, NJ, USA) had been applied during the operation. It was strongly suspected to be caused by an allergic response to the porcine-derived gelatin. When methylprednisolone 1000 mg was administered for 3 days from the 5th postoperative day, swallowing became almost normal within a few hours after the initial administration, and his neurological symptoms improved. The patient left the hospital on the 12th day after the operation. Before using porcine-derived gelatin products during surgery, special consideration should be given to patients with an allergy history before surgery.
1 0 0 0 OA 「死者の尊厳」の憲法上の位置づけと墓地埋葬法制
本研究は、ドイツ、オーストリア、イギリス及びイタリアの墓地埋葬法制を比較法的な観点から分析した結果を踏まえて、①わが国においても憲法13条によって葬送の自由、すなわち「死後、自らの死体(遺骨)をどのように取り扱ってほしいか」についての故人の意思を尊重すべきことが要請されると考えることができる反面で、②死者は敬意をもって葬られるべきことはわが国でも変わらないところ、③わが国では国レベルでの法令、少なくとも墓地埋葬法上はその調整に係るルールに乏しいことを確認し、そうしたルールの法制化の必要を提唱した。
1 0 0 0 OA 中性脂肪蓄積心筋血管症―この難病を1日でも早く克服する―
- 著者
- 平野 賢一
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, no.11, pp.2385-2390, 2017-11-10 (Released:2018-11-10)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 2 3
中性脂肪蓄積心筋血管症(triglyceride deposit cardiomyovasculopathy:TGCV)は,我々が2008年に心臓移植待機症例より見出した新規疾患概念である.細胞内代謝異常の結果,心筋細胞及び血管平滑筋細胞に中性脂肪(triglyceride:TG)が蓄積する.TGCVは既存の内科的・外科的治療に抵抗性を示す心不全,冠動脈疾患・不整脈症例に少なからず存在する.TGCV研究班の使命は「1日でも早くこの難病を克服する」ことであり,治療法の実用化を加速するため,症例登録・情報提供等をお願いしたい.
1 0 0 0 OA <知の先達たちに聞く(6) : 永田雄三先生をお迎えして>質疑応答
- 出版者
- 京都大学イスラーム地域研究センター
- 雑誌
- イスラーム世界研究 (ISSN:18818323)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.223-230, 2013-03
1 0 0 0 OA <知の先達たちに聞く(6) : 永田雄三先生をお迎えして>永田雄三先生 : 略歴と業績
- 出版者
- 京都大学イスラーム地域研究センター
- 雑誌
- イスラーム世界研究 (ISSN:18818323)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.195-207, 2013-03
1 0 0 0 OA 追悼:佐藤方哉先生
- 出版者
- 日本動物心理学会
- 雑誌
- 動物心理学研究 (ISSN:09168419)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.89-95, 2010 (Released:2010-12-22)
1 0 0 0 OA 220. 死亡したBulumiaの1例に対する精神病理学的検討(摂食障害IV)
- 著者
- 多田 克 生田 琢巳
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.Abs, pp.149, 1994-05-17 (Released:2017-08-01)
1 0 0 0 OA 上野千鶴子著『近代家族の成立と終焉』
- 著者
- 山田 昌弘
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.106-107, 1996-06-30 (Released:2009-10-13)
1 0 0 0 OA 健診からみた心房細動有病率と治療の状況
- 著者
- 齋藤 良範 柴田 香緒里 安達 美穂 後藤 明美 阿部 明子 庄司 久美 正野 宏樹 荒木 隆夫 齋藤 幹郎 横山 紘一 後藤 敏和 菊地 惇
- 出版者
- 公益社団法人 日本人間ドック学会
- 雑誌
- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.47-53, 2020 (Released:2020-10-07)
- 参考文献数
- 10
目的:心房細動(atrial fibrillation: AF)は,血栓性脳塞栓症の原因疾患であり予防には抗凝固療法が有用である.高齢者ほど有病率は増加するとされることから,健康診断受診者における有病率および治療の現状を把握し経年推移を検討した.方法:2017年度の受診者175,462(男性86,923,女性88,539)名の12誘導心電図(心電図)所見から,性・年代別のAF有病率および問診票より治療率を算出した.また,2013年から2017年度まで5年間のAF有病率の推移を検討した.結果:AF有病率は1.13(男性1.81,女性0.47)%で,加齢に伴い増加し各年代とも男性が高率であった.治療率は,60歳未満55.7%,60歳代68.8%,70歳代66.6%,80歳以上63.9%で,60歳未満で低かった.CHADS2スコアが1以上となる75歳以上では65.0%であった.AF有病率の経年推移は,2013年度1.03%,2014年度1.04%,2015年度1.10%,2016年度1.12%,2017年度1.13%と増加傾向が認められたが,男女別の年齢調整後の有病率には差を認めず受診者の高齢化が原因と考えられた.結論:AF有病率は1.13%で,男性に多く高齢になるほど増加した.60歳未満では未治療者が多く75歳以上でも35%は未治療であり,加療の必要性を啓発していく必要がある.
1 0 0 0 OA 子どもの発達に及ぼす社会経済環境の影響 : 内外の研究の動向と日本の課題
- 著者
- 喜多 歳子 池野 多美子 岸 玲子
- 出版者
- 北海道公衆衛生学会
- 雑誌
- 北海道公衆衛生学雑誌 (ISSN:09142630)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.33-43, 2013
日本では、子どもの相対的貧困率が上昇しているが、就学前の子どもの発達に及ぼす影響は報告されていない。そこで、諸外国で行われた親の社会経済状態(socioeconomic status; SES)と子どもの発達に関する研究に基づき、今後の課題を探った。PubMedを利用し、主に先進国の原著論文の分析を行った。その結果、①SES指標に親の教育歴、所得、職業が多く用いられていた。②発達は、「発達の遅れ」と「問題行動」に大別して報告されていた。③SESと発達の指標は多様であったが、就学前であっても、SESが子どもの「発達の格差」や「問題行動」に影響していた。④その関連に、親の抑うつ、育児ストレス、不適切な養育態度、物的困窮、少ない育児資源などが複雑に関係していた。欧米の研究は、「関連の強さ」から、「効果的な介入」を求める方向に向かっている。本邦の研究課題は、①日本社会にふさわしいSES指標の発見。②親のSESと子どもの発達に関する調査、及び効果的な介入方法の検討である。
1 0 0 0 マンガでわかるオトコの子の「性」 : 思春期男子へ13のレッスン
- 著者
- Manami OZAKI
- 出版者
- International Society of Life Information Science
- 雑誌
- 国際生命情報科学会誌 (ISSN:13419226)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.115-122, 2007-03-01 (Released:2019-04-30)
- 参考文献数
- 17
目的:本研究の日的は、宗教的伝統のあるS大学の学生と一般大学学生におけるスピリチュアリティーを比較し、意志の働き、内的な喜び、超越性、道徳性にどのような差があるか探索することである。その結果より、スピリチュアル・ヘルスとメンタルヘルスの構成概念を再考し、モデル構築をも目的とする。方法:心理的成熟度として表れるスピリチュアリティーの測定尺度であるSBAS-TEST(尾崎、2005)を、首都圏の一般大学生(N=287)とS大学生(N=107)とに試行し、総得点、各カテゴリー、因子ごとの単純加算得点を比較した。結果:S大学学生は、信念に基づいた行動、超越次元への気づき、倫理観、気遣い、スピリチュアリティーで、一般学生より有意に高得点を示した。しかしながら内面からあふれ出るスピリチュアルな喜びに関しては、一般学生と比較し低い傾向を示した。考察:S大学の宗教教育を背景とするスピリチュアリティーの側面は、超越的次元への気づきと、それに伴う道徳1生として表れた。しかし喜び得点が低いことから、それが必ずしも精神衛生の高さを意味しない可能性を示唆した。道徳性の高次への変容をスピリチュアル・ヘルスとして、適応中心のメンタルヘルスから区別することにより、スピリチュアリティーが、道徳性で記述できる可能性が示された。結論:メンタルヘルスとスピリチュアリティーの高さは必ずしも一致しない。高次の道徳性は、スピリチュアル・ヘルスのひとつの指標となりうる。