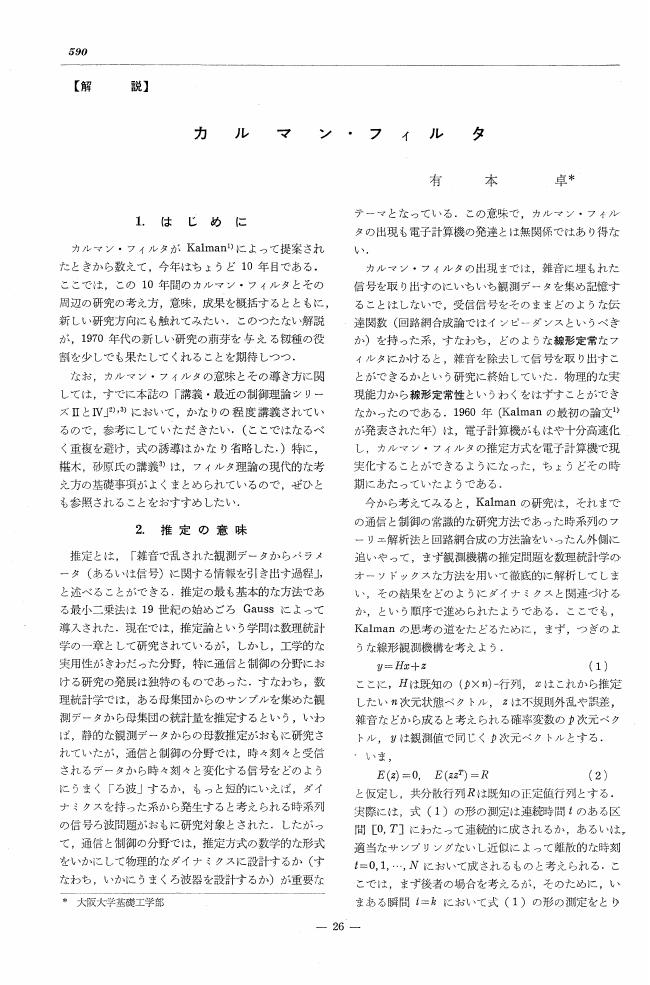1 0 0 0 OA レーダーを用いた夜間の渡り鳥の飛跡数,飛翔高度,渡り経路の追跡
- 著者
- 田悟 和巳 髙橋 明寛 萩原 陽二郎 益子 理 横山 陽子 近藤 弘章 有山 義昭 樋口 広芳
- 出版者
- 日本鳥学会
- 雑誌
- 日本鳥学会誌 (ISSN:0913400X)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.1, pp.41-61, 2020-04-23 (Released:2020-05-16)
- 参考文献数
- 59
渡り鳥の多くは夜間に渡りを行っていることが知られている.しかし,夜間における渡りの動向を調査する方法は限られているため,日本ではその実態はほとんどわかっていない.そこで,北海道から九州の140地点で船舶レーダーを用いた夜間の渡り鳥の調査を実施した.レーダー調査では種の同定はできないものの,夜間でも鳥類の飛跡数を定量的に調査でき,飛翔高度等が把握できるという利点がある.調査は各地点とも秋・春2回ずつ,日没時刻から日出時刻後3時間まで行い,幅2 kmの範囲の上空を飛翔する渡り鳥の飛跡数を計測した.560地点の飛跡数の平均は秋季14,415,春季4,388で,最大は109,693飛跡であった.飛跡数と環境条件との関係について一般化線形混合モデルにより解析した.応答変数は飛跡数,説明変数は調査地点の緯度,経度,調査時期,標高,地形,レーダー画像取得時間の割合,調査開始時の雲量とした.飛跡数に関係する要因として重要なのは,調査開始時の雲量であった.飛翔高度は対地高度300–400 mを頂点とする一山型を示した.飛翔時間は,日の入り時刻後80分から140分後頃に最大値を迎え,その後,徐々に減少した.本調査により推定された渡りのルートの多くが,既存の調査により既に知られており,このことは,本研究の結果の有効性を示唆するとともに,上昇気流を利用して日中に渡りを行う種と夜間に渡りを行う種の渡りルートは類似していることを示唆していた.このように船舶レーダーを用いた手法は,夜間を含む渡り鳥の動向を調査する方法として,優れた手法であることが明らかになった.
1 0 0 0 OA 氷結晶の表面融解現象と表面の微細構造
- 著者
- 古川 義純
- 出版者
- 日本結晶成長学会
- 雑誌
- 日本結晶成長学会誌 (ISSN:03856275)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.156-163, 1991-12-15 (Released:2017-05-31)
A review is given on the surface melting of an ice crystal and the physical properties of the quasi-liquid layer (surface melting layer). The thermodynamics of surface covered with the q.1.1. Is first briefly described and then the recent experimental works about the q.1.1. On ice surface are summarized. An ellipsometric study indicates that the critical temperatures of surface melting are -2℃ and -4℃ for {0001} and {101^^-0} faces, respectively, and the temperature dependences of q.1.1. Thickness for both faces are fundamentally different from each other. This result is discussed in conjunction with both the thermodynamic consideration and the structure of ice/quasi-liquid inter-face. On the other hand, the physical properties of q.1.1. Are discussed on the basis of the results obtained by some experimental methods, that is, the ellipsometry, X-ray diffraction, NMR and so on.
1 0 0 0 OA リチウムイオン電池概要と応用事例
- 著者
- 猿渡 秀郷 阿左美 義明 江草 俊
- 出版者
- The Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics
- 雑誌
- 日本AEM学会誌 (ISSN:09194452)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.4, pp.287-292, 2016 (Released:2017-05-10)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1 1
Lithium ion batteries have higher energy density. Recently, lithium ion batteries are beginning to be utilized in industrial applications. As for the lithium ion batteries in industrial applications, many different performances are required as well as energy density. It is important to develop according to the own requirement for their application. Energy density of Lithium ion batteries using LTO anode is smaller than that of conventional ones. But the batteries with LTO anode have unique features. In this reports, the features and application of lithium ion batteries using LTO anode is explained.
1 0 0 0 OA Digital Cultural Heritageに対する基礎評価モデルの提案とその実践
1 0 0 0 OA カルマン・フィルタ
- 著者
- 有本 卓
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.8, pp.590-598, 1970-08-10 (Released:2009-11-26)
- 参考文献数
- 61
1 0 0 0 OA アーカイブズ学の回顧と展望 アーカイブズ学総論 2004-2019
- 著者
- 坂口 貴弘
- 出版者
- 日本アーカイブズ学会
- 雑誌
- アーカイブズ学研究 (ISSN:1349578X)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, pp.33-53, 2020-06-30 (Released:2021-07-16)
1 0 0 0 OA 古機巡礼/二進伝心 : オーラルヒストリー 和田弘氏インタビュー
1 0 0 0 OA 通俗日本全史
- 著者
- 早稲田大学編輯部 編
- 出版者
- 早稲田大学出版部
- 巻号頁・発行日
- vol.第6巻, 1913
1 0 0 0 OA 半経験的分子軌道法を用いた分子構造と細胞傷害活性の相関関係の予測
- 著者
- 石原 真理子
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.127, no.5, pp.329-334, 2006 (Released:2006-07-01)
- 参考文献数
- 32
医薬品,農薬,内分泌撹乱物質,天然および合成有機化合物などの生理活性物質は,その独自の薬理作用と同時に,大なり小なり細胞傷害活性を持っている.この細胞傷害活性の研究は,特にアポトーシス研究の重要なテーマになっている.作用物質の作用発現の決定因子が作用物質の物理化学性にあるのか,作用点に到達してから作用発現させる化学反応性にあるのかで,作用物質の反応性は異なってくる.半経験的分子軌道法(PM3法)によりHOMOエネルギー,LUMOエネルギー,イオン化ポテンシャル(IP),絶対ハードネス(η),絶対電気陰性度(chemical potential,χ),オクタノールー水分配係数(log P)などのデスクリプター(記述子)を算出することにより,構造が類似した薬物の定量的構造活性相関解析(QSAR)を行なうことができる.Betulinic acid誘導体のメラノーマ細胞に対する細胞傷害性は,IPと直線的相関関係を示した.クマリン誘導体の口腔扁平上皮癌細胞に対する細胞傷害性は絶対ハードネス(η)と強く直線的相関性を示した.分子の硬さや柔らかさをPM3法で計算する際にはCONFLEXの使用が有用であった.ゲラニルゲラニオール類,ビタミンK1,K2,K3,プレニルフラボン類,イソフラボン類,没食子酸誘導体,フッ化活性型ビタミンD3誘導体,2-styrylchroman誘導体の細胞傷害性には,疎水性(log P)が大きく影響した.本方法を,生理活性物質のQSAR解析,最安定化構造の予測,細胞傷害活性の検討,そしてラジカル捕捉数の算定に応用した例なども紹介する.QSARは,より活性の高い物質の構造の創薬への貢献が期待される.
1 0 0 0 OA 視覚言語刺激と発語による脳磁界反応の観察
- 著者
- 藤木 暢也 内藤 泰 塩見 洋作 平野 滋 本庄 巖 長峯 隆 柴崎 浩
- 出版者
- 耳鼻咽喉科臨床学会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.12, pp.1499-1506, 1996-12-01 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 15
Event-related magnetic fields (ERFs) were recorded in seven subjects when they were presented with a rectangle and Japanese Kanji characters, followed by vocalizations. The ERF averages for the Kanji characters were different from those for the rectangle at latencies of about 100ms over the occipital lobe and 150-500ms over the temporo-parieto-occipital region. This observation suggests that the first stage of visual word processing might arise in the occipital lobe.In some cases, difference between the ERFs for the Kanji characters and those for the rectangle were also seen in the frontal lobe at latencies greater than 250ms. This observation suggests that frontal lobe activity may be also involved in visual word processing.Three equivalent current dipoles were estimated on the bilateral precentral gyrus (motor area) and the posterior part of the superior frontal gyros (supplementary motor area) at a latency of about 500ms during vocalization.In some cases, early responses at latencies of less than 150ms were obtained in not only the occipital lobe but also the frontal and temporal lobes. This suggests that parallel processing might occur during visual word processing.
1 0 0 0 農業改良普及資料
- 著者
- 愛知県農業改良課 [編]
- 出版者
- 愛知県農業改良課
- 巻号頁・発行日
- 0000
- 著者
- Gennaro ALTAMURA Bianca CUCCARO Claudia ELENI Carina STROHMAYER Sabine BRANDT Giuseppe BORZACCHIELLO
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.6, pp.881-884, 2022 (Released:2022-06-18)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 7
Recent evidence suggests a possible association of Felis catus papillomavirus type 2 (FcaPV-2) DNA with feline oral squamous cell carcinoma (FOSCC). In this study, type-specific PCR targeting two genes (L1/E6 or E1/E6) of FcaPV-1/-2/-3/-4/-5/-6 was performed to detect viral DNA in a large amount of FOSCC samples collected in Italy and Austria. FcaPV-1/-2/-3/-4/-5 were detected in 7/113 (6.2%), 7/93 (7.5%), 6/113 (5.3%), 1/113 (0.9%) and 2/113 (1.8%) specimens, respectively, with different prevalences in Italian vs. Austrian samples, whilst FcaPV-6 went undetected. Our results confirms that FcaPV-2 is the most prevalent in FOSCC, followed by FcaPV-1/-3 and suggest that FcaPVs have variable circulation rates in European countries.
1 0 0 0 IR 漢語平江方言の音韻及び文法の体系的研究
1 0 0 0 写真集明治大正昭和可児 : ふるさとの想い出254
1 0 0 0 OA 左前頭葉皮質下出血により環境依存症候群 (Lhermitte) を呈した一例
- 著者
- 安達 侑夏 笠井 明美 今村 徹
- 出版者
- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会
- 雑誌
- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.255-259, 2018-06-30 (Released:2019-07-01)
- 参考文献数
- 8
症例は 80 歳, 女性, 右利き。左前頭葉の脳内出血発症 60 日で当施設転入居。四肢に粗大な運動麻痺なし。自発話は乏しく, 話し掛けられると単語~短文レベルで発話がみられることがある程度。問いかけへの肯定 / 否定の意思表示は曖昧だが, 表情や行動, 態度から非言語的な状況理解は基本的に悪くないと思われた。施設内での生活場面で, 窓の鍵やドアが見えると開けようとするといった使用行動がみられた。さらに, 複数の職員がテーブルを囲んでミーティングをしていると, 近づいてきて職員の隣の椅子に座り, ミーティングの参加者のようにうなずきながら話を聞いたり, 机上の資料を手に取ったりする, など, 施設に勤務する職員であるかのように行動する場面が散発した。これは施設の環境が刺激となって出現した, Lhermitte の原著に忠実な環境依存症候群であると考えられた。
1 0 0 0 写真集明治大正昭和美禰・秋芳町美東町 : ふるさとの想い出151
1 0 0 0 写真集明治大正昭和西条 : ふるさとの想い出194
1 0 0 0 OA 政治意識の変容 : 「そのつど支持」から「選挙ばなれ」へ《特別論文》
- 著者
- 松本 正生
- 出版者
- 埼玉大学経済学会
- 雑誌
- 社会科学論集 = SHAKAIKAGAKU-RONSHU (The Social Science Review) (ISSN:05597056)
- 巻号頁・発行日
- vol.164, pp.5-32, 2021
小泉政権当時の2005 年に、無党派層に代わる、新たな概念として筆者が措定した「そのつど支持」は、その後、日本人の政治意識として広く定着した。「そのつど支持」とは、「特定の支持政党を持たず、(選挙のたびに)そのつど政党を選択する」態度を意味する。2009 年の民主党への政権交代以降は、とりわけ、中高年層の「そのつど支持」化が顕著であった。いわゆる無党派層や浮動票とは、若年層の政治意識や投票行動を表象する概念として用いられてきた。こうした意識や態度は、むしろ、中高年層の特性へと転化している。 有権者の「そのつど支持」化は、また、「選挙ばなれ」と表裏の関係にあった。2012 年に自民党が再び政権に復帰してからは、地方選挙で先行してみられた「選挙ばなれ」が国政選挙にも波及してきた。投票率の低落には、政治不信や政党不信と通称される一票のリアリティの消失に加え、社会の無縁化に起因する地域社会の変容も介在している。 本小論の論述スタイルは、仮説-検証の演繹的手法は採用せず、各種の調査結果や統計データの単純比較を通じた経験的解釈に終始する。諸兄のご批判を請いたい。 The term “sonotsudo-shiji” (new independent voter) that I defined at the time of the snap general election in 2005, now seems to have become widely generalized as the political mindset of the general Japanese population. The “sonotsudo-shiji” tendency is significant, especially among middle-aged and elderly voters. The term “independent voter” or “swing voter” has been used to describe the political attitude and voting behavior of young people. However, it is now better used to describe the middle-aged and elderly voter. Their tendency of being “sonotsudo-shiji” is inextricably associated with apathy toward elections. The general election in 2012 showed us that disinterest in local political elections has now spread into the national elections. The decrease in voting turnout in the 2012 general election was caused by a lack of involvement with the local society, and the feeling that a single vote did not count. This is reflected in a distrust of politics and political parties, born out of indifference toward other people. In this report, I present data in support of this hypothesis. I would like to thank you in advance for your comments on this report.