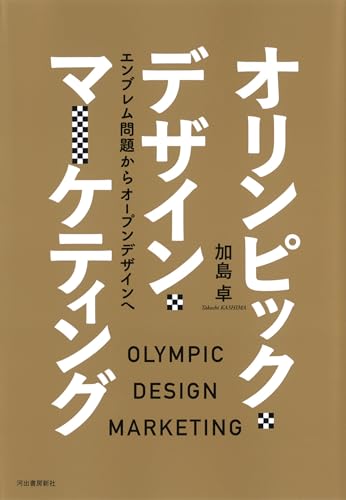- 著者
- 日田 大輔
- 出版者
- 防衛省防衛研究所
- 雑誌
- 防衛研究所紀要 = NIDS journal of defense and security (ISSN:13441116)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.151-185, 2019-11
1 0 0 0 OA アメリカ外交史再考 : アイゼンハワー政権
- 著者
- 岩田修一郎
- 出版者
- 東京家政学院筑波女子大学
- 雑誌
- 東京家政学院筑波女子大学紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.2000年, no.4, 2000
1 0 0 0 IR 大阪市立大学経済学部所蔵 大和国吉野郡川上郷井戸村文書目録
- 著者
- 谷 彌兵衛
- 出版者
- 大阪市立大学
- 雑誌
- 経済学雑誌 (ISSN:04516281)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, no.1, pp.121-150, 2005-06
本文書は, 相続文書や手紙等の内容から見て, 川上村大字井戸の井上家に旧蔵されていたと思われるが, 流出の経緯は詳らかではない。本学部は大阪市内の古書店より購入した。川上村は吉野林業地帯の中心地であり, 井戸は村のほぼ中央部に位置している。井上家は屋号を松屋といい, 代々村役人を勤めた家であり, 材木商人でもあった。……
1 0 0 0 IR バレーボールの試合におけるサーブの重要性について
- 著者
- 田中 愛 西野 明
- 出版者
- 千葉大学教育学部
- 雑誌
- 千葉大学教育学部研究紀要 (ISSN:13482084)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, pp.121-124, 2007-02
本研究の目的は,バレーボールの試合におけるサーブの重要性を明らかにすることである。バレーボールは1999年にルール変更が行われ,「ラリーポイント制」が採用された。このルール変更によって,これまでの「サイドアウト制」とは異なる試合の流れが生じていると考えられる。特にこの変化の影響を大きく受けていると考えられるのが,サーブである。そこで本研究では,実際にスコアリングを行い,1.「試合の流れ」としての連続失点の状況,2.サーブミスが試合の流れに及ぼす影響,3.「攻撃的サーブ」が試合の流れに及ぼす影響についてそれぞれ考察し,ラリーポイント制に適したゲーム分析を試みた。その結果,サーブミスが連続失点のきっかけとなりやすく,また「攻撃的サーブ」が必ずしもラリー取得にはつながらないことから,「ミスを避けるサーブ」が必要であることが示唆された。
1 0 0 0 OA 耐震設計の世界の現況と今後
- 著者
- 柴田 碧
- 出版者
- 安全工学会
- 雑誌
- 安全工学 (ISSN:05704480)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.6, pp.372-378, 1982-12-15 (Released:2018-01-31)
耐震設計の将来の進展について,著者の見解を述べる.現在の世界の耐震設計マベルはまちまちであるが,既存設備対策とか,運転に関係する人々の問題などつぎつぎに対応しなければならないことがでてくる.その辺の問題を紹介しながら議論を展開する.
1 0 0 0 電電公社の漢字処理技術,大きく前進
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- ドクメンテーション研究 (ISSN:00125180)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.5, 1980
1 0 0 0 OA 米国原子力発電シンポジウムから学ぶ
- 著者
- 尾本 彰
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.5, pp.256-257, 2013 (Released:2019-10-31)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 土壌中における重水の挙動追跡法 : 分析の精度と試料調整法
- 著者
- 佐久間 俊雄 倉持 寛太 斉藤 英樹 増谷 雪雄 望月 美千代 森下 諦三
- 出版者
- 日本土壌肥料學會
- 雑誌
- 日本土壌肥料学雑誌 (ISSN:00290610)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.3, pp.197-202, 1989
- 被引用文献数
- 3
以上の実験結果および考察はつぎのように要約できる。 1)軽水電界水素ガスをキャリアーガスとして用いることにより,検出加減を低く維持し,繰返し精度および再現精度を向上することができ,天然存在率以下のD/Hを精度良く測定できる。 2)この場合,較正曲線は良子な直線性を示し,D/H測定の信頼幅は,反複数40以上で3ppm以内(100〜1000ppmの範囲),反複数5でも8ppm以内(100〜260ppmの範囲)であった。3)市販超高純度水素をキャリアーガスとして用いる場合,軸正曲線の直線性には問題はないが,繰返し精度・再現精度は,軽水電界水素ガスをキャリアーガスとして用いたときよりやや悪かった。 4)土壌サンプルを用いた直接真空蒸留にはサンプルフラスコを大容量にするのが効率的であり,精度を損なうこともなかった。 5)テンションライシメータ法は土壌水の継続サンプリングに適しており,pF=2.5相当程度以上の水分率で有用であった。抽出に伴う同位対効果はわずかではあるが認められ,補正の必要があった。6)圃場実験に際しては,土壌水による希釈が著しく,自然存在率付近から300ppm程度までのD/H範囲における測定が多くなり,高い再現性度が要求される。軽水電界水素ガスをキャリアーガスとして用い,一連の測定ごとに2点較正することによって,測定日の違いによる誤差を補正して満足すべき結果を得た。
1 0 0 0 OA 静止地球環境観測衛星ひまわり8号及び9号について
- 著者
- 佐々木 政幸 操野 年之
- 出版者
- The Remote Sensing Society of Japan
- 雑誌
- 日本リモートセンシング学会誌 (ISSN:02897911)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.255-257, 2011-04-30 (Released:2012-03-13)
- 参考文献数
- 1
- 被引用文献数
- 2
- 著者
- 西中 華子
- 出版者
- 一般社団法人 日本発達心理学会
- 雑誌
- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.4, pp.466-476, 2014 (Released:2016-12-20)
- 参考文献数
- 61
- 被引用文献数
- 2
本研究では小学生の居場所感の構造を心理学的観点および学校教育的観点から検討し,居場所づくりの実践研究への示唆を得ること,および性差・学年差の検討を目的とした。まず心理学における先行研究を概観し,居場所感の要素として「被受容感」,「安心感」および「本来感」を仮定した。加えて教育分野における居場所の提言や論考を参考に,「充実感」および「自己存在感」を仮定した。これらに関する計35項目を準備し,小学4~6年生の児童,男女合計931名を対象として調査を実施した。因子分析の結果,「被受容感」「充実感」「自己存在感」「安心感」の4因子が確認され,教育分野の実践においていわれている「充実感」や「自己存在感」が小学生の居場所感の一要素を表すことが明らかにされた。一方で青年期の居場所感において重要視されている「本来感」が小学生の段階では重視されない可能性が示唆された。これらのことより,小学生を対象とした居場所づくりでは,「被受容感」「充実感」「自己存在感」「安心感」を促進するような介入方法の必要性が示唆され,青年期とは異なる介入の検討が必要であると考えられた。また小学生の居場所感において,「被受容感」および「充実感」は5年生および6年生よりも4年生のほうが,「自己存在感」は5年生よりも4年生のほうが高いことが明らかにされた。さらに男子よりも女子のほうが「被受容感」および「安心感」が高いことが明らかになった。
- 著者
- 野﨑 寛
- 出版者
- 愛知教育大学数学教育講座
- 雑誌
- イプシロン (ISSN:0289145X)
- 巻号頁・発行日
- no.60, pp.72, 2018-11-30
1 0 0 0 「奄美・沖縄」の世界自然遺産登録と持続可能な観光への提言
- 著者
- 深見 聡
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2019, 2019
<p>1.はじめに</p><p> 地域にとってプラスにもマイナスにも作用する可能性のある観光は、もはや21世紀における主要産業として欠かすことのできない存在となっている。そのため、「持続可能」という言葉が意味する、「本物」を保全・利用しながら次世代へと承継していく視点は、より高まっていくと考えられる。そこで登場してきたのが、エコツーリズムや世界遺産観光といった、地域への経済的効果ばかりではなく、保全意識の高まりや地域への共感といった、社会的効果が期待される「持続可能な観光」という考え方である。</p><p> そこで、本報告は、2020年に世界自然遺産への登録審査を控える「奄美・沖縄」の事例に焦点をあて、持続可能な観光につながる世界遺産登録の役割について考察を加えていくことを目的とする。</p><p></p><p>2.「奄美・沖縄」の世界自然遺産登録再推薦までの動向</p><p> 2018年の第42回ユネスコ世界遺産委員会が終了した時点で、日本には22件(自然4、文化18)の世界遺産が存在する。ここで取り上げる南西諸島では、屋久島(1993年登録)のほか、「琉球王国のグスク及び関連遺産群」(2000年登録)がある。首里城跡や斎場御嶽、今帰仁城跡など、観光客の増加は、地域経済に恩恵をもたらすと同時に、「観光公害」や「オーバーユース」といった、いわゆる観光客のマナーが原因となるさまざまな課題も生じている。</p><p> 登録件数の増加にともない、世界遺産の登録審査もより狭き門となりつつある。原則として年1回開催の世界遺産委員会における本審査に臨める候補は、従来の1か国につき「自然遺産・文化遺産で各1件まで」から、2020年より「自然遺産・文化遺産のいずれか1件」へと変更される。すなわち、国内での推薦を獲得するハードルが高くなることは確実と指摘されている。2019年1月、「奄美・沖縄」は、ふたたび世界遺産の審査に臨むことが決定した。当該地域の持つ自然や独特の文化の魅力は言わずもがなのものがある。そこに附言するならば、アマミノクロウサギやヤンバルクイナ、イリオモテヤマネコなどの希少生物に代表される、豊かな自然環境とそれらに育まれる文化を承継してきた当事者(主体者)に位置する島民にとって、今回の再推薦の決定に至る合意形成のプロセスが、どの程度ていねいに踏まれたのか、我われ研究者は十分に注視する必要がある。専門家が認める学術的価値や、それらを説明するストーリーは、専門家のなかで完結してしまうものではない。それらの価値が、地域で浸透していく過程が尊重されねばならない。このことを疎かにし、地域が置き去りにされるという感覚に陥った瞬間、保全とその背後にある観光との均衡は、余りにも脆弱なものになってしまうおそれがある。</p><p> 2018年5月、世界自然遺産の現地調査を担うIUCN(国際自然保護連合)は、「登録延期」という中間報告を発表し、政府はいったん申請を取り下げた。そのわずか半年後に、政府が再推薦の方針を示したことになる。この短期間に、学術的価値に限れば、ストーリーの再構築は可能だったかもしれない。しかし、保全の当事者である地域住民に対して、再推薦に向けた意識醸成や一体感といった動向は想定以上に伝わってこない。筆者が対象地の非居住者であり接する情報が少なくなってしまうことだけとは言えないと考えられる。</p><p></p><p>3.考 察</p><p> たとえば、それぞれの道に秀でた専門家の理解と、その理解を求め深めていく対象としての地域住民が価値の共有に至るまでの道のりには、どうしてもタイムラグが生じる。したがって、この時間差を半年の間で埋められたのか大いに疑問が残る。</p><p> 2018年に沖縄県が「奄美・沖縄」に含まれる西表島の島民を対象に実施したアンケート調査結果によれば、世界遺産登録を望まない割合が高く、その理由が「自然遺産に登録されると観光客が増えることで保全への不安が高まる」という、世界遺産制度のジレンマを地域住民が抱えていることがわかった。また、著名な観光サイト「トリップアドバイザー」でも、「奄美・沖縄」を、「世界遺産に登録される前に行っておきたい」と紹介しており、世界遺産観光の本来の役割はどこにあるのかを逆説的ではあるが観光者や研究者への問題提起ととらえられる。</p><p></p><p>4.おわりに</p><p> 世界遺産は、その根拠条約において保全を目的に掲げる一方、観光振興との両立には触れられていない。しかし実際には、魅力ある地域の宝が登録の対象となり、その価値共有の側面からも世界遺産観光が二次的現象として活発化し現在に至る。しかし、これまで繰り返されてきたように、登録決定時の首長コメント等に多い、観光振興(とくに経済的効果)への期待が声高に表明され、本来の保全への決意がかすんでしまうかのような「世界遺産への挑戦」は、再考すべき時機にあると考えられる。</p>
1 0 0 0 OA 船尾外輪船型旅客船"フロンティア"
- 著者
- 日立造船株式会社神奈川工場艦船設計室
- 出版者
- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- らん:纜 (ISSN:09160981)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.69-71, 1997-03-30 (Released:2018-02-25)
1 0 0 0 IR 野上彌生子の〈先生〉 ―漱石という体験―
1 0 0 0 OA 「倫敦塔」点描
- 著者
- 駒場 利男
- 出版者
- 学校法人 須賀学園 宇都宮共和大学 都市経済研究センター
- 雑誌
- 宇都宮共和大学 都市経済研究年報 (ISSN:18817459)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.96-106, 2010 (Released:2018-03-29)
1 0 0 0 D部門英文論文誌のScopusとESCI登録決定について
- 著者
- 大石 潔
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会論文誌. D, 産業応用部門誌 (ISSN:09136339)
- 巻号頁・発行日
- vol.137, no.4, pp.NL4_8, 2017
- 著者
- 南浦 涼介 柴田 康弘
- 出版者
- 全国社会科教育学会
- 雑誌
- 社会科研究 (ISSN:0289856X)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, pp.25-36, 2013-11-30 (Released:2017-07-01)
本研究は,生徒が社会科を学習する際の「学習観」に焦点を当てた研究である。現時点でこの「学習する意味」に着目した研究は多くない(Evans,1989,1990;村井,1996;佐長,2012)。しかし,「学習観」の形成と教師が行う実践には大きな関係があり,実践が生徒の「学習観」に与える影響は大きいと考えられる。本研究では,(1)生徒は,1年間の社会科学習を通してどのような社会科学習観を身につけたか,(2)生徒が身につけた「社会科学習観」には,教師のどのような影響があったか,(3)教師は社会科の目的や教育意図を,社会科指導においてどのように込めていく必要があるか,という点について探索的に考察していくことを目的とする。本研究は,いくつかのデータを取り扱っている。1つは,南浦ら(2011)を基にした4月〜3月の1年間におこなった質問紙による量的データである。2つめに,授業実施者である柴田に対するインタビュー,3つめに,授業を受けていた5人の抽出生徒の卒業後のインタビューという質的データである。インタビュー中,生徒たちは,自らの「社会科学習観」に強く影響を与えたこととして,第1に「日常的継続的な学習活動」第2に,教師が行った社会科学習の意味についてのさまざまな言葉がけ,第3に学校環境の変化を指摘した。この事例からは,教師が学習者の「社会科学習観」を変容させるためにはいくつかの要素が必要であることが推察される。第1に,教師は社会科学習の目的を単元レベルのみならず,日常的な学習活動やことばのレベルにおいても学習の目的を入れ込んでいく必要があるということである。第2に,教師は,こうした実践を柔軟に展開していくと同時に,演繹的に自身の教育目標からカリキュラムのレベルでコントロールしていく必要がある。第3に,教師が学校改革の中心的存在となり,学校で支持される「学習観」と教科で支持されるそれを関連づけていくことも重要である。この事例研究の結果から,筆者らは,社会科実践研究は単元レベルのみではなく,さらに具体的な実践レベルとカリキュラム・レベルを関連づけたものにしていく必要性を示した。
- 著者
- 杉原 周治
- 出版者
- 愛知県立大学大学院国際文化研究科
- 雑誌
- 愛知県立大学大学院国際文化研究科論集 = Bulletin of the Graduate School of International Cultural Studies Aichi Prefectural University (ISSN:13454579)
- 巻号頁・発行日
- no.22, pp.149-171, 2021
1 0 0 0 IR 毛髪から作られるケラチンフィルム
- 著者
- 藤井 敏弘
- 出版者
- 加工技術研究会
- 雑誌
- コンバーテック (ISSN:09112316)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.10, pp.97-101, 2014-10
コンパーテック. 42(10):97-101 (2014)