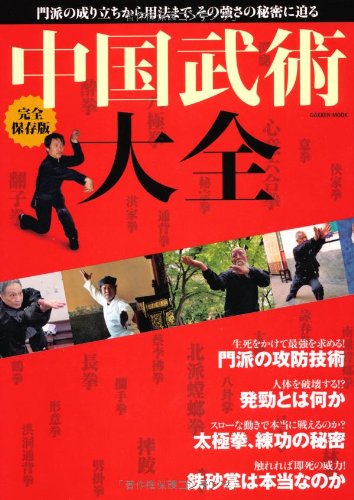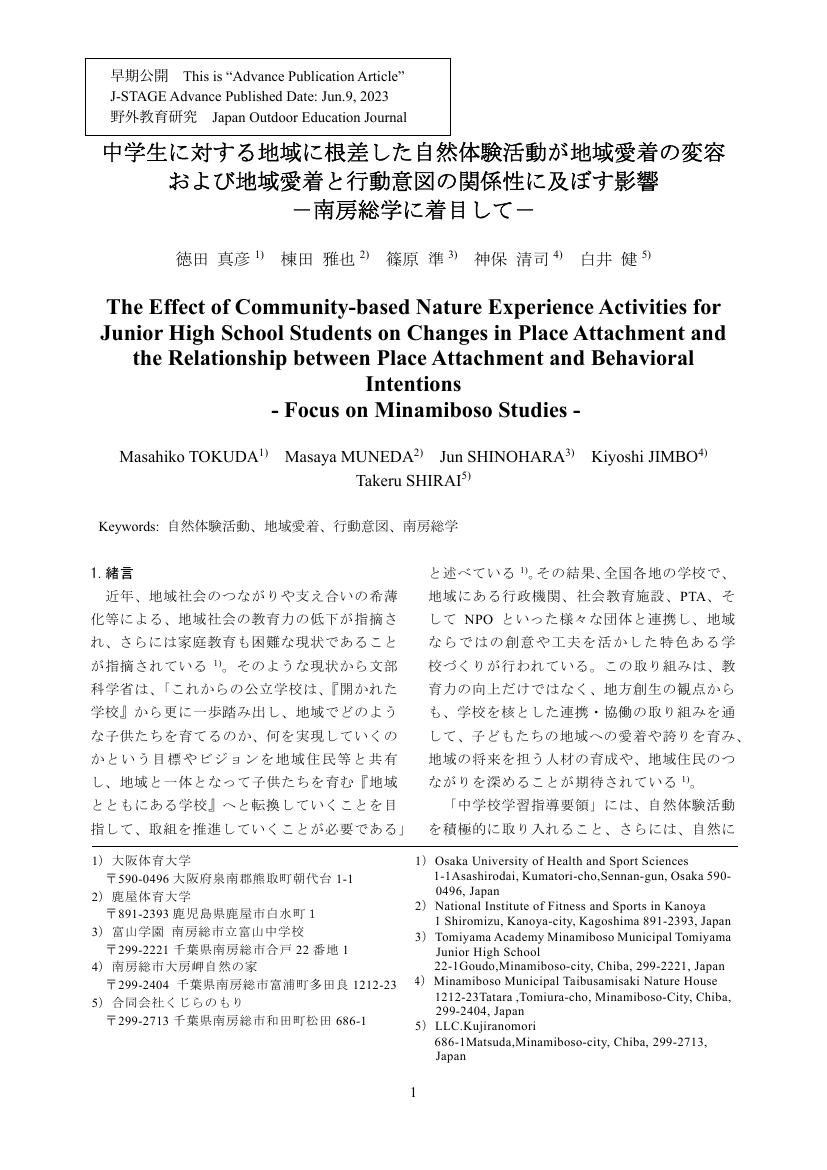1 0 0 0 武道学研究 = Research journal of Budo
- 著者
- 日本武道学会 = Japanese Academy of Budo
- 出版者
- 日本武道学会
- 巻号頁・発行日
- 1968
- 出版者
- 学研マーケティング (発売)
- 巻号頁・発行日
- 2013
- 著者
- 玉川 えり 松岡 有子 角谷 佳城 山田 正一 藤田 篤代 三家 登喜夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.247-253, 2023-04-30 (Released:2023-04-30)
- 参考文献数
- 23
近年,インスリンアナログ製剤が広く用いられているが,これら使用者の抗インスリン抗体を測定し,その有無と臨床像を検討した.初めてのインスリン治療に際し,同一製剤(ヒト:22名,アスパルト:31名,リスプロ:23名,グラルギン:23名)を1年間以上使用している2型糖尿病患者を対象に,抗インスリン抗体を放射免疫測定法(抗原:ヒトインスリン)で測定した.その結果,抗体陽性者はヒト:0 %,アスパルト:58.1 %,リスプロ:39.1 %,グラルギン:34.8 %であった.アナログ使用者で,体格指数,HbA1c,インスリン治療期間,併用糖尿病薬の有無で補正した検討で,1日インスリン投与量は,抗体陽性群で有意に(p=0.009)多かった.その増加分は陰性群の34.3 %であった.以上より,アナログ使用患者では,かなりの高頻度で抗インスリン抗体が認められ,治療に際しより多くのインスリンを必要としていた.
1 0 0 0 OA 現代美術における作為と無作為-絵画上の「線」の意味に沿って-
1 0 0 0 OA ニセ科学と科学者の社会への関わり方
- 著者
- 菊池 誠
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理 (ISSN:03698009)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.10, pp.841-844, 2012-10-10 (Released:2019-09-27)
- 参考文献数
- 4
「ニセ科学」とは「見かけは科学を装っているものの,実際には科学とは呼べないもの」のことである.社会のさまざまな場面でそのようなニセ科学に出会う.では,科学者はそういったニセ科学を放置しておいてよいのか,あるいはなんらかの行動を取るべきなのだろうか.本稿ではニセ科学問題を概観するとともに,筆者がどのようにニセ科学問題と関わってきたかを紹介する.
- 著者
- 渡邉 昌史
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会予稿集 第65回(2014) (ISSN:24241946)
- 巻号頁・発行日
- pp.330, 2014-08-25 (Released:2017-04-06)
- 著者
- Miao Fang Chunhua Liu Yuan Liu Guo Tang Chunling Li Lei Guo
- 出版者
- International Research and Cooperation Association for Bio & Socio-Sciences Advancement
- 雑誌
- BioScience Trends (ISSN:18817815)
- 巻号頁・発行日
- pp.2023.01130, (Released:2023-08-11)
- 参考文献数
- 47
- 被引用文献数
- 2
Sarcopenia is an age-associated skeletal muscle disease characterized by the progressive loss of muscle mass and function. The objective of this systematic review and meta-analysis was to evaluate the associations between sarcopenia and cardio-cerebrovascular disease (CCVD). A comprehensive search of the PubMed/Medline, Embase, Web of Science, Scopus, and Cochrane Library databases was conducted from their inception to April 1st, 2023. A total of eight cross-sectional studies involving 63,738,162 participants met the inclusion criteria. Pooled estimates of odds ratios (ORs) were calculated using random-effects models. The findings demonstrated a significant association between sarcopenia and an increased risk of CCVD (OR: 1.33, 95% CI: 1.18 - 1.50, I2 = 1%; p < 0.001). Subgroup analyses indicated that sarcopenia was associated with a 1.67-fold increase in the risk of stroke and a 1.31-fold increase in the risk of CVD. Four studies included in this review examined the association between sarcopenic obesity and the risk of CCVD, and the results revealed that sarcopenic obesity was associated with a higher risk of CCVD (OR: 1.64, 95% CI: 1.08 - 2.49, I2 = 69%; p < 0.001). Meta-regressions and sensitivity analyses consistently supported the robustness of the overall findings. In conclusion, sarcopenia and sarcopenic obesity are significantly associated with an elevated risk of developing CCVD. However, further prospective cohort studies are warranted to validate this relationship while controlling for confounding factors.
1 0 0 0 OA 日本禅宗の護法神: 大権修利菩薩について
- 著者
- デュルト H
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.686-687, 1984-03-25 (Released:2010-03-09)
1 0 0 0 OA 窒化ホウ素の酸による分解と二,三の酸化剤の影響
- 著者
- 中村 専一 東 伸行 新居 善三郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 工業化学雑誌 (ISSN:00232734)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.6, pp.903-906, 1960-06-05 (Released:2011-09-02)
- 参考文献数
- 5
安定化処理した窒化ホウ素(BN)に塩酸,硫酸,リン酸等を加え,さらに分解促進剤として過マンガン酸カリウム,重クロム酸カリウム, 過塩素酸カリウム等を加えて硬質ガラス管に封入し, 190~300℃でオートクレーブ処理してBNの分解によるアンモニア態窒素の生成条件を検討した。分解液として硫酸がよく,その最適濃度は5Mである。アンモニア態窒素を減少させない分解促進剤としては過塩素酸カリウムが適当である。分解方法はBN30mgを5M硫酸4cc,過塩素酸カリウム40mgとともにL型に曲げた硬質ガラス管に封入し(または棒状封管を水平に置き),280℃で1~2時間保持するのが適当と思われる。
- 著者
- Keisuke NISHIMOTO Tomohiko OZAKI Tomoki KIDANI Shin NAKAJIMA Yonehiro KANEMURA Hiroki YAMAZAKI Toshiyuki FUJINAKA
- 出版者
- The Japan Neurosurgical Society
- 雑誌
- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)
- 巻号頁・発行日
- pp.2022-0389, (Released:2023-06-08)
- 参考文献数
- 34
Flow diverter (FD) stenting is expected to improve cranial nerve symptoms caused by aneurysms via the theoretical reduction of the mass effect by promoting spontaneous thrombosis through the flow diversion effect. However, the factors involved in symptom improvement after treatment remain unclear. This study was performed to identify factors for symptom improvement after FD stenting and the symptom improvement rate of each impaired cranial nerve. We retrospectively evaluated 33 patients who underwent FD stenting for symptomatic internal carotid artery aneurysms at our institution from January 2016 to June 2021. Twenty-three (69.7%) patients had resolved or improved symptoms after 1 year of treatment. The optic nerve was affected in 12 patients; the oculomotor nerve, in 16; the trigeminal nerve, in 2; and the abducens nerve, in 13. There was no statistically significant difference in the symptom improvement rate of each impaired cranial nerve. The patients were classified into the improved and nonimproved groups based on their symptoms after 1 year of treatment, and the factors related to the symptoms were analyzed. The time from onset to treatment was significantly shorter in the improved group than in the nonimproved group (197.1 and 800 days, respectively; p = 0.023). There were no significant differences in age, aneurysm diameter, adjunctive coil embolization, partial thrombosis, change in mass diameter on magnetic resonance imaging, or aneurysm occlusion rate on angiography between the two groups. These results suggest that early treatment after the onset of aneurysm-induced cranial neuropathies increases the likelihood of symptom improvement.
- 著者
- 岡田 薫 草間 芳樹 小谷 英太郎 石井 健輔 宮地 秀樹 時田 祐吉 田寺 長 中込 明裕 新 博次
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.4, pp.373-378, 2008-04-15 (Released:2013-05-24)
- 参考文献数
- 10
症例は66歳,女性.既往に胆石症あり.呼吸困難を主訴に当科を受診.低酸素血症(PaO2 61mmHg),血清Dダイマー高値(10.35μg/mL),心臓超音波検査で右心室の拡大,胸部造影CTにて両側肺動脈に血栓を認め,肺血栓塞栓症と診断.ウロキナーゼ240,000単位/日,ヘパリン12,000単位/日の持続静注を開始.翌日の肺動脈造影検査にて両側肺動脈に血栓を認め,血栓溶解療法,血栓破砕,吸引術を施行し,右下肢深部静脈血栓に対して一時的下大静脈フィルターを挿入した.ヘパリン持続静注により第12病日に血小板数が11.9×104/μLに減少,Dダイマーが124.4μg/mLまで上昇し,下大静脈造影検査でフィルター遠位部が血栓により完全閉塞していた.ウロキナーゼを増量しても改善せず,ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)に伴う血栓症を疑い,第18病日にヘパリンを中止したところ,血小板数31.9×104/μL,Dダイマー1.54μg/mLに改善し,フィルター内の血栓は消失した.抗ヘパリン第4因子複合体抗体が陽性であり,血栓症を伴ったHITと診断した.ヘパリンは循環器疾患の診療において広く使われているが,重大な合供症であるHITに関してはいまだ十分に周知されていない.ヘパリンの使用中には,血小板数の推移を観察し,HITが疑われた場合,直ちに適切な対応を行うことが必要である.
1 0 0 0 OA レーザーブレイクダウン支援長距離火花放電による広域点火に関する研究
火花点火ガソリンエンジンの希薄燃焼限界を向上させる新しい広域点火法を提案した。レーザーブレイクダウンと高電圧印加を組み合わせた長距離放電点火LBALDI (Laser Breakdown Assisted Long-distance Discharge Ignition) の基礎特性明確化と有効性実証を目的としている。レーザーと高電圧印加の角度は90°付近が最も放電距離が長くなる。定容容器を用いて燃料依存性を調査しルイス数1以上の条件にて有効な点火法であることが分かった。急速圧縮装置を用いてエンジンに近い条件の高圧場においても長距離放電可能なLBALDIの有効性を実証し、目標を達成した。
1 0 0 0 富山市におけるアクセントの動態(資料)
1 0 0 0 OA 食農と環境
1 0 0 0 OA LC/MSによる豚および牛組織中のラクトパミンの分析法
- 著者
- 坂井 隆敏 人見 ともみ 菅谷 京子 甲斐 茂美 村山 三徳 米谷 民雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.5, pp.144-147, 2007-10-25 (Released:2008-02-05)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 16 15
液体クロマトグラフィー/質量分析法(LC/MS)による,豚および牛組織中のβ-作動薬ラクトパミンの簡便かつ再現性の高い分析法を開発した.筋肉および肝臓の場合は,酢酸エチルによりラクトパミンを抽出し,得られた酢酸エチル層を減圧乾固後,残留物をアセトニトリル/n-ヘキサン分配により精製した.脂肪の場合は,アセトニトリル/n-ヘキサンにより分配抽出および精製を行った.精製後に得られたアセトニトリル層を減圧乾固し,残留物をメタノールに再溶解後LC/MS測定に供した.LCにおける分離は,分析カラムとしてWakosil-II 3C18HGカラム(150×3 mm i.d.),移動相として0.05%トリフルオロ酢酸-アセトニトリル(80 : 20)を用い,流速0.4 mL/minの条件で行った.MSにおける検出は選択イオン検出(SIR)モードにて行い,エレクトロスプレーイオン化法(ESI)により生じたラクトパミンの擬分子イオン(m/z 302)を検出した.本法による筋肉(0.01 μg/g添加),脂肪(0.01 μg/g添加)および肝臓(0.04 μg/g添加) からのラクトパミンの平均回収率(n=3)は,豚サンプルにおいてそれぞれ99.7%, 99.5%および100.8%,牛サンプルにおいてそれぞれ108.3%, 97.0%および109.4%であった.相対標準偏差は0.1∼9.5%の範囲であった.また,定量下限値は0.001 μg/g (1 ng/g)であった.
- 著者
- edited and with commentaries by Robert Craft
- 出版者
- Faber
- 巻号頁・発行日
- 1982
1 0 0 0 OA Ni基単結晶超合金のラフト組織
- 著者
- 齊藤 拓馬 原田 広史 横川 忠晴 大澤 真人 川岸 京子 鈴木 進補
- 出版者
- 公益社団法人 日本金属学会
- 雑誌
- 日本金属学会誌 (ISSN:00214876)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.9, pp.157-171, 2022-09-01 (Released:2022-08-25)
- 参考文献数
- 80
Series of Ni-base single-crystal superalloys with superior thermal durability have been developed to improve thermal efficiency of gas turbine systems. Microstructural transition during creep so called “raft structure” formation enhances creep properties at lower stress and higher temperature condition. Furthermore, larger perfection degree of the raft structure contributes to better creep properties under the same creep condition. To control the perfection degree of the raft structure, magnitude of a lattice misfit and an elastic misfit between γ and γ′ phases should be controlled. In the current situation, the lattice misfit can be controlled by using alloy design program NIMS has developed. In this review, we focused on the role of the raft structure in alloy design. Observation results and predicted mechanisms about strengthening by the microstructural transition, in addition to the mechanism about microstructural transition itself during creep, were summarized and explained. Finally, under these recognitions mentioned above, our effort to establish a new alloy design approach to control the perfection degree of the raft structure by modifying the elastic misfit was introduced.
1 0 0 0 OA 戦争と階層・格差・不平等
- 著者
- 渡邊 勉
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.12, pp.12_22-12_27, 2022-12-01 (Released:2023-04-28)
- 参考文献数
- 9
アジア・太平洋戦争は、日本人を国家総動員体制のもと、等しく戦争に協力することが求められていた。しかし現実には、社会全体を巻き込む災禍や暴力においてでさえ、人々が等しく協力しているわけではないし、負担を負っているわけでもない。そうした不平等の実態を知るための一つの方法として、社会調査データの分析がある。過去の社会調査データを分析することで、アジア・太平洋戦争時の不平等の実態を、ある程度明らかにすることができる。そこで実際に分析してみてわかることは主に二つある。第一に戦争は格差を消失させるわけではないということである。戦前社会は高格差社会であった。戦時中においてもそうした格差は一部維持されていた。第二に戦争はあらたな格差をつくりだすということである。戦時中に負担を強いられた人々は、戦後も苦しい生活を強いられていた。戦争によってもたらされる負担は、戦時中のみならず、戦後も継続しており、それは特定の社会階層に偏っていたのである。