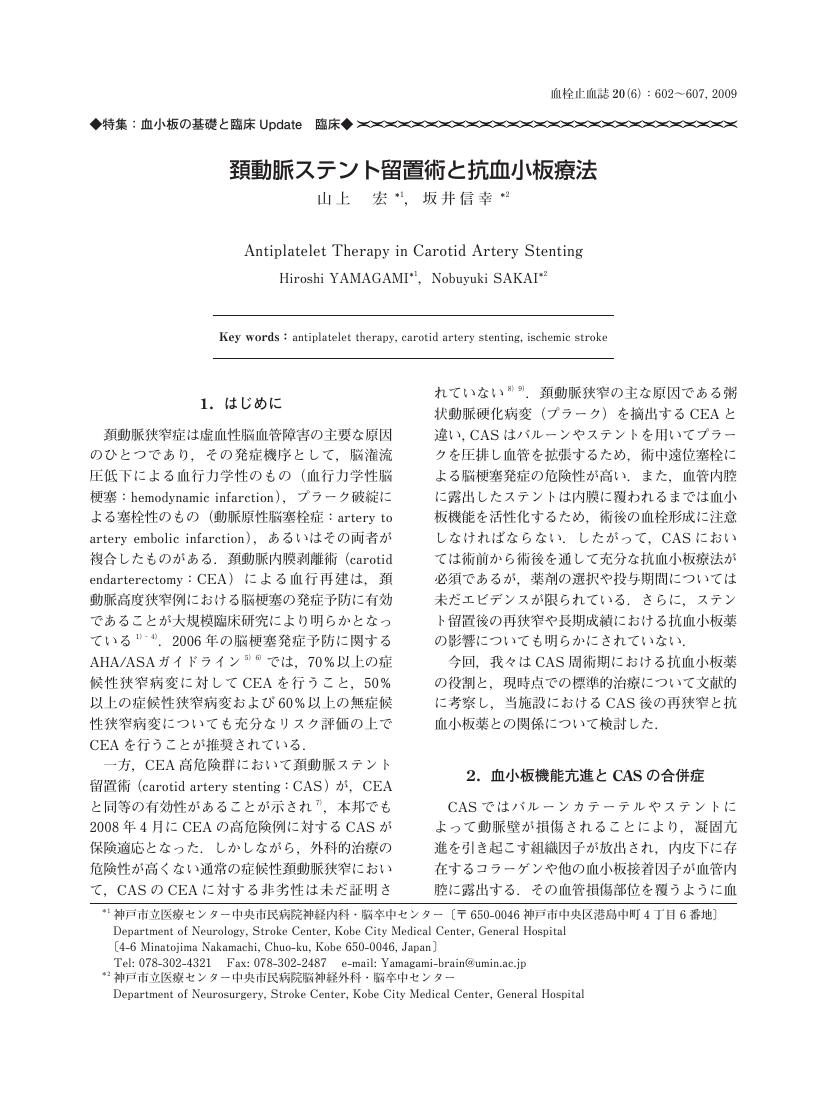1 0 0 0 OA 頚動脈ステント留置術と抗血小板療法
- 著者
- 山上 宏 坂井 信幸
- 出版者
- 一般社団法人 日本血栓止血学会
- 雑誌
- 日本血栓止血学会誌 (ISSN:09157441)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.6, pp.602-607, 2009 (Released:2010-01-05)
- 参考文献数
- 27
1 0 0 0 OA 時間差赤外線画像を用いた埋設地雷探知の方法
- 著者
- 和崎 克己 下井 信浩 滝田 好宏
- 出版者
- 一般社団法人 画像電子学会
- 雑誌
- 画像電子学会研究会講演予稿 画像電子学会第196回研究会講演予稿 (ISSN:02853957)
- 巻号頁・発行日
- pp.3, 2002 (Released:2003-05-27)
本論文は、IRカメラを使用した、遠隔からの埋設地雷及び散布地雷の探知について述べたものである。このため、時間差分のIR画像を用いた、並列画像処理による対象物検出方法について提案する。対人地雷を探知するためには努めて遠隔から探知することが望ましい。埋設されている対人地雷の場合には、埋設地雷と地中の温度差が十分あれば放射熱の違いにより探知することが可能である。地域に冷水を散布して地表面を冷却させ、赤外線カメラによって測定する. このとき、土と埋設物(地雷)の放射熱の違いと、その冷却速度の差により、時間差分画像を得る。各画像はLinuxプラットフォーム上に実装された画像処理プログラムにより、実時間かつパイプライン的に処理される。
1 0 0 0 OA 暑熱作業環境下での水分摂取量の違いが人体に及ぼす影響
- 著者
- 榎本 ヒカル 澤田 晋一 安田 彰典 岡 龍雄 東郷 史治 上野 哲 池田 耕一
- 出版者
- 独立行政法人 労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所
- 雑誌
- 労働安全衛生研究 (ISSN:18826822)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.7-13, 2011 (Released:2011-09-30)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 4 2
熱中症予防のためには水分摂取が重要であることが指摘されているが,その水分補給量の目安は明確に定められてはいない.そこで,ISO7933に採用されている暑熱暴露時の暑熱負担予測のための数値モデルであるPredicted Heat Strain(PHS)モデルに着目し,暑熱環境における水分補給量の違いが人体に与える影響を検討し,PHSモデルから算出される水分補給量の妥当性を検証した.健常な青年男性8名を被験者とし人工気象室を用いて水分摂取条件を3水準(無飲水,PHSモデルによる飲水,ACGIHガイドラインに基づく飲水),運動条件を2水準(座位,トレッドミル歩行)設定し,生理的指標として皮膚温・体内温(直腸温,耳内温),体重,指先血中ヘモグロビン濃度,心電図,血圧・脈拍数,視覚反応時間,心理的指標として温冷感に関する主観的申告,疲労に関する自覚症しらべを測定した.その結果,暑熱環境での作業時には飲水しないよりも飲水するほうが体温や心拍数が上昇しにくく,生理的暑熱負担が軽減されることが示唆された.また,PHSモデルによる体内温と体重の変化量の予測値と本研究での実測値を比較したところ,PHSモデルは作業時の水分補給の目安の一つになりうることが明らかになった.
1 0 0 0 OA 情動刺激が記憶獲得に与える影響
- 著者
- 久保 金弥 檜山 征也 匂坂 恵里 水野 潤造
- 出版者
- 日本教育医学会
- 雑誌
- 教育医学 (ISSN:02850990)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.4, pp.311-322, 2012 (Released:2021-10-08)
- 参考文献数
- 52
Stress affects memory acquisition, but the direction of the effect varies. Some studies report that stress enhances memory, and others report that stress impairs memory. The relation between the effect of pleasant stimuli on neural activity in the hippocampus and memory acquisition is unclear. The amygdala has a primary role in processing emotion and mediates affectively-influenced memory. The hippocampus is critically involved in memory. We evaluated the effect of pleasant and unpleasant stimuli on neuronal activity in these regions during picture-encoding using functional magnetic resonance imaging and memory acquisition. To test whether pleasant and unpleasant stimuli affect memory acquisition, a recall test was administered 20 minutes after encoding. Fifteen subjects (8 men; mean age 37.9±12.9 years [range 20-61]) participated. Pleasant and unpleasant stimuli increased blood oxygenation level-dependent (BOLD) signals in the amygdala. The pleasant stimulus enhanced neuronal activity in the hippocampus (i.e., increased BOLD signals) and increased memory acquisition. The unpleasant stimulus decreased both hippocampal neural activity and memory acquisition. Visual Analogue Scale scores for the pleasant and unpleasant stimuli were 8.7±0.5 and 9.0±0.6, respectively. Thus, pleasant and unpleasant stimuli might influence memory acquisition by increasing or reducing hippocampal activity during picture-encoding.
1 0 0 0 OA ファーストコンタクトは近い
- 著者
- Takashi Kitahara Nao Koyama Junichi Matsuda Yuko Aoyama Yoichi Hirakata Shimeru Kamihira Shigeru Kohno Mikiro Nakashima Hitoshi Sasaki
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.9, pp.1321-1326, 2004 (Released:2004-09-01)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 78 92
The objective of this study was to investigate the antimicrobial activities of saturated fatty acids and fatty amines against methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). The antimicrobial activity of saturated fatty acids and fatty amines was determined by oxygen meters with multi-channels and disposable oxygen electrode sensors (DOX-96). Lauric acid, the most effective among the saturated fatty acids, showed antimicrobial activity at 400 μg/ml against methicillin-susceptible Staphylococcus aureus (MSSA) and MRSA. The minimal inhibitory concentration (MIC) of fatty amines depended on each hydrophobic chain length. The MIC of myristylamine was 1.56 μg/ml; most effective of the fatty amines. In time-kill curves, lauric acid and myristylamine produced a bactericidal effect and a bacteriostatic effect at 4-fold the MIC, respectively. The antimicrobial activities of lauric acid and myristylamine were decreased by human plasma. Cytotoxicity of 3 saturated fatty acids and 3 fatty amines was examined in cultured endothelial cells. Although cytotoxicity of fatty amines was severer than that of saturated fatty acids, myristylamine showed the highest value of apparent therapeutic index among them. DOX-96 was useful for screening antimicrobial substances, especially in the case of insoluble substances. We found that myristylamine showed anti-MRSA activity comparable to that of vancomycin and teicoplanin.
1 0 0 0 OA 植栽初期におけるクマザサとオカメザサの地下茎の伸長・発達
- 著者
- 柴田 昌三
- 出版者
- 社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- 造園雑誌 (ISSN:03877248)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.5, pp.84-89, 1986-03-31 (Released:2011-07-19)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 3 2
植栽された竹笹類の管理方法を考えるために、クマザサとオカメザサを用いて地下茎の季節的な動きを調査した。クマザサは8月の伸長が非常に悪く、6月と9月に盛んな伸長を示した。9月の旺盛な伸長がクマザサにとって非常に重要であることがわかった。オカメザサの地下茎は7月から11月の5ヶ月間しか伸長しない。夏から初秋にかけて活発な伸長を行い、特に7月後半から8月前半の旺盛な伸長が重要であることが示された。
1 0 0 0 OA 災害時の糖尿病セルフケア阻害尺度の開発
- 著者
- 大山 真貴子 岩永 誠
- 出版者
- 日本健康医学会
- 雑誌
- 日本健康医学会雑誌 (ISSN:13430025)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.4, pp.452-457, 2023-01-30 (Released:2023-05-01)
- 参考文献数
- 11
災害による急激な生活環境の変化は,糖尿病患者のセルフケアを阻害する。本研究では,糖尿病患者が被災によって受けるセルフケア阻害に関する心理的な影響を測定する尺度の開発を目的とした。対象者は熊本大地震を経験した糖尿病患者195名(男性143名,女性52名;63.34±12.01歳,HbA1c値=7.09±0.93%)であった。災害時の糖尿病セルフケア阻害尺度の項目は,被災した糖尿病患者へのインタビューを基に作成した。項目の構成は,抽出された4カテゴリー(「炭水化物中心の食事」,「糖尿病薬の不携帯」,「セルフケアの不足」,「高血糖状態」)からの10項目と将来における病気悪化のリスクに関する2項目を追加した全12項目とした。因子分析の結果,セルフケアの諦め,食事の悪化,将来における病気悪化の懸念の3因子が抽出された。各因子のα係数は0.806以上であり,高い内的一貫性を示すことが確認できた。
1 0 0 0 OA 電氣工業の標準化
- 著者
- 原田 久 小山 正徳
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.748, pp.73-81, 1951 (Released:2008-11-20)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA 質感知覚の心理学
- 著者
- 本吉 勇
- 出版者
- 心理学評論刊行会
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.235-249, 2008 (Released:2019-04-12)
1 0 0 0 OA モンゴル国アルシャンツ・ブルト地区の夏営地における母子羊の音声構造
- 著者
- 苗川 博史
- 出版者
- 日本緬羊研究会
- 雑誌
- 日本緬羊研究会誌 (ISSN:03891305)
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, no.45, pp.8-12, 2008-12-20 (Released:2011-04-22)
- 参考文献数
- 10
モンゴル国アルシャンツ・ブルト地区の夏営地における母子羊の音声構造について解析した。母羊においては, 発声タイプ/ηnaeee/の発声時間は/ηηηη/より0.7秒長く, /ηaee/より0.5秒長く, その差は有意であった (P<0.05) 。また発声タイプ/ηηηη/の基本周波数は, /ηnaeee/より120ヘルツ高く, /ηaee/は, /ηnaeee/より18ヘルツ高く, その差は有意であった (P<0.05) 。さらに, 発声タイプ/ηηηη/の音圧は, /ηnaeee/より6デシベル高く, /ηnaeee/は/ηaee/のそれよりも1デシベル高く, その差は有意であった (P<0.05) 。子羊においては, 発声タイプ/ηneeee/の発声時間は, /ηeee/より0.5秒長く, /ηηηη/より0.4秒長く, その差は有意であった (P<0.05) 。また発声タイプ/ηηηη/の基本周波数は, /ηeee/よりも170ヘルツ高く, その差は有意であった (P<0.05) 。子羊における発声時間の発声末型には, 発声タイプ間に有意差があった (χ2=10.8, P<0.05) 。母子羊は音声表記によって発声時間, 基本周波数, 音圧が異なり, 発声状況や行動により音声を使い分けていることが示唆された。
1 0 0 0 OA 臓器移植・贈与理論・自己自身にとって他者化する自己(<特集>先端技術と/の人類学)
- 著者
- 出口 顯
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:24240508)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.439-459, 2002-03-30 (Released:2018-03-27)
臓器移植は生命の贈り物といわれるが、いかなる意味で「贈り物」なのかを考えたい。少なくともそれはモースが考察の対象とした「アルカイック」な贈与とは異なることがアメリカでの臓器移植を積年研究してきたフォックスとスウェイジー批判で示される。さらにこの問題を考えるとき、人類学で培われた贈与理論がどの程度有効なのかを、ワイナーとゴドリエからマリリン・ストラザーンへと、比較的新しい理論からそれ以前の理論へいわば脱構築しながら検討する。ゴドリエの理論は「贈与」されるのが生命それ自体であり、臓器はその表象であることを明らかにするのに有効であるが、西洋近代の人格概念を前提にしているため、ドナーと自らの二つの人格あるいは生命が併存する共同体として自己を受けとめるレシピアントの体験を据えきれない欠点がある。むしろ、ストラザーンのメラネシアの人格観のモデルが、そうした体験をうまく説明できるものとなっている。しかしストラザーンのモデルでは、柄谷行人の言う「他者」が不在であり、また柄谷にしてもストラザーンにしても「自己」が「他者」化する可能性は全く考慮されていない。自己自身にとって他者となる自己という主題を考察してきたのは、さらに時間を遡るが、レヴィ=ストロースである。自己の内部に出現する他者や侵入者というその視点から、臓器移植は概して外部からの侵入者の物語であることがわかるが、それを内部の侵入者としてとらえる余地はないか最後に検討を試みてみる。
- 著者
- 平原 幸輝
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.1-6, 2021-04-25 (Released:2022-04-25)
- 参考文献数
- 14
現代の日本社会においては空き家問題が深刻化しており、多くの自治体がその状況を把握しようと試みている。 しかし、空き家問題の状況を把握する際に用いられる「住宅・土地統計調査」には、全市区町村のデータが含まれているわけではない。 本研究では、全国の市区町村の空き家率を網羅することで、空き家問題の状況を把握することを試みた。 その結果、地域の人口構成や世帯構成は空き家率の高さに関連しており、老年人口比率や単身世帯比率は空き家率に影響していることがわかった。 また、空き家率を社会地図化した結果、山間部において空き家問題が深刻化していることがわかった。
1 0 0 0 OA 双子をもつ父親の体験
- 著者
- 中澤 恵美里 佐々木 睦子 小松 千佳 石上 悦子
- 出版者
- 国立大学法人 香川大学医学部看護学科
- 雑誌
- 香川大学看護学雑誌 (ISSN:13498673)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.37-49, 2022-03-30 (Released:2022-04-05)
- 参考文献数
- 31
目的双子をもつ父親が,妊娠期から現在に至るまでどのように感じ考えて双子育児をしていたのか,その体験を明らかにすることである.方法A県内で双子の父親10名を対象に,半構造化面接法を行い,質的帰納的記述的に内容の分析をした.香川大学医学部倫理委員会の承認後に実施した.結果分析結果より,19サブカテゴリー,6カテゴリーが得られた.双子をもつ父親は妻の妊娠が分かった時,夫婦ともに,【双胎妊娠の喜びと育児の不安】を抱いていた.そして,双子育児が始まると,【親のサポートと双子育児の情報で安心】と感じながらも,手に負えない育児をしている妻をみて,あらためて,【大変な双子育児をしている妻へのねぎらい】の大切さに気付き,【協力してやるしかない双子育児】を覚悟した.また,双子をもつ父親は,【仕事と育児の葛藤】を抱きながらも次第に,【双子の一人一人を大事にした子育てをしたい】という父親役割を認識する体験をしていた.考察双子の父親は,想像していた以上に大変な双子育児を妻とともにすることで,妻の心身への関心と配慮の重要性を実感し,妻へのねぎらいの大切さに気付き,協力してやるしかない双子育児の覚悟を決めていたと考える.また,ワークライフバランスを模索しつつ,父親なりの双子一人一人の個性を大事にする理想の家族像への期待は,双子をもつ父親の価値観の変容と双子の父親の役割認識につながっていると考える.結論双子の父親は妻とともに双子育児をすることで,ワークライフバランスを模索しつつ,父親なりに双子の個性を大事にする理想の家族像を描いていた.双子をもつ父親の体験は,価値観の変容と双子の父親の役割認識に影響していた.
- 著者
- Haruko Yoshie Yoichi Yusa
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF APPLIED ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY
- 雑誌
- Applied Entomology and Zoology (ISSN:00036862)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.4, pp.475-482, 2008-11-25 (Released:2008-11-30)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 21 23
We studied the predatory potential of the turtle Chinemys reevesii on the apple snail Pomacea canaliculata using two series of experiments. First, we investigated the relationship between turtle body size and the maximum size of snails consumed over a period of 3 days within 0.37 m2 containers. The maximum snail size consumed was positively related with turtle size. Secondly, we investigated the predation of snails by turtles over a period of 8 weeks. We released 200 snails (10–30 mm shell height) and an adult turtle (155–183 mm carapace length) into each of two 2.08 m2 plots with soil and rice plants. Subsequently, snail density was monitored every week and 200 snails were added to low density plots up to twice a week. Two control plots with the same initial density of snails but without turtles were also monitored. The density and survival rate of snails were lower in plots with a turtle than in control plots. We estimated that a single turtle consumed >2,000 snails in 8 weeks. In addition, the biomass of duckweed (given as food for snails) was greater in turtle plots than in control plots, suggesting that the presence of turtles had an indirect effect on weed.
1 0 0 0 OA 名古屋離宮の誕生
- 著者
- 石川 寛
- 出版者
- 愛知県
- 雑誌
- 愛知県史研究 (ISSN:18833799)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.31-46, 2008 (Released:2020-02-27)
- 著者
- 中島 裕也 川端 香 杉本 志保理 宮原 智子 小林 康孝
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.6, pp.793-803, 2021-12-15 (Released:2021-12-15)
- 参考文献数
- 9
高次脳機能障害に対する介入として,Self-awareness(自己の気づき)に焦点をあてることは重要である.今回,高次脳機能障害者の社会復帰支援に際して,日本語版SRSIを活用した.その評価結果から,Self-awarenessの程度を把握して介入指針を決定した.Self-awarenessの程度に合わせた有効な補填手段と,実際に用いる補填手段との整合性が合うことで,各ストラテジーが定着し,社会復帰へつながる一因になると考えられた.日本語版SRSIは,Self-awarenessの程度とその変化に対する評価や,高次脳機能障害者支援における的確な介入指針を見出す一助になる可能性が示唆された.
1 0 0 0 OA 感情の経験と知覚における言語の役割 ―理論的整理と発達的検討―
- 著者
- 池田 慎之介
- 出版者
- 心理学評論刊行会
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.4, pp.423-444, 2018 (Released:2020-03-15)
- 参考文献数
- 179
- 被引用文献数
- 2
In this paper, the role of language in emotion experience and emotion perception was investigated by reviewing the theory and evidence. By referring to the model of emergence and perception of emotion, the developmental stage at which language would influence these processes was indicated. The developmental perspective, which has rarely been focused on, was investigated by reviewing studies of infants and children. For emotion experience, our findings suggested that the inner conditions can be represented in two dimensions. For emotion perception, crude information such as information associated with “positive” or “negative” can be decoded without language. However, categorical recognition of emotion in experience and perception may require language.
- 著者
- 柴田 昌三
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.51-62, 2010-03-31 (Released:2017-04-20)
- 参考文献数
- 55
- 被引用文献数
- 1
タケ類の開花は開花周期が長いため、周期性があるとされながらも、それを予測することは困難である。しかし、今回、バングラデシュから北東インド、ミャンマーに至る地域に自生するMelocanna bacciferaに関して、精度が異なる過去の開花情報を詳細に検討し、少なくとも現地で情報収集を行ったインド・ミゾラム州において、本種が48年周期で大面積に一斉開花枯死を繰り返している可能性が高いことを突き止めた。予測に基づいて調査地を設定し、調査を開始したところ、2006〜2007年に、予測どおりの開花が認められた。調査地では、一斉開花の前後年に、少数の走り咲き稈と咲き遅れ稈の開花があり、通算3年にわたる開花が認められた。また、広域の調査によってほぼ5年間にわたって大面積一斉開花地が移動していくことも確認された。過去の記録では、さまざまな規模でみられる開花がすべて同等に扱われているが、このような記載が種の正確な開花周期の推定を困難にしている可能性が示唆され、タケ類の開花周期の特定においては可能な限り予測に基づいた生態学的調査を行う必要性が示された。