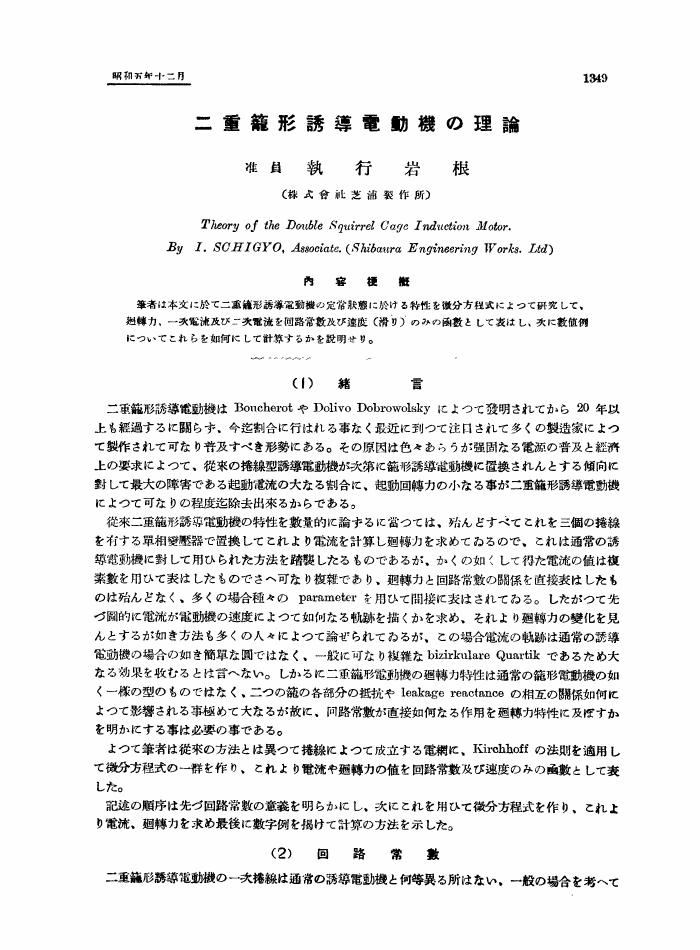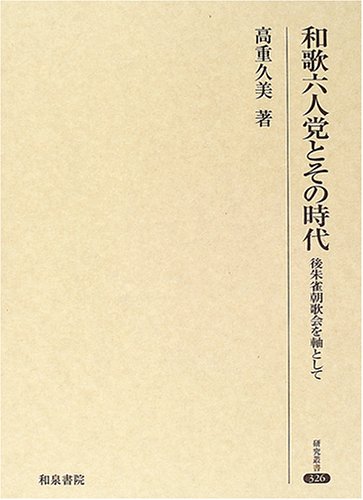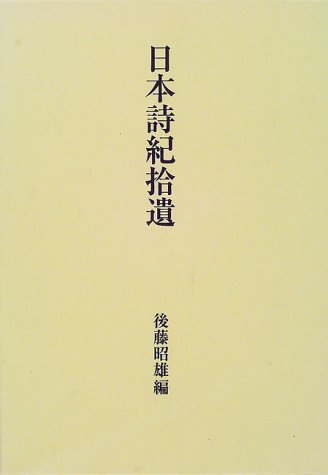1 0 0 0 OA Alan Boothの徒歩日本縦断記 : The Roads to Sataについて 1
- 著者
- 関田 敬一
- 出版者
- 創価大学英文学会
- 雑誌
- 英語英文学研究 (ISSN:03882519)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.115-129, 2013-03-01
- 著者
- 中村 洋樹
- 出版者
- 全国社会科教育学会
- 雑誌
- 社会科研究 (ISSN:0289856X)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, pp.1-12, 2017-11-30 (Released:2019-03-28)
本稿の目的は,中等歴史教育において真正の学習を具現化するために,学習者は何を論述すべきか,またそれを教授するためのカリキュラムや単元をいかに構成すべきかを究明することにある。近年の歴史学習論研究においては,真正の学習を具現化するために,学習者による史料読解に焦点が当てられている。しかし真正の学習の趣旨を踏まえるならば,学習者が自らの歴史解釈を表現する論述により焦点を当てなければならない。そこで本稿では,中等歴史教育における論述の教授・学習に関する研究を進めている米国の社会科教育学者C. モンテ・サノの研究とモンテ・サノが中心となって開発した第8学年向けの合衆国史用教材集“Reading,Thinking,and Writing About History”を考察した。 その結果,真正の学習において学習者が論述すべきは歴史的議論であることを明らかにした。その上で,それを教授するためのカリキュラム構成の原理は,認知的徒弟制に基づき,①カリキュラムの前半において歴史的議論の論述方法を教授すること,②カリキュラムの後半において繰り返し自立的に歴史的議論を論述させること,から成り,単元構成の原理は,①歴史的議論を論述するための学習経験として史料読解を位置付けること,②歴史的文脈や同時代の人々の価値観・考え方を吟味した上で自らの議論を構成する過程を組織すること,③自立的に歴史的議論を論述するための学習経験として他者との対話を位置付けること,から成ることを明らかにした。
1 0 0 0 IR 中間組織の時代 : 社会媒介機能の「分断」から「節合」へ
- 著者
- 工藤 求
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本臨床歯周病学会
- 雑誌
- 日本臨床歯周病学会会誌 (ISSN:13454919)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.64-70, 2022-06-30 (Released:2023-05-25)
1 0 0 0 OA 紙幣用紙の最近の動向
- 著者
- 植村 峻
- 出版者
- 紙パルプ技術協会
- 雑誌
- 紙パ技協誌 (ISSN:0022815X)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.6, pp.700, 2010 (Released:2011-08-02)
1 0 0 0 OA 上咽頭擦過療法(EAT)自律神経反射の心拍変動解析
- 著者
- 伊藤 宏文
- 出版者
- Japan Society of Neurovegetative Research
- 雑誌
- 自律神経 (ISSN:02889250)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.3, pp.320-326, 2022 (Released:2022-11-03)
- 参考文献数
- 24
慢性上咽頭炎の治療法の1つに上咽頭擦過療法(EAT)がある.本研究はEATが自律神経機能に及ぼす影響を解明することを目的として,慢性上咽頭炎症例27名の心電図記録について心拍変動解析を行った.EATを安静時,鼻腔内診察時,経鼻的擦過時,経口的擦過時の4つのイベントに分類した.4つのイベント毎にHR,CVRR,ccv HF,L/Hの4項目を測定して統計的検討を行なった.結果,経鼻的擦過時にはHRの減少とccv HFの増加を認めた.経口的擦過時にはHR,CVRRの増加を認めた.EATは心拍変動に影響を及ぼし,経鼻的擦過時には副交感神経を刺激し,経口的擦過時には交感神経と副交感神経の両方を刺激して咽頭反射を誘発していると考えられた.EATは興奮性と抑制性の相反性刺激により自律神経機能を賦活化すると考えられた.
1 0 0 0 OA 二重籠形誘導電動機の理論
- 著者
- 執行 岩根
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.509, pp.1349-1360, 1930 (Released:2008-11-20)
- 参考文献数
- 14
- 著者
- Tohru OZAWA Akihiro SAITOW Hidemichi HORI
- 出版者
- Japan Association of Mineralogical Sciences
- 雑誌
- Mineralogical Journal (ISSN:05442540)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.4, pp.179-187, 1998 (Released:2007-03-31)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1 1
Giessenite was reported as an acicular crystal that shared a close association with Sb-bearing cosalite from the Otome mine, Yamanashi Prefecture (Ozawa and Hori, 1982). Recent criteria classify it as izoklakeite.The Otome izoklakeite, which is orthorhombic (Pnnm or Pnn2 from its orthogonal lattice and systematic extinction, in agreement with previous reports), has unit-cell dimensions of a 34.067, b 38.085, c 4.056Å. In addition, diffuse reflections which double the periodicity of 4.056Å along the c-axis are observed, also in agreement with the report on Vena izoklakeite (Zakrzewski and Makovicky, 1986).An electron microprobe analysis gives Cu 0.8, Fe 0.3, Ag 1.1, Pb 46.5, Bi 27.2, Sb 7.3, S 16.2, total 99.4wt.%, yielding the empirical formula (Cu2.7Fe1.2)3.9Ag2.2Pb48.7(Bi28.2Sb13.0)41.2S109.7, assuming the total cation=96 in a unit cell. It has a Sb/(Sb+Bi) value of 0.316, and is the most Bi-rich of the known izoklakeites.
1 0 0 0 OA 病変の自然退縮を認めた臨床的に中枢神経ゴム腫が想定された1例
- 著者
- 野原 聡平 由比 友顕
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.8, pp.552-557, 2021 (Released:2021-08-30)
- 参考文献数
- 13
症例は46歳男性.4ヶ月前から頭痛がみられていた.回転性めまい,嘔気が出現し当院へ救急搬送となった.頭部MRI造影T1強調画像で右中小脳脚と左前頭葉にリング状増強効果を呈する結節を脳表近くで認め,その周囲にFLAIR画像で高信号域を認めた.血液・髄液検査結果より神経梅毒と診断し画像所見から中枢神経ゴム腫と考えられた.HIV検査は陰性であった.経過観察中,治療前に施行したMRIで病変の自然退縮を認めた.ペニシリンGを14日間投与した後に病変は完全に消失した.その後再燃なく経過している.中枢神経ゴム腫の画像所見にはいくつかの特徴が知られているが,本症例では病変の自然退縮という珍しい所見がみられた.
1 0 0 0 OA 辺縁系脳炎として突然発症した神経梅毒の1例
- 著者
- 明石(長谷川) 愛子 高橋 義秋 森本 みずき 横田 恭子 森本 展年
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.15-20, 2023 (Released:2023-01-28)
- 参考文献数
- 23
症例は52歳男性.突然の異常行動と意識障害で救急搬送された.搬送直後から全身痙攣をきたし,ミダゾラムにて痙攣は停止するも健忘症状が遷延した.髄膜刺激徴候を認め,臨床経過と合わせ辺縁系脳炎と考えた.血清・髄液梅毒反応陽性の結果より脳炎の原因を神経梅毒と判断し,ペニシリンGで治療を開始した.頭部MRIでは両側側頭葉内側に左側優位のT2/FLAIR高信号病変を認め,ヘルペス脳炎の可能性も考慮し,髄液HSV-DNA陰性が判明するまでアシクロビルを併用し,ステロイドパルス療法も行った.経過とともに症状は改善し職場復帰した.辺縁系脳炎で発症する神経梅毒は稀だが治療方針を考える上で極めて重要な疾患である.
1 0 0 0 OA 磁性細菌—磁気超微粒子の生成機構とその応用—
- 著者
- 松永 是
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理 (ISSN:03698009)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.10, pp.1138-1141, 1998-10-10 (Released:2009-02-05)
- 参考文献数
- 9
磁性細菌はマグネトソームとよばれる50~100nm程度の粒径をもつチェーン状の磁性粒子を菌体内に生成,保持している.これらの磁性粒子は高い分散性,安定な有機薄膜の存在,単磁区微粒子といった特性からその工学的応用が期待されている.最近,遺伝子組み換えによりこの磁気超微粒子表面にタンパクを発現し,タンパク付き磁気超微粒子を作ることが可能になりその応用範囲は大きく広がった.
1 0 0 0 和歌六人党とその時代 : 後朱雀朝歌会を軸として
1 0 0 0 OA 明清時代の牙人・牙行研究
- 著者
- 銭 晟
- 出版者
- Tohoku University
- 巻号頁・発行日
- 2020-03-25
課程
1 0 0 0 OA 電子ビーム露光技術の現状と展望
- 著者
- 松井 真二 落合 幸徳 山下 浩
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理 (ISSN:03698009)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.4, pp.411-417, 2001-04-10 (Released:2009-02-05)
- 参考文献数
- 49
半導体集積回路に代表されるデバイス微細加工のキーテクノロジーである電子ビーム露光技術の最近の動向と将来展望について述べる.パターン描画機能をもっ電子ビーム露光技術は,現在の量産用リソグラフィー技術である光露光の高精度マスク描画,少量多品種システムLSI製造に不可欠の技術である.近年,波長制限によって,光露光技術が解像度限界に達しつつあり, 70nm 以降の次世代量産技術として,分割転写方式,マルチビーム方式などの高スループット電子ビーム露光技術が注目されており,それらの最新動向について解説する.
1 0 0 0 OA 耳鳴の自覚的表現に関する再検討
- 著者
- 大内 利昭 岡田 行弘 小川 郁 藤井 みゆき 神崎 仁
- 出版者
- Japan Audiological Society
- 雑誌
- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.48-55, 1990-02-28 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 14
耳鳴患者自身の自発的擬声語と, 耳鳴周波数及び耳鳴同定音の純音・雑音性との関係を検討し, 標準耳鳴検査法1984の30の擬声語のそれとを比較して以下の結果を得た。 1) 使用された41の自発的擬声語のうち, 標準耳鳴検査法1984に提示されている擬声語は17 (41.5%) のみであった。 2) 使用頻度2%以上の12擬声語のうち標準耳鳴検査法1984に提示されている擬声語は6 (50.0%) のみであった。 3) 17擬声語のうち, 耳鳴周波数及び耳鳴同定音の純音・雑音性がともに標準耳鳴検査法1984に提示されているそれと完全に一致したのは6擬声語 (35.3%) のみであった。 4) 各耳鳴周波数における最多使用擬声語につき検討すると, 使用頻度は高いが, 耳鳴周波数特異性及び純音・雑音性特異性の低い擬声語が存在することが判明した。 5) 耳鳴周波数及び耳鳴の音色 (純音・雑音性) の客観的指標として提示すべき擬声語については再検討すべきであると考えられた。
1 0 0 0 OA 標準耳鳴検査法1993を用いた耳鳴患者の評価について
- 著者
- 山川 卓也 芳川 洋 飯村 尚子 都丸 香織 市川 銀一郎
- 出版者
- Japan Audiological Society
- 雑誌
- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.4, pp.261-270, 1998-08-31 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 14
耳鳴は患者の心理的な要素が強く, 客観的な評価を行うことは難しい。このため耳鳴研究会により, 耳鳴に関する患者の訴えと医師側にとって重要な情報が十分客観的に得られる事を目的として, 標準耳鳴検査法1993が作成され, 臨床で利用されている。今回我々は, この耳鳴検査法と臨床的な利点, 問題点につき検討を加えた。対象は耳鳴を主訴として当科を受診した症例で男性: 55名, 女性: 52名の107名を対象として, まず標準純音聴力検査から聴力型 (無難聴型・高音漸傾型・高音急墜型・低音障害型・水平型・山型・Dip型・聾型・分類不能型) に分類した上で, 臨床的な有用性について検討した。結果として, 本検査法により患者の耳鳴をかなり的確に, かつ客観的に捉えることが可能であった。聴力型別に分けて検討することで, 耳鳴の特徴が捉えやすくなり, 耳鳴を医師がより正確に認識するのに役立ち, 本検査法の有用性を再確認した。