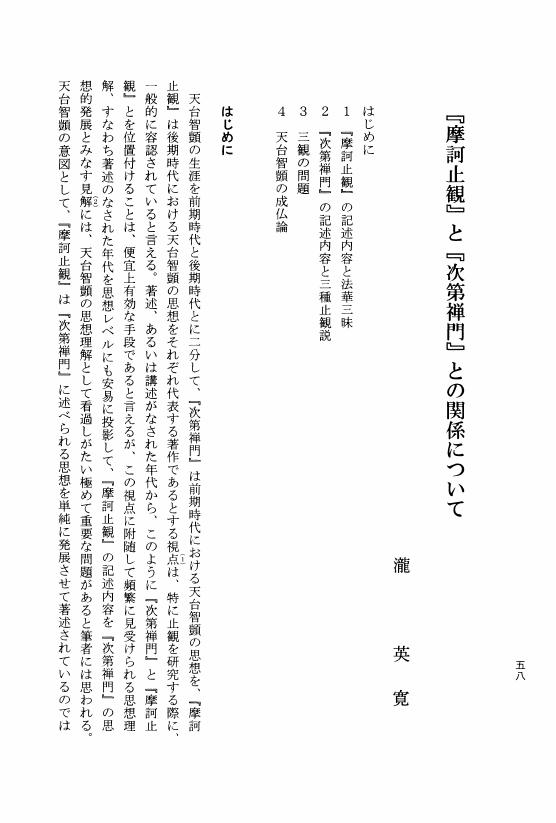1 0 0 0 OA セグロアシナガバチの観察 巣の創設から全個体の離巣まで
- 著者
- 井上 治彦
- 出版者
- 伊丹市昆虫館
- 雑誌
- 伊丹市昆虫館研究報告 (ISSN:21877076)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.19-24, 2020-03-31 (Released:2020-05-06)
1 0 0 0 OA 「生き物供養」と「何でも供養」の連関性を求めて―日本と台湾の比較から―
- 著者
- 相田 満
- 雑誌
- じんもんこん2018論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2018, pp.27-32, 2018-11-24
生き物供養・何でも供養とでもいうべき,人間以外の生物や物品を祀り,供養する,多様な信仰遺物 が,日本国内の随所に遍在する.その総数は不明だが,現在の所,2,600 件を超える遺物を調査した段階 にある.そうした中で,日本の統治下にあった台湾は,遺跡の悉皆調査に恵まれており,日本の供養の在 り方と比較をするのに格好の調査対象となっている.そこで,本論では,その特性に着目した分析を試 みることによって,見えてきたことを中心に分析と考察を試みる.
1 0 0 0 OA 第二次世界大戦期東ガリツィアにおけるユダヤ人・ウクライナ人関係の解明
- 著者
- 野村 真理 Nomura Mari
- 出版者
- 金沢大学経済学経営学系
- 雑誌
- 平成20(2008)年度 科学研究費補助金 基盤研究(C) 研究成果報告書 = 2008 Fiscal Year Final Research Report
- 巻号頁・発行日
- vol.2006-2008, pp.4p., 2009-04-02
ナチ・ドイツによるユダヤ人迫害(ホロコースト)は、一般によく知られているが、その最大の犠牲者は東ヨーロッパのユダヤ人であり、また、そのさい東ヨーロッパ現地の住民が迫害に加担した事実は、ほとんど認識されていない。本研究の成果である著書『ガリツィアのユダヤ人--ポーランド人とウクライナ人のはざまで』(人文書院、2008年)は、現在ではウクライナに属する東ガリツィアを例に、文献資料の他、回想録や同時代の日記史料を用い、現地住民とホロコーストとのかかわりを人びとの心性にまで立ち入って解明した日本ではほとんど唯一の著作である。
1 0 0 0 OA 白金触媒によるC6飽和炭化水素の脱水素反応
- 著者
- 中村 宗和 赤沼 耕一 大塚 啓一 鈴木 羚至
- 出版者
- The Japan Petroleum Institute
- 雑誌
- 石油学会誌 (ISSN:05824664)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.7, pp.572-577, 1973-07-01 (Released:2009-01-30)
- 参考文献数
- 15
The dehydrogenation of 2, 3-dimethylbutane, 3-methylpentane and methylcyclopentane over Pt-C catalyst was studied at low conversion levels and temperatures ranging from 400 to 480°C, under the hydrogen atmospheric pressure.The dehydrogenated products included all possible alkenes and cycloalkenes possessing the same skeletal structures as raw materials and were approximately in thermodynamic equilibrium at conversions as low as 8%. The compositions of these product mixtures observed at 460°C were: 43% 2, 3-dimethyl-1-butene and 57% 2, 3-dimethyl-2-butene; 9% 3-methyl-1-pentene, 11% 2-ethyl-1-butene, 31% 3-methyl-cis-2-pentene and 49% 3-methyl-trans-2-pentene; 68% 1-methylcyclopentene, 20% 3-methylcyclopentene, 10% 4-methylcyclopentene and 2% methylenecyclopentane in each skeletal hydrocarbons, respectively.At the initial step of the reaction, however, it was shown that 2, 3-dimethyl-1-butene, 3-methyl-1-pentene and 3-methylcyclopentene were formed beyond their thermodynamic equilibrium compositions, respectively.It was found that the rate of the dehydrogenation was influenced by the ratio of hydrogen to hydrocarbon and that in the absence of hydrogen the reaction did not proceed at all. The reaction rate increased with the molar ratios, being constant at the molar ratio of one and above.These results suggested that the hydrogen played an important role on the dehydrogenation mechanism over Pt catalyst used in the present study.
- 著者
- 長谷川 晃
- 出版者
- 北海道大学法学部
- 雑誌
- 北大法学論集 (ISSN:03855953)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.137-164, 1989-11-21
1 0 0 0 OA 底 泥 に 残 さ れ た 鉛 汚染 の 歴 史
- 著者
- 平尾 良光
- 出版者
- 日本海洋学会 沿岸海洋研究会
- 雑誌
- 沿岸海洋研究 (ISSN:13422758)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.136-145, 1988 (Released:2020-02-12)
1 0 0 0 OA 女子審判員の育成と強化について
- 著者
- 山岸 佐知子
- 出版者
- Japanese Society of Science and Football
- 雑誌
- フットボールの科学 (ISSN:21873585)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.15-17, 2022-04-20 (Released:2023-02-28)
1 0 0 0 OA 「安全神話」「安全・安心」とリスク時論 コミュニケーションを考える
- 著者
- 大西 有三
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, pp.2-3, 2012 (Released:2019-09-06)
1 0 0 0 OA 第六十四回智山教学大会講演 両部神道の形成―鎌倉時代を中心に
- 著者
- 伊藤 聡
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, pp.7-66, 2022 (Released:2023-02-04)
1 0 0 0 OA RBCCエンジンのスクラムジェットモードでの流入空気とロケット排気との混合評価について
- 著者
- 高木 翔平 富岡 定毅 工藤 賢司 村上 淳郎 升谷 五郎 Takagi Shohei Tomioka Sadatake Kudo Kenji Murakami Atsuo Masuya Goro
- 出版者
- 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)
- 雑誌
- 平成24年度宇宙輸送シンポジウム: 講演集録 = Proceedings of Space Transportation Symposium: FY2012
- 巻号頁・発行日
- pp.1-8, 2013-01
平成24年度宇宙輸送シンポジウム (2013年1月17日-1月18日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)), 相模原市, 神奈川県
1 0 0 0 OA 中国南部におけるトン族の親族組織の再考
- 著者
- 黄 潔
- 出版者
- 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科
- 雑誌
- アジア・アフリカ地域研究 (ISSN:13462466)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.153-183, 2020-03-31 (Released:2020-04-29)
- 参考文献数
- 62
This paper aims to reconsider the kinship organization of ethnic groups in China with a case study of the Dong people, a Tai-speaking ethnic group that inhabits Southern China. It questions the uncritical application in earlier research of the research pattern of the Han Chinese to the analysis of the kinship of non-Han minorities in China, which leads to ignorance of ethnic characteristics and identity. Specifically, this paper rethinks the view of Dong society through reexamination of the customs and practices of the model of kinship and marriage among Dong people, namely, apl weex bux lagx (combination between different descent groups) and pak singv kkeip (intermarriage ignoring the surname system). It is pointed out that the Dong people’s kinship organization is similar to that of the Han Chinese. However, according to field research, Dong people continue to practice their own model of kinship with the Dong language, though as an ethnic group that lacks a writing system, the Dong have also been strongly influenced by the customs of the Han Chinese. These two aspects are characteristic of the Dong people’s kinship organization. In this case, the use of the Chinese language as a written language to express and practice their kinship organization make it appear to have similar characteristics to that of the Han Chinese. It is found that a series of unique social cultural systems have been produced within Dong society as a result of the fact that the Dong people’s kinship organization has both similarities and differences in comparison with that of the Han Chinese and because of the pressure from the tense relationship between using the ethnic language and Chinese language.
1 0 0 0 OA 有明海の赤潮頻発に端を発する生態系異変のメカニズム
- 著者
- 堤 裕昭
- 出版者
- 日本ベントス学会
- 雑誌
- 日本ベントス学会誌 (ISSN:1345112X)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, pp.103-127, 2021-12-25 (Released:2022-02-11)
- 参考文献数
- 137
- 被引用文献数
- 2
Ariake Bay, located in the western coast of Kyushu, Japan, has been praised as “fertile sea” due to its extremely high production of various sea foods. However, since the late 1990s, red tide has occurred about twice as frequently as before, although the total nutrient discharge from the lands surrounding the bay has even decreased slightly since the 1970s. The increase of organic load on the sea floor by the frequent occurrence of red tide has caused seasonal hypoxia in the bottom water, and brought mass mortality of benthic animals in a wide area of the inner parts of the bay. These phenomena have occurred commonly in the enclosed coastal seas that have been suffering from eutrophication throughout the world. In this review, I collected various information on the occurrence of red tide, nutrient discharge, water conditions when red tide occurred, characteristics of the tidal current, etc., in Ariake Bay from the previous studies, and tried to clarify the mechanism how the red tide have occurred frequently, which is the most responsible for the recent marked decline of the benthic ecosystem in the bay. I focus on the impacts of the closure of the dike in a reclamation project conducted in the inner part of Isahaya Bay (an inner bay of Ariake Bay located in its western side of the middle part of the bay) in April 1997 not only on the tidal current in Isahaya Bay, but also the anticlockwise residual current that originally dominates in Ariake Bay.
1 0 0 0 OA 米国判例に見る教育現場での最近のセクハラ・性差別事例
- 著者
- 岡本 幹輝
- 雑誌
- 白鴎大学論集 = Hakuoh Daigaku ronshu : the Hakuoh University journal (ISSN:09137661)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.329-370, 2002-09-01
1 0 0 0 OA 「白物家電」の誕生 20 世紀の日本における主要工業製品色の変遷(1)
- 著者
- 伊藤 潤
- 出版者
- 一般社団法人 芸術工学会
- 雑誌
- 芸術工学会誌 (ISSN:13423061)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, pp.92-99, 2017 (Released:2018-12-25)
本稿は20 世紀の日本における主要な工業製品の色の変遷についての研究の第一報である。日本の製品色に対する嗜好の特性を示す好例と考えられる「白物家電」と呼ばれる冷蔵庫や洗濯機などの家電製品群を研究対象とし,その成立過程を考察した。 日本の新聞記事ならびに各種辞典の比較調査により,「白物家電」という語は1970 年代後半には新聞記事でも使われる程度に普及したが,元は「白もの」あるいは「白モノ」と綴られていたこと,また英語の“white goods” の訳から生まれた語であることが明らかとなった。 次に,『Oxford English Dictionary』(Oxford University Press)をはじめとする各種英英辞典の比較調査により,家電製品を表す“white goods” は英国語というよりも米国語であることが明らかとなった。 また,Oxford University Press 刊行の『Oxford Dictionary』シリーズのフランス語,ドイツ語,イタリア語,スペイン語辞典の比較により,生活家電各種を“white goods” と表現するのは英語特有の表現であると考えられた。 日本では第二次世界大戦前より家電製品の国産化が始まっていたが,その色彩は必ずしも白くはなかった.第二次世界大戦後「DH 住宅(Dependents Housing)」と呼ばれる連合軍住宅向けの什器として,「白い」製品が大量にGHQ から要求されたが,その中には冷蔵庫や洗濯機等の家電製品も含まれていた。GHQ のデザインブランチの責任者である陸軍少佐クルーゼ(Heeren S. Krusé)は,自身の嗜好よりも入居者となる一般的なアメリカ人の嗜好を優先してデザインを監修していたため,「白い」空間や製品の要求は当時の一般的なアメリカ人の嗜好を反映した結果だと考えられた。GHQからの要求が終了した後,各企業が納入品を民生用に転用した結果,白い家電製品が日本に普及することとなった。 以上より,「白物家電」という語ならびに概念は日本の生活環境の中で自然発生的に成立したものではなく,外来の,特に米国より持ち込まれた概念が元となり成立したものと考えられた。
1 0 0 0 OA 『摩訶止観』と『次第禅門』との関係について
- 著者
- 瀧 英寛
- 出版者
- Research Society of Buddhism and Cultural Heritage
- 雑誌
- 佛教文化学会紀要 (ISSN:09196943)
- 巻号頁・発行日
- vol.2003, no.12, pp.58-79, 2003-11-10 (Released:2009-08-21)
- 参考文献数
- 42
1 0 0 0 OA しりとりゲームの数理的解析
- 著者
- 伊藤 隆 田中 哲朗 胡振江 武市 正人
- 雑誌
- ゲームプログラミングワークショップ2001論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2001, no.14, pp.56-63, 2001-10-26
’しりとり’を完全情報ゲームとして数学的に定義した’しりとりゲーム’を考えると,グラフ上のゲームとしてモデル化することができる.これは完全情報ゲームであるため理論上は解けることになるが,問題のサイズが大きくなるにつれ全探索は困難となる.本論文では,しりとりゲームに関する解析を行い,ゲームを効率的に探索する手法を提案する.この手法は数理的解析,探索の効率化の二つの部分から成っており,数理的解析としてグラフのより簡単な形への変形を行っている.加えて,しりとりゲームにおける先手の勝率に関して実験,考察を行う.
1 0 0 0 OA ウズベキスタン随想
- 著者
- 松本 耿郎
- 出版者
- 静岡大学人文社会科学部アジア研究センター
- 雑誌
- アジア研究 = Asian Studies
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.21-28, 2023-03