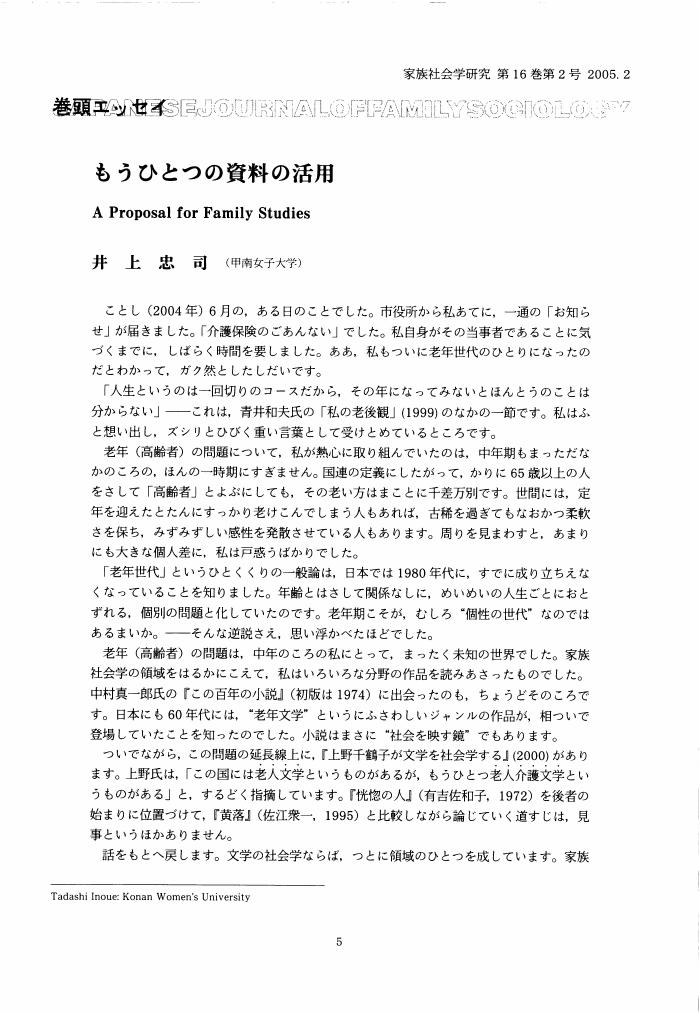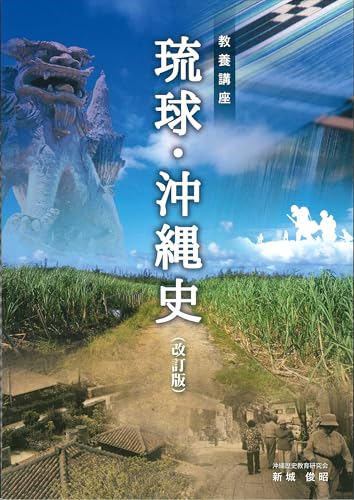1 0 0 0 OA 曜日性と消費との関係に関する予備的考察
- 著者
- 平野 英一
- 出版者
- 明星大学経営学部経営学科研究紀要編集委員会
- 雑誌
- 明星大学経営学研究紀要 = Meisei University, the bulletin of management science (ISSN:18808239)
- 巻号頁・発行日
- no.18, pp.65-76, 2022-03-15
1 0 0 0 OA 電子レンジ解凍による冷凍青汁の栄養、抗酸化活性に及ぼす影響
- 著者
- 佐々木 千恵 寺本 祐之 杉野 智美 伊藤 幸彦 水口 彩 喜瀬 光男 青砥 弘道 吉城 由美子 大久保 一良
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成15年度日本調理科学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.92, 2003 (Released:2003-09-04)
【目的】健康指向の高まりにより、野菜飲料の消費量が伸長してきている。その中でも栄養価が高い野菜のケールを搾汁した冷凍青汁が注目されている。冷凍青汁は、鮮度と栄養価を長期に保持するためには優れた形態であるが、飲用時の解凍方法によっては、青汁の栄養価、機能性が損失される懸念がある。今回は、簡便な解凍方法である電子レンジを冷凍青汁の解凍に使用した場合の栄養価、抗酸化力に及ぼす影響の有無を検討した。【方法】試料は、愛媛県JAで栽培されたケールを搾汁して製造された冷凍青汁(ファンケル社製)を用いた。解凍方法は、スタンダードな手法として用いられている流水に浸した解凍(流水解凍;20_から_23℃水道水、4分30秒)をコントロールとして、電子レンジによる解凍(500W、1分30秒)後の栄養価、抗酸化力を評価した。栄養価はβ‐カロテン、ビタミン類、葉緑素(クロロフィルa、クロロフィルb)、抗酸化力はESRによるSOD様活性(SOSA)、XYZ系活性酸素消去発光法によるH2O2消去活性の分析を行った。また、解凍後の沈殿凝集の程度を粒度分布計で測定し、喉越しなどの官能試験と合わせて評価を行った。【結果】電子レンジによる解凍は、流水解凍と比較して、沈殿凝集物の粒子径が小さくなり、喉越しが良くなることが分かった。β‐カロテン、ビタミン類、葉緑素については、解凍方法による差は認められなかった。抗酸化力の指標となるESRによるSOSA及びXYZ系活性酸素消去発光によるH2O2消去活性は、電子レンジ解凍の方が高い傾向を示した。【結論】冷凍青汁の電子レンジ解凍は、簡便であるだけでなく、栄養価を損なわず、飲用時の品質も優れていると評価した。
1 0 0 0 OA もうひとつの資料の活用
- 著者
- 井上 忠司
- 出版者
- 日本家族社会学会
- 雑誌
- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.5-6, 2005-02-28 (Released:2009-08-04)
1 0 0 0 OA 放送法制における区域外再放送の位置づけ
- 著者
- 西土 彰一郎
- 出版者
- 成城大学法学会
- 雑誌
- 成城法学 = Seijo hogaku : Seijo law review (ISSN:03865711)
- 巻号頁・発行日
- no.86, pp.23-41, 2020-01-20
木畑洋一先生/佐藤文夫先生古稀祝賀記念号
1 0 0 0 OA ニンニク‘北海道在来’の摂取によるアポリポプロテインE欠損マウスの動脈硬化進展抑制効果
- 著者
- 細見 亮太 新井 博文 安永 亜花里 矢萩 大嗣 安武 俊一 吉田 宗弘 福永 健治
- 出版者
- 日本健康医学会
- 雑誌
- 日本健康医学会雑誌 (ISSN:13430025)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.76-82, 2021-04-30 (Released:2021-08-01)
- 参考文献数
- 22
北海道北見市常呂町で生産されているニンニク‘北海道在来’(ピンクニンニク)の生理機能の一つとしてアテローム性動脈硬化症抑制効果を動物実験により評価した。4週齢雄性アポリポプロテインE(ApoE)欠損マウスに高脂肪餌料(HF),HF餌料にさらにコレステロールを添加した高コレステロール餌料(HC),HC餌料にピンクニンニク粉末を5%(w/w)添加したニンニク餌料(HC-G)をそれぞれ自由摂取で与えた。飼育13週間後,常法により解剖を行い,血清および心臓を採取した。また解剖前に各マウスの1日分の糞を採取した。血清および糞の脂質濃度の分析,加えて心臓大動脈弁の脂肪沈着をOil Red O染色で評価した。HC-G群はHC群と比べ,血清総コレステロール濃度の低下,大動脈弁の脂肪沈着の抑制,糞への中性ステロール排泄量の増加が見られた。HC-G群では盲腸重量および1日に排泄される糞重量が増加したことから,ピンクニンニク粉末に含まれる食物繊維の作用により糞への中性ステロール排泄量が増加したと考えられる。これらの結果から,ピンクニンニクの摂取は,血清脂質の改善によって,アテローム性動脈硬化症の進行を抑制することが示唆された。
1 0 0 0 OA 塩酸メチルフェニデートが生活の質改善に奏効したモルヒネ治療中の末期癌4症例
- 著者
- 益田 律子 井上 哲夫 横山 和子 志賀 麻記子
- 出版者
- Japan Society of Pain Clinicians
- 雑誌
- 日本ペインクリニック学会誌 (ISSN:13404903)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.4, pp.397-402, 1999-10-25 (Released:2009-12-21)
- 参考文献数
- 11
モルヒネによる癌性疼痛治療中の眠気に対し, 塩酸メチルフェニデートを用い, 著しい生活の質 (quality of life) 改善が得られた4症例を経験した. いずれもモルヒネによる除痛効果は不十分であるにもかかわらず, 眠気のためにモルヒネ増量が困難な症例であった. 少量の塩酸メチルフェニデート (10~20mg/day) によって得られた効果は, (1)日中の傾眠と夜間覚醒の是正, 睡眠型の正常化, (2)夜間の不安, 恐怖の消失, (3)モルヒネ至適量投与による無痛, (4)摂食・歩行・会話など日常行動型の改善であった. 使用期間は7~50日間で, 明らかな副作用を認めなかった. 少量の塩酸メチルフェニデート投与はモルヒネ治療中の末期癌患者における生活の質 (quality of life) 改善に寄与する.
1 0 0 0 OA 「無墓制」と真宗の墓制
- 著者
- 蒲池 勢至
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, pp.209-236, 1993-03-25
これまで民俗学における墓制研究は、「両墓制」を中心にして進展してきた。「両墓制」は「単墓制」に対しての用語であるが、近年、これに加えて「無墓制」ということがいわれている。「無墓制」については、研究者の捉え方や概念規定が一様でなく混乱も生じているので、本稿ではこの墓制が投げかけた問題を指摘してみたい。さらに、「無墓制」が真宗門徒地帯に多くみられることから、真宗における「墓」のあり方を通して「石塔」や「納骨」といった問題を考えようとするものである。まず、全国各地の事例を整理してみると、これまでの報告には火葬と土葬の場合が区別されずにいたり、あるいは「墓がない」というとき「墓とは何か」が曖昧であった。それはまた、両墓制における「詣り墓」(石塔)とは何かが曖昧であったことを示している。「無墓制」の実態は、火葬したあとに遺骨を放置してしまい、石塔を建立しないものであるが、この墓制は両墓制研究の中で、いま一度、遺体埋葬地や石塔の問題、土葬だけでなく火葬の問題を検討しなければならないことを教えている。真宗門徒になぜ「無墓制」が多いのかについては、真宗信仰が墓をどのように考えていたのか歴史的に考察する。現在の真宗墓地にみられる石塔の形態や本山納骨の成立過程をみて、真宗の墓制観や教団による規制との関係を論じる。そこには、遺体や遺骨を祭祀することは教義的に問題があった。中世においても、真宗は卒塔婆や石塔に否定的であって、このような墓や石塔に対する軽視観は近世を通じて今日まで至り、火葬のあとに遣骨を放置したまま石塔も建立しない習俗が残存したのである。また、真宗は墓としての石塔は否定したが、納骨儀礼は認めて、近世教団体制の確立する段階で中世的納骨儀礼を近世的な形で継承したのであった。
1 0 0 0 教養講座琉球・沖縄史
- 著者
- 新城俊昭著
- 出版者
- 編集工房東洋企画 (発売)
- 巻号頁・発行日
- 2014
1 0 0 0 OA 気胸の発症で明らかとなった骨肉腫肺転移の1例
- 著者
- 林 龍也 重松 久之 坂尾 伸彦 杉本 龍士郎 岡崎 幹生 佐野 由文
- 出版者
- 一般社団法人 日本呼吸器外科学会
- 雑誌
- 日本呼吸器外科学会雑誌 (ISSN:09190945)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.27-31, 2021-01-15 (Released:2021-01-15)
- 参考文献数
- 14
転移性肺腫瘍による続発性気胸は時に経験されるが,その原発腫瘍としては肉腫,特に骨肉腫による報告が多い.今回,骨肉腫の治療終了後,気胸の発症を契機に骨肉腫の肺転移を診断し,その後全身化学療法を施行して無再発生存を得ている症例を経験したので報告する.症例は14歳の男性で,左脛骨原発の骨肉腫と診断され,腫瘍広範切除術と人工関節置換術が施行された.術後化学療法が行われ,治療終了約6ヵ月後に右自然気胸となった.画像上,肺転移巣を疑う陰影は認めなかったが,右上葉胸膜直下に5 mm大の囊胞を認めた.術中同部位からの気漏を確認し,肺部分切除術を施行した.組織学的に骨肉腫の肺転移であり,胸膜直下の転移巣による胸膜の破綻が気胸の原因であると考えられた.骨肉腫の既往や治療後経過観察中に気胸を発症した場合は,骨肉腫の肺転移を疑い,診断と治療を兼ねた外科切除が有用であると考えられた.
1 0 0 0 OA 河出書房<グリーン版>の誕生
- 著者
- 田坂 憲二 Kenji TASAKA
- 雑誌
- 文芸と思想 = Studies in the humanities (ISSN:05217873)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, pp.55-67,
- 著者
- 長田 芙悠子
- 出版者
- 経理研究所
- 雑誌
- 経理知識 (ISSN:03895890)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, pp.21-43, 2013-09-30
1 0 0 0 OA 妻を引き抜く方法 : 規約的必然としての「呪術」的因果関係(<特集>呪術再考)
- 著者
- 浜本 満
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:24240508)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.360-373, 1997-12-30 (Released:2018-03-27)
人類学者は, さまざまな実践をまちまちな理由に基づいて「呪術」に分類しているように見える。呪術というカテゴリーがなんらかの統一された研究対象を規定しているとは考えないほうがよいのかもしれない。本論は, 行為とその結果の結び付きについての知識の特殊な性格が, その知識を前提とした慣行を「呪術的」に見せているような場合について検討する。ケニア海岸地方のドゥルマにおいては, 水甕を夫が動かすことが, 妻に死をもたらす行為であるとして禁じられている。ここでの, 水甕を動かすことと妻の死との因果的な結び付きについての知識を構成している諸要素の関係を明らかにすることが本論の具体的な課題である。この知識の内部では, 妻と彼女が所属する屋敷との関係についての「隠喩的」な語り口の内部での必然性と, 水甕を動かすことと土器の壷をめぐるさまざまな慣行とのあいだの相対的有縁性が, 恣意的な規約性によって結び付いている。この種の規約性と因果性の配置は, 呪術と分類されがちな慣行が前提としている知識の特徴のーつである。従来の象徴論的な分析が, この配置についての誤認に基づいたものであることも示される。
1 0 0 0 OA 近世の神職組織 : 触頭を擁する組織を対象に
- 著者
- 井上 智勝
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.148, pp.357-378, 2008-12-25
本稿では、従来個別の地域に即して蓄積されてきた神職組織研究を相互比較することによって、近世の神職組織の存在形態とその特質を解明した。対象は、これまでの研究が触頭―触下という関係に注目して集積されてきた関係から、触頭などの長を戴く神職組織に設定している。検討対象としては、松前から九州までの事例を取り上げた。かかる神職組織は、領国地域・非領国地域を問わず、各地に多数存在し、多様な展開を見せていた。非領国地域の組織は、領主権力から比較的自由に存在することが可能で、前代以来の自律性を残しつつ存在した。比較的広い封地を有する領主の神職編成には、領主権力によって触頭が設定される場合と、前代以来の地域有力社が保持する既存組織が利用される場合があった。前者の場合でも下部組織として郡や郷などにおいて展開してきた在地の神職組織に依拠することは多かった。また、領主権力によって構築された神職組織は、触頭の奉仕社と同格の神社神職からの強い抵抗を誘発することがあり、当該地域権力が消失あるいは縮小した場合には解体する方向へ進むこともあった。後者においては、在地からの抵抗は比較的少なく、反対に領主権力が地域有力社の自律的な在り方に制限を加えられることもあった。神職組織の編成原理も単に触頭―触下という論理ではなく、官位、称号、参勤など、いくつかの論理によってその関係を正当化していた。このうち参勤という神職集団の形成形態は、やや古い形態を残すものと考えられる。また、本所はかかる組織に依拠して諸国の神職支配を行っていたが、既存の組織や秩序からの脱却を図る神職の動向を助長する役割を果たす場合もあった。
- 著者
- 湯川 真樹江
- 出版者
- 立命館大学社会システム研究所
- 雑誌
- 社会システム研究 = 社会システム研究 (ISSN:13451901)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.29-47, 2013-03
台湾の先住民族による汎エスニシティは、1980年代の権利回復を求める原住民族運動を端緒に顕在化した。こうした異なる民族を「原住民族」としてまとめ上げる汎原住民意識は、既往研究において、運動における政治的戦略としての側面が強調され、その役割や機能が分析されてきた。一方、汎原住民意識の顕現や「都市原住民」の増加に伴い、現代の原住民諸民族間の関係や人々の帰属意識がいかに変化しているのかについては十分に明らかにされていない。本研究では、現代台湾の都市における汎原住民族規模の団体や異なる民族の共住関係に着目することを通じて、汎原住民意識が都市原住民の間でいかに共有・維持されているのかを明らかにしていく。
1 0 0 0 OA ブッダの世界の小さな花 : エレーナ・ガンの『ウトバーラ』が描くカルムィク仏教の世界
- 著者
- 高橋 沙奈美 Sanami Takahashi
- 出版者
- 国立民族学博物館
- 雑誌
- 国立民族学博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Ethnology (ISSN:0385180X)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.235-251, 2015-11-27
マダム・ブラヴァツキーは幼少のうちから,ひとところに長く落ち着いて生活することのない「遊牧民的」生活を余儀なくされた。様々な民族と宗教が混在するロシア帝国の南方を転々と放浪する生活をしたこと,特にアストラハンで遊牧民のカルムィク人とそのチベット仏教に出会っていたことは,彼女のその後の人生に少なくない影響を及ぼしたと考えられている。母エレーナは,この放浪生活に耐えがたい疲弊を感じていたが,その一方で,西欧文明とは異なる生活の中にインスピレーションを見出し,「異郷」を舞台とした一連の小説を発表した。時に,1820–1830 年代のロシア文壇を風靡したロマン主義は,「カフカスもの」と称されるロシア南方を舞台とした小説を輩出していた。エレーナ・ガンの創作も,この潮流に棹差すものだったのであり,1838 年に彼女が発表した,カルムィクを舞台とする小説「ウトバーラ」もまた,ロシアのオリエンタリズムが生み出した作品の一つといえる。本稿はガンを育んだ人々や環境,彼女が抱き続けた理想や,彼女が生きた時代の歴史的・文化的背景を踏まえながら,ガンが見たカルムィクと仏教世界を小説「ウトバーラ」の中から読み解く試みである。
1 0 0 0 OA 入口としてのカルムィク草原 : 19 世紀前半のカルムィク人とその信仰に関する知識と記憶
- 著者
- 井上 岳彦 Takehiko Inoue
- 出版者
- 国立民族学博物館
- 雑誌
- 国立民族学博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Ethnology (ISSN:0385180X)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.215-233, 2015-11-27
本稿では,マダム・ブラヴァツキーが少女時代を過ごしたロシアにおいて,1830 年代から40 年代にカルムィク人やチベット仏教に関する知識がいかなる状況にあったかを考察する。18 世紀には外国人学者・探検家が中心となって,カルムィク人とその信仰は観察され描写された。カルムィク人の信仰はモンゴルやチベットとの類似性が強調され,カルムィク草原は東方への入口として位置付けられた。19 世紀になると,ロシア東洋学の進展ととともに,カルムィク人社会は次第にモンゴルやチベットとは別個に語られるようになった。こうして,学知としてはモンゴルやチベットとの断絶性が強調された一方で,ロシア帝国の完全な支配下に入ったカルムィク草原では,ロシア人の役人が直接カルムィク人と接触するようになる。マダム・ブラヴァツキーの母方の祖父A・M・ファジェーエフが残した『回顧録』からは,彼とその家族のカルムィク体験は鮮烈な記憶として家族のあいだで共有されていたことが読み取れる。
1 0 0 0 OA 再生可能エネルギーの電力市場への統合拡大に向けた需給調整力確保への取り組みと課題
- 著者
- 岡本 浩
- 出版者
- 一般社団法人 日本風力エネルギー学会
- 雑誌
- 風力エネルギー (ISSN:03876217)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.131-134, 2015 (Released:2016-09-30)