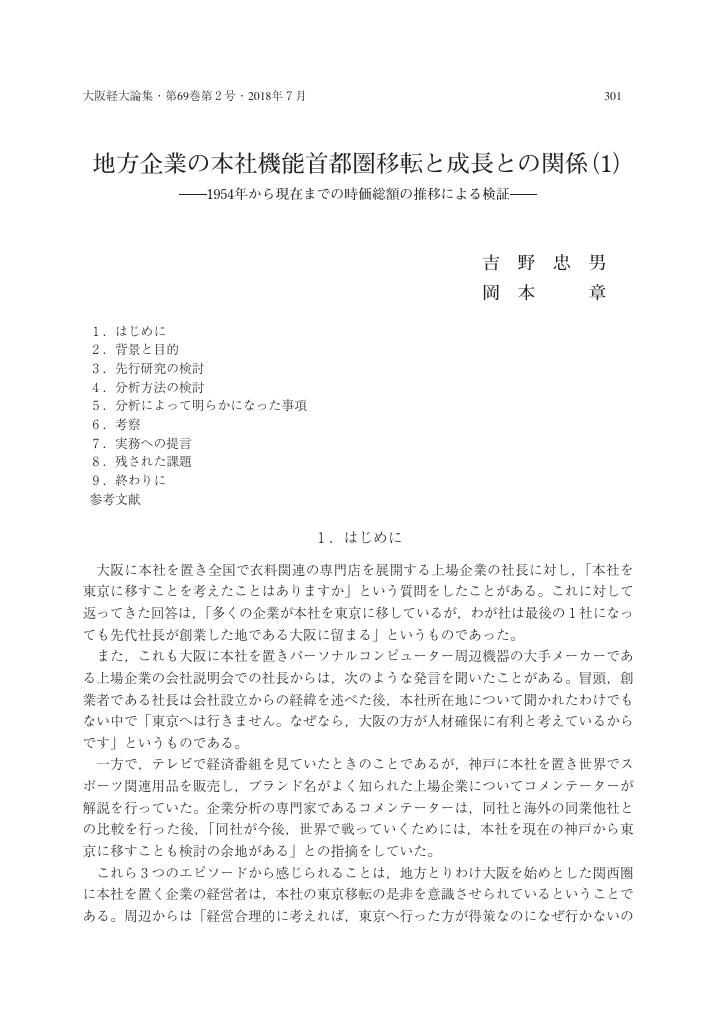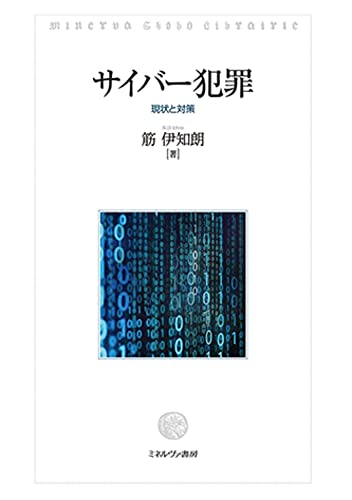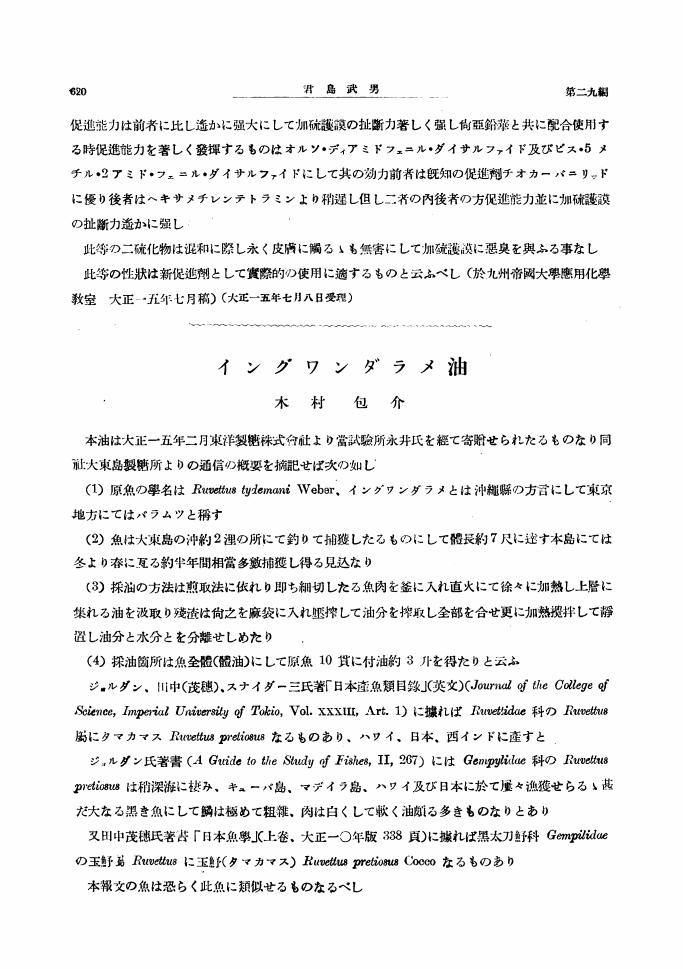1 0 0 0 OA III. フラーレンの作り方
- 著者
- 古賀 義紀
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会誌 (ISSN:13405551)
- 巻号頁・発行日
- vol.114, no.1, pp.23-27, 1993-12-20 (Released:2008-04-17)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 OA 事例投稿が臨床行動に果たす機能—武藤(2016)へのリプライ—
- 著者
- 伊井 俊貴
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.3, pp.365-366, 2016-09-30 (Released:2019-04-27)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 OA 日常的に行う口腔機能訓練による高齢者の口腔機能向上への効果
- 著者
- 大岡 貴史 拝野 俊之 弘中 祥司 向井 美恵
- 出版者
- 一般社団法人 口腔衛生学会
- 雑誌
- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.88-94, 2008-04-30 (Released:2018-03-30)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 17
口腔機能は,摂食・嚥下機能や構音機能など,生活の質の維持・向上,コミュニケーションをはじめとした社会生活を営むうえで重要な役割を担っている.本研究では,在宅高齢者の機能減退に伴う摂食・嚥下機能および構音機能の低下に対して,機能低下の進行を予防するために高齢者自身が行える口腔機能向上における新たな介護予防システムを構築することを目的に,口腔体操が口腔機能の向上に与える効果を検討した.特定高齢者および要支援高齢者計23名(男性4名,女性19名,平均年齢77.9±6.5歳)を対象として,器具を用いない口腔体操および口腔ケアを含む口腔機能向上プログラムを自宅にて約3ヵ月継続して実施した.この介入前後に摂食・嚥下機能および構音機能の改善効果について評価を行い,口腔機能の変化について検討を行った.その結果,口唇閉鎖力および音節交互反復運動の回数に著明な改善がみられた.また,反復唾液嚥下テスト(RSST)においては,介入前の評価で3回の嚥下が行えなかった対象者で明らかな嚥下回数の向上が認められ,初回嚥下までの時間も有意に短縮された.これらより,特定高齢者および要支援高齢者が自宅にて日常的に行える簡便な口腔体操の実践により,摂食・嚥下機能,構音機能をはじめとした口腔機能の向上が得られる可能性が示唆された.
1 0 0 0 OA 日本語能力試験における発達性ディスレクシア(読字障害)への特別措置
- 著者
- 上野 一彦 大隅 敦子 Kazuhiko Ueno Atsuko Oosumi
- 出版者
- 国際交流基金
- 雑誌
- 国際交流基金日本語教育紀要 = The Japan Foundation Japanese-Language Education Bulletin (ISSN:13495658)
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.157-167, 2008-03-17
日本語能力試験は1994年度より障害を持つ受験者に対する特別措置を開始し、2006年度は95名がこの措置を利用している。中でもLD(学習障害)等と分類される学習障害や注意欠陥・多動障害、高機能自閉症に関する措置については、原則を立てつつ試行を重ねている段階である。 一方坂根(2000)によれば、既に日本語教育の現場でもLD(学習障害)等に相当する障害を持つ学習者を受け入れており、教師は「LD学習者の対応は、学習目標、LDの程度や症状の問題など、多くの要因が複雑にからみあうため、一律の対応をするのがよいのか」と懸念しているという。 本稿ではLD(学習障害)等の中核をなすと言われる発達性ディスレクシアに焦点を当て、専門家と実施主体が連携しながら、WAIS-Ⅲをはじめとする認知・記憶特性を理解し、特性に基づいた過去の措置を踏まえて特別措置審査を行っているさまを、実際の事例とともに紹介する。
- 著者
- 押田 正子 川崎 聡大
- 出版者
- 富山大学人間発達科学部附属人間発達科学研究実践総合センター
- 雑誌
- 教育実践研究 : 富山大学人間発達科学研究実践総合センター紀要 (ISSN:18815227)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.27-32, 2013-01
近年,特別支援教育に対する学校現場での関心が高まっているが,学習障害児に対する効果的な指導や支援は,ほとんど行われていない現状がある。本研究では,通常の学級に在籍する読み書きに困難さがみられた小学校3年生A児に対して,大学教育相談にて認知神経心理学的評価に基づき個別支援を行った。支援の経過および変化から通常小学校における学習障害児の支援の在り方について検討を加えたので報告する。対象児の個別支援では,まず書き困難に対する支援の第一段階として,本人の認知機能障害の把握と,カタカナ書字正確性をターゲットとした機能的再編成法による指導を行った。A児は,全般的知能発達遅滞は認めず,年齢相応の語彙力や漢字の読みの正確性を維持していたにもかかわらず,書き到達度は小学校1年生程度と2学年の乖離を認めた。また「繰り返し書いて覚える」書き指導を受け続け,失敗経験蓄積の結果,本学教育相談来所時には学習場面からの逃避行動も散見される現状であった。本学教育相談において,1)書き困難の背景として視覚性記憶の再認の弱さ(視覚情報処理障害)が存在する。2)語彙力,漢字音読力(正確性)と音声言語の長期記憶力は保たれていることが明らかとなった。その結果,良好に保たれた学習経路である音声言語の長期記憶力をバイパス経路とした機能的再編成法によって,短期間で困難であったカタカナ書字の正確性を向上させることが可能となった。
- 著者
- 吉野 忠男 岡本 章
- 出版者
- 大阪経大学会
- 雑誌
- 大阪経大論集 (ISSN:04747909)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.301, 2018 (Released:2019-03-06)
1 0 0 0 サイバー犯罪 : 現状と対策
1 0 0 0 OA 韓国の領土教育 -独島/竹島教育をめぐって-
- 著者
- 藤田 昭造
- 出版者
- 明治大学教育実習指導室
- 雑誌
- 明治大学教職課程年報 (ISSN:13461591)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.51-61, 2019-03-26
- 著者
- 松田 早紀
- 出版者
- 立命館大学映像学会
- 雑誌
- 立命館映像学 (ISSN:18829074)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.79-92, 2022
1 0 0 0 OA リテラシー調査とリテラシー政策を考える ─外国人の日本語リテラシーを中心に─
- 著者
- 前川 喜平
- 出版者
- 基礎教育保障学会
- 雑誌
- 基礎教育保障学研究 (ISSN:24333921)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.66-69, 2022 (Released:2022-09-15)
- 著者
- 藤原 岳 佐藤 格夫 石井 亘 橋本 直哉
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本脳神経外科救急学会 Neurosurgical Emergency
- 雑誌
- NEUROSURGICAL EMERGENCY (ISSN:13426214)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.29-33, 2022 (Released:2022-07-12)
- 参考文献数
- 5
タイ王国コンケン病院外傷センターに短期留学する貴重な機会を得たので概要を報告する.本邦では神経外傷をはじめとする重症外傷の症例数は,自動車工学の発展,ヘルメット着用や飲酒運転の厳罰化とそれらに伴う市民意識の高まりにより減少傾向である.本邦での神経外傷研修には限界があると考え諸外国での研修での補完を企図した.コンケン病院において神経外傷の研修としては日本人初の研修生であり,約1ヶ月間の研修で100例を超える神経外傷症例を経験し,12例の緊急手術に参加した.神経外傷の症例数の減少している本邦の若手脳神経外科医において有用な研修であると考えられた.
1 0 0 0 OA 米国における動物看護学教育
- 著者
- 小田 民美
- 出版者
- 日本動物看護学会
- 雑誌
- Veterinary Nursing (ISSN:21888108)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.37-46, 2019 (Released:2020-07-19)
1 0 0 0 OA 日米における訴訟情報の調査手法
- 著者
- 松本 光司 今井 奈月 鶴森 熊子 谷為 昌彦 河村 光偉 池田 元子
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報プロフェッショナルシンポジウム予稿集 第8回情報プロフェッショナルシンポジウム
- 巻号頁・発行日
- pp.71-75, 2011 (Released:2011-10-14)
- 参考文献数
- 9
知的財産権に関する訴訟は、企業にとって大きなリスクを伴うものであり、権利情報の 1 つの側面でもあることから、企業の情報担当者または知財担当者はこれら訴訟情報にも精通していることが求められる。今回、日本と米国における訴訟情報について、『判例情報』と『経過情報』とに内容を分けて、それぞれの情報源および調査手法の検討を行ったので報告する。なお、本内容は平成 22 年度日本 FARMDOC 協議会 (JFA) での「日米における訴訟情報の調査手法研究会」の成果の一部である。
1 0 0 0 OA 包括的アプローチにより,全盲の高齢者が頚髄損傷受傷後も独居生活を継続できた一例
- 著者
- 野尻 恵里 諸冨 伸夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本在宅医療連合学会
- 雑誌
- 日本在宅医療連合学会誌 (ISSN:24354007)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.58-63, 2021 (Released:2021-10-14)
- 参考文献数
- 9
独居の高齢全盲者が転倒により頸髄損傷を受傷し,重複障害者となった症例を経験した.リハアプローチによる ADL の改善は十分ではなかったが,患者は自宅退院を希望した.医療職種と介護職種の多職種連携による包括的アプローチを行い,自宅環境と定期巡回を軸とした居宅サービスを調整して,自宅退院を実現した.退院から 3 年後も独居生活を継続できている.FIM が低下した項目はあるものの,ケアプランの大幅な変更はなく,社会的交流が増え,本人は楽しみを持って生活しており,包括的アプローチによる自宅退院の実現は有意義であったと考える. 重複障害による ADL 障害があっても,自宅退院の実現可能性を十分に検討する必要がある.
1 0 0 0 OA スティーブン・フォスター再発見
- 著者
- 宮下 和子
- 出版者
- 立命館大学国際言語文化研究所
- 雑誌
- 立命館言語文化研究 = 立命館言語文化研究 (ISSN:09157816)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.79-98, 2014-10
1 0 0 0 OA J.R.コモンズにおける産業統治の思想と社会保障構想
- 著者
- 加藤 健
- 巻号頁・発行日
- 2012
横浜国立大学, 平成24年9月24日, 博士(経済学), 乙第378号
1 0 0 0 OA イングワンダラメ油
- 著者
- 木村 包介
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 工業化学雑誌 (ISSN:00232734)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.11, pp.620-623, 1926-11-05 (Released:2011-09-02)
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 山科 美智子
- 出版者
- 埼玉女子短期大学
- 雑誌
- 埼玉女子短期大学研究紀要 (ISSN:09157484)
- 巻号頁・発行日
- no.37, pp.79-99, 2018-03
1 0 0 0 OA Kinectを用いた指文字認識の検討(学生研究発表会)
- 著者
- 織茂 裕介 玉國 祐司 高橋 大介 岡本 教佳
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会技術報告 38.9 (ISSN:13426893)
- 巻号頁・発行日
- pp.31-32, 2014-02-15 (Released:2017-09-22)
本研究では奥行情報とカラー画像を取得できるセンサとしてKinectを用いて手話の指文字を認識する手法を検討する.手話および指文字の認識に関する研究はこれまで静止画像やビデオ映像を対象として数多く行われてきたが,オクルージョン判定や奥行きの位置情報を正確に把握することは困難であった.Kinectを用いれば比較的安価で奥行情報を取得できるため,手軽に指文字認識が可能なシステムを提案する.