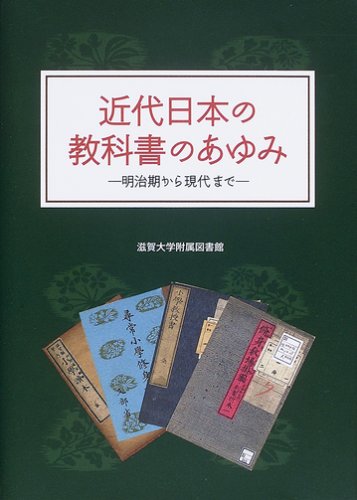1 0 0 0 OA 小児筋電義手の現状と課題 —兵庫県立リハビリテーション中央病院15年の経験から—
- 著者
- 戸田 光紀 陳 隆明 柴田 八衣子 溝部 二十四 高見 響
- 出版者
- 日本義肢装具学会
- 雑誌
- 日本義肢装具学会誌 (ISSN:09104720)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.136-141, 2019-04-01 (Released:2020-04-15)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
先天性上肢欠損児において,筋電義手は両手動作の獲得を可能とし活動,参加の機会を広げる有効な手段である.しかし本邦において小児に対する筋電義手はほとんど普及していない.兵庫県立リハビリテーション中央病院では2002年より小児に対し筋電義手訓練を常時提供できる体制を構築し,これまで15年間で70例以上の児に対して継続的に筋電義手訓練を提供してきた.今回,我々は訓練提供開始から15年間の経過をまとめ,当院における小児筋電義手訓練の現状と今後の課題について検討を行ったので報告する.
1 0 0 0 近代日本の教科書のあゆみ : 明治期から現代まで
- 著者
- 滋賀大学附属図書館編著
- 出版者
- サンライズ出版
- 巻号頁・発行日
- 2006
中国とインドの交流は西域を媒介としており、西域の仏教や国情が密接に関係している。インド・西域からの渡来僧は、中国へ仏教を伝えることを目的にしている。例えば、月支の竺法護や亀茲の鳩摩羅什等の例に見られるように経典翻訳や教義理解や実践の指導を行っている。ところが、中国からインドへの入竺求法の動機は学問的な関心であった。中国僧の入竺は既に三世紀の後半から始まっている。その最初は魏の朱士行であり、魏の甘露五年(260)に西遊しているが、その動機は『道行般若経』を読み、文意が通じなかったため自ら西域に原本を求めるためであった。また道安の『放光光讃略解序』によれば、晋成帝の時代(327〜334)に慧常・進行らが西遊しているが、その目的も学問的な課題であった。かの法顕や玄奘も同様に自らの仏教研究の課題の解決にあった。また中国僧の入る竺の目的として自らの宗教体験や受戒の正否を確かめることもあった。その点で中国僧の入竺は、日本仏教における巡礼や、世の諸宗教にみられる聖地巡拝とは全く異なる性格のものであった。この様な目的でインドに渡った中国僧のためにインドに「漢寺」が存在していたことを確認した。『法苑珠林』所引の王玄策の『西域志』や引継の『印度行程』などによってそれを知ることが出来る。中国とインドの交流が最も活発になるのは5世紀と7世紀であり、逆にそれが減ずるのは6世紀と8世紀である。これは西域の事情や中国の秦や唐など国情と密接に関係している。中国僧の入竺記録としては法顕の『仏国記』や玄奘の『西域記』などは著名であるが、その他に、雲景の『外国伝』、智猛の『遊外国伝』、法勇の『歴国伝記』などが存在した。それらの逸文の収集に努めた。今後の残された研究課題としては、それらの入竺或いは渡来の僧たちが中国仏教の形成と発展に如何なる影響を与えているかの解明が是非とも必要になる。
- 著者
- 平田 淳 松尾 敏実 荻野 亮吾 江口 若香子
- 出版者
- 佐賀大学大学院学校教育学研究科
- 雑誌
- 佐賀大学大学院学校教育学研究科紀要 (ISSN:24325074)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.841-901, 2023-03-10
本稿は、主に本大学院経営コース第3・4期修了生を対象とするインタビュー調査を通して、その教育効果について検討するものである。結論としては、修了生は経営コースにおける各種授業や実習、その他指導の教育効果について肯定的に評価しており、それは特に「データに基づく現状分析と課題の設定」「理論的裏付けのある改革案の実施」「協働づくりと学校組織マネジメント」「リーダーシップ」において現れていた。
- 著者
- Deepak Gautam Jun-ichi Takada
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- IEICE Communications Express (ISSN:21870136)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.5, pp.175-180, 2023-05-01 (Released:2023-05-01)
- 参考文献数
- 7
This paper presents development of passive channel sounder using software defined radio based receivers and commercial transmitter operating in cellular network. Accuracy of developed channel sounder is verified by over-the-air path gain measurement in outdoor open space. For evaluation, line-of-sight path gain is estimated using correlation method and is compared with theoretical path gain.
1 0 0 0 OA 看護分野におけるアロマセラピー研究の現状と課題
- 著者
- 鈴木 彩加 大久保 暢子
- 出版者
- 聖路加看護大学
- 雑誌
- 聖路加看護大学紀要 (ISSN:02893326)
- 巻号頁・発行日
- no.35, pp.17-27, 2009-03
- 著者
- Tsuchimochi Gary Hoichi
- 出版者
- 東洋英和女学院大学
- 雑誌
- 人文・社会科学論集 (ISSN:09157794)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.65-80, 1990-03
1 0 0 0 IR わが国会社財務制度の形成過程に関する研究
1 0 0 0 共形接続空間の理論について(仏文)
1 0 0 0 OA 課税・給付と行動経済学
- 著者
- 森 知晴
- 出版者
- 財務省財務総合政策研究所
- 雑誌
- フィナンシャル・レビュー (ISSN:09125892)
- 巻号頁・発行日
- vol.151, pp.83-106, 2023 (Released:2023-04-21)
- 参考文献数
- 97
本論文では,課税と給付の経済分析において,行動経済学の知見を用いた研究のサーベイをおこない,日本の課税・給付政策を行動経済学の観点から議論する。行動経済学とは,主体が「標準的な仮定」とは異なる仮定で動いているモデルを想定した研究の総称であり,近年では課税・給付の理論分析・実証研究においても研究が急増している。具体的には,税に関する不注意,課税・給付の複雑性がもたらす影響,退職貯蓄と年金の制度設計,納税促進,労働・教育・医療における給付の影響などが研究されている。また,理論的には最適課税との関係が研究されている。行動経済学的な知見は日本における課税・給付にかかる制度・政策を検証する新たな視点を提供し,より現実的な人間像を踏まえた制度設計を提案することができる。
- 著者
- Yoshiaki Kaneko Tadashi Nakajima Tadanobu Irie Fumio Suzuki Masaki Ota Takafumi Iijima Mio Tamura Takashi Iizuka Shuntaro Tamura Akihiro Saito Masahiko Kurabayashi
- 出版者
- International Heart Journal Association
- 雑誌
- International Heart Journal (ISSN:13492365)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.84-86, 2014 (Released:2014-02-07)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 7 9
An 81-year-old man with long RP narrow QRS tachycardia underwent catheter ablation. Ventricular pacing reset the atrial cycle over a retrograde slow pathway, followed by termination of the tachycardia without atrial capture, confirming the diagnosis of fast-slow atrioventricular nodal reentrant tachycardia (AVNRT). The earliest atrial activation during tachycardia was found in the noncoronary sinus of Valsalva, where the first delivery of radiofrequency energy terminated and eliminated the inducibility of the tachycardia, by retrograde conduction block over the slow pathway. This is the first report of a fast-slow AVNRT, with successful ablation of the slow pathway from a noncoronary sinus of Valsalva.
- 著者
- 小平 美香
- 雑誌
- 立教大学ジェンダーフォーラム年報 : Gender-Forum
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.71-83, 2016
- 著者
- 山口 正博
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.4, pp.916-917, 2004-03-30 (Released:2017-07-14)
1 0 0 0 OA タルド模倣説再考
- 著者
- 池田 祥英
- 出版者
- 日仏社会学会
- 雑誌
- 日仏社会学会年報 (ISSN:13437313)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.61-80, 2000-10-20 (Released:2017-06-09)
On meconnaissait la sociologie de Gabriel Tarde a cause du caractere psychologique du mot <<imitation>>. Sans doute la theorie tardienne estelle souvent qualifiee <<psychologique>>, mais cette estimation nous empeche de comprendre pourquoi il a insiste sur l'etablissement de la nouvelle discipline, sociologie. Dans cet article, nous reconsiderons les significations du concept de l'<<imitation>> dans ses Lois de l'imitation. Nous clarifions que s'il a utilise le mot <<imitation>> ce n'etait pas qu'il a insiste sur le psychologisme, mais qu'il a vise a etablir la sociologie scientifique. Le concept de l'<<imitation>> a trois aspects: 1° l'hypnose, cote psychologique; 2° une forme de la repetition universelle que toutes les sciences doivent traiter; 3° la quantification de la sociologie par l'utilisation des concepts quantitatifs, <<croyance>> et <<desir>>. (Paragraphe I) Nous considerons que Tarde a vise a expliquer le changement social, qui est un phenomene macrosociologique, du point de vue microsociologique, c'est-a-dire de l'imitation. Il a explique que les initiatives individuelles creaient ou modifiaient la societe, et que les rapports entre les hommes passaient de l'unilateral au reciproque, en traitant les lois logiques de l'imitation et ses influences extra-logiques. (Paragraphe II) Nous envisageons la critique de la theorie du changement social d'Emile Durkheim par Tarde en la liant avec la theorie de ce dernier dans Les lois de l'imitation. Alors que Durkheim a presente la formule du passage de la solidarite mecanique, qui presuppose la ressemblance entre les personnes, a la solidarite organique, qui presuppose leur difference, c'est-a-dire la division du travail entre eux, Tarde lui, par contre a remarque que l'imitation unilaterale qui passe de la difference a la ressemblance se transformait en imitation reciproque qui passe inversement, conformement a ses lois de l'imitation. (Paragraphe III)
1 0 0 0 日向夏搾汁の製造工程における各種細菌芽胞の汚染
- 著者
- 内田 丈聖 岡 美里 西原 健 坂谷 洋一郎 長田 隆
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- pp.NSKKK-D-23-00012, (Released:2023-05-11)
日向夏飲料の微生物学的安全性確保のために,原材料製造工程における日向夏搾汁について,各種細菌芽胞の汚染度を調べた.計11試料において,好気培養では51菌株,嫌気培養では12菌株を分離し,TABについては検出されなかった.また,分離した菌株のうち,Paenibacillus属細菌を最も多く検出し,その他Bacillus属,Paraclostridium属,Clostridium属細菌を得た,これより,これら細菌種が日向夏100%ジュース(pH3.1)中で発育できないため,殺菌指標菌として管理する必要はないことがわかった.今回の実験では検出できなかったTABだが,過去の変敗事例や本菌種の諸性質を考慮すると,殺菌指標菌として検討する必要がある.そのため,今後はTABによる日向夏100%ジュース中での発育試験を行い,発育する場合は,加熱殺菌指標菌として適切な加熱殺菌条件を設定して管理すべきと考える.また,さまざまな野菜汁や果汁を混ぜるミックスジュースでは,pHによってはPaenibacillus属が発育する可能性があるので注意が必要である.
- 著者
- 柴山 桂太
- 出版者
- 経済理論学会
- 雑誌
- 季刊経済理論 (ISSN:18825184)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.89, 2017 (Released:2019-07-08)
- 著者
- 田中 祐輔
- 出版者
- 言語文化教育研究学会:ALCE
- 雑誌
- 言語文化教育研究 (ISSN:21889600)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.219-239, 2018-12-31 (Released:2019-05-12)
中国における日本語の学習は,戦後複数回にわたってさまざまな緊張状態に置かれた日本と中国との関係を日本理解という形でつなぐ役割の一端を担うものであった。そして現在及び将来においても,日中関係を担う人材育成の重要な場であることは疑い得ない。また,突出した学習者数と,高度な日本語人材育成という量・質の両面から,中国における日本語教育は世界の日本語教育全体を牽引する立場にあるといえる。本研究は,これまで詳しく知られてこなかった国交正常化以前の中国で日本語による情報発信や交流に多大な貢献を果たした放送局・新聞社・雑誌社のアナウンサーや記者のオーラルヒストリー調査を通じて,中国の日本語教育において日本語メディアがどのような役割を果たし,それはいかにして実現したかについて考察し,両国の相互理解と文化交流の歴史の新たな側面に光を当てるものである。
1 0 0 0 OA いまなぜ味噌にPRが必要か
- 著者
- 野口 正義
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.12, pp.966-969, 1993-12-15 (Released:2011-09-20)
いわゆる伝統的食品と呼ばれる食品の中でも, もっとも日本的なものの筆頭に味噌が挙げられよう。その消費が, 米飯とともに衰退の傾向を見せ始めてから, すでに久しい。その原因は何なのか, どうやったらサバイバルの戦略が立てられるのか「みそ健康づくり委員会」の考えを述べていただいた。