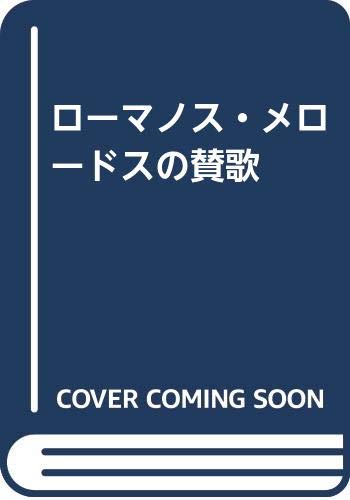1 0 0 0 日本民俗学会年会 : 研究発表要旨
- 出版者
- [日本民俗学会]
- 巻号頁・発行日
- 1986
1 0 0 0 OA 海洋生物からの新規キチナーゼの検索・機能解析および応用技術開発
カニ・エビなどの甲羅を構成するキチン質は地球上に豊富に存在するが、その多くが利用されずに廃棄されている。一方、このキチン質をキチン分解酵素(キチナーゼ)で分解すると、機能性食品素材として有効活用できることがわかりだした。本研究ではカニ・エビのキチンの分解に適したキチナーゼを海洋生物から探し出す基礎研究、それを活用するための応用技術開発を実施した。2魚種の胃より各2種、2種のタコより各1種、計6種のキチナーゼを分離し、機能を解析した。さらに魚類、軟体動物、カニより計11種のキチナーゼ全長遺伝子を取得した。機能解析から活用できるキチナーゼの遺伝子を選び、微生物によるキチナーゼ生産を実施した。
1 0 0 0 OA 明治・大正期の沖縄庶民金融の検討
- 著者
- 金岡 克文
- 出版者
- 高岡法科大学
- 雑誌
- 高岡法科大学紀要 (ISSN:09159347)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, pp.165-189, 2021 (Released:2021-05-16)
1 0 0 0 OA 前回り受け身における効果的な学習方法の検討
- 著者
- 清野 哲也 坂田 洋満
- 出版者
- 独立行政法人 国立高等専門学校機構 木更津工業高等専門学校
- 雑誌
- 木更津工業高等専門学校紀要 (ISSN:21889201)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, pp.36-41, 2017-01-31 (Released:2017-08-02)
- 参考文献数
- 6
It is pointed out that group learning can foster learners' sociability and enhance their learning motivation. In physical education classes, these effects can be expected by setting an appropriate tasks to carry out in a group. In the case of judo lessons, Maemawariukemi is more technically difficult than Usiroukemi and Yokoukemi. Therefore, the speed to acquire the skill, Maemawariukemi, varies from individual to individual. The purpose of this study is to examine the effects of group learning as an active learning method to learn Maemawariukemi.
1 0 0 0 OA 複雑な病変に対する急性期機械的血栓回収療法
- 著者
- 坂本 誠 宇野 哲史 中島 定男 細谷 朋央 桑本 雄平 末吉 駿太郎 神部 敦司 黒崎 雅道
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳卒中の外科学会
- 雑誌
- 脳卒中の外科 (ISSN:09145508)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.6, pp.482-491, 2022 (Released:2022-12-28)
- 参考文献数
- 31
内頚動脈および中大脳動脈M1部の緊急大血管閉塞(emergency large vessel occlusion:ELVO)に対する機械的血栓除去術(mechanical thrombectomy:MT)は,内科的治療単独よりも患者の予後を改善することが示されている.ステントリトリーバー(stent retriever:SR)や吸引カテーテル(aspiration catheter:AC)を用いたMTでは,90%前後の高い再開通率が報告されているが,実臨床では,解剖学的な要因や病変の複雑さから通常のMTでは再開通が困難な複雑な症例を経験することがある.本稿では,臨床で遭遇する可能性が高い以下の6つの典型的な複雑な条件下でのMT症例を提示し,治療戦略と手技を文献的に考察した.①蛇行した血管走行による病変部へのアクセス困難症例,②頚動脈と頭蓋内のタンデム病変,③中大脳動脈 M2 セグメントより遠位部の病変,④椎骨脳底動脈閉塞,⑤頭蓋内動脈硬化性狭窄症(intracranial atherosclerotic stenosis:ICAS),⑥脳動脈解離.当院では,MT手技は主にSRとACのcombined technique を第一選択としている.combined techniqueの利点は以下の点である.①SRとACの両方で血栓を強固に把持することで,遠位塞栓(embolization in new territory:ENT)を減少させる.②遠位にSRを留置して,ACをSR内の血栓部位まで先進させることでSR展開長が短縮しかつSRとACの長軸方向が一致することで,SRの牽引時の血管直線化が減少し穿通枝引き抜き損傷が減少する.③SRを展開し遠位固定することで,SRに追従させてのACの遠位誘導が容易になる.予後を改善するためには,状況に応じてさまざまな治療戦略や技術を駆使し,常に1回のデバイス通過での完全な再開通(first pass effect:FPE)を目指すべきである.
- 著者
- 大沢 昌玄 岸井 隆幸
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.3, pp.711-716, 2013-10-25 (Released:2013-10-25)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1
災害復興土地区画整理事業は、復興という公的性格が強いことから、公共団体もしくは行政庁により事業が実施されてきたが、過去においては民間的性格とも言われる組合施行での事業実施も確認された。本研究は、組合施行による災害復興土地区画整理事業の実施を検討する基礎的研究として、災害復興土地区画整理事業の施行者別の実施実態を踏まえた上で、(1)災害復興土地区画整理事業施行者について法制度の観点から位置づけを確認し、(2)組合施行による災害復興の位置づけの解明を行う。さらに(3)本研究で明らかとなった組合施行による復興の第1号と考えられる1925年の日暮里大火復興土地区画整理事業の実施内容を示した上で、組合施行による災害復興土地区画整理事業の特徴を明らかにする。その結果、震災復興の旧特別都市計画法では、法案審議過程で組合施行が追加されたが、組合施行は行われなかったことが判明した。戦災復興では、組合施行が行われていた。旧都市計画法においては、組合施行が行われていたが事業費や実施体制において公共団体の強力な支援のもと事業が行われ、公共団体による業務代行方式の組合施行であった。
- 著者
- 加藤 太郎 板東 杏太 有明 陽佑 勝田 若奈 近藤 夕騎 小笠原 悠 西田 大輔 髙橋 祐二 水野 勝広
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.326-332, 2021-03-18 (Released:2021-07-03)
- 参考文献数
- 18
目的:脊髄小脳変性症(spinocerebellar degeneration:SCD)に対する短期集中リハビリテーション治療(SCD短期集中リハビリテーション)の効果が,先行研究により示されている.しかし,SCD短期集中リハビリテーションの効果検証は,Scale for the Assessment and Rating of Ataxia(SARA)の総得点により報告されており,SARAの下位項目による詳細な検証はなされていない.本研究は,歩行可能なSCD患者の運動失調に対するSCD短期集中リハビリテーションの効果を,SARAの総得点と下位項目得点から検証することを目的とした.方法:対象は,SARAの歩行項目3点以下に該当し,4週間のSCD集中リハビリテーション治療プログラム(SCD集中リハビリテーション)に参加したSCD患者23名(男15名,女8名)とした.評価項目はSARAとし,SCD集中リハビリテーション実施前後に評価を実施した.対象者のSCD集中リハビリテーション実施前後のSARAの総得点および各下位項目得点を,後方視的に解析した.統計はWilcoxonの符号付き順位検定を用いて分析検討し,有意水準は5%とした.結果:SCD集中リハビリテーション実施前後において,総得点および下位項目得点のうち,歩行,立位,踵-すね試験に有意な点数の改善を認めた(p<0.05).一方,下位項目得点で座位,言語障害,指追い試験,鼻-指試験,手の回内・回外運動は有意な点数の改善を認めなかった.結論:本研究の結果は,SCD集中リハビリテーションはSCD患者のSARAにおける総得点と,特に体幹と下肢の運動失調を有意に改善させることを示した.
1 0 0 0 OA 消費税は本当に消費者が負担しているのか
- 著者
- 西津 伸一郎
- 出版者
- 立正大学経済学会
- 雑誌
- 経済学季報 (ISSN:02883457)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.4, pp.97-116, 2018-03-30
本稿の題目は,「消費税は本当に消費者が負担しているのか」である.しかし本稿の目的は,それを解明することではない.言葉(文字)だけによる説明・主張の危うさを指摘することが目的である.言葉(文字)による説明は,その記述は部分的には正しいあるいは正しく見えるものによって構成される.そのためその説明によって得られた結論は,正しいあるいは正しく見えてしまうことになる.消費税と限界費用を例に,誤った結論に誘導してしまう危険性を指摘する.
- 著者
- 斉藤 理
- 出版者
- 日本国際文化学会
- 雑誌
- インターカルチュラル (ISSN:13485385)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.139-159, 2023-03-31 (Released:2023-05-01)
1 0 0 0 味覚受容障害に及ぼす女性ホルモンおよび加齢の影響
一般的な「味覚」は味刺激の伝導のみならず、「歯ごたえ」「舌ざわり」などの一般体性感覚などを統合した感覚である。近年味覚障害が増加傾向にあるが、その場合は味覚と一般体性感覚が統合した感覚障害である。味覚障害は女性に多い疾患だが、性差の原因は未だ不明である。本研究では、女性ホルモンが味覚障害に及ぼす影響について女性ホルモンの分泌量の異なる幼若期、思春期、成熟期、更年期の4ステージにおける亜鉛欠乏性味覚障害モデル動物を作製し、基本味に対する嗜好性の変化を行動学的に調べ、味刺激に対する神経活動の変化を免疫組織学的手法を用いて調べる。さらに一般体性感覚の変化も検討する。
1 0 0 0 OA M-Vロケット概要
- 著者
- 嶋田 徹 Shimada Toru
- 出版者
- 宇宙航空研究開発機構
- 雑誌
- 宇宙航空研究開発機構特別資料: M-V型ロケット:5号機から8号機まで = JAXA Special Publication: The M-V Rockets: From the Fifth to the Eighth Vehicle (ISSN:1349113X)
- 巻号頁・発行日
- vol.JAXA-SP-07-023, pp.5-10, 2008-02-29
資料番号: AA0064112002
1 0 0 0 OA 新しい生物発光系の化学的研究-キノコを中心に
- 著者
- 磯部 稔
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.736-741, 1992-04-01 (Released:2008-11-21)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA ブロードウェイ・ミュージカルにおける人種とコミュニティ
- 著者
- 岡本 太助
- 出版者
- 一般財団法人 日本英文学会
- 雑誌
- 英文学研究 支部統合号 (ISSN:18837115)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.279-287, 2019 (Released:2021-02-09)
1 0 0 0 OA 「核家族」概念と「二核家族」概念再考 ―タルコット・パーソンズとアーロンズ=ロジャーズ―
- 著者
- 鈴木 健之
- 出版者
- 立正大学人文科学研究所
- 雑誌
- 立正大学人文科学研究所年報 = Annual Bulletin of the Institute of Humanistic Sciences Rissho University (ISSN:03899535)
- 巻号頁・発行日
- no.58, pp.19-28, 2021-03-31
- 著者
- Aya Yoshimura Yoshitaka Obara Yoshikazu Ando Hiroshi Kayano
- 出版者
- Japan Mendel Society, International Society of Cytology
- 雑誌
- CYTOLOGIA (ISSN:00114545)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.1, pp.109-117, 2005 (Released:2005-04-04)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 3 2
The chromosomes of 4 species of grasshopper in the genus Oxya were analyzed by conventional and five differential-staining methods. All 4 species had a chromosome complement of 2n=22+XX(female)/XO(male), with very similar karyotypes. Both O. hyla intricata and O. japonica japonica had acrocentric chromosomes with minute short arms, while the chromosomes of O. chinensis formosana and O. yezoensis were almost all telocentric. In all 4 species, a secondary constriction (SC) was detected at a proximal site in chromosome 8, which had the same staining properties (positive for C- and CMA-banding; negative for G- and QM-banding) in all 4 species. Our C-banding analysis revealed that the short arms of O. hyla intricata and O. japonica japonica consisted of C-heterochromatin. The 4 species yielded species-specific patterns of C-bands, and there appeared to be a close relationship between O. chinensis formosana and O. yezoensis, as suggested by the polymorphism of the distal C-bands of chromosome 2. In all 4 species of Oxya, Ag-NORs were detected on the centromeric regions of all the chromosomes, but not detected on the SC of chromosome 8. The karyosystematic relationships among the 4 species are discussed on the basis of the results of differential staining.
1 0 0 0 OA ウォータージェット法によるセルロースナノファイバー
- 著者
- 小倉 孝太
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 森林科学 (ISSN:09171908)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, pp.7-10, 2017 (Released:2017-11-22)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 OA 認知インタビューの有効性に及ぼす被面接者の性格特性の影響
- 著者
- 山内 佑子 高橋 雅延 伊東 裕司
- 出版者
- 法と心理学会
- 雑誌
- 法と心理 (ISSN:13468669)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.83-92, 2008 (Released:2017-06-02)
認知インタビュー(Cognitive Interview:以下CI)は認知心理学の実験的知見をもとにFisherとGeiselmanによって開発された記憶促進のための事情聴取方法である。想起方法としてCI技法を用いない標準インタビュー(Standard Interview:以下SI)とCIの2条件を設けて比較した従来の研究では、CIはSIよりも正確な情報を引き出すことが明らかにされている。本研究では2つの実験において、CIの有効性に及ぼす目撃者の性格特性の差異の影響を検討した。すなわち、参加者を向性テストの結果によって外向性高群と外向性低群に分けた後、銀行強盗の短いビデオを呈示した。実験1ではSI条件とCI条件を比較した。実験2では全員がCIを受ける前に、CI技法による想起の経験か、CI技法によらない想起の経験のいずれかを行った。その結果、CIの有効性は目撃者の性格特性によって影響を受けることが明らかとなった。これらの結果についてはCIにおけるラポール形成の面から考察した。
1 0 0 0 ローマノス・メロードスの賛歌
- 著者
- [ローマノス・メロードス著] 家入敏光訳
- 出版者
- 創文社
- 巻号頁・発行日
- 2000
- 著者
- 若林 時郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.1-6, 1986-10-25 (Released:2020-09-01)
- 参考文献数
- 10
Four master plans made by the Japan Housing Corporation are much changed. Some of major factors which made them changed were actual conditions of the site; the boundary of developing area, the attainment of land acquisition and the method of development. In Tsukuba, 80% of 1800ha, of the land acquired was used for the research and educational institutions, the land acquisition was so important that the boundary and the method were arranged for the purpose of its attainment. Master plan must be transformed according to these evolving factors, but act on them guiding to log-ranged goal of the development.