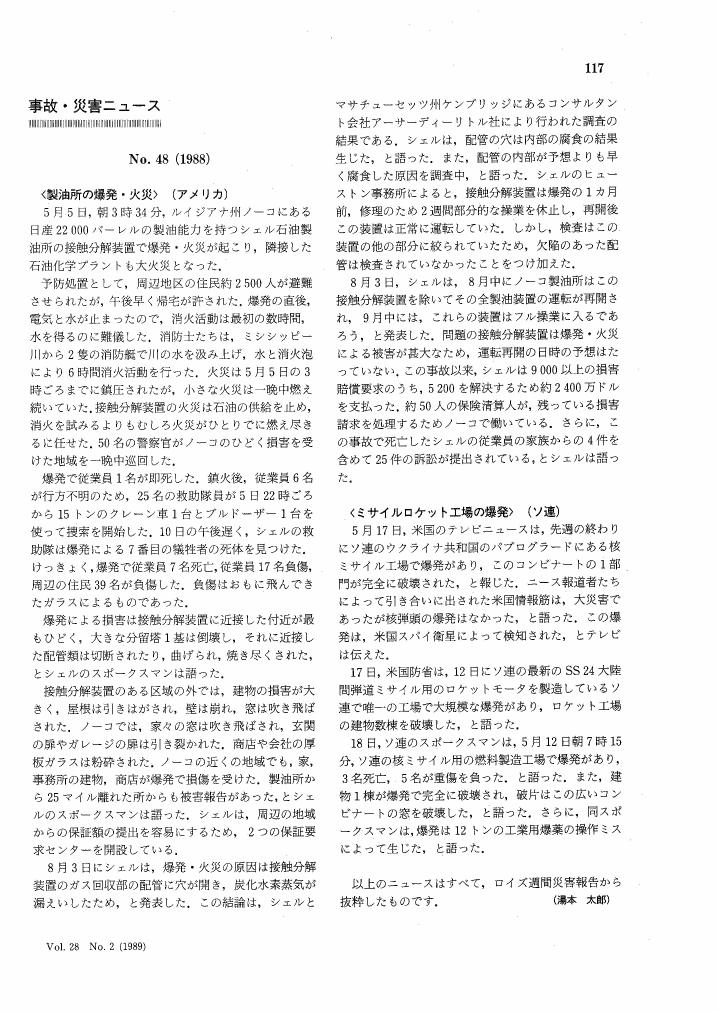1 0 0 0 OA 老化防止剤
- 著者
- 安藤 慎二 深町 真治
- 出版者
- THE SOCIRETY OF RUBBER SCIENCE AND TECHNOLOGYY, JAPAN
- 雑誌
- 日本ゴム協会誌 (ISSN:0029022X)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.2, pp.45-49, 2009 (Released:2010-04-05)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 5 4
The rubber products degrade during use by various factors such as oxygen, ozone, heat, light and dynamic fatigue. Degradation factors are various depending on the conditions of use, and there are a lot of degradation factors besides the above-mentioned. The reagents that are added to prevent degradation are called antioxidants. Degradation causes the phenomena such as physical properties degradation, hardening, softening and cracking, and then rubber products cannot maintain the function of the products. To prevent degradation by these various factors and to maintain the product-life cycle for a long term, addition of antioxidants is very important.
1 0 0 0 OA 地主名鑑
- 出版者
- 不動産研究会名古屋事務所
- 巻号頁・発行日
- vol.第1編, 1918
1 0 0 0 OA ディーセント・ワークの再考
- 著者
- 大友 芳恵
- 出版者
- 社会政策学会
- 雑誌
- 社会政策 (ISSN:18831850)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.68-73, 2019-06-30 (Released:2021-07-01)
- 参考文献数
- 7
1999年の第87回ILO総会において,ディーセント・ワークがILOの主目標と位置づけられてから20年をむかえる。日本においてはこの間,その実現に向けて取り組むことが十分になされてきただろうか。20年間の政策動向からは,多様な働き方を肯定するとしつつも,現実に取り組まれている働き方改革等は経済成長を加速させることが主目標となっており,本来的な人の尊厳を保つ政策には至っていないといえよう。 ディーセント・ワークの真の推進をはかることが,多様な人々の社会参加と生活保障となることを,今一度再考すべきであろう。
1 0 0 0 OA フェルミエネルギー・フェルミ準位および化学ポテンシャルに関する記述をめぐって
- 著者
- 大豆生田 利章
- 出版者
- 独立行政法人 国立高等専門学校機構群馬工業高等専門学校
- 雑誌
- 群馬高専レビュー (ISSN:02886936)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.51-58, 2022 (Released:2022-03-25)
- 参考文献数
- 35
The energy level called Fermi level is an important concept in solid-state physics and electronic device engineering. However, terms, symbols, and explanations are different in various documents, and the descriptions are not always unified. In this report the descriptions for Fermi energy, Fermi level and chemical potential in books are investigated. As a result it is confirmed that there was confusion in the usage of these terms.
- 著者
- 渡辺 徹 稲田 厚 三浦 克己 吉田 暁 田中 敏春
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.3, pp.523-527, 2018-06-30 (Released:2018-06-30)
- 参考文献数
- 6
急性左心不全による心原性肺水腫に対して救急隊員が実施可能な処置は,酸素投与とバッグバルブマスク(BVM)による補助呼吸である。今回,病院前救護においてBVMを用いて1名が両手でマスクを顔面に保持密着させ,もう1名がバッグを圧迫し換気を行う二人法補助呼吸によりSpO2値の改善を認めた疾患例を経験した。心原性肺水腫では呼気終末の気道内圧を高めることで低酸素血症を改善させることができるため,近年医療機関ではNPPVが実施されるようになっている。BVMのマスクを顔面に確実に密着させることができる二人法補助呼吸は,適切に実施すればNPPVに近い効果が期待できる。また,起坐呼吸や不穏状態の傷病者にも有効な換気が可能になる。病院前救護で呼吸困難感を訴え急性左心不全が疑われる例において,高流量酸素投与でもSpO2値が改善しない場合,呼吸原性心停止への移行を予防するためにBVMを用いた二人法補助呼吸を考慮してよいと思われる。
1 0 0 0 OA 新生児期・乳飲期・離乳期における腸の吸収機構
- 著者
- 藤田 守 馬場 良子 熊谷 奈々
- 出版者
- 公益社団法人 日本顕微鏡学会
- 雑誌
- 顕微鏡 (ISSN:13490958)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.229-236, 2010-12-30 (Released:2020-01-21)
- 参考文献数
- 39
消化管,特に腸粘膜上皮の吸収上皮細胞は栄養素の消化と吸収に関して重要な役割を演じているが,哺乳動物においては,出生と離乳というタイミングで消化管の構造と消化吸収機構がダイナミックな変化を遂げる.乳飲期の腸吸収上皮細胞は成熟期とは異なり,部位によって機能的だけでなく,形態的にも分化しており,通常,離乳後には存在しない頂部細胞膜ドメインからの高分子物質の吸収機構(エンドサイトーシス)とそれらに関与するエンドゾームのネットワークが発達する.それらは電子顕微鏡や生物試料作製法の進歩によって初めて観察が可能となった構造であり,最近では多様な手法を用いたアプローチも可能となってきた.本稿では,出生直後から離乳に至る過程で生じる腸の形態および消化吸収機構の変化,特に吸収上皮細胞のエンドサイトーシスとそれに関与するエンドゾームのネットワークの変化について,我々のこれまでの成果も含めて概説する.
1 0 0 0 OA 相互作用的ジェスチャーの確証 ―相互作用的ジャスチャーと家族療法の関係性について―
- 著者
- 若島 孔文
- 出版者
- 一般社団法人 日本家族心理学会
- 雑誌
- 家族心理学研究 (ISSN:09150625)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.91-103, 1996-11-30 (Released:2023-04-30)
- 参考文献数
- 16
This study confirms a new division of illustrators, into topic and interactive gestures, and the function of interactive gestures proposed by Bavelas et al. (1992, 1995). So, the present study carried out four experiments on Japanese university students. In Experiment 1 and 2, to classify illustrators and specify interactive gestures, the same task was assigned to both dyads and individuals : In Experiment 1, dyads had a higher rate of interactive gestures than did individuals, but topic gestures were not significantly affected by condition. In Experiment 2, topic gestures were increased by instruction, but interactive gestures were not. In Experiment 3 and 4, we mentioned the functions of interactive gestures. In Experiment 3, we manipulated visual availability : The rate of interactive gestures was higher for partners interacting face-to-face than for those who could not see each other, but the rate of topic gestures was not changed by condition. In Experiment 4, to examine whether interactive gestures are uniquely affected by the requirement of dialogue, we compared dialogue with sequential monologues: Dialogue had a higher rate of interactive gestures, but rate of topic gestures was not changed by condition. These results supported the theory proposed by Bavelas et al.. Finally, the relationship between this study and family therapy was discussed.
1 0 0 0 OA 彝語の緊喉・非緊喉母音に関する覚書―音声分析の結果をもとに―
- 著者
- 岩佐 一枝
- 出版者
- 日本音声学会
- 雑誌
- 音声研究 (ISSN:13428675)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.51-64, 2019 (Released:2019-04-30)
- 参考文献数
- 16
彝語系諸言語(チベット・ビルマ諸語)は,母音に緊喉・非緊喉の別をもつことで知られているが,緊喉母音生成の詳細な過程についての研究は,従来不十分なものであった。そこで本稿では,彝語系諸言語のうち,アシ・イ語及びノス・イ語に対して実施された音声分析結果をもとに,緊喉・非緊喉母音それぞれの特徴を示し,これを考察する。結果,本稿で取り上げた2言語においては,母音の緊喉に「咽頭化」と「喉頭化」の2タイプがあるとの結論に至った。
1 0 0 0 OA イランの仏教遺跡
- 著者
- 入澤 崇
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.346-339, 2009-12-20 (Released:2017-09-01)
- 著者
- Shuntaro TAKEKUMA Shun-ichi AZUMA Ryo ARIIZUMI Toru ASAI
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences (ISSN:09168508)
- 巻号頁・発行日
- vol.E106-A, no.5, pp.715-720, 2023-05-01
A hopping rover is a robot that can move in low gravity planets by the characteristic motion called the hopping motion. For its autonomous explorations, the so-called SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) is a basic function. SLAM is the combination of estimating the position of a robot and creating a map of an unknown environment. Most conventional methods of SLAM are based on odometry to estimate the position of the robot. However, in the case of the hopping rover, the error of odometry becomes considerably large because its hopping motion involves unpredictable bounce on the rough ground on an unexplored planet. Motivated by the above discussion, this paper addresses a problem of finding an optimal movement of the hopping rover for the estimation performance of the SLAM. For the problem, we first set the model of the SLAM system for the hopping rover. The problem is formulated as minimizing the expectation of the estimation error at a pre-specified time with respect to the sequence of control inputs. We show that the optimal input sequence tends to force the final position to be not at the landmark but in front of the landmark, and furthermore, the optimal input sequence is constant on the time interval for optimization.
1 0 0 0 OA 差別語のメトニミー的原理について : または能力主義をめぐる学生たちとの対話
- 著者
- 野中 進
- 出版者
- 埼玉大学教養学部
- 雑誌
- 埼玉大学紀要. 教養学部 = Saitama University Review. Faculty of Liberal Arts (ISSN:1349824X)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.87-103, 2023
本論では、まず差別語とメトニミー(換喩)的表現の関係について検討する。すべてではないにせよ、相当数の差別語がメトニミー的原理、すなわち〈部分で全体を言い表す〉表現方法に拠っている。なぜ〈部分で全体を言い表す〉と、言葉は差別的に響くのか考察する。論文後半では、前半の議論を「能力主義/業績主義(meritocracy)」に当てはめ、能力/業績(merit)とは人間の部分か全体かという問題を考える。その際、この問題について大学生たちのいくつかの発言を紹介し、考察に付したい。
- 著者
- 野﨑 瑞樹 山尾 貴則 森田 慎二郎 崔 博憲 犬塚 剛 森田 清美 黒沢 麻美 田中 茜
- 出版者
- 東北文化学園大学 現代社会学部 現代社会学科
- 雑誌
- 社会学・社会福祉学研究 = Journal of Sociology and Social Work (ISSN:24368024)
- 巻号頁・発行日
- vol.第2号, pp.85-91, 2023-03-31
- 著者
- 野口 久美子
- 雑誌
- 八洲学園大学紀要 = The bulletin of Yashima Gakuen University (ISSN:2436424X)
- 巻号頁・発行日
- no.19, pp.15-24, 2023-03-31
- 著者
- 田中 信一郎
- 出版者
- 千葉商科大学国府台学会
- 雑誌
- 千葉商大紀要 (ISSN:03854566)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.3, pp.91-113, 2023-03-31
1 0 0 0 OA 看護学生の訪問看護ステーションへの就職意向と訪問看護実習での経験との関連
- 著者
- 為永 義憲 篠崎 惠美子
- 出版者
- 一般社団法人 日本看護学教育学会
- 雑誌
- 日本看護学教育学会誌 (ISSN:09167536)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1-1, pp.15-26, 2023 (Released:2023-04-28)
- 参考文献数
- 27
〔目的〕看護学生の訪問看護ステーションへの就職意向と訪問看護実習での経験との関連を明らかにする。〔方法〕看護系大学4年生387名に、webアンケートによる無記名自記式質問紙調査を行った。単純集計後、訪問看護ステーションへの就職意向と基本属性、訪問看護実習での経験との関連をみた。〔結果〕102名を有効回答(26.4%)とした。訪問看護ステーションで将来働きたい者は29.4%で、卒後すぐに働きたい者はいなかった。訪問看護に関心がある者は57.8%で、実習時期は4年次(62.7%)が最も多かった。訪問看護ステーションへの就職意向は、訪問看護に関する関心、実習時期、実習の満足度、訪問看護師の学生のことを知ろうとする関わりと関連がみられた。〔考察〕看護学生の訪問看護ステーションへの就職意向には、訪問看護実習での経験が重要と示唆された。訪問看護ステーションへの就職を検討するには、インターンシップや新卒訪問看護師に関する情報提供と、就職活動以前に訪問看護実習を経験することが重要と考えられた。
1 0 0 0 OA 事故・災害ニュースNo.48(1988)
- 著者
- 湯本 太郎
- 出版者
- 安全工学会
- 雑誌
- 安全工学 (ISSN:05704480)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.117, 1989-04-15 (Released:2017-10-31)
1 0 0 0 OA 子どもの肥満・身体活動に及ぼす近隣環境の影響
- 著者
- 石井 好二郎
- 出版者
- 一般社団法人日本体力医学会
- 雑誌
- 体力科学 (ISSN:0039906X)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.1, pp.39, 2023 (Released:2023-01-15)
- 著者
- 藤本 一男
- 雑誌
- 津田塾大学紀要 = Journal of Tsuda University (ISSN:02877805)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, pp.119-139, 2023-03-21
1 0 0 0 OA 建国初期における中国共産党の雲南少数民族地域調査報告 ―その構成と内容に関する考察
- 著者
- 美麗 和子
- 出版者
- 日中社会学会
- 雑誌
- 21世紀東アジア社会学 (ISSN:18830862)
- 巻号頁・発行日
- vol.2023, no.12, pp.94-113, 2023-03-01 (Released:2023-03-03)
- 参考文献数
- 17
新中国成立初期,从1950年到1952年,中国共产党向全国少数民族地区派出了“中央民族访问团”。访问团的主要任务是宣传民族政策、慰问和提供救援物资,同时研究者和民族干部进行了对当地少数民族的社会和历史调查。本文关注云南地区的调查报告,分析了当时的中国共产党试图了解什么,以及他们如何将少数民族在 “革命思想”中定位。调查报告具体内容主要包括四个领域:民族分布与民族关系、政治、经济、宗教。除这四个领域外,还有习俗、教育、卫生以及当地人民的要求等,但是都分量不大。从对这些内容的分析可以看到,中共的调查内容反映了马克思主义的社会发展阶段的理论,将少数民族内部以及民族间关系的问题归纳为本质上是“封建势力”与“被统治者”的关系,“阶级剥削”的问题。
- 著者
- 翁 康健 清水 香基 伍 嘉誠
- 出版者
- 日中社会学会
- 雑誌
- 21世紀東アジア社会学 (ISSN:18830862)
- 巻号頁・発行日
- vol.2023, no.12, pp.76-93, 2023-03-01 (Released:2023-03-03)
- 参考文献数
- 17
大多数少数民族由于居住在相对落后的西部地区,所以少数民族的社会经济发展相对落后,与汉族存在差异。为了追求更高的收入,更好的生活,少数民族流动人口不断增加。 那么,通过社会移动是否可以消除少数民族和汉族之间的差异?基于上述问题意识,本文的研究目的为,通过使用CGSS2017 的数据进行探索性的分析,即社会移动是否改变了少数民族与汉族之间所存在的格差。分析结果为,通过社会移动,确实能改善在个人收入,家庭收入,本人学历,母亲学历,健康状态等方面,少数民族与汉族的差异。但另一方面,通过社会移动,使少数民族在人际关系以及社会公平感方面与汉族面临着相同困境。因此整体来说,通过社会移动少数民族的生存和发展未必得到了提升。主观幸福感的数据也显示,通过社会移动未使少数民族更加幸福。