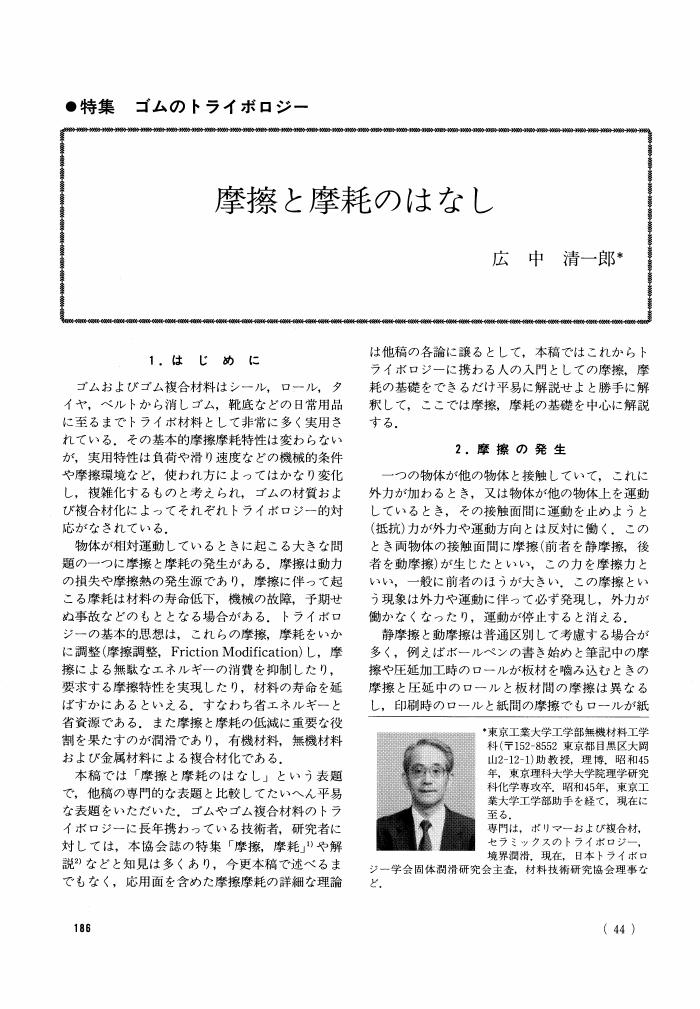1 0 0 0 OA 条約改正問題をめぐる対抗と交錯 -一八八七~九四-
- 著者
- 大石 一男
- 出版者
- JAPAN ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RELATIONS
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, no.139, pp.45-59,L8, 2004-11-29 (Released:2010-09-01)
- 参考文献数
- 62
Were they harmonious with each other, treaty revisions by Munemitu Mutsu and the Sino-Japanese War? This article tried to examine this problem.Shigenobu Okuma (1888-89 in office), one of the minister for foreign affairs in this period, has been thought as a political rival against Okuma's predecessor Kaoru Inoue and the succeeding prime minister Hirobumi Ito. But, when you investigate their own personal histories, the planning process for the Okuma's negotiation, and the character of the negotiating strategy after Okuma retired, it will be apparent that they three politicians —“Kaimei-Ha” or an enlightenment party— had much common points. They thought that treaty revisions, especially the recovery of tariff autonomy, should take first priority, and that an advance to East Asia should be restrained with all their might.Then, why Okuma failed and the cooperation of them three ceased? The reason was that there were some middle-management bureaucrats who were hostile to the common thought of the three politicians. They were active behind the scenes, agitated “the public opinions”, and tried to tear Kaimei-Ha into pieces to prevent the treaty revisions. The typical example was Kowashi Inoue. And as a result, Mutsu the minister for foreign affairs, who were forced to begin the negotiations under insufficient condition, was heavily criticized by “Taigai-Ko-Ha” or hard-liners for foreign affairs. And finally he decided to enter the war. Kaimei-Ha was in power almost throughout in this period because they have the clearest foresight, but small number of them made themselves powerless against internal betrayal or terrorism. So they could not yield sufficient success.
1 0 0 0 OA 補陀落渡海僧日秀上人と琉球 : 史書が創った日秀伝説
- 著者
- 髙橋 康夫
- 出版者
- 法政大学沖縄文化研究所
- 雑誌
- 沖縄文化研究 = 沖縄文化研究 (ISSN:13494015)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.1-40, 2011-03-31
- 著者
- 位田 将司
- 出版者
- 早稲田文芸・ジャーナリズム学会
- 雑誌
- 早稲田現代文芸研究 (ISSN:21858616)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.74-90, 2013-03
1 0 0 0 OA 聴覚特性に基づく重み付け反復スペクトル減算法による音質改善の検討
実環境下での音収録において,周囲の雑音が目的信号に混入し音質が大きく劣化するという問題がある.そのため,収録した音を受聴する場合,混入雑音を抑圧し目的音のみを強調することが重要である.単一マイクロホンでの音収録における雑音抑圧手法としては,SS (Spectral Subtraction) が一般的に利用されている.SS は低演算コストで雑音を抑圧できるが,ミュージカルノイズと呼ばれる聴感上不快な雑音が発生する.そこで,SS を用いて雑音抑圧後の信号を受聴する場合,ミュージカルノイズを発生させずに混入雑音を抑圧する必要がある.これまで,ミュージカルノイズ低減のために SS を反復する手法が提案されており,その有効性が確認されている.しかし,これらの手法では全周波数で一様に雑音を抑圧しており,周波数毎に雑音抑圧量を制御することで更なるミュージカルノイズの低減が期待される.そこで,本研究ではミュージカルノイズが発生しない雑音抑圧手法の構築を目指して,聴覚特性に基づく反復 SS を提案する.提案法の有効性を確認するために,客観・主観評価実験を実施した.各評価実験の結果,提案法は従来法と比較して高い雑音抑圧性能を達成しつつ,主観的にミュージカルノイズを低減できた.
- 著者
- 松崎 慎一郎 佐竹 潔 田中 敦 上野 隆平 中川 惠 野原 精一
- 出版者
- 日本陸水学会
- 雑誌
- 陸水学雑誌 (ISSN:00215104)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.1, pp.25-34, 2014-09-04 (Released:2016-01-31)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 1 2
福島第一原子力発電所事故後に,霞ヶ浦(西浦)の沿岸帯に2定点を設けて,湖水の採水ならびに底生動物である巻貝(ヒメタニシ,Sinotaia quadrata histrica)と付着性二枚貝(カワヒバリガイ,Limnoperna fortunei)の採集を経時的に行い,それらの放射性セシウム137(137Cs)濃度(単位質量あたりの放射能;Bq kg-1)を測定した。これらのモニタリングデータから(2011年7月~2014年3月),貝類における137Csの濃度推移,濃縮係数ならびに生態学的半減期を明らかにした。湖水および貝類の137Cs濃度は定点間で差は認められず,経過日数とともに減少していった。両地点でも,カワヒバリガイよりも,ヒメタニシの137Cs濃度のほうが有意に高かった。濃縮係数を算出したところ,ヒメタニシのほうが2倍近く高かった。巻貝と二枚貝は,摂餌方法や餌資源が異なるため,137Csの移行・蓄積の程度が異なる可能性が示唆された。また生態学的半減期は,ヒメタニシで365~578日,カワヒバリガイで267~365日と推定され,過去の実験的研究で報告されている生物学的半減期よりもはるかに長かった。このことから,餌を通じた貝類への137Csの移行が続いていると考えられた。
1 0 0 0 OA 感温液晶を用いる温度分布の可視化
- 著者
- 秋野 詔夫
- 出版者
- 日本熱物性学会
- 雑誌
- 熱物性 (ISSN:0913946X)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.4, pp.259-265, 1993-10-30 (Released:2010-03-16)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 2 2
感温液晶は、 温度に応じて美しく鮮やかな色彩を呈する. これを物体に塗布したり液体中に懸濁させると、 熱と流れの挙動が、 リアルタイムでカラー映像として直接観察できるようになる. 熱流動現象の理解・把握が直感的に容易になる. この技法は、 使い方が易しく、 安価であり、 最近、 熱流動現象の研究によく用いられるようになってきた. ここでは、 感温液晶の種類、 マイクロカプセル化液晶の光学的特性、 定量的可視化計測に焦点を置いて展望解説する.
1 0 0 0 OA キャラクターの名誉権・同一性保持権 : キャラディス・キャラ改変からのキャラクターの保護
- 著者
- 原田 伸一朗
- 出版者
- 静岡大学人文社会科学部翻訳文化研究会
- 雑誌
- 翻訳の文化/文化の翻訳
- 巻号頁・発行日
- vol.18別冊, pp.131-142, 2023-03-31
1 0 0 0 OA 摩擦と摩耗のはなし
- 著者
- 広中 清一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本ゴム協会
- 雑誌
- 日本ゴム協会誌 (ISSN:0029022X)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.4, pp.186-193, 1999 (Released:2007-07-09)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 2 2
1 0 0 0 OA 水素輝線等価幅とバルマー逓減率のモニタリングから探るBe星の円盤構造
- 著者
- 石田 光宏
- 出版者
- 兵庫県立大学自然・環境科学研究所天文科学センター
- 雑誌
- Stars and Galaxies (ISSN:2434270X)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.10, 2022 (Released:2023-02-10)
- 参考文献数
- 21
長年、Be星(カシオペヤ座γ型変光星)の測光・分光観測が行われているが、未だに星周円盤の生成・消 滅のメカニズムは明らかになっていない。そこで、2018年9月から2020年3月まで、学校天文台にある小口 径望遠鏡+低分散分光器を用いて、複数のBe星の分光モニター観測を行った。得られたスペクトルから水 素輝線等価幅、バルマー逓減率(Hα / Hβ)を計算し、時間変動などを調べた。その結果、バルマー逓減 率に有意な変動がある天体を複数確認した。この現象を説明するため、「Be星の伴星が近星点を通過する ときの潮汐力で円盤がリング化する」という仮説を立てた。
- 著者
- 板垣 竜太 Ryuta Itagaki
- 出版者
- 同志社大学人文科学研究所
- 雑誌
- 社会科学 = The Social Science(The Social Sciences) (ISSN:04196759)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.4, pp.37-68, 2023-02-28
本論文は,黄海道平山郡の刑事訴訟記録(1946~47年の94件)の分析を通じて,日本の植民地支配から解放されて間もない時期の北朝鮮社会における社会規範の急速な変化の様態を明らかにすることを目的としている。この時期、裁かれる側だけでなく,罪を認め,裁き,罰を与える側も,その根拠となる法令も,ともに流動的な状況にあった。新たな予審制度の導入や、公判への参審員の参加、公判の即日宣告制など、裁く方式にも大きな変化が見られた。民衆の新たな政治的要求にある程度応じながら,「人民」の名においておこなわれていった刑事司法では,ときに厳しい,ときに寛大な判断がくだされた。これは<罰>が与えられるべき<罰>だ,これは<罰>が与えられるべきものではない,という判断が繰り返されるなかで,社会の「ノーマル」(標準,正常)が徐々に形成されていった。
1 0 0 0 OA 1946年平壌・普通江改修工事の再検討 : 「突撃」という脱植民地化の技法
- 著者
- 谷川 竜一 Ryuichi Tanigawa
- 出版者
- 同志社大学人文科学研究所
- 雑誌
- 社会科学 = The Social Science(The Social Sciences) (ISSN:04196759)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.4, pp.3-35, 2023-02-28
本稿では、1946年5月21日から55日間にわたって、金日成らの指導の下、平壌で行われた普通江改修工事を扱う。それを通じて工事計画の推移や実施の背景、実際の建設場所や動員計画、そして労働現場の実相を解明する。議論の前半では植民地期に遡って工事の経過を確認するとともに、後半では新資料を用いて動員方法や「突撃隊」の意義などを検討する。最終的には植民地期の建設工事が、解放後に脱植民地化されていくプロセスに迫る。
1 0 0 0 OA 財閥傘下企業への一族内での影響力の継承 : パキスタン4財閥の近年の動向を踏まえて
- 著者
- 川満 直樹 Naoki Kawamitsu
- 出版者
- 同志社大学人文科学研究所
- 雑誌
- 社会科学 = The Social Science(The Social Sciences) (ISSN:04196759)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.4, pp.337-355, 2023-02-28
1947年に、パキスタンは英領インドより分離独立し誕生した。パキスタンの経済は、分離独立当初より、いくつかの財閥にけん引され現在に至っている。それらの財閥傘下企業は、現在でも特定の一族により支配されている。本論では、アトラス財閥、ビボージー財閥、ダーウード財閥とラークサン財閥の4つの財閥を取り上げ、それぞれの財閥傘下企業と一族の関係を検討する。具体的には、2000年代から2020年までの期間を対象に、財閥傘下企業が毎年発行しているAnnual Reportを分析の手掛かりとして、一族の中で誰がもっとも財閥傘下企業に対して影響力があるのかを検討した。
1 0 0 0 OA 本土近接離島の連絡船と海事交通文化 ―本州・四国の小離島を中心に―
- 著者
- 出口 晶子 Akiko DEGUCHI
- 出版者
- 甲南大学文学部
- 雑誌
- 甲南大學紀要.文学編 = The Journal of Konan University. Faculty of Letters (ISSN:04542878)
- 巻号頁・発行日
- vol.173, pp.153-170, 2023-03-30
1 0 0 0 堀辰雄『かげろふの日記』論--運命と<夢>との対峙
- 著者
- 西澤 真理子
- 出版者
- 聖心女子大学
- 雑誌
- 聖心女子大学大学院論集 (ISSN:13428683)
- 巻号頁・発行日
- no.21, pp.29-49, 1999-07
- 著者
- 姉崎 弘
- 出版者
- 常葉大学教育学部初等教育課程研究企画部会
- 雑誌
- 教育研究実践報告誌 (ISSN:24360112)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.1-10, 2023-03
筆者は、特別支援学校における自立活動の一指導方法である「スヌーズレン教育」に着目して一貫した研究を行っている。肢体不自由特別支援学校でさまざまな自立活動の指導方法が用いられているが、どの程度活用されているのか、また教師の各指導方法の習得希望を調査により明らかにすることは、今後のこの教育の発展のために意義があり必要であると考える。そこで本稿では、グループ教師の回答を分析対象にして「スヌーズレン教育」を中心に、各指導方法の活用度や担当教師の習得希望を明らかにすることで、今後特に障害の重い自立類型の担当教師に求められる自立活動の指導方法を検討し特定した。その結果、先行研究の知見より「摂食訓練」「動作法」「理学療法」「感覚統合」「作業療法」「静的弛緩誘導法」「音楽療法」「ムーブメント教育」「スヌーズレン教育」の9つに、新たに「インリアル法」と「心理検査等の評価法」の2つを追加できると考えられた。
1 0 0 0 OA 日本版蘇生ガイドライン2015 と学校におけるCPR の普及について
- 著者
- 田中 秀治
- 出版者
- 日本蘇生学会
- 雑誌
- 蘇生 (ISSN:02884348)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.3, pp.170a, 2016-10-20 (Released:2016-12-17)
PDFファイルをご覧ください。
- 著者
- 小川 賢治 Kenji OGAWA
- 雑誌
- 人間文化研究 = Journal of Human Cultural Studies
- 巻号頁・発行日
- no.48, pp.71-98, 2022-03-31
ABSTRACTEllen Hodgson Brown writes in her book lThe Web of Debtz that the sovereign state can issue money by itself, and that international bankers have deprived sovereign states of power to issue money. Also she says that some events in the world history can be seen from a point of view that those events happened through struggles between sovereign states and international bankers. For example, 'The Glorious Revolution' in England can be seen as that: King James II was a roman catholic and did not permit private banks or money lending. So, Protestants drove him out to establish private banks, and Queen Mary II and King William III were throned. They were Protestants and permitted private banks. Another example: American Independent Revolution was a struggle between American independentists and the British State. American independentists wanted to issue their own money, not to borrow British money and not to pay interest. On the other hand the British State did not admit losing its banks in America. So both joined battle and America won independence from Britain.
1 0 0 0 OA 毛髪の年齢的変化に関する研究 (I) 引張り強度とヤング率について
- 著者
- 成瀬 信子 小川 安朗 藤田 拓男 折茂 肇 大畑 雅洋 岡野 一年 吉川 政己
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.6, pp.487-490, 1968-11-30 (Released:2009-11-24)
- 参考文献数
- 10
2才から91才にいたる81人の健康男子の毛髪を5才ごとに区切り, 各群5人を選び, 1人5本の試料について, 洗浄後, 蒸留水で十分湿潤し, テンシロンIII型万能引張り試験器で切断荷重, 切断伸長率, 切断仕事量および立ち上りのヤング率を測定した. 毛髪の直径は60~140μの間に分布し, 15才前後をピークとして, 以後加齢とともに漸減の傾向を示し, 二次曲線, または, 15才ごろまでは上昇以後下降する2本の直線の合成として表現される. 年齢と切断荷重, 年齢と切断仕事量の推移もほぼ同様である. これに反し, ヤング率は, 20才ごろまでは減少し, 以後加齢とともに徐々に上昇する二次曲線への回帰が統計的に有意である. 加齢の指標の一つとして, 毛髪の物理的性状の研究は有用である.