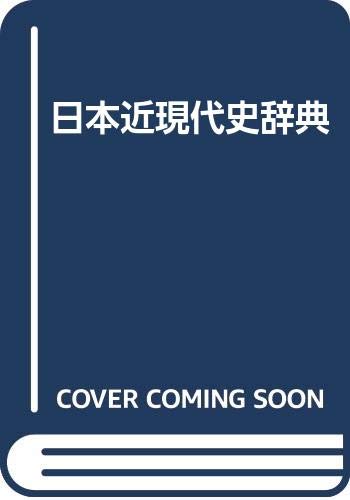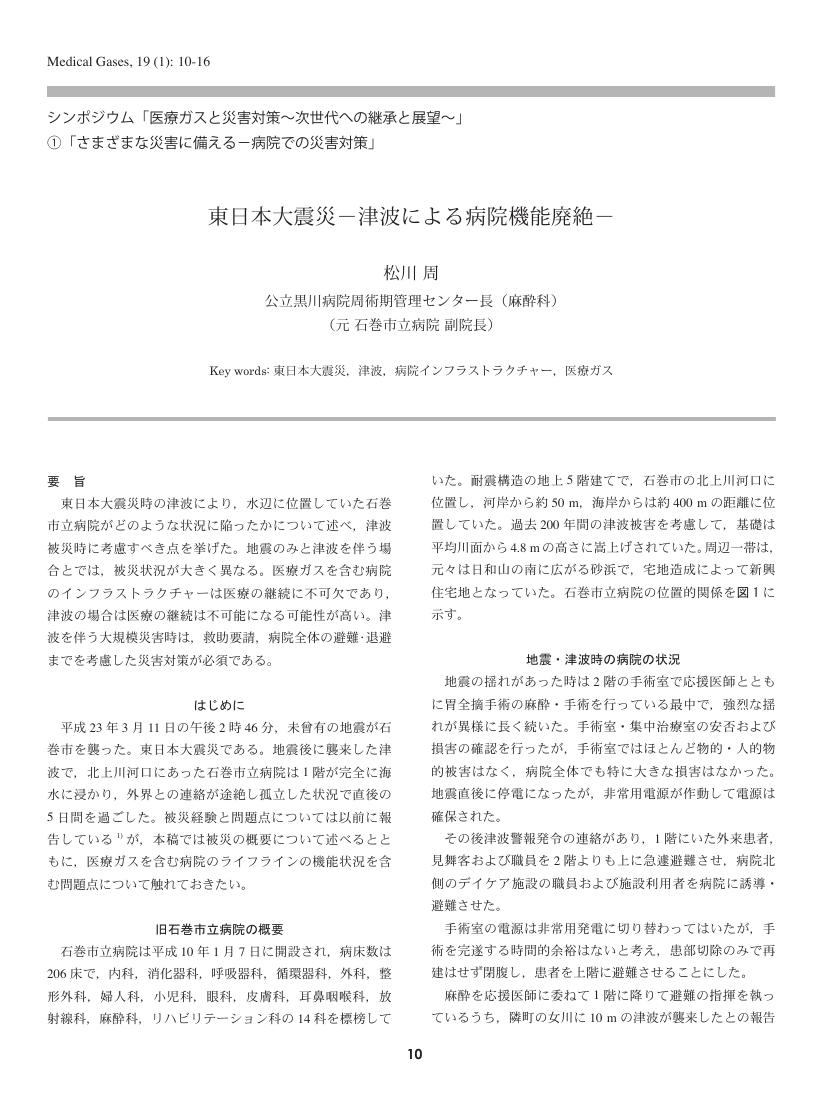1 0 0 0 OA 足底腱膜断裂の一例
- 著者
- 楊 水木 藤田 雅章 乗松 敏晴 鈴木 良平
- 出版者
- West-Japanese Society of Orthopedics & Traumatology
- 雑誌
- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.4, pp.1182-1183, 1984-06-25 (Released:2010-02-25)
- 参考文献数
- 2
A 37 years old female ruptured the plantar fascia of the foot without associated injury to the achilles tendon while she was under a low posture with the knee flexed, ankle plantar flexed and MP joint dorsiflexed during badminton play.It can be considered that the rupture was brought out by the Windlass Action of the plantar fascia due to extreme dorsiflexion of the MP joint. A surgical primary suture was performed with an excellent result.
1 0 0 0 日本近現代史辞典
- 著者
- 日本近現代史辞典編集委員会編
- 出版者
- 東洋経済新報社
- 巻号頁・発行日
- 1978
1 0 0 0 OA CDIF : CASEデータ交換形式
- 著者
- 篠木 裕二 西尾 高典 吉川 彰弘
- 出版者
- 日本ソフトウェア科学会
- 雑誌
- コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.2_109-2_121, 1993-03-15 (Released:2018-11-05)
1 0 0 0 OA 原発巣切除を施行した腹膜播種を伴う大腸癌の治療成績と予後因子
- 著者
- 稲垣 大輔 塩澤 学 里吉 哲太 渥美 陽介 風間 慶祐 樋口 晃生 利野 靖 益田 宗孝
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器外科学会
- 雑誌
- 日本消化器外科学会雑誌 (ISSN:03869768)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.8, pp.607-613, 2017-07-01 (Released:2017-08-24)
- 参考文献数
- 19
目的:原発巣切除を施行した腹膜播種を伴う大腸癌の予後因子を明らかにすることを目的として検討を行った.方法:2000年から2010年まで,当科で治療を行った原発性大腸腺癌を対象とした.結果:大腸癌1,484例のうち77例(5.2%)に腹膜播種を認めた.腹膜播種を伴う大腸癌で原発巣切除を施行したのは74例で,手術根治度Bを得られたのは12例であった.手術根治度Cの65例において,原発巣切除62例と非切除3例の治療成績を比較すると,原発巣切除症例の生存率が有意に良好であった(P=0.037).腹膜播種を伴う大腸癌で原発巣切除を施行した74例で,腹膜播種の程度の分類はP1 32例,P2 17例,P3 25例で,3年生存率(生存期間中央値)は,P1 34.4%(20.2か月),P2 41.2%(24.7か月),P3 8.0%(14.8か月)であった.P3とP1およびP3とP2を比較すると,P3はいずれも有意に予後不良であった(P=0.008,P=0.008).多変量解析の結果,組織型(低分化腺癌・粘液癌・印環細胞癌),腹膜播種P3,手術根治度Cが独立した予後不良因子であった(P<0.001,P=0.015,P=0.002).結語:腹膜播種を伴う大腸癌では,原発巣切除と腹膜播種切除で肉眼的根治切除を行うことができれば治療成績を改善できる可能性があると考えられた.
1 0 0 0 Anthropology and education
- 著者
- Clara K. Nicholoson
- 出版者
- C.E. Merrill
- 巻号頁・発行日
- 1968
1 0 0 0 OA エンロン・ワールドコムの事例に学ぶ企業の内部統制とコーポレート・ガバナンス
- 著者
- 丸山 真弘
- 出版者
- 安全工学会
- 雑誌
- 安全工学 (ISSN:05704480)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.212-219, 2006-08-15 (Released:2016-11-30)
- 参考文献数
- 13
2001 年から2002 年にかけてのエンロンやワールドコムの経営破綻を受け,米国では内部統制やガバナンスに関する制度の見直しが行われた.本稿では,エンロンとワールドコムの経営破綻の状況を振り返りつつ,制度面から見た問題点と対応の動きについてとりまとえめたうえで,日本の状況との比較を行う.
1 0 0 0 OA 氷衛星の地質活動と氷殻のダイナミクス
- 著者
- 木村 淳
- 出版者
- 北海道大学低温科学研究所
- 雑誌
- 低温科学 (ISSN:18807593)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, pp.149-157, 2008-03-31
太陽系の外惑星領域にある衛星は,そのほとんどがH2O主体の氷で覆われた"氷衛星"である.これらは数の多さや多様なサイズを持つが,最も注目すべき点は大規模な地質活動の跡が見られることである.地球の月とは異なるその外見は,氷衛星を覆う氷の存在とその特徴的な物性が作り出している と思われる.本稿では代表例として木星の衛星エウロパに見られる地溝帯と土星の衛星エンセラダスで発見された氷噴出現象に着目し,これらの現象の原因を探る.そこには,液体水が固化する際に体積が増加するという氷特有の物性が大きく関わっている可能性がある.
1 0 0 0 減数分裂の制御機構の解明
減数分裂は遺伝的多様性を生み出し、配偶子形成に必須であるがその制御機構に関しては不明な点が多い。本研究では、減数分裂に特有の諸現象を協調的に進行させる制御機構の解明を目指す。特に、(1)減数分裂前DNA複製と遺伝子組み換え開始の制御機構、(2)減数分裂前DNA複製と第一減数分裂開始の制御機構、 (3)フォークヘッド型転写因子による第一減数分裂開始と遺伝子組換え開始の制御機構、及び(4)減数分裂前DNA複製の開始の制御機構を分裂酵母をモデルとして研究することにより、減数分裂過程の開始から減数分裂前DNA合成及び第一減数分裂までの減数分裂の制御機構を明らかにする。(1)減数分裂前DNA複製と遺伝子組み換え開始の制御機構に関しては、Cds1キナーゼの基質の候補Mei4を同定し、このタンパク質がDNA複製阻害時にCds1 により実際にin vivoとin vitroで主にN末端部分にリン酸化されていることを示した。(2)減数分裂前DNA複製と第一減数分裂開始の制御機構に関しては、上記のMei4変異(Cds1によるリン酸化部位の変異)において、減数分裂前DNA複製を阻害すると、第一減数分裂は開始しなかった。そこで、別の因子が関与している可能性について検討し、候補タンパク質Fkh2を1つ発見した。(3)フォークヘッド型転写因子による第一減数分裂開始と遺伝子組換え開始の制御機構に関しては、Mei4以外のフォークヘッド型転写因子Fkh2がこの過程に関与しているかを検討している。(4)減数分裂前DNA複製の開始の制御機構に関しては、meiRNAがフェロモンシグナルのない状態では減数分裂前DNA複製に必要なことを明らかにした。また、meiRNAのターゲットは転写活性化因子であるRep1である可能性が高くなり、rep1 mRNAはMmi1による分解制御を受けている可能性が高くなった。
1 0 0 0 OA 東日本大震災−津波による病院機能廃絶−
- 著者
- 松川 周
- 出版者
- 日本医療ガス学会
- 雑誌
- Medical Gases (ISSN:24346152)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.10-16, 2017 (Released:2019-09-17)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 止血藥ヲ局所ニ注射シタ場合ニ於ケル局所凝固時間ノ變遷
- 著者
- 鈴木 安恒 尾嶋 禮子
- 出版者
- 一般社団法人 日本内分泌学会
- 雑誌
- 日本内分泌学会雑誌 (ISSN:00290661)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.10, pp.614-620, 1943-11-20 (Released:2012-09-24)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 OA 止血剤ニ就テ
- 著者
- 林 春雄
- 出版者
- 日本医科大学医学会
- 雑誌
- 日本医科大学雑誌 (ISSN:00480444)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.7, pp.917-920, 1937-07-15 (Released:2009-07-10)
1 0 0 0 OA 地理学と主題図
- 著者
- 中村 和郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.3, pp.155-168, 1998-03-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1
In striking contrast to the long history of general maps, it was not until the latter half of the seventeenth century that thematic maps appeared. A. Hettner, (1927), who fully discussed the unique properties and importance of maps in geography, did not yet use the term “thematic maps, ” but stated instead that new types of maps had been introduced in the nineteenth century. A. Kircher (1665) and E. W. Happel (1685) were among the first thematic map makers. The contribution of E. Halley deserves special mention. His world map of trade winds and monsoons (1686) was the first map which used iconic symbols to depict wind directions, and even the seasonal reversal of the Indian monsoon was well demonstrated. Very few had ever used isolines before Halley, who made a chart of compass variations in 1701. Thematic maps made rapid progress in the eighteenth century, when maps of geology, biology, linguistics, population density, economics, administrative divisions, etc. were made. In the author's opinion, Alexander von Humboldt and Karl Ritter made full use of thematic maps to establish the firm foundation of modern geography. “Sechs Karten von Europa” by Ritter, attached to his book “Regional Geography of Europe, ” was the first printed atlas of thematic maps. An incredible amount of information concerning individual locations on the earth's surface was put into an orderly system of knowledge in the form of thematic maps. By making distribution maps of trees and shrubs and of cultivated plants, he delineated several natural regions which were almost parallel to the latitudinal zones. His famous definition of geography, that is, geography deals with the earth's surface as long as it is earthly filled (irdisch erfüllt), can be well understood through his intention to make various thematic maps, because comparable information must be collected for the whole region to complete a map. Halley's isoline map was followed only by those of Ph. Buache (1752) and J. I. Dupain-Triell (1791) until Humboldt made an isothermal chart in 1817. The isoline map is unique in that it can be made with a limited number of data. Humboldt used only 58 cities to produce his chart of a wide area in the Northern Hemisphere. In addition, isoline maps are also unique in that, once made, interpolation and extrapolation allow determination of the figure for every arbitrary point. With the aid of Humboldt, H. Berghaus, the eminent cartographer, published the “Physische Atlas” which included many thematic maps. It cannot be denied that Humboldt was also very keen to illustrate the regularities of physical phenomena and the interrelationships between them using thematic maps.Scrutiny of the history of modern geography from the viewpoint of thematic maps, discovering what type of map was developed for what purpose, etc., is a promising research area.For example, C. Darwin made a distribution map of coral reefs to test his subsidence theory explaining the formation of three types of coral reef. Emphasizing the shapes that maps can describe better than language, O. Peschel believed that a precisely prepared map could illustrate the hidden factors explaining the formation of fjords and other phenomena. F. Ratzel also recognized the importance of map representation in the science of “Anthropogeographie.” His movement theory was highly appreciated by the Kulturkreis school in cultural anthropology. L. Frobenius developed the culture-complex diffusion theory with the help of a number of thematic maps.K. Yanagita (1930), a Japanese folklorist, assembled more than three hundred parochial expressions for the word “snail” into a map. Identifying a concentric pattern with the center in Kyoto from a seemingly chaotic map, he concluded that the distribution pattern of some Japanese dialects resulted from a slow diffusion from the ancient cultural core.
1 0 0 0 OA リファンピシン併用によりステロイド効果の減弱が認められたネフローゼ症候群の1例
- 著者
- 小田 寿 高木 信嘉 常田 康夫 矢花 真知子 金子 好宏
- 出版者
- 社団法人 日本腎臓学会
- 雑誌
- 日本腎臓学会誌 (ISSN:03852385)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.221-225, 1988-02-25 (Released:2010-07-05)
- 参考文献数
- 20
It has been reported that rifampicin attenuates an effect of corticosteroid. We observed nonresponsiveness to prednisolone treatment during rifampicin administration in a case of adult nephrotic syndrome. A 21 years old man had the onset of facial edema and ascites in and was diagnosed as nephrotic syndrome (minimal change) at a certain hospital. He was treated with prednisolone and obtained complete remission. He had the complaint of chest pain in May 1984, and was transfered to our hospital. We diagnosed him as nephrotic syndrome and tuberculous pleuritis. We administered him isoniazid 300 mg/day, rifampicin 450 mg/ day, streptomycin 3 g/week and prednisolone 30 mg/day. His urinary protein was not decreased. Subsequently, we administered him predonisolone 60 mg/day. But his urinary protein was not changed. We thought that rifampicin might attenuate the effect of pre-dnisolone. After rifampicin was discontinued, urinary protein was decreased rapidly. He obtained complete remission and was discharged from our hospital. It was reported that a patient with Addison's disease required increased corticosteroid dosage whilst receiving rifampicin and had cortisol catabolism following hepatic microzomal enzyme induction by rifampicin. Our case of nephrotic syndrome showed the nonresponsi-veness to prednisolone treatment during rifampicin administration. The corticosteroid is essential to treatment of nephrotic syndrome and collagen disease, and rifampicin is an important drug in treatment of tuberculosis. We should pay attension to drug interac-tion between corticosteroid and rifampicin in the cases with combination of these drugs.
1 0 0 0 佐藤春夫『病める薔薇』の一側面--「指紋」からの照射
- 著者
- 齋藤 勝
- 出版者
- 東洋大学大学院
- 雑誌
- 東洋大学大学院紀要 (ISSN:02890445)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.27-39, 2005
1 0 0 0 OA 酸化ストレスによる不安増加の新しい分子機構の解明
本研究では、ビタミンE(VE)欠乏がグルココルチコイド(GC)分泌を増加させて不安行動を増加させる可能性を、CRF, ACTHによるGC分泌制御を中心に検討した。VE欠乏は急性および慢性ストレスによるGC分泌を増加させたが、CRF、ACTH投与による分泌促進を変化させなかった。合成GCであるデキサメタゾンはフィードバック阻害によりGC分泌を抑制し、GC投与は不安行動を増加させたが、これらの作用もVE欠乏の影響を受けなかった。したがって、VE欠乏は視床下部におけるストレス誘導性のCRF分泌促進、あるいはGCによる分泌抑制を低下させることにより、GC分泌を増加させるものと結論した。
- 著者
- 稲林 弘基
- 出版者
- 日本文学協会近代部会
- 雑誌
- 近代文学研究 (ISSN:09105654)
- 巻号頁・発行日
- no.29, pp.44-53, 2012-04
1 0 0 0 OA 周期積分とモチーフの幾何と数論
混合TateモチーフのHodge実現関手の構成のために、semi-algebraic setを使ってある鎖複体を構成し一般化されたコーシー公式を証明した。また混合楕円モチーフについて、深さフィルトレーションをあたえるモチーフのフィルトレーションを定義した。高次チャウ群からコホモロジーへのサイクル写像の像の次元が大きい曲面の構成をした。2変数超幾何方程式系が可約になる特別なパラメーターに関する Schwarz 写像を研究した。このタイプの周期逆写像をテータ関数を用いて記述した。種数2の代数曲線族についてのAbel-Jacobi 写像の像特徴づけた。
1 0 0 0 OA 混合モティーフ層と混合Tateモティーフの理論
複素n次元空間の半代数的集合の上で,極をもつ微分形式の積分の理論を厳密に定式化し, 収束のための幾何的な条件を与えた.また複素解析におけるCauchyの積分公式を高次元の場合に拡張した公式を与え,それを証明した.DG圏の一般化としてquasi DG圏の概念が代表者により提出されていたが,その基礎理論を構築し,とくにquasi DG圏から三角圏を構成する方法を与えた.それを用いて,任意の代数多様体上の混合モティーフ層の三角圏を構成した.混合Tateモティーフの三角圏と代数的サイクルのbar複体上のcomoduleのアーベル圏との関係を研究した.
1 0 0 0 被害記憶への回路という欲望 : 目取真俊「群蝶の木」論
- 著者
- 栗山 雄佑
- 出版者
- 日本近代文学会
- 雑誌
- 日本近代文学 = Modern Japanese literary studies (ISSN:05493749)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, pp.80-94, 2018-11