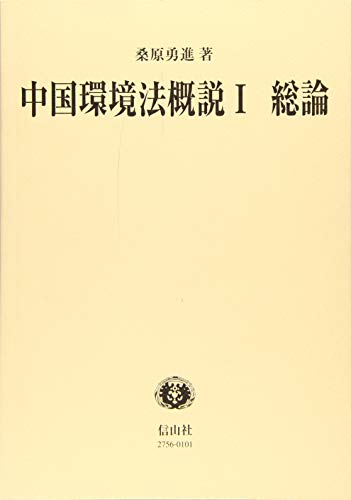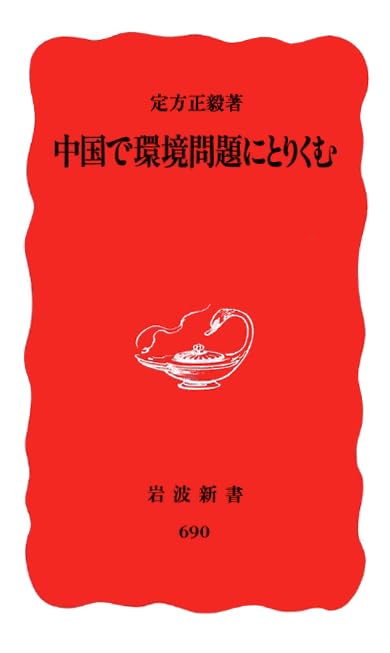1 0 0 0 OA 反対側下肢に対する経皮的電気刺激により幻肢痛の軽減を認めた一症例
- 著者
- 脇本 謙吾 唄 大輔 前谷 朱美 徳田 光紀
- 出版者
- Japanese Society for Electrophysical Agents in Physical Therapy
- 雑誌
- 物理療法科学 (ISSN:21889805)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.37-40, 2017 (Released:2022-09-03)
- 参考文献数
- 9
今回は,義足装着時のみに幻肢痛を認める症例に対して経皮的電気刺激(TENS)の鎮痛効果の検証と痛みの解釈の検討を行ったので報告する.本症例の幻肢痛は,健側の糖尿病性神経障害による痛みと質,部位共に類似していた.方法は,ABAデザインを用い,A期にはプラセボTENS介入,B期にはTENS介入をそれぞれ3日間ずつ実施した.TENSには電気治療器(ESPURGE)を用い,パラメーターはパルス幅150μs,周波数100~250Hzの変調モードに設定し,治療は1日1回30分を同時間帯に実施した.電極の貼付部位は,幻肢痛出現部位及び,断端部と同部位にあたる対側下肢の計4ヶ所とした.幻肢痛の評価としてNRSを用い,痛みの認知的側面に対し破局的思考尺度(PCS)を用いて評価した.TENS介入にて鎮痛効果を認め,鎮痛に伴いPCS得点にも低下を認めた.結果から,本症例の幻肢痛に対する健側へのTENSの有効性と,鎮痛に伴う痛みの認知的側面への効果が推察された.
1 0 0 0 OA 大腿骨頚部骨折術後症例に対する電気刺激併用筋力強化法の効果
- 著者
- 徳田 光紀 唄 大輔 藤森 由貴 亀口 祐貴 庄本 康治
- 出版者
- Japanese Society for Electrophysical Agents in Physical Therapy
- 雑誌
- 物理療法科学 (ISSN:21889805)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.63-66, 2016 (Released:2022-09-03)
- 参考文献数
- 10
本研究の目的は大腿骨頚部骨折術後症例を対象に,術後翌日から電気刺激治療を併用しながら筋力強化運動を実施する電気刺激併用筋力強化法の効果を検討することである.大腿骨頚部骨折術後に人工骨頭置換術を施行した8名を対象に電気刺激併用筋力強化法群(ES群)4名とコントロール群4名に割り付けた.電気刺激併用筋力強化法は電気刺激治療器(ESPERGE)で患側の大腿四頭筋に対して二相性非対称性パルス波,パルス幅300 µs,周波数80 pps,強度は運動レベルの耐えうる最大強度,ON:OFF=5:7秒に設定して毎日20分間実施した.膝伸展筋力(患健側比),股関節JOAスコア,日常生活動作および歩行の自立するまでに要した日数を評価し,各群で比較した.ES群はコントロール群よりも筋力や股関節JOAスコアは早期に改善し,日常生活動作および歩行の自立も早かった.大腿骨頚部骨折後の人工骨頭置換術後症例に対する術後翌日からの電気刺激併用筋力強化法は,膝伸展筋力の改善や日常生活動作および歩行の早期獲得に効果的に寄与することが示唆された.
- 著者
- 小嶌 康介 生野 公貴 庄本 康治
- 出版者
- Japanese Society for Electrophysical Agents in Physical Therapy
- 雑誌
- 物理療法科学 (ISSN:21889805)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.64-68, 2014 (Released:2022-09-03)
- 参考文献数
- 13
本研究の目的は脳卒中1症例にて部分免荷トレッドミル歩行訓練(BWSTT)と足関節背屈筋に対する随意運動介助型電気刺激(IVES)の併用治療の臨床有用性を検証することとした.対象は脳梗塞後左片麻痺を呈した59歳男性とした.研究デザインは各期4週間のABデザインを用い,8週間のフォローアップを行った.B期にBWSTTとIVESの併用治療を実施した.評価はFugl-Meyer Assessment(FMA),足関節背屈の自動関節可動域(A-ROM),膝伸展筋力,10 m歩行速度,2分間歩行距離(2MD)とした.FMA,10 m歩行速度はA期に最も改善した.膝伸展筋力はフォローアップに最も改善した.A-ROMと2MDはB期に最も改善した.機器設定は5分程度で可能で治療の受け入れは良好であった.A-ROMや2MDのB期の改善について本治療が足関節の随意性や歩行の協調性の改善に寄与したものと考えられた.本治療の臨床有用性は良好であった.
1 0 0 0 OA 消去によるバーストと変動性拡大 : 大学生を対象にMIDIドラムを用いた予備的研究
- 著者
- 島宗 理
- 出版者
- 法政大学文学部
- 雑誌
- 法政大学文学部紀要 = Bulletin of the Faculty of Letters, Hosei University (ISSN:04412486)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, pp.119-148, 2022-03-10
This study investigated the effects of extinction on response variabilities in transition states among university students playing MIDI drums. Each of the 4 × 4 tiles on a screen were turned by hitting a drum pad on a variable interval reinforcement schedule (VI 3s). None of the hits caused the tiles to turn when after 17-32 reinforcement (Extinction). Subsequently, changes in response frequency, inter-response time, response strength in terms of velocity, response location, and variabilities in these response dimensions were simultaneously measured and monitored for the next experimental phase. For each participant, the response dimension with the highest increase in variability due to extinction was chosen for differential reinforcement. Reinforcement criteria for each participant were determined by visual inspection of ongoing data and reversed to examine the effects of reinforcement contingencies. The results of eight participants who completed the experiment were then reported. Temporal increases in response strength and/or its variability were observed in four participants, and those in response location and/or its variability were observed in two participants. None of the participants showed clear temporal increases in response frequency, which is often described as “extinction burst.” In the differential reinforcement phase, the responses of six participants changed according to the reinforcement conditions without the participants’ awareness. Conceptual issues about the temporal effects of extinction were discussed and future research is proposed.
1 0 0 0 東洋大学大学院紀要. 文学研究科. 国文学
- 出版者
- 東洋大学大学院
- 巻号頁・発行日
- 2000
1 0 0 0 中国で環境問題にとりくむ
1 0 0 0 OA 中国都市ごみ収集方式の改善方策
- 著者
- 小澤 明日美
- 出版者
- 東洋大学大学院
- 雑誌
- 東洋大学大学院紀要 = Bulletin of the Graduate School, Toyo University (ISSN:02890445)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, pp.145-167, 2014-03-15
1 0 0 0 OA チェスに似たゲームにおける評価関数の共通性
- 著者
- 片寄 裕 ライエル・グリムベルゲン
- 雑誌
- ゲームプログラミングワークショップ2007論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, no.12, pp.164-171, 2007-11-09
ゲーム研究において評価関数はゲームごとに改良が進められており、それぞれの研究がほかのゲームに役立つことは難しい.そこでチェス、中国象棋、将棋の3つのゲームで共通した評価を使うことができるか評価関数の共通点を調査した.これらは戦争・戦闘を模したゲームといえ、実際の戦争で勝つための法則を記した兵法書には3つのゲーム同様、位置の評価と自由度の評価が書かれている.兵法書にある評価を3つのゲームに当てはめ、実際に共通して適用できるか元のプログラムと対戦させた。結果3つ全てで位置による評価、自由度による評価が共通の考え方で作成でき、孫子の九地篇を用いた方法が共通の考え方の一つになりうるということが確認できた.
1 0 0 0 OA 八重山ノート : ユンタ・ジラバをめぐって
1 0 0 0 OA 八重山民謡「アンバルヌミダガーマユンタ」におけるカニの特定
- 著者
- 大山了己
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告音楽情報科学(MUS)
- 巻号頁・発行日
- vol.1994, no.103(1994-MUS-008), pp.33-38, 1994-11-19
八重山の島々には身近にいる小さな生物たちを主題に歌い上げた民謡が多い。石垣市の西北10キロメートルほど離れた場所に網張(アンバル)がある。この場所は広大な干潟(カタバル)で、そこには貝類、エビ・カニ類、鳥類が豊富に棲息している。このアンバルを舞台に展開される八重山の民謡「網張ヌ目高蟹ユンタ(アンバルヌミダガーマユンタ)」には、15種類ものカニが登場する。カニの生態、形態や行動などを巧みに捉え、擬人化したこのユンタはいわば、「鳥獣戯画」の歌謡版といえるほどの傑作である。しかし、、登場するカニの種の生物学的な特定に関して従来いくつかの混乱があった。そこで、カニの民俗学・行動学的な今回の調査結果をもとにユンタに登場するカニの種の特定を試みる。
1 0 0 0 OA 八重山民謡にみるヒトとカニのかかわり: 力二の種の特定と民俗動物学的背景
- 出版者
- Museum of Nature and Human Activities, Hyogo
- 雑誌
- 人と自然 (ISSN:09181725)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.99-124, 1994 (Released:2019-11-01)
八重山の島々には身近にいる小さな生物たちを主題に, ときにはユーモラスに, またときにはアイロニ カルに歌いあげた民謡が多い. 石垣市の西北10キロメートルほど離れた網張( アンパル) にひらけた広大 な干潟( カタバル) には, マングローブなどの植物が生い茂り,33 種の貝類,34 種のエビ・カニ類,3 種 のゴカイとユムシなどの底生動物相や様々な動物たちが息吹く. 四季を問わない生物の楽園は, 時には人 が相撲に興じ, 競馬を楽しみ, 貝などを採る場でもあった. ここに生息する生きものたちを題材にとり上 げ, 歌いあげる人々のエネルギーは, 干潮時に湾奥部まで開ける干潟の広大さ, そこにふり注ぐ太陽のま ばゆさを背景にした, 動植物資源の豊かさと決して無縁なものではない. このアンパルを舞台に展開される八重山の代表的な民謡である「網張ヌ目高蟹( アンパルヌミダガーマ) ユンタ」には, 15 種類ものカニが登場する. カニの生態, 形態や行動などを巧みに捉え, 擬人化したこの ユンタはいわば,「鳥獣戯画」の歌謡版といえるほどの傑作である. しかし, 登場する力二の種の生物学 的な特定に関して従来いくつかの混乱があった. そこで, カニの民俗学・動物行動学的な今回の調査結果 をもとにヒトとカニとのかかわりとその正体を探ってみた. 同時に, 石垣市からおよそ8 キロメートルほ ど東方を流れる宮良川においてカニの種と分布に関する調査も行った. これらの結果もとり入れながら, ユンタに登場するカニの種の解釈( 特定) に関する従来の見解にいくつかの異同と新知見を提示・論述し た.
1 0 0 0 OA 薬物ナノ結晶を基盤とした眼内薬物送達システム
- 著者
- 長井 紀章
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.141, no.1, pp.47-53, 2021-01-01 (Released:2021-01-01)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1 3
The use of eye drops is a well-established practice in the treatment of ophthalmic diseases, although the bioavailability of traditional eye drops, which are either solutions or suspensions, is insufficient, as the corneal barrier and dilution by lacrimation prevent the transcorneal penetration of drugs. Additionally, frequent instillation may cause undesirable systemic side effects and local corneal toxicity. To overcome these problems, micro- and nanoparticles, hydrogels, and viscous solutions have been tested, and solid nanoparticles are also expected to be applied. This review examines the usefulness of ophthalmic formulations based on solid nanoparticles, by using the specific example of indomethacin (IMC). Ophthalmic formulations based on solid IMC nanoparticles (IMC-NP dispersions) have been prepared using various additives (benzalkonium chloride, mannitol, methylcellulose, and cyclodextrin) and a rotation/revolution pulverizer (NP-100), to produce particles of 50-220 nm in size. The solubility of IMC in IMC-NP dispersions was 4.18-fold higher than that in the suspensions containing IMC microparticles (IMC-MP suspensions), and IMC-NP dispersions were better tolerated than commercially available NSAIDs eye drops, such as IMC, pranoprofen, diclofenac, bromfenac, and nepafenac eyedrops, in human corneal epithelial cells. Moreover, the corneal penetration in IMC-NP dispersions was higher than that in commercially available IMC and IMC-MP suspensions, and three energy-dependent endocytosis pathways (clathrin-dependent endocytosis, caveolae-dependent endocytosis, and macropinocytosis) were related to the high ophthalmic bioavailability of IMC-NP dispersions. This information can be used to support future studies aimed at designing novel ophthalmic formulations.
1 0 0 0 OA スクロオキシ水酸化鉄顆粒剤のアドヒアランス, 有効性, 安全性に関する後向き研究
- 著者
- 土井 洋平 下村 明弘 猪阪 善隆
- 出版者
- 一般社団法人 日本透析医学会
- 雑誌
- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.9, pp.477-485, 2020 (Released:2020-09-28)
- 参考文献数
- 9
スクロオキシ水酸化鉄は強力な血清リン低下効果を示す薬剤であるが, 透析患者のリン管理において服薬アドヒアランスも重要であるとされている. 今回スクロオキシ水酸化鉄チュアブル錠から顆粒剤へ切り替えた患者を対象にアンケート調査を行い, 臨床検査所見の推移についても検討した. 対象は92例で85例 (92.3%) が3か月以上切り替え後顆粒剤を継続していた. アンケート調査からは顆粒剤のほうが飲みやすく, 指示された用法・用量通りに服用できる患者が増加することが示唆された. 臨床検査データに関しては血清リン濃度を含めた骨ミネラル代謝, 鉄代謝パラメーター, ヘモグロビンなどに臨床的に有意な変動を認めなかった. スクロオキシ水酸化鉄顆粒剤はチュアブル錠と比較して臨床検査値に大きな変化はなく, 服薬アドヒアランスを考慮すると有用である可能性がある.
1 0 0 0 再分配制約を考慮に入れた資源配分のマーケットデザイン分析
- 著者
- 安田 洋祐
- 出版者
- 大阪大学
- 雑誌
- 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(A))
- 巻号頁・発行日
- 2019
世界各国で貧富の格差や不平等が深刻な社会問題となっている。格差問題が「問題」であり続けている大きな理由は、格差を解消するような再分配の実現が様々な事情から難しいからだろう。基課題においては、この「再分配が難しい」という現実的な制約をモデルに取り込み、同質財市場における資源配分の問題を厚生経済学的な視点から検討した。国際共同研究では、同質財市場からより一般的なマッチング市場へと分析の拡張を行う。さらに、市場参加者たちのインセンティブを考慮に入れて、マーケットデザイン的な視点から分析を深める。具体的には、取引数量が競争市場よりも多くなるような具体的なメカニズムの検証や提案などを試みる予定である。
- 著者
- 信田 幸大 曽根 智子 衛藤 久美
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.4, pp.256-264, 2022-08-01 (Released:2022-09-17)
- 参考文献数
- 28
【目的】野菜摂取動機付けセミナー及び野菜飲料提供による環境サポートに加え,野菜摂取量推定装置による自己モニタリングを取り入れた栄養教育プログラムが,勤労者の野菜摂取量に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。【方法】勤労者男女を対象に層別化無作為比較試験を実施した。解析対象者は145名(介入群74名,対照群71名,平均年齢42歳)であった。両群に,管理栄養士による野菜摂取動機付けセミナー及び野菜飲料提供による4週間の環境サポートを実施し,介入群のみに野菜摂取量推定装置の測定を試験開始から10週間実施した。介入前,環境サポート終了後,及び野菜摂取量推定装置の測定期間終了後に食物摂取頻度調査票を用いた野菜摂取量,及び野菜摂取に関する行動変容ステージを調査し,群内比較及び群間比較を行った。【結果】介入前と比較した野菜摂取量の変化量を群間で比較した結果,介入4週目では有意差は認められなかったが,介入10週目では対照群よりも介入群の方が,有意に変化量が大きかった。行動変容ステージは,介入群では介入前と比較して各期間で有意な前進が認められたが,群間差は認められなかった。【結論】動機付けセミナー及び環境サポートに加え,野菜摂取量推定装置による自己モニタリングを実施することで,環境サポート終了後も野菜摂取に関する行動変容ステージの前進が維持され,それに伴い野菜摂取量の減少も抑えられる可能性がある。
1 0 0 0 OA 居住形態別にみた女子大学生の野菜,栄養素等摂取量と野菜摂取のセルフ・エフィカシー
- 著者
- 江田 真純 河嵜 唯衣 赤松 利恵 藤原 葉子
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.4, pp.239-245, 2022-08-01 (Released:2022-09-17)
- 参考文献数
- 22
【目的】女子大学生の野菜摂取量増加に向けて,居住形態別に野菜摂取量,栄養素等摂取量を比較し,野菜摂取量と野菜摂取のセルフ・エフィカシー(以下,SE)の関連を検討すること。【方法】女子大学生218人を対象に行った簡易型自記式食事歴法質問票による野菜摂取量,栄養素等摂取量と,属性,野菜摂取のSEの回答を使用した。χ2 検定,Mann-WhitneyのU検定を用いて,居住形態別に属性,野菜,栄養素等摂取量を比較し,Spearmanの相関係数を用いて,野菜摂取量と野菜摂取のSEの関連を検討した。【結果】一人暮らしの者は80人(36.7%),家族・その他と同居の者は138人(63.3%)であった。一人暮らしの者は野菜,栄養素等摂取量のほとんどの項目で家族・その他と同居の者より摂取量が低かった(すべてp<0.05)。居住形態別にみた総野菜摂取量と野菜摂取のSEの関連は,一人暮らしの者では中程度の正の相関がみられ(rs=0.60,p<0.001),同居の者では弱い正の相関がみられた(rs=0.27,p=0.032)。【結論】一人暮らしの女子大学生の野菜摂取量と栄養素等摂取量は家族等と同居の者と比較し,低かった。また,野菜摂取のSEを高めることは,一人暮らしの者の野菜摂取量の向上に活用できる可能性が示唆された。
1 0 0 0 ジャン=ポール・サルトルに関する病跡学的試論
- 著者
- 中広全延
- 出版者
- 夙川学院短期大学
- 雑誌
- 夙川学院短期大学研究紀要 (ISSN:02853744)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.33-50, 2011-03